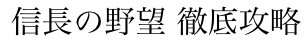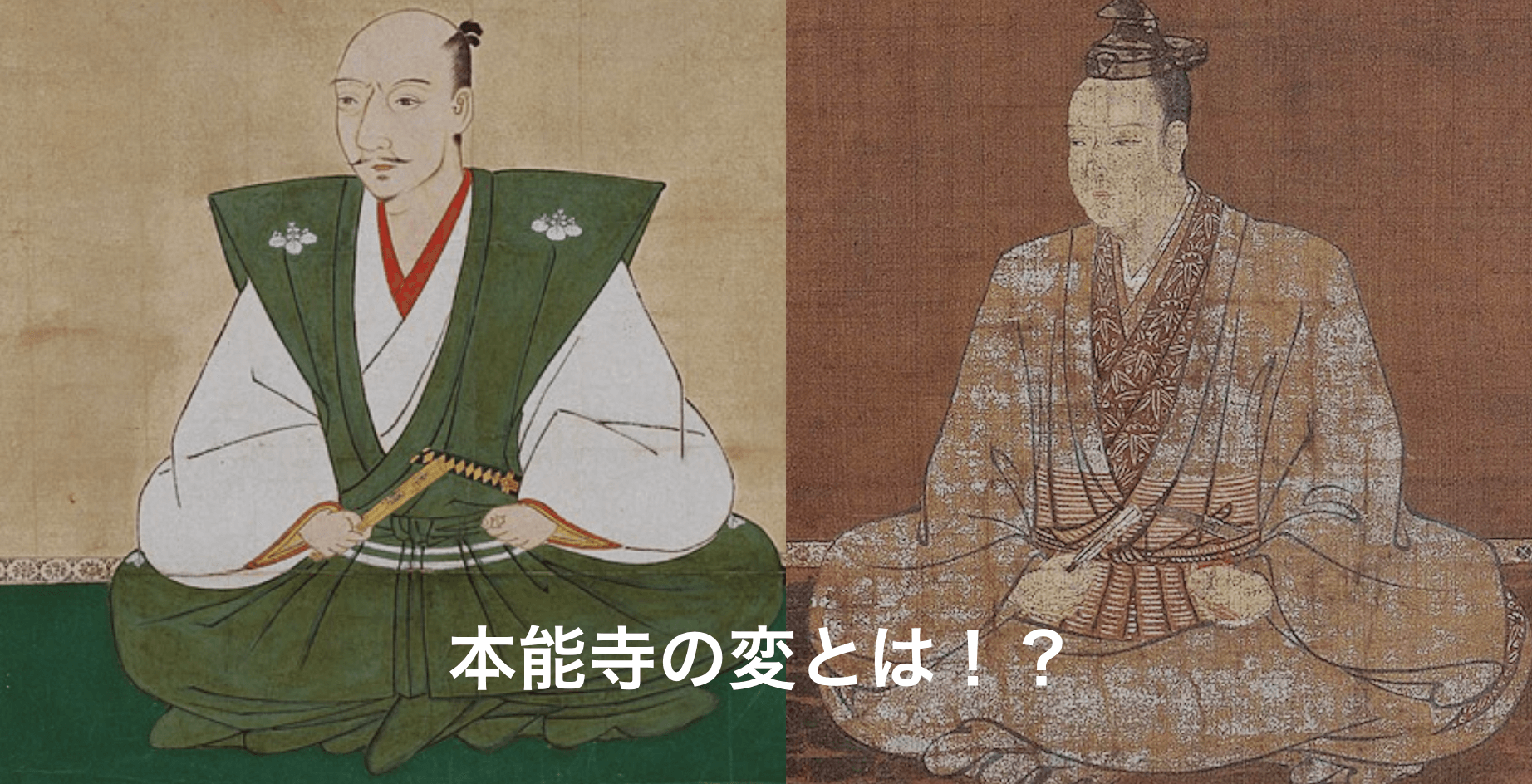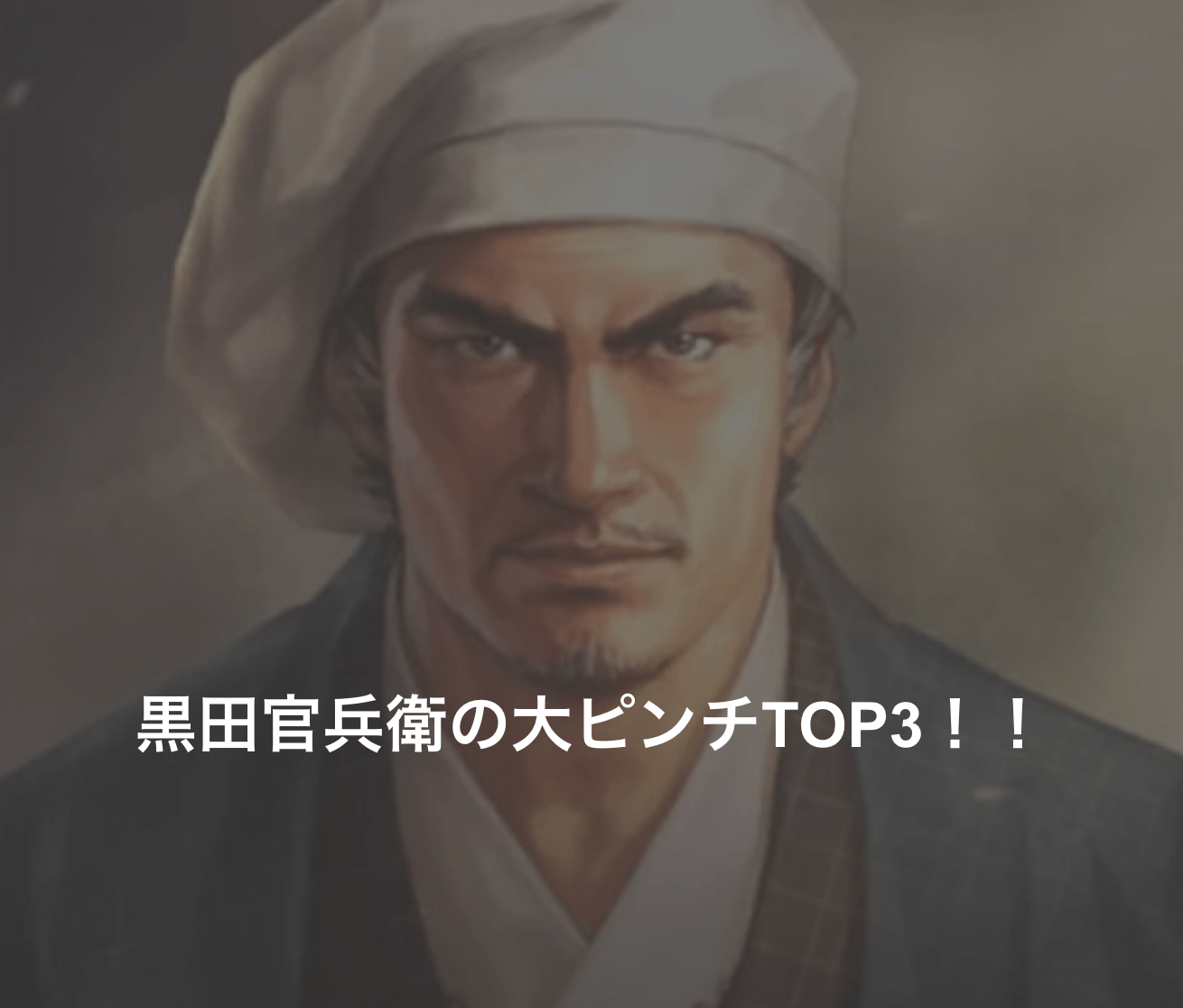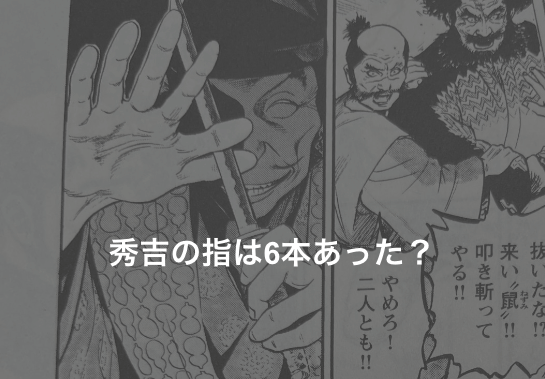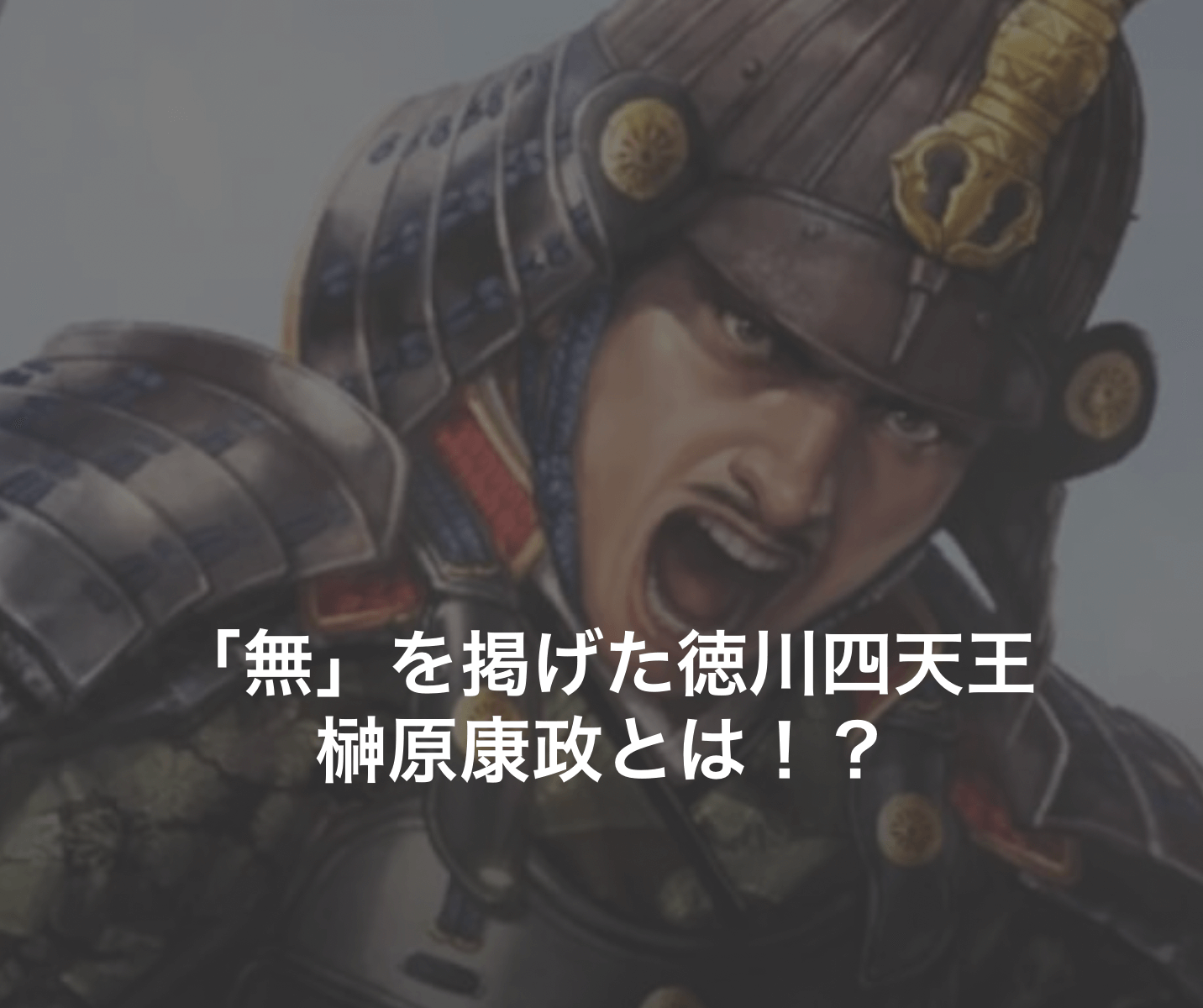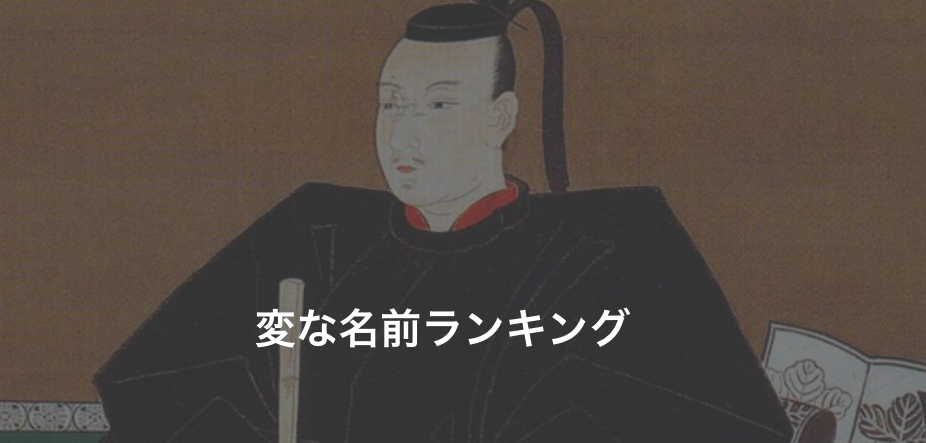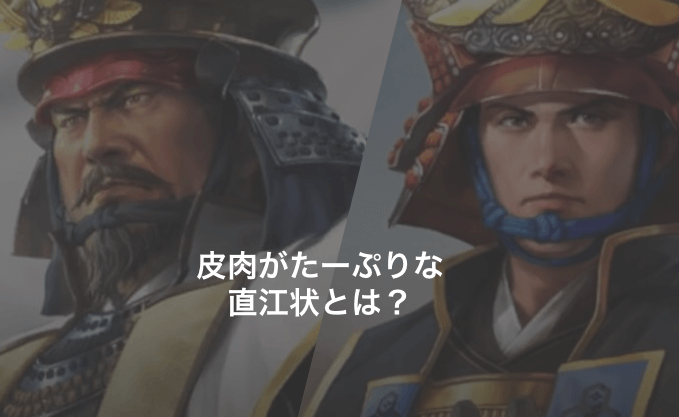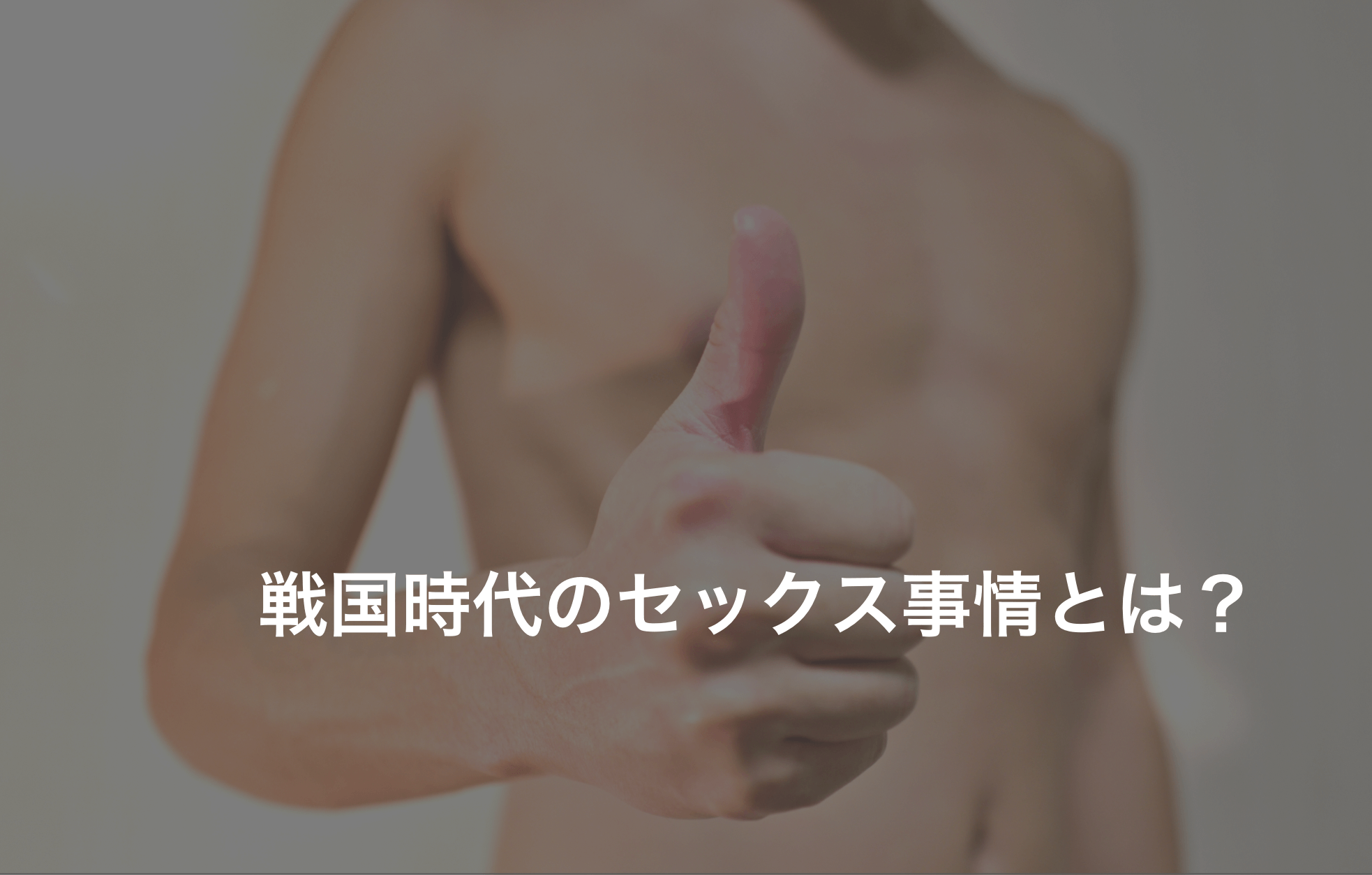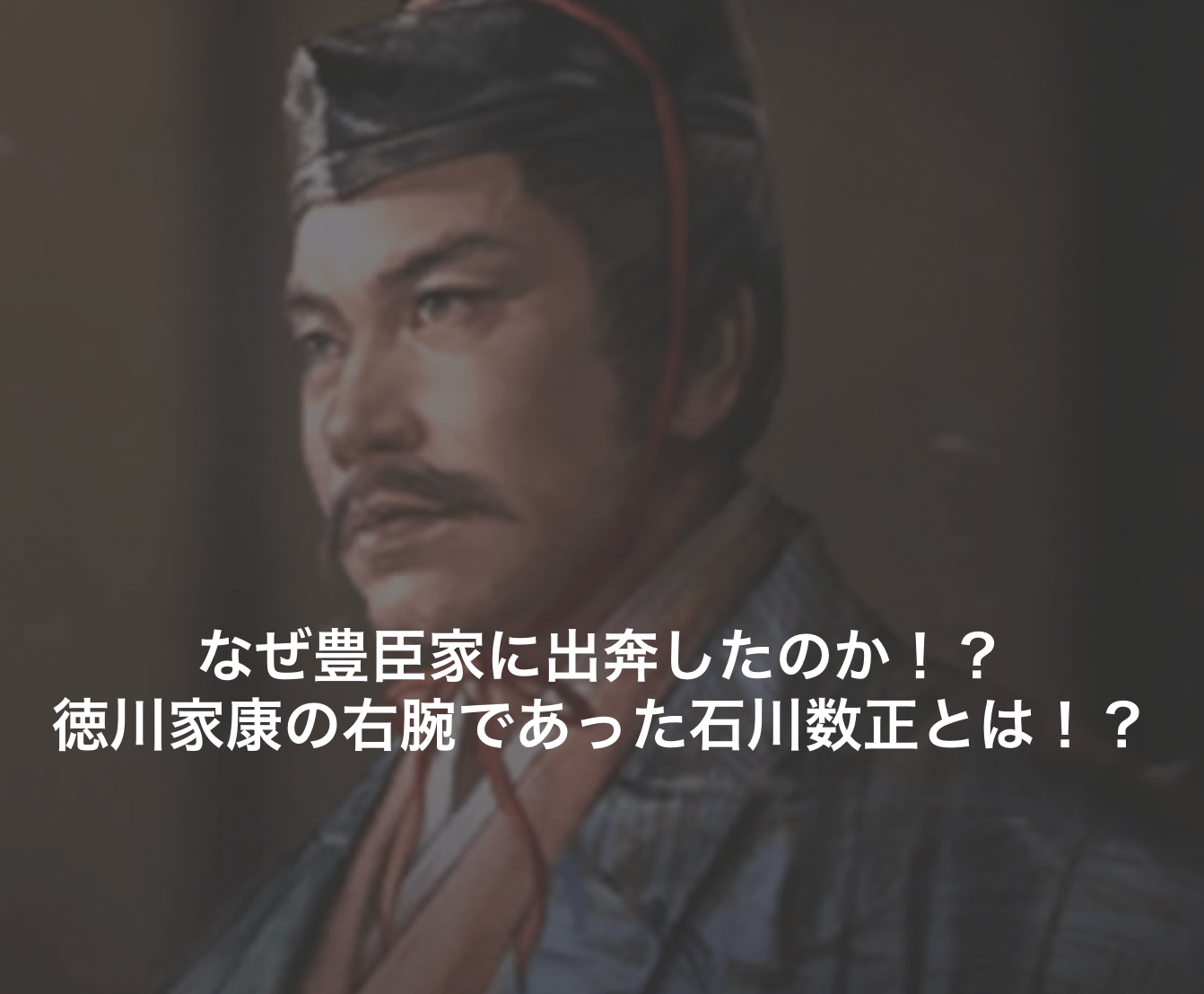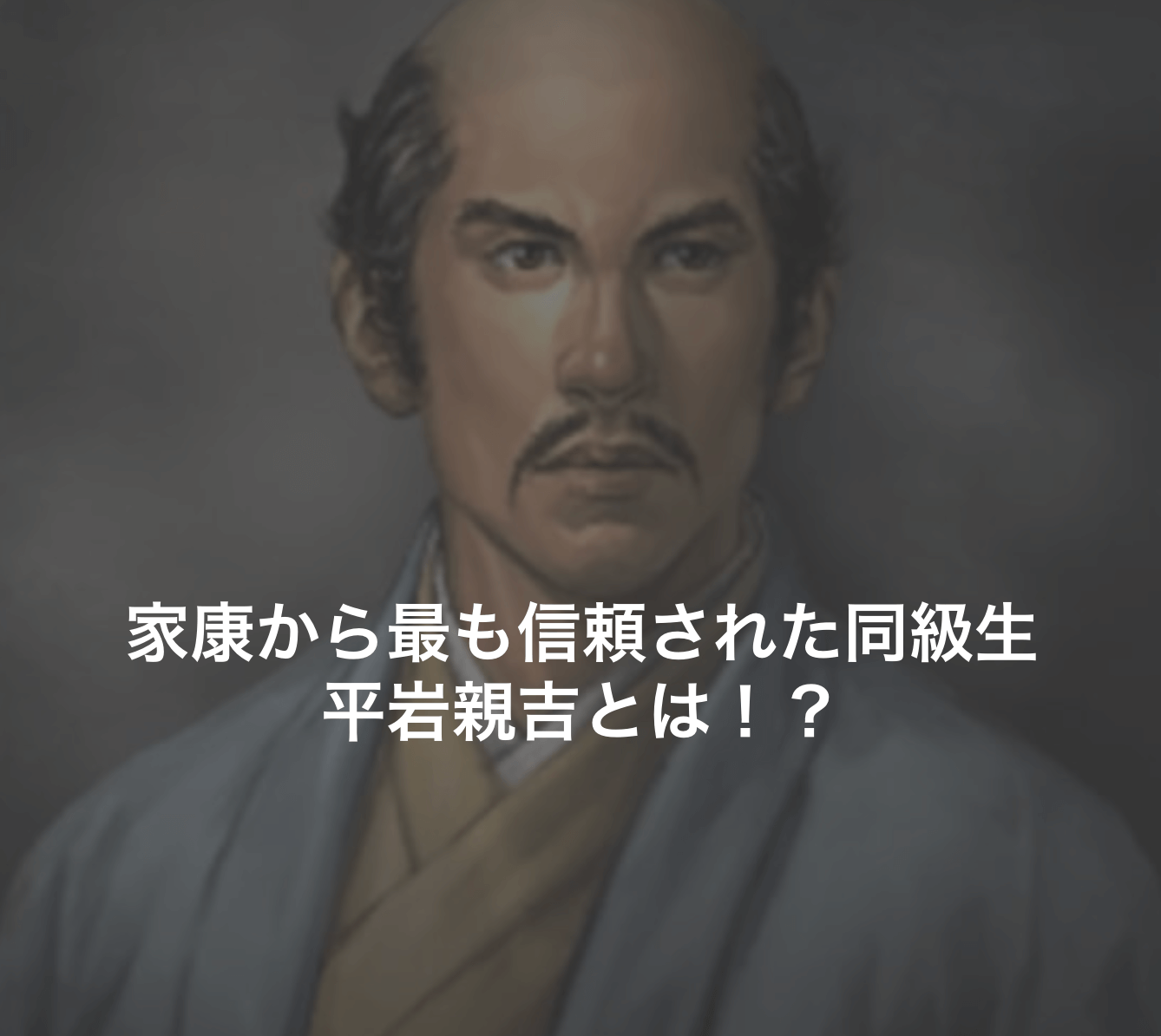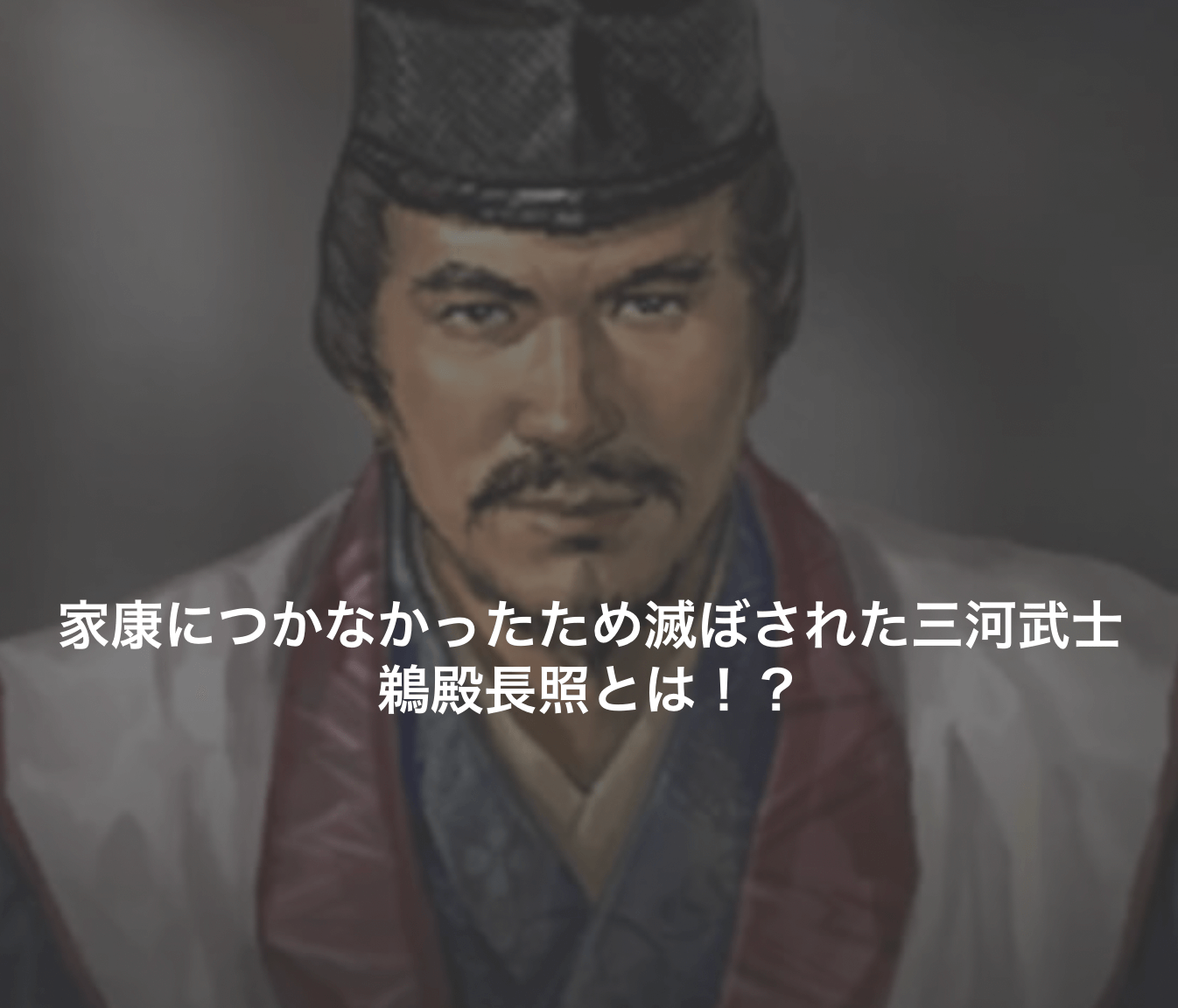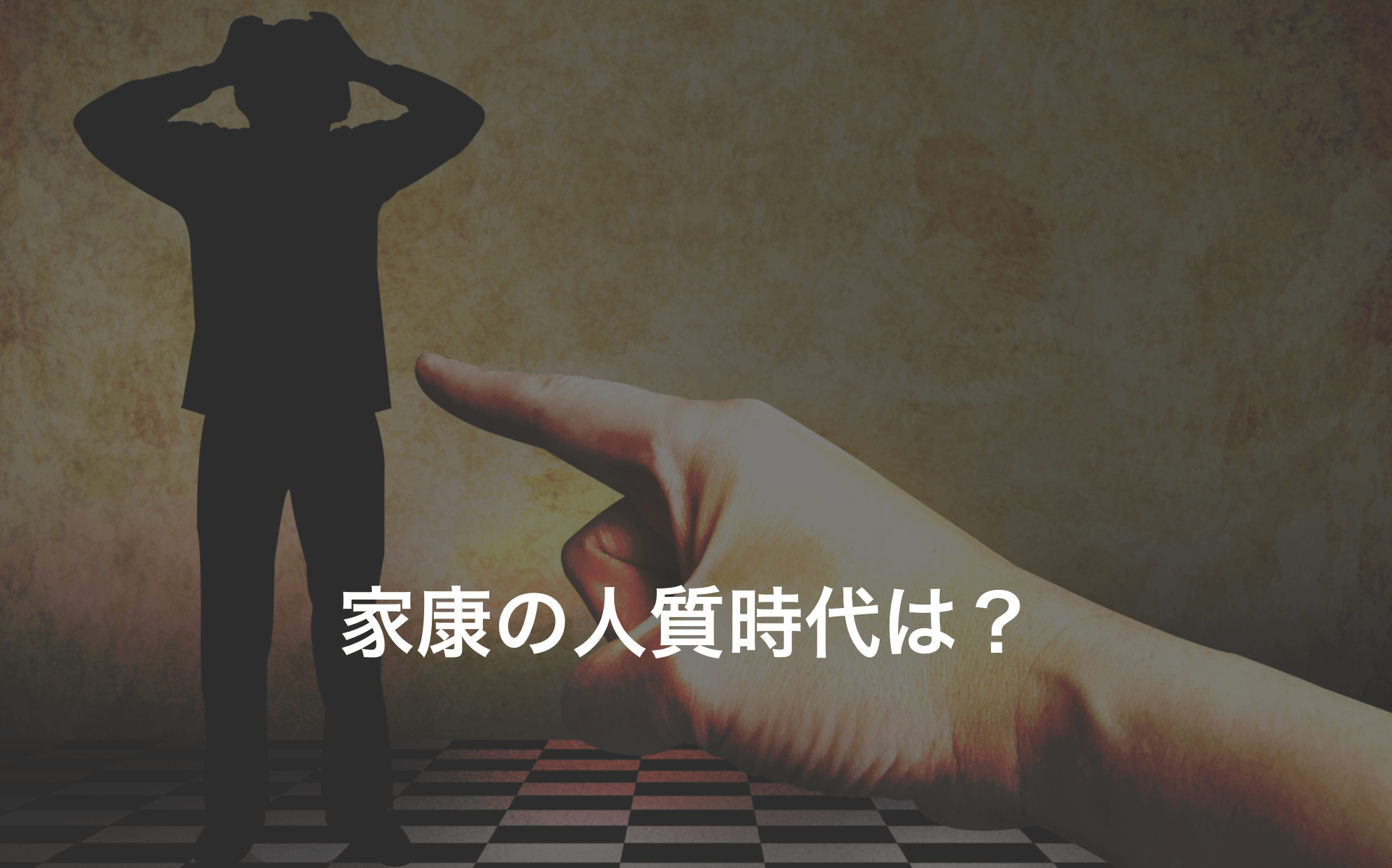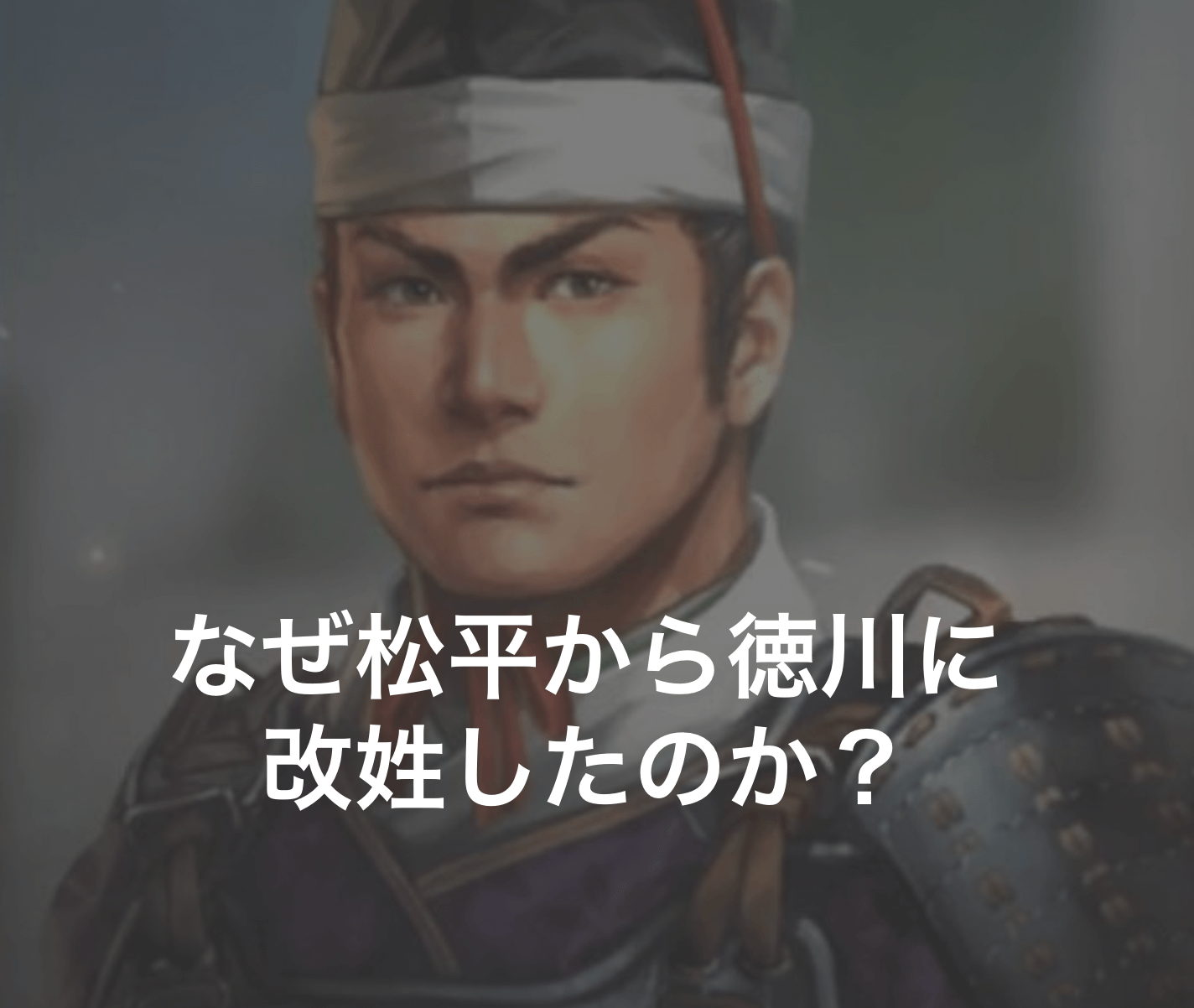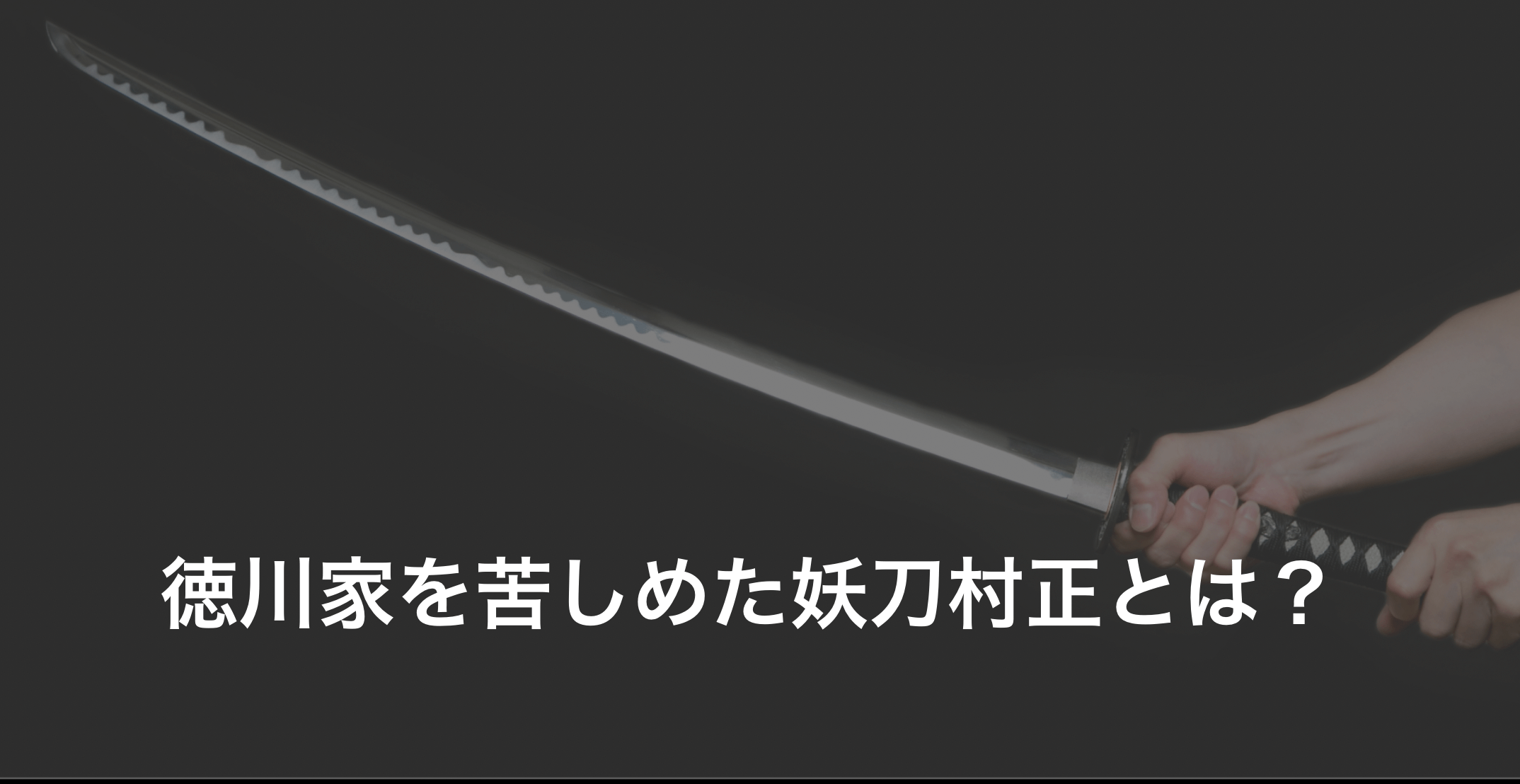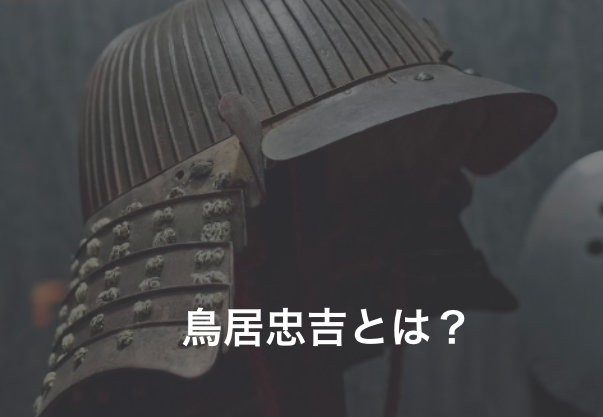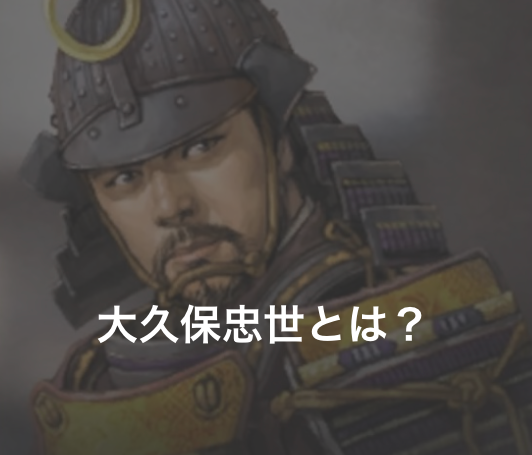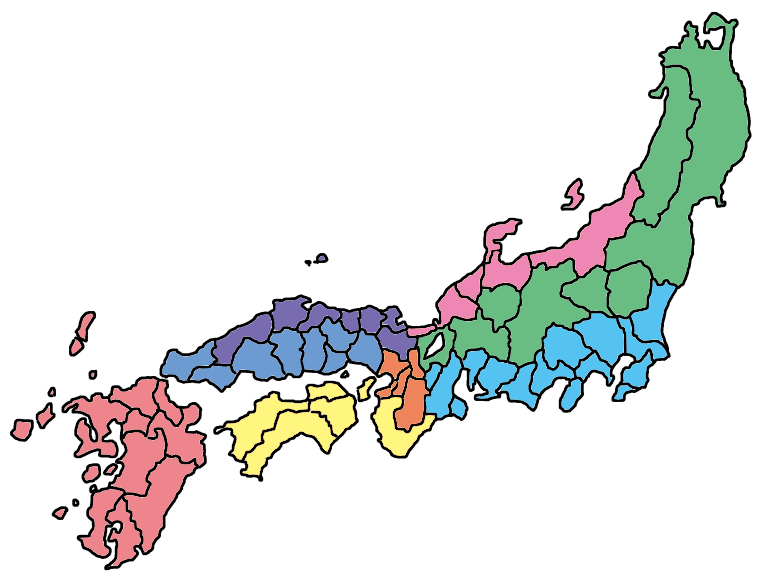武将名鑑【信長の野望 新生】
【新信長の野望】の武将名鑑についてはこちらを参照してください。
【大志PK】の武将名鑑についてはこちらを参照してください。
-

水野忠重 ( みずのただしげ)
三河の豪族。兄・信元が謀反を疑われ殺されると、刈谷城に入る。関ヶ原の戦いでは東軍に属すが、戦前の酒宴で加賀井重望と酔って口論となり、殺害された。
-

愛洲移香斎 (あいすいこうさい)
剣術家。本名は久忠。日向鵜戸の岩屋に参籠した際、奥義を授かり「影流」を創始したといわれる。子の宗通は剣聖・上泉信綱の師である。
-

愛洲宗通 (あいすむねみち)
剣術家。元香斎と号す。影流を創始した移香斎の子。猿飛陰流を開眼し、燕飛の太刀を編み出す。佐竹義重や剣聖・上泉信綱を弟子に持った。
-

青景隆著 (あおかげたかあきら)
大内家臣。奉行人を務めた。杉重矩と対立するが、のちに和解した。相良武任を陶晴賢に讒言し、晴賢が謀叛するきっかけを作る。毛利家との戦いで戦死した。
-

青木一重 (あおきかずしげ)
はじめ今川家、次いで徳川家に仕え、姉川の戦いで活躍。後に出奔。丹羽長秀、豊臣秀吉・秀頼に仕え、七手組組頭となる。大坂の陣の後、徳川家に帰参した。
-

青木一矩 (あおきかずのり)
豊臣家臣。賤ヶ岳の合戦などに従軍し、その功で越前北ノ庄20万石を領す。関ヶ原合戦の際は西軍に属すが、病床にあり、戦後間もなく病死、改易された。
-

青田顕治 (あおたあきはる)
相馬家臣。信濃と称す。黒木城代を務めた。のちに中村城代・中村式部と共謀して謀叛を起こし、田中城攻撃を企てたが相馬盛胤・義胤の軍に敗れて戦死した。
-

青山忠俊 (あおやまただとし)
徳川家臣。土井利勝らとともに徳川家光の傅役となる。家光の勘気を受けて改易されると、出仕要請を断り隠居した。子の宗俊は家光の子・家綱の傅役となる。
-

青山忠成 (あおやまただなり)
徳川家臣。徳川秀忠の傅役を務める。関ヶ原合戦後、内藤清成らとともに江戸奉行・関東総奉行を務めた。しかし、のちに主君・家康の勘気を受け、蟄居した。
-

赤井家清 (あかいいえきよ)
丹波の豪族。直正の兄。細川家の内紛で晴元を支援したため、晴国を支援する波多野家に攻められ、播磨に逃れた。後に晴元政権が安定すると旧領に復した。
-

赤池長任 (あかいけながとう)
相良家臣。薩摩との国境にある大口城を守った。武辺の家臣が多く、たびたび島津家の攻勢を撃退し、島津義弘を窮地に追い込み、川上久朗を討ち取った。
-

赤井時家 (あかいときいえ)
丹波の豪族。越前守を称した。丹波守護代・内藤家に所領を追われ、一時的に播磨に逃れるが、のちに復帰した。次男・直正は赤井家庶流の荻野家を継いだ。
-

赤井直正 (あかいなおまさ)
丹波の豪族。時家の次男。兄・家清の戦死後、若年の甥・忠家を後見した。明智光秀の丹波平定軍を撃退するなど武勇に優れ「丹波の赤鬼」の異名をとった。
-

赤尾清綱 (あかおきよつな)
浅井家臣。海北綱親・雨森弥兵衛とともに「海赤雨三将」と称された。主家の居城・小谷城に赤尾曲輪を設け在番した。主家滅亡時に捕虜となり、斬首された。
-

赤尾津家保 (あかおついえやす)
由利十二頭の一。仙北大曲城主・前田道信が侵攻してくると、これを返り討ちにした。しかし後年、道信の次男・利宗の仇討ち合戦に敗れて戦死したという。
-

赤尾津光政 (あかおつみつまさ)
由利十二頭の一。由利郡に侵攻した大宝寺義氏が赤尾津領に迫ると、安東愛季に救助を要請。安東家の援軍を得た光政は荒沢の戦いで大宝寺軍を壊滅させた。
-

赤川元保 (あかがわもとやす)
毛利家臣。主君・隆元から信任され、五奉行制の成立後、その筆頭奉行に就任した。隆元が出雲遠征に赴く途中で急死したため、その責任を問われて殺された。
-

赤座吉家 (あかざよしいえ)
豊臣家臣。関ヶ原合戦では西軍に属すが朽木元綱らとともに東軍に寝返った。戦後改易されたため、加賀前田家に仕えたが、増水した越中国大門川で溺死した。
-

明石景親 (あかしかげちか)
浦上家臣。坂根城主。明禅寺合戦などに従軍した。宇喜多直家が主家の居城・天神山城を攻めた際、直家に通じて主家滅亡の原因を作る。以後は直家に仕えた。
-

明石全登 (あかしてるずみ)
宇喜多家臣。景親の子。主家内乱の後は国政を執る。関ヶ原合戦では宇喜多軍の先鋒を務めた。のち大坂城に入り、大坂の陣では切支丹武士を率いて奮戦した。
-

明石長行 (あかしながゆき)
赤松家臣。枝吉城主。名は正風とも。黒田孝高の外祖父。武庫河原合戦で浦上村宗を打ち破る。冷泉派の歌に精通し、関白・近衛稙家に和歌を伝授した。
-

赤穴久清 (あかなひさきよ)
尼子家臣。出雲瀬戸山城主。子・光清とともに大内義隆の出雲侵攻軍と戦うが、光清が戦死したため、大内軍に降る。大内軍の撤退後、居城の奪還に成功した。
-

赤穴光清 (あかなみつきよ)
尼子家臣。瀬戸山城主。久清の嫡男。大内義隆の出雲侵攻軍に抵抗し、毛利家臣の熊谷直続を討ち取るなど活躍したが、陶晴賢の家臣に喉を射られ、戦死した。
-

赤穴盛清 (あかなもりきよ)
尼子家臣。瀬戸山城主。光清の三男。父の壮烈な死に感動した主君・晴久により所領を加増された。のち毛利元就の出雲侵攻軍に降り、以後は毛利家に属した。
-

赤星親家 (あかほしちかいえ)
菊池家臣。主君・義武の肥後隈本城回復戦の際は大友家に属し、恩賞として肥後隈府城主となり、菊池郡を支配した。のちに隈部親永と対立し、戦うが敗れた。
-

赤星親武 (あかぼしちかたけ)
加藤清正家臣。統家の子。娘は加藤清正の側室。加藤十六将の一。のち清正を介して豊臣秀頼に仕え、大坂の陣で奮戦。天王寺口の戦いで討死を遂げた。
-

赤星道重 (あかぼしみちしげ)
島原の乱指導者・天草十七人衆の一人。親武の子。大坂の陣で父とともに大坂城に籠城し脱出。島原の乱では原城本丸付近を守り、一騎打ちの末討死した。
-

赤星統家 (あかほしむねいえ)
龍造寺家臣。肥後隈府城主。親家の子。主君・隆信から去就を疑われて人質を殺されたため、島津家に属す。豊臣秀吉の九州征伐後も居城を回復できなかった。
-

赤松則英 (あかまつのりひで)
豊臣家臣。則房の子。父の死後、阿波住吉1万石を相続する。関ヶ原合戦では西軍に属して近江佐和山城に籠城。落城直前に脱出したが、戦後京都で自害した。
-

赤松則房 (あかまつのりふさ)
豊臣家臣。義祐の子。播磨置塩1万石を安堵される。賤ヶ岳合戦や小牧長久手合戦、四国征伐に従軍し、阿波住吉1万石を加増された。朝鮮派兵にも従軍した。
-

赤松晴政 (あかまつはるまさ)
播磨守護。家臣・浦上村宗に傀儡とされる。のち細川晴元と通じ、大物崩れの戦いで村宗を討つが、尼子晴久に攻撃されるなど、領国経営は名のみであった。
-

赤松政秀 (あかまつまさひで)
赤松家臣。龍野城主。主君・晴政を居城に迎える。浦上政宗を討ち、また別所安治と結んで小寺政職や黒田職隆と戦うなど活躍した。のちに毒殺されたという。
-

赤松村秀 (あかまつむらひで)
赤松家臣。政則の庶子という。政則の娘婿となった義村が赤松家を継いだため、塩屋城主・宇野政秀の養子となる。政秀が龍野城を築いたあと、城主となった。
-

赤松義祐 (あかまつよしすけ)
晴政の子。織田信長に通じたが、浦上政宗と戦って敗れ、没落した。赤松家は村上源氏の流れをくみ、建武政府樹立に貢献した赤松則村(円心)を始祖とする。
-

安芸国虎 (あきくにとら)
土佐の豪族。安芸城主。長宗我部元親の居城・土佐岡豊城への招請を断り、元親と戦う。しかし元親の謀略により家臣団が内部崩壊を起こして敗北、自害した。
-

秋田実季 (あきたさねすえ)
檜山安東家9代当主。愛季の嫡男。父の死後、家督を継ぐ。南部家や戸沢家と抗争し、所領を守り抜くが、関ヶ原の合戦での不手際により、秋田領を追われた。
-

秋田俊季 (あきたとしすえ)
実季の長男。勘気を受け蟄居処分を受けた父の後を継ぎ、常陸宍戸藩2代藩主となる。人柄は律義で、懸命に幕府に奉仕した結果、加増され陸奥三春へ移った。
-

秋月種実 (あきづきたねざね)
筑前の豪族。古処山城主。文種の次男。毛利家の援助を受け、居城を大友家から奪回した。豊臣秀吉の九州征伐軍に敗れ「楢柴茶入」を献上して改易を免れた。
-

秋月種長 (あきづきたねなが)
筑前の豪族。古処山城主。種実の長男。豊臣秀吉の九州征伐軍に降り、日向高鍋3万石に転封される。関ヶ原合戦では東軍に寝返り、戦後、所領を安堵された。
-

秋月種信 (あきづきたねのぶ)
秋月家臣。馬ヶ岳城主。秋月文種の子。豊前の豪族・長野家の家督を継ぐ。兄・秋月種実とともに大友家と戦った。長野家は平清盛の従兄弟・康盛を祖とする。
-

秋月種春 (あきづきたねはる)
種長の娘婿・種貞の嫡男。病弱のため廃嫡となった父に代わって種長の後嗣となる。種長の死後、日向高鍋3万石の2代藩主となった。
-

秋月文種 (あきづきふみたね)
筑前の豪族。古処山城主。大友家に属すが待遇に不満を持ち、毛利元就と結んで叛旗を翻す。大友軍2万の軍勢に対して善戦するが、衆寡敵せず敗れ自害した。
-

秋月元種 (あきづきもとたね)
筑前の豪族。秋月種実の次男。豊臣秀吉に降り、日向延岡5万石を領す。関ヶ原合戦では東軍に寝返り、所領安堵。のち謀叛人の縁者を匿った罪で改易された。
-

秋元長朝 (あきもとながとも)
深谷上杉家臣。小田原征伐では豊臣の大軍を相手に深谷城を守りきる。のち徳川家康に仕える。関ヶ原合戦後、上杉景勝に降伏を勧告し、受け入れさせた。
-

安芸元泰 (あきもとやす)
土佐の豪族。山城守と称す。安芸城主。嫡子がないまま早世したため、子の国虎が家督を継いだ。安芸家は壬申の乱で土佐へ配流された蘇我赤兄の後裔という。
-

秋山信友 (あきやまのぶとも)
武田家臣。伊那衆を統率する。徳川家康に「武田軍の猛牛」と評されたほどの猛将。岩村城に籠城して織田信長軍と戦うが、敗れて捕虜となり、磔刑にされた。
-

明智秀満 (あけちひでみつ)
明智家臣。岳父・光秀のもとで本能寺の変に加担した。山崎合戦では安土城を守るが、本軍の敗報を受けて坂本城に退却し、財宝を包囲軍に譲渡して自害した。
-

明智光継 (あけちみつつぐ)
美濃の豪族。明智城主。娘は斎藤道三に嫁ぎ、織田信長の正室・帰蝶を生む。明智家は土岐家の庶流で、初代美濃守護・土岐頼貞の子・頼基を祖とするという。
-

明智光秀 (あけちみつひで)
織田家臣。優れた才知と教養により重用されるが、突如謀叛を起こし信長を本能寺に討つ。しかし事後調略に失敗し、山崎合戦で敗れ逃亡中に殺された。
-

明智光安 (あけちみつやす)
斎藤家家臣で、明智光秀の叔父。道三と義龍の内戦の折、道三側について義龍の軍に居城・明智城を攻められる。籠城して防戦するが敗れ、自害した。
-

浅井亮親 (あざいすけちか)
浅井家庶流。宗家当主・長政が織田信長との同盟を破棄しようとした際、強硬に反対する。のち、小谷城の戦いで織田軍に敗れると捕虜となり、処断された。
-

浅井亮政 (あざいすけまさ)
近江の戦国大名。小谷城主。はじめ京極家に仕えたが、主家の内紛に乗じて勢力を拡大する。朝倉家の援助を受けて六角定頼の軍を撃退し、江北に覇を唱えた。
-

浅井長政 (あざいながまさ)
近江の戦国大名。小谷城主。久政の子。織田信長の妹・市を娶るが、朝倉家との友誼を重んじ信長と敵対。居城を攻められ、市と娘たちを信長に託し自害した。
-

浅井久政 (あざいひさまさ)
近江の戦国大名。小谷城主。亮政の子。六角家の傘下に入る政策を採ったため家臣の不満が集まり、のちに子・長政に家督を譲った。浅井家滅亡時に自害した。
-

朝倉一玄 (あさくらいちげん)
大友家臣。島津軍の豊後侵攻で駄原城を攻められた際、「留守の火縄」を城に仕掛けて放棄。燃え上がる城を占拠する島津軍に逆襲を仕掛け、大損害を与えた。
-

朝倉景鏡 (あさくらかげあきら)
朝倉家臣。景高の子。織田信長追撃の総大将を務めた。主君・義景が刀禰坂合戦に敗れたあとは信長に内応し、義景を自害させた。のち一向一揆勢に討たれた。
-

朝倉景隆 (あさくらかげたか)
朝倉家臣。朝倉敏景の弟・経景の孫。朝倉宗滴が病で帰国したあと、一向一揆討伐の大将として加賀に出陣した。のち3人の子を相次いで失い、間もなく死去。
-

朝倉景健 (あさくらかげたけ)
朝倉家臣。景隆の子。姉川合戦では朝倉軍の総大将として奮戦。主家滅亡後は織田信長に属すが、一向一揆に降伏したため、信長の怒りを買い自害させられた。
-

朝倉景連 (あさくらかげつら)
朝倉家臣。朝倉宗滴の加賀一向一揆攻めで戦功を挙げた。四奉行の一人として内政に手腕を発揮。義景が犬追物を開催した際、豪奢な出で立ちで皆を驚かせた。
-

朝倉景紀 (あさくらかげのり)
朝倉家臣。朝倉家3代当主・貞景の子。朝倉宗滴の養子となる。敦賀城主を務め養父とともに加賀や若狭、近畿などを転戦し活躍した。のち敦賀郡司となった。
-

朝倉宗滴 (あさくらそうてき)
朝倉家臣。朝倉家初代当主・敏景の子。軍奉行を務め、周辺諸国へ出兵し朝倉家の武威を内外に知らしめた。加賀一向一揆討伐の際に発病、帰国後に死去した。
-

朝倉孝景 (あさくらたかかげ)
朝倉家4代当主。卓抜した政治手腕で越前国内を安定させ、朝倉家の最盛期を現出した。隣国・加賀に積極的に侵攻し、一向一揆軍と戦った。歌道に優れた。
-

朝倉義景 (あさくらよしかげ)
朝倉家5代当主。孝景の嫡男。将軍・足利義昭と結び織田信長包囲網の一角を担うが、次第に勢威を失う。刀禰坂合戦で敗北を喫し、一族に背かれて自害した。
-

浅野長晟 (あさのながあきら)
徳川家臣。長政の次男。兄・幸長の死後紀伊和歌山藩主となる。大坂夏の陣では塙直之を討ち取るなど活躍した。福島家の改易後、安芸広島42万石を領した。
-

浅野長重 (あさのながしげ)
長政の三男。徳川秀忠に仕え、大坂の陣で功を立てる。後に常陸笠間5万3千石に加増転封された。吉良上野介を松の廊下で斬った浅野内匠頭は長重の曾孫。
-

浅野長政 (あさのながまさ)
豊臣家臣。秀吉の正室・寧子の義弟。五奉行筆頭として主家の執政に参画した。秀吉の死後、石田三成と対立して徳川家康に接近し、以後は徳川家に仕えた。
-

浅野幸長 (あさのよしなが)
豊臣家臣。長政の嫡男。関ヶ原合戦では東軍に属し、戦後、紀伊和歌山37万石を領する。のちに加藤清正と協力し、徳川家康と豊臣秀頼の会見を実現させた。
-

朝比奈信置 (あさひなのぶおき)
今川家臣。小豆坂合戦などで戦功を立てる。主家滅亡後は武田信玄に仕え、駿河先方衆となった。武田家滅亡の際に、居城・庵原館を攻められ敗北、自害した。
-

朝比奈泰朝 (あさひなやすとも)
今川家臣。泰能の子。駿河を追われた主君・氏真を居城・掛川城に迎え入れ、徳川軍と戦う。5カ月の籠城戦の末に開城し、氏真とともに相模に落ち延びた。
-

朝比奈泰能 (あさひなやすよし)
今川家臣。掛川城主を務める。1548年の小豆坂合戦において、太原雪斎を補佐して織田信秀の軍を破るなど、今川家の西方侵攻軍の先鋒として活躍した。
-

浅利勝頼 (あさりかつより)
出羽の豪族。則頼の次男。安東家と結んで兄・則祐を自害させ、当主となる。のちに津軽家と結び謀叛を企んだため、安東愛季に酒宴へ誘い出され、殺された。
-

浅利定頼 (あさりさだより)
浅利家臣。則頼の弟。花岡城主。則頼・則祐・勝頼に仕え北の守りを任された。勝頼が安東家から独立を図った際、安東愛季と山田合戦で戦い、敗死した。
-

浅利則祐 (あさりのりすけ)
出羽の豪族。十狐(独鈷)城主。則頼の嫡男。安東家への従属を画策する弟・勝頼と対立する。のちに勝頼の手引きを受けた安東軍の攻撃を受け、自害した。
-

浅利則頼 (あさりのりより)
出羽の豪族。朝頼の子。甲斐国浅利郷より出羽比内地方へ移住し、十狐(独鈷)城を築く。また、弟たちを周辺の城に配置し、比内における支配権を確立した。
-

浅利頼平 (あさりよりひら)
出羽の豪族。勝頼の子。父が謀殺された後、津軽に身を隠す。のちに安東家の代官として比内を治めるが、軍役金未納の問題が起き、訴訟中に大坂で急死した。
-

足利晴氏 (あしかがはるうじ)
古河公方。高基の子。足利家の一門として関東武士の間に根強い支持があり、北条家も懐柔に注意を払った。のち北条家に反抗したため、小田原に幽閉された。
-

足利晴直 (あしかがはるなお)
関東管領。古河公方・高基の子。上杉憲房の養子となり、上杉憲寛と名乗る。関東享禄の内乱で敗れ関東管領職を失い、足利姓に復した。
-

足利義昭 (あしかがよしあき)
室町幕府15代将軍。織田信長の後援で将軍職に就くがのちに対立、周辺諸国と協力して信長包囲網を敷く。自らも挙兵するが信長軍に敗れ、京を追われた。
-

足利義明 (あしかがよしあき)
小弓御所。古河公方・政氏の子。父らと対立し、流浪の末、真里谷武田家の後援で小弓城に入った。のちに里見家と結んで北条家と国府台で戦うが、敗死した。
-

足利義氏 (あしかがよしうじ)
古河公方。晴氏の子。北条家の庇護のもとで成人し古河城に復帰するが、実権を持たなかった。死後、古河足利家が断絶したため、娘の氏が喜連川家を立てた。
-

足利義輝 (あしかがよしてる)
室町幕府13代将軍。塚原卜伝、上泉信綱らに師事した剣豪。失われた幕府権力の回復に奔走するが、のちに松永久秀らに奇襲され、孤軍奮闘の末自害した。
-

足利義晴 (あしかがよしはる)
室町幕府12代将軍。阿波で挙兵した三好元長に敗れ、近江に逃亡する。元長の死後、細川晴元に擁されて京に戻ったがのちに晴元と対立し、将軍職を辞した。
-

足利頼純 (あしかがよりずみ)
下野喜連川城主。小弓御所・義明の子。父が第一次国府台合戦で戦死したため、各地を流浪。のちに豊臣秀吉に仕えた。娘・島子は豊臣秀吉の側室となった。
-

蘆田国住 (あしだくにずみ)
丹波の豪族。氷上郡小室城主。他の豪族とともに織田信長の丹波侵攻軍に抵抗するが、1579年5月、羽柴秀長軍の攻撃を受けて落城、滅亡した。
-

蘆田信蕃 (あしだのぶしげ)
武田家臣。信守の子。二俣城主を務め、父とともに徳川軍と戦った。主家滅亡後は徳川家に仕え、信濃攻略に参加するが岩尾城攻撃戦で銃弾を浴び、戦死した。
-

蘆田信守 (あしだのぶもり)
武田家臣。三岳城主。下野守と称した。三方ヶ原合戦後、二俣城主となる。長篠合戦で主家が大敗したあと、徳川家康の軍に居城を囲まれ、防戦中に病死した。
-

蘆名氏方 (あしなうじかた)
盛舜の庶子。実母が白拍子であったためか、家督継承候補から外され、家臣の富田義実に養育される。のち義実に奉じられて謀反を起こすが敗れ、自害。
-

蘆名盛氏 (あしなもりうじ)
蘆名家16代当主。蘆名家を伊達家と並ぶ奥州屈指の大名に育て上げた、蘆名家中興の祖。同盟をうまく利用し、会津一円から北越後に及ぶ所領を獲得した。
-

蘆名盛興 (あしなもりおき)
蘆名家17代当主。盛氏の嫡男。父の隠居により家督を継ぐが、佐竹家との抗争中に夭逝した。盛興の病を治すために、父が領内での造酒を禁じたこともある。
-

蘆名盛舜 (あしなもりきよ)
蘆名家15代当主。猪苗代家の叛乱を鎮定し、伊達稙宗の葛西家攻めに協力、また岩城・白河結城家と戦うなど、事実上の会津守護職としての行動を取った。
-

蘆名盛隆 (あしなもりたか)
蘆名家18代当主。二階堂盛義の子。蘆名盛興の未亡人を娶った。上杉・北条家らと結んで佐竹家と争った。寵の衰えを逆恨みした側近に黒川城内で殺された。
-

蘆名義広 (あしなよしひろ)
蘆名家20代当主。佐竹義重の次男。白河結城家の養子となるが、のち蘆名盛隆の娘を娶り蘆名家を継ぐ。摺上原で伊達政宗の軍に敗れ、故郷の常陸に逃れた。
-

麻生鎮里 (あそうしげさと)
筑前の豪族。花尾城主。隆守の弟。相良武任の失脚により城主となる。のちに山鹿城主・麻生隆実と対立。宗像氏貞の支援を得た隆実に敗れ、島津家を頼った。
-

麻生隆守 (あそうたかもり)
筑前の豪族。岡城主。大内家に属すが、一族の帆柱山城主・麻生家は大友家への接近を試み、対立する。のちに帆柱山城主・麻生家に攻められ落城、戦死した。
-

麻生元重 (あそうもとしげ)
筑前の豪族。山鹿城主。麻生家は遠賀郡山鹿の地頭職を務めた宇都宮家政を祖とする宇都宮家の庶流。豊臣秀吉の九州征伐軍に降り、のちに筑後へ移封された。
-

阿蘇惟種 (あそこれたね)
肥後の豪族。岩尾城主。惟豊の子。兄・惟将に男子がなかったため、兄の養子となって家督を継ぎ、阿蘇大宮司に就任した。しかしそのわずか1カ月後に死去。
-

阿蘇惟豊 (あそこれとよ)
肥後の豪族。岩尾城主。兄・惟長に一時居城を追われるが、家臣・甲斐親宣の助力で阿蘇大宮司職に復した。のちに禁裏修理料を献上し、勅使の下向を迎えた。
-

阿蘇惟長 (あそこれなが)
阿蘇大宮司。惟憲の長男。菊池家臣らに擁立されて菊池家を継ぐが、大友家と対立して追放される。阿蘇大宮司職を巡り弟・惟豊と戦うが敗れ、薩摩に逃れた。
-

阿蘇惟将 (あそこれまさ)
肥後の豪族。岩尾城主。惟豊の子。阿蘇大宮司を務めた。大友家に属す。家臣・甲斐親直の助力で、龍造寺家および島津家と和平交渉を行い、領国を維持した。
-

阿蘇惟光 (あそこれみつ)
肥後の豪族。岩尾城主。惟種の子。わずか3歳で阿蘇大宮司となる。豊臣秀吉に降り、佐々成政に仕えるが、肥後国人一揆を扇動したとの讒言により殺された。
-

阿曽沼広秀 (あそぬまひろひで)
安芸の豪族。毛利家に属す。厳島合戦や防長制圧戦などで先鋒を務めた。しかし公事負担について抗議したり、出雲遠征を渋るなど、一定の独立性も維持した。
-

麻生野直盛 (あそやなおもり)
飛騨の豪族。江馬時経の次男。江馬時盛の弟にあたる。麻生野の洞城を居城としたため、麻生野姓を称した。時盛と子・慶盛はのちに甥・江馬輝盛に殺された。
-

麻生野慶盛 (あそやよしもり)
飛騨の豪族。洞城主。直盛の子。父の死後、家督を継ぐ。武田家と友好を結ぶ。のちに上杉家と結ぶ従兄弟・江馬輝盛と対立し、攻められて敗北、自害した。
-

安宅信康 (あたぎのぶやす)
織田家臣。冬康の子。父の死後家督を継ぎ、淡路水軍を率いる。はじめ石山本願寺と結ぶが、織田信長の畿内平定軍に降り、木津川口合戦で毛利水軍と戦った。
-

安宅冬康 (あたぎふゆやす)
三好家臣。三好元長の三男。安宅家を継ぎ、淡路水軍を統率。兄・三好長慶を助けて活躍したが、松永久秀の讒言により兄に殺された。歌や書、茶道に長じた。
-

足立重信 (あだちしげのぶ)
加藤家臣。関ヶ原合戦では主君・嘉明の居城・伊予松前城の留守居役を務めて毛利軍を撃退し、家老となる。河川工事にすぐれ、領内の灌漑と水防を行った。
-

足立基助 (あだちもとすけ)
丹波の豪族。氷上郡山垣城主。足立家は源家4代に仕え、武蔵国足立郡を領した藤原遠元を祖とする。1579年、羽柴秀長軍の攻撃を受けて落城、戦死した。
-

阿閉貞征 (あつじさだゆき)
浅井家臣。山本山城主。主家滅亡後は織田信長に属す。信長の越前攻めに従軍した。本能寺の変後は明智光秀に属し、光秀の死後、子・貞大とともに殺された。
-

厚谷貞政 (あつやさだまさ)
松前藩士。比石館主・厚谷重政の末裔。松前城が失火して焔硝庫が爆発した際、酒井広種とともに飛び込み藩主・公広を救うが、自身は重傷を負って死去した。
-

跡部勝資 (あとべかつすけ)
武田家臣。跡部家は信濃佐久郡の出身で甲斐守護代をも務めた名家。原昌胤とともに主君・勝頼の近侍を務めた。武田家滅亡時に諏訪で戦死。佞臣と評された。
-

穴沢俊光 (あなざわとしみつ)
蘆名家臣。伊達家の度重なる侵攻を撃退し続け、「北の門番」と恐れられた。伊達政宗の調略により、内応していた一族の奇襲を受け、自害した。
-

穴山信君 (あなやまのぶきみ)
武田家臣。一門衆の筆頭格。合戦ではおもに本陣を守った。武田家滅亡後は、徳川家康に降る。本能寺の変を知り、堺から本国へ帰る途中で何者かに討たれた。
-

穴山信友 (あなやまのぶとも)
武田家臣。武田信虎の次女を正室とする一門衆。甲斐と駿河の国境に近い河内地方を領し、主に今川家との外交において活躍した。信虎追放後は晴信に仕える。
-

姉小路良頼 (あねがこうじよしより)
飛騨の豪族。直頼の子。飛騨国司・姉小路家の名跡を継ぎ、姉小路姓を名乗る。上杉謙信に通じ、武田信玄と結んだ江馬家との間で軍事・外交戦を繰り広げた。
-

姉小路頼綱 (あねがこうじよりつな)
飛騨の豪族。良頼の長男。近隣の豪族を討ち、飛騨の統一を果たす。本能寺の変後、佐々成政と結んで羽柴秀吉に対抗したが敗れ、京都に隠棲。同地で没した。
-

姉崎隆資 (あねざきたかすけ)
小野寺家臣。酒色に溺れていた当主・輝道を諫めた家臣は容赦なく処罰されたが意を決して苦言を呈した隆資もまた、輝道の刺客に襲われて殺害された。
-

阿部定吉 (あべさだよし)
松平家臣。息子・弥七郎が主君・清康を誤殺、その責任から自害をはかるが止められる。清康の子・広忠の岡崎帰城に尽力し、その後は補佐役として活躍した。
-

阿部正次 (あべまさつぐ)
徳川家臣。伏見城番などを歴任。大坂の陣では秀忠に従い出陣し、功を立てる。後に老中に就任、幕政に重きをなした。辞任後は大坂城代となり、同地で没。
-

阿部正豊 (あべまさとよ)
家康の祖父・松平清康が暗殺された「森山崩れ」の当事者。守山城攻略のため布陣中、謀反の噂のあった父・定吉が誅殺されたものと勘違いし、清康を斬った。
-

安倍元真 (あべもとざね)
今川家臣。主家の居城・駿府城を岡部正綱とともに守るが、武田信玄の駿河侵攻軍に敗れ、本貫地・安倍に退く。以後は徳川家に属し、各地で武田軍と戦った。
-

阿部良輝 (あべよしてる)
出羽の豪族。いでわ神社の別当職を務めた。1533年に磐井出館を築き、居城とした。子・貞嗣は最上家に属し、1588年の十五里ヶ原合戦で戦死した。
-

甘粕景継 (あまかすかげつぐ)
上杉家臣。酒田城主。主家の会津移封に従い、白石城代を務めた。関ヶ原合戦では抗戦を主張。のちに居城を空けた隙に伊達軍の攻撃により居城を失った。
-

甘粕景持 (あまかすかげもち)
上杉家臣。三条城主。初名は長重。第四次川中島合戦では殿軍を務め、妻女山を襲撃した武田軍別働隊と戦う。謙信の死後は景勝に仕えて数々の戦功を立てた。
-

天草四郎 (あまくさしろう)
肥後のキリシタン。名は時貞。過酷な徴税に苦しむ農民を指揮して幕府軍と戦った。善戦した一揆軍だが、兵糧攻めの末総攻撃を受け、四郎もろとも全滅した。
-

尼子勝久 (あまごかつひさ)
誠久の子。山中幸盛らに擁立され、尼子家の再興を目指す。織田信長を頼り、出雲入国を試みるが失敗し、のちに播磨上月城の戦いで毛利軍に敗れ、自害した。
-

尼子清久 (あまごきよひさ)
尼子家臣。塩冶興久の嫡男。父・興久の謀反後、許されて尼子姓に復したが、第一次月山富田城の戦いで反尼子方に与したため、晴久に粛清された。
-

尼子国久 (あまごくにひさ)
尼子家臣。経久の次男。新宮党を率いて甥・晴久を支える。宗家を凌ぐ勢力を誇るが、のちに対立。支配体制の強化を目指す晴久によって粛清された。
-

尼子誠久 (あまごさねひさ)
尼子家臣。国久の長男。父と共に新宮党を率いる。増長したために、宗家の晴久と対立。支配体制の強化を目指す晴久によって、父と共に粛清された。
-

尼子経久 (あまごつねひさ)
出雲の戦国大名。京極家に仕えるが、所領押領の罪で出雲守護代を罷免される。のちに居城・月山富田城を奪回して勢力を広げ、中国11カ国の太守となった。
-

尼子晴久 (あまごはるひさ)
出雲の戦国大名。祖父・経久の死後家督を継ぐ。積極的な外征戦略を行い、尼子家の最大版図を築く。脆弱な支配体制を固めるため、新宮党の粛清を行った。
-

尼子久幸 (あまごひさゆき)
尼子家臣。主君・晴久(兄・経久の孫)の安芸侵攻策に反対し「臆病野州」と非難される。結局尼子軍は大敗、退却軍の殿軍を受け持ち、奮戦したが戦死した。
-

尼子義久 (あまごよしひさ)
出雲の戦国大名。月山富田城主。晴久の子。居城に籠城して毛利元就の出雲遠征軍に対抗するが、筆頭家老・宇山久兼を殺すなど、元就の離間策の前に敗れた。
-

天野興定 (あまのおきさだ)
安芸の豪族。大内家より離反して尼子家と結ぶ。のち大内義興の命を受けた陶興房に攻撃され、毛利元就の仲介により降伏。以後は大内家、毛利家に味方した。
-

天野景貫 (あまのかげつら)
今川家臣。犬居城主。田原本宿の合戦で功を立てた。主家滅亡後は武田家に仕え徳川家と戦う。武田家滅亡後は北条家に属し、佐竹家との戦いで功を立てた。
-

天野隆重 (あまのたかしげ)
大内家臣。主家滅亡後は毛利家に属す。尼子家滅亡後、出雲月山富田城代となり山中幸盛の軍を撃退した。のちに元就の五男・元秋を補佐して出雲を支配した。
-

天野隆綱 (あまのたかつな)
安芸の豪族。大内家に属す。幼少の頃、毛利隆元とともに大内家の人質となり、親交を結んだ。のち毛利家が大内家から離反すると、これと行動をともにした。
-

甘利虎泰 (あまりとらやす)
武田家臣。主君・信虎の追放に関わる。以後は信虎の子・信玄に仕え、板垣信方とともに宿老を務めた。上田原合戦で村上義清軍と激闘を展開し、戦死した。
-

雨森弥兵衛 (あめのもりやへえ)
浅井家臣。雨森城主。名は清貞。海北綱親・赤尾清綱と共に「海赤雨三将」と称された。浅井家滅亡後、雨森氏は各地に離散した。
-

荒木氏綱 (あらきうじつな)
丹波の豪族。細工所城主。豪勇をもって知られた。波多野家滅亡後、明智光秀の仕官要請を拒否、代わりに子・氏清を出仕させた。氏清は山崎合戦で戦死した。
-

荒木村重 (あらきむらしげ)
池田家臣。有岡城主。のちに織田家に仕えて摂津経略を担当するが、本願寺・毛利家と結び謀叛を起こして敗れ、逃亡。茶人となり、利休七哲の1人となった。
-

荒木村次 (あらきむらつぐ)
村重の長男。父が信長に謀叛すると、尼崎城にて織田軍と戦うが敗れる。のち羽柴秀吉に従い賤ヶ岳の戦いに参加、負傷し、以後戦には出られなかったという。
-

荒木元清 (あらきもときよ)
荒木村重の親族。従兄弟とも。村重に従って織田信長に謀叛し、居城花隈城を追われる。のち許されて豊臣家臣となるが秀次事件に連座して流刑に処された。
-

荒武宗幸 (あらたけむねゆき)
伊東家近習。1549年、伊東・島津両軍が対峙する中で、節句が祝われた。このとき島津方の中馬武蔵との相撲に勝ちを収め、武蔵の首を得たという。
-

有馬重則 (ありましげのり)
播磨の豪族。はじめ摂津有馬郡に住んだが、のちに播磨に移った。有馬家は、有馬郡の地頭職に任ぜられた赤松義祐を始祖とする、赤松家の庶流である。
-

有馬豊氏 (ありまとようじ)
豊臣家臣。則頼の嫡男。秀吉の死後は徳川家康に属し、関ヶ原合戦、大坂の両陣で戦功を立て、筑後久留米21万石を領した。島原の乱の鎮圧にも功を立てた。
-

有馬直純 (ありまなおずみ)
肥前有馬藩主。晴信の子。岡本大八事件により父が処刑された際、徳川家康の養女を娶っていたため、許されて家督を継ぐ。のち日向延岡5万石に転封された。
-

有馬則頼 (ありまのりより)
播磨の豪族。重則の子。豊臣秀吉に仕え九州征伐、朝鮮派兵などに従軍。秀吉の死後は徳川家康に仕えて関ヶ原合戦に従軍し、戦後、摂津三田3万石を領した。
-

有馬晴純 (ありまはるずみ)
肥前の豪族。日野江城主。島原半島を中心に勢力を拡大、有馬家最大の版図を築く。また大村家に次男・純忠を入嗣させて和睦、安定した支配体制を確立した。
-

有馬晴信 (ありまはるのぶ)
肥前の豪族。日野江城主。義貞の次男。兄・義純の死後、家督相続。島津家と結び勢力の回復をはかる。のち岡本大八事件を起こし、甲斐で斬罪に処せられた。
-

有馬義貞 (ありまよしさだ)
肥前の豪族。日野江城主。晴純の嫡男。将軍・足利義晴の相伴衆となった。龍造寺隆信と抗争を展開するが敗北を続け、所領を失った。詩歌に傾倒したという。
-

粟屋勝久 (あわやかつひさ)
若狭武田家臣。国吉城主。のち織田信長に属して各地を転戦する。旧主・元明が蟄居させられた際は、赦免を信長に嘆願した。本能寺の変後は豊臣秀吉に属す。
-

粟屋光若 (あわやみつわか)
若狭武田家臣。山内城主。家長の子。奉行人を務め、また信豊・義統の2代に侍大将として仕えた。永禄年間(1558~1570)に各地を転戦し活躍した。
-

粟屋元親 (あわやもとちか)
毛利家臣。元就に仕えて歴戦し、多くの武功を挙げている。隆元の信任を得て側近となり、五奉行の一人として内政面を補佐した。毛利十八将にも数えられる。
-

安国寺恵瓊 (あんこくじえけい)
毛利家臣。武田信重の子。武田家滅亡時に逃れ出家。外交僧を務めた。織田信長と豊臣秀吉の将来を予言した事で著名。関ヶ原合戦で西軍に属し、斬首された。
-

安東舜季 (あんとうきよすえ)
檜山安東家7代当主。1550年、蠣崎季広とアイヌ族の和睦協定を裁定するために蝦夷地に渡った。このことにより檜山安東家の蝦夷支配体制が確立された。
-

安東茂季 (あんとうしげすえ)
湊安東家9代当主。舜季の三男。安東堯季の養子となっていた兄・友季の死後、堯季の養子となり、湊安東家の家督を継いだ。蠣崎季広の六女を妻とした。
-

安東堯季 (あんとうたかすえ)
湊安東家7代当主。宣季の子。父の死後家督を継ぎ、管領細川家の執事から「謹上書衆」に遇された。男子に恵まれず、娘婿・舜季の三男・茂季を養子とした。
-

安東愛季 (あんとうちかすえ)
檜山安東家8代当主。舜季の嫡男。湊・檜山の両安東家を統一し、巧みな戦略で安東家最大の版図を築き上げ「斗星の北天に在るにさも似たり」と恐れられた。
-

安藤直次 (あんどうなおつぐ)
徳川家臣。小牧長久手の戦いで池田恒興や森長可を討つ武功を上げた。徳川家康側近となり、家康十男・頼宣の付家老として大坂の陣に出陣。諸軍を統制した。
-

安東尋季 (あんとうひろすえ)
檜山安東家6代当主。忠季の子。1514年、蠣崎光広に対し松前守護職を追認する。同時に「東海将軍」などの称号を使い始め、蝦夷支配権を内外に示した。
-

安東通季 (あんとうみちすえ)
湊安東家10代当主。茂季の嫡男。父の死後、伯父・愛季に湊城を追われ、豊島城に移される。愛季の死後、戸沢家と結んで謀叛を起こすが、失敗に終わった。
-

安藤守就 (あんどうもりなり)
斎藤家臣。美濃三人衆の1人。主家滅亡後は織田信長に属すが、のちに追放された。本能寺の変に乗じて旧領回復の兵を挙げるが、稲葉一鉄と戦って敗死した。
-

安藤良整 (あんどうよしなり)
北条家臣。出納関係の奉行などを担当し家中における政務の中心的存在となる。北条家領国の公定枡「安藤枡」を考案するなど、主家の発展に大きく貢献した。
-

安中重繁 (あんなかしげしげ)
山内上杉家臣。上野碓氷郡を支配した国人。安中城、松井田城を居城としたが、武田信玄の上野侵攻軍に降伏。嫡男・景繁に家督を譲らされ、隠居した。
-

安養寺氏種 (あんようじうじたね)
浅井家臣。近江の豪族。浅井長政と織田信長の妹・市の縁組を仲介した。姉川合戦で織田家の捕虜となるが、浅井勢追撃の非を進言したため、解放された。
-

安楽兼寛 (あんらくかねひろ)
肝付家臣。大隅入船城主。島津義久軍の攻撃を受けた際、居城に籠城して応戦する。しかし主家から援軍は来ず、1年3カ月の籠城戦の末、島津軍に降伏した。
-

飯尾定宗 (いいおさだむね)
織田家臣。織田信秀の従兄弟。尾張守護である斯波家の一族、飯尾家の養子となる。桶狭間の戦いで鷲津砦を守るが、朝比奈泰朝勢の攻撃を受けて戦死した。
-

飯尾連竜 (いいおつらたつ)
今川家臣。引馬城主。桶狭間合戦後、徳川家に寝返ったため、主君・氏真の攻撃を受けて敗北、和睦した。のちに氏真に駿府城に呼ばれ、同地で謀殺された。
-

飯尾乗連 (いいおのりつら)
今川家臣。賢連の子。豊前守と称す。羽柴秀吉の最初の主君として知られる松下加兵衛らを寄騎として抱えていたといわれる。桶狭間合戦に従軍し、戦死した。
-

飯坂猫 (いいざかねこ)
飯坂宗康の娘。伊達秀宗の母。伊達政宗に見初められ、側室となる。扇でねずみを追う姿が猫のようであったことから、「猫御前」と呼ばれた。
-

飯田興秀 (いいだおきひで)
大内家臣。奉行人を務めた。おもに九州方面に在陣。陶晴賢の謀叛の際は晴賢に同調し、主君・義隆の死後は主家を継いだ義長に仕えた。弓馬の故実に通じた。
-

飯田覚兵衛 (いいだかくべえ)
豊臣家臣。名は直景。加藤清正配下の侍大将。朝鮮出兵では亀甲車を建造して、晋州城の攻略戦に投入した。土木技術に通じ、熊本城築城にたずさわった。
-

井伊直勝 (いいなおかつ)
徳川家臣。直政の長男。家康の命により彦根城を築いて本拠としたが、病身だったために本家の家督は弟の直孝に譲り、自身は分家を立てて上野安中を領した。
-

井伊直孝 (いいなおたか)
徳川家臣。直政の次男。病弱だった兄・直継に代わって家督を継ぎ、近江彦根藩主となった。大坂夏の陣に参陣し、長宗我部盛親・木村重成の両軍を撃破した。
-

井伊直親 (いいなおちか)
今川家臣。井伊谷城主。直盛の養子。直盛の死後に家督を継ぐが、主君・氏真に謀反の疑いをかけられ殺された。子・直政は跡を継いだ井伊直虎に養育された。
-

井伊直虎 (いいなおとら)
今川家臣。直盛の娘。井伊家の当主が次々と死亡し、跡を継ぐ男子が絶えたため当主となる。夫を生涯迎えず、のちに井伊直政を養子にして跡を継がせた。
-

井伊直政 (いいなおまさ)
徳川家臣。徳川四天王の1人。軍装を赤で統一した軍兵は「赤鬼」と恐れられ、常に先鋒を争った。関ヶ原合戦では島津軍を追撃し、島津豊久を討ち取った。
-

井伊直盛 (いいなおもり)
今川家臣。井伊谷城主。斯波家臣・大河内貞綱に呼応して三岳城に籠城するが、朝比奈泰以軍の攻撃を受け落城、以後は今川家に属す。桶狭間合戦で戦死した。
-

伊賀久隆 (いがひさたか)
備前の豪族。虎倉城主。宇喜多直家に臣従して頭角を現し、直家が織田につくと毛利を迎え撃って大勝。しかし久隆の勢いを警戒する何者かにより謀殺された。
-

斑鳩平次 (いかるがへいじ)
加藤清正家臣。はじめ上杉謙信に仕え、その後、庄林一心に武勇を認められて清正に仕える。朝鮮の役で一番槍の功を7度まで立て、3千石を与えられた。
-

飯川光誠 (いがわみつのぶ)
畠山家臣。年寄衆を務めた。主君・義綱が能登を追放された際、これに従う。義綱の能登入国作戦の中枢を担い、軍勢を指揮して善戦したが、失敗に終わった。
-

池田勝正 (いけだかつまさ)
摂津の豪族。池田城主。長正の子。織田信長の畿内平定軍に降り、伊丹家・和田家とともに「摂津三守護」と称されるが三好家に通じた一族により追放された。
-

池田重利 (いけだしげとし)
下間頼竜の長男。母は池田恒興の養女・七条。はじめ本願寺教如に仕えたが出奔して叔父・池田輝政に仕え、池田重利と名を変えた。大坂の陣で功があった。
-

池田せん (いけだせん)
恒興の長女。森長可に嫁ぐ。賤ヶ岳合戦の岐阜城攻めでは鉄砲隊を率いて攻城に加わったという。長可討死後、長可遺言により実家に戻り、中村一氏に再嫁。
-

池田忠雄 (いけだただかつ)
輝政の三男。母は徳川家康の娘・督姫。兄・忠継死去に伴い家督を継ぎ、備前岡山藩2代藩主となる。岡山城を改修して防備を固め。城下町を整備した。
-

池田恒興 (いけだつねおき)
織田家臣。信長の乳兄弟。姉川合戦などで活躍した。本能寺の変後は、織田家四宿老の1人となる。羽柴秀吉に味方して小牧長久手の合戦に出陣し、戦死した。
-

池田輝澄 (いけだてるずみ)
輝政の四男。母は徳川家康の娘・督姫。城下町や交通網を整備。6万8千石を領し、官位も侍従まで昇りつめるも、家中で池田騒動が起こり、改易された。
-

池田輝政 (いけだてるまさ)
織田家臣。恒興の次男。本能寺の変後は豊臣家に属し、各地で活躍。関ヶ原合戦では東軍に属し、戦後、播磨姫路52万石を領して「姫路宰相」と呼ばれた。
-

池田利隆 (いけだとしたか)
徳川家臣。輝政の嫡男。父の死後、播磨姫路52万石を継ぐが、治世わずか3年で急逝した。継母・督姫が実子・忠継を後継とするために毒殺したという。
-

池田知正 (いけだともまさ)
摂津の豪族。池田城主。長正の子。兄・勝正を追放し、家督を継ぐ。三好三人衆と結んで織田信長に敵対するが、のち降伏。摂津を支配した荒木村重に属した。
-

池田長正 (いけだながまさ)
摂津の豪族。池田城主。信正の子。父が細川晴元により自害させられたあと、家督を継ぐ。三好長慶に属し、波多野家や河内畠山家との戦いで戦功を立てた。
-

池田長吉 (いけだながよし)
恒興の三男。輝政の弟。秀吉の養子として豊臣家の天下統一事業に寄与。関ヶ原合戦では東軍に属して武功を挙げ、家康より加増を受けて因幡鳥取藩主となる。
-

池田長幸 (いけだながよし)
長吉の長男。幼少のころから老臣・水野善右衛門の薫陶を受けた。家督を継ぎ、因幡鳥取藩主となり、のちに備中松山に移封される。新田開発に努めた。
-

池田信正 (いけだのぶまさ)
摂津の豪族。細川晴元に重用され、将軍家からも厚遇を受けた。三好長慶が細川氏綱を擁して晴元と対立すると、氏綱方に属して敗れ、晴元に自害させられた。
-

池田政綱 (いけだまさつな)
輝政の五男。母は徳川家康の娘・督姫。兄・忠継死去の際に、3万5千石を分与され播磨赤穂藩を立藩。藩政の基礎を固めたが、若くして死去した。
-

池田光政 (いけだみつまさ)
利隆の嫡男。徳川家光より一字を賜る。備前岡山31万石の藩主。儒学を奨励して学校を興し、また領民の生活向上に努めて岡山藩政の基礎を固めた名君。
-

池田盛周 (いけだもりちか)
大宝寺家臣。出羽朝日山城主。太閤検地に反対する農民一揆に加担、天下に逆らう悪党を自認し「悪次郎」と称する。治水や開墾に寄与して、民衆に慕われた。
-

生駒一正 (いこまかずまさ)
豊臣家臣。親正の子。雑賀攻めなどで活躍した。朝鮮派兵の際は渡海し、蔚山城の戦いなどに参加。関ヶ原合戦では東軍に属し、戦後、讃岐高松城主となった。
-

生駒親正 (いこまちかまさ)
豊臣家臣。讃岐高松17万石を領した。主君・秀吉の死後は、三中老の1人となる。関ヶ原合戦で西軍に属すが、子・一正が東軍に属したため、改易を免れた。
-

生駒利豊 (いこまとしとよ)
豊臣家臣。家長の子。幼少より秀次に近侍するが、秀次死後は秀吉に仕えた。関ヶ原では東軍に属し、福島正則配下として戦う。のちに松平忠吉の家臣となる。
-

生駒正俊 (いこままさとし)
一正の長男。父の死後家督を継ぎ、讃岐高松藩17万1千石の2代藩主となる。大坂の陣では遊軍として参加した。正室には藤堂高虎の養女を迎えている。
-

猪去詮義 (いさりあきよし)
奥州斯波家臣。詮高の三男。父が雫石地方を攻略した際に、猪去館主となり、猪去御所を称した。猪去館は、斯波家滅亡の際に南部信直によって攻略された。
-

伊沢綱俊 (いざわつなとし)
阿波の豪族。羽柴秀吉の四国征伐後、阿波に入国した蜂須賀家政に対する一揆などを鎮圧した。その功績を認められ、与頭庄屋に任ぜられた。
-

石亀信房 (いしがめのぶふさ)
南部家22代当主・南部政康の四男。兄の南部安信から石亀の地を与えられ、石亀姓を名乗った。不来方城主を務め、南方の斯波家に備えた。
-

石川家成 (いしかわいえなり)
徳川家臣。数正の叔父。三河一向一揆の平定戦で功を立てた。今川家滅亡後、掛川城主となる。晩年は美濃大垣5万石を領した。家康への忠誠無二と評された。
-

石川数正 (いしかわかずまさ)
徳川家臣。家老を務め、西三河衆を率いて活躍した。小牧長久手合戦の後、豊臣家へ出奔。そのため、徳川家は三河以来の軍制を武田流に改めることになった。
-

石川五右衛門 (いしかわごえもん)
伊賀忍者。百地三太夫の副将であったという。豊臣秀吉の暗殺を謀り大阪城に侵入するが、名器「千鳥の香炉」が鳴いたため失敗した。釜ゆでにされたという。
-

石川貞清 (いしかわさだきよ)
豊臣家臣。尾張犬山城主を務める。関ヶ原合戦では西軍に属して勇戦。戦後、改易されるが死は免れる。その後は剃髪して宗林と号し、京都で金融業を営んだ。
-

石川貞政 (いしかわさだまさ)
豊臣家臣。関ヶ原合戦の際は東軍として一番首を得るなど奮戦した。その後は秀頼に仕えたが、大坂冬の陣直前に高野山に入る。主家滅亡後は徳川家に仕えた。
-

石川高信 (いしかわたかのぶ)
南部家臣。南部政康の次男。津軽郡代として甥・晴政を補佐し、南部家の勢力拡大に大きく貢献した。のちに家臣・大浦(津軽)為信の謀叛により、自害した。
-

石川忠総 (いしかわただふさ)
徳川家臣。大久保忠隣の次男。母方の祖父・石川家成の養子となり、石川家を継いだ。父・忠隣失脚に連座するが、大坂の陣に許されて参陣、奮戦し活躍した。
-

石川直経 (いしかわなおつね)
一色家臣。加悦城主。主・義清の権力が弱った際に実権を握った三奉行の1人。一色九郎を擁立し内乱を起こした延永春信に一度敗れるが、反攻して撃退した。
-

石川久智 (いしかわひさとも)
備中の豪族。高山城主。三村元親に従って明禅寺合戦に従軍するが、宇喜多直家の軍勢に敗れて負傷、死去した。石川家は吉備津神社社務代を基礎とした豪族。
-

石川久式 (いしかわひさのり)
備中の豪族。高山城主。久智の子。父の死後、家督を継ぐ。義兄・三村元親に協力して毛利軍と戦うが敗れる。再興をはかるが、毛利軍の攻撃を受け自害した。
-

石川通清 (いしかわみちきよ)
河野家臣。高峠城主。備中守と称した。一時三好家に属して先鋒を務めるが、河野家に攻められて敗れ、降伏した。のちに長宗我部元親の伊予侵攻軍に降った。
-

石川康勝 (いしかわやすかつ)
豊臣家臣。数正の次男。大坂の陣で大坂城に籠城。真田丸の戦いで火薬を誤爆させたが、これを合図と勘違いし殺到した徳川軍を真田幸村が打ち破った。
-

石川康長 (いしかわやすなが)
徳川家臣。数正の子。父に従い主家を出奔、豊臣家に属す。父の死後、信濃松本6万石を相続。関ヶ原合戦では東軍に属す。のちに領地隠匿の罪で改易された。
-

石田重家 (いしだしげいえ)
三成の子。関ヶ原合戦では人質として大坂城に留まる。戦後、京都寿聖院に入り剃髪。寿聖院住職の助命嘆願により許された。のち寿聖院の三世住職となった。
-

石田重成 (いしだしげなり)
三成の次男。関ヶ原合戦の後、津軽信建の助けで津軽へ逃れ、杉山原吾と名を変えて逼塞。一説に津軽家に仕えたともいう。子孫は津軽家重臣として続いた。
-

石田正澄 (いしだまさずみ)
豊臣家臣。関ヶ原合戦では父・正継とともに弟・三成の居城・佐和山城を守備する。西軍の敗北後、小早川秀秋らの攻撃を受け落城、一族とともに自害した。
-

石田正継 (いしだまさつぐ)
三成の父。文武に優れ、和漢に通じる才人であったと伝わる。佐和山城代を務めて三成の補佐に当たるが、関ヶ原の戦い後、東軍に攻められ、落城と共に自刃。
-

石田三成 (いしだみつなり)
豊臣家臣。五奉行の1人として国政に参画。主君・秀吉の死後、西軍を指揮して徳川家康と関ヶ原で戦うが、諸将の統制をとれずに敗れ、京都で斬首された。
-

伊地知重興 (いじちしげおき)
大隅の豪族。小浜城主。肝付家と結んで島津家に対抗するが、島津軍に居城を落とされたため、降伏した。その後は島津家に属し、大友家攻めなどに従軍した。
-

石野氏満 (いしのうじみつ)
別所家臣。主君・長治とともに三木城に籠城して羽柴秀吉と戦い、羽柴家臣・古田重則を討つなど活躍した。長治の死後は秀吉に属す。のち前田利家に仕えた。
-

石巻康敬 (いしまきやすまさ)
北条家臣。御馬廻衆の1人で、評定衆を務めた。主君・氏直が上洛を反古にした際、弁明のために豊臣秀吉のもとに赴いた。主家滅亡後は徳川家康に仕えた。
-

伊集院忠倉 (いじゅういんただあお)
島津家臣。忠朗の子。父とともに大隅加治木城主・肝付兼演を攻撃して降伏させその所領の処理を担当する。のちに老中に就任し、主家の勢力拡大に貢献した。
-

伊集院忠朗 (いじゅういんただあき)
島津家臣。知勇に優れ、主家の薩摩統一に貢献した。大隅加治木城攻めの際には日本で初めて鉄砲を実戦に使用した。のちに老中に就任し、国政に参画した。
-

伊集院忠棟 (いじゅういんただむね)
島津家臣。忠倉の子。老中を務めた。豊臣秀吉の九州征伐軍に敗れ、人質となった。秀吉から主家と同格の扱いを受けたため、主君・忠恒と対立して殺された。
-

以心崇伝 (いしんすうでん)
徳川家臣。武家諸法度などの法令制定を担当する。方広寺鐘銘事件を引き起こして大坂の陣の口実を作るなど調略面でも活躍し「黒衣の宰相」の異名をとった。
-

泉田胤清 (いずみだたねきよ)
相馬家臣。泉田城主。1588年、守備していた大越城に攻め寄せてきた伊達政宗の軍を撃退するなど、主君・義胤に従って伊達家と攻防を繰り返した。
-

泉山古康 (いずみやまふるやす)
南部家臣。政昭(石亀信房の子)の子。叔父・泉山康朝の養子として三戸郷泉山村を領し、泉山姓を名乗る。娘・慈照院はのちに主君・信直の後室となった。
-

泉山政義 (いずみやままさよし)
南部家臣。古康の嫡男。姉は主君・信直の後室・慈照院。のちに石亀家が絶えたため、石亀姓を名乗った。信直の義弟として南部藩重臣20名のうちに列した。
-

出雲阿国 (いずもおくに)
戦国時代の女性で、歌舞伎踊りの始祖。出雲大社の巫女を称し、京都で念仏踊りを上演して、人気を博す。晩年は出雲国で尼になったというが、謎が多い。
-

伊勢貞昌 (いせさだまさ)
島津家臣。有職故実の伝授を受けた。島津義弘に属し武功多く、関ヶ原合戦では稲津重政との戦いに活躍。筆頭家老を務め島津忠恒参勤の際は必ず供をした。
-

磯野員昌 (いそのかずまさ)
浅井家臣。佐和山城主。姉川合戦では先鋒を務めて奮戦した。のちに織田信長に降った。新庄城主となるが、勘気を蒙って所領を没収され、高野山に出奔した。
-

五十目秀兼 (いそのめひでかね)
安東家臣。愛季の直臣。安東家に叛旗を翻した大館城主・浅利勝頼が、安東家との戦いに敗れて居城を明け渡したのち、大館城に入り、比内代官となった。
-

板垣信方 (いたがきのぶかた)
武田家臣。主君・信虎の追放に関わる。以後は信虎の子・信玄に仕え、各地の合戦で活躍した。上田原合戦で先鋒を務め村上義清軍と戦い、激闘の末戦死した。
-

板倉勝重 (いたくらかつしげ)
徳川家臣。はじめ僧侶であったが、父と弟の死により還俗、家督を継ぐ。駿府や江戸の町奉行を務めたあと、京都所司代となり、西国諸大名らの監視を行った。
-

井田親氏 (いだちかうじ)
秋月家臣。親之の子。早くから武勇の誉れが高かったという。大友家との合戦で総大将に任じられ勇躍出陣するが、敵を深追いして伏兵に襲撃され、戦死した。
-

井田親之 (いだちかゆき)
秋月家臣。左馬助と称す。大友軍に子・親氏を討たれた際、仏壇の柱に和歌一首を書き付けて、子の霊に手向けた。のちに、とある戦で先陣を務め、戦死した。
-

板部岡江雪斎 (いたべおかこうせつさい)
北条家臣。右筆・評定衆を務めた。徳川家康との講和交渉や、豊臣秀吉との折衝など、対外交渉に手腕を発揮した。主家滅亡後は、秀吉に御咄衆として仕えた。
-

伊丹康直 (いたみやすなお)
今川家臣。伊丹城主・雅興の子。幼少の頃に駿河に逃れ、今川家に仕える。氏真の代には海賊奉行を務めた。主家滅亡後は武田家、徳川家で船奉行を務めた。
-

市川経好 (いちかわつねよし)
吉川家臣。父・吉川経世とともに毛利元就の次男・元春の吉川家相続に尽力。のち毛利家に属す。大内家滅亡後は山口奉行を務め、防長両国の庶政を担当した。
-

一栗高春 (いちくりたかはる)
大崎家臣。一栗城主。葛西・大崎一揆の際は居城に籠城し、最後まで奮戦する。一揆鎮定後は最上家に仕え、鶴岡城番を務めたが、謀叛を起こして誅せられた。
-

一栗放牛 (いちくりほうぎゅう)
大崎家臣。一栗城主。一栗高春の祖父という。1591年の葛西・大崎一揆の際は、92歳の高齢であるにも関わらず居城に籠城して戦うが敗れ、戦死した。
-

一条兼定 (いちじょうかねさだ)
土佐一条家4代当主。房基の子。日夜酒色にふける生活を送ったため、家臣たちによって追放された。のちに大友宗麟の後援で旧領回復を企てるが、失敗した。
-

一条内政 (いちじょうただまさ)
土佐一条家6代当主。兼定の嫡男。父を追放した長宗我部元親に擁立され、傀儡当主となる。長宗我部家臣・波川清宗の謀反に加担し、伊予国に追放された。
-

一条信龍 (いちじょうのぶたつ)
武田信玄の異母弟。甲斐上野城主。甲斐源氏の流れを汲む一条家の名跡を継ぐ。信玄の遺言により勝頼の後見人を務め、衰退する武田家に最期まで尽くした。
-

一条房家 (いちじょうふさいえ)
土佐一条家初代当主。関白・一条教房の次男。国人衆の嘆願により元服し、大名となった。本山家に追われた長宗我部国親を保護し、その再興に尽力した。
-

一条房冬 (いちじょうふさふゆ)
土佐一条家2代当主。房家の子。家臣の讒言を信じて傅役・敷地藤安に自害を命じる。藤安の無実を知り赦免の使いを送るが藤安は自害したあとだったという。
-

一条房通 (いちじょうふさみち)
房家の次男。一条兼定の養父。関白に就任した。房基・兼定が、土佐一条家を幼少の身で継いだため、土佐に下向して自ら政務を執った。
-

一条房基 (いちじょうふさもと)
土佐一条家3代当主。房冬の子。姫野々城主・津野基高を討ち、大平家の居城・土佐蓮池城を奪うなど、勢力を拡大するが、突然自害した。狂気のためという。
-

一迫隆真 (いちはさまたかざね)
大崎家臣。真坂城主。伊豆守と称す。狩野姓も称した。一迫・狩野家は大崎一族の参謀を務めたという。天正末期の主家内乱に際しては、氏家吉継に味方した。
-

市橋長勝 (いちはしながかつ)
豊臣家臣。九州征伐、小田原征伐に参陣する。関ヶ原合戦では東軍に味方して、大坂の陣にも従軍。その功によって加増され越後三条4万1千石余を領した。
-

一萬田鑑実 (いちまだあきざね)
大友家臣。豊後小牟礼城主。生涯のほとんどを軍陣で過ごした一方で、主君・宗麟を招いて観桜会を開いた風流人。一族から謀叛人が出た責を負い、自害した。
-

一色在通 (いっしきありみち)
足利家臣。唐橋在数の次男。主君・義昭が京都を追放されたあとは徳川家康に仕えた。のち高家に列す。慶長年間(1596~1615)に唐橋家を相続した。
-

一色藤長 (いっしきふじなが)
足利家臣。御供衆を務めた。細川藤孝とともに幽閉された主君・義昭の脱出に尽力。のちに義昭が京都を追放されると、義昭の将軍職復帰を目指して奔走した。
-

一色満信 (いっしきみつのぶ)
丹後の戦国大名。義道の子。父の死後、家臣・稲富祐直を頼り、細川藤孝軍と戦う。のち明智光秀の斡旋で和睦し藤孝の娘を娶るが、再び背いたため殺された。
-

一色義清 (いっしきよしきよ)
丹後の戦国大名。甥・満信が細川藤孝に謀殺されたあと、弓木城に入り一色宗家を継いだ。しかし、細川忠興に城を包囲されたため、敵陣に突入して戦死した。
-

一色義道 (いっしきよしみち)
丹後の戦国大名。義幸の子。京を追われた将軍・足利義昭を庇護したため、織田軍に攻められる。善戦するが、家臣・沼田勘解由の内通により敗れ、自害した。
-

一色義幸 (いっしきよしゆき)
丹後の戦国大名。隣国の若狭武田家としばしば戦った。一色家は清和源氏足利家一門で、山名・赤松・京極家とともに四職の家格となり、幕府で重きをなした。
-

出浦盛清 (いでうらもりきよ)
武田家臣。出浦城主。村上義清の氏族。甲州忍者の棟梁。武田家に仕える。武田家滅亡後、真田家に仕える。棟梁でありながら、自らも忍び働きを行った。
-

伊東一刀斎 (いとういっとうさい)
戦国時代末期の剣客。鐘巻自斎に剣を学び、一刀流剣術を創始した。諸国を旅して、勝負すること三十三回に及び、一度も敗れなかったと言われる。
-

伊東祐兵 (いとうすけたか)
豊臣家臣。義祐の子。豊臣秀吉の九州征伐軍の先導役を務め、日向飫肥の旧領を回復した。朝鮮派兵にも従軍。関ヶ原合戦では東軍に属すが、戦後、病死した。
-

伊東祐慶 (いとうすけのり)
日向飫肥藩主。祐兵の子。関ヶ原合戦では父とともに東軍に属し、高橋元種軍や島津軍と戦った。父の死後、日向飫肥3万6千石を継ぐ。検地・開墾を行った。
-

伊東祐松 (いとうすけます)
伊東家臣。義祐擁立に功があり、その側近として権勢を誇り家中から憎まれた。空砲で合戦をするという嘘の約束をして肝付家を破り、南郷を奪い取った。
-

伊東祐安 (いとうすけやす)
伊東家臣。義祐の義弟という。知勇兼備の将といわれた。木崎原合戦の際に総大将を務めるが、兵力に劣る島津軍の攪乱戦法や奇襲攻撃の前に敗れ、戦死した。
-

伊東長実 (いとうながざね)
豊臣家臣。日向伊東氏の遠い一族で、流浪の伊東祐兵を保護した。大坂の陣では七手組組頭として大坂城に籠るが、敗戦後、許されて徳川家に仕えた。
-

伊東マンショ (いとうまんしょ)
伊東義祐の孫でキリシタン。名は祐益、マンショは洗礼名。大友宗麟の縁戚で、遣欧使節正使となる。教皇やイスパニア国王に拝謁し、帰国後司祭になった。
-

伊東盛正 (いとうもりまさ)
豊臣家臣。父・盛景の死後、家督を相続し、美濃大垣3万4千石を領す。関ヶ原合戦では西軍に属し、戦後、所領没収の上追放された。のち前田利常に仕えた。
-

伊東義賢 (いとうよしかた)
伊東家臣。義益の子。祖父・義祐とともに大友宗麟を頼る。豊臣秀吉の九州平定後、叔父・祐兵が日向飫肥を回復し、祐兵に従った。朝鮮派兵の際に病死した。
-

伊東義祐 (いとうよしすけ)
日向の戦国大名。伊東家最大の版図を築くが、木崎原合戦で島津軍に敗れ衰退。豊後の大友宗麟を頼るが、大友軍が耳川合戦で大敗したあとは各地を流浪した。
-

伊東義益 (いとうよします)
日向の戦国大名。義祐の子。庶子であったが、嫡子が夭逝のため家督を継ぎ、父の後見を受けて伊東家の全盛時代を築き上げた。島津家との対陣中に病死した。
-

井戸良弘 (いどよしひろ)
筒井家臣。井戸城主。のち居城を子・覚弘に譲り、織田信長に仕える。各地で功を立て、山城槇島2万石を得た。山崎合戦で明智光秀に属したため改易された。
-

稲垣重綱 (いながきしげつな)
徳川家臣。関ヶ原合戦では徳川秀忠に属し、上田城攻めに加わった。大坂の陣では酒井家次に属し戦った。のち、大坂城代を務め、三河刈谷藩初代藩主となる。
-

伊奈忠次 (いなただつぐ)
徳川家臣。主君・家康の近習として民政に参画。関東全土で検地や治水を行い、江戸幕府の経済基盤確立に貢献した。その地方仕法は「伊奈流」と呼ばれた。
-

伊奈忠政 (いなただまさ)
徳川家臣。後方支援で活躍。父・忠次とともに新田開発、治水に務め、父の死後関東郡代職を継ぐ。大坂の陣では普請奉行として堀の埋め立てなどを行った。
-

稲次右近 (いなつぎうこん)
摂津有馬家臣。則頼に従い東軍に属して関ヶ原合戦に参陣。その前哨戦・杭瀬川合戦で石田三成の将・横山監物を討つ。大坂の陣でも活躍。島原の乱で戦死。
-

稲津重政 (いなづしげまさ)
伊東家臣。清武城主。関ヶ原合戦では西軍方の宮崎城を落とす。戦後、幕命による宮崎城返還を拒否。主君・祐慶の自害命令も拒否して居城に籠城、敗死した。
-

稲富祐直 (いなとみすけなお)
一色家臣。稲富流砲術の始祖。主家滅亡後は細川忠興に属し、鉄砲の師範を務める。のちに徳川家に仕え、幕府鉄砲方として国友鍛冶集団の組織化に尽力した。
-

稲富祐秀 (いなとみすけひで)
一色家臣。丹後忍木城主。相模守と称した。佐々木少輔次郎義国に砲術を学び、創意を加えた。のちに孫・祐直に砲術を教え、稲富流砲術の基礎を築き上げた。
-

稲葉一鉄 (いなばいってつ)
斎藤家臣。美濃三人衆の1人。主家滅亡後、織田家に仕える。姉川合戦では浅井軍に横槍を入れ、味方を勝利に導いた。頑固な性格から「一徹」の語源になる。
-

稲葉貞通 (いなばさだみち)
織田家臣。一鉄の長男。本能寺の変後は豊臣秀吉に仕えた。関ヶ原合戦では織田秀信に従い西軍に属すが、のち東軍に降伏。戦後、豊後臼杵5万石を領した。
-

稲葉重通 (いなばしげみち)
織田家臣。一鉄の庶長子。本能寺の変後は豊臣秀吉に仕え、馬廻を務める。小牧長久手合戦や九州征伐などに従軍し、父の死後、美濃清水1万2千石を領した。
-

稲葉典通 (いなばのりみち)
豊臣家臣。貞通の長男。九州征伐の際、主君・秀吉の勘気を蒙り蟄居するが、のちに復帰し、各地の合戦に従軍。父の死後家督を継ぎ、大坂冬の陣に出陣した。
-

稲葉紀通 (いなばのりみち)
徳川家臣。道通の子。大坂の陣で初陣。残虐無道で狩りで獲物が獲れなかった腹いせに領民を大量虐殺するなどしたという。のち謀反の疑いがかかり自害した。
-

稲葉正成 (いなばまさなり)
林政秀の子。稲葉重通の娘を娶り、稲葉姓を名乗る。小早川家に仕え、関ヶ原合戦で秀秋を東軍に寝返らせた。のち徳川家光の乳母・春日局を後妻とする。
-

稲葉道通 (いなばみちとお)
豊臣家臣。重通の五男。兄・牧村利貞の死後、その遺子が幼少であったため、伊勢岩手2万石余を相続した。関ヶ原合戦では東軍に属し、九鬼嘉隆と戦った。
-

猪苗代盛国 (いなわしろもりくに)
蘆名家臣。後妻の讒言により子・盛胤の廃嫡を企むが発覚し、盛胤と争った。のちに主家に背いて伊達家に属し、摺上原合戦では先鋒を務めて蘆名軍と戦った。
-

猪苗代盛胤 (いなわしろもりたね)
蘆名家臣。盛国の子。摺上原合戦で主家が敗れたあと、主君・盛重に従い常陸に逃れる。のちに盛重のもとを去って故郷の猪苗代に戻り、同地で余生を送った。
-

犬甘久知 (いぬかいひさとも)
小笠原家臣。政徳の三男。日岐城攻めや高遠城攻めなど、各地の合戦に侍大将として従軍し、活躍。のちに筆頭家老として家中最高の1千6百石を給与された。
-

犬甘政徳 (いぬかいまさのり)
小笠原家臣。主君・長時が武田信玄に追われたあとも居城・犬甘城に籠城して抵抗した。しかし、長時の軍勢を出迎える途中で武田軍と遭遇し、戦うが敗れた。
-

井上重房 (いのうえしげふさ)
伊予宇都宮家臣。中尾城主。長養寺を創建し、城下に出没する海賊を討って民衆の生活を安定させるなどの施策を行う。のちに長宗我部軍に居城を落とされた。
-

井上元兼 (いのうえもとかね)
毛利家臣。主君・元就の毛利家相続に尽力した。のちに軍役や普請などの諸役を怠るなどの横柄な態度をとったため、元就によって井上一族30名が殺された。
-

井上之房 (いのうえゆきふさ)
黒田家臣。黒田八虎の一人。職隆の頃より四代に仕えた忠臣。石垣原の戦いでは孝高に従って武功を挙げた。長政没後の「黒田騒動」では藩の存続に貢献した。
-

猪俣邦憲 (いのまたくにのり)
北条家臣。北条氏邦に仕え、沼田城代を務めた。真田昌幸の支城・名胡桃城を独断で奪取し、豊臣秀吉に小田原征伐の口実を与えた。戦後、磔刑に処せられた。
-

茨木長隆 (いばらぎながたか)
細川家臣。管領・細川高国を討ち、三好元長を滅ぼし、京の法華一揆を鎮圧するなど各地で活躍した。三好政長が摂津江口合戦で敗死したあとは没落した。
-

今泉高光 (いまいずみたかみつ)
宇都宮家臣。上三川城主。主君・国綱の後継者に浅野長政の子・長重を迎えることを主張し、宿老・芳賀高武と対立。のちに高武の攻撃を受け、敗死した。
-

今川氏真 (いまがわうじざね)
駿河の戦国大名。義元の嫡男。父の死後、家督を継ぐ。しかし、蹴鞠や和歌に傾倒し、無為の日々を送る。その結果、徳川家康と武田信玄に領国を追われた。
-

今川氏輝 (いまがわうじてる)
今川家8代当主。幼くして当主となり、馬廻衆の創設や、検地の実行、流通の活性化などの政策を実施する。しかし、名将の評判が立ち始めた途端、急死した。
-

今川良真 (いまがわよしざね)
今川氏親の子。法名・玄広恵探。8代当主・氏輝死後の家督争いで起こった花倉の乱で、梅岳承芳(今川義元)と戦ったが、敗れて自害した。
-

今川義元 (いまがわよしもと)
駿河の戦国大名。異母兄・玄広恵探を倒して家督を継ぐ。甲相駿三国同盟を結んで後顧の憂いを断ち、上洛の途につくが桶狭間で織田信長の奇襲を受け、絶命。
-

入来院重時 (いりきいんしげとき)
島津家臣。実父は島津以久。重豊の養子となり義弘に属して活躍する。関ヶ原合戦後、撤退する義弘とはぐれてしまい、東軍に捕縛され討ち取られた。
-

入来院重朝 (いりきいんしげとも)
薩摩大隅の豪族。重朝は実際は薩摩の豪族。妹は島津貴久に嫁いだ。島津忠良と島津実久の抗争の際は、忠良を支持して市来城攻めなど各地の合戦で活躍した。
-

色部顕長 (いろべあきなが)
上杉家臣。平林城主。勝長の子。主君・謙信から名を授かった。父の死後、家督を継ぐ。本庄繁長の謀叛鎮圧で活躍し、以降、繁長より上位の席を与えられた。
-

色部勝長 (いろべかつなが)
上杉家臣。平林城主。上条定憲の乱の際は一時上条方に属す。川中島合戦で活躍し、感状を授かった。謀叛を起こした本庄繁長の居城・村上城を攻囲中に病死。
-

色部長実 (いろべながざね)
上杉家臣。平林城主。勝長の子。兄・顕長の死後、家督を継ぐ。出羽仙北一揆の鎮圧などで活躍した。豊臣秀吉の朝鮮派兵に従軍した際、大病を患い死去した。
-

岩井信能 (いわいのぶよし)
上杉家臣。御館の乱では上杉景勝に属し飯山城主となる。城下町を整備して近世飯山町の基礎を築いた。主家の会津転封後は、会津三奉行の1人に数えられた。
-

岩上朝堅 (いわかみともかた)
結城家臣。旧姓は三浦。主君・晴朝から結城四天王の一・岩上姓の名乗りを許された。佐竹義重や田村清顕と文書のやりとりを行うなど、外交面で活躍した。
-

岩城貞隆 (いわきさだたか)
陸奥大館城主。佐竹義重の三男。岩城常隆の養子となる。関ヶ原合戦に出陣せず改易された。のちに大坂の陣に参加し、信濃川中島1万石を与えられた。
-

岩城重隆 (いわきしげたか)
陸奥大館城主。伊達家の内紛(天文の大乱)の際は、娘・久保が晴宗の妻であった関係から、晴宗方に属した。佐竹義篤ともたびたび争った。和歌をよくした。
-

岩城親隆 (いわきちかたか)
陸奥大館城主。伊達晴宗の長男。岩城重隆の養子となって家督を継ぎ、養父が築いた領国を継承する。しかし、佐竹家の侵攻を受け、従属を余儀なくされた。
-

岩城常隆 (いわきつねたか)
陸奥大館城主。親隆の子。豊臣秀吉の小田原征伐に参陣して戦功を立て、秀吉から所領を安堵されたが、北条家の降伏後間もなく、鎌倉で病没した。
-

岩城由隆 (いわきよしたか)
陸奥の豪族。常隆の子。古河公方の足利政氏・高基親子の争いでは、佐竹家とともに政氏方に属し、高基方に属した宇都宮家や下総結城家と戦いを繰り広げた。
-

岩城吉隆 (いわきよしたか)
佐竹氏20代当主・佐竹義重の三男・岩城貞隆の長男。父の遺領・信濃中村1万石を領す。のち伯父・佐竹義宣の養子となり後を継ぎ久保田藩2代藩主となる。
-

岩清水義長 (いわしみずよしなが)
斯波家臣。肥後と称す。政務を省みず遊興に耽る主君・詮直をたびたび諫めるが聞き入れられなかったという。南部家が斯波家を滅ぼした際に、主家に殉じた。
-

岩清水義教 (いわしみずよしのり)
斯波家臣。義長の弟。右京を称す。主家の前途に不安を抱き、南部家に内通。居城・石清水館で兵を挙げ、これをきっかけに南部軍が侵攻、斯波家は滅亡した。
-

岩成友通 (いわなりともみち)
三好家臣。三好三人衆の1人。三好家一族同様の扱いを受けた。将軍・足利義昭の挙兵に応じ、山城淀城に籠城するが、細川藤孝らの軍に攻められ、敗死した。
-

犬童頼兄 (いんどうよりもり)
相良家臣。頼安の子。関ヶ原合戦では主君・頼房を東軍に内応させ、主家の存続に貢献。のち国家老を務めたが、専横の振る舞いが多く、津軽へ流罪となった。
-

犬童頼安 (いんどうよりやす)
相良家臣。武勇に優れ、各地で活躍。肥後水俣城攻防戦では敵将・新納忠元と連歌を応酬した。主君・義陽の死後は、深水長智とともに幼主・頼房を補佐した。
-

植木秀資 (うえきひですけ)
備中の豪族。佐井田城主。下総守と称した。父・秀長と同様に毛利・宇喜多両家の間で離合集散を繰り返す。一時尼子家に居城を奪われるが、のちに奪回した。
-

植木秀長 (うえきひでなが)
備中の豪族。佐井田城主。下総守と称した。父・藤資は庄為資の弟にあたる。居城が宇喜多家と毛利家の国境にあったため、両家の間で離合集散を繰り返した。
-

上杉景勝 (うえすぎかげかつ)
出羽米沢藩主。長尾政景の子。上杉謙信の養子となった。謙信の死後、御館の乱に勝利して家督を継いだ。関ヶ原合戦では西軍に属し、最上・伊達軍と戦った。
-

上杉景虎 (うえすぎかげとら)
北条氏康の七男。越相同盟成立の際に越後に赴き、のちに上杉謙信の養子となった。謙信の死後、御館の乱において義弟の上杉景勝と家督を争うが、敗死した。
-

上杉景信 (うえすぎかげのぶ)
上杉家臣。主君・謙信が関東管領に就任した際、謙信とともに上杉姓に改める。一門衆の重鎮として各地を転戦した。御館の乱で上杉景虎方に属し、戦死した。
-

上杉謙信 (うえすぎけんしん)
越後の戦国大名。為景の次男。上杉憲政から関東管領職を譲られ、上杉姓を名乗る。「毘」の軍旗を翻して疾駆する姿は軍神と恐れられた。通称「越後の龍」。
-

上杉定勝 (うえすぎさだかつ)
景勝の嫡男。出羽米沢藩30万石の2代藩主。母が早世したため直江兼続とお船に養育された。三女は「忠臣蔵」で有名な吉良上野介に嫁いだ。
-

上杉定実 (うえすぎさだざね)
越後守護。越後守護代・長尾為景に擁立され、養父・房能を自害させて越後守護となる。のちに為景と対立、宇佐美房忠とともに為景排除を企むが、失敗した。
-

上杉朝興 (うえすぎともおき)
扇谷上杉家当主。家臣・太田資高の北条家内通により、居城・江戸城を奪われ河越城に逃れた。江戸城奪還を目指し北条家と戦うが、勢力回復はならなかった。
-

上杉朝定 (うえすぎともさだ)
扇谷上杉家当主。朝興の子。北条家に居城・河越城を奪われる。周辺諸国と和睦して大軍で河越城を囲むが、北条軍の奇襲に遭い戦死、扇谷上杉家は断絶した。
-

上杉憲政 (うえすぎのりまさ)
山内上杉家当主。河越合戦に敗れて勢力を失い、北条軍に追われ越後に逃走。長尾景虎に上杉姓と関東管領職を譲った。御館の乱で上杉景勝に殺された。
-

上田重安 (うえだしげやす)
豊臣家臣。九州征伐、小田原征伐などに従軍した。関ヶ原合戦では西軍に属し、戦後改易される。のち浅野家に仕え、大坂の陣に出陣した。茶人としても著名。
-

上田朝直 (うえだともなお)
扇谷上杉家臣。北条家の武蔵侵攻軍に降り、以後は北条家に仕える。他国衆として松山城主となり、独自の朱印状を使用して北条家から独立した支配を行った。
-

上田憲定 (うえだのりさだ)
北条家臣。朝直の次男。父や兄・長則と同じく、松山城の城下町経営に努めた。豊臣秀吉の小田原征伐に際して小田原城に籠城し、落城後、行方不明となった。
-

上田政広 (うえだまさひろ)
扇谷上杉家臣。朝直の子。松山城主。川越城合戦で、敗れた上杉朝定が落ち延びてくると匿うが、後に北条家に降る。上杉謙信との戦いで討死した。
-

植田光次 (うえだみつつぐ)
伊賀の豪族。伊賀十二人衆の中心人物。織田信雄の伊賀侵攻の際は、信雄の臣・柘植三郎左衛門を討ち、織田軍を撃退した。のち織田軍に敗れ、三河に逃れた。
-

上野隆徳 (うえのたかのり)
三村家臣。常山城主。主君・家親の娘を娶った。義兄・元親の死後も居城に籠城して毛利家に抵抗したため、小早川隆景率いる毛利軍の攻撃を受け、玉砕した。
-

上村長種 (うえむらながたね)
相良家臣。頼興の弟。頼興と主君・義滋の提携を実現させ、国政に参画した。家中の信望は高く、その勢力を恐れた兄に殺された。のちに祟りがあったという。
-

上村頼興 (うえむらよりおき)
相良家臣。肥後上村城主。子・晴広を継嗣とする約束で主君・義滋に協力する。義滋政権の陰の実力者として、その実現と存続のために義兄や実弟を謀殺した。
-

上村頼孝 (うえむらよりよし)
相良家臣。肥後上村城主。頼興の次男。父の死後、2人の弟とともに甥・義陽に背くが敗れ、薩摩に逃亡。のちに謀略によって帰国させられ、義陽に殺された。
-

魚住景固 (うおずみかげかた)
朝倉家臣。一乗谷四奉行の1人として国政に参画した。織田信長の越前侵攻軍に降り、本領を安堵され越前守護代となるが、富田長繁の攻撃を受けて敗死した。
-

宇喜多詮家 (うきたあきいえ)
宇喜多家臣。忠家の子。主家の内乱により出奔、徳川家康に属す。関ヶ原合戦の戦功により石見浜田2万石を領した。大坂の陣では家康の孫娘・千を救出した。
-

宇喜多興家 (うきたおきいえ)
浦上家臣。能家の子。父が島村盛実に襲われて自害したあと、備前福岡の豪商・阿部善定のもとに逃げ込むが、間もなく病死。「愚なる上に臆病」と評された。
-

浮田国定 (うきたくにさだ)
浦上家臣。宇喜多能家の異父弟。不仲の兄を謀殺して砥石城を奪う。浦上家が政宗派と宗景派に分裂すると、政宗につき能家の孫で宗景派の直家に討たれた。
-

宇喜多忠家 (うきたただいえ)
宇喜多家臣。興家の子。兄・直家の創業に大いに貢献した。兄の死後は甥・秀家の後見人となる。朝鮮派兵の際は、豊臣軍総督を務める秀家に従って渡海した。
-

宇喜多直家 (うきたなおいえ)
浦上家臣。乙子城主。権謀術数の限りを尽くして敵を葬り去り、家中最大の勢力を築き上げる。最後は主君・宗景を追放して備前国を掌握した稀代の謀将。
-

宇喜多秀家 (うきたひでいえ)
豊臣家臣。直家の嫡男。主君・秀吉に寵愛され、五大老の1人となるが、内乱により重臣の大半を失う。関ヶ原合戦では西軍に属し、戦後八丈島へ配流された。
-

宇佐美定満 (うさみさだみつ)
上杉家臣。越後流軍学の祖という。上条定憲の乱の際は上条方に属すが、定憲の死後、帰参。国政に参画するなど活躍したが、長尾政景と舟遊び中に溺死した。
-

氏家定直 (うじいえさだなお)
最上家臣。天文の大乱の際には主君・義守の名代として出陣した。主家の御家騒動の際は、重病の身ながら義守を説得して義光への家督譲り渡しを実現させた。
-

氏家隆継 (うじいえたかつぐ)
大崎家臣。三丁目城主。氏家家の祖は、斯波家兼の執事を務めた氏家左衛門重定であるという。子・吉継が岩出山城主となった際に、三丁目城に隠棲した。
-

氏家卜全 (うじいえぼくぜん)
斎藤家臣。美濃三人衆の1人。主家滅亡後、織田家に仕える。伊勢平定戦で功を立てた。長島一向一揆との戦いで織田軍が敗れた際、殿軍を務め、戦死した。
-

氏家守棟 (うじいえもりむね)
最上家臣。定直の子。知略に長け、天童家や白鳥家の討伐に貢献した。また伊達家への使者を務めたり、真室城の攻略で戦功を立てるなど、各方面で活躍した。
-

氏家行広 (うじいえゆきひろ)
豊臣家臣。卜全の子。小田原征伐に従軍し、伊勢桑名2万2千石を得る。関ヶ原合戦で西軍に属し、戦後流浪。大坂城に入り、大坂夏の陣で豊臣秀頼に殉じた。
-

氏家吉継 (うじいえよしつぐ)
大崎家臣。岩出山城主。大崎内乱の際には伊場野惣八郎と結び、反主流派の中心人物として活動した。主家の没落後は伊達政宗に仕えたが、間もなく病没した。
-

雲林院祐基 (うじいすけもと)
長野家臣。長野稙藤の子。雲林院家は長野祐尊(長野工藤家初代当主・祐政の次男)を祖とする。織田信包に雲林院城を追われるが、その後は織田家に仕えた。
-

牛尾幸清 (うしおゆききよ)
尼子家臣。家老を務める。吉田郡山城攻めなどに従軍した。月山富田城籠城戦では落城寸前まで城内に留まって戦うが、のちに嫡男・久信らとともに降伏した。
-

内ヶ島氏理 (うじがしまうじまさ)
飛騨の豪族。帰雲城主。豊臣家臣・金森長近の飛騨侵攻軍に降るが、大地震により居城が埋没、山崩れによる洪水が起こり滅亡した。現代に埋蔵金伝説が残る。
-

臼杵鑑続 (うすきあきつぐ)
大友家臣。筑前好士岳城督を務め、筑前経略に従事。また主家の外交事務を管理し、大内家との和睦や主君・宗麟の弟・晴英の大内家入嗣などをとりまとめた。
-

臼杵鑑速 (うすきあきはや)
大友家臣。豊後三老の1人。外交事務を担当する一方で、肥前方分を務めて主家の国政に参画する。また筑前平定軍の総大将を務めるなど、各方面で活躍した。
-

内ヶ島雅氏 (うちがしままさうじ)
飛騨の豪族。帰雲城主。氏理の父。豊富な鉱山資源を収入源に領地経営を安定させる。熱心な一向衆門徒で、本願寺家と協力して長尾為景と争うが、敗北した。
-

内田実久 (うちださねひさ)
秋月家臣。大友家に敗れて逃れてきた当主・種実を匿い、休松の戦いで大友郡を撃退、種実の旧領回復に貢献した。隠居後は荒廃した高城の復興に尽力した。
-

宇都宮清綱 (うつのみやきよつな)
伊予の豪族。1532年頃、三男・房綱とともに萩森城を築き、居城とした。伊予宇都宮家は武茂景泰(下野宇都宮家8代当主・貞綱の甥)を祖とするという。
-

宇都宮国綱 (うつのみやくにつな)
宇都宮家22代当主。広綱の嫡男。豊臣秀吉の小田原征伐に参陣し、所領を安堵される。しかし、のちに豊臣家内部の権力闘争に巻き込まれ改易処分となった。
-

宇都宮豊綱 (うつのみやとよつな)
伊予の豪族。地蔵嶽城主。土佐一条家と結んだ。飛鳥城の戦いで西園寺公高を討つなど勢威を振るうが、鳥坂峠合戦で河野・毛利連合軍に敗れ、以後衰退した。
-

宇都宮尚綱 (うつのみやひさつな)
宇都宮家20代当主。興綱の嫡男。那須政資・高資父子の抗争の際、政資を支持した。のちに高資の支城・喜連川城を攻めるが、那須軍の奇襲に遭い敗死した。
-

宇都宮広綱 (うつのみやひろつな)
宇都宮家21代当主。尚綱の嫡男。佐竹義昭の娘を娶り同盟を結ぶ。また、芳賀高定とともに、北条家と結ぶ領内の反宇都宮勢力と戦った。病弱だったという。
-

宇都宮房綱 (うつのみやふさつな)
西園寺家臣。萩森城主。伊予宇都宮家の一族という。近隣の元城主・摂津親宣と領地問題で何度も争った。西園寺十五将の1人に数えられ、萩森殿と呼ばれた。
-

鵜殿氏長 (うどのうじなが)
今川家臣。長照の子。父が戦死した際に徳川家康に捕らえられ、家康の妻子と引き換えに駿府城に赴く。主家滅亡後は徳川家に属し、長篠合戦などに従軍した。
-

鵜殿長照 (うどのながてる)
今川家臣。長持の子。桶狭間合戦後、三河の武将が次々と徳川家に属す中、唯一今川方に残る。そのため、三河平定を目指す徳川軍の攻撃を受け、敗死した。
-

鵜殿長持 (うどのながもち)
今川家臣。上ノ郷城主。今川義元の妹を娶った。鵜殿家は藤原実方の末孫で、鎌倉時代に紀伊新宮の別当の子が取り立てられて西ノ郡(蒲郡)を領したという。
-

宇野祐清 (うのすけきよ)
赤松家臣。長水城主。政頼の子。宇野家は赤松家のもとで守護代を務めた。のち毛利家に属して織田家に対抗したが、羽柴秀吉の中国侵攻後に敗れ、自害した。
-

宇野政頼 (うのまさより)
赤松家臣。長水城主。宇野家は赤松家と同じ村上源氏の出身。尼子晴久の播磨侵攻軍に降り、所領を安堵された。のち羽柴秀吉の中国侵攻軍に敗れ、自害した。
-

祖母井之重 (うばがいゆきしげ)
伊予宇都宮家臣。城を築いた際、水が出ずに移転を考えるが、現れた老婆から水の出所を教わり、移転を留まる。のち泉と城に「祖母井」の名をつけたという。
-

祖母井之照 (うばがいゆきてる)
伊予宇都宮家臣。祖母井城主。大野直守の夜襲により居城が落城し、愛馬の首をはねて自害した。以後、命日になると之照の霊を乗せた首なし馬が走るという。
-

梅津憲忠 (うめずのりただ)
佐竹家臣。大坂の陣では重傷を負うも奮戦、「佐竹の黄鬼」の異名をとる。のちに家老となり、その正明果断な人となりで主君・義宣から絶大な信頼を受けた。
-

梅津政景 (うめずまさかげ)
佐竹家臣。勘定奉行や家老を歴任し兄・憲忠とともに主君・義宣の厚い信頼を得た。当時の藩政を記録した「梅津政景日記」は、歴史学上の貴重な史料である。
-

宇山久兼 (うやまひさかね)
尼子家臣。筆頭家老を務めた。月山富田城籠城戦では、私財を投じて糧食を購入し、城兵に配った。のちに毛利元就の離間策にかかった主君・義久に殺された。
-

浦上国秀 (うらがみくにひで)
浦上家臣。大物崩れで当主・村宗が討死し、幼少の政宗が家督を継ぐと、後見人として渦中の差配を務めた。家中が分裂すると失脚し、播磨を離れたという。
-

浦上政宗 (うらがみまさむね)
赤松家臣。室津城主。子・清宗に黒田職隆の娘を娶らせ、職隆の主君・小寺政職との連携強化を企むが、婚礼当日に赤松政秀に襲われ、清宗とともに戦死した。
-

浦上宗景 (うらがみむねかげ)
備前の戦国大名。室津城主を務める兄・政宗と争う一方で、備前に勢力を拡大した。しかし、のちに台頭した家臣・宇喜多直家の攻撃を受けて居城を追われた。
-

上井覚兼 (うわいかくけん)
島津家臣。おもに日向方面で活躍した。また老中を務めて主君・義久の領国経営を補佐した。文芸に造詣が深く「伊勢守心得書」や「上井覚兼日記」を著した。
-

海野棟綱 (うんのむねつね)
信濃の豪族。海野家は、信濃国小県郡海野を本拠とした古代からの豪族で、禰津家や望月家は海野家の庶流といわれる。娘は真田頼昌に嫁ぎ、幸隆を生んだ。
-

海野幸義 (うんのゆきよし)
信濃の豪族。棟綱の嫡子。滋野一族の本家として勢力を保持していたが、海野平合戦で村上義清、諏訪頼重など、武田信虎と結んだ近隣豪族に敗れて戦死した。
-

頴娃久虎 (えいひさとら)
島津家臣。耳川合戦、肥後水俣城攻撃、沖田畷合戦などに従軍し、各地で功を立てた。主君・義弘は「豊肥戦の勝利はすべて久虎のおかげだ」と語ったという。
-

江上家種 (えがみいえたね)
龍造寺家臣。龍造寺隆信の次男。江上家の家督を継ぐ。「当世無双の大力」と評された勇将で、各地の合戦で活躍した。朝鮮派兵に従軍するが釜山で死去した。
-

江上武種 (えがみたけたね)
少弐家臣。肥前勢福寺城主。龍造寺隆信の家督相続に反対した東肥前十九将の1人。龍造寺家臣・小田政光を討つなど活躍したが、のちに龍造寺家臣となった。
-

江口光清 (えぐちあききよ)
最上家臣。義光重臣。慶長出羽合戦にて最前線にあたる畑谷城に寡兵で籠もり、上杉軍の猛攻を食い止める。直江兼続の勧告を固辞し、壮絶な最期を遂げた。
-

江口正吉 (えぐちまさよし)
丹羽家臣。豊臣秀吉による丹羽家減封により多くの重臣が丹羽家を去る中、仕え続ける。関ヶ原合戦の浅井畷の戦いで、前田軍に夜襲をかけ、大戦果を上げた。
-

江戸重通 (えどしげみち)
常陸の豪族。水戸城主。通政の子。上杉家と結んで北条家に対抗した。小田原征伐後、水戸城の明け渡しを拒否し、佐竹義宣に居城を追われ、結城領へ逃れた。
-

江戸忠通 (えどただみち)
常陸の豪族。水戸城主。通泰の子。はじめ佐竹義篤に従うが、義篤の死後、義昭が家督を継ぐと敵対し抗争を繰り返す。のちに和睦し、再び佐竹家に従属した。
-

江戸通政 (えどみちまさ)
常陸の豪族。水戸城主。忠通の子。生来病弱のため、家督を間もなく子・重通に譲り、水戸城外の武熊城に籠居したまま病没した。家臣への官途状写しが残る。
-

江井胤治 (えねいたねはる)
相馬家臣。顕胤・盛胤・義胤に仕え、内政や外交で活躍した。義胤に従って田村家を訪れた際、伊達家に通じた田村家臣の田村月斎に狙撃され、死去した。
-

江馬輝盛 (えまてるもり)
飛騨の豪族。時盛の嫡男。意見を異にする父を殺し、弟・信盛を追放して江馬家を掌握した。本能寺の変に乗じて姉小路頼綱の打倒を企むが、逆に討たれた。
-

江馬時盛 (えまときもり)
飛騨の豪族。諏訪城主。三木家と争う。武田家と友好を結ぼうとするが、上杉家との関係構築を主張する嫡男・輝盛と対立し、輝盛の刺客によって殺された。
-

江馬信盛 (えまのぶもり)
飛騨の豪族。時盛の子。右馬丞と称す。はじめ僧侶であったが、人質として武田家に送られた際に還俗し、以後は武田家に仕える。高天神城攻防戦で戦死した。
-

江村親家 (えむらちかいえ)
長宗我部家臣。吉田重俊の次男。江村親政の娘婿となる。父と同じく備後守を称したため「小備後」と呼ばれた。多くの合戦に参加し、近隣に勇名を轟かせた。
-

江村親俊 (えむらちかとし)
長宗我部家臣。親家の子。津野親忠が豊臣秀吉の人質となった際は、親忠に従って伏見へ赴いた。朝鮮派兵では渡海し、晋州城攻撃戦に参加して戦功を立てた。
-

江良房栄 (えらふさひで)
陶家臣。主君・晴賢の腹心として活躍。折敷畑合戦後、毛利元就に誘われるが、条件に不服を唱えたため、元就により内奥の事実を暴露され、晴賢に殺された。
-

江里口信常 (えりぐちのぶつね)
龍造寺家臣。龍造寺四天王の1人。沖田畷合戦で主君・隆信戦死の報を聞くと、単身で島津家久軍の本陣に突入し戦死。「無双の剛の者」と家久に賞賛された。
-

恵利暢堯 (えりのぶたか)
秋月家臣。豊臣秀吉の九州征伐の際、偽の降礼使として秀吉のもとへ赴く。この時に抗戦の不利を悟り、主君・種実に降伏を促すが逆に勘気を蒙り、自害した。
-

円城寺信胤 (えんじょうじのぶたね)
龍造寺家臣。龍造寺四天王の1人といわれる。沖田畷合戦で主君・隆信戦死の報告を受けると、隆信に似せた出で立ちをしたのち、敵陣に斬り込んで戦死した。
-

遠藤俊通 (えんどうとしみち)
宇喜多家臣。主君・直家の密命を受けて備中より美作に進出していた三村家親の暗殺を敢行。兄と共に敵地に潜入し、家親を火縄銃で狙撃、暗殺に成功した。
-

遠藤直経 (えんどうなおつね)
浅井家臣。家中随一の猛将として知られた。主君・長政に織田信長の暗殺を献策するが容れられなかった。姉川合戦の際に信長の本陣へ単身突入し、戦死した。
-

遠藤基信 (えんどうもとのぶ)
伊達家臣。中野宗時の失脚後、輝宗の厚い信任を受けて宿老となる。政事を担当し、織田信長などとも書簡をやりとりした。輝宗の死後、その墓前で殉死した。
-

遠藤盛胤 (えんどうもりたね)
二階堂家臣。但馬と称す。主家滅亡の際に捕らえられ、伊達家に属す。武勇に秀で、関ヶ原合戦では松川菱の旗を背に奮戦し、敵味方双方から賞賛を浴びた。
-

遠藤慶隆 (えんどうよしたか)
美濃の豪族。郡上八幡城主。豊臣秀吉に仕える。小牧長久手合戦の際、織田家への内通疑惑により減封された。関ヶ原合戦では東軍に属し、戦後旧領に復した。
-

及川頼家 (おいかわよりいえ)
葛西家臣。柏木城主。沖田及川党の頭領であった。1559年、千葉三郎信近と争い、これがきっかけで柏木城事件が発生。大原氏により及川党は討伐された。
-

お市 (おいち)
織田信長の妹。浅井長政に嫁ぐが、長政の自害後、実家に戻る。本能寺の変後は柴田勝家に嫁ぎ、勝家とともに越前北ノ庄城で自害した。絶世の美女と伝わる。
-

淡河定範 (おうごさだのり)
別所家臣。淡河城主。羽柴秀吉軍に対し居城に籠城して抵抗した。のち三木城に入り、主君・長治を補佐。羽柴家臣・谷衛好を討った戦いで負傷し、自害した。
-

黄梅院 (おうばいいん)
北条氏政の正室。武田信玄の娘。甲相駿三国同盟に際して北条家に嫁ぐ。夫婦仲は良好だったが、同盟の破綻により離縁となり、甲斐に戻って出家、早世した。
-

阿梅 (おうめ)
真田幸村の娘。母は高梨内記の娘。大坂夏の陣では父に従い、大坂城に籠城。幸村から片倉重長に託されて大坂城を脱出しのちに重長の継室となった。
-

大井貞清 (おおいさだきよ)
武田家臣。もとは信濃の豪族で、たびたび武田に攻められ、降伏する。村上義清や上杉憲政に内通するが、再び武田に降伏。長篠の戦いに出陣し、討死した。
-

大井貞隆 (おおいさだたか)
信濃の豪族。岩村田城主。武田信玄の信濃侵攻軍に敗れて居城を失い、長窪城に退く。しかし、長窪城も攻められて生け捕りにされた。のちに殺されたという。
-

大石定久 (おおいしさだひさ)
扇谷上杉家臣。大石家は木曾義仲の子・義宗を祖とする。武蔵守護代を務めた。主家滅亡後は北条家に降り、北条氏康の次男・氏照に家督を譲って隠退した。
-

大石綱元 (おおいしつなもと)
山内上杉家臣。主家滅亡後は上杉景勝に仕える。景勝の会津転封に従い、保原城代となった。安田能元、岩井信能とともに会津三奉行の一人に数えられた。
-

大石智久 (おおいしともひさ)
宗家臣。通称は荒河介。家中随一の勇将で、弟とともに虎と格闘して退治したという伝説も残っている。対馬護郡代に任じられた。
-

大井田景国 (おおいだかげくに)
上杉家臣。長尾房長の次男。大井田氏景の婿養子となる。上杉謙信の下、関東出兵はどに活躍。景勝にも側近として仕えたが、突如切腹を命じられて自害した。
-

大内定綱 (おおうちさだつな)
陸奥の豪族。塩松城主。伊達政宗が伊達家当主となると、これに帰属するが、間もなく敵対。政宗の攻撃を受けて敗北し以後は伊達家に仕えた。槍術に秀でた。
-

大内親綱 (おおうちちかつな)
蘆名家臣。大内定綱の弟。1589年、兄を介して伊達家に帰属し、5百石を与えられた。摺上原合戦では兄とともに左右を固めて功を立て、戦後加増された。
-

大内輝弘 (おおうちてるひろ)
周防大内家一門。従兄弟の義隆と対立して豊後大友家へ逃れ庇護を受けた。後に宗麟の援助を受け大内家再興のため旧領周防で挙兵したが、毛利に敗れて自害。
-

大内義興 (おおうちよしおき)
大内家30代当主。逃れてきた前将軍足利義稙を擁し、細川高国と結んで上洛。管領代として10年幕府政治を司る。帰国後は尼子や安芸武田家と戦った。
-

大内義隆 (おおうちよしたか)
大内家31代当主。7カ国の守護を務め中国・九州に覇を唱えた。養嗣子・晴持の死後は文事に傾倒して独自の文化を築くが、家臣・陶晴賢の謀叛に遭い自害。
-

大内義綱 (おおうちよしつな)
田村家臣。小浜城主。定綱の父。石橋四天王の1人として、石橋家に仕えたが、田村家に内応して主君・尚義を追放、塩松地方の実験を掌握した。
-

大内義長 (おおうちよしなが)
大内家32代当主。大友義鑑の子。大内義隆の死後、陶晴賢に擁されて大内家を継いだ。厳島合戦で晴賢が戦死したあとは毛利軍の侵攻を受け続け、自害した。
-

大浦為則 (おおうらためのり)
南部家臣。政信の嫡男。大浦城主。父の死後、家督を継ぐ。生来病弱であったという。のちに娘・戌の婿に大浦(津軽)為信を迎えて後継者とした。
-

大浦政信 (おおうらまさのぶ)
南部家臣。大浦城主。わがままで家臣に信望がなかった。和徳城攻めで戦死したが、味方はその事実を知らずに退却、帰城後に初めて主君不在を知ったという。
-

大浦盛信 (おおうらもりのぶ)
南部家臣。光信の嫡男。1502年、父の命により、新たに築かれた大浦城の城主となる。1528年、父の菩提を弔うため、種里城下に長勝寺を建立した。
-

大浦守信 (おおうらもりのぶ)
津軽の武将。政信の子。当主である兄・為則が病弱であったことから、代わりに政務を執ったという。津軽為信の実父といわれている。
-

大木俊光 (おおきとしみつ)
蒲池家臣。龍造寺家から島津家への寝返りを企む主君・鎮漣が龍造寺隆信から招かれた際、訪問を中止するよう諫めた。しかし鎮漣は隆信を訪問し、殺された。
-

大久保忠員 (おおくぼただかず)
徳川家臣。兄・忠俊とともに主君・広忠の岡崎帰城に尽力。蟹江城攻めでも活躍した。三河一向一揆では一族の者とともに上和田砦に籠城し、一揆勢と戦った。
-

大久保忠教 (おおくぼただたか)
徳川家臣。忠員の子。通称・彦左衛門。高天神城攻めで、岡部元信を討ち取る。多くの浪人を保護し、義侠の士と慕われた。晩年には「三河物語」を著した。
-

大久保忠隣 (おおくぼただちか)
徳川家臣。忠世の嫡男。徳川秀忠の付家老を務める。秀忠および直参旗本からの信頼は絶大であったが、のちに政敵・本多正信の失脚工作によって改易された。
-

大久保忠俊 (おおくぼただとし)
徳川家臣。主君・広忠の岡崎帰城に尽力し、また三河一向一揆が勃発した際には主君・家康を助けて一揆勢を撃破するなど、主家の苦難時代を支え続けた忠臣。
-

大久保忠世 (おおくぼただよ)
徳川家臣。忠員の長男。三方ヶ原合戦、長篠合戦など多くの合戦に従軍し、その豪胆な性格で抜群の功を立て、織田信長や豊臣秀吉にも器量を高く評価された。
-

大久保長安 (おおくぼながやす)
徳川家臣。主家の天領の統括、新技術を利用した金銀の採鉱、一里塚・伝馬宿の設立など幕府の民政、財政面に大きく貢献し「天下の総代官」の異名をとった。
-

大久保忠佐 (おおくぼらだすけ)
徳川家臣。忠員の次男。兄・忠世とともに各地で戦功を立てる。その剛勇ぶりは織田信長をも賞嘆させるほどであった。関ヶ原合戦後、駿河沼津2万石を領す。
-

大熊朝秀 (おおくまともひで)
長尾家臣。箕冠城主。主君・景虎の側近として政務に参画した。景虎の出家騒動に乗じて謀叛を起こすが敗れる。以後は武田家に仕え、甲斐天目山で戦死した。
-

大関資増 (おおざきすけます)
那須七騎の一。高増の三男。兄・晴増の死後、下野黒羽1万3千石を継ぐ。関ヶ原合戦では東軍に属し、本領を安堵された。のち兄の子・政増に家督を譲った。
-

大崎義隆 (おおさきよしたか)
大崎家13代当主。義直の子。伊達政宗の軍を一度は退けるが、のちにその傘下に入る。豊臣秀吉の小田原征伐に遅参したため改易され、上杉景勝に仕えた。
-

大崎義直 (おおさきよしなお)
大崎家12代当主。伊達稙宗の援助によって家臣の謀叛を鎮圧するなど、勢力を次第に失う。天文の大乱では伊達晴宗に与力し稙宗に属した大崎義宣と戦った。
-

大崎義宣 (おおさきよしのぶ)
大崎家11代当主。伊達稙宗の子。大崎高兼の娘・梅香を娶り家督を継ぐ。天文の大乱では稙宗方に属し大崎義直と戦った。戦後、葛西領へ逃走中に殺された。
-

大須賀忠政 (おおすがただまさ)
徳川家臣。康高の養嗣子。実父は榊原康政。家康の関東移封に伴い、上総久留里3万石を与えられた。関ヶ原合戦後は遠江横須賀に移封。藩政の基礎を固めた。
-

大関高増 (おおぜきたかます)
那須七党の一。大田原資清の子。大関・大田原・福原家を率い、伊王野・蘆野家と結び、大伯父として主君・資晴を後見するなど家中最大の勢力を築き上げた。
-

大関宗増 (おおぜきむねます)
那須家臣。福原資安とともに大田原資清を主君・資房に讒言、資清を追う。のちに復帰した資清に子・増次を討たれ、資清の子・高増に大関家を乗っ取られた。
-

太田氏資 (おおたうじすけ)
北条家臣。岩付城主。資正の嫡男。父に疎まれたため、父と弟を追って岩付城主となった。三船山合戦の際、北条軍の殿軍を務めて里見軍と戦い、戦死した。
-

太田垣輝延 (おおたがきてるのぶ)
山名家臣。竹田城主。太田垣家は山名四天王の一。織田家から毛利家に寝返ったため、羽柴秀吉に攻められる。一時は居城を奪還するがのちに敗れ、逃亡した。
-

太田垣朝延 (おおたがきとものぶ)
山名家臣。宗寿の子。1538年、5代目の竹田城主となった。居城・竹田城は室町時代中期に、太田垣光景が築いた。光景の子・景近は応仁の乱で活躍した。
-

太田垣宗寿 (おおたがきむねひさ)
山名家臣。宗朝の子。1521年、4代目の竹田城主となった。太田垣家は山名四天王の一に数えられる重臣の家柄で、但馬国造・日下部家の末裔といわれる。
-

太田一吉 (おおたかずよし)
丹羽家臣。主家没落後は豊臣秀吉に仕える。関ヶ原合戦では西軍に属し居城・豊後臼杵城に籠城して戦うが、主力の敗北により開城。その後は京都に隠棲した。
-

大高光忠 (おおたかみつただ)
安東家臣。外交に活躍。1558年、南部家と和睦交渉にあたった。1589年の港騒動の際には、由利十二頭の赤尾津家を味方につけるべき使者に立った。
-

太田牛一 (おおたぎゅういち)
織田家臣。柴田勝家に仕えるが、弓の腕を見込まれ、信長の直臣となる。文才もあり、信長の障害を綴った「信長公記」は特に有名である。
-

太田定久 (おおたさだひさ)
紀伊の豪族。太田城主。雑賀党と抗争を繰り広げた。小牧長久手合戦の際は徳川家康の招きに応じて戦う。豊臣秀吉の紀州征伐では居城を水攻めされ、敗れた。
-

太田重正 (おおたしげまさ)
徳川家臣。康資の子。はじめ父とともに里見家に属す。父の死後は、佐竹家に属していた太田資正を頼る。のちに徳川家康に仕えた。妹は家康の側室となった。
-

太田資顕 (おおたすけあき)
扇谷上杉家臣。岩付城主。資頼の嫡男。1535年、父の隠居により家督を継いだ。河越夜戦において主君・朝定が北条軍に敗死したあとは北条家に属した。
-

太田資高 (おおたすけたか)
扇谷上杉家臣。北条家に通じて江戸城を占拠し、主君・朝興を河越城に追う。のち、北条家臣の遠山・富永両家とともに江戸城を守り、香月亭に住んだという。
-

太田資正 (おおたすけまさ)
扇谷上杉家臣。岩付城主。資頼の次男。主家滅亡後は上杉家や佐竹家に属し、生涯を通じて北条家と戦った。豊臣秀吉の小田原征伐では、秀吉の本陣を訪れた。
-

大館義実 (おおだてよしざね)
足利家臣。関岡城主。義輝・義昭の2代に仕えた。幕府滅亡後は所領を失い、堺に住む。のちに朝鮮派兵に従い、伊賀に所領を得た。甲冑の研究家として著名。
-

大谷吉継 (おおたによしつぐ)
豊臣家臣。関ヶ原合戦で西軍に属す。親友・石田三成のために病をおして奮戦、藤堂高虎の軍を撃退するが、寝返った小早川秀秋軍に攻められ敗北、自害した。
-

大谷吉治 (おおたによしはる)
豊臣家臣。吉継の長男。関ヶ原合戦では父とともに西軍に属して戦った。戦後、浪人となるが、豊臣秀頼に招かれ大坂城に入る。天王寺口の戦いで戦死した。
-

太田政景 (おおたまさかげ)
佐竹家臣。太田資正の次男。手這坂の合戦で小田氏治を破り、小田城主となる。主家の秋田転封に従ったが、のちに越前福井藩主・結城秀康のもとに転仕した。
-

太田宗正 (おおたむねまさ)
紀伊の豪族。太田城主。左近と称した。豊臣秀吉の紀州征伐では大軍を相手に善戦するが、居城を水攻めされ、1カ月におよぶ籠城戦の末に降伏し、自害した。
-

太田康資 (おおたやすすけ)
北条家臣。資高の子。のちに里見家に属し、第二次国府台合戦に従軍した。武田家・上杉家に飛脚を送るなど、外交でも活躍。三十人力の豪傑であったという。
-

大田原資清 (おおたわらすけきよ)
那須七党の一。大田原城主。黒羽城主・大関増次を討って子・高増に大関家を継がせたり、娘を主君・政資の側室とするなど、那須家中で最大の勢力を築いた。
-

大田原綱清 (おおたわらつなきよ)
那須七党の一。資清の三男。兄の高増・資孝が別家を立てたため、大田原家を継ぐ。豊臣秀吉の小田原征伐に際しては、子・晴清を秀吉の出迎えに遣わした。
-

大田原晴清 (おおたわらはるきよ)
那須七党の一。綱清の子。豊臣秀吉の小田原征伐に参陣し、所領を安堵された。関ヶ原合戦では東軍に属し、上杉家の様子を探るなど活躍し、戦後加増された。
-

大塚隆成 (おおつかたかなり)
岩城家臣。大塚家の庶流で、菅俣城主を務めた。のちに宗家の当主・政成の跡を継いで竜子山城に入る。これにより大塚家は再び岩城家に属することとなった。
-

大塚親成 (おおつかちかなり)
岩城家臣。隆成の子。はじめ佐竹家と争うが、岩城・佐竹両家の同盟が成立した際に佐竹家に属す。のちに主君・義重の子で岩城家を継いだ常隆に仕えた。
-

大塚政成 (おおつかまさなり)
佐竹家臣。竜子山城主。大塚家はもと岩城家臣。政成の時に、佐竹一家の待遇を受けて佐竹家に属し、のちに佐竹・岩城両家の間に入って和睦を成立させた。
-

大月景秀 (おおつきかげひで)
医師。朝倉義景に仕え、気つけや解毒に効能がある丸薬「万金丹」を創って朝倉家の軍兵を支えた。主家が滅亡すると出家、薬屋を営んで大いに評判を得た。
-

大友宗麟 (おおともそうりん)
大友家第21代当主。名は義鎮。義鑑の子。最盛期には九州6カ国を領したが、高城川合戦で島津軍に敗れて家臣を多数失い、以後は没落の一途をたどった。
-

大友親家 (おおともちかいえ)
大友家臣。宗麟の次男。父の命で僧侶となるが、武術に励み、のちに還俗。島津義久に通じたため、所領を没収される。主家改易後は肥後細川家などに仕えた。
-

大友義鑑 (おおともよしあき)
大友家20代当主。大内家ら周辺諸国と争い、勢力を拡大する。嫡男・義鎮の廃嫡を画策したため二階崩れの変が勃発。家臣に斬られて重傷を負い、死去した。
-

大友義統 (おおともよしむね)
大友家22代当主。義鎮の子。島津・龍造寺両家に圧迫され、豊臣秀吉を頼り豊後1国を安堵された。しかし朝鮮派兵の際に敵前逃亡を犯したため改易された。
-

大西覚養 (おおにしかくよう)
阿波の豪族。白地城主。頼武の子。出雲守と称した。近隣の重清豊後守を滅ぼした際、重清家の一族・伊沢権之進に攻められ、敗れて願成寺で自害したという。
-

大西頼包 (おおにしよりかね)
阿波の武将。大西家は三好家と誼を結んでいたが、頼包は人質として出された長宗我部元親に厚遇を受けて家臣となり、父を説得して長宗我部家に降伏させた。
-

大西頼武 (おおにしよりたけ)
阿波の豪族。白地城主。出雲守と称す。大西家は三好郡大西村の出身。三好郡や讃岐豊田郡などを侵略し、大井荘として支配した。長宗我部軍との戦いで戦死。
-

大西頼晴 (おおにしよりはる)
阿波の豪族。白地城主。上野介と称す。大西家は清和源氏小笠原家または近藤家の流れをくむという。父・頼武とともに伊予で長宗我部元親と戦い、戦死した。
-

大貫武重 (おおぬきたけしげ)
佐野家臣。佐野四天王の1人。財務の才に優れたという。足尾銅山の採掘を行うなど、主家の財政基盤確立に尽力した。主君・宗綱の死後、自害させられた。
-

大野直昌 (おおのなおしげ)
河野家臣。大除城主。土佐一条家や毛利家などが河野領に攻め入った際は、これを撃退した。豊臣秀吉の四国征伐軍に降り、主君・通直に従い安芸に移住した。
-

大野直之 (おおのなおゆき)
河野家臣。直昌の弟。地蔵嶽城主・宇都宮豊綱の娘婿となる。豊綱の没落後は地蔵嶽城主となった。たびたび主家に背き兄や主家の軍と戦いを繰り返した。
-

大野治胤 (おおのはるたね)
豊臣家臣。治長の弟。道犬斎と称した。大坂夏の陣の際は堺を焼き討ちした。大坂城が落城すると脱出を図り、逃走するが捕らえられ、堺で斬首された。
-

大野治長 (おおのはるなが)
豊臣家臣。片桐且元が大坂城を退去した後、大坂城内を取りまとめる。大坂の陣では豊臣方の指導者的役割を果たした。大坂城落城の際、主君・秀頼に殉じた。
-

大野治房 (おおのはるふさ)
豊臣家臣。治長の弟。大坂の陣の際は、主戦派の中心人物の一人となる。大坂落城後、国松丸(主君・秀頼の子)を擁して脱出するが、捕らわれて斬首された。
-

大祝鶴 (おおほうりつる)
三島水軍宗大祝氏の娘。「鶴姫伝説」によばれ、大内氏との戦いで甲冑に身を包んで奮戦後、戦死した恋人を追って海に身を投げたとされる。
-

大村純伊 (おおむらすみこれ)
肥前の豪族。有馬家に敗れ、大村の地を追われるが、のちに有馬軍を破って帰還した。この時の戦勝祝いの踊りが「沖田踊・黒丸踊・寿古踊」の起源という。
-

大村純前 (おおむらすみさき)
肥前の豪族。三城城主。有馬晴純の圧迫を受け、晴純の次男・純忠を養子に迎えて家督を譲る。のちに嫡男・貴明が誕生すると、後藤家へ養子に出した。
-

大村純忠 (おおむらすみただ)
肥前の豪族。三城主。有馬晴純の次男。大村純前の養子となり、家督を継ぐ。長崎を開港し、ポルトガル貿易を行った。日本初の切支丹大名として著名である。
-

大村純頼 (おおむらすみより)
喜前の長男。「御一門払い」という家中粛清で財源確保と当主権力強化を成功させた。大坂の陣後、豊臣家残党追捕に尽力。父同様、キリシタンを弾圧した。
-

大村由己 (おおむらゆうこ)
羽柴家臣。播磨出身。織田家が播磨攻めをした際に羽柴秀吉の右筆となる。新作能を創作するなど、文化人として長じ、羽柴秀吉の軍記「天正記」を著した。
-

大村喜前 (おおむらよしさき)
肥前の豪族。三城主。純忠の嫡男。関ヶ原合戦では東軍に属し、所領を安堵される。キリスト教から日蓮宗に転じ、切支丹を迫害したため、のちに毒殺された。
-

大和田光盛 (おおわだみつもり)
小野寺家臣。横手城主。1546年、金沢金乗坊とともに謀叛を起こし、主君・稙道を討つ(平城の乱)。しかし、のちに稙道の嫡男・輝道によって討たれた。
-

岡家利 (おかいえとし)
宇喜多家臣。利勝の子。主家の内乱により出奔、徳川家康に仕える。しかし、大坂の陣において子・平内が大坂方に属したため、家康の勘気を蒙り、自害した。
-

岡国高 (おかくにたか)
大和の豪族。岡城主。周防守と称す。興福寺一乗院方国民の1人で、松永久秀に属した。1574年、織田信長に拠点を焼き討ちされる。主家の滅亡に殉じた。
-

岡左内 (おかさない)
蒲生家臣。蒲生家の改易後、会津に入封した上杉家に仕える。ばらまいた金の上で寝るという奇行があった。関ヶ原合戦で、蓄財した全財産を主家に献上した。
-

小笠原貞種 (おがさわらさだたね)
小笠原家臣。長時の弟。諸国を流浪したあと、上杉景勝の後援で深志城を奪還。しかし、甥・貞慶が徳川家康の助力を得て信濃に入国すると、城を明け渡した。
-

小笠原貞慶 (おがさわらさだよし)
徳川家臣。長時の嫡男。各地を流浪後、徳川家康の後援を得て旧領を回復し、以後は徳川家に仕える。家康の孫娘を子・秀政に迎えるなど、関係強化に努めた。
-

小笠原忠真 (おがさわらただざね)
秀政の次男。大坂夏の陣で父と兄・忠脩が戦死したため家督を継ぐ。播磨明石、後に豊前小倉藩主となった。茶道に造詣深く、上野焼を育成した。
-

小笠原長雄 (おがさわらながたか)
大内家臣。温湯城主。主君・義隆の死後は尼子家に属した。大森銀山に進出し、これを領有した。のちに毛利元就軍に攻められ、抵抗するが敗北し、降伏した。
-

小笠原長時 (おがさわらながとき)
信濃守護。長棟の長男。武田信玄に信濃を追われ、越後・摂津・会津など諸国を流浪する。子・貞慶が信長の下で旧領に復帰するが、戻ることなく死亡した。
-

小笠原長棟 (おがさわらながむね)
信濃守護。支族・伊那小笠原家を屈伏させ、分裂状態にあった小笠原家の統一に成功した。また、隣国の諏訪家とは講和を結び、領内の治政の安定化に努めた。
-

小笠原成助 (おがさわらなりすけ)
三好家臣。一宮城主。主君・長慶の妹を娶る。和泉久米田合戦で三好軍が敗北を喫した際、軍をまとめて退却させ、賞賛された。のち長宗我部元親に殺された。
-

小笠原信浄 (おがさわらのぶきよ)
津軽家臣。主君・為信の創業期を支えた大浦三老の1人。信濃国の出身で津軽に移住し、大浦家に仕える。大光寺城、石川城攻めに従軍するなど、活躍した。
-

小笠原信定 (おがさわらのぶさだ)
信濃の豪族。長棟の次男、長時の弟。父や兄の命により、飯田の鈴岡小笠原家を再興する。武田家に敗れると東海道を通り三好家を頼るが、本國寺の変で戦死。
-

小笠原信之 (おがさわらのぶゆき)
徳川家臣。酒井忠次の三男。小笠原信嶺の養子となって家督を継ぎ、武蔵本庄藩主となった。小田原征伐、上田城攻めに参陣。後に下総古河に加増転封された。
-

小笠原秀政 (おがさわらひでまさ)
徳川家臣。貞慶の嫡男。石川康長の改易後、旧領の信濃松本6万石を領す。大坂夏の陣で戦死した。主君・家康に「信濃は…」と言い残して絶命したという。
-

小笠原政信 (おがさわらまさのぶ)
信之の嫡男。父の死後家督を継ぎ、下総古河藩2万石の2代藩主となった。後に下総関宿2万7千石に加増転封された。板倉重昌の娘を妻に迎えている。
-

岡利勝 (おかとしかつ)
宇喜多家臣。宇喜多三老の1人。刀槍の術に長じ、40余度の合戦に出陣した勇将。岡山城の修築や城下町の建設などにも携わる。朝鮮派兵の陣中で病死した。
-

岡部親綱 (おかべちかつな)
今川家臣。主君・氏輝の死後、その後継者を巡って起こった花倉の乱で、梅岳承芳(今川義元)方に属し、方上城を落城させるなど、大いに活躍した。
-

岡部長盛 (おかべながもり)
徳川家臣。正綱の子。長久手合戦などで戦功を立て、主君・家康が関東に入部した際に上総・下総で1万2千石を与えられた。のちに丹波亀山2万石を領した。
-

岡部正綱 (おかべまさつな)
今川家臣。主家滅亡後は武田家に仕え、清水城主となる。駿河先方衆として三方ヶ原合戦などに従軍した。武田家滅亡後は徳川家に仕え、甲斐平定に貢献した。
-

岡部元信 (おかべもとのぶ)
今川家臣。桶狭間合戦では主君・義元の首級を駿河に持ち帰った。主家滅亡後は武田家に仕え、高天神城主となるが、徳川家康の攻撃を受けて落城、戦死した。
-

岡見頼忠 (おかみよりただ)
小田家臣。多賀谷政経らに居城・谷田部城を奪われるが、10年後に北条氏照の後援を得て奪回した。しかしのちに多賀谷重経(政経の子)に敗れ、戦死した。
-

岡本顕逸 (おかもとけんいつ)
佐竹家臣。禅哲の子。僧体で佐竹義重・義宣2代に仕えた側近。外交面で活躍したほか、義重の三男・貞隆の岩城家入嗣に随行し、岩城家の執政に参画した。
-

岡本禅哲 (おかもとぜんてつ)
佐竹家臣。僧体で義篤・義昭・義重3代に仕えた側近。白河結城家や古河公方と文書を交わすなど、外交面で重要な役割を果たし、佐竹一門に次ぐ地位を得た。
-

岡本宣綱 (おかもとのぶつな)
佐竹家臣。顕逸の子。はじめ父祖にならって剃髪するが、のちに主君・義宣の命により還俗した。義宣の秋田移封に従い大坂の陣にも出陣して戦功を立てた。
-

岡本良勝 (おかもとよしかつ)
織田家臣。信長の三男・信孝は良勝の屋敷で生まれたという。のち主家を出奔、豊臣家に仕え伊勢亀山城主となる。関ヶ原合戦では西軍に属し、戦後自害した。
-

岡本頼氏 (おかもとよりうじ)
相良家臣。初陣以来19度の合戦で戦功を立てる。薩摩大口合戦では島津家臣・川上久朗を討った。のちに相良家中の軍忠覚書「岡本頼氏戦場日記」を著した。
-

岡本頼元 (おかもとよりもと)
里見家臣。義頼の重臣として仕え、安房岡本城を拠点に里見水軍の一翼を担う。義頼の死後、岡本城火災の責任を負わされて追放されたが、のちに復帰した。
-

岡吉正 (おかよしまさ)
紀伊の豪族。雑賀党の一員。石山本願寺に籠城して活躍した。優れた射撃の腕を持ち、織田信長が攻め寄せた際、信長を狙撃し大腿部に重傷を負わせたという。
-

小川祐忠 (おがわすけただ)
近江の豪族。明智光秀に属す。光秀の死後は柴田勝豊の家老を経て豊臣秀吉に仕え、伊予府中7万石を領した。関ヶ原合戦で東軍に寝返るが、戦後改易された。
-

小河信安 (おがわのぶやす)
龍造寺家臣。居城・春日山城を神代勝利に落とされ、一族の多くを失った。弔い合戦のために出陣した際、鉄布峠で勝利本人と遭遇し、一騎討ちの末討たれた。
-

荻野秋清 (おぎのあききよ)
丹波の豪族。赤井直正の外叔父。内藤国貞が攻めてきた際、これを撃破。しかしその後、配下を見殺しにして信望を失い直正に謀殺されて、黒井城を奪われた。
-

奥重政 (おくしげまさ)
紀州の豪族。津田算正・算長父子に砲術を学び、数年で奥義を極めると、織田信長や羽柴秀吉を苦しめた。のち浅野幸長に請われ、津田流砲術を伝授した。
-

奥平家昌 (おくだいらいえまさ)
信昌の嫡男。母は徳川家康の娘・亀姫。関ヶ原合戦では徳川秀忠に従い、上田城攻めに参加。武勇に優れたが大坂の陣には病で出陣できず、やがて没した。
-

奥平貞勝 (おくだいらさだかつ)
三河の豪族。貞能、貞治の父。はじめ松平氏に属し、今川、織田、徳川、武田と時勢に応じて主家を転じ家名を存続させた。武田滅亡後、徳川に帰参している。
-

奥平貞治 (おくだいらさだはる)
貞能の弟。徳川家臣として長篠合戦などに参戦。関ヶ原の戦いでは小早川秀秋の監視役となり、秀秋と共に西軍の大谷吉継隊と交戦、致命傷を負って陣没した。
-

奥平貞能 (おくだいらさだよし)
今川家臣。桶狭間合戦後、徳川家に仕える。掛川城攻めや姉川合戦に従軍した。一時武田信玄に属すが、信玄の死後は徳川家に帰参し、長篠合戦で活躍した。
-

奥平忠隆 (おくだいらただたか)
徳川家臣。忠政の長男。父の死により美濃加納藩を継ぐが、まだ幼かったため、祖父・信昌や祖母・亀姫が後見した。若くして死去し、奥平氏は改易となった。
-

奥平忠昌 (おくだいらただまさ)
家昌の嫡男。父の急死後、7歳で家督を相続し、下野宇都宮藩2代藩主となる。のち下総古河に加増転封されるが、宇都宮釣天井事件後、宇都宮に再封された。
-

奥平信昌 (おくだいらのぶまさ)
徳川家臣。貞能の子。一時武田信玄に属すが、信玄の死後、帰参。長篠合戦では長篠城を死守し勝利に大きく貢献した。その功により、家康の娘・亀を娶った。
-

小国義操 (おぐによしもち)
二本松畠山家臣。伊達政宗が二本松城を攻めた際、政宗の本陣に何度か襲撃をかけるが、失敗したという。主家滅亡後は政宗の度重なる招きを断り、帰農した。
-

奥村助右衛門 (おくむらすけえもん)
前田家臣。能登末森城主。佐々成政率いる1万5千の大軍を、わずか3百の兵で撃退した。この際、長福の妻が城兵を叱咤激励して回ったという逸話が残る。
-

お江 (おごう)
小督、祟源院とも。浅井長政とお市の間に生まれた娘。三姉妹の三女。後に徳川秀忠の妻となり、江戸幕府三代将軍・徳川家光を産む。
-

小坂雄長 (おさかおなが)
織田家臣。信雄の命により、豊臣秀吉の臣となる。関ヶ原の戦いでは、東軍の福島正則に仕えて戦った。戦後は、各地を流浪するが、最終的には旗本となった。
-

長船貞親 (おさふねさだちか)
宇喜多家臣。宇喜多三老の1人。明禅寺合戦など各地の合戦に従軍し、主君・直家の創業を助けた。戸川秀安の隠退後は国政を担当する。のち妹婿に殺された。
-

長船定行 (おさふねさだゆき)
宇喜多家臣。貞親の子。兄・綱直の死後家督を継ぐ。家中屈指の大身で、2万4千石を知行した。主君・秀家に従い関ヶ原合戦に出陣、戦後行方不明となった。
-

長船綱直 (おさふねつななお)
宇喜多家臣。貞親の子。主家の国政を執り、領内の検地や城下町整備などを行った。主君・秀家の寵を得て専権を振るったため、敵対勢力に毒殺されたという。
-

小島政章 (おじままさあき)
土佐一条家臣。主君・兼定の豊後追放に憤り、兼定を裏切った家臣らの居城を攻撃した。のちに長宗我部元親の土佐平定軍に降り、幡多地方の平定に尽力した。
-

お船 (おせん)
直江兼続の正室。豊臣の天下が成ると上杉景勝の正室・菊姫に従い京に移住。のち兼続の封地・米沢に移る。病疫した菊姫に代わり景雄の子・定勝を養育した。
-

小田氏治 (おだうじはる)
小田家15代当主。政治の子。北条家と結んで佐竹家の南進阻止を試みるが連戦連敗、居城を奪われて降伏した。以後も失地を回復できず、結城秀康に仕えた。
-

小田朝興 (おだともおき)
成田家臣。成田親泰の次男。騎西城主・小田家の家督を継ぐ。兄・長泰が上杉謙信に背いた際、謙信に居城を奪われた。のちに騎西城は兄によって奪還された。
-

小田友治 (おだともはる)
氏治の庶長子。八田左近と称した。小田家と結んだ北条家に仕えた。主家滅亡後は豊臣家に仕え、朝鮮派兵の際には舟奉行を務め、伊勢で所領を与えられた。
-

織田長益 (おだながます)
信秀の十男。有楽斎と号す。茶の湯に傾倒し、利休七哲の1人となった。兄・信長の死後は豊臣家に属すが、大坂の陣直前に徳川方に通じ、大坂城を退去した。
-

織田信雄 (おだのぶかつ)
信長の次男。伊勢国司・北畠家の養子となり、家督を継ぐ。本能寺の変後は豊臣家に従属した。小田原征伐後、徳川家康の旧領への転封を拒否し、改易された。
-

織田信勝 (おだのぶかつ)
信秀の次男。名は信行とも。うつけと呼ばれた兄・信長に対し、利発で家中の評判が良かった。林秀貞らに擁立されて家督を争うが、清洲城で信長に殺された。
-

織田信包 (おだのぶかね)
信秀の四男。越前攻めや石山本願寺攻めに参戦した。本能寺の変後は豊臣秀吉に仕え、秀吉の子・秀頼の傅役を務めた。娘は秀吉の側室となり、寵愛された。
-

織田信清 (おだのぶきよ)
織田家臣。犬山城主。織田信秀の娘を娶り一時期織田信長に協力するも、やがて敵対する。信長に犬山城を落とされ、甲斐へと逃亡したといわれる。
-

織田信定 (おだのぶさだ)
斯波家臣。良信の子。織田達勝配下で、「清洲三奉行」の一人として活躍。勝幡城を築いて居城とし、近隣の津島湊を支配して、織田家の財政的基盤を築いた。
-

織田信澄 (おだのぶずみ)
信勝の子。伯父・信長に仕える。明智光秀の娘を娶った。「一段の逸物」と評された器量の持ち主であったが、本能寺の変の際に、従兄弟・信孝に殺された。
-

織田信孝 (おだのぶたか)
信長の三男。伊勢の豪族・神戸具盛の養子となり、家督を継ぐ。本能寺の変後、柴田勝家と結んで羽柴秀吉に対抗するが敗れ、秀吉の命により自害させられた。
-

織田信忠 (おだのぶただ)
信長の嫡男。松永久秀の謀叛鎮圧や甲斐平定戦などで功を立てた。信長から家督を譲られ、美濃・尾張の2国を領する。本能寺の変の際、二条御所で自害した。
-

織田信友 (おだのぶとも)
尾張斯波家臣。尾張下4郡の守護代。名は広信とも。清洲城主を務めた。主君である義統を殺したため、織田信長の命を受けた織田信光に攻められ、自害した。
-

織田信長 (おだのぶなが)
信秀の嫡男。今川義元を桶狭間で破る。以後、天下布武を標榜して敵対勢力を次々と滅ぼした。天下統一を目前にして、明智光秀の謀叛に遭い本能寺に散った。
-

織田信秀 (おだのぶひで)
尾張の戦国大名。「尾張の虎」と呼ばれた猛将で、尾張統一を目指して近隣の今川家、斎藤家らと抗争を続けたが、志半ばにして流行病にかかり、急死した。
-

織田信広 (おだのぶひろ)
織田家臣。信秀の長男。信長の庶兄。小豆坂の戦いでは先陣を務める。のちに謀反を画策するも信長に許され、心を入れ替えて働くが、伊勢長島攻めで戦死。
-

織田信光 (おだのぶみつ)
信定の子。武勇に優れ、今川家との小豆坂合戦では殿軍を務めた。甥・信長の清洲城攻略戦で活躍し、那古野城主となるが、その数カ月後に家臣に謀殺された。
-

織田信安 (おだのぶやす)
尾張の豪族。岩倉城主。織田信勝を支持したため、織田信長と浮野で戦い敗北。のちに子・信賢らに追放された。その後も斎藤義龍を頼り、信長に対抗した。
-

織田秀雄 (おだひでかつ)
豊臣家臣。信雄の子。越前大野5万石を領す。関ヶ原合戦では東軍に属すが、のちに父とともに西軍に属したため、改易された。その後は武蔵浅草に閑居した。
-

織田秀信 (おだひでのぶ)
信忠の嫡男。本能寺の変後、羽柴秀吉に擁立されて3歳で織田家を継ぐが、実権は秀吉に奪われた。関ヶ原合戦で西軍に加担して敗北し、高野山で出家した。
-

織田昌澄 (おだまさずみ)
津田信澄の長男。母は明智光秀の娘。本能寺の変後、父が殺されると父の旧臣・藤堂高虎を頼る。のち豊臣家に仕え、大坂の陣後、高虎に助命され旗本となる。
-

小田政治 (おだまさはる)
小田家14代当主。堀越公方・足利政知の子。小田成治の養子となる。江戸家らと戦い、河越合戦で古河公方・足利家を支持するなど多彩な軍事行動を取った。
-

小田政光 (おだまさみつ)
少弐家臣。肥前蓮池城主。龍造寺隆信の家督相続に反対した東肥前十九将の1人で、隆信と争う。隆信の肥前復帰後は隆信に仕え、江上武種討伐戦で戦死した。
-

織田達勝 (おだみちかつ)
斯波家臣。大和守と称す。内乱を起こして自害した織田達定の跡を継ぎ、尾張下四郡の守護代となる。織田信長の父・信秀は達勝の家臣「清洲三奉行」の一人。
-

小田守治 (おだもりはる)
小田家16代当主。氏治の子。同盟を結んでいた北条家の滅亡後は結城秀康に仕える。妹が秀康の側室となったため、秀康の越前移封に従って越前へ移住した。
-

織田頼長 (おだよりなが)
豊臣家臣。長益の嫡男。豊臣秀頼に仕えるが、大坂夏の陣の直前に突然、大坂城を退去。以後は京都で隠遁生活を送り、茶道・有楽流を継承した。
-

越智家増 (おちいえます)
大和の国人。家増は大和の国衆で、家栄の三男。家広の弟という。はじめ楢原姓を名乗った。市尾深介に命じて甥・家高を謀殺し、越智家の惣領となった。
-

おつやの方 (おつやのかた)
織田信長の叔母。遠山景任の妻。嗣子なく夫が病疫したため、岩村城主となる。武田信玄の西上作戦が始まると、秋山信友と婚姻し、武田家に寝返った。
-

鬼庭左月斎 (おににわさげつさい)
伊達家臣。稙宗の子・盛重が国分家に入嗣する際、国分家に赴き仕置を行った。のちに評定役となる。人取橋合戦の際に老齢の身ながら殿軍を務め、戦死した。
-

鬼庭綱元 (おににわつなもと)
伊達家臣。主君・政宗の腹心となる。朝鮮派兵の際に、豊臣秀吉の愛妾・香の前を賜り、政宗の怒りを買って出奔。のちに帰参し、国老として国政に携わった。
-

小貫頼久 (おぬきよりひさ)
佐竹家臣。義重・義宣2代に側近として仕え、外交面で重要な役割を果たした。知行割替時には、和田昭為、人見藤通とともに義宣の三奉行として活躍した。
-

小野木重次 (おのぎしげつぐ)
豊臣家臣。小田原征伐などに従軍し、丹波福智山4万石を領す。関ヶ原合戦では西軍に属し、田辺城を落城させるが、西軍主力が敗北したため開城、自害した。
-

小野崎従通 (おのざきつぐみち)
常陸の豪族。額田城主。佐竹家に属したが自立性が強く何度も主家に反抗した。のちに謀叛を起こすが敗れ、松平忠輝などに仕えた。画に巧みであったという。
-

小野鎮幸 (おのしげゆき)
立花家臣。通称・和泉。由布惟信とともに立花家の両翼として活躍。朝鮮出兵でその勇名を轟かせた。関ヶ原合戦で主家が改易された後は加藤清正に仕えた。
-

小野忠明 (おのただあき)
剣術家。はじめ里見家に仕えたが、剣術修業のため諸国を遍歴する。のちに一刀流の開祖・伊藤一刀斎に師事し、名を小野忠明と改め、小野一刀流を創始した。
-

小野寺稙道 (おのでらたねみち)
小野寺家12代当主。泰道の嫡男。はじめ上洛して将軍家に仕えたが、父の死により帰国、家督を継いだ。のちに権力闘争に巻き込まれ、家臣らに殺害された。
-

小野寺輝道 (おのでらてるみち)
小野寺家13代当主。稙道の嫡男。父の死後、一時大宝寺家を頼るが、のちに仇敵・大和田光盛らを滅ぼし、横手城に復帰。小野寺家の全盛時代を築き上げた。
-

小野寺康道 (おのでらやすみち)
小野寺家臣。輝道の子。最上家との合戦で活躍した。関ヶ原合戦では最上家の大軍と戦い居城・大森城を死守。戦後、兄の義道とともに津和野に配流となった。
-

小野寺義道 (おのでらよしみち)
小野寺家14代当主。輝道の次男。豊臣秀吉の小田原征伐に参陣して、所領を安堵される。関ヶ原合戦では徳川家の出陣要請を無視したため、戦後改易された。
-

小野政次 (おのまさつぐ)
井伊家臣。政直の嫡男。当主・直親を讒言によって謀殺。井伊家の実権を握って専横の限りを尽くすが、家康の命を受けた井伊谷三人衆に敗北し、処刑された。
-

小幡景憲 (おばたかげのり)
徳川家臣。甲州流兵学者。昌盛の子。主君・秀忠の小姓となるが、のちに出奔。大坂の陣後、帰参を果たした。甲州流兵学を集大成し、多くの門弟に教授した。
-

小幡虎盛 (おばたとらもり)
武田家臣。甲陽五名臣の1人。「鬼虎」の異名をとり、生涯で36枚の感状を受けた。晩年は高坂昌信の副将を務めた。「よくみのほどをしれ」の遺言が有名。
-

小幡信貞 (おばたのぶさだ)
武田家臣。憲重の子。西上野先方衆の主力として活躍した。主家の滅亡後は北条家に仕え、北条家滅亡後は上田城主・真田昌幸のもとに赴き、庇護を受けた。
-

小幡憲重 (おばたのりしげ)
山内上杉家臣。妻は長野業正の妹。一族の謀叛により流浪、武田信玄に属す。信玄の上野攻略に貢献、西上野先方衆筆頭となった。長篠合戦で戦死したという。
-

小幡昌盛 (おばたまさのり)
武田家臣。虎盛の子。豊後守と称した。はじめ海津城の城番を務めるが、父の死後、城番を辞して旗本足軽大将衆となり騎馬3騎、足軽10人を率いた。
-

お初 (おはつ)
常高院とも。浅井長政とお市の間に生まれた娘。三姉妹の次女。小谷城、賤ヶ岳の戦いを生き延び京極高次の妻となる。キリスト教に帰依していたという。
-

小浜景隆 (おはまかげたか)
志摩海賊衆。伊勢北畠家に属す。九鬼嘉隆に敗れ志摩を追われ、武田信玄に招かれて武田家の船大将となる。武田家滅亡後は徳川家に仕え、船手大将を務めた。
-

小浜光隆 (おはまみつたか)
徳川家臣。景隆の子。船手頭を務め、相模・上総両国で3千石を領した。大坂冬の陣に出陣し、大野治長の関船、早船をそれぞれ2隻ずつ乗っ取る功を立てて。
-

小場義成 (おばよしなり)
佐竹一門・佐竹西家当主。佐竹義昭の三男・義宗の子。佐竹家の秋田転封後、浅利家残党の反乱を鎮圧。南部家、津軽家の抑えとして、大舘城を任された。
-

飯富虎昌 (おぶとらまさ)
武田家臣。軍装を赤で統一した部隊を率いて活躍、「甲山の猛虎」の異名をとった。信玄の長男・義信の傅役を務めたが義信の謀叛未遂事件の責任をとり自害。
-

小山隆重 (おやまたかしげ)
紀伊の豪族。下野小山家の庶流という。豊臣秀吉の紀州征伐軍に降り、本領を安堵される。のち関ヶ原合戦で西軍に属して改易された。大坂冬の陣で戦死した。
-

小山高朝 (おやまたかとも)
下野の豪族。結城政朝の次男。小山政長の養子となった。兄・結城政勝の後援を得て小山家の威勢を回復する。北条家とも結び、安定した領国経営を行った。
-

小山田茂誠 (おやまだしげまさ)
武田家臣。真田昌幸の長女・村松殿を娶る。武田家が滅亡した後に真田家の家臣となった。大阪の陣では、信之の代わりに参陣した信吉・信政を補佐した。
-

小山田信有 (おやまだのぶあり)
武田家臣。越中守信有の子。出羽守を称した。志賀城攻略、上田原合戦などで活躍。砥石城攻略戦で重傷を負い、死去した。葬儀には1万人が参列したという。
-

小山田信茂 (おやまだのぶしげ)
武田家臣。出羽守信有の子。投石を得意とする部隊を率いて各地の合戦で活躍。織田信長の甲斐侵攻軍に降るが、主君・勝頼の死後、裏切り者として斬られた。
-

小山秀綱 (おやまひでつな)
下野の豪族。高朝の嫡男。弟・結城晴朝と協力し、上杉家や北条家と結んで小山家の命脈を保つが、豊臣秀吉の小田原征伐に際し北条家に属して所領を失った。
-

甲斐宗運 (かいそううん)
阿蘇家臣。肥後御船城主。大友家と結んで龍造寺家や島津家と外交交渉を行い、阿蘇家の存続に努めた。島津家に属した相良義陽の攻撃を受けるが、撃退した。
-

甲斐親宣 (かいちかのぶ)
日向の豪族。阿蘇惟長に追われて、日向に逃れた阿蘇惟豊(惟長の弟)を保護。1517年、惟長を破って惟豊を阿蘇領に復帰させ、そのまま阿蘇家臣となる。
-

甲斐親英 (かいちかひで)
阿蘇家臣。肥後御船城主。宗運の子。島津軍に敗れて和睦するが、大友家との連絡を警戒され、肥後八代に抑留された。国人一揆に加担し、敗走中に討たれた。
-

戒能通森 (かいのうみちもり)
河野家臣。小手ヶ滝城主を務めた。1553年、大野利直らの攻撃を受け、属城の大熊城へ逃れる。のちに大熊城も攻撃を受けるが、奮戦してこれを撃退した。
-

海北綱親 (かいほうつなちか)
浅井家臣。画家・海北友松の父。豊臣秀吉が「我が軍法の師」と讃えた勇将。武者奉行を務め各地で活躍した。主家滅亡時に戦死した。「海赤雨三将」の1人。
-

香川親和 (かがわちかかず)
長宗我部元親の次男。讃岐の豪族・香川家を継ぎ、天霧城主となるが、豊臣軍に敗れて土佐に帰る。兄・信親の死後、家督相続の沙汰がなく、失意の内に病死。
-

香川光景 (かがわみつかげ)
安芸武田家臣。安芸八木城主。のちに己斐直之らとともに主家を離反し、毛利家に属した。厳島合戦の際は、真言寺院の東林坊とともに仁保城の城番を務めた。
-

香川元景 (かがわもとかげ)
細川家臣。満景の子。細川家の家督を巡って澄元と高国が争った際は、高国を支持した。高国の没落後は澄元の子・晴元に属すなど、香川家の存続に尽力した。
-

香川之景 (かがわゆきかげ)
細川家臣。天霧城主。主家の没落後は三好家に従う。のち織田信長に通じるが、長宗我部元親の讃岐侵攻軍に降り、元親の次男・親和を養子とし家督を譲った。
-

柿崎景家 (かきざきかげいえ)
上杉家臣。主君・謙信に「越後七郡で彼にかなう者はなし」と評された家中随一の猛将。上杉軍の主力として活躍したが織田信長への内通疑惑により殺された。
-

蠣崎季広 (かきざきすえひろ)
蠣崎家4代当主。義広の子。先祖より対立の続いていたアイヌと和睦し、蝦夷商船往来の制を定める。この政策により、蝦夷地の領主としての地位を確立した。
-

蠣崎基広 (かきざきもとひろ)
蠣崎家臣。高広(光広の次男)の子。光広の子ともいう。父の死後家督を継ぎ、勝山館主となった。のちに謀叛を起こし従兄弟・季広と戦うが敗れ、討たれた。
-

蠣崎守広 (かきざきもりひろ)
松前藩家老。季広の十一男。一家を興して家臣となる。4代藩主・氏広を自宅で饗応した際、偶然火災が起こったため、その罪を負って火中に入り死去した。
-

蠣崎義広 (かきざきよしひろ)
蠣崎家3代当主。蠣崎家の始祖・信広がアイヌの首領・コシャマインを討ったため、恨みに燃えるアイヌの大軍が度々来襲し、生涯戦いに明け暮れたという。
-

蠣崎吉広 (かきざきよしひろ)
季広の子。一時、兄・慶広の仮養子となっていた。慶広以後、三代に渡って藩政の補佐を行う。歴代藩主から厚く信任され、子孫も重臣として藩政に携わった。
-

垣見一直 (かきみかずなお)
豊臣家臣。金切裂指物使番を務め、豊後富来2万石を領す。関ヶ原合戦では西軍に属し美濃大垣城に籠城するが、東軍に寝返った相良頼房らによって殺された。
-

垣屋続成 (かきやつぐなり)
山名家臣。楽々前城主。主君・致豊の但馬守護就任に伴って守護代となり、領国経営の実権を握った。のちに田結庄是義と対立し、是義に奇襲されて自害した。
-

垣屋恒総 (かきやつねふさ)
豊臣家臣。光成の子。小田原征伐や朝鮮派兵などに従軍し、因幡浦住木山1万石を領す。関ヶ原合戦では西軍に属し近江大津城攻撃などに参加、戦後自害した。
-

垣屋光成 (かきやみつなり)
山名家臣。続成の子。父を殺した田結庄是義と戦い、是義を討った。のちに羽柴秀吉の中国征伐軍に降り、因幡鳥取城攻撃などに参加、因幡で1万石を領した。
-

加来統直 (かくむねなお)
豊前の豪族。大畑城主。大友家に属し、反大友勢力の野仲鎮兼と激しく争った。豊臣秀吉の九州征伐後、豊前に入国した黒田孝高と戦うが敗北し、滅亡した。
-

懸田俊宗 (かけだとしむね)
伊達家臣。天文の大乱に際しては舅・稙宗に属して活躍。乱の終息後、居城・懸田城を廃城とする講和条件に不満を持ち謀叛を起こすが、捕らえられ斬られた。
-

葛西親信 (かさいちかのぶ)
葛西家16代当主。晴胤の嫡男。寺池城主。父の死後、葛西家の家督を継ぐ。しかし、病弱のため、さしたる事跡も残せぬまま、治世わずか5年で病没した。
-

葛西俊信 (かさいとしのぶ)
伊達家臣。父・重俊は胤重(晴信の弟)の子。兄・重信は宇和島伊達家に仕えて宇和島に赴いた。馬術の名手として知られ、京都で数回、妙技を披露している。
-

葛西晴胤 (かさいはるたね)
葛西家15代当主。晴重の次男。寺池城主。兄・守信とその養子・晴清(伊達稙宗の子)がともに早世したため、家督を継ぐ。将軍・足利義晴の偏諱を受けた。
-

葛西晴信 (かさいはるのぶ)
葛西家17代当主。晴胤の次男。寺池城主。兄・親信の死後、家督を継ぐ。伊達家と結んで大崎家と戦った。豊臣秀吉の小田原征伐に参陣せず、改易された。
-

笠原清繁 (かさはらきよしげ)
信濃の豪族。志賀城主。山内上杉家に属した。武田信玄の攻撃に頑強に抵抗したが援軍を武田軍に撃破され、孤立。間もなく武田軍の総攻撃を受け、自害した。
-

笠原信為 (かさはらのぶため)
北条家臣。康勝の父。早雲の代から仕えた古参の重臣で、伊豆衆の筆頭格。氏綱の代に小机城の城代に任じられ、武蔵南部の豪族で組織される小机衆を率いた。
-

笠原政尭 (かさはらまさたか)
北条氏家臣。松田憲秀の子で笠原氏を継ぐ。豊臣氏の小田原攻めの際、父と共に秀吉に内応しようとしたが、弟・秀治に密告され発覚、主君の氏政に殺された。
-

笠原康勝 (かさはらやすかつ)
北条家臣。能登守と称す。笠原家は父・信為の時に北条家に属したという。1554年、今川家との加島合戦において、北条氏繁らとともに先陣を務めた。
-

柏山明助 (かしやまあきすけ)
葛西家臣。明宗の嫡男。主家滅亡後、南部家に仕える。岩崎城代を務め、和賀兵乱の鎮定などに活躍したが、剛勇ぶりを恐れた主君・利直によって毒殺された。
-

柏山明長 (かしやまあきなが)
葛西家臣。柏山明吉の三男。小山城主。弟・折居明久とともに領内屈指の荒武者といわれる。1581年の柏山家内乱の際には家老・三田将監を殺害した。
-

柏山明久 (かしやまあきひさ)
葛西家臣。柏山明吉の四男。折居館主。領内屈指の荒武者といわれ、柏山家内乱の際には家老・三田将監を殺害。葛西・大崎一揆では叛乱軍の総帥となった。
-

柏山明吉 (かしやまあきよし)
葛西家臣。大林城主。柏山家は奥州千葉家の一族。胆沢郡の惣領職を務め、家中屈指の軍事力を誇っていた。葛西・大崎一揆で総大将を務めた柏山明宗の父。
-

梶原景宗 (かじわらかげむね)
北条家臣。北条氏康に紀伊より招かれ、水軍を束ねる。里見家との合戦で活躍した。主家滅亡後、旧主・氏直に従い高野山に赴く。氏直の死後は紀伊に戻った。
-

果心居士 (かしんこじ)
正体不明の術師。松永久秀の前でその死んだ妻に化けたり、笹を魚に変えるなど様々な術を使った。のち豊臣秀吉により磔となるが、鼠に化けて逃げたという。
-

春日元忠 (かすがもとただ)
上杉家臣。はじめ武田家に仕えた。直江兼続の側近となる。兼続の信頼は厚く、「直江被官の棟梁」と呼ばれた。軍事面においても最上家攻めなどで活躍した。
-

糟屋武則 (かすやたけのり)
豊臣家臣。播磨の出身。賤ヶ岳七本槍の1人。関ヶ原合戦の際は西軍に属し、伏見城攻撃などに参加した。戦後、改易されるが、のちに幕臣として登用された。
-

片桐且元 (かたぎりかつもと)
豊臣家臣。賤ヶ岳七本槍の1人。主君・秀頼の傅役として主家存続のため奔走するが、徳川家康への内通疑惑により大坂城を退去した。以後は徳川家に属した。
-

片桐貞隆 (かたぎりさだたか)
豊臣家臣。且元の弟。小田原征伐などに従軍。豊臣秀吉の死後は秀頼に仕えたが方広寺鐘銘事件で徳川家への内通を疑われ、兄とともに大坂城を去った。
-

片倉喜多 (かたくらきた)
伊達家臣・鬼庭良直の娘。伊達政宗を支える名将・鬼庭綱元、片倉景綱らの姉。政宗の乳母、教育係を務めた。片倉家の旗指物「黒釣鐘」を考案した。
-

片倉小十郎 (かたくらこじゅうろう)
伊達家臣。19歳で主君・政宗の傅役となり「智」の面で政宗を補佐した智将。豊臣秀吉の小田原征伐に参陣するよう政宗を説得し、伊達家の存続に貢献した。
-

片倉重長 (かたくらしげなが)
伊達家臣。景綱の子。大坂夏の陣で後藤基次らを討ち取るなど活躍し、徳川家康から「鬼」と評された。この時に真田幸村の娘・梅を保護し、のちに妻とした。
-

堅田元慶 (かただもとよし)
毛利家臣。はじめ粟屋姓を名乗るが、主君・輝元より堅田姓を賜った。小早川隆景の伊予転封後は備後三原城主となる。関ヶ原合戦には輝元の代理で出陣した。
-

桂元澄 (かつらもとずみ)
毛利家臣。安芸桜尾城主を務め、厳島神社を含む神領の管理・支配を担当した。厳島合戦の際は陶晴賢に偽の書簡を送り晴賢を厳島へ誘き出すことに成功した。
-

葛山氏元 (かつらやまうじもと)
今川家臣。葛山城主。家臣屋敷分の年貢減免や領内社寺の保護など、自領内に独自の政策を施した。主家滅亡後は没落し武田信玄の六男・氏貞が跡を継いだ。
-

加藤明成 (かとうあきなり)
嘉明の嫡男。父の死後、陸奥会津40万石を相続。若松城天守閣を改修した。一歩金を好み一歩殿と呼ばれた。家老と対立し会津騒動を起こし、改易された。
-

加藤清正 (かとうきよまさ)
豊臣家臣。賤ヶ岳七本槍の1人。朝鮮派兵で活躍し「虎加藤」の逸話を残す。秀吉死後は石田三成と対立、関ヶ原合戦で東軍に属し、肥後熊本52万石を得た。
-

加藤貞泰 (かとうさだやす)
光泰の次男。豊臣秀吉に仕える。関ヶ原合戦では東軍に味方して島津勢と戦い、戦後、水口城を攻略。大坂の陣でも武功を立て、伊予大洲城主となった。
-

河東田清重 (かとうだきよしげ)
白河結城家臣。上総守と称した。武勇に優れ、善政を敷いたので民衆はよく服したという。佐竹家との戦いなどで活躍した。主家の滅亡後は伊達家に仕えた。
-

加藤忠広 (かとうただひろ)
清正の次男。父の死後、藤堂高虎の後見を受けて肥後熊本藩54万石を継ぐ。若年のため家臣団を掌握できず、後年、幕法違反のかどで除封された。
-

加藤段蔵 (かとうだんぞう)
「飛び加藤」の綽名をもつ優秀な忍者。上杉謙信に仕えるが段蔵の能力を恐れた謙信に越後を追われ、続いて仕えた武田信玄にも命を狙われ厠にて暗殺された。
-

加藤政貞 (かとうまささだ)
尼子家臣。尼子清久の子。尼子家滅亡後尼子勝久が率いる尼子再興軍に呼応。布部山合戦に敗れて出雲を追われ、上月城で毛利家の大軍に包囲されて自害した。
-

加藤光泰 (かとうみつやす)
斎藤竜興、豊臣秀吉に仕え、浅井攻め・播磨三木城攻めで功を立てた。小田原征伐ののち甲府城主となる。文禄の役では朝鮮に渡ったが、日本への帰途で病没。
-

加藤嘉明 (かとうよしあきら)
豊臣家臣。賤ヶ岳七本槍の1人。「沈勇の士」と評された。豊臣水軍の主力として各地の合戦で活躍。関ヶ原合戦では東軍に属し、伊予松山20万石を領した。
-

門脇政吉 (かどわきまさよし)
出羽の豪族・浅利家家臣。浅利則頼の女婿となり、浅利姓を与えられる。のちに浅利家を出奔し、鷹匠として信長の子の信高や蒲生氏郷に重用される。
-

金上盛備 (かながみもりはる)
蘆名家臣。主君・盛隆の死後、伊達政宗の弟・小次郎を跡継ぎに推す一派を抑え佐竹義重の次男・義広を当主に迎えることに成功した。摺上原合戦で戦死した。
-

金森重頼 (かなもりしげより)
可重の次男。兄・重近が感動されたため家督を継ぎ飛騨高山藩主となる。鉱山や新田開発に努め、飢饉の際には家宝の茶器を売って領民救済にあてたという。
-

金森長近 (かなもりながちか)
織田家臣。赤母衣衆の1人。柴田勝家に従い北陸平定に貢献。勝家の死後は蟄居するが、のち豊臣秀吉に仕えた。茶の湯に秀で、利休七哲の1人に数えられる。
-

金森可重 (かなもりよししげ)
織田家臣。長屋景重の子で、長近の養子となる。養父の死後、家督を相続。大坂の陣に従軍し、功を立てた。養父と同じく茶の湯を好み、茶会記に名を残した。
-

嘉成重盛 (かなりしげもり)
安東家臣。米内沢城主。安東家の鹿角攻めで功を立て、阿仁郡代となる。南部家の攻撃を撃退し、のちに大館城の奪還に成功するが、この時の合戦で戦死した。
-

可児才蔵 (かにさいぞう)
福島家臣。侍大将を務める。宝蔵院胤栄に槍術を学ぶ。関ヶ原合戦では討ち取った17の首級すべてに笹を差して目印としたため「笹の才蔵」の異名をとった。
-

金子元宅 (かねこもといえ)
伊予の豪族。金子城主。長宗我部元親の四国統一に貢献する。人格・識見ともに優れた勇将と評された。豊臣秀吉の四国征伐軍に抵抗するが敗れ、自害した。
-

金田弘久 (かねだひろひさ)
三浦家臣。加賀守と称した。主君・貞勝の高田城奪還作戦に船津貞家や牧尚春らとともに従う。尼子家臣・宇山久信が守る高田城を攻め、見事奪還に成功した。
-

兼平綱則 (かねひらつなのり)
津軽家臣。主君・為信の創業期を支えた大浦三老の1人。兼平家は大浦一族で、種里盛純(大浦盛信の弟)が兼平村を領した際に、地名を姓としたという。
-

印牧美満 (かねまきよしみつ)
朝倉家臣。加賀一向一揆攻めで朝倉宗滴が病に倒れ、朝倉景隆が代行すると、それを補佐した。1560年まで、府中の奉公職を務めて朝倉家の基盤を支えた。
-

兼松正吉 (かねまつまさよし)
織田家臣。越前刀根山の合戦で奮戦し、主君・信長から足半(草履の一種)を賜る。本能寺の変後は尾張に戻り、織田信雄や松平忠吉など代々の領主に仕えた。
-

狩野秀治 (かのうひではる)
上杉家臣。父・秀基は神保家の臣。御館の乱では景勝方として活躍。上杉の内政や外交の取り次ぎ役として、直江兼続と二頭体制を築く。のちに讃岐守を受領。
-

神生通朝 (かのうみちとも)
江戸家臣。大部城(神生城)主。家老を務めた。同じく家老の江戸道澄と対立し叛乱を起こすが、敗死した。この事件以来、江戸家は衰退の一途をたどった。
-

狩野泰光 (かのうやすみつ)
北条家臣。氏康の代から仕え、馬廻衆として活躍。小田原征伐の際に、八王子城で前田・上杉軍と戦って死んだ狩野一庵宗円を同一人物とする説もある。
-

鹿子木親員 (かのこぎちかかず)
菊池家臣。肥後隈本城主。大友義長の次男・義武の菊池家入嗣後は義武の家老となる。三条西実隆から「源氏物語」を購入するなど、文事にも関心が深かった。
-

樺山忠助 (かばやまただすけ)
島津家臣。善久の子。久高の父。貴久、義久に重臣として仕え、薩摩・日向・大隅の三州統一に貢献した。歌人として知られた父に似て、自身も和歌を好んだ。
-

樺山久高 (かばやまひさたか)
島津家臣。家老を務めた。豊臣秀吉の朝鮮派兵に従軍し、李舜臣の率いる亀甲船水軍を破った。琉球遠征では総大将を務め、首里を占拠して王子を捕虜にした。
-

樺山善久 (かばやまよしひさ)
島津家の庶流。貴久に仕えて度々武功を挙げた。歌人としても知られ、城内に歌を書きつけて逃亡した敵を追撃し、返歌を矢に結んで放ったという逸話が残る。
-

鹿伏兎定秀 (かぶとさだひで)
伊勢の豪族。鹿伏兎城主。鹿伏兎家は関家の庶流。織田信長の三男・信孝が神戸家の養子となってからは織田家に従うが姉川合戦の際は浅井家に属して戦った。
-

鎌田政年 (かまたまさとし)
島津家臣。肥後矢崎城攻めなどで活躍した。薩摩馬越城攻めで大活躍し、主君・忠良から功を賞され、島津家の看経所に名を残した4人のうちの1人となった。
-

蒲池鑑久 (かまちあきひさ)
筑後の豪族。蒲池城主。武蔵守と称す。蒲池家の嫡流・下蒲池家の祖となった。柳河城を築いて居城とした。大友家に属し二十四城持大名の旗頭を務めていた。
-

蒲池鑑盛 (かまちあきもり)
筑後の豪族。柳河城主。鑑久の嫡男。大友家に属した。滅亡の危機に瀕した龍造寺家を2度に渡って保護した。耳川合戦に参陣し、一族郎党とともに戦死した。
-

蒲池鎮漣 (かまちしげなみ)
筑後の豪族。柳河城主。鑑盛の嫡男。父の死後家督を継ぐ。龍造寺隆信の筑後経略に協力するが、のちに対立。隆信の居城・肥前佐賀城に呼び出され殺された。
-

上泉信綱 (かみいずみのぶつな)
剣術家。はじめ長野家に仕える。主家滅亡後は、一時武田信玄に仕えるが、間もなく武芸修業のため浪人し、新陰流を創始した。門弟には柳生宗厳などがいる。
-

上泉泰綱 (かみいずみやすつな)
新陰流の創始者・上泉信綱の孫。関ヶ原合戦の直前、上杉景勝の浪人徴募に応じ直江兼続の指揮下に属した。出羽長谷堂城における最上軍との戦いで戦死した。
-

亀井茲矩 (かめいこれのり)
尼子家臣。主家滅亡後は豊臣家に仕え、鹿野城主となる。干拓や用水路の建設など、領内の産業振興に努めた。また朱印状を得て、シャムに貿易船を派遣した。
-

亀井秀綱 (かめいひでつな)
尼子家臣。1511年の船岡山合戦には主君・経久とともに従軍した。毛利元就の異母弟・相合元綱を籠絡して毛利家の分裂を図ったが、失敗に終わった。
-

亀井政矩 (かめいまさのり)
徳川家臣。茲矩の次男。徳川秀忠の近習を務めた。父の死去に伴い、因幡鹿野2代藩主となる。ねねと親しく、彼女を訪問する途中で落馬、若くして死去した。
-

亀ヶ森光広 (かめがもりみつひろ)
稗貫家臣。図書と称す。1540年、八十沢氏に代わって亀ヶ森城主となる。のち主家に背いたため攻撃を受けるが、撃退した。子孫は南部家に仕えたという。
-

亀田高綱 (かめだたかつな)
浅野家臣。関ヶ原合戦などで軍功多く、大坂夏の陣の樫井の戦いでは塙団右衛門を討ち取るが、その功を他人のものとされた。のち上田重安と争い、下野した。
-

蒲生氏郷 (がもううじさと)
織田家臣。賢秀の子。主君・信長の娘を娶る。本能寺の変後は豊臣秀吉に仕え活躍、陸奥会津92万石を領した。文武に秀でたその器量を秀吉は恐れたという。
-

蒲生賢秀 (がもうかたひで)
六角家臣。定秀の子。織田信長上洛の際は信長の三男・信孝が妹婿・神戸具盛の養子となった関係から織田家に属す。本能寺の変の際は信長の妻子を保護した。
-

蒲生定秀 (がもうさだひで)
六角家臣。六角軍の先鋒として各地に出陣し、勇名を馳せた。主君・義治が後藤賢豊を謀殺して観音寺騒動が起こった際は、義治と家臣団間の調停役を務めた。
-

蒲生茂綱 (がもうしげつな)
織田家臣。蒲生定秀の子。青地家の養子となる。北畠家攻めなどに従軍した。のちに森可成らとともに坂本城を守るが、浅井・朝倉連合軍に攻められ戦死した。
-

蒲生忠郷 (がもうたださと)
秀行の嫡男。父の死後家督を継ぐ。曾祖父は織田信長、母方の祖父は徳川家康というそうそうたる血脈に生まれたが、早世。嫡子がいなかった蒲生家は断絶した。
-

蒲生忠知 (がもうただとも)
秀行の次男。兄・忠郷の早世で断絶した蒲生家を幕府の計らいで再興、伊予松山24万石を領した。しかし、忠知も早世し、嗣子なく、蒲生家は再び断絶した。
-

蒲生範清 (かもうのりきよ)
大隅の豪族。島津家と争い、岩剣城に義久・義弘・歳久3兄弟が攻め寄せると、日本初となる鉄砲同士による合戦を行った。のちに島津家に降伏した。
-

蒲生秀行 (がもうひでゆき)
豊臣家臣。氏郷の嫡男。陸奥会津92万石を継ぐが、家中内紛により下野宇都宮18万石に減封された。関ヶ原合戦で東軍に属し、陸奥会津60万石に戻った。
-

蒲生元珍 (がもうもとよし)
織田家臣。父・茂綱の死後、家督を継ぎ所領を安堵される。佐久間信盛の与力として各地に従軍した。本能寺の変後は織田信孝に属す。のちに前田家に仕えた。
-

萱場元時 (かやばもととき)
伊達家臣・伊達成実の配下。鉄砲の扱いに長けた。成実が何度も褒美を出すが、そのたびに辞退する。辞退ばかりで気が引けたのか、一文のみ拝受した。
-

ガラシャ (がらしゃ)
明智光秀の三女。名は玉子とも伝わる。細川忠興の妻で、敬虔なキリスト教徒。関ヶ原合戦の直前に西軍の人質になることを拒み、家臣の手で最期を遂げる。
-

河合吉統 (かわいよしむね)
朝倉家臣。一乗谷四奉行の1人として国政に参画したほか、浅井家救援のために近江に出陣するなど活躍した。刀禰坂合戦において、織田軍に討たれたという。
-

川上忠克 (かわかみただかつ)
島津家臣。串木野城主。はじめ薩州島津家に属すが、のちに島津忠良に降り、甑島に3年間配流された。のち家老を務め白山権現の再興に尽くすなど活躍した。
-

川上忠実 (かわかみただざね)
島津家臣。島津以久に属す。沖田畷合戦で龍造寺家就を討つ功を上げる。朝鮮の役では以久の子・彰久を補佐。彰久病死により軍代として彰久軍を指揮した。
-

川上久朗 (かわかみひさあき)
島津家臣。忠克の子。島津家の看経所に名を残した4人のうちの1人。18歳の時には主君・義久から守護代に推されたという。薩摩大口城攻撃戦で戦死した。
-

川口宗勝 (かわぐちむねかつ)
織田家臣。本能寺の変後は信雄に仕え、その没落後は秀吉に従った。関ヶ原合戦では西軍に属し、敗戦後は伊達政宗預かりとなる。のち許されて徳川家に仕官。
-

川崎祐長 (かわさきすけなが)
伊東家臣。目井城主。駿河守と称す。主君・義祐の豊後退去に従う。貧窮を助けるために酒や織物を作り売ったという。主家が旧領に復すと酒谷城主となった。
-

川島宗泰 (かわしまむねやす)
二階堂家臣。主家滅亡後は伊達家に仕える。葛西・大崎一揆の際は満身創痍となりながらも退かなかったという。のちに仙台城や江戸城外濠の普請を担当した。
-

河尻秀隆 (かわじりひでたか)
織田家臣。黒母衣衆筆頭。信長の嫡男・信忠の補佐役となる。甲斐平定戦で活躍し、戦後、甲斐一国を与えられた。本能寺の変後、甲斐の国人一揆で殺された。
-

河尻秀長 (かわじりひでなが)
豊臣家臣。苗木城主。秀隆の子。小牧長久手合戦や小田原征伐などに従軍した。朝鮮派兵では肥前名護屋城に在陣する。関ヶ原合戦で西軍に属し、戦死した。
-

河副久盛 (かわぞえひさもり)
尼子家臣。経久の代から活躍した。林野城代として美作方面軍を指揮する。尼子家滅亡後、立原久綱と尼子家再興軍を結成。月山富田城攻略中に病に倒れた。
-

河田長親 (かわだながちか)
上杉家臣。近江の出身。上杉謙信が上洛した際に召し出され、家臣となる。上杉家の北陸攻略に大きく貢献した。のちに松倉城主となり、織田信長軍と戦った。
-

河原綱家 (かわはらつないえ)
真田家臣。昌幸の従兄。長篠の戦いで兄を失い家督を継ぐ。関ヶ原合戦では真田親子の会談を覗き見し、激怒した昌幸に下駄を投げつけられ、前歯を折られた。
-

川原具信 (かわはらとものぶ)
浪岡北畠家臣。具永の子。断絶していた川原御所を継ぐ。「津軽郡中名字」を編纂した。のちに甥・具運と対立して具運を討つが、具運の弟・顕範に討たれた。
-

川村重吉 (かわむらしげよし)
伊達家臣。算術、水利に精通し、北上川の改修工事をはじめとして数々の土木事業を担当する。実質200万石といわれた仙台藩の経済基盤の礎を作り上げた。
-

神吉頼定 (かんきよりさだ)
別所家臣。神吉城主。神吉家は赤松家の庶流。羽柴秀吉の中国侵攻軍に対して頑強に抵抗したが、敗れて戦死。居城は焼け落ち、将兵の大半が焼死したという。
-

願証寺証意 (がんしょうじしょうい)
長島願証寺の僧。父・証恵を継いで門跡となる。本願寺顕如の檄に呼応し、織田信長と対立。門徒衆を率いて壮絶な死闘を繰り広げる中、謎の急死を遂げる。
-

願証寺証恵 (がんしょうじしょうけい)
蓮淳の孫。伊勢長島願証寺の住職を務めた。一向宗門徒を率いて織田信長の討伐軍に激しく抵抗するが、信長の焦土化作戦の前に敗北し、木曽川に身を投げた。
-

願証寺蓮淳 (がんしょうじれんじゅん)
本願寺8世法主・蓮如の六男。大津顕証寺を経て、門徒の要望により河内顕証寺の住職となる。伊勢長島に願証寺を建立するなど、本願寺の発展に貢献した。
-

鎌原幸定 (かんばらゆきさだ)
真田幸隆の弟。昌幸の叔父。海野家の支族である鎌原家に養子に入る。早くより武田家に臣従し、幸隆と共に先方衆の一手を担って信玄の信濃進出に貢献した。
-

神戸具盛 (かんべとももり)
伊勢の豪族。神戸城主。織田信孝(信長の子)を養子とする。のちに信長により日野城に幽閉されるが、信孝が四国へ出陣する際、許されて留守居役を務めた。
-

菅正利 (かんまさとし)
黒田家臣。黒田二十四騎の一。賤ヶ岳合戦で初陣。九州征伐や城井長房との戦いで活躍、関ヶ原合戦で島左近を討ち取るなど武功抜群で朱具足を許されていた。
-

菅達長 (かんみちなが)
豊臣家臣。もとは淡路の土豪で、毛利・長宗我部らに従い織田・豊臣と戦った。四国征伐後は豊臣に属し、水軍衆として九州征伐や小田原征伐で活躍した。
-

城井鎮房 (きいしげふさ)
城井宇都宮家16代当主。長房の子。大友、島津家に属して所領を保つ。のち豊臣秀吉に降るが、伊予への転封を拒否して謀叛を起こし、黒田長政に殺された。
-

城井長房 (きいながふさ)
城井宇都宮家15代当主。正房の子。早くから子・鎮房に家督を譲る。自らは下野宇都宮家の継嗣問題に2度関与した。のち鎮房とともに黒田長政に殺された。
-

城井正房 (きいまさふさ)
城井宇都宮家14代当主。大内家に仕える。少弐・大友家と結んで主家に対抗するが、一族の佐田俊景の攻撃を受けて敗北し降伏、以後は再び大内家に従った。
-

菊池義武 (きくちよしたけ)
大友義長の次男。肥後の名家・菊池家を継ぐ。大内家と結んで兄・義鑑と戦うが敗れた。のちに、大友家の家督を継いだ甥・宗麟の謀略によって討たれた。
-

菊姫 (きくひめ)
武田信玄の五女。武田家と上杉家の同盟に伴い、上杉景勝に嫁ぐ。美貌と聡明さを兼ね備えた女性で、上杉家中では甲斐御前と呼ばれて大切にされたという。
-

木沢長政 (きざわながまさ)
細川家臣。信貴山城主。主君・晴元に従って旧主・畠山義宣を自害させ、三好元長を討った。のちに晴元と対立し、河内太平寺合戦で細川軍と戦うが敗死した。
-

岸田忠氏 (きしだただうじ)
筒井家臣。筒井順慶に従って松永久秀と攻防戦を展開。のち豊臣家に仕え、関ヶ原では旧知の島左近らとともに西軍に参加。助命され、南部家に預けられた。
-

来次氏秀 (きすぎうじひで)
出羽の豪族。時秀の子。大宝寺家と最上家の間で去就に迷う。十五里ヶ原合戦以降は上杉家に従った。1601年、居城の観音寺城を捨て米沢に赴いたという。
-

来次時秀 (きすぎときひで)
出羽の豪族。16世紀後半、飽海郡に観音寺城を築き、居城とした。尾浦城主・大宝寺家に仕え、約2千5百石を知行したという。
-

木曾義在 (きそよしあり)
信濃木曾谷の豪族。温和な人柄で、父・義元の頃から対立状態にあった飛騨の三木家との関係修復に尽力、領内の治世安定に努めた。「風流太守」と呼ばれた。
-

木曾義利 (きそよしとし)
徳川家臣。義昌の嫡男。父の死後、家督を継ぐ。粗暴の振る舞いが多く、叔父・義豊を殺害した罪により改易された。その後は京都で剃髪し、各国を流浪した。
-

木曾義昌 (きそよしまさ)
信濃木曾谷の豪族。義康の嫡男。武田信玄の娘を娶る。のち織田信長に通じ、武田家滅亡の原因を作った。本能寺の変後は徳川家康に属し、下総に転封された。
-

木曾義康 (きそよしやす)
信濃木曾谷の豪族。義在の嫡男。村上義清・小笠原長時・諏訪頼重とともに「信濃の四大将」と呼ばれた。武田信玄の攻撃に頑強に抵抗したが敗れ、降伏した。
-

北里政義 (きたざとまさよし)
阿蘇家臣。肥後石櫃城主。大友家とも親交を結び、豊前に出陣している。島津家の肥後侵攻軍に降るが、親大友家の子・重義と争った。のち加藤清正に仕えた。
-

北条景広 (きたじょうかげひろ)
上杉家臣。高広の子。父とともに厩橋城に在城し、主君・謙信の関東経略を助けた。御館の乱の際は上杉景虎方の中核を担うが、のちに上杉景勝に暗殺された。
-

北条高広 (きたじょうたかひろ)
上杉家臣。厩橋城主を務め、関東経略を担当するなど活躍した。武田信玄や北条氏康らの誘いに乗り、たびたび謀叛を起こすが、そのたびに許されて帰参した。
-

北楯利長 (きただてとしなが)
最上家臣。大学と称す。治水工事を行って庄内平野の水不足を解消させた。この堰は「大学堰」と呼ばれ、主君・義光が「庄内末世の重宝」と絶賛したという。
-

北愛一 (きたちかかず)
南部家臣。信愛の子。九戸政実の乱の後陸奥寺田城主となって寺田北家を立てたため、父の花巻北家が断絶したとき後を継がなかった。大坂の陣に従軍。
-

北之川親安 (きたのがわちかやす)
西園寺家臣。三滝城主。西園寺十五将の1人。長宗我部家臣・波川玄蕃の娘を娶ったが、のちに玄蕃が謀叛を企てたため長宗我部元親の攻撃を受け、敗死した。
-

北之川経安 (きたのがわつねやす)
西園寺家臣。甲之森城主。西園寺十五将の1人。紀氏の末裔で紀経安ともいう。彼のもと、所領の北之川庄は発展したようで、2ヵ村に分割されている。
-

北信景 (きたのぶかげ)
南部家臣。信愛の養子。主君利直と不仲で出奔する。大坂の陣では豊臣方に与し、派手な甲冑をまとって活躍したことから「南部の光り武者」と呼ばれた。
-

北信愛 (きたのぶちか)
南部家臣。剣吉城主。晴政死後の御家騒動では信直を支持、信直の筆頭家老として活躍した。合戦に臨む際は、必ず小さな観音像を髻の中に収めていたという。
-

北畠具教 (きたばたけとものり)
伊勢国司・北畠家8代当主。晴具の子。織田信長に敗れ、信長の次男・信雄を養子とするが、のちに殺された。塚原卜伝より秘伝「一の太刀」を授けられた。
-

北畠具房 (きたばたけともふさ)
伊勢国司・北畠家9代当主。具教の子。父が織田信雄に殺されたあと、滝川一益に預けられ安濃郡河内に3年間幽閉された。のち解放されるが、間もなく病死。
-

北畠晴具 (きたばたけはるとも)
伊勢国司・北畠家7代当主。伊勢神宮の門前町・宇治山田の町衆(山田三方)らと対立し、長期に渡って抗争を続けた。弓馬の達人で、和歌や書をよくした。
-

北畠昌教 (きたばたけまさのり)
具房の嫡男。織田信雄が北畠家一族を謀殺した際、難を逃れた母が逃亡先で産んだ。各地を放浪後、津軽家の客分となり北畠家再興を目指すが果たせなかった。
-

北原兼孝 (きたはらかねたか)
日向の豪族。伊東家と結び、北郷家などと戦う。しかし、後継者問題を巡る紛争で北原家は伊東家に乗っ取られ、兼孝自身も伊東家家臣の凶刃に倒れた。
-

北致愛 (きたむねちか)
南部家臣。信愛の父。南部家21代目当主・信義の嫡男だが、信義が死去した翌日に生まれたため南部家を継承できず、母方の北家に追いやられたという。
-

帰蝶 (きちょう)
斎藤道三の娘。濃姫。父と織田家が和睦した際、織田信長に嫁ぐ。本能寺の変後は信長の次男・信雄を頼り、尾張に化粧領を与えられ安土殿と呼ばれたという。
-

吉川興経 (きっかわおきつね)
安芸の豪族。尼子家と大内家の間で裏切りを繰り返し、家中の分裂を招く。毛利元就から次男・元春を養嗣子として送り込まれ、その直後に殺された。
-

吉川経家 (きっかわつねいえ)
毛利家臣。経安の子。山名豊国の追放を受け、因幡鳥取城に入り羽柴秀吉軍と戦う。しかし秀吉の「渇え殺し」戦法により敗れ、城兵の助命を条件に自害した。
-

吉川経安 (きっかわつねやす)
毛利家臣。毛利家が石見を平定したあと物不言城を築き、居城とする。のちに所領問題で主家に背いた福屋隆兼の攻撃を受けるが、子・経家とともに撃退した。
-

吉川経世 (きっかわつねよ)
吉川家臣。国経の次男。甥・興経に近侍する大塩氏が圧政を敷いていたため、森脇祐有とともに大塩氏を討ち、興経を隠居させて毛利元就の子・元春を迎えた。
-

吉川広家 (きっかわひろいえ)
元春の三男。関ヶ原合戦で西軍の敗北を予想し、外交工作によって毛利家の存続をはかる。しかし宗家は防長2国に減封され、家中から裏切り者と非難された。
-

吉川元氏 (きっかわもとうじ)
吉川元春の次男。初め周防の旧族仁保三浦氏を継ぐ。のち三浦の家は娘婿の元忠に譲り、姓を繁沢と称した。後年、毛利姓を許され、阿川毛利氏の祖となる。
-

吉川元長 (きっかわもとなが)
元春の長男。父に劣らぬ武勇を誇り、豊臣秀吉の九州征伐に従軍した際も、常に勝利を収めたという。父の隠居後、家督を継ぐが、父の死後間もなく病死した。
-

吉川元春 (きっかわもとはる)
毛利元就の次男。安芸の豪族・吉川家を継ぎ、山陰地方の攻略にあたる。不敗を誇った家中随一の猛将である一方、陣中で「太平記」40巻を写本したという。
-

吉乃 (きつの)
織田信長の側室。生駒家宗の娘。信忠・信雄・徳姫を生んだが、産後の肥立ちが悪く逝去した。信長の実質的な正室とも言われている。
-

喜連川頼氏 (きつれがわよりうじ)
小弓公方・義明の孫。頼純の子。兄の死後、兄の正室である足利氏姫(古河公方足利義氏の娘)と結婚して遺領を継ぐ。のちに喜連川藩初代藩主となった。
-

衣笠範景 (きぬがわのりかげ)
別所家臣。衣笠城主。衣笠家は赤松家の庶流。一時三好長慶に属して各地を転戦した。羽柴秀吉の中国侵攻軍と戦い、敗北。野に下ったとも戦死したともいう。
-

木下勝俊 (きのしたかつとし)
豊臣家臣。家定の長男。若狭小浜城主。関ヶ原合戦では東軍に属して伏見城を預かるが、任務放棄の罪で改易され、京都に隠棲した。近世和歌の祖といわれる。
-

木下重賢 (きのしたしげかた)
荒木家臣。主君・村重の小姓を務めた。主家没落後は豊臣秀吉に仕え、のちに木下姓を賜り因幡若桜2万石を領す。関ヶ原合戦では西軍に属し、戦後自害した。
-

木下延俊 (きのしたのぶとし)
豊臣家臣。家定の次男。姫路城代を務め関ヶ原合戦で西軍の弟・小早川秀秋の入城を拒んだ。『慶長日記』は彼の1613年の1年間を記した資料である。
-

木下昌直 (きのしたまさなお)
龍造寺家臣。龍造寺四天王の1人といわれる。沖田畷合戦で主君・隆信戦死の報を聞くと、鍋島直茂を離脱させたのち、敵陣に突入した。生死は諸説あり不明。
-

木村定光 (きむらさだみつ)
豊臣家臣。常陸介と称す。賤ヶ岳合戦などに従軍し、越前府中10万石を領す。出羽の検地奉行などを務めた。のちに豊臣秀次事件に連座し、自害させられた。
-

木村重成 (きむらしげなり)
豊臣家臣。定光の子という。主君・秀頼の乳兄弟で、小姓を務めた。徳川家との和睦の際は豊臣家の使者を務めた。大坂夏の陣で井伊直孝軍と戦い、戦死した。
-

木村又蔵 (きむらまたぞう)
加藤清正家臣。加藤十六将の一。はじめ六角義賢に属し臆病又蔵の異名を取ったが八幡神の加護で無敵の勇士となる。清正の命で、大坂の陣で豊臣に味方した。
-

肝付兼篤 (きもつきかねあつ)
島津家臣。肝付兼盛の子。伊集院忠棟の死後、主家の許しを得て肝付家の名跡に返り咲く。のち庄内の乱鎮圧に功績を挙げ、晩年、琉球への出兵にも参加した。
-

肝付兼亮 (きもつきかねすけ)
大隅の戦国大名。高山城主。兼続の子。兄・良兼の死後家督を継ぐ。伊東家などと結んで島津家に対抗したため、母(島津忠良の娘)と家臣たちに追放された。
-

肝付兼武 (きもつきかねたけ)
島津家臣。兼篤の子。父の死により家督を継ぎ、喜入肝付家2代当主となる。大坂冬の陣に参陣すべく薩摩を出たが、肥後で和睦成立を聞き、引き返した。
-

肝付兼続 (きもつきかねつぐ)
大隅の戦国大名。高山城主。肝付家最大の版図を築く。島津忠良の娘を娶るが、のち忠良の子・貴久と敵対。居城を島津軍に奪われたとの報を聞くと自害した。
-

肝付兼演 (きもつきかねひろ)
大隅肝付家の庶流。義盛の父。本家が島津家に対抗する中、島津忠良に通じて加治木城主となる。のち忠良、貴久と敵対するも敗退して降伏、再び臣従した。
-

肝付兼盛 (きもつきかねもり)
島津家臣。肝付家の庶流。父・兼演から加治木城主を継いだ。島津貴久・義久の家老を務めた。蒲生家攻めや伊東家攻めで特に軍功があった。
-

肝付兼護 (きもつきかねもり)
大隅の戦国大名。高山城主。兼続の子。次兄・兼亮の追放により家督を継ぐが、島津軍の攻撃を受けて敗れ、所領を差し出し降伏した。関ヶ原合戦で戦死した。
-

肝付良兼 (きもつきよしかね)
大隅の戦国大名。高山城主。兼続の子。伊東家と結んで日向飫肥城を攻撃し、城主・島津忠親を追う。また伊地知重興を援助するなど、終生島津家と抗争した。
-

京極高次 (きょうごくたかつぐ)
豊臣家臣。高吉の子。妻と妹の縁故により豊臣秀吉に仕え、近江大津6万石を領す。関ヶ原合戦では東軍に属し居城に籠城、西軍の一部を大津に足止めさせた。
-

京極高知 (きょうごくたかとも)
豊臣家臣。高吉の次男。信濃飯田10万石を領し、城下町の整備に尽力した。関ヶ原合戦では東軍に属し、戦後、高野山に逃れた兄に徳川家への仕官を説いた。
-

京極高広 (きょうごくたかひろ)
北近江半国の守護。高清の長男。父が養子・高吉に家督を譲ろうとした際、浅井亮政らに擁立され高清・高吉を追う。家督を継ぐも、実権は亮政に奪われた。
-

京極高吉 (きょうごくたかよし)
足利家臣。主君・義輝の近習を務めた。義輝の死後は、近江に逃れた義輝の弟・義昭のために奔走。義昭の将軍就任後、織田信長と対立して上平寺に隠居した。
-

京極忠高 (きょうごくただたか)
高次の子。大坂の冬の陣の講和は、それを仲介した義母・初の縁で、忠高の陣で行われた。徳川秀忠の娘を妻とし、毛利家への抑えとして出雲隠岐が与えられた。
-

清野清秀 (きよのきよひで)
村上家臣。主家に背いた家臣を討ったり真田幸隆と戦うなど、主家の勢力維持に尽力。主君・義清の信濃退去に従い、のちに義清の子・国清の教育係を務めた。
-

清野長範 (きよのながのり)
上杉家臣。蘆名四天王・平田舜範の子。人質として上杉家に入り、上杉景勝に才を見いだされ近侍となる。景勝、定勝の信任厚く、米沢奉行に任じられた。
-

吉良親貞 (きらちかさだ)
長宗我部国親の次男。剛毅かつ知略に富んだ武将で、兄・元親の片腕として土佐統一に貢献した。土佐一条家滅亡後は土佐中村城代となるが間もなく病死した。
-

吉良親実 (きらちかざね)
長宗我部家臣。親貞の嫡男。宗家の家督相続に際し、四男・盛親の擁立を望む伯父・元親を諫めるが、対立勢力の久武親直に讒言され、元親に自害させられた。
-

吉良義堯 (きらよしたか)
三河吉良家11代当主。義元の子。遠江浜松荘に勢力を拡げ、大河内貞綱を代官として派遣するが、今川家の侵攻により貞綱が戦死したため、浜松荘を失った。
-

吉良義安 (きらよしやす)
三河吉良家13代当主。義堯の子。兄・義郷の早世により家督を継ぐ。のちに今川家に敗れ、駿府に連行された。松平元康の元服に際しては、理髪役を務めた。
-

木脇祐守 (きわきすけもり)
伊東家臣。鬼ヶ城主。島津軍を奇襲で破るなど活躍し、執事となる。主家の豊後退去に従えず、櫛間に隠れるが島津軍に発見され、弟とともに自害させられた。
-

九鬼広隆 (くきひろたか)
織田家臣。母の兄九鬼嘉隆に養われ九鬼姓を名乗る。初め織田信孝に仕え、後に加藤清正家臣となるが出奔。その後黒田家・小早川家・藤堂家と歴仕した。
-

九鬼守隆 (くきもりたか)
志摩鳥羽藩主。嘉隆の子。関ヶ原合戦では東軍に属し、西軍の父と戦う。戦後、自らの行賞と引き替えに父の助命を乞うが、父はすでに自害した後だった。
-

九鬼嘉隆 (くきよしたか)
織田家臣。志摩海賊衆の1人。木津川口合戦での大敗を契機に「鉄甲船」を建造し、毛利水軍を粉砕する。その功で大名に出世し「海賊大名」の異名をとった。
-

草野直清 (くさのなおきよ)
相馬家臣。顕胤に仕え、中村城代を務めていた。中村城は801年に坂上田村麻呂が菅原実敬に命じて築かせたという。その後は中村家が代々居城としていた。
-

櫛橋伊定 (くしはしこれさだ)
赤松家臣。志方城主。黒田官兵衛が16歳の時、その才を見抜いて赤合子の兜と具足を送り、後に娘・光を嫁がせた。天正年間に織田軍との籠城戦で没した。
-

櫛橋光 (くしはしてる)
黒田官兵衛の正室。黒田長政の生母。院号は照福院。十五歳で官兵衛に嫁ぐと、その才と徳で夫を支えた。浄土宗を篤く信仰していたと伝わる。
-

福島正成 (くしままさしげ)
今川家臣。高天神城主。家中随一の猛将といわれた。武田信虎との飯田河原合戦に敗れて戦死したとも、花倉の乱で敗北後、逃亡中に信虎に殺されたともいう。
-

楠木正虎 (くすのきまさとら)
足利家臣。当代随一の書家。楠木正成の末裔を称する。主君・義輝が討たれると松永久秀に仕えた。のち織田信長、そして豊臣秀吉の右筆を歴任した。
-

口羽通良 (くちばみちよし)
毛利家臣。志道広良の次男。吉川元春を補佐して山陰方面の経略を行う。主君・元就の死後、四人衆の1人となり当主・輝元を補佐して主家の国政に参画した。
-

朽木稙綱 (くつきたねつな)
近江の豪族。三好元長に京を追われた将軍・足利義晴を居館にかくまう。その功により申次七人衆の1人に加えられた。以後も何度か足利将軍家をかくまった。
-

朽木宣綱 (くつきのぶつな)
徳川家臣。元綱の長男。身分こそ旗本であったが、近江源氏の名族出身だったため、交代寄合に列せられ、大名と同列の待遇を与えられた。寛文地震で死去。
-

朽木晴綱 (くつきはるつな)
近江の豪族。稙綱の嫡男。宮内少輔と称した。はじめ貞綱といったが、将軍・足利義晴の偏諱を受けて晴綱と改名した。高島郡で高島越中守と戦い、戦死した。
-

朽木元綱 (くつきもとつな)
近江の豪族。晴綱の子。織田信長の越前撤退の際に道案内を務め、以後は織田家に属した。本能寺の変後は豊臣秀吉に仕える。関ヶ原合戦では東軍に寝返った。
-

忽那通著 (くつなみちあき)
河野家臣。水軍の将。大友宗麟が伊予に侵攻すると、来島通康・村上武吉らと共に撃退する。のち織田家と毛利家が争うと、海から毛利家を支援した。
-

国司元相 (くにしもとすけ)
毛利家臣。郡山合戦で敵将34人を倒した勇将。のち五奉行の一員となる。主君の隆元の名代として上洛した際、将軍・足利義輝から「槍の鈴」を免許された。
-

九戸実親 (くのへさねちか)
南部家臣。信仲の子。南部晴政の次女と結婚し、後継者候補となる。主家に叛旗を翻した兄・政実とともに九戸城に籠城し、豊臣軍と戦うが敗れ、斬首された。
-

九戸信仲 (くのへのぶなか)
南部家臣。信実の長男。九戸城主。右京と称す。九戸家は南部家の庶流で、南部行連(南部家の始祖・光行の六男)を祖とするという。八戸信長の娘を娶った。
-

九戸政実 (くのへまさざね)
南部家臣。信仲の子。南部晴政の死後、弟・実親を後継者に推すが敗れ、叛乱を起こす。南部信直の要請で出陣した豊臣軍相手に善戦するが敗れ、斬首された。
-

九戸康真 (くのへやすざね)
南部家臣。九戸信仲の子。はじめ高水寺城主・斯波詮真の娘婿となるが、のちに斯波家を出奔、斯波家討伐軍の先鋒を務めた。従兄弟・連尹に斬られ死去した。
-

久能宗能 (くのむねよし)
今川家臣。久能城主。主家滅亡の直前に徳川家臣・高力清長の仲介により徳川家康に属す。家康の関東入国時に佐倉城主となるが、のちに久能城に復帰した。
-

窪川俊光 (くぼかわとしみつ)
土佐一条家臣。串山城主。高岡郡窪川郷を本拠とし、山内から窪川に改姓した。のちに長宗我部元親に属す。久武親直に従って南伊予地方を攻略中に戦死した。
-

窪田経忠 (くぼたつねただ)
加賀の豪族。安吉城主。大炊介と称す。はじめ安吉家長に仕えたが、1550年に家長から安吉城を譲られ、城主となった。加賀一向一揆軍の頭領を務めた。
-

熊谷信直 (くまがいのぶなお)
安芸武田家臣。のちに主家と対立し、毛利家に属す。娘が元就の次男・吉川元春に嫁いでからは一門衆として重用され、吉川軍の先鋒を務めて各地で奮戦した。
-

熊谷元直 (くまがいもとなお)
毛利家臣。信直の孫。各地の合戦に従軍して活躍した。黒田孝高の影響を受けて切支丹となる。のちに主君・輝元の改宗命令を拒否し、一族全員死罪となった。
-

神代勝利 (くましろかつとし)
少弐家臣。肥前三瀬城主。「北山に枕し南海に足を浸す」という夢を買い取り、武運に恵まれる。龍造寺家臣・小田政光を討つなど、終生龍造寺家に対抗した。
-

神代長良 (くましろながよし)
少弐家臣。勝利の嫡男。父の隠居により家督を継ぐ。父の死後は龍造寺家と和睦し、家臣となった。のちに小川信俊(鍋島直茂の弟)の子・家良を養子とした。
-

隈部親永 (くまべちかなが)
菊池家臣。肥後長野城主。主家没落後は龍造寺家に属す。豊臣秀吉の九州征伐軍に降るが、佐々成政の検地に抵抗して肥後国人一揆を起こし、敗れて殺された。
-

久米五郎 (くめごろう)
別所家臣。三木合戦の際、三木城に籠城した。敗色濃厚となると、敵軍に紛れて羽柴秀吉の陣に潜入。秀吉に切り掛かるが取り押さえられ、討死した。
-

公文重忠 (くもんしげただ)
土佐の豪族。徳善城主。はじめ長宗我部国親と戦うが、のちに家臣となり各地の合戦で活躍した。勇将であったが貧乏で正月の餅つきができなかったという。
-

来島通総 (くりしまみちふさ)
豊臣家臣。通康の四男。はじめ河野家に属す。主君・秀吉の四国征伐の際は兄・得居通年とともに先鋒を務めた。朝鮮派兵に水軍を率いて従軍し、戦死した。
-

栗山善助 (くりやまぜんすけ)
黒田家臣。黒田八虎の一人。名は利安。官兵衛に仕えた股肱の臣。関ヶ原に際しては、義弟・母里太兵衛とともに官兵衛に従い、豊後の大友軍と戦った。
-

栗山大膳 (くりやまたいぜん)
黒田家筆頭家老。利安の子。名は利章。時代に逆行した軍拡を行う主君・忠之と対立。幕府に忠之謀反を訴え、黒田騒動を起こすが、敗訴して流罪となった。
-

久留島通春 (くるしまみちはる)
来島通総の孫。彼の代で姓を久留島と改めた。大坂城、江戸城普請に参加するかたわら、家中の人材刷新、大坂の蔵屋敷設置による財政健全化を成功させた。
-

車斯忠 (くるまつなただ)
佐竹家臣。和田昭為を主君・義重に讒言して追放、義重の側近となる。関ヶ原合戦の際は上杉家に属した。主家転封後、水戸城の奪回を企むが敗れて殺された。
-

黒岩種直 (くろいわたねなお)
安芸家臣。父・越前は、主家滅亡時に主君・国虎の夫人を実家の土佐一条家へ送り届けたのち、国虎の墓前で殉死した。長宗我部家に仕え、中富川合戦で戦死。
-

黒川清実 (くろかわきよざね)
上杉家臣。蒲原郡奥山荘北条(黒川)を領した。上条定憲の乱の際は、はじめ長尾為景に属すが、のち上条方に転じた。乱後に帰参し、郡司不入を認められた。
-

黒川晴氏 (くろかわはるうじ)
大崎家臣。鶴楯城主。黒川家は大崎家の庶流で、応永年間から伊達家に属す。1588年、伊達家の大崎領侵入の際は大崎家に味方し、伊達軍を撃破した。
-

黒沢道家 (くろさわみちいえ)
小野寺家臣。黒沢城主。有屋峠合戦などで活躍した。主家改易後は佐竹家に仕え一揆の鎮圧や新田開発に携わった。大坂の陣では旗頭として従軍し、活躍した。
-

黒田一成 (くろだかずしげ)
黒田八虎の一人。荒木村重に捕らわれた黒田官兵衛を助ける。関ヶ原合戦では石田三成の重臣を討ち取り、のち長政の命で『大坂夏の陣図屏風』も制作した。
-

黒田官兵衛 (くろだかんべえ)
豊臣家臣。主君・秀吉の参謀を務め、秀吉の天下統一に大きく貢献した。しかしその卓抜した戦略的手腕を恐れられ、禄高は豊前中津12万石におさえられた。
-

黒田重隆 (くろだしげたか)
播磨の豪族。備前福岡から播磨姫路に移り住む。「玲珠膏」と名付けた目薬を売って財力を蓄え、子・職隆を小寺家に出仕させるなど、黒田家の土台を作った。
-

黒田忠之 (くろだただゆき)
長政の嫡男。長政は忠之の力量に疑問を抱き、廃嫡を目論んでいたといわれる。のちに家老の栗山大膳と対立して黒田騒動を引き起こすが、改易は免れた。
-

黒田長政 (くろだながまさ)
豊臣家臣。官兵衛孝高の嫡男。九州征伐などで活躍した。関ヶ原合戦では東軍に属し、戦後筑前福岡52万石を領す。以後は徳川幕府への恭順の姿勢を貫いた。
-

黒田秀忠 (くろだひでただ)
上杉家臣。黒滝城主。主君・晴景に対し謀叛を起こすが敗れ、助命を嘆願して許される。しかし、のちに再び叛逆、越後守護・上杉定実の命で自害させられた。
-

黒田職隆 (くろだもとたか)
小寺家臣。姫路城主。播磨の豪族・香山重道を討つ功を立てたため、主君・政職の養女を娶り、家老に就任した。のちに「小寺」姓と「職」の一字を拝領した。
-

桑名吉成 (くわなよしなり)
長宗我部家臣。土佐中村城代を務める。戸次川合戦、浦戸一揆鎮圧などで活躍した。主家改易後は藤堂家に属す。大坂夏の陣の際に旧主・盛親と戦い戦死した。
-

桑山一直 (くわやまかずなお)
徳川家臣。一晴の弟。関ヶ原合戦では本多忠勝に属して大谷吉継と戦い、大坂夏の陣でも活躍し加増を約束されたが、旗本の喧嘩に巻き込まれ、閉門となった。
-

桑山一晴 (くわやまかずはる)
豊臣家臣。祖父・重晴より家督を継ぐ。関ヶ原合戦が起こると、西軍についた熊野水軍・堀内氏善を攻めて城を奪い、東軍に加勢。大和に新領を加増された。
-

桑山重晴 (くわやましげはる)
豊臣家臣。賤ヶ岳合戦では豊臣軍の本陣を守り、勝利に貢献する。のちに豊臣秀長に仕え、和歌山城の城代となって3万石を領した。千利休に茶の湯を学んだ。
-

桑山元晴 (くわやまもとはる)
徳川家臣。重晴の次男。はじめ豊臣秀吉に仕え、朝鮮派兵などに従軍した。関ヶ原合戦の際は東軍に属し、戦後、大和御所2万6千石余を領した。
-

郡司敏良 (ぐんじとしよし)
田村家臣。娘は主君・清顕の娘で伊達政宗に嫁いだ愛の侍女となった。清顕死後の御家騒動では田村顕盛らとともに相馬家方に属し、下枝城の戦いで戦死した。
-

傑山雲勝 (けつざんうんしょう)
上杉家臣・本庄家菩提寺の長楽寺住職。本庄繁長の軍師として、数々の献策を行い、補佐した。上杉家が越後から会津に転封されると、繁長とともに移った。
-

祁答院良重 (けどういんよししげ)
大隈の豪族。岩剣城主。大隈・薩摩の国境で支配地を拡大するが、島津貴久の侵攻を受け、次第に所領を奪われる。岩剣城を落とされた後、殺害される。
-

毛馬内秀範 (けまないひでのり)
南部家臣。南部安信の五男。鹿角侵攻で功を挙げ、信直の厚い信頼を得た。安東家中での淡騒動では、檜山安東家に協力するなど、一定の独立性を保っていた。
-

毛馬内政次 (けまないまさつぐ)
南部家臣。秀範の子。秀範の代で鹿角郡毛馬内を領して、地名を姓とした。信直を支援し、その子・利直にも仕えて厚い信頼を得た。孫の代で無嗣断絶した。
-

毛屋武久 (けやたけひさ)
黒田家臣。近江の出身。柴田勝家など数家を経て、黒田家に仕官。物見に優れ、関ヶ原合戦では徳川家康に「敵は寡勢」と報告し、饅頭を与えられたという。
-

小出秀政 (こいでひでまさ)
豊臣家臣。和泉岸和田3万石を領す。主君・秀吉から秀頼の補佐を頼まれた。関ヶ原合戦では西軍に属すが、次男・秀家が東軍に与したため本領を安堵された。
-

小出三尹 (こいでみつただ)
秀政の四男。母は、豊臣秀吉の母・なかの妹。はじめ豊臣秀頼に仕える。甥・吉英から1万石を分与され和泉陶器初代藩主となる。大坂の陣で徳川方についた。
-

小出吉親 (こいでよしちか)
吉政の次男。兄・吉英に譲られ但馬出石城主となったが、後に兄が出石に再封されたため、新たに丹波園部2万8千石を領した。園部城を築城している。
-

小出吉英 (こいでよしひで)
吉政の嫡男。但馬出石6万石を領し、新たに出石城を築城、有子山城より居城を移した。出石出身の沢庵宗彭に帰依し、その薫陶を受けた。
-

小出吉政 (こいでよしまさ)
豊臣家臣。秀政の嫡男。但馬出石6万石を領す。関ヶ原合戦では西軍に属し、丹後田辺城攻撃に参加した。弟・秀家が東軍に属したため、本領を安堵された。
-

己斐直之 (こいなおゆき)
安芸武田家臣。己斐城主。豊後守と称した。祖は厳島神領衆という。のちに香川光景らとともに主家を離反し、毛利家に属した。厳島合戦では宮尾城を守った。
-

香西元定 (こうざいもとさだ)
細川家臣。香西家は、承久の乱において戦功を立て、讃岐香川・阿野両郡を賜った資村を始祖とする。1508年、三谷城主・三谷景久を攻撃したが、敗れた。
-

香西元成 (こうざいもとなり)
細川家臣。三好長慶が主君・晴元を追放したあと、政権回復を目指し戦う。波多野晴通を援護して松永久秀を破るなど活躍したが、三好家との戦いで戦死した。
-

香西佳清 (こうざいよしきよ)
讃岐の豪族。勝賀城主。居城に籠城して長宗我部元親の讃岐侵攻軍と戦うが天霧城主・香川元景の仲裁で和睦した。病のため失明し「盲目の大将」と呼ばれた。
-

高坂昌信 (こうさかまさのぶ)
武田家臣。武田四名臣の1人。主君・信玄の小姓から侍大将となる。武略・用兵は家中随一といわれ「逃げ弾正」と呼ばれた。「甲陽軍鑑」の原著者と伝わる。
-

香宗我部親秀 (こうそかべちかひで)
土佐の豪族。安芸家との戦いで嫡男・秀義を失い、弟・秀通に家督を譲り隠退。のちに秀通を暗殺して長宗我部国親の三男・親泰を養子に迎え、家督を譲った。
-

香宗我部親泰 (こうそかべちかやす)
長宗我部国親の三男。阿波中富川合戦で十河存保軍を破るなど、兄・元親の片腕として四国統一に貢献した。織田家に使者として赴くなど、外交でも活躍した。
-

香宗我部秀通 (こうそかべひでみち)
土佐の豪族。香宗城を拠点とした香宗我部家は、長宗我部家の圧迫を受け、同盟を結ぼうとする兄・親秀と秀通が対立、秀通は兄の手にかかって謀殺された。
-

河野晴通 (こうのはるみち)
伊予の戦国大名。湯築城主。河野家の庶流・予州家の出身。河野通直の娘婿・来島通康との家督争いに勝利し、河野宗家を継いで通政と改名するが、早世した。
-

河野通直 (こうのみちなお)
伊予の戦国大名。湯築城主。家臣の謀叛や他国からの侵攻が相次ぎ、対策に苦慮した。娘婿・来島通康に家督を譲ろうとするが家臣に反対され、内紛を招いた。
-

河野通直 (こうのみちなお)
伊予の戦国大名。湯築城主。庶流・池原河野家の出身。長宗我部元親に敗れて家臣となり、豊臣秀吉の四国征伐軍と戦い敗北。改易されたため安芸に移住した。
-

河野通宣 (こうのみちのぶ)
伊予の戦国大名。湯築城主。兄・晴通が早世したため、家督を継いだ。大野家などの家臣の謀叛や、毛利家など他国からの侵攻が相次ぎ、その対応に苦慮した。
-

神森出雲 (こうのもりいずも)
本山家臣。神森城主。長宗我部元親に攻められると籠城するが、水の手を攻められて落城、自害した。白米で馬を洗ってみせ、水の手攻めに対抗したという。
-

国府盛種 (こうもりたね)
伊勢の豪族。国府城主。国府家は関家の庶流。織田信雄に属す。小牧長久手合戦に従軍し、加賀井城で戦死したとも、蒲生氏郷軍に敗れ尾張に逃れたともいう。
-

小浦一守 (こうらかずもり)
畠山家臣。池田城主。上杉謙信の能登侵攻軍に降る。謙信の死後は佐々成政に属し、成政の肥後移封にも従った。成政の死後は能登羽咋郡に移住し、隠棲した。
-

高力清長 (こうりききよなが)
徳川家臣。駿府時代から家康に従う古参の将。多くの激戦に参加したが敵に対しても寛大で、清廉実直に働く様は「仏高力」と称された。関ヶ原合戦後に隠居。
-

高力忠房 (こうりきただふさ)
徳川家臣。祖父・清長から家督を譲られ武蔵岩付藩主となる。全焼した岩付城の復興に功があった。島原の乱後、島原藩主となり、島原復興を見事成し遂げた。
-

桑折貞長 (こおりさだなが)
伊達家臣。播磨守と称す。主君・晴宗が奥州探題となった際、牧野久仲とともに奥州守護代となった。これに対して鷹や馬、および黄金30両などを進上した。
-

桑折宗長 (こおりむねなが)
伊達家臣。父・景長が伊達稙宗の子を嫡子としたため出家するが、のち還俗して家督を継ぐ。輝宗、政宗の二代に重用され、軍政両面で多大な功績を残した。
-

郡宗保 (こおりむねやす)
豊臣家臣。馬廻を務めた。関ヶ原合戦では西軍に属し大津城攻撃に参加。主君・秀頼の近侍として諸大名との交渉を担当した。大坂城落城時に、秀頼に殉じた。
-

国分盛顕 (こくぶんもりあき)
陸奥の豪族。盛氏の子。国分家は源頼朝の奥州征伐に従った千葉常胤の五男・胤通を祖とする。子がなかったため、伊達晴宗の十男・盛重を養子として迎えた。
-

国分盛氏 (こくぶんもりうじ)
陸奥の豪族。能登守と称した。1189年、源頼朝が陸奥平泉の藤原家を滅ぼした際に、焼け落ちて名前だけが残っていた国分尼寺を、1570年に再建した。
-

小島職鎮 (こじまもとしげ)
神保家臣。日宮城主。主君・長職とともに上杉家に属した。長職の死後は主家の実権を握る。のち越中に帰還した神保長住を幽閉し、主家滅亡の原因を作った。
-

小島弥太郎 (こじまやたろう)
上杉家臣。幼少から側近として主君・謙信に仕えた。川中島合戦には旗本として従軍。剛力無双の豪傑で「鬼小島」と呼ばれて恐れられ、数々の伝説を残した。
-

小田辺勝成 (こたべかつなり)
二本松畠山家臣。騎戦に長け、単騎で敵陣を破ること多く、乗込大学の異名をとる。主家滅亡後は浪人生活を経て伊達家に仕え、武頭役として3百石を領した。
-

児玉就方 (こだまなりかた)
毛利家臣。兄・就忠の推挙により毛利家に仕える。陶家の勢力が安芸から駆逐されたあと草津城主となった。毛利水軍を率い、北九州や山陰の海上に転戦した。
-

児玉就忠 (こだまなりただ)
毛利家臣。主君・元就の家督相続直後より側近として活躍し、のちに五奉行の一員となった。「視野も広く人ざわりもよく、事務練達の者」と元就に評された。
-

木造雄利 (こづくりかつとし)
織田家臣。木造俊茂の子。滝川一益の娘を娶り滝川姓を名乗る。小牧長久手合戦後は軍師格として豊臣秀吉に仕えた。関ヶ原合戦では西軍に属し、所領を失う。
-

木造俊茂 (こづくりとししげ)
北畠家臣。木造城主。1526年、正四位下・参議となる。のち従三位に昇るが1533年に出家した。1528年から3年がかりで居城を整備したという。
-

木造具政 (こづくりともまさ)
北畠家臣。北畠晴具の子。木造家を継いだ。兄・具教に背いて織田信長の軍に降る。その後は織田信雄に属し、小牧長久手合戦では蒲生氏郷軍と戦うが敗れた。
-

木造具康 (こづくりともやす)
北畠家臣。木造城主。俊茂の子。木造家は北畠顕俊(伊勢国司初代・顕能の子)を祖とする北畠家庶流。他の一門と異なり、宗家と同等の官位に任官していた。
-

木造長正 (こづくりながまさ)
織田家臣。木造城主。具政の子。主君・信雄の改易後は織田秀信の家老となる。関ヶ原合戦では秀信に東軍加担を説くが失敗した。戦後は福島正則に仕えた。
-

籠手田安経 (こてだやすつね)
松浦家臣。生月島山田邑を領す。南蛮貿易を望む主君・隆信の代理で受洗。宮の前事件のあと、貿易や布教の中心は長崎に移るが、引き続き信仰を守り続けた。
-

籠手田安昌 (こてだやすまさ)
松浦家臣。主君・興信の死後、主家で家督争いが起きた際、反対派を抑えて隆信を擁立。以後、隆信の重臣として活躍した。のちに子・安経とともに受洗した。
-

小寺則職 (こでらのりもと)
赤松家臣。御着城主。主君・義村の命で浦上村宗の支城・岩屋城を攻めるが敗れる。この直後、義村は村宗に殺された。のちに村宗を討ち、主君の敵をとった。
-

小寺政職 (こでらまさもと)
赤松家臣。御着城主。則職の子。別所家と親交を結ぶ。のち織田家に属すが、別所家とともに荒木村重の謀叛に同調。羽柴秀吉軍の攻撃を受け敗北、逃亡した。
-

後藤賢豊 (ごとうかたとよ)
六角家臣。進藤家とともに「六角家の両藤」と称された。主君・義賢親子が上洛した際は警護役を務めた。いわゆる観音寺騒動において主君・義治に殺された。
-

後藤勝国 (ごとうかつくに)
美作の豪族。三星城主。後藤家は代々、塩湯郷地頭職を務めた家柄。父・勝政が立石家を攻めて戦死したため家督を継ぎ立石家を滅ぼして東美作に覇を唱えた。
-

後藤勝元 (ごとうかつもと)
美作の豪族。三星城主。勝国の子。近隣豪族を支配下に置き、また尼子家や浦上家と友好を結んで、後藤家を隆盛に導いた。のち宇喜多直家に敗れて自害した。
-

後藤寿庵 (ごとうじゅあん)
葛西家臣。主家滅亡後、五島列島でキリシタンとなり、姓を五島とする。支倉常長を介し政宗に仕えて鉄砲隊を率いた。また大規模用水路「寿庵堰」を造った。
-

後藤高治 (ごとうたかはる)
六角家臣。賢豊の次男。観音寺騒動で父が死去したのち、家督を継ぐ。進藤家と並ぶ「両藤」として義治の重臣となったが、織田信長の上洛軍に敗れ降伏した。
-

五藤為重 (ごとうためしげ)
山内家臣。山内一豊に従って、ほとんどの合戦に出陣。天正大地震では一豊の妻を救出した。その後も小田原征伐、関ヶ原合戦などで武功を立てた。
-

後藤信康 (ごとうのぶやす)
伊達家臣。湯目重弘の子で、後藤家を継ぐ。檜原城を守り、蘆名家に備えた。知勇に秀で、合戦では必ず黄色の母衣を用いたため「黄後藤」の異名をとった。
-

後藤又兵衛 (ごとうまたべえ)
黒田家臣。侍大将を務めるが、謀叛の嫌疑により浪人。のち豊臣秀頼に招かれ、大坂城に入る。人望を集め、徳川軍相手に奮戦するが、大坂夏の陣で戦死した。
-

後藤元政 (ごとうもとまさ)
美作の豪族。三星城主。勝元の子。父の隠居により、家督を継ぐ。父の後見を受けて諸政策を行った。のちに宇喜多直家と争うが敗北し、城を捨てて逃亡した。
-

小西行景 (こにしゆきかげ)
豊臣家臣。行長の甥。キリスト教に帰依した。関ヶ原合戦では行長の居城・肥後宇土城を守備して加藤清正軍と戦うが、西軍の敗戦を聞いて開城し、自害した。
-

小西行長 (こにしゆきなが)
豊臣家臣。堺の豪商・小西隆佐の子。朝鮮派兵の際は先鋒を務めた。関ヶ原合戦では西軍に属して戦うが敗れ、斬首された。熱心なキリスト教信者として有名。
-

木幡高清 (こばたたかきよ)
相馬家臣。駿河と称した。相馬家五代に仕えた重臣。検地代官や利胤の傅役も務めた。「相馬旧記」を編纂する際には、昔の出来事を詳しく語ったという。
-

木幡継清 (こばたつぐきよ)
相馬家臣。大膳、因幡と称した。盛胤・義胤・利胤と相馬家3代に仕えた老臣。各地の合戦に従軍し、たびたび軍功を立て活躍した。
-

小早川興景 (こばやかわおきかげ)
小早川家臣。竹原小早川家の当主。毛利興元の娘を娶った。武田家の居城・佐東銀山城を攻撃中に死去し、子がなかったため、元就の三男・隆景が跡を継いだ。
-

小早川繁平 (こばやかわしげひら)
安芸の豪族。正平の子。父の死後家督を継ぐが、3歳の時に失明した。軍事指揮を執ることが困難なため、毛利元就の三男・隆景を養子として迎え、剃髪した。
-

小早川隆景 (こばやかわたかかげ)
毛利元就の三男。安芸の豪族・小早川家を継ぎ、山陽地方の攻略にあたる。本能寺の変後は毛利家の存続をはかって豊臣秀吉に接近し、五大老の1人となった。
-

小早川秀秋 (こばやかわひであき)
豊臣家臣。木下家定の子。豊臣秀吉の命により小早川隆景の養子となる。関ヶ原合戦では東軍に寝返り、東軍勝利に大きく貢献したが、その2年後に急死した。
-

小早川正平 (こばやかわまさひら)
安芸の豪族。大内家に属した。のち尼子方への転身をはかるが、大内家に居城・高山城を占拠されて失敗した。大内家の出雲遠征に従軍し、退却中に戦死した。
-

小林良道 (こばやしよしみち)
松前家臣。蝦夷の豪族。アイヌの大酋長コシャマインに攻められて死んだ忠苔館主・小林良景の曾孫。1543年、若狭武田家に使者として派遣された。
-

小堀遠州 (こぼりえんしゅう)
豊臣家臣。茶の湯を古田重然に学び、近世の茶道芸術を大成した。のちに徳川家康に仕えて普請奉行を担当し、公武作事奉行の第一人者となる。
-

駒井高白斎 (こまいこうはくさい)
武田家臣。信虎の代から重臣として仕え信濃調略に尽力。信虎追放後も晴信の政務の内外両面を支える。家中の事跡を連ねた『高白斎記』を書き残したという。
-

駒井重勝 (こまいしげかつ)
豊臣家臣。六角家臣であったが主家滅亡後に秀吉配下になる。秀次の重臣を経て秀吉直臣へ抜擢、『駒井日記』を記す。関ヶ原にも西軍として参加している。
-

小牧源太 (こまきげんた)
斎藤家臣。美濃屈指の槍の使い手と言われる。長良川合戦では、義龍側につき道三の首級を取る。晒された道三の首を盗み出し、手厚く葬ったとも伝えられる。
-

小牧根利政 (こまきねとしまさ)
豊臣・徳川家臣。陸奥岩城の地侍をよく掌握していたため、3千石を与えられ、代官となる。関ヶ原合戦後は徳川家に仕え、平藩主となった鳥居忠政に仕えた。
-

小間常光 (こまつねみつ)
椎名家臣。小間家は椎名家重臣の家柄という。神保家や領内の寺社、能登畠山家に書状を出すなど、おもに外交に手腕を発揮した。主君・長常の偏諱を受けた。
-

小梁川宗朝 (こやながわむねとも)
伊達家臣。天文の大乱に際しては稙宗側に属し、西山城に幽閉されていた稙宗を救出するなど活躍した。乱の終息後も稙宗に近侍し、稙宗の死後、殉死した。
-

小梁川宗秀 (こやながわむねひで)
伊達家臣。宗朝の子。天文の大乱の際は父とともに稙宗側に属した。中野宗時の謀叛の際は追討軍の先鋒を務め、小松城攻めで戦死した。文武に秀でたという。
-

近藤政成 (こんどうまさなり)
堀家臣。堀秀政の四男。堀家重臣・近藤重勝の養子となり後を継ぐ。堀家改易後独立し、近藤藩を立藩した。大坂の陣では、永井直勝に属し活躍した。
-

近藤康用 (こんどうやすもち)
徳川家臣。井伊谷三人衆の一人。家康の遠江攻略に際し、懐柔され今川家から離反。戦傷のため歩行さえ困難であったが武田家との戦いにも功があったという。
-

近藤義武 (こんどうよしたけ)
松前藩士。袮保田館主・近藤季常の末裔という。公卿・花山院忠長が蝦夷に配流された際は、接待役を務めた。大坂夏の陣では主君・慶広に従って出陣した。
-

西園寺公広 (さいおんじきんひろ)
伊予の豪族。黒瀬城主。叔父・実充の養子となり家督を継ぐ。のちに豊臣秀吉の四国征伐軍に降るが、西園寺旧臣の叛乱を警戒した戸田勝隆により謀殺された。
-

西園寺実充 (さいおんじさねみつ)
伊予の豪族。黒瀬城主。宇都宮豊綱との戦いで嫡子・公高を失い、甥・公広を養子に迎えた。文武に優れ、上洛した際には三条公朝邸での和歌会に列席した。
-

西園寺宣久 (さいおんじのぶひさ)
西園寺家臣。公広の弟。板島城主。西園寺十五将の1人に数えられ、板島殿と呼ばれた。伊勢神宮に参拝した際、紀行日記である『伊勢参宮海陸記』を著した。
-

佐伯惟定 (さいきこれさだ)
大友家臣。豊後栂牟礼城主。惟教の孫。島津家久の豊後侵攻の際は居城に籠城して島津軍を撃退し、豊臣秀吉に功を賞された。主家改易後は藤堂高虎に仕えた。
-

佐伯惟教 (さいきこれのり)
大友家臣。二階崩れの変の際は、主君・宗麟を奉じて変を鎮圧した。一時西園寺家に仕えるが、のち帰参。宗麟の命で日向に進出するが、耳川合戦で戦死した。
-

西郷純堯 (さいごうすみたか)
有馬家臣。純久の子。熱心な仏教徒で、切支丹となった従兄弟・大村純忠とたびたび戦った。「詭計、策略、欺瞞の点では第一人者」とフロイスに酷評された。
-

西郷純久 (さいごうすみひさ)
有馬家臣。高城城主。有馬晴純の弟で、西郷家を継ぐ。武雄城主を務める姉婿・後藤純明と戦うなど、兄を助けて各地で活躍した。娘は大村純忠などに嫁いだ。
-

斎藤定信 (さいとうさだのぶ)
長尾家臣。昌信の子。下野守と称す。1510年、苅羽郡原田竹町に関する文書を善照寺増珎に渡し、また苅羽郡竹町の名田について、証状を作成したという。
-

斎藤龍興 (さいとうたつおき)
美濃の戦国大名。義龍の嫡男。父の死後家督を継ぐ。美濃三人衆に背かれ、織田信長に敗れて追放された。その後は朝倉家に属し、越前刀禰坂合戦で戦死した。
-

斎藤道三 (さいとうどうさん)
「蝮」の異名をとった美濃の戦国大名。僧から油商人に転身、次いで美濃守護・土岐頼芸に仕官、頼芸を追放して国主となった。のちに子・義龍と戦い、敗死。
-

斎藤利茂 (さいとうとししげ)
美濃国守護・土岐頼武より守護代に任じられる。旧主を裏切って頼芸に属し守護代に復帰するも、斎藤道三が台頭すると頼芸とともに国を追われたという。
-

斎藤利三 (さいとうとしみつ)
斎藤家臣。主家滅亡後は明智光秀の家老となる。本能寺の変や山崎合戦に従軍し敗戦後に捕らえられ、斬首された。娘は将軍・徳川家光の乳母を務めた春日局。
-

斎藤利良 (さいとうとしよし)
土岐家臣。祖父・妙純と父・利親が六角家との戦いで戦死したため家督を継ぎ、美濃守護代となった。のちに斎藤道三によって主君・政頼とともに追放された。
-

斉藤朝信 (さいとうとものぶ)
上杉家臣。川中島合戦や唐沢山城攻めなどで活躍し「越後の鐘馗」の異名をとった。御館の乱では上杉景勝に属す。私欲なく、行政にも優れた手腕を発揮した。
-

斎藤福 (さいとうふく)
斎藤道三の娘。関ヶ原の戦いにおいて、小早川秀秋を説得し東軍に寝返らせる。のち徳川家光の乳母となり、春日局と称され、大奥で絶大な権勢を築いた。
-

斎藤義龍 (さいとうよしたつ)
美濃の戦国大名。道三の子。美濃守護・土岐頼芸の子ともいう。家督を巡って父と対立、父を討って美濃国主となるが急死した。身長6尺5寸の巨漢と伝わる。
-

斎村政広 (さいむらまさひろ)
豊臣家臣。赤松政秀の子。藤原惺窩により漢学を学んだ。関ヶ原合戦で西軍から東軍に寝返るが、因幡鳥取城下を焼き払ったため、徳川家康の命により自害した。
-

三枝昌貞 (さえぐさまささだ)
武田家臣。駿河の花沢城攻めで一番槍の功名を立て、信玄から感状を受けた。のちに山県昌景の猶子となる。長篠の合戦で織田軍の奇襲を受け、戦死した。
-

酒井家次 (さかいいえつぐ)
徳川家臣。忠次の嫡男。主君・家康の偏諱を受ける。家康の関東入国の際に臼井城主となった。大坂夏の陣で活躍し、その功により越後高田10万石を領した。
-

酒井重忠 (さかいしげただ)
徳川家臣。幕府大老・忠世の父。伊賀越えを行った家康を船で救うなど数々の功を上げ、武蔵川越1万石の大名となる。関ヶ原の戦いでは大津城を守った。
-

酒井忠勝 (さかいただかつ)
徳川家臣。関ヶ原合戦で初陣。家康・秀忠・家光・家綱と将軍4代に仕える。老中や大老を務めて内政・外交全般に活躍した。家綱に「名臣第一」と評された。
-

酒井忠次 (さかいただつぐ)
徳川家臣。徳川四天王筆頭。主君・家康の養育係を務めた。家康成人後は東三河衆を率いて各地を転戦し活躍。その才覚は織田信長や豊臣秀吉にも称賛された。
-

酒井忠利 (さかいただとし)
徳川家臣。小牧長久手合戦で活躍。関ヶ原合戦では徳川秀忠西が立って上田城攻めに加わり、駿河田中藩初代藩主となる。大坂の陣では江戸城留守居役を務めた。
-

酒井忠世 (さかいただよ)
徳川家臣。大坂冬・夏の陣では全軍の参謀役を務めた。のちに土井利勝・青山忠俊とともに3代将軍家光の教育係に就任し、幕府の中枢を担う。老中も務めた。
-

酒井敏房 (さかいとしふさ)
里見家臣。東金城主。正木時茂や土岐為頼とともに里見家中で勇名を馳せる。第一次国府台合戦の際には殿軍を務めた。のちに主家を離反し、北条家に属した。
-

酒井豊数 (さかいとよかず)
波多野家臣。丹波丹後の国人で、和泉守を称した。波多野家との抗争に敗れ、その家臣となる。重用され、主君・元秀に代わって書状の発給などを行った。
-

坂井成政 (さかいなりまさ)
徳川家臣。山岡景友らの口利きで会津征伐に向かう徳川家康の面識を得る。関ヶ原合戦で功を立て近江に所領を与えられた。大坂の陣後は旗本に列された。
-

酒井広種 (さかいひろたね)
松前家臣。父の代に蝦夷に移住し、松前公広に小姓として仕えた。のちに町奉行となる。福山館の火事から公広を救出したが、その時の火傷が元で死去した。
-

酒井政辰 (さかいまさとき)
北条家臣。東金城主。敏房の子。豊臣秀吉の小田原征伐の際は居城に籠城した。主家滅亡後は居城を退去し、隠退した。子孫は徳川家に旗本として仕えた。
-

坂井政尚 (さかいまさひさ)
織田家臣。信長入京後、柴田勝家、森可成らと京の政務に携わる。姉川合戦では先鋒を務めて勝利に貢献。のち、浅井方の近江堅田攻めで激戦の末に討死した。
-

榊原忠次 (さかきばらただつぐ)
徳川家臣。大須賀忠政の長男。榊原康政の孫だったため、榊原家を継ぐ。井伊直孝死後、後を継いで幕府の大政参与となる。領内では治水や新田開発に励んだ。
-

榊原康勝 (さかきばらやすかつ)
徳川家臣。康政の三男。長兄・忠政は他家の養子、次兄・忠長は早世のため、父の死後上野館林10万石を継いだ。大坂冬の陣では佐竹軍の窮地を救っている。
-

榊原康政 (さかきばらやすまさ)
徳川家臣。徳川四天王の1人。「無」の旗を掲げて戦場を疾駆し、各地で抜群の功を立てた。晩年、「老臣権を争うは亡国の兆し」と老中への就任を辞退した。
-

相良武任 (さがらたけとう)
大内家臣。有職故実に通じ、主君・義隆の信頼を受けた。のち陶晴賢と対立し出奔するが、杉興運により抑留される。晴賢の謀叛の際、筑前花尾城で殺された。
-

相良晴広 (さがらはるひろ)
肥後の戦国大名。古麓城主。上村頼興の子。相良義滋の養子となり家督を継ぐ。対明貿易を行う。また分国法「相良氏法度」を制定し、支配力の強化に努めた。
-

相良治頼 (さがらはるより)
相良家臣。肥後岡城主。器量才覚に優れ家中の信望を集めていた。謀叛の風聞により出奔、主家と戦うが敗れ、流浪中に病死した。のちに祟りがあったという。
-

相良義滋 (さがらよししげ)
肥後の戦国大名。菊池義武らと反大友連合を形成し、大友家と戦う。また謀叛疑惑のあった家臣を粛清、領内で銀を生産するなど、相良家支配の基盤を作った。
-

相良義陽 (さがらよしひ)
肥後の戦国大名。人吉城主。晴広の子。祖父・上村頼興の後見を受ける。2度の内乱を乗り切って領国を拡大するが島津家に降り、阿蘇家との戦いで戦死した。
-

相良頼房 (さがらよりふさ)
肥後人吉藩主。義陽の次男。兄・忠房の夭逝により家督を継ぐ。豊臣秀吉の九州征伐軍に降伏した。関ヶ原合戦では美濃大垣城で東軍に内応し、所領を保った。
-

佐川信利 (さがわのぶとし)
松浦家臣。朝鮮派兵では渡海。一時福島正則に属すが、正則の改易後は松浦家に戻る。外国商館との折衝や財政整理の断行など、内政や外交に辣腕を振るった。
-

佐久間勝之 (さくまかつゆき)
織田・北条・蒲生家を経たのち関ヶ原で東軍につき徳川家臣に。上野東照宮・京南禅寺・尾張熱田神宮に寄進した大灯篭が「日本三大灯篭」として現世に残る。
-

佐久間信栄 (さくまのぶひで)
織田家臣。信盛の子。父とともに追放されるが、父の死後、許されて織田信雄に仕えた。信雄の改易後は豊臣秀吉に仕えて御咄衆となった。茶人としても著名。
-

佐久間信盛 (さくまのぶもり)
織田家臣。各地の合戦で活躍し「のき佐久間」の異名をとる。石山本願寺攻めの総大将を務めるが、本願寺の退去後、怠慢不手際の叱責を受け、追放された。
-

佐久間盛重 (さくまもりしげ)
織田家臣。織田信勝の家老。信勝と信長が対立すると信長に味方し、戦功を上げる。桶狭間の戦いでは丸根砦を守るが、徳川家康の攻勢を受け、戦死した。
-

佐久間盛政 (さくまもりまさ)
柴田家臣。盛次の嫡男。叔父・勝家に仕える。「鬼玄蕃」の異名をとった猛将。賤ヶ岳合戦で深入りし、柴田軍の敗因を作った。戦後、捕らえられ斬首された。
-

佐久間安政 (さくまやすまさ)
柴田家臣。盛次の三男。はじめ保田姓を称した。賤ヶ岳合戦後は織田信雄に仕える。その後は北条家、蒲生家を経て徳川家に仕え、信濃飯山3万石を領した。
-

桜庭直綱 (さくらばなおつな)
南部家臣。南部四天王の一人。岩崎一揆鎮圧などに活躍。親族の北信景が豊臣家に加担して大坂城に入ると、家系図を偽造して敗戦後の処分を免れたとされる。
-

鮭延貞綱 (さけのべさだつな)
小野寺家臣。本姓佐々木。1535年に鮭延城を築く。1546年には鮭川のほとりに堂を建て、先祖より伝わる慈覚大師作の聖観音像を祀った(庭月観音)。
-

鮭延秀綱 (さけのべひでつな)
小野寺家臣。鮭延城主。貞綱の子。最上義光との合戦に敗れ、家臣となる。仙北地方で起こった一揆の鎮圧や、最上領に侵入した上杉軍との戦いで功を立てた。
-

佐々木小次郎 (ささきこじろう)
別名は巌流。武者修行の末、「燕返し」の剣法を創案する。増田長盛に仕えようとしたが豊臣秀吉に許されなかった。巌流島で宮本武蔵と試合をし、敗死する。
-

佐世清宗 (させきよむね)
尼子家臣。次席家老を務めた。おもに内政面で活躍したが、毛利元就の居城・吉田郡山城攻撃にも従軍した。元就の出雲侵攻軍に最後まで抵抗するが降伏した。
-

佐瀬種常 (させたねつね)
蘆名家臣。佐瀬家は、蘆名四天の宿老の一。耶麻郡中田付で六斎市を開いていたが、中田付では不便だとして、小田付村に六斎市を移した。摺上原合戦で戦死。
-

佐世元嘉 (させもとよし)
尼子家臣。清宗の子。父とともに毛利元就の出雲侵攻軍に降る。以後は毛利家に仕え、朝鮮派兵や関ヶ原合戦の際には主家の居城・広島城の留守居役を務めた。
-

佐竹親直 (さたけちかなお)
長宗我部家臣。上ノ加江城主。父・義秀が戦死したあと家督を継ぐ。長宗我部元親の娘を妻とした。大坂の陣では旧主・盛親に従って戦い、夏の陣で戦死した。
-

佐竹義昭 (さたけよしあき)
佐竹家17代当主。義篤の嫡男。南陸奥の白河結城家を降し、常陸の覇権を巡って小田家と争った。関東管領・上杉憲政が庇護を求めた際は、これを拒否した。
-

佐竹義篤 (さたけよしあつ)
佐竹家16代当主。実弟・義元と家督を争い、たびたび合戦を行うが、部垂城の合戦で義元を討って支配権を確立。佐竹一門による領国支配体制を成立させた。
-

佐竹義堅 (さたけよしかた)
佐竹家臣。東家・政義の嫡男。若年の宗家・義昭に仕え、北家・義廉や南家・義里らと交代で佐竹家の家政を執行した。1566年には那須家と戦い、敗れた。
-

佐竹義廉 (さたけよしかど)
佐竹家臣。北家・義信の次男。兄・義住の戦死により家督を継ぐ。若年の宗家・義昭に仕え、東家・義堅や南家・義里らと交代で佐竹家の家政を執行した。
-

佐竹義里 (さたけよしさと)
常陸佐竹氏一族。義舜の四男。南殿と呼ばれ、佐竹氏の家政を司った。北家・義廉や東家・義堅と共に宗家を補佐し、特に外交面で重要な役割を果たした。
-

佐竹義重 (さたけよししげ)
佐竹家18代当主。義昭の嫡男。父の遺志を継ぎ、常陸の統一に成功する。北条家と伊達家を敵に回し、陣頭で自ら采配を振るう姿は「鬼義重」と恐れられた。
-

佐竹義斯 (さたけよしつな)
佐竹家臣。北家・義廉の嫡男。常陸南部方面の総指揮を執り、江戸家などの有力国人の指南にあたった。また、上杉家に書状を発するなど外交活動も行った。
-

佐竹義宣 (さたけよしのぶ)
佐竹家19代当主。義重の嫡男。父に劣らぬ猛将ぶりで知られた。関ヶ原合戦では西軍に属す決意を固くし、徳川家康から「今の世に稀な律儀者」と評された。
-

佐竹義憲 (さたけよしのり)
佐竹家臣。北家・義斯の嫡男。義重の三男・貞隆の岩城家入嗣に随行、植田城に入り岩城家の家政を執行した。主家が出羽秋田に転封された際、これに従った。
-

佐竹義久 (さたけよしひさ)
佐竹家臣。東家・義堅の次男。南陸奥方面支配の総指揮を執り、内政、軍事、外交などに幅広い活躍を見せた。石田三成を通じて豊臣秀吉とも親交を結んだ。
-

佐竹義昌 (さたけよしまさ)
紀州の豪族。石山合戦で鈴木重秀と共に本願寺家に与し、織田軍を翻弄して武名を轟かせる。雑賀で内紛が起こった際、窮地に陥った重秀を救った。
-

佐田鎮綱 (さだしげつな)
大友家臣。隆居の子。宇佐郡衆を率いて各地の合戦に従軍した。耳川合戦で主家が大敗したあと、主家を離反する国人が続出する中、引き続き大友家に仕えた。
-

佐田隆居 (さだたかおき)
大内家臣。宇佐郡代を務めた。主家滅亡後は大友家に属し、宇佐郡衆の中核として活躍した。安心院麟生が大友家に背いた際は、本領安堵を条件に帰順させた。
-

佐多忠増 (さたただます)
島津家臣。耳川の戦いを始め多くの合戦で一番槍の戦功を立てる。のち豊臣秀吉からの要請を受けて小田原にも参陣、忍城攻略に当たる石田三成らを助けた。
-

佐々成政 (さっさなりまさ)
織田家臣。柴田勝家に属して北陸の攻略に貢献する。本能寺の変後、羽柴秀吉と対立するが、敗れて降伏。転封先・肥後の領国経営に失敗し自害を命じられた。
-

佐藤堅忠 (さとうかたただ)
美濃の国人。斎藤家に仕えた佐藤忠能と同族で、佐藤信則の子。のち豊臣家に仕えて伏見城の普請奉行を務め、徳川家に移ってからは駿府城築城にも携わった。
-

佐藤為信 (さとうためのぶ)
相馬家臣。好信の子。小斎城主。伊達家との合戦の際、援軍に来た郡左馬助を討ち、父の敵をとる。直後に伊達家に属した。のちに佐沼の戦いで戦死した。
-

佐藤好信 (さとうよしのぶ)
相馬家臣。佐藤家はもと岩城家臣であったが、好信の代に相馬家に属す。軍奉行を務めたが、郡左馬助の讒言により領地を没収され、失意のうちに病死した。
-

里見忠義 (さとみただよし)
安房館山藩主。義康の嫡男。大久保忠隣の孫娘を娶る。忠隣失脚に連座、伯耆倉吉に配流された。「南総里見八犬伝」は忠義に殉じた8名の臣がモデルという。
-

里見義重 (さとみよししげ)
義弘の嫡男。幼名を梅王丸。里見家の家督相続問題から、叔父である義頼に追われ、強制的に出家させられた。のちに一時還俗し、義重を名乗ったとされる。
-

里見義堯 (さとみよしたか)
房総の戦国大名。父・実堯を殺した従兄弟・義豊を討ち、当主となる。国府台合戦では北条氏康に敗れたが、その後も房総に勢力を広げ、北条家と戦い続けた。
-

里見義弘 (さとみよしひろ)
房総の戦国大名。義堯の長男。上杉謙信と結んで北条家と争う。国府台合戦では北条軍に敗れたが、のちに勢力を回復した。父の死後、北条家と和議を結んだ。
-

里見義康 (さとみよしやす)
房総の戦国大名。義頼の子。豊臣秀吉の小田原征伐に遅参したため、安房1国のみを所領安堵された。のちに館山城を築く。関ヶ原合戦では東軍に属した。
-

里見義頼 (さとみよしより)
房総の戦国大名。義堯の次男。里見梅王丸(兄・義弘の子)に出家を強要し、家督を継ぐ。この一件に憤激し謀叛を起こした正木憲時を討ち、上総を平定した。
-

真田大助 (さなだだいすけ)
幸村の子。父の蟄居先・紀伊九度山で生まれた。父とともに大坂城へ入り、真田丸に出張って奮戦した。夏の陣では城内にあり、落城時に豊臣秀頼に殉じた。
-

真田信勝 (さなだのぶかつ)
昌幸の四男。通称・左馬助。徳川家臣の牧野康成の娘を娶る。徳川幕府の旗本。徳川秀忠に従って京に滞在中、戸田勝興と刃傷沙汰に及び、逃亡した。
-

真田信尹 (さなだのぶただ)
真田家臣。幸隆の子。昌幸の弟。北条綱成の黄八幡旗を奪うなど功を立てる。武田滅亡後は、主を次々と変えるが、大坂の陣以降は徳川家に仕えた。
-

真田信綱 (さなだのぶつな)
武田家臣。幸隆の長男。父の隠居後、信州先方衆の1人として各地を転戦、勇名を馳せる。長篠合戦では3尺3寸の大刀を振るって奮戦するが、銃弾に倒れた。
-

真田信政 (さなだのぶまさ)
信之の次男。兄・信吉とともに大坂の陣に参加、毛利勝永と戦うが敗れた。兄の死後沼田城主となる。隠居した父のあとを受け、信濃松代藩主となった。
-

真田信之 (さなだのぶゆき)
昌幸の長男。徳川家臣・本多忠勝の娘を娶った縁から、関ヶ原河川では父や弟と別れて東軍に属す。その後も徳川家に忠節を尽くし、真田家の存続に尽力した。
-

真田信吉 (さなだのぶよし)
信之の長男。大坂の陣に参加し、毛利勝永と戦うが敗れる。戦後上野沼田3万石を領すが父に先立ち病死。遺領は弟の信政と信吉の次男・信利に分割された。
-

真田昌輝 (さなだまさてる)
真田幸隆の次男。兄・信綱と共に各地の合戦で活躍。小田原城の攻防戦では、北条氏照を破る。その最期は長篠の合戦で信綱と共に戦死をとげた。
-

真田昌幸 (さなだまさゆき)
幸隆の三男。「表裏比興の者」と豊臣秀吉に評された稀代の謀将。関ヶ原へ行軍途中の徳川秀忠軍3万8千を数千の兵で翻弄し、秀忠軍を信濃に釘付けにした。
-

真田幸隆 (さなだゆきたか)
武田家臣。信州先方衆。主君・信玄が攻略出来なかった信濃砥石城を謀略で落城させ、知略は信玄に勝ると賞された。以後、信玄の参謀の1人として活躍する。
-

真田幸村 (さなだゆきむら)
昌幸の次男。蟄居先の紀伊九度山から大坂城に入り、大坂の陣で寡兵ながらも徳川の大軍を相手に奮戦した。その戦いぶりは「真田日本一の兵」と称賛された。
-

佐野豊綱 (さのとよつな)
佐野家14代当主。唐沢山城主。泰綱の嫡男。隼人佐を称した。祖先にならって古河公方・足利家に属し、有力豪族として山内・扇谷両上杉家と戦い続けた。
-

佐野信吉 (さののぶよし)
豊臣家臣。富田一白の子。佐野房綱の隠居により下野唐沢山城主となる。関ヶ原合戦では東軍に属して本領安堵されるがのち兄・富田信高に連座し改易された。
-

佐野秀綱 (さのひでつな)
佐野家12代当主。越前守と称す。居城の唐沢山城を大幅に修築・拡大した。佐野家は藤原秀郷の後裔・足利基綱が佐野庄に住み、地名を姓としたのに始まる。
-

佐野弘綱 (さのひろつな)
小弓公方足利家臣。主君・義明の奏者を務めた。第一次国府台合戦で敗れ、義明が討死すると、義明の末子・頼純を連れて落ちのび、里見義堯を頼った。
-

佐野房綱 (さのふさつな)
佐野家臣。昌綱の子。豊綱の子とも。佐野宗綱の死後、北条氏忠が家督を継いだため、豊臣秀吉に仕えた。天徳寺了伯と呼ばれ、剣術の達人であったという。
-

佐野昌綱 (さのまさつな)
佐野家15代当主。唐沢山城主。豊綱の嫡男。古河公方・足利家に従って河越合戦に参陣するが敗北。以後は北条家に従い、上杉謙信の攻撃をたびたび受けた。
-

佐野宗綱 (さのむねつな)
佐野家16代当主。昌綱の嫡男。佐竹家と結んで北条家に対抗。また軍事・経済両面の改革を進めるが、家臣の反発を招いた。のちに須花坂の戦いで戦死した。
-

佐野泰綱 (さのやすつな)
佐野家13代当主。秀綱の嫡男。修理亮と称す。1559年、家臣・赤見伊賀守が主家に背いたため、伊賀守の居城・赤見城を攻撃し、伊賀守を常陸に追った。
-

佐波隆秀 (さはたかひで)
石見の豪族。はじめ大内家に属す。主家滅亡後は毛利家に仕え、石見平定戦で活躍した。主君・輝元の朝鮮出陣の際は、輝元の居城・広島城の留守居を務めた。
-

佐牟田長堅 (さむたながかた)
相良家臣。薩摩・肥後国境の大畑城主。胆略があり、常に犬を連れて国境で狩猟をした。島津家の誘降勧告を断ったため狩猟の行路で伏兵に遭い、殺された。
-

猿渡信光 (さるわたりのぶみつ)
島津家臣。沖田畷合戦に従軍して龍造寺軍を破るなど、主に肥前・肥後方面で戦功を立てた。のちに豊臣秀吉の九州征伐軍と根白坂で戦うが敗北し、戦死した。
-

寒川元隣 (さんがわもとちか)
讃岐の豪族。虎丸城主。三好家に属す。安富家と篠原家が寒川家の討伐を企んだ際、領地と居城を主君・長治に献上し難を逃れた。阿波中富川合戦で戦死した。
-

三条の方 (さんじょうのかた)
武田信玄の妻。清華家の一つ・三条家の出身。今川家の幹施により16歳で武田家に輿入れした。長男・義信の謀反や長女の早死など、晩年は不幸が多かった。
-

山本寺定長 (さんぽんじさだなが)
越後上杉氏家臣。上杉氏一族として家中に重きをなす。謙信の養子・景虎の後見役となった為、謙信死後の家督争いの際は景虎を推して戦うが敗れ、出奔した。
-

椎名景直 (しいなかげなお)
越中の豪族。養父・康胤の死後、家督を継ぐ。織田信長の越中侵攻軍に敗れ、越後に逃れた。御館の乱では上杉景虎に属すが敗れ逃亡、以後は織田家に属した。
-

椎名長常 (しいなながつね)
越中の豪族。兄・慶胤が長尾為景との戦いで敗死したため、家督を継ぐ。のちに為景に降り、新川郡守護代となった為景の又守護代となり、新川郡を支配した。
-

椎名康胤 (しいなやすたね)
越中の豪族。松倉城主。上杉謙信の従兄弟・長尾景直を養子とし、謙信と結ぶ。しかし、のちに武田家と結んだため、謙信に攻められて敗れ、戦死したという。
-

塩屋秋貞 (しおやあきさだ)
飛騨の豪族。尾崎城主。上杉謙信に属して越中や飛騨で活躍、謙信から目代に任ぜられた。謙信の死後は織田信長に属したが、越中の豪族との戦いで戦死した。
-

志賀親次 (しがちかつぐ)
大友家臣。豊後岡城主。親度の子。島津家臣・新納忠元率いる3万5千の軍勢をわずか千の兵で撃退し、さらに近隣の諸城を奪回し、豊臣秀吉に功を賞された。
-

志賀親度 (しがちかのり)
大友家臣。豊後岡城主。親守の子。肥後方分を務めた。主君・義統とたびたび対立する。のち島津義久の豊後侵攻軍に内応し、子・親次により自害させられた。
-

志賀親守 (しがちかもり)
大友家臣。豊後岡城主。肥後方分を務めた。耳川合戦の際は消極的行動を取り、大友軍大敗の原因を作った。主君・義統が朝鮮派兵に従った際は豊後に残った。
-

四釜隆秀 (しかまたかひで)
大崎家臣。四釜城主。剛勇にして智力ありと謳われた。大崎家内乱の際には、主君・義隆の命で中新田城を守り、侵攻してきた伊達軍と抗戦、これを撃退した。
-

敷地藤安 (しきちふじやす)
土佐一条家臣。民部少輔と称す。主君・房冬の傅役を務めたが、娘が房冬の妻となったことから、ほかの家臣が嫉妬して讒言され、房冬から自害を命じられた。
-

執行種兼 (しぎょうたねかね)
江上家臣。のち主君・武種とともに龍造寺家に属す。勇将として知られ、各地の合戦で活躍した。沖田畷合戦では具足をつけず羽織袴で奮戦するが、戦死した。
-

重見通種 (しげみみちたね)
大内家臣。はじめ河野家に仕える。大内軍を返り討ちにするなど活躍するが、叛意を疑われ、大内家に逃れた。厳島の戦いで陶軍の右翼を担うが、敗死した。
-

宍戸隆家 (ししどたかいえ)
安芸の豪族。毛利元就と争うが、のちに元就の娘・五龍を娶って和睦し、毛利家の一門衆となる。吉川元春と軍事行動をともにし、各地の合戦で活躍した。
-

宍戸元続 (ししどもとつぐ)
毛利家臣。隆家の孫で、筆頭家老を務めた。豊臣秀吉の朝鮮派兵では、渡海して奮戦する。関ヶ原合戦後は主家に従って萩に移り、萩城の普請工事を担当した。
-

志道広良 (しじひろよし)
毛利家臣。主君・元就の毛利家相続に尽力。のちに元就の要請で元就の子・隆元の後見役を務めた。隆元に「君は船、臣は水にて候」と当主のあり方を説いた。
-

雫石詮貞 (しずくいしあきさだ)
奥州斯波家臣。詮高の次男。父が雫石地方を攻略した際に、雫石城主となり、雫石御所を称した。雫石城は、斯波家滅亡の際に南部信直によって攻略された。
-

信太範宗 (しだのりむね)
小田家臣。木田余城主。伊勢守と称す。主君・氏治と不和になったため、菅谷政貞に土浦城で謀殺されたという。謀殺したのは政貞の父・勝貞という説もある。
-

志駄義秀 (しだよしひで)
上杉家臣。川中島合戦で父・義時の跡を継ぐ。酒田城主を務めた。関ヶ原合戦では最上家の背後を衝くなど活躍。のちに米沢藩の執事となり、藩政を統括した。
-

七条兼仲 (しちじょうかねなか)
阿波の豪族。七条城主。中富川合戦で敗死した。怪力の豪傑で、武勇伝が多数伝承されている。大山寺で催される「力餅大会」は伝承の1つに由来するという。
-

七戸家国 (しちのへいえくに)
南部家臣。津軽為信の攻勢を受け、平内領を失う。九戸政実の乱に加わり、近隣諸城を攻略した。欧州仕置軍の攻撃を受けて降伏し、処刑された。
-

七里頼周 (しちりよりちか)
加賀の本願寺の代官。一向宗門徒の要請により富田長繁を討つが、翌年、織田信長の討伐軍に降る。のち法主・顕如の命によって松任城主・鏑木頼信を討った。
-

篠原長房 (しのはらながふさ)
三好家臣。主家の領国経営の基礎となる分国法「新加制式」を制定した。三好三人衆に次ぐ地位にあったが、同族・篠原自遁に讒言され主君・長治に殺された。
-

斯波詮真 (しばあきざね)
奥州斯波家当主。経詮の子。隣国の南部家とたびたび争ったが、劣勢に追い込まれたため和睦。のちに九戸信仲の四男・高田康真を娘婿として迎えた。
-

斯波詮高 (しばあきたか)
奥州斯波家当主。高水寺城主。1549年に南部家と戦い、雫石城を攻略した。次男・詮貞を雫石城、三男・詮義を猪去館に置いて、領内を統治した。
-

斯波詮直 (しばあきなお)
奥州斯波家当主。詮真の子。南部信直の軍に敗れて逃走、各地に潜伏した。のちに南部家に仕えたが、大坂冬の陣の際、浪人となって京都に住んだという。
-

柴田勝家 (しばたかついえ)
織田家臣。「かかれ柴田」の異名をとった猛将。北陸方面軍の総大将を務めた。本能寺の変後、羽柴秀吉と争い賤ヶ岳合戦で敗れ、居城・北庄城で自害した。
-

柴田勝豊 (しばたかつとよ)
柴田家臣。叔父・勝家の養子となる。長浜城主を務めた。のちに勝家と対立し、その事を知った羽柴秀吉に攻められ、降伏した。賤ヶ岳合戦の直後、病死した。
-

柴田勝政 (しばたかつまさ)
柴田家臣。盛次の次男。武勇に優れ、叔父・勝家から柴田姓を下賜される。加賀一向一揆の平定に活躍した。賤ヶ岳合戦後は豊臣秀吉に仕え、豊臣姓を受けた。
-

新発田重家 (しばたしげいえ)
上杉家臣。綱貞の子。御館の乱では上杉景勝に属して活躍した。しかし恩賞に不満を持ち、織田信長に通じて新発田城に籠城、謀叛を起こすが敗北、自害した。
-

新発田綱貞 (しばたつなさだ)
上杉家臣。新発田・五十公野城主。伯耆守と称した。上条定憲が長尾為景と戦った乱の際は、はじめ長尾方に属したが、のちに上条方に転じて長尾軍と戦った。
-

新発田長敦 (しばたながあつ)
上杉家臣。新発田・五十公野城主。綱貞の子。上条定憲の乱が終息したあと、上条方国人の長尾家への帰参を斡旋した。御館の乱の際には上杉景勝に属した。
-

斯波経詮 (しばつねあき)
奥州斯波家当主。詮高の嫡男。奥州斯波家は、足利尊氏の家臣・斯波家長が奥州管領として斯波郡に派遣され、高水寺城を築いて本拠としたことに始まる。
-

斯波長秀 (しばながひで)
織田家臣。斯波義統の次男。各地を転戦し、信濃平定後、信濃伊那郡を領す。本能寺の変後は豊臣秀吉に属して九州征伐などに従軍、再び信濃伊那郡を領した。
-

斯波秀秋 (しばひであき)
毛利秀秋とも。室町幕府の管領をも務めた斯波武衛家の落胤とされる。関ヶ原の戦いでは西軍に属し、改易。その後、豊臣秀頼に仕え、大坂夏の陣で討死した。
-

斯波義銀 (しばよしかね)
尾張斯波家15代当主。義統の嫡男。織田広信によって父が殺害されると、織田信長を頼って広信と戦う。のちに信長と敵対して追放され、各地を流浪した。
-

斯波義冬 (しばよしふゆ)
織田家臣。斯波義統の三男。織田信雄の家老として松ヶ島城主を務めた。小牧長久手合戦の直前、豊臣秀吉の謀略により岡田重孝らとともに長島城で殺された。
-

斯波義統 (しばよしむね)
尾張斯波家14代当主。守護代・織田広信の傀儡として清洲城に住む。広信が織田信長の暗殺を企んだ際、密かにこれを信長に知らせたため、広信に殺された。
-

渋江内膳 (しぶえないぜん)
佐竹家臣。主君・義宣の絶大な信頼を受け、秋田藩の経略に尽力。独自の検地法「渋江田法」により、藩財政の根幹を固めた。大坂冬の陣に従軍し、戦死した。
-

島左近 (しまさこん)
筒井家臣。のち浪人し、石田三成に高禄で召し抱えられる。「三成に過ぎたるもの」と謳われた名将。関ヶ原合戦で縦横無尽の活躍をし、壮絶な戦死を遂げた。
-

島津家久 (しまづいえひさ)
島津家臣。貴久の四男。永吉島津家の祖となる。沖田畷合戦の際は10倍の兵力の龍造寺軍を破る。豊臣秀吉の九州征伐軍に降り、豊臣秀長との会見後に急死。
-

島津勝久 (しまづかつひさ)
島津家14代当主。忠昌の三男。島津実久が守護職を強要したため、島津忠良・貴久親子に国政を委ねるが、のちに復帰を企てたため、領内に混乱を招いた。
-

島津実久 (しまづさねひさ)
薩州島津家5代当主。宗家当主の地位を望むが拒否されたため、宗家に背く。一時は勢力を拡大するが、島津忠良との戦いに敗れて降伏、薩摩出水に逼塞した。
-

島津日新斎 (しまづじっしんさい)
伊作島津家10代当主。嫡男・貴久に島津宗家の家督を継がせる。「いろは歌」を作って家臣の教育にあたるなど、島津家隆盛の基盤を作った島津家中興の祖。
-

島津貴久 (しまづたかひさ)
島津家15代当主。忠良の嫡男。父の補佐を受けて所領を広げ、薩摩統一を果たす。新兵器・鉄砲の導入や積極的な外交政策などで島津家飛躍の土台を築いた。
-

島津忠興 (しまづただおき)
以久の三男。父の死後、その遺領を継いで佐土原2代藩主となる。大坂冬の陣には徳川方として参陣したが、翌年の夏の陣には間に合わなかった。
-

島津忠親 (しまづただちか)
島津家臣。飫肥城主。父・忠広の隠居により家督を継ぐ。近隣の伊東・肝付家の攻撃をよく防いだが、のちに猛攻撃を受けて日向都城に逃れ、同地で死去した。
-

島津忠恒 (しまづただつね)
島津家18代当主。義弘の三男。父とともに朝鮮派兵に従軍し、功を立てた。関ヶ原合戦後、家督を継ぐ。城下町や港湾の整備を行い、薩摩藩の基礎を作った。
-

島津忠辰 (しまづただとき)
島津家臣。薩摩出水領主。義虎の嫡男。朝鮮派兵の際、釜山に出陣するが、病と称して進軍を停止。豊臣秀吉の叱責を受け、改易された。のち朝鮮で病死した。
-

島津忠直 (しまづただなお)
信濃の豪族。長沼城主。武田信玄に居城を追われ、上杉謙信を頼る。以後は上杉家に仕えた。武田家滅亡後、旧領を回復した。のちに主家の会津移封に従った。
-

島津忠長 (しまづただなが)
島津家臣。尚久の子。岩屋城攻めでは総大将を務める。その後も、義弘麾下で活躍。関ヶ原合戦後は島津代表として徳川家康と交渉した。
-

島津忠広 (しまづただひろ)
島津家臣。忠朝の子。右馬頭と称す。飫肥城主。領地を接する伊東義祐の侵攻をたびたび受けるが、その都度撃退し、日向における島津家の所領を守り抜いた。
-

島津忠将 (しまづただまさ)
忠良の次男。貴久の弟。兄を支え、各地を転戦する。島津家が守護大名から戦国大名へと転身する礎を築いた1人。肝付家との大隅廻城戦で戦死した。
-

島津歳久 (しまづとしひさ)
島津家臣。貴久の三男。日置島津家の祖となる。豊臣秀吉の九州征伐軍に最後まで抵抗した。多くの家臣が梅北国兼の乱に加担したため、責任をとり自害した。
-

島津豊久 (しまづとよひさ)
島津家臣。家久(貴久四男)の子。朝鮮派兵などに従軍し戦功を立てた。関ヶ原合戦では退却戦の殿軍を務め、本多忠勝や井伊直政らの軍と戦い、討死した。
-

島津尚久 (しまづなおひさ)
島津家臣。忠良の子。鹿籠領主。幼少より兄・貴久の供をして活躍。大太刀を振るい、弓の達人であったと伝わるが、病を得て早世する。
-

島津久元 (しまづひさもと)
島津家臣。忠長の次男。新納家に養子に入るが、兄の死去に伴い父の家督を継いだ。島津忠恒に家老として仕え、島原の乱では忠恒の子・光久を補佐した。
-

島津以久 (しまづもちひさ)
相州家5代当主。忠将の子。一門として義久に重用され、数々の合戦で武功を挙げた。関ヶ原合戦で戦死した島津豊久の所領を継承し、初代佐土原藩主となる。
-

島津義虎 (しまづよしとら)
島津家臣。薩摩出水領主。実久の嫡男。相良家攻めの際は先鋒を務め、相良義陽を降伏させる。のち沖田畷合戦にも従軍するなど、肥後・肥前方面で活躍した。
-

島津義久 (しまづよしひさ)
島津家16代当主。貴久の嫡男。優秀な弟たちの協力により領土を拡大、九州をほぼ手中に収めるが、豊臣秀吉の九州征伐軍に敗北し、薩摩1国を安堵された。
-

島津義弘 (しまづよしひろ)
島津家17代当主。貴久の次男。伊東・大友両家を粉砕し、島津家を隆盛に導いた家中随一の猛将。朝鮮派兵の際は明の大軍を破り「鬼石曼子」と恐れられた。
-

島村盛実 (しまむらもりざね)
浦上家臣。入道名は貫阿弥。宇喜多能家を砥石城に襲って自害させ、家中の実権を独占する。しかし、のちに謀叛疑惑により能家の孫・宇喜多直家に討たれた。
-

清水景治 (しみずかげはる)
毛利家臣。父・宗治の切腹を称賛した豊臣秀吉から直臣大名にと誘われたが辞退した。財政に功があり、関ヶ原の後、益田元祥の下で藩の財政再建に活躍した。
-

清水宗治 (しみずむねはる)
毛利家臣。高松城主。織田信長の中国征伐軍に頑強に抵抗したが、羽柴秀吉による「水攻め」に遭い苦戦を強いられる。城兵の助命を条件に和睦し、自害した。
-

清水康英 (しみずやすひで)
北条家臣。伊豆衆の筆頭。北条氏康の側近として各地で功を立てた。豊臣秀吉の小田原征伐では下田城に籠城し、豊臣水軍を相手に善戦するが敗れ、降伏した。
-

志村光安 (しむらあきやす)
最上家臣。主君・義光の腹心として活躍し「いかなる強敵も彼には降った」といわれた。関ヶ原合戦の際は長谷堂城を守り、直江兼続の大軍を見事に撃退した。
-

下方貞清 (しもかたさだきよ)
織田家臣。小豆坂の戦いで活躍し七本槍に数えられる。その後も桶狭間・姉川など数々の戦いで武功を挙げ、晩年は松平忠吉に招かれた。
-

下国師季 (しもくにもろすえ)
安東家傍流。蠣崎家臣。アイヌ族の攻撃に遭い居城・茂別館から逃れ、蠣崎家の庇護を受けて嫡子に家督を譲った。のち蠣崎家から追放され瀬棚で没した。
-

下間真頼 (しもつましんらい)
石山本願寺の坊官。頼竜の父。頼廉や仲孝とは別流で、下間三家のうち宮内郷家の傍流。10世法主・証如の奏者役を務めたとされ、大蔵丞、上野介を称した。
-

下間仲孝 (しもつまちゅうこう)
本願寺の坊官。頼照の子という。石山合戦で活躍した。織田信長と本願寺の和議に際しては、法主・顕如に代わって血判した。能楽に長じ「童舞抄」を著した。
-

下間頼慶 (しもつまらいけい)
真宗本願寺派の僧。本願寺9世・実如に仕える。甥の頼秀・頼盛に不穏な動きがあり、一時出仕をやめるが、のち復帰した。温和な性格で人々に重んぜられた。
-

下間頼照 (しもつまらいしょう)
本願寺の坊官。法主・顕如の命で越前の一向宗門徒を指導し、織田信長を苦しめた。のちに信長が比叡山や長島と同じ焦土化作戦をとったため敗北、殺された。
-

下間頼竜 (しもつまらいりゅう)
石山本願寺の坊官。顕如が本願寺11世法主に就任した際に坊官に就任した。茶の湯を好み、「天王寺屋会記」に津田宗達らを招いて茶会を開いた記録が残る。
-

下間頼廉 (しもつまらいれん)
本願寺の坊官。石山合戦において法主・顕如に代わって全軍を指揮、織田信長に対し徹底抗戦を挑んだ。信長の死後、豊臣秀吉から本願寺町奉行に任じられた。
-

寿桂尼 (じゅけいに)
今川氏親の正室。今川氏輝、義元の母。夫の死後、家督を継いだ氏輝を補佐し、女戦国大名と呼ばれた。義元や氏真の代にも政治に関与したとされる。
-

定恵院 (じょうけいいん)
今川義元の正室。武田信虎の娘。信玄の姉。氏真の生母。今川氏輝の死を受けて家督を継いだ義元に輿入れし、甲駿同盟の成立に大きな役割を果たした。
-

上条定憲 (じょうじょうさだのり)
越後守護・上杉定実の甥。旧上杉家勢力を糾合し挙兵。三分一原合戦において長尾軍と戦うが、数千人の兵が討ち捕らえられるという大敗北を喫し、戦死した。
-

庄高資 (しょうたかすけ)
備中の豪族。為資の子。元祐(三村家親の子)の死後、家督を継いだ。尼子家に属したため、毛利家に属す三村元親と対立する。のちに元親に敗れ、戦死した。
-

庄為資 (しょうためすけ)
備中の豪族。庄家は武蔵七党の一・児玉党の出身。上野頼久を討って松山城を奪い、備中最大の勢力となるが、三村家親に敗れ、家親の子・元祐を養子とした。
-

城親賢 (じょうちかかた)
大友家臣。肥後隈本城主。親冬の嫡男。主家没落後は島津家に属し、島津勢を城外に招いて国内経営に協力した。龍造寺勢力の南下に伴い、龍造寺家に従った。
-

城親冬 (じょうちかふゆ)
菊池家臣。主君・義武の肥後隈本城回復戦の際は大友家に属し、恩賞として肥後隈本城主となり、飽田・詫摩二郡を支配する。のちに肥前に出兵するが敗れた。
-

少弐資元 (しょうにすけもと)
少弐家第16代当主。肥前勢福寺城主。大内義隆の攻勢を受けると居城を明け渡して和睦する。のち欺かれて所領をすべて失い、追撃を受けて自害した。
-

少弐冬尚 (しょうにふゆひさ)
少弐家17代当主。資元の子。龍造寺家兼の一族を殺し、東肥前の領主の後援を得て勢力回復をはかるが、再起した家兼の曾孫・隆信の軍勢に敗れ、自害した。
-

庄林一心 (しょうばやしかずただ)
加藤清正家臣。通称隼人。飯田覚兵衛、森本義太夫と加藤家三傑と呼ばれた。はじめ荒木村重、仙石秀久に仕える。天草一揆討伐に功があり、朱槍を許された。
-

庄元祐 (しょうもとすけ)
備中の豪族。三村家親の長男。庄為資の養子となった。明禅寺合戦では父に従って出陣し、延原景能・宇喜多忠家の軍と戦うが負傷し、忠家の軍勢に討たれた。
-

白河顕頼 (しらかわあきより)
白河結城家当主。政朝の子。1520年には岩城家と結んで那須家を攻めるが敗れた。1531年、白河結城家の祖・宗広が開基した長雲山智徳院を再興した。
-

白河晴綱 (しらかわはるつな)
白河結城家当主。義綱の子。内乱を鎮定して北上を続ける佐竹家と抗争し、次第に所領を奪われる。蘆名家と結んで対抗したが、間もなく失明、病死した。
-

白河義顕 (しらかわよしあき)
白河結城家当主。晴綱の嫡男。父の死後に家督を継ぐが、後見役の小峰義親をはじめとする家臣たちによって居城を追われた。子孫は秋田藩に仕えたという。
-

白河義親 (しらかわよしちか)
白河結城家臣。結城顕頼の子。結城義綱の子ともいう。宗家の義顕を追放して宗家を乗っ取る。のちに佐竹義重に敗れ、義重の子・義広を養子に迎え隠居した。
-

白河義綱 (しらかわよしつな)
白河結城家当主。顕頼の子。白河結城家は祐広を祖とし、南北朝期は南朝方に属して戦った。永享の大乱の際には直朝が南陸奥の中心人物として活躍している。
-

白鳥長久 (しらとりながひさ)
出羽の国人領主。天文の乱より最上家に味方し、天正最上の乱では義光と伊達輝宗の和議を仲介する。のち信長に通じる動きを義光に危険視され、謀殺される。
-

白石宗実 (しろいしむねざね)
伊達家臣。輝宗・政宗の2代に仕え、各地の合戦で功を立てる。摺上原合戦では伊達成実とともに伊達軍の主力を形成した。豊臣秀吉の朝鮮派兵にも従軍した。
-

新開実綱 (しんがいさねつな)
三好家臣。富岡城主。三好義賢の娘婿。勇将として知られた。のち長宗我部元親に属すが、元親に謀殺された。この時の縁板が「丈六寺の血天井」として残る。
-

新庄直定 (しんじょうなおさだ)
豊臣家臣。直頼の嫡男。関ヶ原合戦では父とともに西軍に属す。戦後会津に流された。のち徳川家康に仕え、大坂夏の陣に従軍、勲功を立てた。
-

新庄直忠 (しんじょうなおただ)
豊臣家臣。豊臣家直領代官を務めた。朝鮮派兵では渡海して活躍。関ヶ原合戦後近江で少禄を得た。兄・直頼とともに文武に長け人倫を心得た武士と評された。
-

新庄直頼 (しんじょうなおより)
豊臣家臣。高槻城主を務めた。関ヶ原合戦の際は西軍に属し、伊賀上野城を占拠するが、戦後改易され蒲生秀行に預けられた。のちに常陸麻生3万石を領した。
-

新城村尚 (しんじょうむらなお)
二本松家臣。政国の次男。新城氏は二本松家の分家であり、宗家の家泰・義氏が相次いで死去したため、村尚の子の義国が二本松宗家を継いだ。
-

秦泉寺泰惟 (じんぜんじやすこれ)
長宗我部家臣。秦泉寺城主。長浜戸合戦で初陣を迎えた長宗我部元親に、槍の使い方を教示した。のちに農民と争いを起こして元親の怒りを買い、討伐された。
-

進藤賢盛 (しんどうかたもり)
六角家臣。織田信長の上洛軍に降る。以後は佐久間信盛の与力として、各地に従軍した。信盛の改易後は旗本となる。本能寺の変後は蒲生氏郷の与力となった。
-

進藤貞治 (しんどうさだはる)
六角家臣。木浜城主。後藤賢豊とともに「両藤」と称された。幕府や細川家、本願寺との折衝や、延暦寺と法華宗の紛争の調停など、おもに外交面で活躍した。
-

神馬忠春 (じんばただはる)
佐野家臣。浅利城主。遠江守を称した。神馬家は佐野家の一族という。1546年、主家に従って河越合戦に参陣するが北条軍の攻撃を受けて戦死した。
-

神保氏張 (じんぼううじはる)
越中の豪族。森山城主。はじめ上杉家に属すが、のちに織田家の佐々成政に仕える。成政の肥後移封に従い、国人一揆と戦った。成政の死後は徳川家に仕えた。
-

神保相茂 (じんぼうすけしげ)
徳川家臣。越中神保氏の同族。大坂夏の陣で水野勝成に属して戦うも、明石全登に敗れ全滅した。味方の伊達政宗に鉄砲の一斉射撃を受けたという説もある。
-

神保覚広 (じんぼうただひろ)
神保家臣。神保家の一族。主家の内紛により上杉家との関係が悪化した際、関係修復に尽力した。のちに居城・火宮城を一向一揆に落とされ、石動山に逃れた。
-

神保長住 (じんぼうながずみ)
越中の豪族。長職の子。父に追放され、京都で浪人となるが、織田信長に招かれる。越中経略に携わるが、小島職鎮らに襲われて富山城に幽閉され、失脚した。
-

神保長城 (じんぼうながなり)
越中の豪族。父・長職が兄・長住を追放したあと家督を継ぐ。父の死後は家臣・小島職鎮に実権を握られた。長住が越中に戻ると、神保家の家督を返還した。
-

神保長職 (じんぼうながもと)
越中の豪族。富山城主。神保家を越中最大の勢力に築き上げるが、上杉謙信に敗れ、降伏した。のちに意見の対立により家中が分裂し、再び神保家は衰退した。
-

瑞渓院 (ずいけいいん)
今川氏親の娘。北条氏康の正室となり氏政・氏邦らを生んだ。河東の乱で実家と北条家が抗争した際も離縁しなかった。娘の蔵春院は今川氏真の正室となった。
-

水心 (すいしん)
石谷光政の娘。長宗我部元親が25歳の時に正室となり、信親・信和・信忠・盛親らを生んだ。輿入れの際、元親は京都まで上洛したという。
-

水原親憲 (すいばらちかのり)
上杉家臣。水原館主。御館の乱の際は上杉景勝を支持した。主家の会津移封後は猪苗代城代を務める。大坂の陣で戦功を立て、徳川秀忠から感状を下賜された。
-

陶興房 (すえおきふさ)
大内家臣。周防守護代を務める。主君・義興に従い上洛したほか、安芸や九州に出陣するなど、各地で活躍した。和歌・連歌に優れ、文化人とも交流を持った。
-

陶晴賢 (すえはるかた)
大内家臣。興房の子。「西国無双の侍大将」と評された。主君・義隆を自害させ大友晴英を当主に迎えて主家を傀儡化した。厳島合戦で毛利元就に敗れ、自害。
-

菅沼定盈 (すがぬまさだみつ)
今川家臣。野田城主。桶狭間合戦後、徳川家に仕える。武田信玄の三河侵攻では一族の多くが信玄に寝返る中、一貫して徳川家に属し、居城を攻め落とされた。
-

菅沼定芳 (すがぬまさだよし)
徳川家臣。定盈の六男。兄が早世したため、その養子となって家督を継ぎ伊勢長島2代藩主となる。大坂の陣に参陣。のちに丹波亀山に移封された。
-

菅沼忠久 (すがぬまただひさ)
今川家臣。井伊谷三人衆の1人。桶狭間の戦いで今川義元が討死すると、徳川家に仕える菅沼定盈から離反の誘いを受けて追従。のち井伊直政の被官となった。
-

杉浦玄任 (すぎうらげんにん)
本願寺の坊官。加賀一向一揆の大将。門徒を率いて、朝倉軍や上杉軍と互角に渡り合う。亥山城に入った際に作らせた掘水が、「本願清水」の始まりとされる。
-

杉興運 (すぎおきかず)
大内家臣。筑前守護代を務めた。肥前田手畷合戦では総大将を務め、少弐家臣・龍造寺家兼の軍と戦うが、敗北した。陶晴賢の謀叛の際に主君・義隆に殉じた。
-

杉重矩 (すぎしげのり)
大内家臣。豊前守護代を務めた。はじめ陶晴賢と対立するが、晴賢の謀叛に同調し、主君・義隆を自害させた。のち再び晴賢と対立して敗れ、長門で自害した。
-

杉重良 (すぎしげよし)
大内家臣。祖父・重矩と父・重輔を陶晴賢に殺されたため、毛利家に属し、福原貞俊の娘を娶る。のちに大友家に属すが大友家を離反した高橋鑑種に討たれた。
-

杉谷善住坊 (すぎたにぜんじゅうぼう)
甲賀の忍者。鉄砲の名手。六角義賢に依頼され、甲賀の郷を滅ぼした織田信長を狙撃するが失敗する。のち磯野員昌に捕らえられ、処断された。
-

杉原長房 (すぎはらながふさ)
豊臣家臣。但馬豊岡3万石を領す。関ヶ原合戦では西軍に属し、丹後田辺城攻撃に参加した。妻の父が浅野長政であった関係もあり、戦後所得は安堵された。
-

杉原理興 (すぎはらまさおき)
大内家臣。山名忠勝の拠る神辺城を攻略し、居城とする。主家が出雲遠征に失敗すると尼子家に寝返り、攻撃を受けて出雲に逃走した。のちに神辺城に戻った。
-

杉原盛重 (すぎはらもりしげ)
毛利家臣。はじめ神辺城主・杉原理興に仕えた。理興の死後、吉川元春の推挙により神辺城の城代となる。以後は元春率いる山陰方面軍の先鋒として活躍した。
-

菅谷勝貞 (すげのやかつさだ)
小田家臣。土浦城主。1516年、土浦城を築いた豪族・若泉五郎左衛門を討って土浦城を奪い、居城とした。近隣の豪族や上杉・佐竹家などと各地で戦った。
-

菅谷範政 (すげのやのりまさ)
小田家臣。政貞の子。主君・氏治が小田城を奪われるたびに居城に迎え、その奪還に努めた。氏治の没後、浅野長政の推挙を受けて徳川家に旗本として仕えた。
-

菅谷政貞 (すげのやまささだ)
小田家臣。土浦城主。勝貞の子。佐竹家に奪われた小田城を奪還し、大掾家・宇都宮家などと戦うなど活躍したが、のちに主君・氏治とともに佐竹家に属した。
-

鈴木佐大夫 (すずきさだゆう)
紀伊の豪族。雑賀城主。鉄砲で武装した傭兵集団・雑賀党を率い、本願寺と結んで織田信長と戦った。のち紀伊に入った豊臣家臣・藤堂高虎に欺かれ自害した。
-

鈴木重兼 (すずきしげかね)
紀伊の豪族。佐大夫重意の子。平井に住み「平井の孫市」と呼ばれた。思慮深い人物で、雑賀党の背後にあって部族間の調整や政治工作といった役割を担った。
-

鈴木重次 (すずきしげつぐ)
水戸徳川家臣。重朝の嫡男。3千石を領し、大番頭や家老を務めた。のち将軍・徳川家光に拝謁した。男子に恵まれず主君・頼房の末子・重義を婿養子とした。
-

鈴木重時 (すずきしげとき)
今川家臣。井伊谷三人衆の1人。桶狭間の戦いの後、家康が独立すると娘婿・菅沼忠久の誘いを受けて徳川家に仕えた。遠江攻め中に反攻を受け、討死した。
-

鈴木重朝 (すずきしげとも)
豊臣家臣。重秀の子。朝鮮派兵に参加した。関ヶ原合戦では西軍に属し、伏見城を守る鳥居元忠を討つ戦功を立てた。戦後、浪人したのち水戸徳川家に仕えた。
-

鈴木重則 (すずきしげのり)
真田家臣。名胡桃城代。北条家臣・猪俣邦憲の奇襲を受け敗北、自害した。この事件は、私戦の禁令に反するとして、豊臣秀吉に小田原征伐の口実を与えた。
-

鈴木重秀 (すずきしげひで)
紀伊の豪族。佐大夫重意の子。通称「雑賀孫市」。雑賀の鉄砲衆を率いて石山本願寺に入り、織田信長の軍を苦しめた。石山開城後は豊臣秀吉に仕えたという。
-

鈴木重泰 (すずきしげやす)
紀伊雑賀の鈴木家の一族という。本願寺から加賀に派遣され、鳥越城を築いて加賀の一向宗門徒を指導した。のちに柴田勝家に討たれ、首級は安土に送られた。
-

鈴木重好 (すずきしげよし)
徳川家臣。武田の遠州侵攻により居城を失う。のち井伊直政付きとなり、小牧・長久手の戦いなどで活躍した。晩年は秀忠の命で水戸に移り、家老を務めた。
-

薄田兼相 (すすきだかねすけ)
豊臣家臣。大坂冬の陣で博労ヶ淵砦の守備に失敗し、「橙武者」と嘲られた。大坂夏の陣で勇戦し、戦死した。ヒヒ退治の豪傑・岩見重太郎と同一人物という。
-

鈴木忠重 (すずきただしげ)
真田家臣。重則の子。柳生宗章や宗厳に剣を学んだという。関ヶ原など大戦の前に二度、真田家を出奔しており、諜報活動を行っていたとする説もある。
-

鈴木元信 (すずきもとのぶ)
伊達家臣。おもに内政面で活躍した。伊達家が天下を制した時を想定し式目などの草案を準備するが、臨終の際に「無用の長物」とこれらを焼却させたという。
-

須田長義 (すだながよし)
上杉家臣。梁川城代。満親の子。関ヶ原合戦では本庄繁長と協力し、伊達政宗軍を福島口に撃破する。大坂の陣でも戦功を立て、徳川秀忠から感状をもらった。
-

須田満親 (すだみつちか)
信濃の豪族。信濃の一向一揆衆を指導した。のち上杉景勝に仕え、北陸の一向一揆対策の責任者となる。信濃海津城主を務め、徳川家康の信濃侵攻軍と戦った。
-

須田盛久 (すだもりひさ)
宇都宮家臣。主家改易後は姉の夫・小貫頼久を介して佐竹家に属す。大坂冬の陣で功を立て、のちに家老となる。見識があり、慎重な人となりであったという。
-

須田盛秀 (すだもりひで)
二階堂家臣。家老を務めた。主君・盛隆が謀殺されたあとは、実質的な城代として領内を統治。摺上原合戦後、伊達家の大軍に攻められ、将兵全員戦死した。
-

諏訪忠恒 (すわただつね)
徳川家臣。頼水の長男。大坂夏の陣に出馬し、榊原康勝に属して若江の戦い、天王寺での戦いで活躍。父の隠居により信濃諏訪藩を継ぎ、新田開発に努めた。
-

諏訪姫 (すわひめ)
諏訪頼重の娘。武田信玄の側室。勝頼の母。武田と敵対した頼重が死んだ後、信玄の側室となる。信玄は当初、自分と諏訪姫の子に諏訪家を継がせようとした。
-

諏訪満隣 (すわみつちか)
諏訪家臣。頼満の四男。甥・頼重の死後諏訪領で横暴をふるう諏訪家の庶流・高遠頼継を討つため、武田信玄と結ぶ。頼継の滅亡後、諏訪家は武田家に属した。
-

諏訪頼重 (すわよりしげ)
信濃の戦国大名。祖父・頼満の死後、諏訪大社大祝となる。義兄・武田信玄と戦うが敗れ、幽閉の後に自害させられた。娘は信玄の側室となり、勝頼を産んだ。
-

諏訪頼忠 (すわよりただ)
武田家臣。満隣の子。主家の統治下で諏訪大社大祝となった。主家滅亡後は諏訪を平定して自立。一時北条家に属すが、のち徳川家に仕え、本領を安堵された。
-

諏訪頼水 (すわよりみず)
頼忠の嫡男。信濃高島藩主。父の死後家督を継ぎ、2万7千石を領した。内政に励み領国の安定に尽力。改易され蟄居処分を受けた松平忠輝を預かった。
-

諏訪頼満 (すわよりみつ)
信濃の戦国大名。諏訪大社の大祝を務める。金刺家を滅ぼして諏訪地方を平定、隣国の武田信虎と戦うなど、諏訪家の勢力回復に尽力した、諏訪家中興の英主。
-

関一政 (せきかずまさ)
伊勢の豪族。亀山城主。盛信の次男。蒲生家に仕え、奥州征伐で活躍。関ヶ原合戦の際は東軍に属し、伯耆黒坂5万石を領すが、のちに内紛により改易された。
-

関口氏広 (せきぐちうじひろ)
今川家臣。瀬名氏俊の子。用宗城主を務めた。今川義元の妹を娶った。娘・瀬名(築山殿)は徳川家康に嫁ぐ。のちに主君・氏真の命により自害させられた。
-

関盛雄 (せきもりかつ)
伊勢の豪族。種盛の子。亀山城主。関家は南北朝時代には一貫して南朝方に属し北朝方に属した長野家らと戦った。南北朝の合一後、ようやく幕府に服属した。
-

関盛信 (せきもりのぶ)
伊勢の豪族。亀山城主。織田信長の伊勢侵攻軍に降る。本能寺の変後は豊臣秀吉に従った。のちに蒲生氏郷の与力となり氏郷の会津転封に従って会津に移った。
-

関盛吉 (せきもりよし)
柴田家臣。盛信の子。主君・勝豊の死後蒲生氏郷に仕え、九州征伐などで活躍した。主家内紛の際に出奔、兄・一政に仕える。兄の改易後は土井利勝を頼った。
-

瀬名氏貞 (せなうじさだ)
今川家臣。瀬名家は南北朝時代に九州探題を務めた名将・今川貞世(了俊)の末裔。玄広恵探と梅岳承芳(今川義元)が争った花倉の乱では承芳方に属した。
-

瀬名氏俊 (せなうじとし)
今川家臣。氏貞の子。別名に貞綱。桶狭間の戦いで先手侍大将を務めた。ただし先発隊として入り、先に大高城へ向かっていたため本戦には参加していない。
-

瀬名姫 (せなひめ)
今川義元の養女。築山殿。徳川家康に嫁ぐ。桶狭間合戦後、夫が織田信長と同盟を結んだため、不和となる。武田家への内通の疑いを受けて夫に殺された。
-

仙石権兵衛 (せんごくごんべえ)
豊臣家臣。淡路島平定の功により、淡路州本5万石を領す。九州征伐の先鋒を務めた際、戸次川合戦で島津軍に大敗し、領国を没収されるが、のちに帰参した。
-

仙石忠政 (せんごくただまさ)
秀久の嫡男。関ヶ原合戦では信濃上田城攻めに参加。父の死後家督を継ぎ、信濃小諸5万石を領す。大坂の陣で功を立て後に信濃上田へ加増転封された。
-

仙石秀範 (せんごくひでのり)
秀久の次男。関ヶ原合戦で西軍についたため、廃嫡の上、追放された。大坂の陣では、弟・忠政(徳川方)とは異なり、豊臣方で参戦。戦後、行方不明となる。
-

仙桃院 (せんとういん)
長尾為景の娘。名は綾。長尾政景に嫁ぎ二男二女を産む。夫が野尻池で溺死した後は弟・上杉謙信を頼り、仙桃院と名乗る。息子・景勝は謙信の養子となった。
-

千姫 (せんひめ)
徳川秀忠の娘。母は江。豊臣秀頼の妻となり、大坂城に住む。夏の陣で大坂城が落城した際、坂崎直盛により救い出された。その後は、本多忠刻の妻となった。
-

千利休 (せんりきゅう)
戦国時代の茶人。武野紹鴎から茶の湯を学ぶ。織田信長や豊臣秀吉に茶匠として仕え「わび茶」を大成させるなど活躍したが、秀吉と対立し、自害させられた。
-

蔵春院 (ぞうしゅんいん)
北条氏康の娘。北条・武田・今川家間で三国同盟が成立した際、今川氏真に嫁ぎ範以を産む。主家滅亡後は実家に戻る。父の死後は夫に従い徳川家康を頼った。
-

相馬顕胤 (そうまあきたね)
相馬家14代当主。盛胤の嫡男。小高城主。天文の大乱の際は舅・伊達稙宗を助けて各地で奮戦し、伊達晴宗に圧迫された稙宗を居城に引き取るなど活躍した。
-

相馬隆胤 (そうまたかたね)
盛胤の次男。中村城代を務めた。伊達家との戦いで戦死した。勇猛な武将だったが「小利を貪ってついには大利を失うであろう」と言われていたという。
-

相馬利胤 (そうまとしたね)
相馬家17代当主。義胤の子。関ヶ原合戦では相馬家は中立を保ち、このため一時、所領を失った。のちに許され本領を回復、秀忠の養女を娶る厚遇を受けた。
-

相馬盛胤 (そうまもりたね)
相馬家15代当主。顕胤の嫡男。小高城主。天文の大乱後は伊達家と敵対し、各地で死闘を展開する。一方、近隣の田村清顕とは和睦し、所領の基盤を固めた。
-

相馬義胤 (そうまよしたね)
相馬家16代当主。盛胤の嫡男。伊達家と各地で抗争を展開した。関ヶ原合戦で西軍に属していったん改易されるが、伊達政宗の取りなしで本領を安堵された。
-

宗義調 (そうよししげ)
対馬守護。家中の反乱が相次ぐ中、父の遺志を継ぎ安定に尽力。少弐家を擁して九州進出を図ったが遂げられなかった。のち豊臣秀吉に降伏した。
-

宗義智 (そうよしとし)
対馬守護。義調の養子。当主が2代続けて早世したため、義調の後見を得て家督を継ぐ。豊臣秀吉に巨従し、対馬一円の本領を安堵された。
-

十河一存 (そごうかずまさ)
三好家臣。三好元長の四男。十河家を継ぎ、十河城主となる。家中随一の猛将として鳴らし「鬼十河」の異名をとった。有馬権現への参詣途中に落馬し、死去。
-

十河存春 (そごうまさはる)
讃岐の豪族。大永~享禄年間の人。子・金光が早世したため、三好元長の四男・一存を養子に迎えた。十河家は讃岐山田郡を支配していた植田家の支族という。
-

十河存保 (そごうまさやす)
三好義賢の子。叔父・十河一存の養子となる。豊臣秀吉に従い、長宗我部家に奪われた讃岐を奪回した。九州征伐では先鋒を務め、豊後戸次川合戦で戦死した。
-

曾根高昌 (そねたかしげ)
伊予の豪族。曾根城主。曹洞宗に帰依し近隣の常久寺を曾根家の菩提寺として厚く保護した。常久寺はのち高昌寺と名を改めた。西園寺家との戦いで戦死した。
-

園田実明 (そのださねあき)
島津家臣。通称は清左衛門。貴久が分家の実久に清水城を攻められた際、貴久を助けて脱出。自邸に匿うなどして追撃を振り切り、無事に亀ヶ城まで退かせた。
-

太原雪斎 (たいげんせっさい)
今川家臣。執権を務めた。小豆坂の合戦で織田軍を破り、甲相駿三国同盟を成立させるなど、主家の政治、文化、経済、軍事、外交すべてに大きく貢献した。
-

大掾清幹 (だいじょうきよもと)
常陸の豪族。府中城主。貞国の子。豊臣秀吉の小田原征伐に参陣しなかったため佐竹義宣の攻撃を受けて自害した。一族諸氏も太田城に招かれて謀殺された。
-

大掾貞国 (だいじょうさだくに)
常陸の豪族。府中城主。大掾慶幹の死後佐竹義昭の弟が家督を継ぎ、昌幹と名乗ったが、大掾家中の反対にあったため実家に戻り、貞国が家督を継いだという。
-

大掾慶幹 (だいじょうのりもと)
常陸の豪族。府中城主。大掾家の始祖は常陸の大掾を務めた平国香で、その子孫4人が地名をとって多気・吉田・石毛・小栗に分かれ、大掾姓を称したという。
-

大道寺直次 (だいどうじなおつぐ)
北条家臣。政繁の四男。主家滅亡後は遠山長右衛門と名乗り、福島家に仕えた。関ヶ原合戦にも参陣した。福島家の改易後は徳川家に仕え、旧姓に復した。
-

大道寺直英 (だいどうじなおひで)
北条家臣。政繁の養子。小田原征伐後、徳川家康預かりとなり、家康の子・義直に仕える。のちに築城技術を見込まれ、津軽信枚に招聘されて津軽家へ移る。
-

大道寺政繁 (だいどうじまさしげ)
北条家臣。盛昌の子。行政に手腕を発揮し、河越城下の繁栄に貢献した。豊臣秀吉の小田原征伐軍に降伏し、道案内を務めたが、秀吉によって自害させられた。
-

大道寺盛昌 (だいどうじもりまさ)
北条家臣。鎌倉代官や河越城代を歴任した。大道寺家は「御由緒家」と呼ばれる北条家譜代の家臣で、北条早雲に従い駿河に下った太郎(発専)を始祖とする。
-

大藤信基 (だいとうのぶもと)
北条家臣。根来金石斎とも呼ばれる。鉄砲の技術を北条家にもたらすなど、政治軍事両面で主家を支えた。第一次国府台合戦などで活躍。
-

田結庄是義 (たいのしょうこれよし)
山名家臣。鶴城主。田結庄家は山名四天王の一。織田家への従属を唱え、毛利家への接近をはかる垣屋続成と対立。続成を討つが、続成の子・光成に討たれた。
-

大宝寺義興 (だいほうじうよしおき)
出羽の豪族。義増の子。兄・義氏の死後家督を継ぐ。上杉家臣・本庄繁長の次男を養子に迎え、上杉家との関係強化をはかるが、最上義光に攻められ自害した。
-

大宝寺晴時 (だいほうじはるとき)
出羽の豪族。澄氏の子。氏説の子ともいう。大宝寺家は、祖・武藤氏平が庄内大泉荘の地頭となったことに始まる。大宝寺姓を名乗るのは武藤長盛の時である。
-

大宝寺義氏 (だいほうじよしうじ)
出羽の豪族。義増の子。合戦に明け暮れて領政を軽んじたため、領民から「悪屋形」と憎悪された。最上義光に通じた家臣・前森蔵人に謀叛され、自害した。
-

大宝寺義増 (だいほうじよします)
出羽の豪族。九郎(政氏の子または弟)の子。庶流の砂越家と合戦を繰り返すが1532年に居城・鶴ヶ岡城を焼かれたため、尾浦城に本拠を移した。
-

平盛長 (たいらもりなが)
畠山家臣。鎌倉時代に活躍した平一揆の首領の末裔という。主家の滅亡後は織田信長、豊臣秀吉、豊臣秀次に歴仕した。秀次の死後は高野山に登り、隠棲した。
-

高木鑑房 (たかぎあきふさ)
龍造寺家臣。龍造寺隆信の家督相続に反対した、東肥前十九将の1人。隆信の肥前復帰の際に討たれた。斬られた際、頭が無い状態で従者の首を斬ったという。
-

高城胤辰 (たかぎたねとき)
原家臣。胤吉の子。下野守と称した。上杉謙信の関東遠征の際、一時上杉家に従うが、以後は一貫して北条方の姿勢を貫いた。のちに栗原6カ郷を与えられた。
-

高城胤則 (たかぎたねのり)
原家臣。胤辰の子。豊臣秀吉の小田原征伐では小田原城に籠城、敗戦後は信濃国に蟄居。のちに豊臣家への仕官を許されるが、秀吉の死により果たせなかった。
-

高城胤吉 (たかぎたねよし)
原家臣。高城家は千葉一族で、原家の軍事部門を担った重臣。小金城を築いて居城とした。第一次国府台合戦の際は北条家に属して奮戦、父と兄の敵を討った。
-

多賀貞能 (たがさだよし)
浅井家臣。主家滅亡後、織田家に従う。本能寺の変では明智光秀に従ったため、所領を没収された。堀秀重の次男・秀種を娘婿にし、跡継ぎとした。
-

高島正重 (たかしままさしげ)
長宗我部家臣。主君・元親の近習を務めた。主家の改易後は山内家に出仕した。文筆の才に恵まれ書も巧みで、元親の三十三回忌に際して「元親記」を著した。
-

高瀬忠行 (たかせただゆき)
佐野家臣。下野免鳥城代。佐野宗綱の戦死後、佐野家中を重臣の合議で経営し、佐野氏忠を支えたと伝わる。一方で、長尾顕長に攻められ戦死したという説も。
-

高田憲頼 (たかだのりより)
山内上杉家臣。武田信玄の侵攻で父・遠春が討たれると家督を相続。憲頼も信玄の侵攻に対抗するも敗北し、武田家に降った。三方ヶ原の戦いで負傷し、死去。
-

高田吉次 (たかだよしつぐ)
高田流槍術の祖。宝蔵院胤栄に槍術を学んだ。大坂の陣で豊臣方に加わったため浪人となり、江戸で道場を開いた。のちに豊前小倉藩主・小笠原忠政に仕えた。
-

高遠頼継 (たかとうよりつぐ)
信濃の豪族。高遠家は諏訪信員を祖とする諏訪家の庶流。武田信玄と結び諏訪宗家を滅ぼす。諏訪家総領の座を欲して挙兵するも、信玄の攻撃を受けて滅んだ。
-

高梨内記 (たかなしないき)
真田家臣。娘は真田幸村の側室。九度山に真田昌幸・幸村父子が流されたときに同行。昌幸の死後も残って幸村に仕えた。大坂夏の陣で討死。
-

高梨秀政 (たかなしひでまさ)
信濃の豪族。政頼の子。上杉家に属す。主君・謙信の関東出兵の際には、謙信の居城・春日山城を守った。第四次川中島合戦の際には、上杉軍の先鋒を務めた。
-

高梨政頼 (たかなしまさより)
信濃の豪族。信濃中野小館に拠る。高梨家は清和源氏で、高井郡高梨に住んだ井上盛満を始祖とする。武田信玄の北信濃侵攻軍に敗れ越後の長尾景虎を頼った。
-

高梨頼親 (たかなしよりちか)
信濃の豪族。信濃中野小館に拠る。高梨家は清和源氏で、高井郡高梨に住んだ井上盛満を始祖とする。武田信玄の北信濃侵攻軍に敗れ越後の長尾景虎を頼った。
-

多賀山通続 (たかのやまみちつぐ)
備後の豪族。山内豊通の娘を娶る。尼子家からの独立をはかったため居城・蔀山城を攻められるが、大風雨のため落城を免れたという。のちに毛利家に仕えた。
-

高橋鑑種 (たかはしあきたね)
大友家臣。筑前宝満城主を務め、筑前の経略を担当する。のちに毛利家に通じて謀叛を起こし、大友家と毛利家が筑前を舞台に全面対決するきっかけを作った。
-

高橋紹運 (たかはしじょううん)
大友家臣。筑前岩屋城主。吉弘鑑理の次男。立花道雪と双璧をなした猛将。島津軍5万の軍勢を居城にてわずか7百の兵で迎撃、敵兵多数を道連れに玉砕した。
-

高橋統増 (たかはしむねます)
大友家臣。高橋紹運の子。九州征伐後は豊臣家に属す。関ヶ原合戦では兄・宗茂とともに西軍に属し、戦後改易された。大坂の陣には徳川方として参陣した。
-

高原次勝 (たかはらつぐかつ)
讃岐の豪族。次利の子。豊臣秀吉に仕え朝鮮派兵などに従軍。関ヶ原合戦では東軍に属し、以後徳川家に仕えた。大坂の陣後、残党追補のため小豆島に赴いた。
-

高原次利 (たかはらつぐとし)
讃岐の豪族。直島・男木島・女木島などの地を代々領した。豊臣秀吉が備中高松城を攻撃した際は、海陸の案内役を担当し、のちに備前児島郡で加増を受けた。
-

多賀秀種 (たがひでたね)
豊臣家臣。堀秀重の次男。関ヶ原合戦では西軍に属して大津城攻めに参加。戦後改易され、甥・堀秀治を頼った。のちに前田利常に仕え、大坂の陣に従軍した。
-

高森惟直 (たかもりこれなお)
肥後の豪族。高森城主。阿蘇家と島津家の説得を拒否し、大友家に属した。そのため島津軍が居城を攻撃、期待した大友家の援軍が無いまま戦うが、敗死した。
-

多賀谷重経 (たがやしげつね)
結城家臣。下妻城主。政経の子。豊臣秀吉の小田原征伐に参陣し、所領を安堵された。関ヶ原合戦で西軍に属したため改易され、放浪の末近江彦根で死去した。
-

高山右近 (たかやまうこん)
織田家臣。高槻城主。友照の子。父と同じくキリスト教に入信する。各地の合戦で活躍するが、後に改宗を拒否したため改易され、幕府の命で呂宋へ追放された。
-

高山友照 (たかやまともてる)
織田家臣。荒木村重に属して高槻城主となる。村重の謀叛に同調、村重の敗走後は越前の柴田勝家に預けられた。のち各地を流浪した。切支丹として著名。
-

多賀谷政広 (たがやままさひろ)
結城家臣。佐竹家や宇都宮家へ使者として赴くなど、外交面で活躍した。のちに徳川家康の次男・秀康の結城家入嗣を取りまとめ、豊臣秀吉に功を賞せられた。
-

高屋良栄 (たかやりょうえい)
一色家臣。良閑とも。満信・義清2代に仕えて多大な功績を挙げた。細川藤孝の丹後侵攻の際、細川興元に攻めらせ、討死した。
-

滝川一益 (たきがわかずます)
織田家臣。各地の合戦で活躍し「進むも退くも滝川」と称された。甲斐平定後、関東管領となる。本能寺の変後、北条軍と戦って惨敗し、以後は勢威を失った。
-

滝川辰政 (たきがわたつまさ)
一益の子。織田信包、浅野長政、石田三成らに仕える。関ヶ原合戦では小早川秀秋家臣として活躍するものちに出奔、縁あって池田輝政に仕えた。
-

滝川益重 (たきがわますしげ)
滝川家臣。一益の従兄弟。甥とも。本能寺の変後、一益とともに柴田勝家に属し北伊勢で羽柴秀吉軍と激戦を展開。のち秀吉に仕え、九州征伐などに従軍した。
-

田北鎮周 (たきたしげかね)
大友家臣。豊後蚊ノ尾城主。加判衆を務めた。耳川合戦の際、総大将・田原親賢が佐伯惟教の慎重論を支持した事に憤り先鋒として島津軍に突撃し、戦死した。
-

滝野吉政 (たきのよしまさ)
伊賀の豪族。柏原城主。貞清の子。織田信長の伊賀侵攻軍に対して、国内の豪族連合軍を率いて頑強に抵抗したが敗れ、戦後、筒井順慶に居城を明け渡した。
-

田鎖光守 (たぐさりみつもり)
田鎖家は奥州の名族・閉伊源氏の宗家で南部家と争っていた。豊臣秀吉の奥州仕置により南部信直に属す。遠征の留守中南部家に居城・田鎖城を破却された。
-

竹内久盛 (たけうちひさもり)
美作の豪族。一ノ瀬城主。宇喜多直家の美作侵攻軍に敗れ、その臣下となる。戦場における組み討ちを基本とした日本最古の柔術流派・竹内流柔術を創始した。
-

武田勝頼 (たけだかつより)
甲斐の戦国大名。信玄の四男。家督相続後は強硬策で領国を広げるが、長篠合戦での大敗により家臣団が瓦解。織田軍に追い詰められ、天目山で自害した。
-

武田信玄 (たけだしんげん)
甲斐守護。信虎の嫡男。苛烈な政策に反対して父を追放、当主となる。精強な騎馬軍団を率い、臨機応変の知略で織田信長を苦しめた。通称「甲斐の虎」。
-

武田信廉 (たけだのぶかど)
信虎の三男。次兄・信繁の死後、親族衆の筆頭として長兄・信玄を補佐。容貌が信玄に似ていたため、影武者も務めた。画才があり、人物画などの作品を残す。
-

武田信実 (たけだのぶざね)
安芸武田家11代当主。光和の死後、若狭武田家より当主に迎えられた。尼子家に属すが、尼子家が郡山合戦で敗れたあと毛利軍の攻撃を受け出雲に逃亡した。
-

武田信繁 (たけだのぶしげ)
信虎の次男。文武に優れて人望も高く、兄・信玄の副将として活躍した。川中島合戦で本陣を守って奮戦、戦死した。後年「まことの武将」と高く評価される。
-

武田信重 (たけだのぶしげ)
安芸武田家臣。光和の甥。光和の死後、若狭武田家より迎えられた信実と家督を争い、敗れた。主家滅亡時に戦死した。子・竹若丸はのちの安国寺恵瓊である。
-

武田信豊 (たけだのぶとよ)
信繁の子。信濃小諸城主。川中島合戦で父が戦死したため、家督を継ぐ。父譲りの軍才をもって主君・勝頼を補佐した。織田信長の甲斐侵攻の際、謀殺された。
-

武田信豊 (たけだのぶとよ)
若狭守護。元光の子。細川晴元に協力して三好長慶と戦うが、家臣・粟屋右京亮を失う。のちに子・義統と不和になり近江に逃れるが、和議成立後に帰国した。
-

武田信虎 (たけだのぶとら)
甲斐守護。甲斐を平定するが、その苛烈な政策方針に反発した嫡男・信玄によって駿河に追放された。以後は各地を放浪し、甲斐に再び戻ることはなかった。
-

武田光和 (たけだみつかず)
安芸武田家10代当主。佐東銀山城主。尼子家に属した。たびたび大内家に攻められるが、家臣団の奮闘で城を守る。しかしのちに家臣団の離反を自ら招いた。
-

武田元明 (たけだもとあき)
若狭守護。義統の長男。朝倉義景に攻められ、越前に幽閉される。朝倉家滅亡後は若狭に帰国した。本能寺の変後は明智光秀に属すが、光秀の死後、殺された。
-

武田元光 (たけだもとみつ)
若狭守護。後瀬山城を築き居城とする。管領・細川高国の要請により上洛するが三好・柳本軍に敗れ、将軍・足利義晴を奉じて近江に逃れた。和歌に優れた。
-

武田義統 (たけだよしずみ)
若狭守護。信豊の子。父と和睦したあとに家督を継ぐ。のち義弟・足利義昭が頼ってくるが、内紛が相次いでいたため、義昭を奉じての上洛は果たせなかった。
-

武田義信 (たけだよしのぶ)
信玄の長男。川中島合戦などで活躍。妻の実家・今川家攻略に反対し、謀叛を企むが失敗する。東光寺に幽閉され、2年後に死去した。自害とも病死ともいう。
-

竹中重門 (たけなかしげかど)
豊臣家臣。半兵衛重治の嫡男。関ヶ原合戦では東軍に属し、粕子山中で小西行長を捕らえた。歌道・文筆に長じ、のちに豊臣秀吉の一代記「豊鏡」を著した。
-

竹中重利 (たけなかしげとし)
竹中半兵衛の従兄弟。豊臣秀吉の馬廻。関ヶ原合戦では黒田官兵衛に誘われ東軍につく。戦後大分城を与えられ、港や城下を整備。現在の大分の基礎を作った。
-

竹中重義 (たけなかしげよし)
重利の長男。徳川秀忠により長崎奉行に抜擢された。キリシタン弾圧に努め、残酷な拷問を考案した。秀忠死後、密貿易関与が発覚。切腹させられた。
-

竹中半兵衛 (たけなかはんべえ)
斎藤家臣。わずか16人で主家の居城・稲葉山城を乗っ取る。その卓抜した知略を羽柴秀吉に見込まれ、軍師となった。秀吉の中国攻めに従軍し、陣中で病没。
-

竹腰正信 (たけのこしまさのぶ)
徳川家臣。母・お亀の方が徳川家康の側室となり徳川義直を産んだため召し出され、義直の付家老となった。徳川秀忠の前で砲術を披露し1万石を加増された。
-

竹俣慶綱 (たけのまたよしつな)
上杉家臣。揚北衆の一人。謙信に仕えて歴戦する。御館の乱では景勝を支持して武田家との取次役を務めた。越中魚津城の守将として織田勢と戦い、討死した。
-

多功長朝 (たこうながとも)
宇都宮家臣。多功城主。主君・尚綱が戦死した戦いに従軍し、奮戦した。1558年の上杉・小山・結城連合軍との戦いでは先鋒を破り、連合軍を後退させた。
-

多功房朝 (たこうふさとも)
宇都宮家臣。長朝の子。那須家との五月女坂の戦いで先鋒として奮戦した。北条家との合戦では、他の城が落とされる中、敵軍を撃退して多功城を守った。
-

多胡戊敬 (たこときたか)
尼子家臣。彼の作った『多胡辰敬家訓』にある「命は軽く、名は重く」の一説は有名である。その言葉通り、尼子家への忠誠を貫き通して討死した。
-

田坂全慶 (たさかぜんけい)
小早川家臣。田坂家は土倉夏平(小早川家8代当主・貞平の次男)を祖とする小早川家の庶流。小早川隆景の宗家相続に強く反対したため、のちに謀殺された。
-

田尻鑑種 (たじりあきたね)
筑後の豪族。鷹尾城主。龍造寺隆信に仕え、三池鎮実攻めで先鋒を務めた。一時隆信と不和になるが、間もなく和解。朝鮮派兵に従軍し「高麗日記」を著した。
-

多田満頼 (ただみつより)
武田家臣。甲陽五名臣の1人。美濃の出身。信濃虚空蔵山の砦において、地獄の妖婆・火車鬼を退治したという伝説を持つ。夜襲の采配は家中随一と評された。
-

立花誾千代 (たちばなぎんちよ)
立花道雪の娘。家督を継ぎ立花城主となり、立花宗茂を夫に迎えた。父譲りの武勇を誇り、関ヶ原合戦で宗茂が留守の間は自ら兵を率いて城を守ったと伝わる。
-

立花道雪 (たちばなどうせつ)
大友家臣。立花城西城督。落雷で歩行不能となるが、輿に乗って常に大友軍の先陣を切り「鬼道雪」の異名をとった。生涯を軍陣で過ごした、家中随一の猛将。
-

立花宗茂 (たちばなむねしげ)
大友家臣。高橋紹運の子。立花道雪の娘を娶る。豊臣秀吉に「忠義と剛勇は鎮西一」と評された。関ヶ原合戦で西軍に属して改易されるが、のち旧領に復した。
-

立原久綱 (たちはらひさつな)
尼子家臣。甥・山中幸盛とともに、尼子勝久を擁して主家再興をはかる。播磨上月城落城後、毛利軍に捕えられるが、脱出して上洛した。のちに阿波へ赴いた。
-

立石正賀 (たていしまさよし)
長宗我部家臣。伊予三滝城攻めなどで功を立てた。関ヶ原合戦で敗れた際は降伏の使者を務める。主家改易後は肥後細川家に仕えた。のち「長元記」を著した。
-

楯岡満茂 (たておかみつしげ)
最上家臣。湯沢城主。関ヶ原合戦の際には小野寺家の攻撃を受けたが、孤軍奮闘して居城を守り抜いた。知行は最上家臣団の中で最高の4万8千石を領した。
-

伊達阿南 (だておなみ)
伊達晴宗の長女。二階堂盛義の正室。蘆名盛隆、二階堂行親の母。行親死後、須賀川城主となり、甥・伊達政宗と対立。落城後は岩城常隆、佐竹義宣を頼った。
-

伊達小次郎 (だてこじろう)
伊達輝宗の次男。幼名は竺丸。蘆名家の後継者候補と目されたこともあったが蘆名義広にその座を奪われた。家中の争いの末、実兄・伊達政宗に斬られる。
-

伊達実元 (だてさねもと)
伊達家臣。稙宗の三男。越後上杉家に入嗣する予定だったが、兄・晴宗の阻止により天文の大乱が起こった。乱中は稙宗に属すが、乱の終息後は晴宗に仕えた。
-

伊達成実 (だてしげざね)
伊達家臣。実元の子。「武」の面で主君の政宗を補佐した伊達家中随一の猛将。「英毅大略あり」と評された。晩年には徳川家光に奥州の軍談を語っている。
-

伊達忠宗 (だてただむね)
政宗の次男。父の死後家督を継ぎ、仙台藩2代藩主となる。徳川将軍家との関係を固めるなどして仙台藩の地位を盤石のものとし、「守成の賢君」と評された。
-

伊達稙宗 (だてたねむね)
伊達家14代当主。奥州探題を獲得し、婚姻外交を駆使して版図を拡大。三男・実元の越後上杉家入嗣問題で嫡男・晴宗と対立し、天文の大乱を引き起こした。
-

伊達輝宗 (だててるむね)
伊達家16代当主。晴宗の次男。相馬家とたびたび争う。嫡男・政宗に家督を譲った翌年、二本松義継に拉致され、救援に来た伊達軍の銃撃に巻き込まれ死去。
-

伊達晴宗 (だてはるむね)
伊達家15代当主。稙宗の嫡男。父と対立して天文の大乱を引き起こすが、終息後に家督を相続。父と同じく、婚姻外交を駆使して伊達家の地位を不動にした。
-

伊達秀宗 (だてひでむね)
政宗の長庶子。秀吉のもとで元服し、一字を賜って秀旨と名乗る。大坂の陣では徳川方に属し、武功を上げて伊予宇和島10万石を拝領、藩祖となった。
-

伊達政宗 (だてまさむね)
伊達家17代当主。輝宗の嫡男。瞬く間に周辺諸国を切り従えて24歳で奥州に覇を唱え「独眼竜」と畏怖された。権謀術数で豊臣・徳川両政権を生き抜いた。
-

伊達盛重 (だてもりしげ)
伊達家臣。伊達晴宗の十男。国分家を継ぐ。1599年、病と称して岩出山城に出仕せず、叛意を疑われたため出奔。姉の嫁ぎ先である佐竹家に身を寄せた。
-

田中忠政 (たなかただまさ)
吉政の四男。家督を継ぎ、筑後柳川2代藩主となる。開拓に努め、キリシタンを保護した。大坂夏の陣で家臣から豊臣側に味方すべきとの意見が出て遅参した。
-

田中吉興 (たなかよしおき)
吉政の三男。兄・吉次の廃嫡後、病弱との理由で、家督は弟・忠政が継いだ。弟が死し無嗣断絶となると、近江野洲など2万石を与えられ田中家の名跡を継ぐ。
-

田中吉次 (たなかよしつぐ)
吉政の長男。豊臣秀吉、秀次に仕えた。奥州仕置では下間頼廉と協力し、奥州一揆の本願寺門徒対策を行う。のち父と対立して出奔し、廃嫡された。
-

田中吉政 (たなかよしまさ)
豊臣家臣。はじめ宮部継潤に属す。豊臣秀次の家老を務め三河岡崎5万石を領した。関ヶ原合戦では東軍に属し石田三成を捕らえ、筑後柳川32万石を領した。
-

谷忠澄 (たにただずみ)
長宗我部家臣。知略に優れ、外交を担当した。豊臣秀吉の四国征伐軍と戦うが、抗戦は無理と判断して主君・元親に和睦を勧め、主家を滅亡の危機から救った。
-

谷衛友 (たにもりとも)
豊臣家臣。小田原征伐など主な戦いに従軍した。関ヶ原合戦では、西軍に属して小野木公郷とともに行動するが、東軍に寝返り、本領を安堵された。
-

種子島恵時 (たねがしまさととき)
島津家臣。種子島の領主。薩摩市来城攻めなどで活躍。大隅の豪族・禰寝家と争い、一時屋久島に逃れた。種子島に漂着したポルトガル船から鉄砲を入手した。
-

種子島時堯 (たねがしまときたか)
島津家臣。種子島の領主。恵時の嫡男。大隅の豪族・禰寝家と抗争した。種子島に漂着したポルトガル船から鉄砲を入手し、分析・改良して国産化に成功した。
-

種子島久時 (たねがしまひさとき)
島津家臣。種子島の領主。時堯の次男。兄・時次が早世したため、主君・義久の加冠で元服し、家督を継いだ。鉄砲隊を率いて各地で活躍し、武名を轟かせた。
-

田原重綱 (たはらしげつな)
北畠家臣。浜田城主。滝川一益軍の攻撃で父・元綱が戦死し、美濃に逃れる。のち織田信雄に属すが、小牧長久手合戦の際、美濃加賀野井城の戦いで戦死した。
-

田丸直昌 (たまるなおまさ)
蒲生家臣。田丸城主。主君・氏郷の妹を娶った。のちに美濃岩村4万石を領す。関ヶ原合戦では西軍に属して改易され、越後へ追放されるが、のちに許された。
-

田村顕盛 (たむらあきもり)
田村家臣。義顕の子。小野城主。主君・清顕の死後、相馬家と結び、伊達家と結んだ田村月斎らと対立。敗れて居城に籠もったが、伊達軍に攻められ降伏した。
-

田村清顕 (たむらきよあき)
陸奥の豪族。三春城主。隆顕の子。近隣の高倉城を攻略し、また佐竹家と結んで蘆名家の長沼城を攻めるなど、盛んに活動した。娘・愛は伊達政宗に嫁いだ。
-

田村隆顕 (たむらたかあき)
陸奥の豪族。三春城主。伊達稙宗の娘を娶る。伊達家の内紛(天文の大乱)の際は舅・稙宗に与力した。佐竹義重・石川昭光の連合軍を破ったのちに急逝した。
-

田村友顕 (たむらともあき)
田村家臣。隆顕の子。1584年8月、兄・清顕に従って出陣し、大内定綱と戦うが敗れ、戦死した。子・宗顕はのちに田村家の家督を継いだ。
-

田村宗顕 (たむらむねあき)
陸奥の豪族。友顕の子。伯父・清顕に子がなかったため、伊達政宗の後援で田村家を継いだ。豊臣秀吉の奥州征伐で所領を没収され、その後は伊達家に仕えた。
-

田村義顕 (たむらよしあき)
陸奥の豪族。盛顕の子。岩城常隆の娘を娶る。1504年に三春城を築き居城とした。田村家は坂上田村麻呂の玄孫・古哲が田村姓を称したのに始まるという。
-

多目元忠 (ためもとただ)
北条家臣。北条氏康の軍師。北条五色備の「黒備」を率いる。河越夜戦で深追いした氏康を呼び戻すため、独断で全軍に退却の号令を発し、氏康を救った。
-

多羅尾光俊 (たらおみつとし)
甲賀の土豪。道賀斎と号す。甲賀五十三家に列する。本能寺の変の際、徳川家康を護衛した。のち羽柴家に仕えたが、関白秀次粛清に連座して失脚。
-

田原紹忍 (たわらじょうにん)
大友家臣。義兄弟・宗麟の側近として国政に参画。耳川合戦の際は総大将を務めるが、諸将の統制が取れずに大敗を喫した。関ヶ原合戦の際、九州で戦死した。
-

田原親盛 (たわらちかもり)
大友家臣。宗麟の三男。耳川合戦の際は豊後に残った。おもに豊前方面で活動する。戸次川合戦に従軍するが、島津軍に敗れた。主家改易後は細川家に仕えた。
-

知久頼元 (ちくよりもと)
信濃の豪族。阿島城主。武田信玄の伊那谷侵攻軍に対し最後まで抵抗するが、敗れて降伏し、信州先方衆の一員となる。しかし、のちに信玄により殺された。
-

千坂景親 (ちさかかげちか)
上杉家臣。越後国針盛城主。上杉謙信の死後、御館の乱では上杉景勝に与する。外交面で活躍し、関ヶ原合戦後には本庄繁長と共に徳川家との和睦に尽力した。
-

千々石ミゲル (ちぢわみげる)
大村家臣。名は紀員。キリシタンでミゲルは洗礼名。大村純忠の甥。遣欧使節正史となるが帰国後に棄教。のち主君・喜前に疎まれ、失意のうちに没した。
-

千葉邦胤 (ちばくにたね)
千葉家29代当主。胤富の三男。反北条であった兄・良胤が廃嫡されたため、家督を継ぐ。北条氏政の娘を娶った。のちに叱責を逆恨みした近臣に暗殺された。
-

千葉重胤 (ちばしげたね)
千葉家31代当主。邦胤の嫡男。北条氏政の子・直重が千葉家30代当主となったため、人質として小田原城にあった。北条家の滅亡後は下総国に隠棲した。
-

千葉胤富 (ちばたねとみ)
千葉家27代当主。昌胤の次男。周辺の佐竹、里見家が上杉家と結ぶ中で、北条家と結んだ。のちに上杉・結城連合軍の攻撃を受けるが、撃退に成功している。
-

千葉親胤 (ちばちかたね)
千葉家26代当主。利胤の嫡男。父の死後、家督を継ぐ。母は北条氏康の娘だが北条家に対抗する考えを持っていたため氏康によって幽閉され、殺害された。
-

千葉利胤 (ちばとしたね)
千葉家25代当主。昌胤の子。父の死後家督を継ぐが翌年に死去した。妻は北条氏康の娘。当時は宿老・原家の力が強く「千葉は百騎、原は千騎」といわれた。
-

千葉昌胤 (ちばまさたね)
千葉家24代当主。第一次国府台合戦の際は、北条軍に属して戦った。千葉家は桓武平氏の一族で、平安時代末期に下総国千葉郷を領した平常重を始祖とする。
-

千村良重 (ちむらよししげ)
木曾家臣。主家改易後、関ヶ原合戦の際に徳川家康に招かれ、家臣となる。徳川秀忠軍の先導役を務め、また木曾を守る西軍の石川貞清を討つなど活躍した。
-

中馬重方 (ちゅうまんしげかた)
島津家臣。三州一の大力。島津義弘お気に入りの家臣で多くの逸話を残す。関ヶ原合戦に参陣。島津の退き口で奮戦。伊勢路退却時、義弘に馬印を捨てさせた。
-

長寿院盛淳 (ちょうじゅいんもりあつ)
島津家臣。高野山や根来寺で修業を積み鹿児島安養院の住職となる。のちに家老となって国政に参画した。関ヶ原合戦で主君・義弘の影武者となり、戦死した。
-

長宗我部国親 (ちょうそかべくにちか)
土佐の戦国大名。岡豊城主。父・兼序の死後、一条房家を頼り、房家の援助により居城に復帰。婚姻外交と積極的な富国策で長宗我部家の再興に生涯を捧げた。
-

長宗我部親忠 (ちょうそかべちかただ)
長宗我部元親の三男。土佐の豪族・津野家の家督を継ぐ。父が弟・盛親に家督を譲ったあと幽閉される。関ヶ原合戦後、久武親直の讒言により盛親に殺された。
-

長宗我部親吉 (ちょうそかべちかよし)
兼序の子。父の死後、兄の国親に従い長宗我部家の再興に尽力。さらに甥の元親を支えて四国統一に貢献した。秀吉による四国征伐の際は阿波を守ったが敗退。
-

長宗我部信親 (ちょうそかべのぶちか)
元親の嫡男。織田信長の偏諱を賜る。文武に優れ、人望を集めた。豊臣秀吉の九州征伐に従軍し、豊後戸次川合戦で戦死した。元親は非常に落胆したという。
-

長宗我部元親 (ちょうそかべもとちか)
土佐の戦国大名。岡豊城主。国親の子。剽悍の一領具足衆を率い、瞬く間に周辺諸国を制圧。10数年で四国統一を成し遂げ「土佐の出来人」の異名をとった。
-

長宗我部盛親 (ちょうそかべもりちか)
元親の四男。関ヶ原合戦で西軍に属して改易され、京で寺子屋を開く。のち大坂城に入り、藤堂高虎軍を壊滅させるなど活躍したが、大坂落城後、斬首された。
-

長宗我部康豊 (ちょうそかべやすとよ)
元親の末子。大坂の陣では兄・盛親に従い豊臣方で奮戦。戦後、安倍晴明の子孫を名乗って駿府へと逃れ、城主・酒井忠利の命を救ってその家臣となった。
-

長続連 (ちょうつぐつら)
畠山家臣。畠山七人衆に名を連ねた。温井・三宅一党の叛乱鎮圧に活躍し、重臣筆頭として畠山家の実権を握る。のちに織田信長に通じ、上杉謙信に討たれた。
-

長連龍 (ちょうつらたつ)
畠山家臣。続連の次男。父と兄・綱連の死後、還俗して家督を継いだ。織田信長に従属して福水城主となり、旧領を回復した。のちに前田利家の与力となった。
-

津軽建広 (つがるたけひろ)
津軽家臣。元の名は大河内江春。医者として北条家に仕える。北条滅亡後、津軽為信に登用され婿養子となるが、お家騒動で追放となり、江戸で御典医となる。
-

津軽為信 (つがるためのぶ)
弘前藩初代藩主。大浦為則の娘を娶る。主家・南部家から独立し、17年かけて津軽を統一した。豊臣秀吉の小田原征伐に参陣し、正式に津軽の領主となった。
-

津軽信建 (つがるのぶたけ)
津軽家臣。津軽為信の嫡男。津軽家は為信の活躍で南部家から独立を果たし、関ヶ原の功でその地位を確固たるものにしたが、信建は父に先だって病死した。
-

津軽信枚 (つがるのぶひら)
弘前藩2代藩主。為信の三男。幼い頃に父の勧めで受洗した。2人の兄が幼くして世を去ったため父の死後家督を継ぐ。弘前城を築くなど、藩の基礎を固めた。
-

筑紫惟門 (つくしこれかど)
肥前の豪族。五箇山城主。少弐家に属し大内家臣・陶興房に攻められ敗れる。大内家滅亡後は秋月文種とともに毛利元就に属すが、大友軍に攻められ自害した。
-

筑紫広門 (つくしひろかど)
肥前の豪族。五箇山城主。惟門の子。毛利・大友・龍造寺・島津家の間で離合集散を繰り返し、のちに豊臣秀吉に降る。関ヶ原合戦で西軍に属して改易された。
-

佃十成 (つくだかずなり)
加藤嘉明家臣。関ヶ原合戦では伊予に残り、毛利家の後援で蜂起した河野残党と村上元吉軍を撃退。その功で6千石を領し、松山城に佃郭を与えられた。
-

津田算長 (つださんちょう)
日本最古の砲術・津田流砲術の祖。監物と称す。種子島時堯から砲術を学ぶ。のちに堺の鍛冶・芝辻清右衛門に鉄砲の製造技術を伝え、堺を鉄砲生産地とした。
-

津田重久 (つだしげひさ)
細川家臣。主家の滅亡後は、三好家や足利将軍家などを経て明智光秀に仕え、山崎合戦に従軍した。光秀の死後は豊臣秀吉に仕え、賤ヶ岳合戦などに従軍した。
-

津田秀政 (つだひでまさ)
織田家庶流。信長に仕えて滝川一益の与力となる。一益の没落後は信雄、秀吉、家康に仕えた。旗本としては大身の4千石を扶持され、90歳の長寿を得た。
-

土橋重治 (つちばししげはる)
紀伊の豪族。兄・守重を殺した鈴木重朝とともに豊臣秀吉に招かれるが、応じなかった。のち徳川家を経て北条家に仕える。北条家の滅亡後は毛利家に仕えた。
-

土橋守重 (つちばしもりしげ)
紀伊の豪族。4人の子とともに石山本願寺に籠城して戦い、信長軍を苦しめた。のちに石山本願寺を退去するが、所領に戻って抵抗を続けたため、謀殺された。
-

土持親佐 (つちもちちかすけ)
県土持家15代当主。松尾城主。伊東家と抗争を繰り広げ、門川城を奪われるが伊東軍を夏田で破って奪還。のちに高千穂の領主・三田井家の仲介で和睦した。
-

土持親成 (つちもちちかなり)
県土持家16代当主。親佐の子。松尾城主。歴代当主の中でもまれにみる文武両道に優れた名将と評されていた。島津家と結ぶが、大友軍の攻撃に敗れ、自害。
-

土屋昌恒 (つちやまさつね)
武田家臣。金丸虎義の子。土屋家の家督を継ぐ。甲斐天目山において主君・勝頼を守って孤軍奮闘し、戦死した。その奮闘ぶりは「片手千人斬り」と呼ばれた。
-

筒井定次 (つついさだつぐ)
豊臣家臣。慈明寺順国の子。叔父・順慶の養子となり、家督を継ぐ。のち素行不良のため改易された。大坂冬の陣の際、大坂方に内通した罪で自害させられた。
-

筒井順慶 (つついじゅんけい)
大和の国衆。順昭の嫡男。父・順昭の夭逝により2歳で家督を継ぐ。松永久秀と争い、居城・筒井城を追われたが、のちに織田信長に従属して勢力を回復した。
-

筒井順興 (つついじゅんこう)
大和の国衆。友好関係にあった越智家が一向宗徒に攻められると、援軍を派遣してこれを破る。近隣の国衆と姻戚関係を結び、筒井家の勢力拡大を図った。
-

筒井順弘 (つついじゅんこう)
筒井家臣。筒井順興の四男。福須美家の家督を継ぐ。兄・順昭の娘を娶った。順昭死去の際は、一族とともに影武者・黙阿弥を立てて順昭の死を秘したという。
-

筒井順国 (つついじゅんこく)
筒井家臣。筒井順興の三男。慈明寺家の家督を継ぐ。兄・順昭の娘を娶った。順昭死去の際は、一族とともに影武者・黙阿弥を立てて順昭の死を秘したという。
-

筒井順昭 (つついじゅんしょう)
大和の国衆。順興の嫡男。はじめ木沢長政と結んで畠山稙長と戦うが、長政の敗死後は稙長と結んだ。越智家を破るなど筒井家の勢力を拡大するが、夭逝した。
-

筒井順政 (つついじゅんせい)
順興の次男。兄・順昭の死後、その嫡子である順慶が後を継ぐが、幼い順慶を補佐する後見となる。のちに島清興と共に三好家と争い、敗れて領国を追われた。
-

筒井定慶 (つついじょうけい)
豊臣家臣。福須美順弘の子。叔父・順慶の養子となる。従兄弟・定次の改易後、家督を継いだ。大坂夏の陣で城方に居城を落とされて逃亡し、のちに自害した。
-

角隈石宗 (つのくませきそう)
大友家臣。主君・宗麟の軍師を務めた。戸次鎮連を弟子に持つ。宗麟の日向遠征に際して延期を進言したが拒否されたため、秘伝の書を焼いて出陣、戦死した。
-

津野定勝 (つのさだかつ)
一条家臣。土佐七雄の一・津野家当主。基高の子。鳥坂峠合戦に従軍。長宗我部元親が一条家からの離反を要求するも拒絶。長宗我部派の家臣に追放された。
-

津野基高 (つのもとたか)
土佐七雄の一・津野家当主。幼くして家督を相続したため、一条基房の攻撃を受ける。太平家や本山家と結んで抵抗したが、ついには屈服。その傘下に入った。
-

妻木煕子 (つまきひろこ)
明智光秀の妻。玉(ガラシャ)の母。流浪の身で貧窮した光秀を、自らの髪を亮って助けたという逸話が残る。二人は仲睦まじく、光秀は側室を置かなかった。
-

妻木広忠 (つまきひろただ)
明智家臣。妻木城主。妻木家は、美濃守護・土岐家の庶流。姪・煕子(弟・範煕の娘)は主君・光秀に嫁ぐ。山崎合戦で光秀が敗れた際、近江坂本で自害した。
-

妻木頼忠 (つまきよりただ)
明智光秀の妻・熙子の属子。一族が山崎合戦の後自刃し家督を継ぐ。森長可に攻められその傘下に降るがのち独立。関ヶ原合戦で東軍に属し田丸直昌と戦った。
-

手島興信 (てしまおきのぶ)
吉川家臣。幼少の頃より主君・興経に仕える。興経が隠退する際は、これに従った。のちに吉川元春の舅・熊谷信直らの襲撃を受け、興経とともに殺害された。
-

寺崎盛永 (てらさきもりなが)
越中の豪族。願海寺城主。早くから神保家に仕え、敵対勢力を討つなど活躍。のち織田家に属すが、上杉家に寝返ったため攻撃を受け敗北し、自害させられた。
-

寺崎行重 (てらさきゆきしげ)
越中の豪族。願海寺城主。神保家に従っていたが、長尾景虎に攻められて討死した。家督を継いだ盛永は長尾家に属し、天神林合戦で飯田利忠を撃破した。
-

寺崎良次 (てらさきよしつぐ)
葛西家臣。峠城主。金沢良通の子。寺崎時胤の養子。実家が謀叛を起こした際、良次は葛西軍に従った。後に河﨑合戦で戦死した。
-

寺沢広高 (てらざわひろたか)
豊臣家臣。朝鮮派兵の際、肥前名護屋城の普請を担当。主君・秀吉の側近として兵力輸送や補給、船舶の運航統制などを行った。関ヶ原合戦では東軍に属した。
-

寺島職定 (てらしまもとさだ)
神保家臣。池田城主。椎名家との交渉を担当し、また民政などにも活躍した。主家内紛の際は神保長住とともに武田方に属し、上杉謙信の攻撃を受けて敗れた。
-

天童頼貞 (てんどうよりさだ)
最上家庶流。最上八楯盟主。頼長の弟。義光の義父。義守・義光の間で争いが起こると義守派として戦った。頼貞死後、延沢満延が裏切り、天童家は滅亡した。
-

天童頼長 (てんどうよりなが)
最上家庶流。最上八楯盟主。伊達稙宗が侵攻してくると激しく抵抗するが、強大な軍事力に屈した。義守が幼くして当主になると、盟主としてこれを補佐した。
-

土居清晴 (どいきよはる)
西園寺家臣。伊予大森城主。西園寺十五将の1人。清良の父。当主・実充の信頼を得てその娘を娶るが、大友家との戦いで父・清宗と共に討死した。
-

土居清宗 (どいきよむね)
西園寺家臣。伊予大森城主。西園寺十五将の1人。土佐一条家や大友家の侵攻軍をたびたび撃退し、主君・実充から厚い信頼を受けた。大友家との戦いで戦死。
-

土居清良 (どいきよよし)
西園寺家臣。伊予大森城主。西園寺十五将の1人。一時土佐へ逃れるが、土佐一条家の援助で復帰し、各地で活躍した。知略勇武で知られ「清良記」を著した。
-

土居宗珊 (どいそうさん)
土佐一条家臣。放蕩三昧の主君・兼定に対してたびたび諫言を行うが、兼定の勘気を蒙り手討ちにされた。これが家臣の離反を招き、兼定追放の一因となった。
-

問田隆盛 (といだたかもり)
大内家臣。石見守護代を務めた。陶晴賢の謀叛では晴賢に同調し、主家を継いだ義長に仕えた。晴賢の居城・若山城に滞在中に杉重輔の襲撃を受け、戦死した。
-

土井利勝 (どいとしかつ)
徳川家臣。水野信元の子。徳川家康の落胤という説もある。秀忠・家光と将軍2代に仕えて老中・大老などを歴任。江戸幕府の基盤安定に多大な功績を残した。
-

土肥政繁 (どいまさしげ)
越中の豪族。弓庄城主。上杉謙信の死後は織田家に属す。のちに再び上杉家に属したため、佐々成政に越中を追われた。上杉景勝の越中侵攻では先鋒を務めた。
-

東郷重位 (とうごうしげただ)
島津家臣。島津義久に従い京に上洛した際に、天寧寺の善吉和尚から剣術を学び薩摩自顕流(示現流)を創始した。のち島津家久の剣術指南役を務めた。
-

東禅寺勝正 (とうぜんじかつまさ)
大宝寺家臣。義長の弟。主君・義氏の死後、兄から尾浦城代に任じられる。のちに十五里ヶ原で本庄繁長に敗れ、戦後、繁長の暗殺をはかるが失敗、討たれた。
-

東禅寺義長 (とうぜんじよしなが)
大宝寺家臣。はじめ前森蔵人と名乗る。最上義光と結んで謀叛を起こし、主君・義氏を討った。義光の命で庄内の仕置を行うが、本庄繁長と戦って敗死した。
-

藤堂高次 (とうどうたかつぐ)
高虎の嫡男。父の死後伊勢津藩32万石を継ぐ。年貢増収による藩財政安定を目指し新田開発を進めたが、幕府への普請費用の負担増により財政は悪化した。
-

藤堂高虎 (とうどうたかとら)
徳川家康ほか7人の主君に仕え、主君を変える度に知行を増やし、伊勢安濃津32万石を領す。合戦では常に先鋒を務め奮戦、また多くの城の普請を担当した。
-

藤堂高刑 (とうどうたかのり)
藤堂家臣。高虎の甥。関ヶ原合戦で大谷吉継の家臣・湯浅五助を討ち取る活躍を見せる。大坂の陣にも出陣するが、長宗我部盛親隊の猛攻を受けて討死。
-

藤堂高吉 (とうどうたかよし)
高虎の養子。実父は丹羽長秀。様々な戦で活躍するが、高虎に実子・高次が生まれると家を出て家臣となり、伊勢名張に領地を得る。高次には疎まれたという。
-

十市遠勝 (とおちとおかつ)
大和の国衆。遠忠の子。筒井家に属すが松永久秀に降った。三好三人衆と久秀が対立すると、三好方に属して内部分裂を起こす。久秀の攻勢に押され降服した。
-

十市遠忠 (とおちとおただ)
大和の国衆。竜王山城主。はじめ木沢長政と結んだ筒井家と争うが、のちに和睦し、長政の死後、勢力を伸ばした。和歌や連歌、書に通じた文人としても著名。
-

遠山景前 (とおやまかげさき)
美濃の豪族。景友の子。岩村城主。八幡神社の社殿を造営したり、菩提寺の大円寺に僧を招くなど、領内の統治に尽力。大円寺は武田軍の攻撃により焼亡した。
-

遠山景任 (とおやまかげとう)
美濃の豪族。岩村城主。織田信長の叔母を娶る。武田家臣・秋山信友に岩村城を攻撃されると信長に援軍を依頼、援軍の将・明智光秀とともに武田軍と戦った。
-

遠山綱景 (とおやまつなかげ)
北条家臣。江戸衆筆頭。連歌師・宗牧を居城・江戸城に招き、連歌会を催した。第二次国府台合戦の際には先鋒を務めて里見軍と激戦を繰り広げ、戦死した。
-

遠山友勝 (とおやまともかつ)
美濃の豪族。苗木城主。遠山家は遠山庄を領した加藤景朝(源頼朝に仕えた景廉の子)を祖とする。のちに「遠山七家」が諸城に拠って東美濃に勢威を張った。
-

遠山友忠 (とおやまともただ)
美濃の豪族。苗木城主。友勝の子。織田家に従って武田家と戦う。信玄の娘婿・木曾義昌を織田家に寝返らせた。のちに森長可と争って出奔、徳川家康を頼る。
-

遠山友政 (とおやまともまさ)
美濃の豪族。苗木城主。友忠の子。金山城主・森長可と争って居城を出奔し、徳川家康を頼る。関ヶ原合戦では東軍に属して河尻秀長を破り、居城を奪還した。
-

遠山秀友 (とおやまひでとも)
徳川家臣。友政の長男。刑部少輔。父の死により後を継いで美濃苗木藩2代藩主となる。大坂城番や江戸城本丸奥の間普請手伝いを務めた。
-

冨樫晴貞 (とがしはるさだ)
野々市城主。稙泰の子。父が享徳の錯乱により能登に逃れたあと、家督を継ぐ。織田信長の越前侵攻軍に通じたため、一揆勢に居城を攻撃され敗北、自害した。
-

戸川秀安 (とがわひでやす)
宇喜多家臣。宇喜多三老の1人。明禅寺合戦や児島八浜合戦など多くの合戦に従軍し、主君・直家の創業を助けた。のちに筆頭家老を務め、国政にも参画した。
-

戸川達安 (とがわみちやす)
宇喜多家臣。秀安の嫡男。朝鮮派兵などで活躍した。熱心な日蓮宗徒で、切支丹の長船綱直らと対立。のちに内乱を引き起こして主家を退去、徳川家に仕えた。
-

常田隆永 (ときだたかなが)
武田家臣。真田幸隆の弟。常田家の養子となり、幸隆と共に各地を転戦。信玄の命により上野国長野原城を守るが、上杉軍の攻撃を受け、戦死した。
-

土岐為頼 (ときためより)
里見家臣。万喜城主。家中屈指の戦上手といわれ「万喜少弼」と呼ばれて恐れられた。第二次国府台合戦後に里見家を離反、北条家に属して里見家と戦った。
-

土岐政頼 (ときまさより)
美濃守護。父・政房の死後、家督を継ぐが、弟・頼芸を擁立する西村勘九郎(斎藤道三)の攻撃を受け敗北、越前に逃れた。のち美濃に戻るが、間もなく死去。
-

土岐頼次 (ときよりつぐ)
松永家臣。頼芸の次男。兄・頼栄が父の勘気を蒙ったため嫡子となる。父とともに国を追われ、松永久秀に仕えた。久秀の死後は豊臣家を経て徳川家に仕えた。
-

土岐頼芸 (ときよりのり)
美濃守護。家臣・斎藤道三と結んで兄・政頼を追放し、家督を継ぐ。しかし、のちに道三に美濃を追われた。一時和睦して帰国するが再び追放され、流浪した。
-

土岐頼春 (ときよりはる)
北条家臣。万喜城主。為頼の子。父の死後、家督を継ぐ。武田信栄や里見義康の攻撃をたびたび受けるが、居城を守り通す。小田原落城の直前に消息を絶った。
-

土岐頼元 (ときよりもと)
徳川家臣。頼芸の四男。父の追放後は斎藤道三の扶助を受ける。斎藤家の滅亡後は武田・豊臣家に仕え、関ヶ原合戦の後に徳川家康に属し、所領を安堵された。
-

得居通幸 (とくいみちゆき)
村上通康の長男。弟・来島通総とともに羽柴秀吉に通じたため、毛利・河野連合軍の攻撃を受けたが、撃退。以後水軍を率いて秀吉の合戦で活躍した。
-

徳川家光 (とくがわいえみつ)
徳川幕府3代将軍。秀忠の次男。参勤交代制の確立、武家諸法度の改定、鎖国の実施など、のちに「寛永の治」と呼ばれる政治を行い、幕府の安定を図った。
-

徳川家康 (とくがわいえやす)
江戸幕府の創始者。広忠の子。桶狭間の合戦後に自立。織田家との同盟、豊臣家への従属を経て勢力を拡大する。関ヶ原合戦で勝利を収め征夷大将軍となった。
-

徳川秀忠 (とくがわひでただ)
家康の三男。関ヶ原合戦の際、中山道からの進軍を真田昌幸に阻まれ、父の不興を買う。しかし、凡庸篤実な人柄を父に見込まれ、江戸幕府2代将軍となった。
-

徳川光圀 (とくがわみつくに)
頼房の三男。「黄門漫遊記」で有名であるが、実際には関東から出たことはなかった。全国から学者を招き、歴史書「大日本史」を編纂した。
-

徳川義直 (とくがわよしなお)
家康の九男。徳川御三家の一・尾張藩の藩祖で「剛」と評された。学問を好んで儒教を奨励。産業振興、税制整備、治水などを行い、藩政の基礎を固めた。
-

徳川頼宣 (とくがわよりのぶ)
家康の十男。徳川御三家の一・紀州藩の藩祖。血気盛んで「勇」と評された。大坂の陣で後方の陣に置かれたことを、涙を流して悔しがったという。
-

徳川頼房 (とくがわよりふさ)
家康の十一男。徳川御三家の一・水戸藩の藩祖で「才」と評された。幼少より才気溢れ、家康の寵愛を受けた。家康に希望を尋ねられ「天下」と答えたという。
-

徳田重清 (とくだしげきよ)
加賀の豪族。岩淵・千代城主。志摩守と称す。加賀一向一揆軍の中心人物。織田信長の加賀侵攻軍に抵抗するが、柴田勝家に討たれ、首級は安土に送られた。
-

徳永寿昌 (とくながながまさ)
柴田家臣。賤ヶ岳合戦の際、主君・勝豊とともに豊臣秀吉の傘下に入る。秀吉の死後、朝鮮に渡って全軍に撤退命令を伝えた。関ヶ原合戦では東軍に属した。
-

徳永昌重 (とくながまさしげ)
徳川家臣。寿昌の長男。関ヶ原合戦で東軍に属し、大坂の陣にも参戦した。禁裏普請、大坂城石垣普請の助役を務めたが作業遅延を理由に改易された。
-

徳姫 (とくひめ)
織田信長の娘。松平信康に嫁ぐ。夫の乱行と姑・築山殿の武田家内通を父に訴える。その結果、姑と夫はともに父の命で殺された。夫の死後は実家に戻った。
-

督姫 (とくひめ)
徳川家康の次女。北条氏直に嫁ぐ。北条家の滅亡後は池田輝政の妻となった。輝政の先妻の子・利隆を毒入りの饅頭で殺害しようとしたという逸話が残る。
-

徳山則秀 (とくやまのりひで)
柴田家臣。主君・勝家に従って越前一向一揆制圧戦に参加し、小松城主となる。勝家の死後は豊臣秀吉に属す。以後、丹羽家、前田家を経て徳川家康に仕えた。
-

土佐林禅棟 (とさばやしぜんとう)
大宝寺家臣。土佐林家は羽黒山別当職を務めたが、のちに大宝寺家に別当職を奪われたという。禅棟は上杉家との関係を深めたため主家と対立、滅ぼされた。
-

戸沢政重 (とざわまさしげ)
戸沢家臣。戸沢家14代当主・征盛の三男。安房守と称す。小館に住んだといわれる。のちに仏門に入っていた戸沢盛重(甥・道盛の嫡男)を養子とした。
-

戸沢政房 (とざわまさふさ)
戸沢家臣。南部家出身という。九戸の乱で主君・光盛に従って出陣し奮戦。豊臣秀次の目にとまり、大坂に召し出されるが、秀次事件により帰国した。
-

戸沢政盛 (とざわまさもり)
戸沢家20代当主。角館城主。盛安の庶子。叔父・光盛の死後、家督を継ぐ。関ヶ原合戦では上杉家の酒田城を攻略、大坂の陣では小田原城などを守備した。
-

戸沢道盛 (とざわみちもり)
戸沢家16代当主。角館城主。秀盛の嫡男。父の死により、幼少の身で家督を継ぐ。その後、若くして隠居し、孫・政盛の移封先である常陸小河城で死去した。
-

戸沢盛重 (とざわもりしげ)
戸沢家17代当主。角館城主。道盛の嫡男。病弱のため、早くに家督を弟・盛安に譲って出家する。のちに還俗し戸沢政重(祖父・秀盛の弟)の養子となった。
-

戸沢盛安 (とざわもりやす)
戸沢家18代当主。角館城主。道盛の三男。積極的な軍事行動で戸沢家最大の版図を築いた。「夜叉九郎」の異名をとった反面、慈悲深い一面もあったという。
-

豊島重村 (としましげむら)
安東家臣。畠山重忠の末裔という。1570年、湊安東家臣の下刈右京らと結んで謀叛を起こすが、安東愛季の軍勢に敗れ、妻の実家・仁賀保家を頼った。
-

戸田氏鉄 (とだうじかね)
徳川家臣。一西の長男。美濃大垣藩主。大坂城修築なので活躍。新田開発や治水に努めた。教育にも力を注ぎ、修養を説いた『八道集』『四角文修』を著した。
-

戸田氏信 (とだうじのぶ)
氏鉄の長男。父の隠居により、美濃大垣2代藩主となる。二条城石垣普請で功があった。また藩の法令集「定帳」を制定するなど藩政の安定化に努めた。
-

富田景政 (とだかげまさ)
朝倉家臣。富田流剣術の始祖。勢源と号した。主家滅亡後は前田家に仕え、数々の合戦で活躍した。隠居後は七尾城の守将となり、豊臣秀次に剣術を指南した。
-

戸田勝成 (とだかつなり)
丹羽家臣。主君・長秀の死後、豊臣家に属す。小田原征伐などに従軍し、功を立てた。関ヶ原合戦で西軍に属して戦死。東軍の諸将にもその死を惜しまれた。
-

土田御前 (どたごぜん)
織田信秀の妻。織田信長、信勝、お市らの生母。奇矯な振舞いの目立つ信長を愛さず、信勝を寵愛したという。信長死後は織田信雄、信包らに引き取られた。
-

富田重政 (とだしげまさ)
前田家臣。景政の婿養子。「名人越後」の異名をとった富田流剣術の剣豪。末森城の戦いで一番槍の功を立てたほか、関ヶ原合戦や大坂の陣などでも活躍した。
-

戸田尊次 (とだたかつぐ)
徳川家臣。忠次の長男。小牧長久手合戦に出陣。関ヶ原合戦では越前丸岡城攻略に功があった。大坂夏の陣で徳川頼宣に属して出陣。陣中にて病に倒れた。
-

戸田忠能 (とだただよし)
徳川家臣。尊次の長男。関ヶ原合戦、大坂の陣に従軍。父が大坂の陣で病没したため後を継ぎ、三河田原藩2代藩主となるが、飢饉などに苦しめられた。
-

十時連貞 (とときつらさだ)
立花家臣。沈勇にして剛直と評された。関ヶ原合戦後に主家改易となるも、あくまで立花宗茂に従う。大坂の陣で豊臣に招かれたが辞退し宗茂への忠を通した。
-

百々安信 (どどやすのぶ)
豊臣家臣。山崎合戦などに従軍した。のち織田秀信の家老となる。関ヶ原合戦では秀信に東軍加担を説くが失敗、西軍に属し敗れた。戦後は山内一豊に仕えた。
-

戸蒔義広 (とまきよしひろ)
戸沢家臣。戸蒔城主を務めた。関ヶ原合戦の際は主家とともに東軍に属す。東軍の最上義光に従って出陣し、西軍の小野寺義道軍と戦うが、角間川で戦死した。
-

富田一白 (とみたいっぱく)
豊臣家臣。幼少より信長に仕えるが、本能寺の変後、秀吉に従う。小牧・長久手の戦いで信雄・家康との講和に奔走するなど、外交面で秀吉に大きく貢献する。
-

富田氏実 (とみたうじざね)
蘆名家臣。四天の宿老の1人。主君・盛隆の死後、伊達政宗の弟・小次郎を後継に推すが敗れた。摺上原合戦では留守居を務め、主力の敗北後、伊達家に降る。
-

富田隆実 (とみたたかざね)
蘆名家臣。氏実の子。摺上原合戦では先鋒を務め、伊達軍の本陣に迫るなど奮戦した。敗北後は主君・盛重に従い常陸に逃れるが、間もなく盛重の元を去った。
-

富田長繁 (とみたながしげ)
朝倉家臣。主家滅亡後は織田家に仕え、長島一向一揆の討伐戦で功を立てた。のちに織田家での待遇に不満を持って謀叛を起こすが、味方に撃たれて死去した。
-

富田信高 (とみたのぶたか)
豊臣家臣。関ヶ原合戦では東軍に属し、伊勢安濃津城に籠城するが敗れ、高野山に登る。戦後、召し出されて伊予宇和島12万石を領すが、のちに改易された。
-

富永忠安 (とみながただやす)
吉良家臣。父・正安は永正(1504~1521)年間に牟呂城を築いた。松平広忠は父・清康の死後、各地を転々とするが、その際、一時牟呂城に在城した。
-

富永直勝 (とみながなおかつ)
北条家臣。北条五色備の「青備」を率いる。一門以外では最も高禄を受けたといわれる。第二次国府台合戦で先陣を務めるが、里見義弘の反撃で戦死した。
-

朝長前安 (ともながさきやす)
大村家臣。純盛(純利の甥)の子。朝鮮派兵では平壌から撤退する日本軍の殿軍を務める主君・喜前に従い、抜群の戦功を立てた。のち江戸で外交を担当した。
-

朝長純利 (ともながすみとし)
大村家臣。筆頭家老を務めた。フロイスの書簡にも名が見える。朝長家は大村家譜代の臣で、弟・純安は横瀬の宗門奉行を務めるなど、主家を助けて活躍した。
-

鳥屋尾満栄 (とやのおみつひで)
北畠家臣。石見守と称す。「文武を得、知略深し」と評された。織田信雄が北畠家一族を謀殺したあと、北畠具親とともに旧臣を糾合して兵を挙げるが、戦死。
-

豊臣秀次 (とよとみひでつぐ)
豊臣家臣。豊臣秀吉の義兄・三好吉房の子。秀吉から関白職を譲られるが、のちに「殺生関白」と呼ばれるほどの乱行を振るまい、謀叛の罪で自害させられた。
-

豊臣秀長 (とよとみひでなが)
秀吉の異父弟。兄の片腕として、その覇業に貢献する。温和で人望高く、秀吉と他大名との折衝役を務めた。秀吉に先立って死去、諸将にその死を惜しまれた。
-

豊臣秀吉 (とよとみひでよし)
戦国一の出世頭。織田信長に仕え、傑出した人望と知略を武器に活躍し、頭角を現す。本能寺の変後、明智光秀、柴田勝家らを次々と倒し、天下に覇を唱えた。
-

豊臣秀頼 (とよとみひでより)
秀吉の次男。関ヶ原合戦後は摂河泉65万石という一大名の地位に転落する。大坂の陣では母・淀殿らの過剰な庇護を受け、一度も出陣できぬままに自害した。
-

豊永勝元 (とよながかつもと)
長宗我部家臣。主君・元親に従って阿波統一戦で活躍、また奉行として国政に参画した。関ヶ原合戦後、浪人となる。大坂の陣では旧主・盛親に従って戦った。
-

鳥居成次 (とりいなりつぐ)
徳川家臣。元忠の三男。伏見城で父を西軍に攻め殺されていたが、関ヶ原合戦後父の仇である石田三成を預けられた時に丁重に遇し、三成を感じ入らせた。
-

鳥居元忠 (とりいもとただ)
徳川家臣。関ヶ原合戦の際に主君・家康の命で伏見城に籠城する。13日間の攻防戦の末、城兵とともに玉砕した。その忠節は「三河武士の鑑」と称賛された。
-

内藤興盛 (ないとうおきもり)
大内家臣。宿老として大内義隆を支えるが、義隆に疎まれ、政治から遠ざけられた。陶晴賢の謀叛を黙認し、直後に隠居した。文人として声望があった。
-

内藤清成 (ないとうきよなり)
徳川家臣。主君・家康の小姓を務める。家康の信頼を受け、秀忠の傅役や関東総奉行などを歴任した。しかし、のちに家康の勘気を受けて籠居の身となった。
-

内藤国貞 (ないとうくにさだ)
管領細川家臣。丹波守護代。細川氏綱・三好長慶と結んで主君・晴元と争う。のち松永久秀らとともに晴元方の波多野晴通を攻めるが、晴元軍に敗れ戦死した。
-

内藤如安 (ないとうじょあん)
豊臣家臣。フロイスに洗礼を受ける。朝鮮派兵では小西行長とともに講和交渉を行った。徳川家康が禁教令を出した際、高山重友とともにマニラに追放された。
-

内藤隆春 (ないとうたかはる)
大内家臣。主家滅亡後は毛利家に属す。姉が毛利隆元の妻という縁から重用され防長両国の治安維持に尽力した。晩年は大坂に上り、中央情勢を本国に伝えた。
-

内藤忠興 (ないとうただおき)
徳川家臣。政長の長男。血気盛んで、大坂の陣で留守居を命じられたが、本多正信に参陣を頼み込み、徳川家康に喜ばれた。新田開発や検地で税収を強化した。
-

内藤信成 (ないとうのぶなり)
徳川家臣。幼少より家康に仕える。三方ヶ原の戦いでは殿軍を務めた。関ヶ原合戦後に駿府、次いで近江長浜を治める。一説には家康の異父弟だという。
-

内藤信正 (ないとうのぶまさ)
徳川家臣。信成の長男。小牧長久手合戦や小田原征伐、九戸政実の乱の鎮圧に参陣。大坂の陣では尼崎を守り、戦後、伏見城代、大坂城代を務めた。
-

内藤昌豊 (ないとうまさとよ)
武田家臣。武田四名臣の1人。武田信繁の死後、主君・信玄の副将格となる。武略に優れ、箕輪城主として西上野方面の治政を担当した。長篠合戦で戦死した。
-

内藤政長 (ないとうまさなが)
徳川家臣。家長の長男。小牧長久手合戦で初陣。父が伏見城で戦死すると後を継ぐ。関ヶ原合戦では上杉景勝に備え、大坂夏の陣では江戸城留守居を務めた。
-

直江景綱 (なおえかげつな)
上杉家臣。与板城主。主君・謙信の信頼厚く、側近として内政・外交に辣腕を振るう。のちに謙信の旧名・景虎から一字を拝領し、実綱から景綱へと改名した。
-

直江兼続 (なおえかねつぐ)
上杉家臣。筆頭家老を務めた。豊臣秀吉の評価は高く、陪臣ながら出羽米沢30万石を領した。関ヶ原合戦の際は西軍に属し、徳川家康に「直江状」を送った。
-

永井直勝 (ながいなおかつ)
徳川家臣。家康の長男・信康に仕えたが信康が自刃させられたために一時出奔。のちに再仕官して小牧長久手の戦いでは池田恒興を討ち取る大功を挙げている。
-

中井久包 (なかいひさかね)
尼子家臣。尼子晴久の傅役。毛利家の吉田郡山城攻めで大敗。小笠原長雄救援に失敗。毛利家の出雲侵攻に月山富田城で頑強に抵抗。戦後、病没した。
-

長尾景広 (ながおかげひろ)
北条家臣。憲景の次男。主家滅亡後は浪人となり、加賀に住む。関ヶ原合戦の直前に上杉家に仕える。大坂の陣には旗本の将として出陣し、前備を務めた。
-

長尾種常 (ながおたねつね)
神戸家臣。山路紀伊守正幽の長男で、はじめ山路久之丞と称す。織田信雄が神戸城を接収したあとは福島正則に仕え、関ヶ原合戦では岐阜城外で西軍と戦った。
-

長尾為景 (ながおためかげ)
越後守護代。越後守護や関東管領を討ち国政を掌握。しかし、のちに越後守護・上杉定実と対立、上杉方国人の叛乱を招いた。出陣は百回を超えるという猛将。
-

長尾憲景 (ながおのりかげ)
山内上杉家臣。惣社長尾家の出身で、白井長尾家当主・景誠が殺されたため、その遺跡を継いだ。主家滅亡後は上杉謙信に仕え、謙信の死後は北条家に属した。
-

長尾憲長 (ながおのりなが)
足利長尾家当主。関東管領・山内上杉家に仕え、家宰を務めた。足利高基の子・亀王丸(晴氏)が元服する際は、将軍・足利義晴からの一字拝領を依頼した。
-

長尾晴景 (ながおはるかげ)
越後の戦国大名。為景の嫡男。父の死後に家督を継ぐ。しかし病弱で統率力に欠けたため諸将から反発を受け、上杉定実の調停のもと弟・景虎に家督を譲った。
-

長尾房景 (ながおふさかげ)
長尾家臣。古志長尾家。豊前守と称す。1495年、父・孝景の隠居により家督を継ぐ。関東管領・上杉顕定が越後に侵攻した際は、主君・為景に従い戦った。
-

長尾房長 (ながおふさなが)
長尾家臣。魚沼郡上田荘を領した。上条定憲の乱に呼応し主家に敵対する。しかし定憲の戦死、越後守護・上杉定実の死去により劣勢となり、主家と和睦した。
-

長尾政景 (ながおまさかげ)
上杉家臣。房長の子。父とともに主家に敵対するが和睦し、主君・景虎の姉を娶った。その後は景虎を補佐して活躍するが、宇佐美定満と舟遊び中に溺死した。
-

長尾当長 (ながおまさなが)
足利長尾家当主。山内上杉家に仕えた。主君・上杉憲当(憲政)の偏諱を受けて「当長」を名乗った。由良成繁とともに上杉・北条両家の仲介に活躍した。
-

中川清秀 (なかがわきよひで)
池田家臣。茨木城主。和田惟政を討つなど活躍した。のち荒木村重に属す。村重の逃亡後は羽柴秀吉に属し、山崎合戦で戦功を立てた。賤ヶ岳合戦で戦死した。
-

中川久盛 (なかがわひさもり)
秀成の長男。母は秀成の父・清秀を討った佐久間盛政の娘・虎姫。豊後岡2代藩主。子孫は明治維新に至るまで加増・転封ともになく、代々岡藩を領している。
-

中川秀成 (なかがわひでなり)
豊臣家臣。清秀の次男。兄・秀政の死により家督を継ぎ、豊後岡7万石を領す。朝鮮派兵などに従軍した。関ヶ原合戦では東軍に属し、太田一吉の軍を破った。
-

長倉祐有 (ながくらすけなお)
伊東家臣。島津軍との戦いで敵将を討ち取る功を立て、伊東姓を賜る。主家の豊後退去後、日向に残る旧臣を糾合して一揆を企むが失敗した。耳川合戦で戦死。
-

長倉祐政 (ながくらすけまさ)
伊東家臣。島津軍との戦いで敵将を討ち取る功を立て、伊東姓を賜る。主家の豊後退去後、日向に残る旧臣を糾合して一揆を企むが失敗した。耳川合戦で戦死。
-

長倉義重 (ながくらよししげ)
佐竹家臣。長倉城主。義篤・義昭2代に仕える。1543年に勃発した相馬家との陸奥久保田合戦では、弟・義尚と共に義篤に従い、戦功を挙げた。
-

長坂信政 (ながさかのぶまさ)
松平家臣。通称は九郎。清康・広忠・家康の3代にわたって仕える。織田家との戦いで数多くの戦功を上げたため、清康から「血槍九郎」の異名を授かった。
-

長坂光堅 (ながさかみつかた)
武田家臣。勝頼の寵臣で、長篠合戦では跡部勝資とともに進撃を主張し、武田家の大敗を招いた。主家滅亡時に、織田信長に殺されたという。佞臣と評された。
-

長崎純景 (ながさきすみかげ)
大村家臣。キリシタン。西郷純堯らの攻撃を受け、大村純忠の勧めで所領の長崎をイエズス会に寄進した。のち大村家を去って田中吉政に仕えた。
-

長崎元家 (ながさきもといえ)
滝川一益の家臣だったが、本能寺の変後は織田信雄、豊臣秀吉と主君を変えた。秀吉の命により小早川秀秋の家臣となり関ヶ原合戦後は家康に出仕している。
-

長沢光国 (ながさわみつくに)
越中の豪族。森寺城主。上杉謙信の越中侵攻軍に降り、松波城を攻略するなど活躍し、穴水城主となる。謙信の死後、畠山家旧臣に攻められて敗れ、戦死した。
-

中島輝行 (なかじまてるゆき)
備中の豪族。経山城主。父・氏行が大内義隆に従って出雲に遠征した際は、居城を守った。氏行の留守を狙った浦上宗景に攻められるが、撃退に成功した。
-

中島元行 (なかじまもとゆき)
毛利家臣。経山城主。明禅寺合戦で戦死した父・輝行の跡を継ぐ。清水宗治の娘を娶り、宗治とともに各地の合戦で活躍した。のちに「中国兵乱記」を著した。
-

中条藤資 (なかじょうふじすけ)
上杉家臣。主君・為景が関東管領・上杉顕定と戦った際は、為景に従い各地で活躍した。一時背くが、間もなく帰参。のち川中島合戦に従軍し、感状を受けた。
-

長門広益 (ながとひろます)
蠣崎家臣。武勇に優れる。主君・季広の従兄弟に当たる蠣崎基広が謀叛を起こすと、基広を討ち取り、その首級を季広の元に持ち帰った。
-

長野稙藤 (ながのたねふじ)
長野工藤家14代当主。長野工藤家は、北畠家・関家らとともに勢州四家の一に数えられる。中伊勢をめぐって、北畠家と抗争、あるいは共闘を繰り返した。
-

長野具藤 (ながのともふじ)
長野工藤家16代当主。北畠具教の子。北畠家と長野家の和睦の際、長野家の養子となる。父とともに織田信長の伊勢侵攻軍と戦う。のち織田信雄に殺された。
-

長野業正 (ながのなりまさ)
山内上杉家臣。主家滅亡後も居城・箕輪城を守り、武田信玄の侵攻を6度に渡って撃退した。「業正がいる限り、上州には手は出せぬ」と信玄を嘆かせた智将。
-

長野業盛 (ながのなりもり)
山内上杉家臣。箕輪城主。業正の子。父の死後、家督相続。上野攻略を企む武田軍に徹底抗戦を挑み、死者1千6百余、負傷数千という損害を与え、自害した。
-

長野藤定 (ながのふじさだ)
長野工藤家15代当主。南伊勢の支配を巡って北畠家と争う。男子に恵まれず、のちに北畠具教の次男・具藤を養子として和睦した。以後は北畠家に属した。
-

中坊秀祐 (なかのぼうひですけ)
筒井家臣。家中で島清興と対立、主君・定次に讒言して清興を追放した。関ヶ原合戦後、政務を顧みない定次の所業を家康に訴えて筒井家を改易に追い込んだ。
-

中野宗時 (なかのむねとき)
伊達家臣。天文の大乱では主君・晴宗の参謀を務め、乱の終息後は家中で最大の勢力を誇った。輝宗の代に謀叛を起こすが敗れて逃亡し、流浪の末、餓死した。
-

永原松雲 (ながはらしょううん)
丹羽家臣。兵法、故実、和歌に通じた。同僚の南部無右衛門に憎まれて襲われた時、軽く柔術でいなし名を上げたが、浅井畷の戦いで後れを取り名を落とした。
-

永原孝治 (ながはらたかはる)
赤座吉家の子。父とともに前田利長に仕えた。大坂冬の陣では、真田丸の戦いで真田幸村に敗れ、大きな被害を出している。天下普請で前田家の奉行を務めた。
-

中村一氏 (なかむらかずうじ)
豊臣家臣。岸和田城主を務める。主君・秀吉の死後、三中老の1人となり、駿河府中14万石を領した。関ヶ原合戦では東軍に属すが、決戦の直前に病死した。
-

中村惟冬 (なかむらこれふゆ)
阿蘇家臣。甲斐親宣が病に倒れ出仕しなかった時、親宣がいないと会議が進まないと嘆いた。矢崎城代を務め、島津軍の侵攻を迎撃して討死した。
-

中村忠滋 (なかむらただしげ)
別所家臣。娘を人質に出すことで、羽柴軍を騙し討ちにして撃退した。三木城が落城した後、娘を犠牲にするほどの忠義を評価され、秀吉に召し抱えられた。
-

中村則治 (なかむらのりはる)
美作の豪族。岩屋城主。はじめ浦上家に属したが、尼子晴久の美作侵攻軍に降った。のちに尼子家から派遣された芦田秀家の子・正家の謀叛により謀殺された。
-

中村春続 (なかむらはるつぐ)
山名家臣。羽柴秀吉に降伏した主君・豊国を鳥取城から追い、毛利家より吉川経家を城主に招いた。しかし、秀吉の「渇え殺し」戦法によって敗れ、自害した。
-

中山家範 (なかやまいえのり)
北条家臣。北条氏照に仕えた。豊臣秀吉の小田原征伐に際しては、八王子城の二の丸を守り奮戦。前田利家が軍門に降るよう説得したがこれを拒否、自害した。
-

中山照守 (なかやまてるもり)
北条家臣。家範の子。主家滅亡後は徳川家康に仕える。関ヶ原合戦や大坂の陣に従軍し、のちに槍奉行となった。馬術の達人で、高麗八条流の奥義をきわめた。
-

中山信正 (なかやまのぶまさ)
浦上家臣。亀山城主。娘は宇喜多直家に嫁いだ。のちに島村盛実と談合して謀叛を企んだとの風聞により、主君・宗景の命を受けた娘婿・直家により殺された。
-

那古野勝泰 (なごやかつやす)
尾張斯波家臣。16、7歳の頃、簗田弥次右衛門と只ならぬ仲となる。のちに2人で織田信長に通じ、清洲城内の老臣を信長方につけるために画策したという。
-

名古屋山三郎 (なごやさんさぶろう)
蒲生家臣。絶世の美男。九戸政実討伐で一番乗りの功を立て「名古屋山三は一の槍」と謂われた。のちに森忠政に仕えたが、同僚と喧嘩して斬り殺された。
-

那須資景 (なすすけかげ)
下野那須藩主。資晴の嫡男。小田原征伐に遅参して改易された父に代わって5千石を領した。関ヶ原合戦では東軍に属した。大坂の陣にも参加し、功を立てた。
-

那須資胤 (なすすけたね)
下野の戦国大名。政資の次男。兄・高資の横死後、大関高増らの後見で家督を継ぐ。のちに高増ら上那須衆と対立して攻撃を受け敗北、隠居を条件に和睦した。
-

那須資晴 (なすすけはる)
下野の戦国大名。資胤の嫡男。薄葉ヶ原合戦で宇都宮軍に大勝し、近隣に武名を轟かせた。豊臣秀吉の小田原征伐の際に遅参したため、所領を没収された。
-

那須資房 (なすすけふさ)
下那須家当主。内紛で上那須家が断絶した後、家督を継ぎ上下那須家を統一。箒川の合戦で行った、白河結城家との縄引きが「大捻縄引」の起源とされる。
-

那須高資 (なすたかすけ)
下野の戦国大名。政資の嫡男。父と対立し、父と結ぶ宇都宮尚綱に攻められるが尚綱を討って撃退した。のち尚綱の子・広綱と芳賀高定の謀略に遭い横死した。
-

那須政資 (なすまさすけ)
下野の戦国大名。那須家は藤原道長の曾孫・資家が始祖。資隆の時、はじめて那須姓を称した。資隆の子が、屋島の合戦で扇の的を射抜いた与一宗隆である。
-

長束正家 (なつかまさいえ)
丹羽家臣。主家没落後は豊臣家に仕え、五奉行の1人となる。算術に通じ、主家の賦課収納の財政処理を担当した。関ヶ原合戦では西軍に属し、戦後自害した。
-

鍋島勝茂 (なべしまかつしげ)
肥前佐賀藩主。直茂の嫡男。関ヶ原合戦で西軍に属すが、巧みな事後処理で所領を安堵される。島原の乱の際は、多大な犠牲を払いながらも乱鎮圧に貢献した。
-

鍋島清久 (なべしまきよひさ)
龍造寺家臣。田手畷合戦の際、赤熊の毛を被り鬼面をつけた軍勢を率いて大内軍の側面を突き、主君・家兼の危難を救った。戦後、家兼から所領を与えられた。
-

鍋島清房 (なべしまきよふさ)
龍造寺家臣。清久の子。田手畷合戦において父とともに龍造寺軍を救い、龍造寺家純の娘を娶る。のち主君・隆信の母・慶誾尼と再婚し、主家との絆を深めた。
-

鍋島茂里 (なべしましげさと)
鍋島家臣。石井信忠の長男。器量を見込まれ鍋島直茂の養子となる。沖田畷合戦で初陣。勇ましい戦いぶりから鍋島家の戦法は茂里が務めることが定められた。
-

鍋島茂賢 (なべしましげまさ)
鍋島家臣。石井信忠の次男。茂里の弟。深堀家の養子となり、のちに鍋島姓を与えられた。関ヶ原合戦後の柳川の戦いでは兄とともに先峰を務め活躍した。
-

鍋島忠茂 (なべしまただしげ)
直茂の次男。関ヶ原合戦で兄・勝茂が西軍についたため、西軍の立花宗茂を攻めお家存続に尽力。徳川秀忠に寵愛され、幕府とのつながりで鍋島家に貢献した。
-

鍋島直茂 (なべしまなおしげ)
龍造寺家臣。清房の子。主家の発展に貢献した知勇兼備の将。主君・政家を後見して国政を執った。関ヶ原合戦で東軍に属し、戦後、肥前の支配権を獲得した。
-

浪岡顕範 (なみおかあきのり)
浪岡北畠家臣。具統の子。謀叛を起こした叔父・川原具信が兄・具運を殺害した際に、具信を討ったという。この事件以後、浪岡北畠家の勢力は急速に衰えた。
-

浪岡顕村 (なみおかあきむら)
浪岡北畠家当主。具運の子。安東愛季の娘を娶る。津軽為信に居城・浪岡城を落とされたため安東家を頼り、北畠弾正と改名した。落城時に自害したともいう。
-

浪岡慶好 (なみおかちかよし)
安東家臣。顕村の子。津軽為信に居城・浪岡城を奪われた父とともに安東家を頼る。のちに北畠右近と改名し、使者として豊臣秀吉のもとに赴くなど活躍した。
-

浪岡具運 (なみおかともかず)
浪岡北畠家当主。具統の子。寺社の修築などに力を注ぐが、そのために財政を逼迫させて内紛を引き起こし、川原御所を継いでいた叔父・川原具信に殺された。
-

浪岡具永 (なみおかともなが)
浪岡北畠家当主。顕具の子。浪岡北畠家は南北朝後期に北畠顕邦(顕家の曾孫)が入部したのが始まりといわれる。顕邦の子・顕義のときに浪岡城が築かれた。
-

浪岡具統 (なみおかともむね)
浪岡北畠家当主。具永の子。浪岡城を居城とし、浪岡御所と称された。近隣の大光寺家や大浦家などと協力して津軽地方を統治し、津軽の支配強化に努めた。
-

楢崎元兼 (ならざきもとかね)
三村家臣。月田山城主。弾正忠と称す。主君・家親の娘を娶る。毛利家が備中に侵攻した際は義兄・元親に背き、毛利家と結んだ宇喜多軍を居城に駐留させた。
-

成沢道忠 (なりさわみちただ)
最上家臣。成沢城主。氏家守棟の従弟。氏家光氏の父。柏木山合戦で最上義光と伊達輝宗が衝突すると、最上家の要衝である成沢城を守り、奮戦した。
-

成沢光氏 (なりさわみつうじ)
最上家臣。成沢家の出身で、守棟の跡を継いだ。関ヶ原合戦では、侵攻してきた上杉景勝軍を相手に奮戦する。家親が当主になると、領国の治政を担当した。
-

成田氏長 (なりたうじなが)
北条家臣。忍城主。長泰の嫡男。豊臣秀吉の小田原征伐では小田原城に籠城。居城は石田三成の水攻めに抗戦、落ちなかった。主家滅亡後は蒲生氏郷に仕えた。
-

成田氏宗 (なりたうじむね)
徳川家臣。長忠の次男。父に従い大坂夏の陣に参陣。翌年父が死ぬと、兄が既に死去していたため、家督を相続し、下野烏山藩2代藩主となった。
-

成田長忠 (なりたおさただ)
北条家臣。忍城主。長泰の次男。主家滅亡後は蒲生氏郷に仕える。兄・氏長の死後、その遺領を継いだ。関ヶ原合戦では東軍に属した。大坂の陣にも参陣した。
-

成田甲斐 (なりたかい)
成田氏長の娘。小田原攻めでは三宅高繁を討ち取るなど、石田三成率いる大軍から忍城を守る。東国一の美貌と謳われ、のちに羽柴秀吉の側室となった。
-

成田長親 (なりたながちか)
北条家臣。泰季の嫡男。小田原攻めでは忍城代である父が合戦直前に死去したため、防衛の指揮を執る。石田三成率いる大軍から甲斐姫とともに忍城を守った。
-

成田長泰 (なりたながやす)
山内上杉家臣。忍城主。主家滅亡後は上杉謙信に属した。しかし、謙信が鶴岡八幡宮に参拝した際、謙信の怒りを買ったため離反し、その後は北条家に属した。
-

成田泰季 (なりたやすすえ)
成田家臣。親泰の子。忍城の城代を務めた。1566年、兄・長泰が家督を長忠(長泰の次男)に譲ると宣言した際は、他の重臣らとともにこれに反対した。
-

成富茂安 (なりとみしげやす)
龍造寺家臣。各地の合戦で多くの戦功を立て、豊臣秀吉にもその武勇を認められた勇将。のちに肥前佐賀藩主・鍋島家に仕え、土木・水利事業などに従事した。
-

成松信勝 (なりまつのぶかつ)
龍造寺家臣。龍造寺四天王の1人。今山合戦で大友軍総大将を討つ功を立てた。沖田畷合戦に軍奉行として従軍、主君・隆信の戦死を聞くと敵陣に突入し戦死。
-

成瀬正成 (なるせまさなり)
関ヶ原で手柄を立て、和泉堺奉行に取立てられた。のち尾張・徳川義直の補佐に任ぜられ、大坂の陣では総堀の埋立てを指揮した。
-

南光坊天海 (なんこうぼうてんかい)
徳川家臣。比叡山で教学を究めた天台宗の僧。主君・家康の側近となり国政に辣腕を振るい「黒衣の宰相」と呼ばれた。明智光秀と同一人物との異説がある。
-

南条隆信 (なんじょうたかのぶ)
大崎家臣。中新田城主。大崎家内乱の際には居城を守備し、神技に等しい作戦と指揮で、見事に伊達政宗の軍勢を撃退。大崎家侍大将中の名将とたたえられた。
-

南条広継 (なんじょうひろつぐ)
蠣崎家臣。勝山館主。蠣崎季広の長女を娶った。のちに妻が弟の舜広、元広(季広の長男、次男)を毒殺した罪に連座して自害。「逆さ水松」の伝説を残した。
-

南条宗勝 (なんじょうむねかつ)
南条家7代当主。羽衣石城主。尼子経久の攻撃を受けて居城を追われ、浪人となる。のち毛利元就の援助を受けて居城の奪還に成功し、以後は毛利家に属した。
-

南条元清 (なんじょうもときよ)
南条家臣。南条宗勝の庶子。東伯耆の名門・小鴨家を継ぐ。朝鮮派兵の際、甥・元忠の讒言に遭い失脚し、小西行長に属す。関ヶ原合戦後は加藤清正に仕えた。
-

南条元忠 (なんじょうもとただ)
南条家9代当主。羽衣石城主。元続の嫡男。関ヶ原合戦で西軍に属して改易。のちに豊臣秀頼に属すが、大坂冬の陣の際に徳川軍への内通疑惑により殺された。
-

南条元続 (なんじょうもとつぐ)
南条家8代当主。羽衣石城主。宗勝の嫡男。豊臣秀吉に仕え、九州征伐などに従軍した。病のため弟・元清に政務を任すが、小田原征伐には病の身で参加した。
-

難波田憲重 (なんばだのりしげ)
扇谷上杉家臣。松山城主。居城を追われた主君・朝定を迎え北条家と戦った。北条家臣・山中主膳との戦は、和歌のやりとりがあった「風流合戦」として著名。
-

南部重直 (なんぶしげなお)
利直の三男。父の死後家督を継ぎ、陸奥盛岡藩2代藩主となった。祖父・信直の代から始まった盛岡城の築城工事を引き継ぎ、完成させた。
-

南部季賢 (なんぶすえかた)
安東家臣。宮内少輔と称した。安東家の外交官としてたびたび京都へ赴き、山科言継や織田信長と会見した。愛季が信長に馬と鷹を贈った際も使者を務めた。
-

南部利直 (なんぶとしなお)
南部家27代当主。信直の子。父の死後に家督を継ぐ。関ヶ原合戦では東軍に属し、最上家を救援した。領内の一揆を平定するなど、南部藩の基礎を築いた。
-

南部信直 (なんぶのぶなお)
南部家26代当主。石川高信の子。晴継(晴政の子)死後の御家騒動に勝ち、家督を継ぐ。九戸政実の乱などに苦しむが豊臣秀吉に接近して領内を統一した。
-

南部晴政 (なんぶはるまさ)
南部家24代当主。安信の子。将軍・足利義晴の偏諱を賜り、晴政と名乗る。三戸城を本拠に「三日月の丸くなるまで南部領」といわれる広大な版図を築いた。
-

南部無右衛門 (なんぶぶえもん)
丹羽家臣。加藤清正などに仕えた傍若無人な武辺もの。浅井畷の戦いで突出し危機に陥った江口正吉を永原松雲が見捨てる中、単身救出し、形勢を逆転させた。
-

南部政直 (なんぶまさなお)
利直の次男。利直が家臣・柏山明助を毒殺しようとした際、明助の警戒を払拭するため、あえて父の勧める毒酒を先に飲んで見せ、明助暗殺を成功させ死んだ。
-

南部安信 (なんぶやすのぶ)
南部家23代当主。政康の嫡男。弟(次男)・石川高信を津軽石川城主、弟(四男)・石亀信房を不来方城主とするなど一門を中心とする家臣団を作り上げた。
-

新関久正 (にいぜきひさまさ)
最上家臣。因幡守と称す。赤川の水を引く工事を行うが、主家改易により土井利勝預かりとなり、工事は中断。後年、用水堰は完成し「因幡堰」と呼ばれた。
-

新井田隆景 (にいだたかかげ)
大崎家臣。新井田城主。義隆の小姓を務めた。家中屈指の美少年で、同じく小姓の伊場野惣八郎と寵を争い、これがきっかけで大崎家の内乱が引き起こされた。
-

新野親矩 (にいのちかのり)
今川家臣。井伊直虎の伯父。井伊家当主・直親が謀殺された際、子・直政を保護した。井伊家の歴史上最大の危機を救ったと評される。遠州錯乱中に討死した。
-

新見国経 (にいみくにつね)
備中の豪族。新見家は承久の乱において戦功を立て、新見庄の地頭職となった新見資満を祖とする。尼子家に属し、多治部家や三村家と新見庄を巡って争った。
-

新見貞経 (にいみさだつね)
備中の豪族。国経の弟(子ともいう)。尼子家に属した。東寺領・相国寺領新見庄の代官請として、1543年から1566年の間、新見庄の経営にあたった。
-

新納忠元 (にいろただもと)
島津家臣。薩摩馬越城攻めや肥後経略など、各地の合戦で活躍し、島津家の看経所に名を残した4人のうちの1人。「二才咄格式定目」を著して子弟を戒めた。
-

二階堂輝行 (にかいどうてるゆき)
二階堂家17代当主。伊達家や蘆名家という強敵に挟まれ、苦境に立たされる。三春城主・田村清顕の軍によって支城を奪われるなど、威勢は振るわなかった。
-

二階堂晴行 (にかいどうはるゆき)
二階堂家17代当主。伊達家や蘆名家という強敵に挟まれ、苦境に立たされる。三春城主・田村清顕の軍によって支城を奪われるなど、威勢は振るわなかった。
-

二階堂盛義 (にかいどうもりよし)
二階堂家18代当主。はじめ蘆名盛氏と争うが、子・盛隆を人質に出して降伏。のちに盛隆が蘆名家を継いだため、援助を受けて二階堂家の勢力を回復した。
-

仁賀保誠政 (にかほしげまさ)
由利十二頭の一。仁賀保挙誠の次男。将軍・徳川家光の字を憚って光政から誠政に名を改めた。挙誠が没すると二千石を領したため、二千石家と称された。
-

仁賀保挙誠 (にかほたかのぶ)
由利十二頭の筆頭。文禄の役では肥前名護屋城に在陣した。会津征伐で功を立て徳川家康から感状を授かった。関ヶ原合戦では東軍に属し、所領を安堵された。
-

仁賀保挙晴 (にかほたかはる)
由利十二頭の一。最上義光と争う。欧州仕置で出羽由利郡南部の領有を認められた。関ヶ原合戦後、移封。しかし奮戦がのちに評価され、旧領に復した。
-

仁木義治 (にきよしはる)
細川家臣。勝瑞城下に住んだ。勝瑞城の落城後は隠棲するが、のちに蜂須賀家政に招かれ、その後は商人として家政に仕えた。のちに「昔阿波物語」を著した。
-

西尾忠永 (にしおただなが)
徳川家臣。大老・酒井忠世の弟。西尾吉次の養子となり後を継ぐ。大坂の陣では大和国や和泉国の警備を命じられ、兵士による略奪行為を取り締まった。
-

西尾嘉教 (にしおよしのり)
木下吉隆の次男という。祖父・光教の後嗣となる。大坂冬の陣に祖父とともに参陣。祖父の死により美濃揖斐藩を継ぎ、夏の陣では大和方面軍三番手を務めた。
-

仁科盛信 (にしなもりのぶ)
武田信玄の五男。信濃の豪族・仁科家の名跡を継ぐ。兄・勝頼の命により信濃高遠城を守る。織田信長軍に対し、頑強に抵抗したが衆寡敵せず敗北、自害した。
-

西野道俊 (にしのみちとし)
出羽の豪族で、西野館主。修理亮と称した。小野寺家に仕え、1586年に最上家と戦った有屋峠合戦や、1587年の唐松山合戦などに従軍し、活躍した。
-

西牟田鎮豊 (にしむたしげとよ)
筑後の豪族。西牟田城主。はじめ大友宗麟に属すが、宗麟の神仏破壊を厭い、蒲池鎮漣らとともに龍造寺隆信に属す。肥後攻めや戸原城攻めなどで功を立てた。
-

蜷川親長 (にながわちかなが)
足利家臣。主家滅亡後は長宗我部家に仕えた。関ヶ原合戦で長宗我部家が改易されたあと、一揆の鎮圧に活躍。のち故実に対する知識を買われ徳川家に仕えた。
-

二宮惟宗 (にのみやこれむね)
一条家臣。二ノ宮城主。房資の子。四万十川の戦いで長宗我部家に寝返った小島出雲守らに居城を攻められて落城。川原谷に逃れた後、自刃したという。
-

二宮経方 (にのみやつねかた)
吉川家臣。主君・興経が毛利元就の子・吉川元春に家督を譲って隠退する際、手島興信など10数名の家臣とともに、興経に従って移住した。
-

仁保隆慰 (にほたかやす)
大内家臣。奉行人を務めた。主君・義隆の死後は陶晴賢が擁立した大内義長に仕える。主家滅亡後は毛利家に属し、豊前門司城番と規矩郡代官職に任ぜられた。
-

二本松家泰 (にほんまついえやす)
二本松畠山家11代当主。村国の嫡男。居城・二本松城は、7代当主・満泰によって応永年間(1394~1427)に築かれた。別名を霞ヶ城という。
-

二本松常頼 (にほんまつつねより )
蘆名家臣。二本松義国の次男。高玉家を継ぎ、高玉城主を務めた。摺上原合戦の直前、伊達家臣・片倉景綱の降伏勧告を拒否して戦うが、衆寡敵せず戦死した。
-

二本松村国 (にほんまつむらくに)
二本松畠山家10代当主。政国の嫡男。二本松家は畠山義忠の未亡人を娶った畠山義純を始祖とし、奥州探題となった4代当主・高国以後、二本松と号した。
-

二本松義国 (にほんまつよしくに)
二本松畠山家13代当主。新城村尚の子であるが、二本松義氏の早世により、宗家の家督を継いだ。蘆名家と田村家が争った際には、講和の斡旋を行っている。
-

二本松義孝 (にほんまつよしたか)
義継の次男。二本松家滅亡後、会津に逃れ、蘆名家を頼る。蘆名家滅亡後は上杉家に仕え、慶長出羽合戦に参戦。その後会津に入った蒲生家、加藤家に仕えた。
-

二本松義継 (にほんまつよしつぐ)
二本松畠山家14代当主。義国の子。伊達政宗に攻められて降伏。その会見の席で政宗の父・輝宗を拉致し逃亡するが、政宗軍に追われ、輝宗と刺し違えた。
-

入田親誠 (にゅうだちかざね)
大友家臣。主君・義鑑の嫡男・義鎮の教育係を務めるが義鎮に疎まれ、義鎮の廃嫡を義鑑に進言、二階崩れの変を引き起こす。変後は逃亡し、肥後で殺された。
-

如春尼 (にょしゅんに)
今川氏親の正室。今川氏輝、義元の母。夫の死後、家督を継いだ氏輝を補佐し、女戦国大名と呼ばれた。義元や氏真の代にも政治に関与したとされる。
-

丹羽長重 (にわながしげ)
豊臣家臣。長秀の嫡男。越前北庄120万石を継ぐが、次第に減封され、関ヶ原合戦後は所領を失う。大坂の陣に従軍して活躍、陸奥白河10万石を領した。
-

丹羽長秀 (にわながひで)
織田家臣。「米五郎左」の異名をとる。安土城の普請奉行を務めるなど、行政面で活躍した。本能寺の変後は羽柴秀吉に属し、越前北庄120万石を領した。
-

温井景隆 (ぬくいかげたか)
畠山家臣。続宗の子。祖父・総貞の死後に逐電するが、主君・義綱の追放後に帰参。のち織田家に属す。本能寺の変後、所領回復を狙って挙兵するが敗死した。
-

温井続宗 (ぬくいつぐむね)
畠山家臣。総貞の子。父を軍事面で補佐し、温井家を家中最大の勢力に発展させた。父が主君・義綱に殺されたあと、一族とともに謀叛を起こすが、敗死した。
-

温井総貞 (ぬくいふささだ)
畠山家臣。和歌に造詣深く、主君・義総の寵愛を得る。遊佐家を倒して主家の実権を握り、領内の動揺を招く。のちに権力奪回を目指す主君・義綱に殺された。
-

沼田顕泰 (ぬまたあきやす)
上野の豪族。沼田城を築き居城とする。上杉謙信の関東侵攻軍に降った。のちに嗣子・朝憲を殺し末子・景義の擁立をはかったため家臣の反発を買い逐電した。
-

沼田景義 (ぬまたかげよし)
上野の豪族。顕泰の子。父が異母兄・朝憲を殺して家臣に反発された際、父とともに会津に逃れる。のちに沼田城奪回の兵を挙げるが、真田昌幸に謀殺された。
-

沼田麝香 (ぬまたじゃこう)
沼田祐光の妹という。細川幽斎に嫁ぎ、忠興らを産む。忠興の妻玉(ガラシャ)の影響でキリスト教に帰依。田辺城の戦いでは夫とともに具足を着け奮戦した。
-

沼田祐光 (ぬまたすけみつ)
津軽家臣。上野国沼田の出身。武者修業のため全国を行脚していた際に、為信の器量を見込んで仕官、その軍師となる。為信の津軽統一に多大な功績を残した。
-

沼田泰輝 (ぬまたやすてる)
上野の豪族。1519年、幕岩城を築き居城とする。この際、伊勢の外宮を勧請し、原田神明宮を建てた。沼田家は源頼朝に仕えた三浦義澄の末裔といわれる。
-

禰寝清年 (ねじめきよとし)
禰寝家15代当主。根占領主。肝付兼続らとともに島津勝久と島津忠良の間を仲裁するが、失敗。のちに兼続から大隅高隈城を譲られるが、やがて奪回された。
-

禰寝重長 (ねじめしげたけ)
禰寝家16代当主。根占領主。清年の嫡男。肝付家に従う。のちに島津家と単独講和し、肝付軍に攻められるが、島津家の援助で撃退した。対明貿易を行った。
-

禰寝重張 (ねじめしげひら)
禰寝家17代当主。根占領主。重長の嫡男。安芸守と称す。島津義久・義弘・忠恒の3代に仕えた。豊臣秀吉による検地が行われたあと薩摩吉利に転封された。
-

禰津元直 (ねづもとなお)
武田家臣。もとは信濃の豪族で、信虎と戦うが敗北。諏訪頼重を通じて所領安堵を受ける。のち長篠の戦いに出陣し、討死した。信玄の側室・禰津御寮人の父。
-

禰々 (ねね)
諏訪頼重の正室。武田信虎の三女。信玄の諏訪攻略によって夫が自害に追い込まれ、子の寅王も政争に巻き込まれる。心労が重なり16歳の若さで世を去った。
-

ねね (ねね)
高台院、北政所とも。秀吉の妻。妻としてだけでなく、朝廷との交渉など政治家としても秀吉を支えた。子はなかったが加藤清正ら多くの家臣を養育した。
-

納富信景 (のうとみのぶかげ)
龍造寺家臣。小河信安や福地信重らとともに家老職を務め、国政に参画した。また、江上家攻めや黒土原合戦、今山合戦など各地の合戦に従軍し、功を立てた。
-

野仲鎮兼 (のなかしげかね)
大内家臣。下毛郡代を務めた。主家滅亡後は大友家と争うが敗れ、家臣となる。豊臣秀吉の九州征伐後、豊前に入国した黒田孝高と戦うが敗北し、滅亡した。
-

野長瀬盛秀 (のながせもりひで)
紀伊の豪族。盛次の子。野長瀬家は八幡太郎義家の子・義忠の末裔という。豊臣秀吉の紀州征伐軍に抵抗するが敗れ、降伏した。のちに一族とともに殺された。
-

野々村幸成 (ののむらゆきなり)
豊臣家臣。北条攻めで功を挙げ、黄母衣衆に任じられる。秀吉の死後は秀頼に仕え、七手組の一員を務めた。大坂の陣で奮戦するも敗れ、自害した。
-

延原景能 (のぶはらかげよし)
浦上家臣。主家滅亡後は宇喜多家に仕える。花房職秀とともに三星城主・後藤勝元や飯岡城主・星賀藤内らの浦上家残党を討伐した。知勇兼備の士と評された。
-

延沢満延 (のべさわみつのぶ)
最上家臣。はじめ天童家に仕えたが、嫡男・康満に最上義光の娘・松尾を迎える条件で和睦した。大力剛勇の武将で、義光は内心脅威を感じていたという。
-

乃美景興 (のみかげおき)
小早川家臣。乃美家は乃美是景(小早川家11代当主・熈平の次男)を祖とする小早川家の庶流。小早川隆景の宗家相続を推進し、毛利元就から功を賞された。
-

乃美隆興 (のみたかおき)
小早川家臣。小早川家の庶流。毛利元就に乃美大方を嫁がせて協力体制を築き、主君・繁平を拘禁して、元就の三男・隆景を小早川家の当主にした。
-

乃美宗勝 (のみむねかつ)
毛利家臣。小早川水軍を統率した。厳島合戦の際は村上水軍を味方に引き入れ、毛利軍の勝利に貢献した。木津川口合戦では総大将を務め、織田水軍を破った。
-

野村直隆 (のむらなおたか)
浅井家臣。横山城主を務めた。主家滅亡後は豊臣家に仕える。鉄砲頭を務め、各地の合戦で活躍した。関ヶ原合戦では西軍に属し、伏見城攻撃に参加した。
-

拝郷家嘉 (はいごういえよし)
柴田家臣。大聖寺城主。北陸戦線で柴田勝家に従い、戦功を挙げる。賎ヶ岳の戦いでは羽柴軍を圧倒するが、羽柴秀吉の機転により劣勢に立たされて討死した。
-

垪和氏続 (はがうじつぐ)
北条家臣。伊予守と称す。松山衆の1人で、千貫文を与えられていた。駿河興国寺城主となり、駿河方面の守備を担当。1571年には武田軍の攻撃を退けた。
-

芳賀高定 (はがたかさだ)
宇都宮家臣。益子勝宗の子。芳賀高経の死後、芳賀家を継ぐ。壬生家に乗っ取られた宇都宮城を奪還し、宿老として国政に参画、主家の勢力回復に尽力した。
-

芳賀高武 (はがたかたけ)
宇都宮家臣。宇都宮広綱の三男。芳賀高継の跡を継ぐ。兄・国綱の片腕として活躍した。主家改易後は、伊勢内宮にたびたび主家再興の願文を奉納している。
-

芳賀高継 (はがたかつぐ)
宇都宮家臣。高経の次男。父の横死により益子領へ逃亡するが、のちに芳賀高定から家督を譲られて帰参。宿老として家中の内政・外交全般を取り仕切った。
-

芳賀高経 (はがたかつね)
宇都宮家臣。一族の者が宇都宮家に殺されたのを恨み、壬生綱房と結んで主君・興綱を討った。のちに皆川家と結んで挙兵するが、興綱の子・尚綱に討たれた。
-

垪和康忠 (はがやすただ)
北条家臣。氏続の弟。評定衆。越相同盟締結の際に使者を務め、厩橋城代として東上野を治めるなど、内政・外交面で活躍した。主家滅亡後は伊豆に隠棲した。
-

箸尾高春 (はしおたかはる)
筒井家臣。知行4万石を領し、主君・順慶の妹を娶った。筒井家の伊賀転封には従わず、豊臣秀長に属す。関ヶ原合戦後に所領を失い、のち大坂城に入城した。
-

初鹿野昌次 (はじかのまさつぐ)
武田家臣。川中島合戦において戦死した初鹿野源五郎の跡を継ぐ。主家滅亡後は徳川家康に仕え、小牧長久手合戦、小田原征伐、大坂の陣など各地で活躍した。
-

長谷川守知 (はせがわもりとも)
宗仁の子。豊臣秀吉に仕えた。関ヶ原合戦では石田三成の居城・佐和山城の守りにつくが、実は内応しており、東軍を城内に引き入れて石田一族を滅ぼした。
-

支倉常長 (はせくらつねなが)
伊達家臣。主君・政宗の命を受け、宣教師・ルイス=ソテロとともに慶長遣欧使節としてスペインなどを訪問。しかし目的を達成できず、8年後に帰国した。
-

畠山昭高 (はたけやまあきたか)
河内畠山家当主。高屋城主。政国の子。兄・高政が遊佐信教らに追放されたあと信教らに擁立されて家督を継ぐ。のちに信教の暗殺をはかるが、逆に殺された。
-

畠山高政 (はたけやまたかまさ)
河内守護。政国の子。三好家と和戦を繰り返した。のちに織田信長に降って河内半国を与えられるが、家臣・遊佐信教との争いに敗北し、紀伊岩室城に逃れた。
-

畠山稙長 (はたけやまたねなが)
河内守護。高屋城主。弟・長経が木沢長政・遊佐長教によって擁立された際、紀伊に逃亡。のち長経が殺されると、再び居城に戻り、河内守護に再補任された。
-

畠山政国 (はたけやままさくに)
河内守護。高屋城主。兄・稙長の死後、家督を継ぐ。細川晴元と細川氏綱が争った際は氏綱に属す。三好義賢らと舎利寺で戦った。のち紀伊岩室城で死去した。
-

畠山政繁 (はたけやままさしげ)
上杉家臣。畠山義続の次男。上杉謙信の養子となり上条家を継ぐ。上野・越中などを転戦した。謙信の死後、上杉景勝と対立して出奔、以後は徳川家に仕えた。
-

畠山義隆 (はたけやまよしたか)
能登の戦国大名。義綱の子。兄・義慶が当主となると、二本松伊賀守と名乗って義慶を補佐した。義慶の死後、畠山家の家督を相続するが、間もなく急死した。
-

畠山義続 (はたけやまよしつぐ)
能登守護。義総の嫡男。相次ぐ内乱で権力を失い、重臣の台頭を許す。子・義綱と協力して実権を回復するが、のちに重臣たちに反発され、能登を追放された。
-

畠山義綱 (はたけやまよしつな)
能登守護。義続の嫡男。父とともに実権の回復に尽力するが、重臣らに追放されて失敗に終わる。その後、何度も能登入国を試みるが、すべて失敗に終わった。
-

畠山義慶 (はたけやまよしのり)
能登の戦国大名。義綱の嫡男。祖父・義続と父が追放されたあと、幼年で重臣たちに擁立される。のちに重臣たちの派閥闘争に巻き込まれ、何者かに殺された。
-

畠山義総 (はたけやまよしふさ)
能登守護。七尾城を築く。能登では義総の治世30年間、政治的安定が続いた。教養人・義総を頼って、多くの公家が戦乱の京から逃れてきた。
-

波多野稙通 (はたのたねみち)
管領細川家臣。将軍・足利義稙の偏諱を受け、稙通と名乗る。主君・高国に与力して丹波一帯に一大勢力を築き上げた。のちに細川晴元に属し、高国と戦った。
-

波多野晴通 (はたのはるみち)
管領細川家臣。稙通の子。三好軍の度重なる攻撃を受ける。撃退に努めるがのちに松永久秀に降り、城を追われた。居城の八上城には久秀の甥・彦六が入った。
-

波多野秀尚 (はたのひでなお)
波多野家臣。晴通の子。兄・秀治とともに八上城に籠城して明智光秀軍と戦うが1年半に及ぶ攻防の末、降伏。秀治とともに安土に送られ、磔刑に処せられた。
-

波多野秀治 (はたのひではる)
丹波の豪族。八上城主。晴通の子。居城を三好家から奪還し、勢力を拡大した。明智光秀の攻撃を受け、籠城して戦うが降伏、安土に送られ磔刑に処せられた。
-

波多野宗高 (はたのむねたか)
波多野家臣。氷上城主。「丹波鬼」の異名をとった勇将。正親町天皇即位の際は主君・秀治とともに金銀を献上した。朝倉家の援軍として越前に赴き戦死した。
-

畑山元氏 (はたやまもとうじ)
安芸家臣。八流の戦いで長宗我部家に敗れて当主・国虎が自害すると、遺児・弘恒を保護して阿波に逃れる。後に中富川の戦いに参戦するが討死した。
-

蜂須賀家政 (はちすかいえまさ)
豊臣家臣。正勝の嫡男。関ヶ原合戦の際は子・至鎮を東軍に属させ、阿波徳島藩の安泰をはかる。以後も実質的に藩政を主導し、徳島藩の体制確立に貢献した。
-

蜂須賀小六 (はちすかころく)
豊臣家臣。墨俣一夜城の築城に協力し、以後、秀吉の参謀として民政・調略に手腕を発揮。四国征伐後、長宗我部家への抑えとして阿波徳島18万石を領した。
-

蜂須賀至鎮 (はちすかよししげ)
豊臣家臣。家政の嫡男。小田原征伐などに従軍。関ヶ原合戦では東軍に属した。戦後、家督を相続、阿波徳島藩の初代藩主となる。大坂の陣でも戦功を立てた。
-

八戸政栄 (はちのへまさよし)
南部家臣。八戸根城主。北信愛とともに主家を支えた重臣。信直が豊臣秀吉の小田原征伐に参陣した際には、留守居役を務めている。眼疾で盲目だったという。
-

蜂屋頼隆 (はちやよりたか)
織田家臣。黒母衣衆の1人。斎藤家を経て織田信長に仕える。以後は遊軍を率いて各地で活躍した。本能寺の変後は豊臣秀吉に属し、越前敦賀5万石を領した。
-

服部友貞 (はっとりともさだ)
伊勢の豪族。鯏浦砦を本拠とし、伊勢長島願証寺と結んで織田信長に抵抗した。のち、斎藤龍興ら信長に敗れた多くの武将が服部党に身を投じて信長と戦った。
-

服部半蔵 (はっとりはんぞう)
徳川家臣。半三保長の子。父の跡を継ぎ隠密頭を務める。主君・家康の伊賀越えの際には、警護を担当し、無事に帰国させた。「鬼の半蔵」の異名をとった。
-

服部康成 (はっとりやすなり)
津軽家臣。伊賀国の出身。関ヶ原合戦の際に召し抱えられ、大垣城攻撃戦に活躍した。のちに筆頭家老となって藩政を取り仕切り「無類の良臣」と評された。
-

花房正成 (はなぶさまさなり)
宇喜多家臣。正幸の子。羽柴秀吉の中国征伐軍に従った際、高松城を水攻めにすることを進言したという。のちに内乱により主家を出奔し、徳川家康に仕えた。
-

花房正幸 (はなぶさまさゆき)
宇喜多家臣。虫明城主。主君・直家の創業を支えた重臣の1人。弓の名手として知られ、各地の合戦で活躍した。細川藤孝から古今伝授を受けた文人でもある。
-

花房職秀 (はなぶさもとひで)
宇喜多家臣。一番槍や一番乗りの功を多数立てた武勇の士。のち主君・秀家に諫言して勘気を蒙り出奔。関ヶ原合戦では東軍に属し、備中高松で8千石を得た。
-

花輪親行 (はなわちかゆき)
出羽の土豪。安東氏に誼を通じ、南部氏の支城である長牛(なごし)城を攻撃した。余りの戦闘の激しさに、城下の小川が真っ赤に染まって流れたという。
-

馬場信春 (ばばのぶはる)
武田家臣。武田四名臣の1人。多くの合戦に参加し一度も負傷せず「不死身の鬼美濃」と呼ばれた。長篠合戦の際に殿軍として主君・勝頼の逃亡を助け、戦死。
-

馬場頼周 (ばばよりちか)
少弐家臣。肥前綾部城主。謀略を用いて政敵・龍造寺家兼の一族を討ち、家兼を失脚に追い込む。しかしのちに肥前に復帰した家兼に攻められ敗北、討たれた。
-

浜田広綱 (はまだひろつな)
葛西家臣。東館城主。主家に背いて周辺豪族と争い勢力を拡大したが、劣勢に追い込まれ降伏した。この浜田兵乱は、主家・葛西家の弱体化を招いた。
-

早川長政 (はやかわながまさ)
豊臣家臣。秀吉の馬廻衆を務める。功績を積み、大友家が改易されたのち、豊後府内城を与えられた。関ヶ原合戦や大坂の陣でも一貫して豊臣方で戦う。
-

林崎甚助 (はやしざきじんすけ)
居合の始祖。父を殺され、仇討ちをするため、剣術を学ぶ。あるとき、林崎明神から居合の極意を授かり、仇討ちを果たす。諸国を廻り、数多の弟子を育てた。
-

林秀貞 (はやしひでさだ)
織田家臣。筆頭家老。主家の家督争いでは信勝を擁立して敗れるが、許される。その後は目立つ働きがなく、のちに信勝擁立の件を蒸し返され、追放された。
-

林羅山 (はやしらざん)
徳川家臣。林家朱子学の祖。以心崇伝とともに方広寺鐘銘事件で豊臣秀頼を誹謗し、大坂の陣のきっかけを作った。のちに幕政に参画、各種公文書を起草した。
-

速水守久 (はやみもりひさ)
豊臣家臣。近習組頭として小牧長久手合戦や小田原征伐に従軍した。秀吉没後は秀頼に仕え、七手組頭の1人となる。夏の陣の際、秀頼に殉じて自害した。
-

羽床資載 (はゆかすけとし)
讃岐の豪族。羽床城主。長宗我部元親の攻撃を受け、元親の勧告により次男・資吉を人質に入れて降伏した。十河存保の居城・讃岐十河城を攻略中に病死した。
-

原田貞佐 (はらださだすけ)
美作の豪族。稲荷山城主。忠長の子。父が山名氏兼に敗れて自害したため、逼塞する。のちに宇喜多直家の後援を得て居城に復帰、直家の美作経略に貢献した。
-

原田隆種 (はらだたかたね)
筑前の豪族。高祖城主。大内家と結んで筑前西部に勢力を築き、大友家の軍勢をたびたび撃破した。原田家は藤原純友の乱の鎮定に功を立てた大蔵春実の嫡流。
-

原田忠佐 (はらだただすけ)
宇喜多家臣。行佐(貞佐の子)の子。豊臣秀吉の朝鮮派兵の際は主君・秀家に従い渡海するが、配下の足軽が軍律違反を犯したため、召還され帰国、隠退した。
-

原田忠長 (はらだただなが)
美作の豪族。稲荷山城主。尼子家に属した。近隣の神楽尾城主・山名氏兼とたびたび抗争を繰り広げる。一時は氏兼を一宮村に追うが、のちに敗れ、自害した。
-

原田親種 (はらだちかたね)
筑前の豪族。高祖城主。隆種の四男。立花鑑載が大友家に謀叛した際、同調したため大友と対立。後に父の首を要求されると、自らの首を切って渡した。
-

原胤清 (はらたねきよ)
千葉家臣。筆頭家老を務めた。一貫して親北条家の立場にあり、第一次国府台合戦の際には北条軍に属した。反北条だった主君・親胤の暗殺に関わったという。
-

原胤貞 (はらたねさだ)
千葉家臣。胤清の子。生実城主。臼井家が原家に降伏した際には、臼井城に入り臼井家の家政を執行した。一時里見家に居城を奪われるが、のちに奪還した。
-

原胤栄 (はらたねひで)
千葉家臣。胤貞の子。利胤・親胤2代に執権として仕えた。主家と同等の勢力を有していたという。のちに主家とともに北条家に従属、臼井衆の筆頭となった。
-

原種良 (はらたねよし)
黒田家臣。豊前の豪族・宝珠山氏の出。九州征伐で黒田家に仕え、案内役を務める。この時、姓が長いとして改姓した。関ヶ原合戦は黒田官兵衛に属し戦った。
-

原田信種 (はらだのぶたね)
筑前の豪族。高祖城主。草野鎮永の子。原田隆種の子・親種の死後、養子となり家督を継ぐ。のちに豊臣秀吉に降り、所領を安堵された。朝鮮派兵で戦死した。
-

原田宗時 (はらだむねとき)
伊達家臣。18歳で兵馬の権を与えられ各地で功を立てた剛勇の士。豊臣秀吉の朝鮮派兵に従軍中、病死した。伊達騒動の主人公・原田甲斐宗輔は孫にあたる。
-

原田嘉種 (はらだよしたね)
信種の長男。はじめ加藤清正に仕えるが清正と対立し追放。寺沢家に仕えたが、島原の乱で改易され浪人する。のち保科正之に仕え会津表留守役に任じられた。
-

原虎胤 (はらとらたね)
武田家臣。甲陽五名臣の1人。下総千葉家臣・原家の一族。生涯で38度の合戦に参加。城攻めに長じ、また情けに厚い豪傑で「夜叉美濃」の異名をとった。
-

原長頼 (はらながより)
織田家臣。柴田勝家の与力となる。賤ヶ岳合戦では柴田軍の先鋒として奮戦し、戦後、豊臣家に仕える。関ヶ原合戦で西軍に属して活躍したが、戦後自害した。
-

原野恵俊 (はらのしげとし)
蒲池家臣。龍造寺隆信が周辺豪族の圧迫を受け蒲池家を頼った際、主君・鑑盛は3百石を与えて一木村に住まわせた。この時、鑑盛の命で隆信一行を世話した。
-

孕石元成 (はらみいしもとしげ)
元泰の子。はじめ父とともに今川家に仕え、その後武田家に属す。武田家滅亡後浪人し、小田原征伐で奮戦して山内一豊に召し抱えられた。
-

針生盛信 (はりゅうもりのぶ)
蘆名家臣。盛幸(蘆名盛滋の子)の孫。1576年、金上盛実と席次の上下を争ったという。関ヶ原合戦で西軍に属したため所領を失い、伊達家に仕えた。
-

針生盛幸 (はりゅうもりゆき)
蘆名氏第十四代当主盛滋の実子。先に叔父の盛舜が十五代を継いでいたので、長じて針生家をたてた。子孫は伊達氏の家臣となった。
-

塙団右衛門 (ばんだんえもん)
加藤家臣。鉄砲大将を務めたが、関ヶ原合戦の際に主君・嘉明と対立して出奔、浪人となる。のちに大坂城に入城、大坂夏の陣で浅野長晟軍と戦い、戦死した。
-

塙直政 (ばんなおまさ)
織田家臣。赤母衣衆の1人。のちに原田姓を名乗る。主君・信長が蘭奢待を賜った際は、その奉行を務めた。石山本願寺攻めの際、一揆勢に攻められ戦死した。
-

塙安友 (ばんやすとも)
織田家臣。直政の子。本能寺の変後は佐々家を経て豊臣秀次に仕える。秀次の死後は浪人し、関ヶ原合戦では東軍に属した。戦後は江戸で小児科の医師となる。
-

稗貫輝時 (ひえぬきてるとき)
陸奥の豪族。奥州斯波家の出身という。1555年に上洛して将軍・足利義輝に黄金10両を献上した。この際、義輝の偏諱を賜って輝時と名乗ったという。
-

稗貫晴家 (ひえぬきはるいえ)
陸奥の豪族。葛西宗清(伊達成宗の子)の子。稗貫家は伊達為家(伊達家始祖・朝宗の三男)の子・為重が稗貫郡に下向した際に、地名を姓としたという。
-

稗貫広忠 (ひえぬきひろただ)
陸奥の豪族。和賀家の出身。豊臣秀吉の小田原征伐に参陣せず、改易された。のちに弟・和賀義忠とともに一揆を起こしたが、奥州征伐軍に敗れて逃走した。
-

日笠頼房 (ひかさよりふさ)
浦上家臣。日笠貴山城主。尼子晴久が進行してきた際は、親尼子派の浦上政宗に味方した。家中で反尼子派の宗景が優勢になると、頼房もその軍門に下った。
-

樋口兼豊 (ひぐちかねとよ)
上杉家臣。直峰城主。直江兼続の父。上杉家の会津転封に従う。兼続が不在の際には米沢城の留守役を務めた。最上家の諜報なども行い、上杉家に尽くした。
-

彦鶴 (ひこつる)
鍋島直茂の正室。石井忠常の娘。納富信澄に嫁ぐが、夫の戦死により実家に炊事をしているところを直茂に見初められ、再婚した。後に陽秦院と称する。
-

久武親直 (ひさたけちかなお)
長宗我部家臣。策謀や讒言で多くの同僚を自害に追い込み、主家滅亡の因を作った。兄・親信は主君・元親に「弟は必ず主家に仇をなす」と語っていたという。
-

久武親信 (ひさたけちかのぶ)
長宗我部家臣。誠実で分別があり、元親から厚い信頼を受けた。南伊予地方の攻略を任され、小豪族らとの合戦を繰り返した。伊予岡本城を攻撃中に戦死した。
-

土方雄氏 (ひじかたかつうじ)
徳川家臣。はじめ豊臣家に仕えた。関ヶ原合戦前夜、父・雄久に徳川家康暗殺を計画した容疑がかかり連座。のち許され徳川家に仕え、菰野藩を立藩した。
-

土方雄重 (ひじかたかつしげ)
徳川家臣。雄久の次男。雄氏の弟。2代将軍・徳川秀忠の小姓を務める。大坂の陣で酒井忠世に属して活躍。戦後加増され、陸奥久保田藩の初代藩主となった。
-

土方雄久 (ひじかたかつひさ)
織田信雄の家臣。信雄の除封後は豊臣秀吉に仕える。1599年、大野治長らと徳川家康暗殺を計画したが未然に発覚、常陸の佐竹氏に預けられた。
-

日高喜 (ひだかこのむ)
波多家臣。日高家は波多家の一族。波多盛の死後、御家騒動によって父を殺され壱岐に出奔。宗家を継いだ波多親の攻撃を受けるが、松浦家の協力で撃退した。
-

一柳直盛 (ひとつやなぎなおもり)
豊臣家臣。小田原征伐で戦死した兄・直末の後を継ぐ。関ヶ原合戦では東軍につき、功を立てる。大坂の陣にも参戦。のちに伊予西条に加増転封となった。
-

日根野弘就 (ひねのひろなり)
豊臣家臣。はじめ斎藤家に仕え、織田信長と戦う。主家滅亡後は浅井家に属し、浅井家の滅亡後、豊臣家に仕えた。合戦に実用的な兜「日根野鉢」を考案した。
-

日根野吉明 (ひねのよしあき)
徳川家臣。弘就の孫。関ヶ原合戦では真田昌幸に備えた。大坂の陣、日光東照宮造営の功で豊後府内2万石に加増され、初瀬井路開削など灌漑事業に従事した。
-

百武賢兼 (ひゃくたけともかね)
龍造寺家臣。龍造寺四天王の1人。今山合戦などで活躍し、武勇百人にまさると主君・隆信から百武姓を賜る。沖田畷合戦の際は隆信の身辺を守り、戦死した。
-

平井経治 (ひらいつねはる)
有馬家臣。肥前須古高城主。主君・晴純の娘を娶る。龍造寺家と抗争を展開し、一時和睦するが、のちに再び敵対。龍造寺家の大軍に攻められ敗北、自害した。
-

平岩親吉 (ひらいわちかよし)
徳川家臣。温厚篤実な性格から、主君・家康の絶大な信頼を受け、家康の長男・松平信康の傅役を務める。信康の自害後は家康の九男・義直の傅役となった。
-

平岡直房 (ひらおかなおふさ)
河野家臣。房実の子。主家滅亡後、伊予を領した加藤嘉明が関ヶ原合戦に出陣するため領国を留守にした際、主家再興の兵を挙げるが敗北し、毛利家に仕えた。
-

平岡房実 (ひらおかふさざね)
河野家臣。伊予荏原城主。奉行人を務めた。主家に背いた大野家や和田家と戦う一方で、周辺諸国の大友家などの侵入を防ぐなど、主家のために東奔西走した。
-

平岡頼勝 (ひらおかよりかつ)
小早川家臣。諸国を放浪後、豊臣家を経て小早川家の家老となる。関ヶ原合戦では黒田長政に通じ主君・秀秋を東軍に寝返らせた。秀秋死後は徳川家に仕えた。
-

平賀隆宗 (ひらがたかむね)
安芸の豪族。祖父・弘保とともに大内家に属し、尼子家に属した父・興貞と2度に渡って激しい争いを繰り広げた。のちに備後神辺城攻撃に従軍し、戦死した。
-

平賀広相 (ひらがひろすけ)
安芸の豪族。兄・隆宗の死後、大内義隆が推す小早川隆保に平賀家の家督を奪われる。しかし、義隆が陶晴賢に討たれたあと、毛利家の後援で家督を奪還した。
-

平賀元相 (ひらがもとすけ)
毛利家臣。広相の子。豊臣姓を受けた。関ヶ原合戦後、主家の減封により知行が4分の1に減らされたため、隠居して上洛。のちに孫・就忠の住む萩に移った。
-

平田舜範 (ひらたきよのり)
蘆名家臣。輔範の子。平田家は蘆名四天の宿老の一。是亦斎と称す。大槻城主の大槻政通が謀叛を起こした際、主君・盛氏に従って出陣し、鎮定した。
-

平田範重 (ひらたのりしげ)
蘆名家臣。平田舜範の子。松本行輔(氏輔の子)の謀叛鎮定などに活躍した。伊達軍が蘆名領に侵攻した際は、中目盛光とともに奮戦し、これを破った。
-

平田光宗 (ひらたみつむね)
島津家臣。宗秀の次男。日向石城攻めや肥後堅志田攻め、沖田畷合戦など各地で戦功を立てた。のちに肥後八代城を守った。老中として主君・貴久を補佐した。
-

平田宗茂 (ひらたむねしげ)
島津家臣。薩摩苦辛城主。宗秀の子。安房守を称す。はじめ島津実久に属していたが、島津忠良に攻められ、居城を開城して忠良に降伏。以後は忠良に仕えた。
-

平塚為広 (ひらつかためひろ)
豊臣家臣。小田原征伐などに従軍した。関ヶ原合戦では西軍に属し、病の大谷吉継に代わって大谷軍を率いた。寝返った小早川軍と戦い、奮戦するが敗死した。
-

平手政秀 (ひらてまさひで)
織田家臣。次席家老。信長の傅役を務めた。信長の妻に斎藤道三の娘・帰蝶を迎えるよう尽力するなど、外交面で活躍。信長の奇行を改めさせるため諫死した。
-

平野長泰 (ひらのながやす)
豊臣家臣。賎ヶ岳七本槍の一人。関ヶ原合戦では東軍に属す。大坂の陣直前、徳川家康に大坂城入りを告げたが、危惧した家康に江戸城に留め置かれたという。
-

平林正恒 (ひらばやしまさつね)
武田家臣。主家滅亡の際、居城・牧之島城を失うが、のちに上杉景勝の後援を得て回復し、以後は上杉家に仕えた。主家の会津転封に従い、白河城代となった。
-

弘中隆兼 (ひろなかたかかね)
大内家臣。安芸守護代を務めた。陶晴賢の謀叛後は大内義長に仕える。のちに晴賢の命により江良房栄を謀殺した。晴賢に従って厳島合戦に従軍し、敗死した。
-

風魔小太郎 (ふうまこたろう)
相州乱波の頭領。情報収集や敵地撹乱に奔走し、北条家の治政を陰から支えた。身長は7尺2寸、目はさかさまに裂け、口からは牙が4本飛び出ていたという。
-

深水長智 (ふかみながとも)
相良家臣。戦死した主君・義陽の子・忠房の地位を島津家に認めさせ、肥後国人一揆の際は上坂して誤解を解くなど、外交面で活躍し、主家の存続に尽力した。
-

福島高晴 (ふくしまたかはる)
豊臣家臣。正則の弟。関ヶ原の戦いでは東軍に属して伊勢桑名城を攻め、戦後、大和松山3万石を領す。大坂の陣の際、豊臣方への内通を疑われて改易された。
-

福島忠勝 (ふくしまただかつ)
正則の嫡男。正則が広島城無断修築の罪で川中島に減封された時、家督を譲られ高井野藩主となる。翌年、父に先立って死去。正則はその死を大変悲しんだ。
-

福島正則 (ふくしままさのり)
豊臣家臣。賤ヶ岳七本槍の筆頭。関ヶ原合戦では東軍の主力として奮戦し、安芸広島49万石を得る。しかし、のちに居城・広島城無断修築の罪で改易された。
-

福田兼親 (ふくだかねちか)
大村家臣。福田城主。主君・純忠の娘を娶る。豊臣秀吉の朝鮮派兵の際は純忠の子・喜前とともに従軍。のちに居城を離れ、主家の居城・玖島城下に移住した。
-

福留親政 (ふくどめちかまさ)
長宗我部家臣。安芸家との戦いで奮戦し「福留の荒切り」の逸話を残す。主君・元親から受けた感状は21枚という家中屈指の勇将。南伊予攻略戦で戦死した。
-

福留儀重 (ふくどめのりしげ)
長宗我部家臣。親政の子。童謡にも唄われた猛将で主家の四国統一に貢献した。主君・元親が禁酒令を発した際、酒樽を砕いて諌めた。戸次川合戦で戦死した。
-

福原貞俊 (ふくはらさだとし)
毛利家臣。筆頭家老を務めた。小早川隆景を補佐して山陽方面の経略を行う。主君・元就の死後、四人衆の1人となり当主・輝元を補佐して主家の国政に参画。
-

福原資孝 (ふくはらすけたか)
那須七党の一。大田原資清の子。父が強制的に隠居させた福原資安の跡を継ぎ、兄・大関高増を補佐した。豊臣秀吉の小田原征伐に遅参し、所領を削られた。
-

福原資保 (ふくはらすけやす)
那須七党の一。資孝の次男。兄・資広の養子となり家督を継ぐ。関ヶ原合戦では東軍に属す。大坂の陣では本多正信に属して戦った。のちに大坂城番を務めた。
-

福原長堯 (ふくはらながたか)
豊臣家臣。則尚の弟。石田三成の妹婿。朝鮮派兵の際は奉行として渡海した。関ヶ原合戦では西軍に属し、大垣城を守った。主力の敗北後に開城し、自害した。
-

福原広俊 (ふくはらひろとし)
毛利家臣。貞俊の孫。朝鮮派兵に従軍。関ヶ原合戦後は主家に従って萩に移り、吉川広家とともに萩藩の基盤確立に尽力した。江戸城などの普請奉行も務めた。
-

藤方朝成 (ふじかたともなり)
北畠家臣。織田信長の伊勢侵攻軍に降り北畠家を継いだ織田信雄に仕える。のちに信長の命により、旧主・具教を謀殺した。本能寺の変後は豊臣秀吉に属した。
-

藤方安正 (ふじかたやすまさ)
織田家臣。朝成の子。はじめ織田信包に仕え、信包改易後は豊臣秀次に仕える。秀次事件の後、徳川家康に招かれ下総で5百石を賜る。以後は徳川家に仕えた。
-

藤沢頼親 (ふじさわよりちか)
信濃の豪族。福与城主。武田軍に敗れたあとは小笠原家を頼り、小笠原家滅亡後は諸国を放浪した。のち伊那谷に戻るが徳川家に属する豪族に攻められて滅亡。
-

藤田信吉 (ふじたのぶよし)
武田家臣。主家滅亡後は上杉家に仕え、佐渡攻略などに活躍した。関ヶ原合戦の直前に上杉家を出奔、上杉・徳川家間の調停工作を行うが失敗し、剃髪した。
-

藤田康邦 (ふじたやすくに)
山内上杉家臣。武蔵七党の1つ、猪俣党に属す。河越夜戦で北条氏康に敗れて降服した。氏康の三男・氏邦を娘婿として家督を譲り、隠居後は用土康邦と称す。
-

藤林正保 (ふじばやしまさやす)
伊賀の豪族。通称は長門守。藤林家は伊賀の上忍三家の一つで、後に忍術伝書「万川集海」を著したのも藤林家の子孫であった。
-

二木重高 (ふたつぎしげたか)
小笠原家臣。塩尻峠合戦では主家を裏切り主家大敗の要因を作るが、その後は一門をあげて主君・長時を補佐した。長時が摂津へ去ったあとは武田家に仕えた。
-

二木重吉 (ふたつぎしげよし)
小笠原家臣。重高の嫡男。武田家の滅亡後、徳川家康の援護で小笠原貞種を深志城から退却させ、主家の旧領復帰を実現させた。のちに「二木家記」を著した。
-

船尾昭直 (ふなおあきなお)
佐竹家臣。船尾家は岩城由隆の弟・隆輔を祖とする。佐竹家に属し義昭・義重・義宣の3代に渡って仕え、陸奥方面における佐竹家の先鋒として活躍した。
-

冬姫 (ふゆひめ)
織田信長の次女。蒲生賢秀が巨従の証として差し出した子・氏郷の器量に惚れ込み、娘の冬姫を与えて娘婿とした。会津藩主となる秀行と一女を産んだ。
-

古田織部 (ふるたおりべ)
豊臣家臣。名は重然。織部正に任じられたことから「織部」と呼ばれ、陶器「織部焼」を創始する。利休七哲の1人でもあり、諸大名の茶の師匠を務めた。
-

古田重勝 (ふるたしげかつ)
豊臣家臣。父・重則が播磨三木城攻めで戦死した後、家督を継ぐ。伊勢松坂3万5千石を領した。関ヶ原合戦では東軍に属して戦い、戦後2万石を加増された。
-

古田重治 (ふるたしげはる)
徳川家臣。重勝の弟。兄が死んだ時、兄の子が幼かったため後を継ぐ。大坂の陣の功で石見浜田に移封。治水や城下町建設に努め、後を兄の子に譲り隠居した。
-

不破光治 (ふわみつはる)
斎藤家臣。主家滅亡後は織田家に属す。主君・信長の馬廻を務め、各地で活躍した。のちに柴田勝家の目付として越前に赴く。本能寺の変後は勝家に属した。
-

別所重棟 (べっしょしげむね)
別所家臣。就治の子。甥・長治を補佐する。長治が織田信長に背いた際は、これに従った。長治の死後、浪人生活を経て豊臣秀吉に仕え、九州征伐に従軍した。
-

別所長治 (べっしょながはる)
播磨の豪族。三木城主。安治の嫡男。織田信長の中国征伐軍の先鋒となるが、のち敵対。羽柴秀吉軍と約2年に及ぶ籠城戦の末、城兵の助命を条件に自害した。
-

別所就治 (べっしょなりはる)
播磨の豪族。三木城主。別所家は赤松家の庶流。赤松宗家の衰退に乗じて勢力を拡大し、東播磨8郡を領した。のち細川晴元や三好長慶に属して各地で戦った。
-

別所安治 (べっしょやすはる)
播磨の豪族。三木城主。就治の嫡男。三好長慶の侵攻軍を撃退した。将軍・足利義昭が三好三人衆に襲われた際、弟・重宗を派遣し、織田信長に功を賞された。
-

別所吉治 (べっしょよしはる)
豊臣家臣。重棟の子。丹波園部1万5千石を領した。関ヶ原合戦では西軍に属すが、所領を安堵された。大坂夏の陣も参加。のちに職務怠慢の罪で改易された。
-

逸見昌経 (へみまさつね)
若狭武田家臣。高浜城主。逸見家は若狭武田家の庶流。織田信長の若狭侵攻軍に降り、各地を転戦した。その功により、旧領を安堵され、3千石を加増された。
-

穂井田元清 (ほいだもときよ)
毛利元就の四男。備中の豪族・穂井田家を継いだ。山中幸盛が拠る播磨上月城を攻略するなど、各地で功を立てた。のち毛利姓に戻り、長府毛利家の祖となる。
-

北条氏勝 (ほうじょううじかつ)
北条家臣。氏繁の子。父の死後、玉縄城主となる。豊臣秀吉の小田原征伐の際は山中城を守るが落城、その後は居城に籠城するが降伏、戦後は徳川家に仕えた。
-

北条氏邦 (ほうじょううじくに)
北条家臣。氏康の三男。上杉家との和睦を成立させた。豊臣秀吉の小田原征伐では出撃を唱えるが退けられる。前田利家に居城・鉢形城を落とされ、降伏した。
-

北条氏繁 (ほうじょううじしげ)
北条家臣。綱成の子。家中随一の猛将と恐れられた父に劣らず、武勇に優れていた。玉縄城主を務め、上杉謙信の関東侵攻軍を撃退するなどの戦功を立てた。
-

北条氏重 (ほうじょううじしげ)
保科正直の四男。母は徳川家康の異父妹の多劫姫。北条綱成の孫・氏勝の養子となって後を継ぐ。大坂冬の陣では岡崎城を守備した。孫に大岡忠相がいる。
-

北条氏尭 (ほうじょううじたか)
北条家臣。氏綱の子。上杉謙信が関東に進出した際は河越城に入り、籠城の末、守り切った。伊達家との外交などでも活躍を見せている。
-

北条氏綱 (ほうじょううじつな)
後北条家2代当主。「北条」の姓を初めて使用した。扇谷上杉家との戦いや、小弓公方・足利家との第一次国府台合戦に勝つなど、着実に関東に地盤を築いた。
-

北条氏照 (ほうじょううじてる)
北条家臣。氏康の次男。軍事・外交の両面で兄・氏政を補佐。おもに下野や下総方面の攻略を担当した。小田原落城後、豊臣秀吉の命により、兄とともに自害。
-

北条氏直 (ほうじょううじなお)
後北条家5代当主。氏政の嫡男。豊臣秀吉の上洛命令に応ぜず、秀吉の小田原征伐軍の攻撃を受けた。籠城3カ月ののち降伏、高野山に上り、同地で病没した。
-

北条氏規 (ほうじょううじのり)
北条家臣。氏康の四男。人質として今川家にいた頃、同じ境遇の徳川家康と知り合う。豊臣秀吉の小田原征伐では韮山城に籠城するが、家康の説得で開城した。
-

北条氏房 (ほうじょううじふさ)
北条家臣。岩付城主。北条氏政の三男。太田氏資の娘を娶り、家督を継いだ。豊臣秀吉の小田原征伐では居城に籠城。戦後、兄・氏直とともに高野山に上った。
-

北条氏政 (ほうじょううじまさ)
後北条家4代当主。氏康の嫡男。優秀な弟たちや家臣団に支えられ、北条家の地位を不動のものにした。豊臣秀吉の小田原征伐軍に抗戦するが敗れ、自害した。
-

北条氏康 (ほうじょううじやす)
後北条家3代当主。氏綱の嫡男。武田信玄・上杉謙信ら強豪としのぎを削り、関東に一大王国を築いた。知勇兼備の名将で、戦国期随一の民政家としても著名。
-

北条幻庵 (ほうじょうげんあん)
北条家臣。早雲の三男。北条家5代に仕え、箱根権現の第40世別当を務めた。主君・氏康の娘が吉良家に嫁ぐ際、「幻庵おほへ書」という心得書を与えた。
-

北条早雲 (ほうじょうそううん)
今川家臣。小鹿範満の乱を平定し、発言力を持つ。堀越公方や扇谷上杉家臣・三浦家らを滅ぼして伊豆・相模を領国化した。「戦乱の梟雄」として名高い人物。
-

北条為昌 (ほうじょうためまさ)
氏綱の三男。叔父・北条氏時が死去すると幼くして玉縄城主となり、大道寺盛昌の後見を受ける。花倉の乱で敗れた福島正成の子・綱成の養父となった。
-

北条綱成 (ほうじょうつなしげ)
北条家臣。福島正成の子。父の死後、北条氏綱を頼り、氏綱の娘を娶って一門となる。河越合戦などで活躍し、その旗印より「地黄八幡」と呼ばれ畏怖された。
-

北条綱高 (ほうじょうつなたか)
北条家臣。北条五色備えの赤備えを率いた勇将。初名を種政といったが、北条氏綱が上杉朝定を攻めた際に大功を立て、氏綱より「綱」の字を拝領した。
-

宝蔵院胤栄 (ほうぞういんいんえい)
安土桃山時代の興福寺の僧。子院にあたる宝蔵院の院主になったのち、宝蔵院と名乗る。十文字槍を使用した宝蔵院流槍術を創始した。
-

法華津前延 (ほけづさきのぶ)
西園寺家臣。伊予法華津城主。西園寺十五将の1人。大友家の侵攻軍を何度も撃退した。豊臣秀吉の四国平定後、宇和郡を領した戸田勝隆の命により下城した。
-

保科正俊 (ほしなまさとし)
武田家臣。高遠城主。信濃先方衆として各地の合戦に従軍し、活躍した。「槍弾正」の異名をとり「甲陽軍鑑」に戦国三弾正の1人として名を挙げられている。
-

保科正直 (ほしなまさなお)
武田家臣。正俊の子。主家の滅亡後は一時北条家に属すが、敵対する小笠原貞慶らが豊臣家に属したため、徳川家に仕える。第一次上田合戦などに従軍した。
-

保科正光 (ほしなまさみつ)
保科正直の子。徳川家康の臣。信濃国高遠城主。家康が関東に移封されると、下総に転封された。関ヶ原後、旧領を回復徳川家光の弟・正之が家督を継いだ。
-

保科正之 (ほしなまさゆき)
徳川秀忠の四男。武田信玄の娘・見性院に養育された。会津藩主となり「会津家訓」を制定。一方で、将軍・家光、家綱を補佐して幕政にも重きをなした。
-

細川昭元 (ほそかわあきもと)
織田家臣。晴元の嫡男。足利義昭を擁して上洛した織田信長に属す。義昭の偏諱を受け昭元と名乗り、信長の妹・犬を娶った。信長の蹴鞠の相手などを務めた。
-

細川氏綱 (ほそかわうじつな)
室町幕府最後の管領。三好長慶らに擁立され、細川晴元と争う。晴元が近江に逃れたあとに入京し、管領に就任した。のち山城淀城に移され、同城で死去した。
-

細川興秋 (ほそかわおきあき)
忠興の次男。関ヶ原合戦に東軍として参加。のち衝動的に出奔して大坂城に入るも敗戦後に自害を命じられた。密かに助命され、町民として生きたともされる。
-

細川興元 (ほそかわおきもと)
藤孝の次男。信長に従って松永久秀と戦ったほか、小田原征伐や関ヶ原でも戦功があった。のち兄・忠興と対立し京に隠棲するが、徳川秀忠より呼び戻された。
-

細川定輔 (ほそかわさだすけ)
長宗我部家臣。土佐十市栗山城主。阿波海部の戦い、伊予北川・高森の戦いなどに従軍して戦功を挙げ、主君・元親の四国統一に貢献した。のちに宗桃と号す。
-

細川真之 (ほそかわさねゆき)
持隆の子。父を殺した三好義賢に擁立され、阿波勝瑞城主となる。のち長宗我部元親とともに三好長治を討つが、長治の弟・十河存保に敗れ自害したという。
-

細川忠興 (ほそかわただおき)
織田家臣。藤孝の子。明智光秀の娘を娶るが、本能寺の変後は豊臣家に属した。関ヶ原合戦では東軍に属し、豊前中津39万6千石を領した。利休七哲の1人。
-

細川忠利 (ほそかわただとし)
忠興の三男。徳川秀忠・家光より厚く信任され、加藤家の改易後に肥後熊本藩主に。武芸を好んで柳生新陰流を修め、晩年には宮本武蔵を招いて知遇を与えた。
-

細川晴貞 (ほそかわはるさだ)
細川家臣。元常の次男。京で主・晴元を補佐する和泉守護の父に国を任された。江口の戦いで和泉国の細川家の支配が揺らぐと、没落していった。
-

細川晴元 (ほそかわはるもと)
摂津の戦国大名。三好元長と結んで細川高国を討ち、政権を樹立する。のちに元長を討つが、細川氏綱を擁立した三好長慶(元長の子)に敗れ、近江に逃れた。
-

細川藤賢 (ほそかわふじかた)
典厩細川家当主。織田信長に擁され上洛した足利義昭に属す。義昭と信長が対立した際は挙兵を諫めるが、のち義昭とともに戦い敗北。その後は信長に仕えた。
-

細川藤孝 (ほそかわふじたか)
足利家臣。主君・義輝の横死後は義輝の弟・義昭の擁立に貢献した。その後は的確な情勢判断で細川家の命脈を保った。古今伝授を受けた文化人としても著名。
-

細川通薫 (ほそかわみちただ)
野洲細川家当主。晴国の子。毛利家の客将となって野洲家の備中旧領の回復に奔走するが叶わなかった。杉山合戦では敵将を討ち取る大功を挙げた。
-

細川通政 (ほそかわみちまさ)
野洲細川家当主。備中鴨山城主。京兆細川家に養子入りした高国の弟。尼子家の圧力を受けて備中を放棄し、伊予に逃れた。備中に戻ることなく伊予で没した。
-

細川持隆 (ほそかわもちたか)
阿波守護。播磨守護・赤松晴政の要請により尼子晴久と備中で戦うが敗れる。のち足利義栄を擁し入京を試みるが、家臣の三好義賢と対立し、義賢に殺された。
-

細川元常 (ほそかわもとつね)
細川家臣。細川澄元・高国の争いでは澄元に属し、和泉半国守護を罷免される。澄元の死後は晴元(澄元の子)に属し、晴元の家督相続後、守護に復帰した。
-

細野藤敦 (ほそのふじあつ)
長野家臣。藤光の嫡男。織田信長の伊勢侵攻軍に対して徹底抗戦を主張、安濃城に籠城して抗戦を続けたが、のちに和睦した。本能寺の変後は豊臣家に仕えた。
-

細野藤光 (ほそのふじみつ)
長野家臣。長野通藤の子。長野工藤家の庶流・細野家の養子となり、安濃に屋敷を構えた。細野家は長野藤信(長野工藤家5代当主・豊藤の次男)を祖とする。
-

堀田作兵衛 (ほったさくべえ)
真田家臣。真田幸村の側室・阿梅の兄。幸村長女・菊を養女として育て、嫁がせた。大坂の陣では信濃から幸村の元へ駆けつけ、ともに戦い、討死した。
-

堀田正吉 (ほったまさよし)
徳川家臣。もとは信長に仕えたが、その後、浅野長政、小早川隆景、小早川秀秋に仕え、秀秋死後、徳川幕府の幕臣となった。妻が春日局の義理の娘。
-

保土原行藤 (ほどはらぎょうとう)
二階堂家庶流。伊達政宗が主家を攻めた際に内応し、以後は伊達家に仕える。和歌や茶道に精通していたため、政宗に敬われて伊達家の一家に準ぜられた。
-

堀江景忠 (ほりえかげただ)
朝倉家臣。各地で功を立てるが、謀叛疑惑により能登に退去させられる。織田家に通じて本領を回復するが、一向一揆討伐の恩賞に不満を表したため殺された。
-

堀江頼忠 (ほりえよりただ)
里見家臣。1587年の鹿野山神野寺の棟札に名が見える。家老を務め、1千3百石を知行した。主家改易後は主君・忠義に従い伯耆倉吉に赴き、同地で病没。
-

堀尾忠氏 (ほりおただうじ)
豊臣家臣。吉晴の次男。徳川秀忠の偏諱を受ける。関ヶ原合戦では秀忠軍に従い功を立てた。戦後、出雲・隠岐24万石に加増されるが、父に先立ち早世した。
-

堀尾忠晴 (ほりおただはる)
忠氏の長男。父が早世し幼くして家督を継ぎ祖父・吉晴の後見を受けた。大坂冬の陣で活躍したが軍法違反に問われた時見事に切り返して周囲を感心させた。
-

堀尾吉晴 (ほりおよしはる)
豊臣家臣。情に厚く「仏の茂助」の異名をとる。主君・秀吉の死後、三中老の1人となる。関ヶ原合戦では子・忠氏が東軍に属し、出雲松江24万石を領した。
-

堀親良 (ほりちかよし)
豊臣家臣。秀政の次男。越後蔵王堂4万石を領す。関ヶ原合戦では兄・秀治とともに東軍に属した。のちに堀家を出奔、下野烏山2万5千石の領主となった。
-

堀利重 (ほりとししげ)
秀政の弟。徳川秀忠に仕えた。関ヶ原合戦では上田城攻めに奮戦。のち大久保忠隣失脚に連座して改易されるが、大坂の陣で活躍。罪を許され、大名となった。
-

堀直政 (ほりなおまさ)
織田家臣。姓は奥田とも。親族である堀秀政に付き従い、各地で戦功を立てる。秀政死後は息子の堀秀治を補佐。その実績から天下の三陪臣の一人とも称される。
-

堀直寄 (ほりなおより)
堀家臣。直政の子。兄と家督を争い、これが元で堀家は改易。徳川家に仕える。豊臣秀吉が器量人と讃え徳川家康が信頼した才でついには村上10万石を得た。
-

堀内氏善 (ほりのうちうじよし)
紀伊の豪族。熊野神宮別当を務めた。豊臣秀吉の紀州征伐軍に降る。朝鮮派兵では水軍を率いた。関ヶ原合戦で西軍に属して改易され、加藤清正に預けられた。
-

堀秀治 (ほりひではる)
豊臣家臣。秀政の嫡男。父の死後、家督を継ぐ。越後春日山45万石を領す。関ヶ原合戦では東軍に属し、上杉景勝が扇動した一揆を鎮め、所領を安堵された。
-

堀秀政 (ほりひでまさ)
織田家臣。各地で戦功を立てる一方、徳川家康の饗応役も務めるなど、文武の両面に才能を発揮した。本能寺の変後は豊臣秀吉に属し、一門格の待遇を受けた。
-

堀秀村 (ほりひでむら)
浅井家臣。鎌刃城主。姉川合戦で織田家に寝返る。浅井家に鎌刃城を奪われるが戦勝後、決死の奮戦をたたえられ、鎌刃城主に戻る。のち豊臣家に仕えた。
-

本願寺教如 (ほんがんじきょうにょ)
本願寺12世法主。顕如の長男。気性が激しく、織田信長との和睦後も徹底抗戦を主張した。父の死後、法主の座を巡り弟・准如と対立、東本願寺を建立した。
-

本願寺顕如 (ほんがんじけんにょ)
本願寺11世法主。証如の子。武家勢力に抵抗し、日本各地で一向宗門徒を蜂起させる。信長包囲網では中心的役割を担い、十年の長きに渡り戦いを続けた。
-

本願寺証如 (ほんがんじしょうにょ)
本願寺10世法主。日蓮宗徒と六角定頼に山科本願寺を焼き討ちされ、石山本願寺に本山を移した。蓮如の書状を集めて出版し、諸方の末寺や門徒に配った。
-

北郷忠相 (ほんごうただすけ)
日向の豪族。伊東家とたびたび激しく争う。伊東尹祐が急死した際、一時和議を結ぶが、島津忠朝らと結んで再び伊東家を攻め、旧領を回復した。
-

北郷時久 (ほんごうときひさ)
日向の豪族。庄内領主。島津家に属して伊東家や肝付家の軍勢と戦った。豊臣秀吉の九州征伐軍に降伏し、所領を安堵された。のちに薩摩宮之城へ転封された。
-

北郷三久 (ほんごうみつひさ)
島津家臣。時久の三男。北郷家当主だった兄・島津義虎の遺児を補佐する。庄内の乱で奮戦し、北郷家伝来の地である日向都城の復帰を果たした。
-

本庄実乃 (ほんじょうさねより)
上杉家臣。栃尾城主。主君・景虎の栃尾城入城以来、側近となる。景虎の初陣の際は補佐役として活躍した。のち景虎が当主になると、政権の中枢に参画した。
-

本庄繁長 (ほんじょうしげなが)
上杉家臣。村上城主。叔父・小川長資を討って居城を奪回、家督を継ぐ。武田信玄と結んで謀叛を起こすが、許されて帰参する。以後は各地の合戦で活躍した。
-

本荘右述 (ほんじょうすけのぶ)
大友家臣。義長・義鑑の二代に仕え、加判衆を務めた。筆頭宿老として幕府交渉を統括し、また筑後に出陣して大内家と戦うなど、外交・軍事全般で活躍した。
-

本城常光 (ほんじょうつねみつ)
尼子家臣。山吹城主を務め、大森銀山を守る。毛利元就や吉川元春の攻撃を撃退し、勇名を馳せた。のち元就に降伏するが、その豪勇を恐れた元就に殺された。
-

本庄房長 (ほんじょうふさなが)
越後の豪族。揚北衆。時長の子。大和守と称す。上条定憲の乱の際は長尾為景に属した。のちに弟・小川長資や鮎川盛長に攻められて居城を追われ、死去した。
-

本庄義勝 (ほんじょうよしかつ)
本庄繁長の次男。大宝寺義興の養子となり、上杉景勝の後援で大宝寺家を継ぐ。のちに一揆煽動の疑いにより大和に配流されたが、許されて上杉家臣となった。
-

本泉寺蓮悟 (ほんせんじれんご)
本願寺8世法主・蓮如の七男。1506年、北陸一向一揆の総指揮を命じられ、北陸地方の諸氏と戦った。のちに弟・蓮淳と対立して戦うが敗れ、破門された。
-

本多小松 (ほんだこまつ)
本多忠勝の娘。稲姫とも。徳川家康の養女として、真田信幸に嫁いだ。関ヶ原合戦では、敵対する義父・真田昌幸の訪問を断り、沼田城を守ったといわれる。
-

本多重次 (ほんだしげつぐ)
徳川家臣。岡崎奉行を務め、「鬼作左」の異名をとる。豊臣秀吉の母・大政所が徳川家の人質となった際、冷遇したため秀吉の怒りを買い、閉居処分となった。
-

本多忠勝 (ほんだただかつ)
徳川家臣。徳川四天王の1人。「家康に過ぎたるもの」と評された家中随一の猛将。名槍・蜻蛉切を手に57度の合戦に参陣し、傷一つ負わなかったという。
-

本多忠純 (ほんだただずみ)
徳川家臣。正信の三男。大坂の陣で活躍するも、毛利勝永と戦い敗走している。粗暴で家臣を虐待し、ささいなことで殺したため、ついには家臣に暗殺された。
-

本多忠高 (ほんだただたか)
松平家臣。忠勝の父。清康・広忠の2代に仕え、数多くの合戦で活躍。広忠の死後、太原雪斎の麾下で織田家の安祥城を攻めたが、矢を受けて戦死した。
-

本多忠朝 (ほんだただとも)
徳川家臣。忠勝の次男。関ヶ原合戦に従軍し、戦後、上総大多喜5万石を領す。大坂夏の陣では天王寺口の先鋒を務め、毛利勝永軍に正面から突入、戦死した。
-

本多忠政 (ほんだただまさ)
徳川家臣。忠勝の嫡男。小田原征伐や関ヶ原合戦、大坂の陣などに従軍し、播磨姫路15万石を領した。嫡男・忠刻は豊臣秀頼と死別した千と結婚している。
-

本多利朝 (ほんだとしとも)
豊臣家臣。利久の子。高取城主。関ヶ原合戦では東軍に属し、居城が城主不在となる。そのため西軍の攻撃を受けるが落城を免れた。戦後、本領を安堵された。
-

本多利久 (ほんだとしひさ)
豊臣家臣。はじめ水野半右衛門と名乗り岩倉城主・織田信安に仕えた。のちに豊臣秀長に属し、脇坂安治の転封により高取城主となり、2万5千石を領した。
-

本多政重 (ほんだまさしげ)
正信の次男。知に優れた父や兄・正純と対照的に豪胆で武勇に優れた。徳川家を出奔して諸大名に仕え、一時期、直江兼続の養子になっていたこともある。
-

本多正純 (ほんだまさずみ)
徳川家臣。正信の嫡男。駿府城付の年寄を務める。以心崇伝とともに内政・外交に活躍、下野宇都宮15万石を領すが、のちに秀忠の不興を買い、改易された。
-

本多政武 (ほんだまさたけ)
徳川家臣。利朝の長男。大和高取藩2代藩主。大坂夏の陣・道明寺口の戦いに功があった。大坂城修築、高野山大塔造営に活躍。囲碁の名人であった。
-

本多政朝 (ほんだまさとも)
徳川家臣。忠政の次男。伯父・忠朝が大坂の陣で戦死するとその後を継ぐ。のち兄・忠刻が死ぬと、本多宗家の後継ぎとなり、父の死後、姫路藩を相続した。
-

本多正信 (ほんだまさのぶ)
徳川家臣。三河一向一揆に身を投じて主家を離反、諸国を放浪したのちに帰参。行政と謀略に優れた手腕を発揮した。主君・家康には「友」と呼ばれたという。
-

本多康重 (ほんだやすしげ)
徳川家臣。元服に際し、家康から偏諱を受ける。掛川城攻めで初陣を飾り、以後多数の戦いに参陣した。特に長篠の戦いにおける奮戦で名高い。
-

本多康俊 (ほんだやすとし)
徳川家臣。酒井忠次の次男。母は徳川家康のおば・碓井姫。本多忠次の養子となり、後を継ぐ。大坂の陣で活躍。近江膳所3万石を与えられた。
-

本多康紀 (ほんだやすのり)
徳川家臣。康重の長男。父の死により、三河岡崎藩を継ぐ。大坂の陣で、堀埋め立てや石垣破壊に活躍した。のちに岡崎城の修築に努め、天守閣を再建した。
-

本堂茂親 (ほんどうしげちか)
出羽の豪族。本堂城主。本堂忠親の死により家督相続。関ヶ原合戦では、徳川家康の命で本堂城を守った。のちに常陸新治郡に転封され、志筑に陣屋を定めた。
-

本堂忠親 (ほんどうただちか)
出羽の豪族。本堂城主。朝親の子。豊臣秀吉の小田原征伐に参陣し、所領を安堵された。秀吉の朝鮮派兵の際は、前田利長軍に属して肥前名護屋城に在城した。
-

本間高貞 (ほんまたかさだ)
佐渡の豪族。羽茂城主。高信の次男。上杉家との関係は良好であったが、景勝の代になると佐渡金山を巡る争いが勃発。逃亡したが捕縛され、斬首された。
-

本間高信 (ほんまたかのぶ)
佐渡の豪族。羽茂城主。高季の子。妻は長尾為景の姪。永正の乱で関東管領・上杉顕定に追い込まれた為景が佐渡に逃れてきた際、一時的に匿った。
-

本間憲泰 (ほんまのりやす)
佐渡の豪族。雑太城主。泰高の子。上杉景勝の佐渡平定後も生き延びるが、佐渡が上杉家の領地となったため、越後に移された。
-

蒔田広定 (まいたひろさだ)
豊臣家臣。関ヶ原合戦の際は西軍に属して伊勢安濃津攻めに参加した。戦後、高野山に蟄居するが、浅野幸長らの尽力により備中浅生1万石の大名となった。
-

米谷常秀 (まいやつねひで)
葛西家臣。米谷城主。常時の嫡男。米谷家は亀掛川千葉家の流れ。桃生郡深谷において弟(五男)・常忠、弟(七男)・信忠とともに伊達政宗に謀殺された。
-

前田慶次 (まえだけいじ)
戦国一の傾奇者。滝川益重の子。前田利家の兄・利久の養子となる。槍を使えば天下無双、風雅の道にも造詣深かった。関ヶ原合戦では上杉家に属して戦った。
-

前田玄以 (まえだげんい)
豊臣家臣。はじめ延暦寺の僧であったが還俗し、織田信忠に仕える。本能寺の変の際は信忠の嫡男・秀信を守って脱出した。のちに豊臣家五奉行の1人となる。
-

前田利家 (まえだとしいえ)
織田家臣。数々の合戦で活躍し「槍の又左」の異名をとった。のちに柴田勝家に従って北陸平定に貢献。信長の死後は豊臣秀吉に仕え、五大老の1人となった。
-

前田利常 (まえだとしつね)
加賀金沢藩主。利家の四男。兄・利長の跡を継ぐ。大坂の陣に参陣して功を立てた。藩の存続に努め、江戸幕府の警戒を欺くために愚鈍を装っていたともいう。
-

前田利長 (まえだとしなが)
利家の嫡男。家督を相続後、謀叛の兆しありとの噂が流れるが、母・芳春院を人質に出して討伐を免れた。関ヶ原合戦で東軍に属し、加賀100万石を領した。
-

前田利久 (まえだとしひさ)
織田家臣。利家の兄。慶次の養父。前田家当主であったが器量不足と見なされ、信長の命で利家に家督を譲る。このため一時、利家と不仲であったとされる。
-

前田利政 (まえだとしまさ)
利家の次男。蒲生氏郷の娘を娶る。能登21万石を領した。関ヶ原合戦で西軍に属したため、改易される。その後は京に隠棲し、大坂の陣では中立を保った。
-

前野忠康 (まえのただやす)
豊臣家臣。長康の女婿。舞兵庫の名で知られる。若江八人衆の一人。秀次に重用されるが、その自刃後に浪人。のち石田三成に仕え、関ヶ原で奮戦して討死。
-

前野長康 (まえのながやす)
豊臣家臣。蜂須賀正勝とともに墨俣一夜城の築城に協力し、以後、秀吉の片腕として活躍、但馬出石5万石を領した。のちに豊臣秀次事件に連座し、自害した。
-

前波吉継 (まえばよしつぐ)
朝倉家臣。織田信長の越前侵攻軍にいち早く降り、道案内を担当した。この功によって越前守護代となるが、これを不服とした富田長繁に攻められ、敗死した。
-

真壁氏幹 (まかべうじもと)
常陸の豪族。真壁城主。佐竹家に従う。刀槍の代わりに約一丈の木杖を振り回して武勇を示し「鬼真壁」と恐れられた。のちに佐竹家の秋田転封に従った。
-

真壁宗幹 (まかべむねもと)
常陸の豪族。真壁城主。名は家幹とも。関東享禄の内乱で足利晴氏を擁して古河公方の地位を就かせることに成功した。鹿島神宮を崇敬し、連歌にも精通した。
-

真柄直隆 (まがらなおたか)
朝倉家臣。弟・直澄とともに家中随一の剛勇の士として名を馳せる。姉川合戦で味方兵が敗走する中、徳川軍を相手に奮戦するが、子・隆基とともに戦死した。
-

牧国信 (まきくにのぶ)
三浦家臣。良長の弟。主家滅亡後は兄とともに宇喜多家に仕え、土器尾城主となる。宇喜多家・毛利家間で和議が成立した後は、兄とともに高田城を守った。
-

牧野忠成 (まきのただなり)
徳川家臣。康成の長男。関ヶ原合戦では徳川秀忠に従う。上田攻めで抜け駆けし真田昌幸の策にかかった部下をかばい出奔。のち復帰し、大坂の陣で活躍した。
-

牧野久仲 (まきのひさなか)
伊達家臣。中野宗時の次男。桑折貞長とともに奥州守護代を務め、父とともに伊達家中の政務を取り仕切る。輝宗の代に謀叛を起こすが敗れ、相馬領に逃れた。
-

牧野康成 (まきのやすなり)
徳川家臣。牛久保城主。関ヶ原合戦では徳川秀忠軍に属す。上田城攻めで奮戦するが、軍令違反があり、蟄居する。のちに許されるが、健康を害して隠居した。
-

牧良長 (まきよしなが)
三浦家臣。主君・貞勝の自害後、貞勝の正室を引き取って宇喜多直家に再嫁させる。のちに直家の後援を得て貞勝の弟・貞広を擁して戦い、高田城を奪還した。
-

正木為春 (まさきためはる)
里見家臣。頼忠の子。甥・徳川頼宣(実妹・お万の方の子)が紀伊和歌山藩主となった際、家老として紀伊に赴いた。晩年には仮名草子「あだ物語」を著した。
-

正木時茂 (まさきときしげ)
里見家臣。大多喜城主。槍に長じ「槍大膳」の異名をとった。2度の国府台合戦をはじめとする里見家の合戦にはほとんど参陣し、勇名を近隣諸国に轟かせた。
-

正木時忠 (まさきときただ)
里見家臣。勝浦城主。兄・時茂とともに多くの合戦で戦功を立てる。第二次国府台合戦ののち、正木家の存続を優先して北条家に寝返ったが、のちに帰参した。
-

正木憲時 (まさきのりとき)
里見家臣。時忠または弘季の子という。伯父・時茂の養子となって家督を継ぐ。主君・義頼の強引な家督相続に憤激して謀叛を起こすが敗れ、家臣に殺された。
-

正木頼忠 (まさきよりただ)
里見家臣。時忠の子。父が北条家に属した際、人質となる。兄・時通の死後、居城・勝浦城に戻った。主家改易後は、紀伊徳川家に仕える子・為春を頼った。
-

益子勝清 (ましこかつきよ)
宇都宮家臣。外戚の譜代として、結城家と戦う。重い軍役を強いられ続けたため負担に耐えきれず、宇都宮家から離反して、結城家の水谷正村に降った。
-

増田長盛 (ましたながもり)
豊臣家臣。五奉行の1人として検地などを行う。豊臣秀次の死後、大和郡山20万石を領した。関ヶ原合戦の際は大坂城で豊臣秀頼を守る。戦後、改易された。
-

増田盛次 (ましたもりつぐ)
長盛の子。関ヶ原合戦で父が改易された後は尾張徳川家に仕えていたが、大坂夏の陣直前に大坂城へ入場。長宗我部盛親軍に属し、藤堂勢との戦いで戦死した。
-

鱒沢広勝 (ますざわひろかつ)
阿曾沼家臣。鱒沢館主。関ヶ原合戦の際主君・広長が不在にした隙をついて謀叛を起こす。のちに居城・鍋倉城奪回のため来攻した広長軍との戦いで戦死した。
-

益田景祥 (ますだかげよし)
毛利家臣。元祥の次男。武勇に優れ、小早川隆景に軍功を讃えられる。隆景死後未亡人・問田大方を保護した。関ヶ原後家中の経済再建に父とともに尽力した。
-

益田尹兼 (ますだただかね)
石見の豪族。越中守。大内義興に従って上洛、在京して義興を補佐した。帰国後は大内家と共に尼子家に対抗。子の藤兼に家督を譲ってからも長く後見した。
-

益田藤兼 (ますだふじかね)
大内家臣。益田城主。主家滅亡後は毛利家に従い、山陰平定戦で活躍した。晩年は仏教を厚く信仰した。家臣・品川大膳は山中幸盛と一騎討ちをして敗れた。
-

益田元祥 (ますだもとよし)
毛利家臣。藤兼の子。山陰平定戦で活躍した。関ヶ原合戦後に主家が減封されたあと、国家老に任ぜられて財政の立て直しを行い、萩藩の基盤確立に貢献した。
-

まつ (まつ)
前田利家の正室。2男9女を産む。秀吉の正室・ねねとは昵懇の仲で、賤ヶ岳の戦いでは秀吉と自ら交渉して和議を成立させた。利家没後は、芳春院と号した。
-

松井興長 (まついおきなが)
細川家臣。康之の次男。細川忠興から4代にわたって仕えた。関ヶ原合戦では岐阜城攻めで負傷。島原の乱では幕府や他藩との折衝で活躍した。
-

松井康之 (まついやすゆき)
足利家臣。主君・義輝の横死後は細川藤孝に仕え、丹後平定戦などで活躍した。関ヶ原合戦の際は東軍に属し、豊後杵築2万6千石を得た。茶人としても著名。
-

松岡貞利 (まつおかさだとし)
信濃の豪族。松岡城主。織田家が信濃に進行してくると巨従。本能寺の変後は徳川家に属すが、小笠原貞慶の豊臣方への寝返りに協力したため、改易された。
-

松岡頼貞 (まつおかよりさだ)
信濃の豪族。松岡城主。武田家が伊那に進行してくると、抵抗せずに巨従した。今川義元に父を殺害された井伊直親を城下の菩提寺・松源寺で保護した。
-

松倉右近 (まつくらうこん)
筒井家臣。島清興・森好之とともに、筒井家三老臣の1人に数えられる。主君・定次が伊賀上野に転封となった際は、伊賀名張城を築き、8千3百石を領した。
-

松倉勝家 (まつくらかついえ)
重政の子。父同様キリシタンを厳しく弾圧し、また圧政を敷いて島原の乱を引き起こした。乱鎮圧後改易。切腹すら許されず、大名としては異例の斬首となる。
-

松倉重政 (まつくらしげまさ)
筒井家臣。重信の子。主家の改易後は徳川家に属す。大坂の陣後、肥前島原城主となるが、重税や切支丹弾圧などの圧政を行い、島原の乱の原因を作った。
-

松平清康 (まつだいらきよやす)
松平家7代当主。13歳で家督を継ぐ。積極的な軍事行動で三河を平定し、尾張の織田信秀と戦うが、いわゆる守山崩れにおいて家臣・阿部弥七郎に殺された。
-

松平定勝 (まつだいらさだかつ)
徳川家臣。徳川家康の異父弟。長篠合戦や天目山合戦、小牧長久手合戦に活躍。家康は死に臨んで、2代将軍・秀忠の相談役になるよう頼んだという。
-

松平定行 (まつだいらさだゆき)
徳川家臣。徳川家康の異父弟・定勝の次男。伊予松山藩主として一門初の四国入りをし外様大名の抑えとなった。長崎で南蛮菓子に感動し、タルトを伝えた。
-

松平忠明 (まつだいらただあきら)
奥平信昌の四男。徳川家康の養子となり松平姓を名乗る。大坂の陣で美濃衆を率い、戦後、道頓堀開削など大坂の復興に努めた。のち幕閣の元老的存在となる。
-

松平忠輝 (まつだいらただてる)
徳川家康の六男。容貌の醜さから父に疎まれて育つ。成人後は越後高田75万石を領すが、大坂夏の陣への遅参が豊臣家への内通疑惑を招き、戦後改易された。
-

松平忠利 (まつだいらただとし)
徳川家臣。家忠の長男。伏見城で父が戦死。仇を討つべく関ヶ原本線への参加を願うが、上杉景勝への備えに残された。連歌に優れ里村紹巴とともに信仰があった。
-

松平忠直 (まつだいらただなお)
結城秀康の嫡男。父の死後家督を継ぐ。大坂の陣では真田幸村軍の突撃を阻止するなど活躍。のちに幾多の不行跡を起こしたため、改易され配流処分となった。
-

松平忠昌 (まつだいらただまさ)
徳川家臣。結城秀康の次男。大坂夏の陣に年が若いため出陣を許されないことを恐れ直前に急いで元服。兄・忠直の軍に属して片鎌槍を手に大いに功を上げた。
-

松平忠吉 (まつだいらただよし)
徳川家康の四男。関ヶ原合戦では舅・井伊直政とともに戦端を開く。負傷しながらも島津義弘軍を討つなど戦功を立て、戦後、尾張清洲62万石を領した。
-

松平忠良 (まつだいらただよし)
徳川家臣。徳川家康の異父弟・松平康元の長男。姉妹に津軽信枚の妻・満天姫がいる。関ヶ原合戦に従軍。大坂の陣で功を上げ、美濃大垣5万石に加増された。
-

松平直政 (まつだいらなおまさ)
結城秀康の三男。大坂の陣で、祖父・徳川家康の目にかなうよう、兄・松平忠直に属して奮戦。戦後、大名となる。「油口」と呼ばれるほど弁が立った。
-

松平長親 (まつだいらながちか)
松平家5代当主。今川氏親や北条早雲の度重なる攻撃から領国を守り抜き、松平家発展の基礎を築く。徳川家康が生まれた際、竹千代と命名した。
-

松平信綱 (まつだいらのぶつな)
大河内久綱の長男。徳川家光に仕えて小姓から老中にまで出世し、「知恵伊豆」の異名を取った。島原の乱では総大将を務め、鎮圧に成功した。
-

松平信康 (まつだいらのぶやす)
徳川家康の長男。織田信長の娘・五徳を娶る。剛勇英邁の人となりで、将来を嘱望されるが、のちに信長から武田家への内通を疑われ、父の命により自害した。
-

松平乗寿 (まつだいらのりなが)
徳川家臣。家乗の長男。徳川家綱に仕え家綱が4代将軍になると、老中として幕政を取り仕切った。時の儒者・林鵞峰は彼を「柔懦な人物」と評した。
-

松平秀康 (まつだいらひでやす)
徳川家康の次男。結城家の家督を継ぐ。関ヶ原合戦の際は関東に残って上杉景勝に備え、戦後、越前福井75万石を領した。激しい気性の持ち主だったという。
-

松平広忠 (まつだいらひろただ)
三河の戦国大名。清康の子。一時は居城の岡崎城を追われるがのちに復帰。今川義元の庇護を受けて領国経営を進めるが反松平派の刺客・岩松八弥に殺された。
-

松平康重 (まつだいらやすしげ)
徳川家臣。康親の長男。元服時に家康から一字を賜る。駿河沼津城を守り、北条家に備えた。小田原征伐で活躍し、関東入国の際に武蔵騎西2万石を領した。
-

松平康長 (まつだいらやすなが)
徳川家臣。旧姓戸田。家康より松平姓を許される。高天神城攻めに初陣して以来各地で功を立てた。関ヶ原合戦では大垣城を攻略。後に信濃松本7万石を領す。
-

松田憲秀 (まつだのりひで)
北条家臣。筆頭家老を務めた。豊臣秀吉の小田原征伐の際は小田原城への籠城を主張し採用された。のちに秀吉に寝返ろうとして失敗、戦後、自害させられた。
-

松永長頼 (まつながながより)
三好家臣。久秀の弟。軍事的才幹をもって主君・長慶に仕え、のちに山科七郷の代官となる。しかし、丹波黒井城主・赤井直正の攻撃を受けて敗れ、戦死した。
-

松永久秀 (まつながひさひで)
三好家臣。主家を簒奪し、将軍・足利義輝を殺し、東大寺大仏殿を焼いた稀代の梟雄。のち織田信長に属し、謀叛を起こすが敗れ「平蜘蛛」とともに爆死した。
-

松永久通 (まつながひさみち)
三好家臣。大和多聞山城主。久秀の子。父に従い、将軍・足利義輝の謀殺などに加担した。のちに織田信長に属すが、父とともに信長に背いて敗れ、自害した。
-

松根光広 (まつねみつひろ)
三好家臣。大和多聞山城主。久秀の子。父に従い、将軍・足利義輝の謀殺などに加担した。のちに織田信長に属すが、父とともに信長に背いて敗れ、自害した。
-

松野重元 (まつのしげもと)
小早川家臣。鉄砲頭を務め、主馬首に任官された。関ヶ原合戦では主君・秀秋の寝返りに呼応せず、戦場を離脱した。その後は田中吉政、徳川忠長に仕えた。
-

松姫 (まつひめ)
武田信玄の娘。武田家と織田家の同盟強化のため、織田信長の長男・信忠の婚約者となるが、両家が手切れしたことで婚約は破棄。生涯独身で過ごした。
-

松前景広 (まつまえかげひろ)
松前家臣。慶広の七男。松前氏が先祖とする新羅三郎義光にちなみ新羅大明神の社を建て、松前氏代々のアイヌとの戦いの記録『新羅之記録』を著した。
-

松前公広 (まつまえきんひろ)
蠣崎松前家7代当主。盛広の子。祖父・慶広の後見により家督を継ぐ。のちに江戸幕府から正式に跡目として認められ、慶広の死後、松前藩3代当主となった。
-

松前盛広 (まつまえもりひろ)
蠣崎松前家6代当主。盛広の子。徳川家康が内大臣となった際、父とともに家康に拝謁した。1600年に松前藩2代藩主となるが、父が先立ち病死した。
-

松前慶広 (まつまえよしひろ)
蠣崎松前家5代当主。季広の子。豊臣秀吉に接近して蝦夷地における交易権を獲得、独立領主となった。1599年に徳川家康に家系図を献上し、松前姓に改めた。
-

松本氏輔 (まつもとうじすけ)
蘆名家臣。舜輔の子。松本家は蘆名四天の宿老の一。図書助と称し、船岡城主を務めた。1575年、田村清顕の軍と安積郡福原で戦った際に戦死した。
-

松浦興信 (まつらおきのぶ)
肥前の豪族。平戸城主。大内家に属し、主君・義興の偏諱を受けた。松浦家は、嵯峨源氏渡辺家の流れで、渡辺久が肥前松浦郡に住み松浦姓を名乗ったという。
-

松浦鎮信 (まつらしげのぶ)
肥前の豪族。平戸城主。隆信の子。豊臣秀吉の九州征伐軍に従う。海外通商を行い、唐船・南蛮船の寄港に尽力。関ヶ原合戦で東軍に属し、所領を安堵された。
-

松浦隆信 (まつらたかのぶ)
肥前の豪族。平戸城主。興信の子。平戸港を拠点として南蛮貿易を行う。豊富な資金力を背景に勢力を拡大するが、のちに龍造寺隆信に敗れ、隆信に従属した。
-

松浦隆信 (まつらたかのぶ)
平戸松浦氏28代当主。久信の嫡男。曾祖父も同名の隆信。父の死により平戸3代藩主になる。貿易に無理に介入したため、イギリス人からバカ殿と呼ばれた。
-

的場昌長 (まとばまさなが)
紀州の豪族。石山合戦で本願寺家に与して織田軍を破り、勇名を馳せる。狙撃・撤退を繰り返す戦術を得意とし、「小雲雀(こひばり)」の異名で恐れられた。
-

間宮康俊 (まみややすとし)
北条家臣。信高の父。伊豆の水軍を率い里見家に備えた。小田原征伐では、山中城で奮戦するが討死した。死に際して、白髪を晒さぬように染めていたという。
-

真里谷全方 (まりやつぜんほう)
真里谷武田家の一族。信勝の子。恕鑑の弟。当主・恕鑑死後の家督争いで、真里谷信応に味方し、勝利を収める。以後は当主となった信応の補佐役となった。
-

真里谷信隆 (まりやつのぶたか)
真里谷武田家一族。信保の庶長子。異母弟・信応と家督を争う。一時は居城・峯上城を落とされて逃亡したが、北条家の後援で真里谷城に復帰、家督を継いだ。
-

真里谷信高 (まりやつのぶたか)
真里谷武田家一族。信応の子。豊臣秀吉の小田原征伐において徳川軍に敗れ、那須に逃れた。この際、財宝をどこかに隠して逃れたという伝説が残っている。
-

真里谷信応 (まりやつのぶまさ)
真里谷武田家一族。信保の次男。異母兄の信隆と家督を争う。一時は小弓公方・足利義明の後援で家督を継ぐが、義明死後は力を失い、里見家を頼ったという。
-

真里谷信政 (まりやつのぶまさ)
真里谷武田家の第6代当主。上総椎津城主。北条は信政を味方につけ里見を討とうとするが、里見は先手を打ち、椎津城を攻撃。信政は敗れ、自刃した。
-

丸目長恵 (まるめながよし)
相良家臣。上泉信綱に剣術を学び、新陰タイ捨流を開いた。島津軍との戦いで敗因を作り、一時逼塞。のちに復帰して兵法師範を務め、開墾事業にも従事した。
-

三浦按針 (みうらあんじん)
徳川家外交顧問。イギリス人。本名はウィリアム・アダムス。豊後に漂着した南蛮船の航海士だったが、家康の命で徳川家に仕え、日本名・按針を与えられた。
-

三浦貞勝 (みうらさだかつ)
美作の豪族。高田城主。貞久の嫡男。旧臣を糾合し、父の死により尼子家に奪われた高田城を奪還した。しかし、のちに三村家親の攻撃を受け敗北、自害した。
-

三浦貞久 (みうらさだひさ)
美作の豪族。高田城主。尼子家に攻められ、数年の攻防の末に病死する。間もなく高田城は尼子家に占領された。三浦家は関東の豪族・三浦義明の末裔という。
-

三浦貞広 (みうらさだひろ)
美作の豪族。高田城主。貞久の次男。尼子家に属したため、毛利家に居城を追われる。山中幸盛らの援助で奪還するが、再び毛利家に居城を追われ、逐電した。
-

三浦貞盛 (みうらさだもり)
三浦家臣。貞久の弟。甥・貞勝を自害に追い込んだ三村元親が宇喜多直家に殺されたあと、三村家に奪われていた高田城を奪回し貞勝の弟・貞広を城主とした。
-

三浦元忠 (みうらもとただ)
毛利家臣。吉川元春の次男・繁沢元氏の娘を娶り、元氏に代わって周防の旧族・三浦家を継ぐ。主君・輝元の側近として取次役を務め、1万6千石を知行した。
-

三木通秋 (みきみちあき)
播磨の豪族。英賀城主。三木家は河野家の庶流。織田信長の石山本願寺攻めでは本願寺に協力した。羽柴秀吉の中国侵攻軍に対抗するが敗れ、九州に逃亡した。
-

三雲成持 (みくもしげもち)
六角家臣。兄・賢持の死後、家督を継いだ。「六角氏式目」には父・定持とともに署名している。主家滅亡後は浪人生活を経て、織田信雄・蒲生氏郷に仕えた。
-

三沢為清 (みさわためきよ)
尼子家臣。三沢城主。一時大内義隆に属すが、義隆の出雲侵攻が失敗した際に帰順した。のちに毛利元就の出雲侵攻軍に降伏した。子孫は長府毛利家に仕えた。
-

御宿勘兵衛 (みしゅくかんべえ)
北条家臣。初名は綱秀、別名に政友。今川・武田家に仕えたあと、結城秀康に仕官。秀康の子・忠直の代に出奔して大坂城に入城、大坂夏の陣にて戦死した。
-

水越勝重 (みずこしかつしげ)
神保家臣。富山城や滝山城の築城に携わった。主家衰退後は一向一揆とともに上杉謙信と戦うが敗れ、一揆勢の首謀者を捕らえて上杉軍に降伏し、助命された。
-

水谷胤重 (みずたにたねしげ)
相馬家臣。関ヶ原合戦後、領内の通過を願う伊達政宗の殺害を唱える声が多い中で唯一反対し、政宗は無事領内を通過。この一件により、主家は改易を免れた。
-

水野勝成 (みずのかつなり)
徳川家臣。遠江高天神城攻めなど多くの合戦に従軍した。一時は豊臣秀吉などに仕えたが、のちに帰参し、備中福山10万石を領す。島原の乱にも参陣した。
-

水野重央 (みずのしげなか)
徳川家臣。徳川家康の母・於大の方の甥に当たるため家康に重用された。家康の十男・徳川頼宣の付家老に任じられ、紀州新宮3万5千石を与えられた。
-

水野忠清 (みずのただきよ)
徳川家臣。忠重の四男。家督は兄・勝成が継いだため、徳川秀忠に仕えた。大坂夏の陣で大野治房を討ち取ったが、論功行賞で争ったため、閉門を命じられた。
-

水野忠政 (みずのただまさ)
三河の豪族。徳川家康の母・於大の方の父。三河国に刈谷城を築く。織田家と松平家の間をうまく立ち回り、水野家の領土を守りきった。
-

水野信元 (みずののぶもと)
三河の豪族。刈谷城主。早くから信長と良好な関係を築き、清洲同盟の仲介役となる。姉川や三方ヶ原の戦いでも活躍するが、武田との内通を疑われ殺された。
-

水谷勝隆 (みずのやかつたか)
常陸下館2代藩主。のち備中成羽を経て備中松山藩主となり、交通路と水路の整備、玉島新田開発、製鉄業振興を行う。また幕府の信頼も厚かった。
-

水谷正村 (みずのやまさむら)
結城家臣。下館城主。結城四天王の一。おもに下野方面に出陣し、宇都宮家と抗争を繰り広げた。のちに豊臣秀吉の小田原征伐に参陣し、所領を安堵された。
-

水野分長 (みずのわけなが)
徳川家臣。忠政の孫。重央の兄。小牧長久手合戦や小田原征伐に出陣。徳川家康の命で蒲生氏郷に属し九戸政実の乱鎮圧に活躍した。のち帰参し大番頭となる。
-

溝江長逸 (みぞえながゆき)
朝倉家臣。堀江景忠に謀叛の風聞があった際は景忠を攻撃し、追放した。織田信長の越前侵攻軍に降り、本領を安堵されるが、一向一揆勢に攻められ戦死した。
-

溝尾茂朝 (みぞおしげとも)
明智家臣。通称は庄兵衛。主君・光秀の側近を務め、厚い信頼を受けた。山崎合戦の敗北後、光秀の命で介錯を行い、光秀の首を藪中へ隠したのち、自害した。
-

溝口貞泰 (みぞぐちさだやす)
小笠原家臣。主君・貞慶の旧領復帰に尽力する。貞慶の側近として政務に参画、また侍大将として各地に出陣するなど活躍した。のちに『溝口家記』を著した。
-

溝口長勝 (みぞぐちながかつ)
小笠原家臣。武田信玄に居城を追われた主君・長時を援助し、弓などを下賜される。のちに長時を居城に迎えるが、信玄に敗れ、長時に従い三好長慶を頼った。
-

溝口長友 (みぞぐちながとも)
小笠原家臣。美作守と称す。嫡男・長勝とともに主家に仕え、活躍した。主君・長時が信濃を退去し、三好家を頼った際これに従う。72歳で戦死したという。
-

溝口宣勝 (みぞぐちのぶかつ)
秀勝の嫡男。父の死後家督を相続、越後新発田藩5万石の2代藩主となった。その際、弟の善勝に1万2千石を分与し、沢海藩を創設させている。
-

溝口秀勝 (みぞぐちひでかつ)
丹羽家臣。のちに織田家直臣となる。本能寺の変後は豊臣秀吉に属す。朝鮮派兵の際は肥前名護屋城を守備した。関ヶ原合戦で東軍に属し、所領を安堵された。
-

溝口善勝 (みぞぐちよしかつ)
徳川家臣。秀勝の次男。徳川秀忠に仕えた。父の死に際し、兄・宣勝が江戸での奉公のためと遺領を分与。これに秀忠が感動し分与が認められ、大名となった。
-

三田井親武 (みたいちかたけ)
日向の豪族。三田井家は祖母嶽明神の子孫と称する大神家の一門。日向延岡を領した高橋元種に従わず、反抗したため、高橋軍の攻撃を受け、敗死した。
-

三木顕綱 (みつきあきつな)
姉小路家臣。姉小路良頼の次男。養父・鍋山安室を毒殺して養母を追放し、鍋山城を乗っ取る。のちに兄・頼綱への謀叛を企てたため、妻とともに暗殺された。
-

三木国綱 (みつきくにつな)
姉小路家臣。主君・頼綱の妹を娶る。金森長近率いる飛騨侵攻軍に敗れ、捕縛されるが助命される。のち、長近の支配に不満を持ち謀叛を起こすが、敗死した。
-

三木近綱 (みつきちかつな)
姉小路頼綱の末子。豊臣秀吉に姉小路家が滅ぼされた時、他家に人質に出ていて生き残る。大坂の陣で徳川家に仕え、敵中で奮戦。戦後5百石を与えられた。
-

三木直頼 (みつきなおより)
飛騨の豪族。桜洞城を築いて居城とし、版図を拡大する。飛騨国司・姉小路家や美濃の土岐家、本願寺などと友好関係を結び、飛騨国内に一大勢力を築いた。
-

三淵晴員 (みつぶちはるかず)
足利家臣。細川藤孝の父。義晴・義輝・義昭の3代に仕える。義晴・義輝が細川晴元に攻められた際、二人を近江の坂本へ逃がした。
-

三淵光行 (みつぶちみつゆき)
細川藤孝の甥。父・藤英の自害後、藤孝に養育される。関ヶ原合戦に際し、丹後田辺城に籠もり、西軍と戦う。功績を徳川家康に賞され、近江に所領を得た。
-

三刀屋久扶 (みとやひさすけ)
尼子家臣。主家が毛利家攻めに敗れると大内家に寝返る。しかし、大内家が尼子家攻めに失敗すると、再び尼子家に帰属するが、その後また毛利家に降った。
-

南方就正 (みなかたなりまさ)
毛利家臣。周防右田岳城主。大友宗麟の援助を得た大内輝弘が、大内家旧臣を糾合して周防で叛乱を起こした際、防府に退却する輝弘軍を追撃、これを討った。
-

皆川広照 (みながわひろてる)
下野の豪族。皆川城主。俊宗の子。北条家滅亡時に徳川家康に降る。のちに家康の六男・松平忠輝の付家老となったが、忠輝の不行跡を訴えて逆に改易された。
-

南長義 (みなみながよし)
南部家臣。南部政康の三男。浅水城主。三戸城の南に屋敷を構えたため、南殿と呼ばれた。晴政死後の家督争いで信直を支持、家督相続に貢献した。
-

壬生綱雄 (みぶつなたけ)
宇都宮家臣。壬生・鹿沼城主。綱房の嫡男。北条家に接近し、主家からの自立をはかったため、宇都宮家に通じていた叔父・周良に鹿沼城に招かれて殺された。
-

壬生綱房 (みぶつなふさ)
宇都宮家臣。壬生城主。筆頭家老を務めた。権謀術数を駆使して主君の忠綱・興綱を死に追いやり、興綱の子・尚綱が戦死したのち、宇都宮城を乗っ取った。
-

壬生義雄 (みぶよしたけ)
宇都宮家臣。壬生城主。綱雄の嫡男。叔父・周良を討ち父の敵を取る。のち北条家に属す。豊臣秀吉の小田原征伐の際は小田原城に籠城、戦後間もなく没した。
-

三村家親 (みむらいえちか)
備中の豪族。鶴首城主。周辺の豪族を切り従え、備中最大の勢力となる。備前・美作への進出を企み、宇喜多直家と抗争を展開するが、直家により暗殺された。
-

三村親成 (みむらちかしげ)
三村家臣。家親の弟。甥・元親が勢力回復を目指して織田信長に通じた際、反対して追放される。のちに毛利軍を案内して元親を討ち、戦後鶴首城主となった。
-

三村元親 (みむらもとちか)
備中の豪族。家親の子。父の死後家督を継ぐ。毛利家に属して勢力回復を企むが父の敵・宇喜多直家が毛利家と結んだため毛利家から離反、攻められ自害した。
-

三村元範 (みむらもとのり)
三村家臣。杠(こう)城主。家親の子。兄・元親が毛利家から離反したため、毛利家の大軍に居城を攻められ衆寡敵せず戦死した。長刀の達人であったという。
-

宮城政業 (みやぎまさなり)
岩付太田家臣。北条氏政の三男・氏房の岩付太田家入嗣後は北条家に属す。孫・泰業は馬上奉行を務め、主家滅亡後は主君・氏房らとともに高野山に上った。
-

三宅総広 (みやけふさひろ)
畠山家臣。畠山七人衆の一人。温井総貞と結んで遊佐家を破り、権勢を振るう。のち加賀の一向一揆を扇動して畠山義綱に反乱するが敗死したという。
-

三宅康信 (みやけやすのぶ)
徳川家臣。康貞の長男。関ヶ原合戦で横須賀城番、戦後、伊勢亀山の城番を務めた。大坂冬の陣では駿府城を、夏の陣では淀城を守備。のち亀山藩主となる。
-

宮崎隆親 (みやざきたかちか)
大崎家臣。宮崎城主。侍大将を務めた。葛西・大崎一揆の際は総大将を務め、居城に籠城して伊達軍と戦ったが敗れた。落城後は秋田仙北に隠れ住んだという。
-

宮部継潤 (みやべけいじゅん)
浅井家臣。はじめ比叡山の僧。主家滅亡後は織田信長に属す。羽柴秀吉率いる中国征伐軍の先鋒を務め、因幡鳥取城主となった。晩年は秀吉の御咄衆となった。
-

宮部長房 (みやべながふさ)
豊臣家臣。因幡鳥取城主。継潤の子。朝鮮派兵などに従軍。関ヶ原合戦では一時東軍に属すが、西軍に寝返り伏見城攻撃などに参加したため、戦後改易された。
-

宮本武蔵 (みやもとむさし)
独自の剣法「二天一流」を創出し、生涯六十六回の試合で無敗を誇った剣豪。晩年は細川忠利の客分となり、書画や禅に親しみながら「五輪書」を著した。
-

妙玖 (みょうきゅう)
毛利元就の正室。吉川国経の娘。隆元、元春、隆景の生母。夫婦仲は良好だったらしく、その死後に書かれた元就の書状には妻を偲ぶ言葉が多く残されている。
-

妙蓮夫人 (みょうれんふじん)
種子島時堯の次女。島津義久の継室になるが、男児には恵まれなかった。薩摩藩の初代藩主となる忠恒の正室・亀寿を産んだ。
-

三好実休 (みよしじっきゅう)
三好家臣。元長の次男。兄・長慶の畿内進出後、本国・阿波の経略を担当。長慶の片腕として内政、軍事に活躍したが、和泉久米田合戦で戦死。茶道に長じた。
-

三吉隆亮 (みよしたかすけ)
備後の豪族。比熊山城主。大内家に属し毛利家と和戦を繰り返したが、のちに父・到高とともに毛利家に属す。以後は毛利家臣として備中や石見を転戦した。
-

三好長治 (みよしながはる)
義賢の子。父の死後、篠原長房の後見で家督を継ぐが、讒言に惑わされ、細川真之とともに長房を討った。のちに長宗我部元親に通じた真之と戦い、敗死した。
-

三好長逸 (みよしながゆき)
三好家臣。三好三人衆の筆頭。主君・義継や松永久秀らと離合集散を繰り返し、家中に混乱を招く。のち織田信長の畿内平定軍に敗れ逃亡、行方不明となった。
-

三好長慶 (みよしながよし)
細川家臣。主家の実権を奪って勢力を拡げ、主君・晴元を追放して畿内の掌握に成功した。しかし嫡男・義興や弟たちの死後は心身に支障をきたし、病死した。
-

三吉広高 (みよしひろたか)
毛利家臣。比熊山城主。隆亮の子。関ヶ原合戦後、主家が防長に移封され居城は廃されたため、浪人となり京都に上る。のち安芸広島藩主・浅野長晟に仕えた。
-

三好政勝 (みよしまさかつ)
細川家臣。榎並城主。政長の子。父を殺した三好長慶と争う。長慶死後は三好三人衆と和解した。織田信長の畿内平定軍に降った。のち豊臣、徳川家に仕えた。
-

三好政長 (みよしまさなが)
細川家臣。摂津榎並城主。主君・晴元の側近として各地の合戦で活躍する。のちに一族の三好長慶と対立してたびたび合戦におよび、摂津江口合戦で敗死した。
-

三好政康 (みよしまさやす)
三好家臣。三好三人衆の1人。松永久秀とともに将軍・足利義輝を殺害した。織田信長の畿内平定軍に敗れ、逃亡。のち豊臣家に仕え、大坂夏の陣で戦死した。
-

三好康長 (みよしやすなが)
三好家臣。長慶の叔父。咲岩と号した。織田信長の上洛軍に敗れ、家臣となる。阿波・讃岐の国衆を多く信長方に誘引した。本能寺の変後は豊臣秀吉に従った。
-

三好義興 (みよしよしおき)
長慶の嫡男。室町幕府御供衆を務めた。六角家や畠山家との合戦に勝つなど活躍し、将来を嘱望されたが、22歳で急逝した。松永久秀に毒殺されたともいう。
-

三好義継 (みよしよしつぐ)
十河一存の子。三好長慶の死後、三好三人衆の後見で宗家を継ぐ。織田信長に降るが、京を追われた足利義昭を保護したため、織田軍の攻撃を受け、敗死した。
-

明叔慶浚 (みんしゅくけいしゅん)
三木家臣。臨済宗妙心寺本山の高僧。三木直頼が再興した三木家の菩提寺・禅昌寺の住持となる。懇意であった太原雪斎に招かれ、一時今川家にも仕えた。
-

向井忠勝 (むかいただかつ)
徳川家臣。正綱の子。通称将監。父同様水軍を率い、大坂の陣で活躍。大坂湾の制海権を確保する。幕府の船手頭として水軍を管轄。造船の名手だった。
-

向井正綱 (むかいまさつな)
武田家臣。父・正重が徳川軍の攻撃を受けて戦死したため、家督を相続する。主家滅亡後は徳川家に仕えて御船奉行となり、徳川水軍の中核として活躍した。
-

椋梨盛平 (むくなしもりひら)
小早川家臣。大内家が出雲遠征に失敗したあと、尼子家に寝返った杉原理興に攻められるが、毛利元就や乃美隆興らとともに迎え撃ち、理興の軍勢を撃退した。
-

武藤友益 (むとうともます)
若狭の豪族。石山城主。稲葉館の伊崎堯為を討ち、近隣の豪族を従えて織田信長の若狭侵攻軍と戦うが敗れ、降伏。しかし織田軍が若狭から退くと再び背いた。
-

宗像氏貞 (むなかたうじさだ)
大内家臣。宗像大社大宮司。正氏の子。父の猶子・ 氏男の死後、陶晴賢の支持を得て家督争いを制した。宗像家最大の版図を築くが、嗣子が無いまま急死した。
-

宗像正氏 (むなかたまさうじ)
大内家臣。宗像大社大宮司を務めた。尼子家との戦いや安芸大野城攻撃などで活躍し、主君・義隆から周防黒川郷を与えられる。以後は黒川隆尚と名を改めた。
-

武鑓重信 (むやりしげのぶ)
葛西家臣。武鑓城主。富沢家の叛乱鎮定や、浜田家と熊谷家の兵乱鎮圧などに従軍し、活躍した。桃生郡深谷において弟の儀信とともに伊達政宗に謀殺された。
-

村井貞勝 (むらいさだかつ)
織田家臣。家中随一の吏僚。京都所司代を務め、京の治安維持、禁裏の修築などに従事し、主君・信長の内政を助けた。本能寺の変の際、二条御所で戦死した。
-

村井長頼 (むらいながより)
前田家臣。伊勢攻めの功により、利家から「又」の一字を貰い又兵衛と名乗る。奥村長福と共に前田家の重鎮として活躍する。金沢奉行を務め1万石を領した。
-

村上景親 (むらかみかげちか)
毛利家臣。武吉の子。小早川隆景に従い転戦。その武勇から、関ヶ原合戦後に他家より招きを受けるが、引き続き毛利家に属し御船手組組頭を務めた。
-

村上国清 (むらかみくにきよ)
上杉家臣。義清の子。武田信玄との戦いに敗れた父とともに越後に逃れる。以後は上杉家に仕え、山浦姓を名乗った。徳川家康との和議締結などに貢献した。
-

村上武吉 (むらかみたけよし)
能島村上水軍の頭領。厳島合戦において毛利軍の勝利に大きく貢献する。以後は毛利家に仕え、木津川口合戦で織田水軍に大勝するなど各地で勇名を馳せた。
-

村上忠勝 (むらかみただかつ)
徳川家臣。義明の養嗣子。家臣の争いを収められず、それを理由に改易、忠勝は配流されて早世した。改易は大久保長安事件に連座したためともいわれる。
-

村上通康 (むらかみみちやす)
河野家臣。来島村上水軍の頭領。主君・通直から後継者に指名されるが、反対意見が多く実現しなかった。厳島合戦では毛利軍に協力し、その勝利に貢献した。
-

村上元吉 (むらかみもとよし)
毛利家臣。武吉の嫡男。父より村上水軍頭領の座を継ぐ。関ヶ原合戦では西軍に属し、故地伊予を治める加藤嘉明を攻めるも、討死する。
-

村上義明 (むらかみよしあき)
豊臣家臣。名は頼勝とも。初め丹羽長秀に仕える。長秀死後、秀吉の直臣となるが、のちに秀吉の命で堀秀政の与力大名となった。関ヶ原合戦では東軍に与す。
-

村上義清 (むらかみよしきよ)
信濃の豪族。葛尾城主。武田信玄軍の攻撃を2度も退け、近隣に勇名を轟かす。しかし、真田幸隆の計略に敗れて居城を失い、越後の長尾景虎の庇護を受けた。
-

村上義忠 (むらかみよしただ)
能島村上水軍の頭領。村上水軍は村上師清が村上家を三分割し、嫡男・義顕を能島家、次男・顕忠を因島家、三男・顕長を来島家の祖としたことに始まる。
-

村田吉次 (むらたよしつぐ)
黒田家臣。黒田二十四騎の一。宝蔵院流槍術の免許皆伝で武勇に優れ、朱槍を許可された。一方で気性が激しく、気に食わないからと領民を虐殺したりしている。
-

村松殿 (むらまつどの)
小山田茂誠の正室。真田昌幸の長女。真田家が織田家に従属する際、安土城で暮らしていたとも。大坂夏の陣の直前、実弟・幸村から最後の手紙を受け取った。
-

室賀正武 (むろがまさたけ)
北信濃の豪族。武田家滅亡後は森長可に仕え芋川一揆鎮圧に活躍。本能寺の変後は徳川家康に属し、真田昌幸と対立。昌幸抹殺を謀るが、逆に暗殺された。
-

愛姫 (めごひめ)
伊達政宗の正室。陸奥豪族・田村清顕の娘。伊達家との友好のため政宗に嫁いだ。才色兼備で知られ、よく内助の功を尽くして政宗を支えたといわれている。
-

米良祐次 (めらすけつぐ)
伊東家臣。日向門川城主。主家の日向退去後、人質を出して島津家に属すが、大友家に通じて日向国内の情報を流した。耳川合戦では大友軍に属し、戦死した。
-

毛受勝照 (めんじゅかつてる)
柴田家臣。主君・勝家の小姓頭として1万石を領す。賤ヶ岳合戦で柴田軍が壊走した際、羽柴軍の追撃を阻んで奮戦。勝家を越前へ退却させたあと、戦死した。
-

毛利勝永 (もうりかつなが)
豊臣家臣。関ヶ原合戦で西軍に属して土佐に配流されるが、脱走して大坂城に入る。真田幸村に次ぐ人望を得て大坂夏の陣で活躍したが、落城に伴い自害した。
-

毛利新助 (もうりしんすけ)
織田家臣。桶狭間合戦では敵将今川義元の首級を取り、戦後黒母衣衆の一員となる。その後は馬廻役として活躍するが、本能寺の変の際に二条御所で討死した。
-

毛利高政 (もうりたかまさ)
豊臣家臣。備中高松城攻めの際に毛利家の人質となり、以後、森姓を毛利姓に改めた。関ヶ原合戦では西軍に属したが、戦後、豊後佐伯2万石を与えられた。
-

毛利隆元 (もうりたかもと)
安芸の戦国大名。元就の嫡男。大内家の人質となり、大内義隆から加冠され元服した。父の後見を受けて中国経略に従事するが、出雲遠征に向かう途中に急死。
-

毛利輝元 (もうりてるもと)
毛利隆元の嫡男。祖父・元就の死後、毛利家を継ぎ、秀吉の下では五大老の1人となる。関ヶ原合戦では西軍総大将の座に就くが、戦場に出ることはなかった。
-

毛利秀包 (もうりひでかね)
毛利元就の九男。兄・隆景の養子となった。豊臣秀吉に寵愛され、偏諱を賜る。朝鮮派兵の際は隆景を助けて活躍した。関ヶ原合戦で西軍に属し、改易された。
-

毛利秀就 (もうりひでなり)
輝元の長男。関ヶ原合戦後に家督相続。初代萩藩主となる。結城秀康の娘を娶り大坂の陣には関東方として出陣した。遊興飲酒を好み、義兄・秀元と対立した。
-

毛利秀元 (もうりひでもと)
穂井田元清の子。従兄弟・輝元の養子となる。豊臣秀吉の朝鮮派兵の際は毛利軍を指揮した。関ヶ原合戦の際は主戦場に赴き「宰相殿の空弁当」の逸話を生む。
-

毛利元就 (もうりもとなり)
安芸の戦国大名。権謀術数を駆使して勢力を拡大、中国10カ国の主となった稀代の謀将。厳島合戦では数々の謀略で陶晴賢を翻弄、5倍の兵力の敵を破った。
-

毛利元康 (もうりもとやす)
毛利元就の八男。出雲末次城を居城として末次姓を名乗る。のちに備後神辺1万5千石を領した。関ヶ原合戦では西軍に属し、近江大津城への攻撃を指揮した。
-

最上家親 (もがみいえちか)
最上家12代当主。義光の次男。父の死後、家督を継ぐ。対立していた弟・義親を討ち領内統一を進めるが、間もなく死去。叔父・楯岡光直が毒殺したという。
-

最上義光 (もがみよしあき)
最上家11代当主。義守の嫡男。父を隠居させ、弟を殺して当主となる。密約外交や敵重臣の暗殺など、権謀術数の限りを尽くし、最上家最大の版図を築いた。
-

最上義忠 (もがみよしただ)
最上家臣。最上義光の四男。甥・義俊に代わる当主候補に推される。しかしこれが御家騒動を招き、主家は改易された。のちに水戸徳川家に仕え家老を務めた。
-

最上義親 (もがみよしちか)
最上義光の三男。兄・家親と同年生まれという。清水城主・清水義氏の養子となった。のちに兄と対立し、家親の家臣・日野将監らの攻撃を受け、自害した。
-

最上義時 (もがみよしとき)
最上家臣。最上義守の次男。父の偏愛を受け、兄・義光と家督を巡り対立。義光の政策に反発する天童頼貞らに擁立されて戦うが、義光に攻められて自害した。
-

最上義俊 (もがみよしとし)
最上家13代当主。家親の嫡男。父の死後、家督を継ぐ。しかし若年の上、不行跡などで御家騒動を招き、改易された。改易後は近江に1万石を与えられた。
-

最上義守 (もがみよしもり)
最上家10代当主。2歳で家督を相続する。次男・義時を偏愛して家督を譲ろうとするが、伊達家の騒動に乗じた長男・義光が決起、強制的に隠居させられた。
-

望月千代女 (もちづきちよめ)
武田家臣。夫が川中島合戦で討死すると武田信玄にくの一として仕える。全国各地を歩き、様々な術を用いて情報収集する「歩き巫女」たちを育成した。
-

本山茂辰 (もとやましげとき)
土佐の豪族。茂宗の子。長宗我部国親の娘を娶る。のちに敵対し、長浜戸合戦で長宗我部軍に敗れて平野部の拠点・土佐朝倉城を失い、凋落の一途をたどった。
-

本山茂宗 (もとやましげむね)
土佐の豪族。本山城主。嶺北地方一帯に加え南方の平野部に支配圏を広げ、本山家最大の版図を築いた。のちに子・茂辰に本山城を譲り、土佐朝倉城に移った。
-

本山親茂 (もとやまちかしげ)
土佐の豪族。茂辰の子。長宗我部元親との戦いで初陣、奮戦するが敗退する。間もなく家督を継ぐが、長宗我部軍の猛攻に遭い降伏し、長宗我部家臣となった。
-

籾井教業 (もみいのりなり)
波多野家臣。籾井城主。武勇をもって鳴り、「赤鬼」と称された赤井直正と並んで「青鬼」の異名をとった。羽柴秀吉率いる中国侵攻軍に攻められ、戦死した。
-

百地三太夫 (ももちさんだゆう)
伊賀の豪族。服部・藤林と並ぶ伊賀上忍家の一つ。忍術を駆使して織田信雄の伊賀侵攻軍を撃退するが、のちに織田信長の大軍の攻撃を受け、戦死したという。
-

桃井義孝 (もものいよしたか)
上杉家臣。上杉謙信の父・長尾為景に従うが、のちにその仇敵・上条定憲に寝返る。御館の乱では上杉景虎に加勢して御館に入るが、討死した。
-

森岡信元 (もりおかのぶもと)
津軽家臣。主君・為信の創業期を支えた大浦三老の1人。石川高信との戦いに参加して和徳城を攻略、城主となる。のちに為信から叛意を疑われ謀殺された。
-

森下道誉 (もりしたみちよ)
山名家臣。中村春続とともに主君・豊国を追放し、吉川経家に属して鳥取城を守る。しかし羽柴秀吉の「渇え殺し」戦法に敗れ、経家や春続とともに自害した。
-

森田浄雲 (もりたじょううん)
伊賀の豪族。猪田郷を所領とした。豪族連合の中心人物の1人という。織田信長の伊賀侵攻軍に対し、一之宮城を守って奮戦したが衆寡敵せず落城、戦死した。
-

森忠政 (もりただまさ)
豊臣家臣。可成の六男。兄・長可の戦死により家督を継ぐ。関ヶ原合戦では徳川秀忠に従い、上田城攻撃に従軍した。のちに美作津山18万石に転封された。
-

母里太兵衛 (もりたへえ)
黒田家臣。後藤基次と双璧をなした家中屈指の猛将。福島正則が大杯に満たした酒を呑み干し、名槍「日本号」を拝領した。その姿は今も「黒田節」に残る。
-

森長可 (もりながよし)
織田家臣。可成の嫡男。伊勢長島一向一揆鎮圧や武田家征伐に参戦し「鬼武蔵」の異名をとった。本能寺の変後は豊臣秀吉に従い、小牧長久手合戦で戦死した。
-

森本具俊 (もりもとともとし)
北畠家臣。台城(森本城)の城主。俊信の子。木造家の一族という。士15人、兵50人を率いた。木造家に従って伊勢松ヶ島城攻撃戦に参陣し、戦死した。
-

森可成 (もりよしなり)
織田家臣。尾張統一戦や桶狭間合戦などで活躍した。宇佐山城主を務め、琵琶湖の南岸を固める。のちに浅井・朝倉連合軍の攻撃を受け、衆寡敵せず戦死した。
-

森可春 (もりよしはる)
森家臣。可政の四男。大坂夏の陣で初陣する。その後は幕府の折衝や饗応で活躍し、森忠政の子と徳川秀忠の養女の結婚の時の貝桶渡しでは受け取り役を務めた。
-

森好之 (もりよしゆき)
筒井家臣。島清興・松倉重信とともに、筒井家三老臣の1人に数えられる。家中で重要な地位を占めたが、主君・定次と対立して致仕、大和に戻って帰農した。
-

森蘭丸 (もりらんまる)
織田家臣。可成の三男。主君・信長の小姓を務める。利発で容姿美しく、信長に寵愛された。将来を嘱望されるが、本能寺の変で信長に従って奮戦し戦死した。
-

森脇祐有 (もりわきすけあり)
吉川家臣。主君・興経に近侍する大塩氏が圧政を敷いていたため、興経の叔父・経世とともに大塩氏を討ち、興経を隠居させて毛利元就の次男・元春を迎えた。
-

茂呂久重 (もろひさしげ)
佐野家臣。藤岡城主。主君・佐野昌綱の妹を娶る。のちに北条家に属した。豊臣秀吉の小田原征伐の際に居城を攻められ上野国世良田に逃亡、同地で自害した。
-

問註所統景 (もんぢゅうじょむねかげ)
筑後の豪族。長岩城主。耳川合戦後も大友家に属して戦い、主君・義統から恩賞を賜る。豊臣秀吉の九州征伐後は小早川家に属す。朝鮮派兵に従軍し戦死した。
-

谷柏直家 (やがしわなおいえ)
最上家臣。義光の小姓。慶長出羽合戦では、上杉軍に追われて逃げる民を救う。谷柏城を堅守し、味方の武将が討たれると、敵中を突破し、首を奪い返した。
-

八柏道為 (やがしわみちため)
小野寺家臣。八柏館主。家中随一の知将として名を馳せる。道為がいる限り、仙北の支配は困難と悟った最上義光は、当主・義道に謀略を仕掛けて殺害させた。
-

八木豊信 (やぎとよのぶ)
山名家臣。八木城主。八木家は山名四天王の一。羽柴秀吉の但馬侵攻軍に敗れて降伏した。以後は秀吉に属して因幡攻略に従事し、若桜鬼ヶ城を守ったという。
-

柳生家厳 (やぎゅういえよし)
大和の豪族。剣豪・宗厳の父。筒井順昭に攻められて、筒井家に属した。三好家の松永久秀が大和国に進出すると、三好方に寝返って筒井家と戦った。
-

柳生十兵衛 (やぎゅうじゅうべえ)
徳川家臣。宗矩の子。名は三厳。幼少時の事故で片目を失明。徳川家光の剣術指南役になるが、勘気を被り、出仕停止。以後諸国を放浪し修行に専念した。
-

柳生石舟斎 (やぎゅうせきしゅうさい)
大和の豪族。上泉信綱に師事して奥義を会得、柳生新陰流を開く。のちに徳川家康に招かれて柳生新陰流を伝授した。以後、柳生家は徳川家兵法師範となった
-

柳生兵庫助 (やぎゅうひょうごのすけ)
祖父・宗厳より一国一人の印可を受け、柳生新陰流の継承者となった。加藤清正に仕えたが、人を斬って浪人する。放浪後、尾張徳川家の剣法指南役になる。
-

柳生宗章 (やぎゅうむねあき)
宗厳の四男。中村家家老・横田村詮の客将。村詮が讒言により誅殺されると、遺臣とともに中村一忠に反抗。吹雪の中、18人を斬り倒す奮戦の末、討死した。
-

柳生宗矩 (やぎゅうむねのり)
徳川家臣。宗厳の子。兵法師範を務め、主君・秀忠に柳生新陰流を伝授した。秀忠の死後は、秀忠の子・家光に仕える。のちに大目付となり、1万石を領した。
-

薬丸兼将 (やくまるかねまさ)
肝付家臣。伊集院忠朗の催した宴席において、鶴の羮(肝付家の家紋は対い鶴)を勧められる。この一件を契機として主家と島津家が争うようになったという。
-

矢沢頼綱 (やざわよりつな)
真田家臣。真田幸隆の弟。甥・昌幸が上野沼田城を攻略後、沼田城代となる。第一次上田合戦の際は沼田城を守備するなど、持ち前の武勇で真田家を支えた。
-

矢沢頼康 (やざわよりやす)
真田家臣。頼綱の子。父に劣らぬ武勇の持ち主で、徳川家との神川合戦の際には右手に9尺柄の大長刀の石突を握って振り回し、片手討ちに敵を倒したという。
-

屋代景頼 (やしろかげより)
伊達家臣。14歳で政宗に近侍。知勇の才群を抜き、政宗不在時の留守居役を任された。しかし傲慢の振る舞いが多かったため改易され、流浪の末に病死した。
-

屋代勝永 (やしろかつなが)
武田家臣。満正の子。伯父・政国の養子となる。主家滅亡後は徳川家康の信濃平定に協力し、以後は徳川家に仕えた。大坂冬・夏の両陣では旗奉行を務めた。
-

屋代政国 (やしろまさくに)
信濃の豪族。屋代城主。はじめ村上義清に属すが、武田信玄の信濃侵攻軍に降り家臣となる。武田家の滅亡後は、海津城主となった織田家臣・森長可に従った。
-

安井道頓 (やすいどうとん)
大坂の町人。名は成安。大坂城外堀の掘削の功を豊臣秀吉に認められ、道頓堀開拓を任される。しかし、大坂の陣に豊臣方で参戦し、志半ばで戦死した。
-

弥助 (やすけ)
モザンビーク出身。宣教師ヴァリニャーノに従って来日。信長に気に入られ、家臣となる。本能寺の変では、信忠と共に奮戦。「十人力の剛力」と評された。
-

安田顕元 (やすだあきもと)
上杉家臣。安田城主。景元の子。武田家への備えとして飯山城主を務めた。御館の乱では上杉景勝を支持して活躍したがのちに恩賞問題のこじれから自害した。
-

安田景元 (やすだかげもと)
上杉家臣。安田城主。上条定憲の乱の際は長尾為景に従い活躍した。北条高広が主家に背いた際は、これを直江景綱に報じ、主君・謙信に従って高広と戦った。
-

安田作兵衛 (やすださくべえ)
明智家臣。名は国継。明智三羽烏の一。本能寺の変で森蘭丸を討ち、織田信長に一番槍をつける活躍をした。のち変名して蒲生氏郷、寺沢広高らに仕えた。
-

安田長秀 (やすだながひで)
上杉家臣。主君・謙信の側近を務めた。川中島合戦で活躍し「血染めの感状」を受けた。御館の乱では上杉景勝を支持した。新発田重家との交戦中に病死した。
-

安田能元 (やすだよしもと)
上杉家臣。安田城主。恩賞問題のこじれにより自害した兄・顕元の跡を継ぐ。主家の会津移封に従い、二本松城代となった。会津三奉行の1人に数えられた。
-

安富純治 (やすとみすみはる)
有馬家臣。肥前深江城主。主君・晴信に従い龍造寺隆信と戦うが、のち隆信に属す。これを契機に有馬・龍造寺家間に講和が結ばれた。沖田畷合戦で戦死した。
-

安富純泰 (やすとみすみやす)
有馬家臣。深江城主。のち龍造寺隆信に属す。有馬軍に居城を攻められるが、龍造寺軍の援護で撃退した。沖田畷合戦で隆信が戦死したあとは深江姓に改めた。
-

安富盛方 (やすとみもりかた)
讃岐の豪族。雨滝城主。安富家は香川・香西・奈良家とともに「細川四天王」と呼ばれた家柄。細川家の勢力が衰えると大内家に属し、近隣の寒川家と争った。
-

安見勝之 (やすみかつゆき)
畠山家臣。信国の子。鉄砲の名手であったという。主家滅亡後は豊臣秀吉に仕え伊予国で1万石を領した。関ヶ原合戦では西軍に属して没落、前田家に仕えた。
-

安見直政 (やすみなおまさ)
畠山家臣。河内交野城主。河内守護代を務めた。主君・高政を紀伊に追放し、高政の弟・昭高を擁立する。のち織田信長の畿内平定軍に降り、本願寺と戦った。
-

安見信国 (やすみのぶくに)
畠山家臣。右近丞と称す。1569年、岩清水八幡宮の料所である河内国星田荘の年貢を抑留したため、幕府に訴えられた。のちに松永久秀に殺されたという。
-

矢田野義正 (やだのよしまさ)
二階堂家臣。郡山合戦で伊達家と戦い活躍。伊達政宗が二階堂家を滅ぼした時にも居城に籠もって徹底抗戦し撃退。豊臣秀吉もその武勇を賞賛したという。
-

柳川調信 (やながわしげのぶ)
宗家臣。主に外交面で活躍し、足利義昭や羽柴秀吉・徳川家康との交渉で宗家の安泰を維持した。対馬藩が成立すると、家老となった。
-

柳沢元政 (やなぎさわもとまさ)
足利家臣。義晴・義輝・義昭の三代に仕える。織田信長によって義昭が京を追放されると共に備後へ移る。義昭の庇護を受ける代わりに、毛利家に出仕した。
-

簗田詮泰 (やなだあきやす)
斯波家臣。大学と称す。主家の前途に不安を抱き、石清水義教らとともに南部家に内通し、斯波家滅亡のきっかけを作った。のち南部家から千石を与えられた。
-

簗田高助 (やなだたかすけ)
古河足利家臣。関宿城主。主君・晴氏と北条氏綱の娘の結婚に奔走し、両家の盟約を成立させた。河越合戦の際には晴氏に従って出陣し、戦後、隠居した。
-

簗田晴助 (やなだはるすけ)
古河足利家臣。関宿城主。高助の子。北条氏康打倒を企んだ主君・晴氏が逆に幽閉されると、晴氏の子・藤氏を擁立。上杉家や武田家と結んで北条家と争った。
-

簗田政綱 (やなだまさつな)
織田家臣。桶狭間合戦では斥候として奇襲成功の立役者となり、戦後尾張沓掛3千貫を与えられた。のちに大聖寺城主となるが、一揆の再起により改易された。
-

矢作重常 (やはぎしげつね)
葛西家臣。外館城主。浜田兵乱鎮定に功を立て、浜田家に代わって気仙郡の旗頭となった。この際、金の采配を許されたという。のちに伊達政宗に謀殺された。
-

山内一豊 (やまうちかずとよ)
織田家臣。妻・千代の内助の功が著名。本能寺の変後は豊臣秀吉に属す。関ヶ原合戦の際は居城・掛川城を徳川家康に献上し、戦後、土佐高知24万石を得た。
-

山内忠義 (やまうちただよし)
豊臣家臣。康豊の子。伯父・一豊に子がなかったため、養子となって土佐24万石を継いだ。大坂夏の陣の際は、暴風雨に遭遇したために参戦できなかった。
-

山内千代 (やまうちちよ)
山内一豊の正室。見性院。内助の功を尽くして一豊を盛り立てた。中でも、関ヶ原合戦の直前、「笠の緒の密書」で石田三成挙兵を知らせた実績は、特に有名。
-

山内康豊 (やまうちやすとよ)
山内家臣。初代土佐藩主で実兄の一豊から、土佐中村2万石を与えられる。一豊の養子となっていた長男・忠義が2代目藩主となると、その後見人となった。
-

山岡重長 (やまおかしげなが)
伊達家臣。大崎合戦の軍目付、岩崎城代を務め、葛西大崎一揆鎮圧で武功を上げた。関ヶ原合戦で白石城攻略に活躍。戦後、徳川家康への戦勝の使者を務めた。
-

山県昌景 (やまがたまさかげ)
武田家臣。武田四名神の1人。兄・飯富虎昌と同様、軍装を赤で統一。内政・軍事・外交全般で主君・信玄を補佐した。長篠合戦で全身に銃弾を浴び戦死した。
-

山上道及 (やまがみどうきゅう)
佐野家臣。名は照久、氏秀とも。佐野四天王の1人。首供養を3度行ったという家中随一の猛将。のち武者修業のため致仕した。関ヶ原合戦では上杉家に属す。
-

山口重政 (やまぐちしげまさ)
徳川家臣。はじめ織田家臣・佐久間信栄に仕える。信栄失脚後は織田信雄に仕え信雄改易後、家康の招きを受けた。しかし、のちに家康の勘気を受け蟄居した。
-

山口弘定 (やまぐちひろさだ)
豊臣家臣。宗永の次男。大坂の陣で豊臣家に味方し籠城。妻の兄・木村重成に属して戦い、夏の陣・若江の戦いで重成とともに井伊直孝隊に討たれた。
-

山口宗永 (やまぐちむねなが)
豊臣家臣。地方支配にすぐれたという。一時小早川秀秋の補佐役を務めるが、不和になり出奔した。関ヶ原合戦では西軍に属し、前田利長との戦いで戦死した。
-

山崎家治 (やまざきいえはる)
徳川家臣。家盛の長男。大坂夏の陣では池田利隆に属し奮戦。戦後、築城の腕を活かし大坂城の修築に活躍した。島原の乱後、天草を領し、その復興に尽力した。
-

山崎家盛 (やまざきいえもり)
豊臣家臣。片家の嫡男。伏見城の普請工事などを担当した。関ヶ原合戦では西軍に属すが、縁戚・池田輝政の尽力により改易を免れ、因幡若桜3万石を領した。
-

山崎片家 (やまざきかたいえ)
六角家臣。山崎城主。主君・義治と不和になり、織田信長に仕える。本能寺の変後は一時明智光秀に属すが、のち豊臣秀吉に仕え摂津三田2万3千石を領した。
-

山崎長徳 (やまざきながのり)
朝倉家臣。主家滅亡後は明智光秀に属し本能寺の変に従軍。光秀の死後は柴田勝家に属し、賤ヶ岳合戦に従軍した。勝家の死後は前田家を経て徳川家に仕えた。
-

山崎吉家 (やまざきよしいえ)
朝倉家臣。軍略に優れる。朝倉宗滴に従い、加賀一向一揆などで活躍する。姉川の戦いの後、森可成を討ち取るが、のちに織田軍の猛攻を受けて戦死した。
-

山路正国 (やまじまさくに)
柴田家臣。正幽の次男。賤ヶ岳合戦では主君・勝豊とともに羽柴秀吉に属すが、のちに寝返る。佐久間盛政に中入れ作戦を進言し、自らも従軍するが戦死した。
-

山田有栄 (やまだありなが)
島津家臣。有信の嫡男。伊集院忠真の謀叛鎮圧や関ヶ原合戦などで抜群の戦功を立てた。出水地頭を務め、家臣教育や産業開発などにも尽力した知勇兼備の将。
-

山田有信 (やまだありのぶ)
島津家臣。各地の合戦で活躍した。伊東家の滅亡後、日向高城主となる。耳川合戦の際は少数の兵で大友家の大軍から居城を守り抜き、主家の勝利に貢献した。
-

山田重直 (やまだしげなお)
伯耆の豪族。毛利家に仕え、父・高直の代に尼子家に奪われた居城・堤城を奪還した。のちに南条元続に属す。元続が羽柴家に属した際、元続と戦うが敗れた。
-

山田長政 (やまだながまさ)
シャム(現在のタイ)の日本人町頭領。アユタヤ国王・ソンタムの信任を得て活躍する。国王の死後、政争に巻き込まれ戦闘で受けた傷に毒を塗られ死亡した。
-

山田宗昌 (やまだむねまさ)
伊東家臣。主家滅亡後は大友家臣・佐伯惟定を頼る。島津家の豊後侵攻軍に対して惟定の居城・豊後栂牟礼城に籠城、抗戦の準備および合戦の総指揮を執った。
-

山中鹿之介 (やまなかしかのすけ)
尼子家臣。三日月に対し「我に七難八苦を…」と願ったという。尼子勝久を擁して主家再興を企むが、播磨上月城で毛利軍に敗れ、安芸への護送中に殺された。
-

山名祐豊 (やまなすけとよ)
但馬守護。出石城主。叔父・誠豊の養子となって家督を継ぐ。弟・豊定を因幡に派遣し、但馬・因幡両国を支配した。のち羽柴秀吉に攻められ敗北、降伏した。
-

山名豊国 (やまなとよくに)
因幡守護。鳥取城主。豊定の三男。武田高信を討ち居城を奪回する。羽柴秀吉に属すが、毛利家に通じた家臣たちに追放された。のち、秀吉の御咄衆を務めた。
-

山名豊定 (やまなとよさだ)
因幡守護。鳥取城主。叔父・誠豊の死後兄・祐豊の命により因幡に入る。因幡守護を自称して主家に対抗する山名誠通を討つなど、因幡の領国経営に尽力した。
-

山名豊頼 (やまなとよより)
因幡守護。誠通の父。兄・豊重の跡を継ぐ。左馬助と称す。1513年、因幡国高草郡布施郷の一部を家臣の北河与三衛門尉に所領として与えた。
-

山名誠通 (やまなのぶみち)
因幡守護。豊頼の子。左馬助と称す。但馬山名家を継いだ祐豊と対立し、尼子家と結び自立を図るが、祐豊との戦いに敗れて戦死し、因幡山名家は断絶した。
-

山内隆通 (やまのうちたかみち)
備後の豪族。多賀山通続の子。宗家の山内直通が尼子家から大内・毛利家に寝返ろうとし、尼子家に廃されたため、宗家の家督を継いだ。のち毛利家に属した。
-

山内直通 (やまのうちなおみち)
備後の豪族。大内家に属し、和智豊郷を大内家に仲介するなど活躍。のちに塩冶興久を匿ったため、興久の父・尼子経久に攻められて敗北し、隠居させられた。
-

山手殿 (やまのてどの)
真田昌幸の正室。信之・幸村の母。出自については様々な説がある。関ヶ原合戦後、昌幸が紀伊に蟄居となった際は落飾して寒松院と称し、信之の元に残った。
-

山村良勝 (やまむらよしかつ)
木曾家臣。良候の子。関ヶ原合戦では東軍に属し、千村良重とともに木曾を平定する。また犬山城を攻略した。のちに尾張徳川家に仕え、大坂の陣に参加した。
-

山村良候 (やまむらよしとき)
木曾家臣。良利の子。主家の転封後も木曾に残る。関ヶ原合戦では東軍に属し、西軍に捕まるが、のち解放。戦後、徳川家康から木曾福島の関所を預かった。
-

山本勘助 (やまもとかんすけ)
武田家臣。文武百般に通じ、主君・信玄の軍師を務めた。第四次川中島の合戦で「きつつきの戦法」を上杉謙信に見破られた責を負い、乱軍に突入し戦死した。
-

山吉景長 (やまよしかげなが)
上杉家臣。木場城主。父、兄の死後、家督継承。御館の乱で景勝に与し、新発田重家討伐でも活躍した。豊臣秀吉への降服後も、小田原征伐などに参陣する。
-

山吉豊守 (やまよしとよもり)
上杉謙信の旗本で、秘書官のような役割を果たす。謙信の越中出陣の際は、景勝を助けて春日山城の守備に当たったという。家中最大の軍役を負担していた。
-

山吉政久 (やまよしまさひさ)
越後の豪族。山吉氏は蒲原郡山吉村の出身で、のち三条長尾家に仕えるという。三条城主を務めた。主君・為景が上田長尾家と対立した際は、為景に属した。
-

湯浅隆貞 (ゆあさたかさだ)
大谷家臣。関ヶ原合戦で吉継の自害を介錯する。吉継の首級を埋めたが敵の藤堂高刑に見つかり、主の首の場所の秘匿を高刑に願って、自らの首を差し出した。
-

結城忠正 (ゆうきただまさ)
松永家臣。当初は主君・久秀の命によりキリスト教を弾圧するが、日本人宣教師のロレンソに感化され、間もなく受洗。畿内の有力なキリスト教保護者となる。
-

結城朝勝 (ゆうきともかつ)
宇都宮広綱の次男。結城晴朝の養子となるが、のちに徳川家康の次男・秀康が結城家に入嗣したため、宇都宮家に戻る。以後は反徳川、反結城の姿勢を貫いた。
-

結城晴朝 (ゆうきはるとも)
結城家17代当主。小山高朝の次男。伯父・政勝の養子となる。北条・上杉両家の間で離合集散を繰り返した。のちに徳川家康の次男・秀康を養子とした。
-

結城政勝 (ゆうきまさかつ)
結城家16代当主。政朝の子。「結城氏新法度」を定めて支配力を強化する。北関東に勢力を伸ばす北条氏康と結び、佐竹、宇都宮、小田家らと抗争を続けた。
-

結城政朝 (ゆうきまさとも)
結城家15代当主。多賀谷祥永を誅殺し佐竹、岩城、宇都宮家を破り、次男・高朝を小山家に送り込んで小山家を傘下に置くなど、結城家の勢力を回復させた。
-

湯川直春 (ゆかわなおはる)
紀伊の豪族。直光の子。父の死後、家督を継ぐ。豊臣秀長率いる紀州征伐軍に対して抵抗するが、降伏し、本領を安堵された。のちに秀長によって毒殺された。
-

湯川直光 (ゆかわなおみつ)
紀伊の豪族。湯河家は甲斐武田家の庶流で、紀伊国人衆の旗頭として活躍した家柄。河内畠山家に属して三好家と戦うが敗れ、一族の者多数とともに戦死した。
-

行松正盛 (ゆきまつまさもり)
伯耆の豪族。尾高城主。1524年、尼子経久に攻められて居城を奪われたため毛利家に属す。のち毛利家の出雲侵攻軍に従い、38年ぶりに居城を奪還した。
-

遊佐続光 (ゆさつぐみつ)
畠山家臣。温井家との政争に敗れて出奔するが、和睦して帰参する。のちに上杉家に通じて能登を治めるが、織田家の台頭により逐電し、捕縛され斬首された。
-

遊佐長教 (ゆさながのり)
畠山家臣。河内守護代を務めた。軍略に優れ、主家の実権を握る。三好長慶と争うが、娘を長慶に嫁がせて和睦した。のちに反長慶派の刺客により暗殺された。
-

遊佐信教 (ゆさのぶのり)
畠山家臣。長教の子。河内守護代を務めた。主君・高政を紀伊に追放し、高政の弟・昭高を擁立。その昭高をも暗殺するが、のちに織田信長によって討たれた。
-

遊佐秀頼 (ゆさひでより)
畠山家臣。能登守護代を務めた。将軍・足利義晴との外交などで活躍した。のちに温井総貞と対立し、羽咋郡一宮で温井軍と戦うが敗北、生け捕りにされた。
-

遊佐盛光 (ゆさもりみつ)
畠山家臣。続光の子。年寄衆として政権に参画。上杉家に通じて長家を追い落とす。織田家の勢力が及ぶと長家の攻撃を受け逐電するが、捕縛され斬首された。
-

湯地定時 (ゆぢさだとき)
伊東家臣。主家の日向退去後も、日向三納城に籠城して島津家と戦う。しかし耳川合戦で大友軍大敗。勢いに乗る島津勢に居城を囲まれ、自害して果てた。
-

湯目景康 (ゆのめかげやす)
伊達家臣。人取橋合戦、摺上原合戦、葛西大崎一揆鎮圧に参加。伊達政宗が秀次事件に連座させられそうになったときには豊臣秀吉に直訴して弁明に努めた。
-

由布惟信 (ゆふこれのぶ)
立花家臣。道雪にちなみ「雪下」と号した。参加した合戦は六十五以上という猛将。関ヶ原合戦で主家が改易された後も宗茂を助け、立花家の再興に尽力した。
-

横瀬顕長 (よこぜあきなが)
足利長尾家当主。由良成繁の次男。長尾景長の娘を娶り、家督を継いだ。豊臣秀吉の小田原征伐に際しては北条家に従った。北条家滅亡後は流浪の身となった。
-

横瀬国繁 (よこぜくにしげ)
横瀬由良家9代当主。成繁の嫡男。豊臣秀吉の小田原征伐の際は小田原城に籠城した。子・貞繁が豊臣方に属したため、小田原落城後、常陸牛久に所領を得た。
-

横瀬繁詮 (よこぜしげあき)
由良成繁の四男。豊臣秀吉に仕え、紀州征伐などに従軍。小田原征伐にも参陣し戦後、遠江横須賀3万石を領した。のちに豊臣秀次事件に連座して自害した。
-

横瀬成繁 (よこぜなりしげ)
横瀬由良家8代当主。泰繁の嫡男。由良姓に改める。上杉家に属し、北条・武田家の侵略に対抗した。のち北条家に属し北条家と上杉家との同盟を仲介した。
-

横瀬泰繁 (よこぜやすしげ)
横瀬由良家7代当主。父・景繁が戦死した武蔵須賀合戦で負傷。上野の豪族・岩松昌純を暗殺、のちに昌純の子・氏純と和睦した。下野壬生合戦で戦死した。
-

横田高松 (よこたたかとし)
武田家臣。甲陽五名臣の1人。近江の出身。敵の先手を打つ戦法を得意とした。「戸石崩れ」と呼ばれる村上義清との戦いで殿軍を務め、奮戦するが戦死した。
-

横山喜内 (よこやまきない)
蒲生家臣。九州征伐で功を立て、蒲生の姓と「郷」の字を賜り蒲生郷舎と称す。その後は石田家、藤堂家などを渡り歩きながら何度か蒲生家にも戻っている。
-

横山友隆 (よこやまともたか)
土佐の豪族。介良城主。はじめ長宗我部国親と戦うが、のちに家臣となる。安芸家との戦いで活躍したほか、主家の崇敬が篤い若宮八幡宮を造営するなどした。
-

横山長隆 (よこやまながたか)
前田家臣。美濃で稲葉良通に仕えたが、刃傷沙汰を起こして越前に逃れ、金森長近、のちに前田利家に仕えた。賤ヶ岳合戦に参戦して殿軍を務め、戦死した。
-

横山長知 (よこやまながちか)
前田家臣。長隆の子。通称は大膳。利家の死後、前田利長が家康によって謀反の嫌疑をかけられると、大坂城に派遣されて家康に釈明、前田家の危機を救った。
-

吉江宗信 (よしえむねのぶ)
越後の豪族。蒲原郡吉江村を領した。主君・謙信死後は景勝に属し、越中方面に転戦した。のち魚津城に籠城して織田家臣・柴田勝家と戦うが敗れ、戦死した。
-

吉岡定勝 (よしおかさだかつ)
山名家臣。防己尾城主。羽柴秀吉の因幡侵攻軍に対抗し、千成瓢箪の馬標を奪うなど勇名を馳せる。しかし鳥取城落城により逃亡し、娘夫婦を頼って帰農した。
-

吉岡長増 (よしおかながます)
大友家臣。豊後三老の1人。知略に優れた。大友家と毛利家が筑前で対峙した際は、大内義隆の従兄弟・輝弘を扇動して周防に侵攻させ、毛利軍を撤退させた。
-

吉岡妙林 (よしおかみょうりん)
大友家臣・吉岡鑑興の妻。夫が耳川合戦で戦死後に出家して妙林と号す。島津軍の侵攻に対し鶴埼城を守って撃退。一旦講和し油断させて追撃し打撃を与えた。
-

吉田重俊 (よしだしげとし)
長宗我部家臣。孝頼の弟。安芸国虎との戦いの際は、調略を用いて安芸家中を内部崩壊に導いた。知略に優れた武将で、兄とともに主家の版図拡大に貢献した。
-

吉田重政 (よしだしげまさ)
六角家臣。吉田流弓術の祖・重賢の子。主君・義賢から弓術の伝授を求められるが拒否して出奔、一時朝倉家に仕える。数年後に帰参し、義賢に弓術を授けた。
-

吉田孝頼 (よしだたかより)
長宗我部家臣。主君・国親の妹を娶る。知勇兼備の将と評され、権謀術数を駆使する一方で、各地で戦功を立て、国親の片腕として主家の勢力拡大に貢献した。
-

吉田政重 (よしだまさしげ)
長宗我部家臣。115の首級を挙げ、朝鮮では猛虎を退治したという猛将。大坂の陣の際は旧主・盛親に従い奮戦した。大坂落城後は土佐に戻り医者になった。
-

吉田康俊 (よしだやすとし)
長宗我部家臣。中富川合戦や戸次川合戦で功を立てる。主家の改易後は山内家臣になるが、間もなく大和に隠棲。のち大坂城に入り旧主・盛親に従って戦った。
-

義姫 (よしひめ)
最上義光の妹。伊達輝宗に嫁ぐ。「奥羽の鬼姫」と呼ばれたほどの激情家であった。政宗、小次郎を産むが、隻眼の政宗を忌み嫌い、毒殺を試みたこともある。
-

吉弘鑑理 (よしひろあきただ)
大友家臣。豊後三老の1人。主君・義鎮の執政を補佐した。勢場ヶ原合戦で大内軍を撃退し、また多々良浜合戦で毛利軍を破るなど、多くの合戦で功を立てた。
-

吉弘鎮信 (よしひろしげのぶ)
大友家臣。鑑理の子。幼い頃から主君・宗麟に近侍する。立花城西城督を務めて博多の経営に従事し、豪商・島井宗室らと親交を持った。耳川合戦で戦死した。
-

吉弘政宣 (よしひろまさのぶ)
立花家臣。吉弘氏嫡流。統幸の子。先祖が千人斬りをし妖蜘蛛から父を守った生き剣「蜘蛛切」を主家に献上したが、怪異が次々と起きたので返却された。
-

吉弘統幸 (よしひろむねゆき)
大友家臣。鎮信の子。関ヶ原合戦の際に主君・義統の西軍加担案に反対し、東軍加担を主張するが却下された。義統に従って黒田孝高の軍と戦い、戦死した。
-

吉松光久 (よしまつみつひさ)
本山家臣。万々城主。吉松家は秦泉寺家の一族という。長宗我部元親の攻撃を受けて降伏し、元親の娘を妻とした。以後は一門衆として各地の合戦で活躍した。
-

吉見広長 (よしみひろなが)
毛利家臣。処遇に不満を抱き、たびたび出奔、内通する。そのたび許され帰参を果たしたが、父・広頼の死後、謀叛のかどで輝元に追討され、ついに自害した。
-

吉見広頼 (よしみひろより)
毛利家臣。正頼の子。出雲白鹿城攻撃などで功を立てた。正室・継室に相次いで先立たれ、嫡男が朝鮮派兵の際に戦死するなど、家庭的に不遇な武将であった。
-

吉見正頼 (よしみまさより)
大内家臣。主君・義隆の姉を娶る。義隆の敵・陶晴賢打倒を目指して挙兵し、毛利元就と結んで晴賢と戦う。晴賢が厳島合戦で敗死したあとは毛利家に属した。
-

淀殿 (よどどの)
浅井長政の長女。淀殿。豊臣秀吉に引き取られて側室となり、秀頼を産む。秀吉の死後に大阪城内で絶大な権力を誇る。大阪落城時に秀頼とともに自害した。
-

楽巌寺雅方 (らくがんじまさかた)
村上家臣。楽巌寺城主。もとは楽巌寺の僧であったという。1548年頃、武田信玄に居城を奪われ、砥石城に逃れる。主家の滅亡後は武田信玄に臣従した。
-

龍造寺家兼 (りゅうぞうじいえかね)
少弐家臣。田手畷合戦で大内軍を破るなど活躍するが、馬場頼周の策謀で多くの一族を殺され、筑後に逐電。のち肥前に復帰して頼周を討ち、再興を果たした。
-

龍造寺家純 (りゅうぞうじいえずみ)
少弐家臣。家兼の子。父が馬場頼周の策謀によって筑後に退去した際、弟・家門や三男・純家とともに筑前に赴くが、途中で神代勝利軍に攻められ、敗死した。
-

龍造寺家就 (りゅうぞうじいえなり)
龍造寺家臣。胤久の次男。龍造寺隆信が村中・水ヶ江両家を統一したあとは隆信に従う。少弐家討伐戦で活躍した。のち肥後に赴き、北上する島津軍と戦った。
-

龍造寺家晴 (りゅうぞうじいえはる)
龍造寺家臣。鑑兼の子。柳河城攻めなどで活躍した。のちに柳河城主となり、大友軍と戦った。豊臣秀吉の九州征伐後は諫早城主となり、諫早家の祖となった。
-

龍造寺隆信 (りゅうぞうじたかのぶ)
龍造寺家19代当主。周家の子。村中・水ヶ江両家を統一して勢力を拡大し、九州5カ国2島を領した「肥前の熊」。沖田畷合戦で島津軍に大敗し、戦死した。
-

龍造寺周家 (りゅうぞうじちかいえ)
少弐家臣。家純の子。祖父・家兼が馬場頼周に騙されて筑後に退去した際、弟・頼純らと謝罪使として少弐冬尚を訪ねるが、途中で馬場軍に攻められ敗死した。
-

龍造寺長信 (りゅうぞうじながのぶ)
龍造寺家臣。周家の三男。多久家の祖となる。肥前梶峯城主を務め、西肥前の有馬家や松浦家に備える。兄・隆信の肥前における勢力の確立に大きく貢献した。
-

龍造寺信周 (りゅうぞうじのぶちか)
龍造寺家臣。周家の次男。須古鍋島家の祖となる。大友家の衰退後は豊前方面に進出し、豊前の諸将を服属させて政務を司り、兄・隆信の勢力拡大に貢献した。
-

龍造寺政家 (りゅうぞうじまさいえ)
龍造寺家20代当主。隆信の嫡男。豊臣秀吉の九州征伐軍の先鋒を務め、所領を安堵される。病のため、秀吉の許可を得て領国経営を家臣・鍋島直茂に委ねた。
-

留守顕宗 (るすあきむね)
留守家17代当主。景宗の嫡男。国分家らと戦いを繰り返した。のちに伊達晴宗の三男・政景を娘婿として隠居。この際嫡男・宗綱は高城家の養子となった。
-

留守景宗 (るすかげむね)
留守家16代当主。伊達尚宗の子。15代当主・郡宗の娘を娶り、家督を継ぐ。戦国大名の組織などを知る上で貴重な史料とされる「留守分限帳」を作成した。
-

留守政景 (るすまさかげ)
留守家18代当主。伊達晴宗の三男。留守顕宗の娘を娶り家督を継ぐ。兄・輝宗や甥・政宗に従い、相馬家や最上家などと戦った。のちに伊達姓に復した。
-

嶺松院 (れいしょういん)
今川義元の娘。甲相駿三国同盟の一環として、武田信玄の嫡男・義信の正室となる。しかし、義信は信玄と対立し自害に追い込まれ、嶺松院は駿河へ帰された。
-

冷泉隆豊 (れいぜいたかとよ)
大内家臣。安芸銀山城主を務めた。陶晴賢が謀叛すると主君・義隆に従って長門に逃亡し、義隆の介錯を行った。義隆の死後は陶軍と戦い、凄絶な死を遂げた。
-

六郷政乗 (ろくごうまさのり)
出羽の豪族。豊臣秀吉の小田原征伐に参陣し、所領安堵。朝鮮出兵の際は肥前名護屋城を守る。のち関ヶ原合戦、大坂の陣に参加し、出羽本庄2万石を領した。
-

六角定頼 (ろっかくさだより)
近江の戦国大名。近江に逃れた将軍・足利義晴を支援した。楽市楽座の創始や、一国一城令の先駆をなす「城割り」を初めて行った人物として著名。
-

六角義賢 (ろっかくよしかた)
近江の戦国大名。定頼の子。江南に勢力を伸ばす。三好家に京を追われた足利将軍家を保護し、仲裁に奔走した。のち織田信長の上洛軍に敗れ、所領を失った。
-

六角義治 (ろっかくよしはる)
近江の戦国大名。義賢の子。筆頭家老・後藤賢豊を謀殺し、家臣の信頼を失う。織田信長の上洛軍に敗れ、諸国を流浪した。晩年は豊臣秀頼の弓師範を務めた。
-

和賀忠親 (わがただちか)
陸奥の豪族。義忠の子。関ヶ原合戦では伊達政宗の後援で南部家を攻める(和賀兵乱)が敗北。真相の発覚を恐れた政宗の命により従者7名とともに自害した。
-

和賀義勝 (わがよしかつ)
陸奥の豪族。和賀家は源頼朝の庶子・忠頼を祖とするという。外からは南部家の圧迫を受け、国内では一族をはじめとした諸氏の統制に苦しんだという。
-

和賀義忠 (わがよしただ)
陸奥の豪族。義勝の子。豊臣秀吉の小田原征伐に参陣せず改易される。一揆を起こして居城・二子城を奪回するが、豊臣軍に敗れ、逃走中に領民に殺された。
-

脇坂安治 (わきざかやすはる)
豊臣家臣。賤ヶ岳七本槍の1人。主君・秀吉の中国征伐の際に「丹波の赤鬼」赤井直正を討ち取る功を立てた。関ヶ原合戦では東軍に寝返り所領を安堵された。
-

脇坂安元 (わきさかやすもと)
徳川家臣。安治の子。父の死後、伊予大洲5万3千石を継ぐ。のち信濃飯田5万5千石に転封された。子孫の代に播磨竜野5万3千石となり明治維新を迎えた。
-

和久宗是 (わくそうぜ)
豊臣家臣。小田原攻めでは伊達政宗を説き参陣させる。秀吉亡き後、伊達家に仕えるが、大坂の陣が始まると豊臣家に帰参。白装束で敵陣に突入し戦死した。
-

分部光高 (わけべみつたか)
長野家臣。分部家は長野祐成(長野工藤家5代当主・豊藤の五男)を祖とする。細野藤光の次男・光嘉を養子とした。のちに北畠家との葉野合戦で戦死した。
-

分部光信 (わけべみつのぶ)
徳川家臣。光嘉の孫。祖父の養子となって後を継ぐ。大坂の陣で活躍。近江大溝藩に移封され、織田信長が焼き打ちした比叡山復興のための造営奉行を務めた。
-

分部光嘉 (わけべみつよし)
長野家臣。細野藤光の次男。織田信長の伊勢侵攻軍に対して恭順を主張し、長野家を継いだ織田信包に属した。のちに豊臣秀吉に仕え、伊勢上野城主となった。
-

和田昭為 (わだあきため)
佐竹家臣。一時白河結城家に属すが、義昭・義重・義宣の3代に仕え、内政や外交など各方面で活躍。豊臣秀吉の朝鮮出兵の際は国元に残り、国政を代行した。
-

和田惟政 (わだこれまさ)
足利家臣。主君・義輝の横死後は義輝の弟・義昭に仕え、将軍職就任を陰から支えた。キリスト教を保護し、宣教師・ルイス=フロイスを織田信長に紹介した。
-

渡辺勘兵衛 (わたなべかんべえ)
阿閉家臣。主家滅亡後は豊臣・中村・増田・藤堂家に歴仕した。豊臣秀吉の小田原征伐の際、山中城に一番乗りし秀吉から賞賛された。大坂の陣後、浪人した。
-

渡辺糺 (わたなべただす)
豊臣家臣。槍の名手として作られる。母の正栄尼は秀頼の乳母を務めた。大坂の陣の主戦派で、大坂夏の陣では真田幸村とともに奮戦。城中で自害した。
-

渡辺通 (わたなべとおる)
毛利家臣。相合元綱の擁立を企んで殺された勝の子。大内義隆が出雲遠征で大敗した際、殿軍を受け持つ主君・元就を救い、郎党とともに壮絶な戦死を遂げた。
-

渡辺教忠 (わたなべのりただ)
西園寺家臣。河後森城主。土佐一条家の出身。主家と実家が争った際に傍観し、主家の攻撃を受けるが、人質を出して降伏した。のちに家臣に居城を追われた。
-

渡辺守綱 (わたなべもりつな)
徳川家臣。各地を転戦して戦功を立て、「槍の半蔵」の異名をとる。関ヶ原合戦には旗本として参陣。晩年は尾張徳川家の家老となり、当主・義直を補佐した。
-

和田業繁 (わだなりしげ)
上野の豪族。はじめ山内上杉家に仕えるが、1560年より武田家に仕え、西上野衆の一員として騎馬30騎を率いた。1575年の長篠合戦で戦死した。
-

和田信業 (わだのぶなり)
上野の豪族。業繁の養子。武田家に属すも、主家滅亡後は滝川一益に従った。神流川合戦後は、北条家に仕えた。小田原征伐後は、紀伊に逃れたという。
-

和田通興 (わだみちおき)
河野家臣。岩伽羅城主。次第に勢力を拡大して主家に従わなくなったため、平岡房実率いる追討軍に攻められる。居城を落とされて山之内に敗走し、自害した。
-

亘理重宗 (わたりしげむね)
伊達家臣。元宗の子。父とともに、相馬家との戦いで中心となって活躍した。政宗が秀吉の命で転封されたのちは、百々城、次いで涌谷城に入った。
-

亘理宗隆 (わたりむねたか)
伊達家臣。小堤城主。伊達稙宗の子・元宗の義父。天文の乱で稙宗方に属すが、後に晴宗に仕えた。相馬家との前線を隠居領とし、生涯を伊達家守護に捧げた。
-

亘理元宗 (わたりもとむね)
伊達家臣。伊達稙宗の十二男。亘理家の養嗣子となる。伊達家における対相馬家の総大将。人取橋合戦では、圧倒的な大軍であった連合軍を相手に奮戦した。
-

和知直頼 (わちなおより)
白河結城家臣。主君・義綱の近津大明神への寄進状の添状を発給した。後裔の和知美濃守は、主君・義顕を白河城から追い、小峰義親の入城を手引きした。
-

和智誠春 (わちまさはる)
毛利家臣。出雲遠征に赴く毛利隆元を饗応するが、直後に隆元が急死したため、毒殺の疑いを持たれる。のちに伊予征討から帰る途中で主君・元就に討たれた。