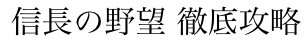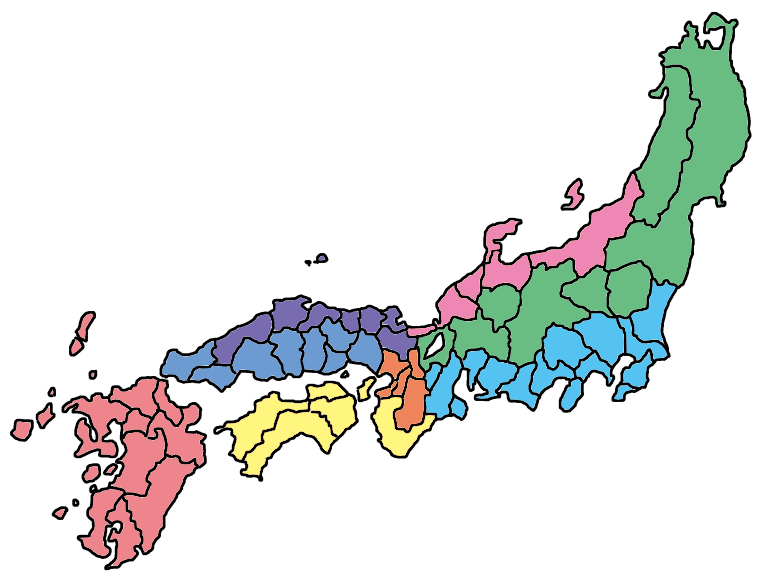戦国時代用語集

戦国時代用語集
戦国時代に出てくる用語集です。
※随時更新中
| 用語 | 読み | 説明 |
|---|---|---|
| 赤備 | あかぞなえ | 軍勢編制のひとつで、具足や甲冑、旗指物などの武具を朱塗りで統一した部隊。 色を統一することで軍の団結力を高め、敵味方の区別を明確にした。 |
| 足軽 | あしがる | 雑兵の呼び名のひとつ。戦国時代前半では、身分の低い兵士を指した。 奇襲作戦に利用されたが、忠誠心に乏しく、しばしば暴徒と化した。 戦国時代後半には弓、鉄砲、長槍を訓練された常備兵として活躍した。 |
| 足軽大将 | あしがるたいしょう | 足軽隊を率いた部隊の大将。集団戦が中心となった戦国時代では、槍。鉄砲、弓の役割が重要になったために、総大将、侍大将に次ぐ地位を有した。 |
| 安宅船 | あたけぶね | 海賊船が使用した、巨体で重厚な船。戦艦としての機能が重視され、2層、もしくは3層の櫓が搭載された。収容人数は数十人から数百人ほど。 |
| 安堵 | あんど | 武士が、領地の所有を認められること。公家側が領主に対し、権利を保障することも指す。 安堵の証明として発行される文書は安堵状と呼ばれた。 |
| 一番槍 | いちばんやり | 戦の際に一番初めに敵と槍を交わす者。にらみあいで緊張が続く状態を破って敵に接近することは、その行為自体が勇敢であると高く評価され、恩賞の対象になった。 |
| 一揆 | いっき | 人々が同じ理由のもと、一つの共同体として結束し、目的を達成しようとすること。国人一揆は、守護大名に対抗するべく、国人と呼ばれた地頭などの領主が結束した一揆。 また土一揆とは、農民などの庶民が領主にさまざまな要求を通すために集まったもの。 |
| 一向一揆 | いっこういっき | 浄土真宗本願寺教団の信徒らが結束した宗教的共同体。守護大名など、既存の組織に対しての武力行使、およびその抗争劇の意味も含む。 |
| 諱 | いみな | 正式な名前、本名のこと。当時は貴人や死者を本名で呼ぶことを避ける習慣があり、通り名としての名前は字(あざな)といった。諱を呼ぶことを許されたのは、親や主君だけであった。 |
| 馬印 | うまじるし | 戦国武将が己の位置を示すと同時に武威を誇示するために、指揮官や自身の周りに立てた旗。遠くからでも目立つよう、瓢箪や大きな扇などが装着されることもあった。 |
| 海賊衆 | かいぞくしゅう | 海上で武力を持った集団。当初は海賊と変わらない存在であったが、平時の漁業権を認められる代わりに、有事に水軍として働く役割を取り決めていたことから、公的権力を持った組織となった。 |
| 花押 | かおう | 文末に署名の代わりとして使われる記号。初めは楷書体で署名されていたが、次第に文字を崩した草書体になり、やがて極端に紋様化されるようになる。この形が花のようであったことから、花押と称された。 |
| 刀狩 | かたながり | 百姓や社寺などから、刀、鉄砲、槍などを取り上げる兵農分離政策。豊臣秀吉もこの政策を行い、取り上げた武器は当時造っていた大仏のくぎや鎹(かすがい)に再利用すると建前を述べた。 |
| 鎌倉公方 | かまくらくぼう | 京都に本拠を置く室町幕府が、関東を支配するために鎌倉に設けた役職。足利家の親族がその職を務めた。 |
| 唐物 | からもの | 中国で製造された輸入品の総称。主に絵画や磁器などの美術工芸品のことを指す。「唐」とは中国のことを指し、唐時代に作られたという意味ではない。 |
| 家老 | かろう | 戦国大名家の家臣団の中で最も地位の高い役職。平時には政治、経済を補佐し、戦時には部隊の長として軍の指揮を行った。 |
| 管領 | かんれい | 室町幕府において、将軍を補佐し、幕政を統括する役職。職務や権限は法律で定められず、将軍よりも権威を持つ者も現れた。関東統治のために設置した関東官僚も存在し、後に鎌倉公方の補佐役にもなった。 |
| 近習 | きんじゅう | 平時には将軍の身辺警護にあたり、戦時は親衛隊の役割を担った家臣。鎌倉時代に制度化され、守護大名の一族や有力な地方武士がその役職を務めた。 |
| 公家 | くげ | 朝廷に仕える貴人、官人の呼称。武力で朝廷に奉仕した幕府を武家と呼ぶのに対して、政務で奉仕する貴族が公家と呼ばれるようになった。 |
| 公方 | くぼう | 国家に関する公的権力全般を指し、天皇、朝廷、将軍に起源する言葉。江戸時代以降、将軍との完全な同意語となる。 |
| 軍旗 | ぐんき | 軍の象徴とされる軍旗は、軍の中で最も勇敢な者が持つことが多かった。 |
| 軍師 | ぐんし | 大将の戦略や指揮を助ける役目。作戦の立案も行ったことから、智将や策士とも呼ばれる。役割として名前がつけられたのは後世になってからで、その当時は明確な役職ではなかった。 |
| 軍配団扇 | ぐんばいうちわ | 戦の際に、総大将が方角を見極め、軍勢を指揮するときに使ったとされる軍配状の団扇。矢石を防ぐための道具としても用いられた。 |
| 喧嘩両成敗 | けんかりょうせいばい | 領主が関わっていないところで、実力行使によって問題を解決しようとする「私闘」に対し、その原因を問わず双方を均等に罰する法原則。 |
| 検地 | けんち | 田畑などの農地を測量し、面積とその土地の生産高を算出する調査。豊臣秀吉の太閤検地は、耕作者に直接課税をしたものであり、中間搾取をしていた領主がほぼ一掃された。 |
| 元服 | げんぷく | 男性の成人を示す儀式で、通過儀礼のひとつ。「元」は首(頭)、「服」は着用を意味したように、儀式では頭に冠をつけた。数え年でおおよそ11~16歳の頃に行われる。 |
| 国人 | こくじん | 諸国の開発を推進した地頭のこと。土地同士のつながりが強く、国・地域ごとに結束して独自の領域支配を目指すものが多かった。 |
| 小姓 | こしょう | 将軍の身辺に仕え、日常における雑用をこなす役職。また、戦時には主君のため命をかけ護衛した。 |
| 小荷駄 | こにだ | 合戦において必要な兵糧や弾丸、予備の武器をはじめ、炊事用具などの陣地設営具を運ぶ輸送隊。原則的には非戦闘部隊であり、軍勢の後方に配置された。 |
| 采配 | さいはい | 戦の際に、大将が軍勢を率いるために用いた指揮用の道具。1尺ほどの柄に10本前後の紙片や獣毛などがつけられることもあった。 |
| 冊封 | さくほう | 中国王朝の皇帝が、周辺諸国の君主と君臣関係を結び、国王などの位を授けること。冊封により臣下となった君主の国を冊封国と呼んだ。 |
| 指物 | さしもの | 鎧の背につけられた旗。 |
| 侍大将 | さむらいだいしょう | 大将の下で数百名から数千単位の部隊を指揮する者。戦況を判断し最善の行動を取る主要な役割を果たす。優秀な侍大将を多く持つことは戦の際に有利になった。 |
| 地頭 | じとう | 鎌倉幕府が設置した荘園などの公家領地を管理する職。荘園などに対して徴税、軍事、警察、管理などを行った。 室町時代になると国人へと変質していった。 |
| 守護 | しゅご | 各国単位で設置された軍事指揮官および行政官。非常時に御家人を召集したり、平時に警察としての役割を担ったが、地方によってその権限は異なった。 守護は主に京都に居住したため、実質的に地方で統治をする者は守護代と呼ばれた。 |
| 城下町 | じょうかまち | 領主の居住を中心に発展した都市。戦国大名は自身の城下町に家臣団を集めることを目指した。また、防衛のため周囲に堀を造り、土塁や石垣を築くなどの工夫があった。この堀は物流用としても活用された。 |
| 城主 | じょうしゅ | 城の主。城を持つのはステータスのひとつであり、戦国大名が本拠とする城をもつのはもちろん、その家臣の中の有力者も城を保有することがあった。 |
| 城代 | じょうだい | 城主の留守中に城を管理、政務、防衛を執り行う者。留守居頭、大留守居とも呼ばれた。 |
| 相伴衆 | しょうばんしゅう | 将軍が他家訪問の際に、供として随従した者。管領家の一族や、有力な守護大名に限定されていたが、戦国時代に入ると名誉職の意味合いも強まり、新興の戦国大名などに許されることもあった。正式名は御相伴衆。 |
| 殿 | しんがり | 部隊の最後尾を担当する部隊。本隊が撤退する際、敵からの追撃を阻止する役目を負った。限られた戦力で敵の進撃を止めなければいけない危険な役割であったことから、人徳と信頼のある武将が務めた。 |
| 征夷大将軍 | せいいたいしょうぐん | もとは朝廷が蝦夷を征伐するために派遣した総指揮官のこと。戦国時代に入り、武家政権が築かれてからは将軍家が世襲し、日本全土を実質的に統治する者を指した。 |
| 正室 | せいしつ | 身分の高い男性の正式な妻のこと。正室は原則ひとりで、それ以外は全て側室と分類された。同義語に正妻、本妻などがある。正室が産んだ子どもは嫡子と呼ばれた。 |
| 先陣 | せんじん | 軍勢の前方に配置された部隊。先鋒、先手衆ともいう。戦の始まりを決め、戦況を見渡す役目も持つことから、対象の中で最も優秀な者が指揮を執った。 |
| 惣 | そう | 農民による村落の自治的な協同組織。惣村とも呼ぶ。惣掟という法令を遵守し、外部からの侵略に備えたり、領主との交渉に圧力をかけるなどの役割を持った。 |
| 側室 | そくしつ | 身分の高い男性に寵愛を受けた女官、女中、女房のこと。同義語に妾、側室、遣女などがある。一夫多妻制とは異なり、家族の一員にはならない。側室の子どもは庶子と呼ばれた。 |
| 大将 | たいしょう | 軍の最高責任者で、戦において指揮をとった者。2軍以上の軍で構成された複数の大将がいる軍勢では、差別化のため総大将と呼ばれた。 |
| 大名 | だいみょう | 一定以上の領地を支配し、地方で勢力をふるう者。武家社会においては、多くの部下を持つ武士のことも指す。当時大きな力を持った者全般、またその役職などを指すことも。 |
| 使番 | つかいばん | 合戦において主君の命令を舞台に伝達、監察をした騎馬武者。最前線の情報を本陣に伝える役割も果たしていたので、馬術、話術だけでなく、冷静な状況判断ができる人間であることが求められた。 |
| 当世具足 | とうせいぐそく | 戦国時代に生じた鎧の形式で、日本の甲冑の分類名称のひとつ。戦国時代には集団戦や鉄砲戦が増えたため、より実践的に改良された鎧。生産性も高く、下級兵士にも支給された。 |
| 外様 | とざま | 譜代の反意語で、主君と主従関係を持つ一般の御家人のことを指す。戦国時代には、敵勢であったが家臣として編入した者たちも外様と呼ばれるようになった。 |
| 土民 | どみん | 大名や武将など、支配者階層の者が民衆をよぶときの言葉。あくまで区別のための呼称であり、差別的な意図を含むことは少ない。 |
| 南蛮 | なんばん | 漢民族から見て南方の地域、および人物に対して用いた蔑称。ポルトガル、スペインを意味したが、貿易が盛んになると侮辱語としての意味合いよりも、珍しい文物を指す語として使われた。 |
| 年貢 | ねんぐ | 領主が農民に課した税。主に米で納められることが多かったが、鎌倉時代になると貨幣流通が増加したため、代銭納が行われることもあった。 |
| 旗頭 | はたがしら | 武士の集団を率いる者を意味した言葉。概念的なものであり、明確な役職は存在しない。室町幕府の体制では、地頭を束ねる守護が旗頭的存在であった。 |
| 旗奉行 | はたぶぎょう | 戦場で旗指物の管理を行う役目であり、江戸幕府では老中の支配を受ける立場。旗を倒すことは軍の苦戦や敗戦を意味したことから、士気を左右する重要な役割だった。 |
| 旗本 | はたもと | 主君に属する直属部隊の家臣。主君の軍旗を守る武士団に由来する。主に譜代の家臣を中心に編成され、合戦においては本陣を構成していた。 |
| 伴天連 | ばてれん | 日本に渡来した、キリスト教の神父、宣教師、司祭のこと。伴天連門徒といわれたことから、キリスト教の俗称にも使われる。語源は神父という意味のポルトガル語、パードレ(padre)に由来する。 |
| 百姓 | ひゃくしょう | もとは皇族以外の貴族を含むすべての人々を指した言葉。戦国時代には民衆を意味し、農民に限らず商工業者なども百姓と呼ばれた。 |
| 兵糧米 | ひょうろうまい | 出陣中に武士に供給される食料のこと。戦国時代には、兵糧米を平時から蓄えられるように蔵を設置して、戦時になると兵に給付していた。 |
| 譜代 | ふだい | 数代にわたって一主君に仕えた家臣(またはその家系)のことを指す。武家社会では譜代の家臣は信用されると同時に重用されたが、主家滅亡時に離反すると激しく非難を受けた。 |
| 本陣 | ほんじん | 合戦の際に、大将が位置する場所に陣取られた中心部隊。戦況を見渡せる小高い丘や、地形的に有利な場所に設営された。 |
| 名物 | めいぶつ | 優れた茶道具のこと。名物の中でもひときわ優れた道具は大名物といい、更なる上位は天下無双、日本第一、天下一といった称号がつけられた。 |
| 門前町 | もんぜんまち | 大規模で多くの参詣者を集める寺院、神社の周辺で発達した町。絶えず人が集まることから、宿泊所が多く設営され、食料品や特産品を売買する商人も集まった。 |
| 幼名 | ようみょう | 武士や貴族の子が幼少期の期間につけられる名前。 元服して諱を与えられるまでは幼名で過ごす。 農民の名前も幼名というが、諱をつけられることはない。 |
| 与力 | よりき | 本来は戦に加勢する人のこと指したが戦国時代には在地の土豪のことも指した。大きな大名に加勢する与力大名の例も見られた。 |
| 楽市楽座 | らくいちらくざ | 各地の戦国大名が城下町などの支配地で商業の自由を認めた経済政策。「楽」とは規制が緩和され、自由になった状態を指す。通行税が徴収されない、商品に対し課税がされないなどの権利が認められることもあった。 |
| 浪人 | ろうにん | 主人を失った、あるいは持たない武士。戦国時代は小規模な戦乱が頻繁に起きたため、新しい主人を得る機会は多かった。また、治安状況も悪かったため、浪人同士で徒党を組み一揆を起こす者もいた。 |
| 倭寇 | わこう | 朝鮮半島や中国大陸の沿岸部および一部の内陸、インドシナ半島などの諸地域で活動した海賊。勘合貿易が途絶したことにより、倭寇を通じた密貿易も盛んになった。 |
| 用語 | 読み | 説明 |