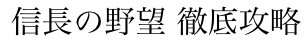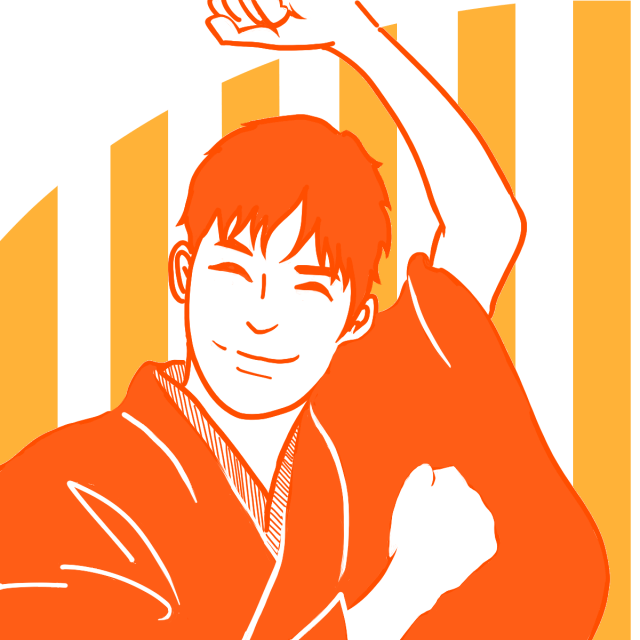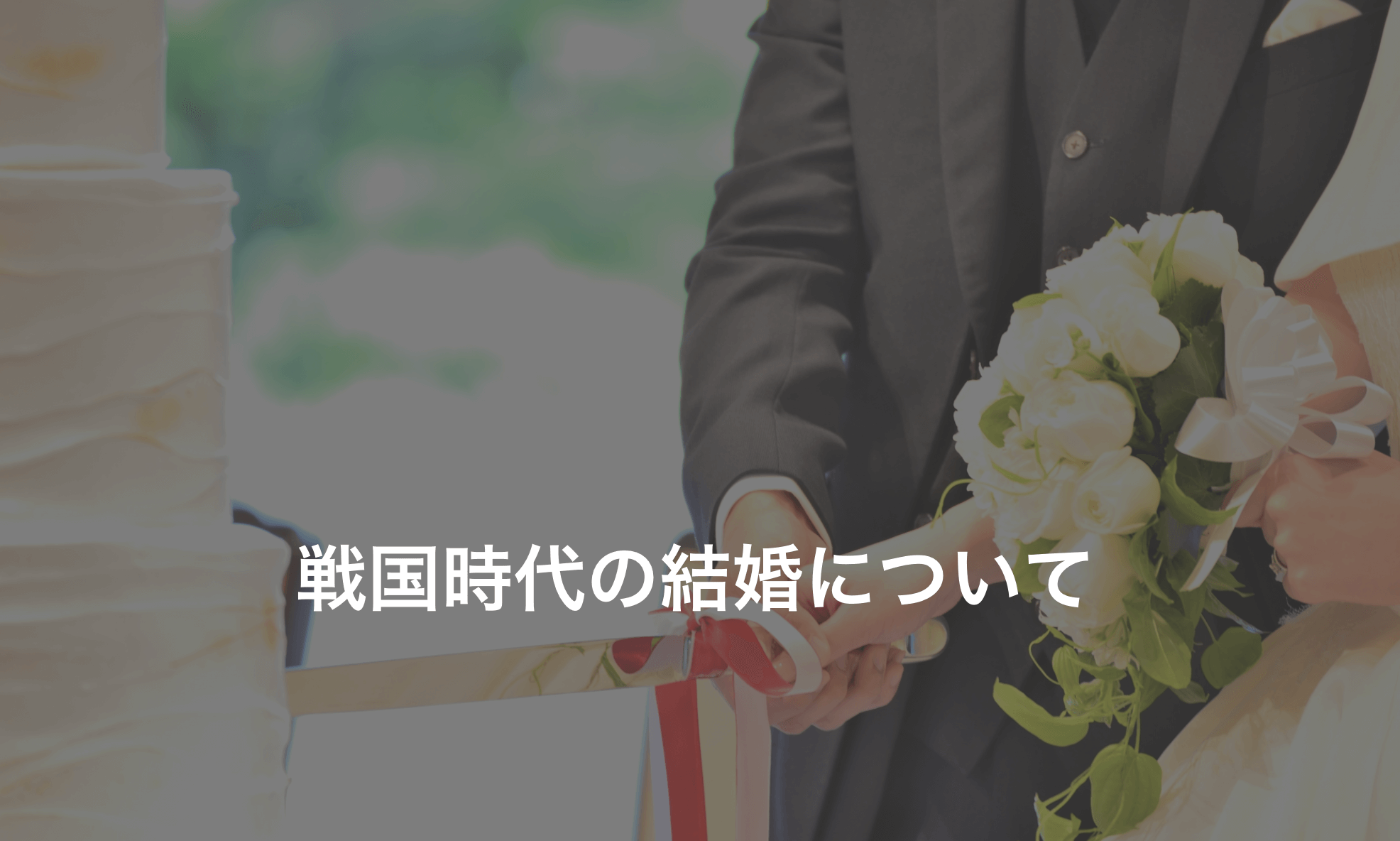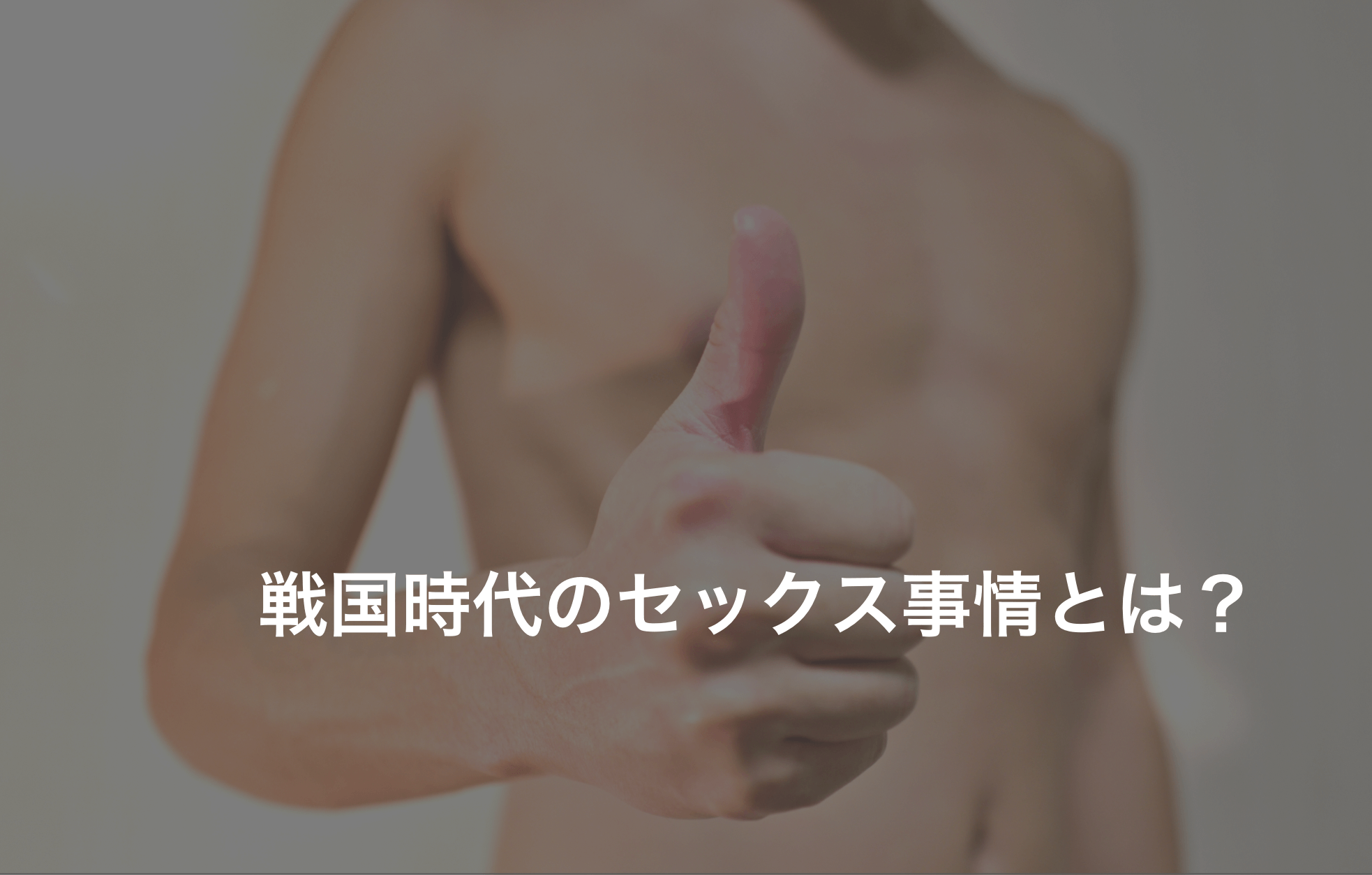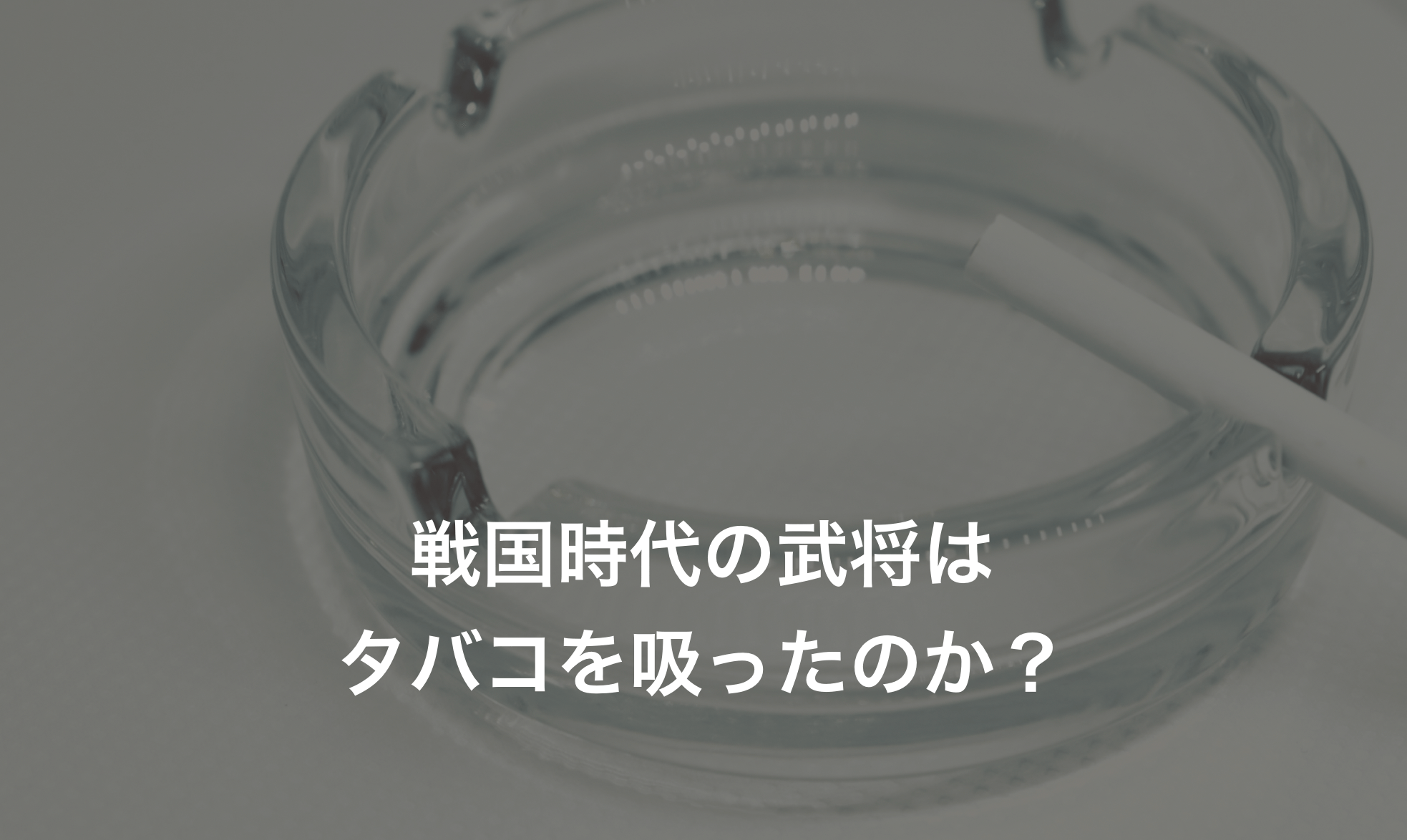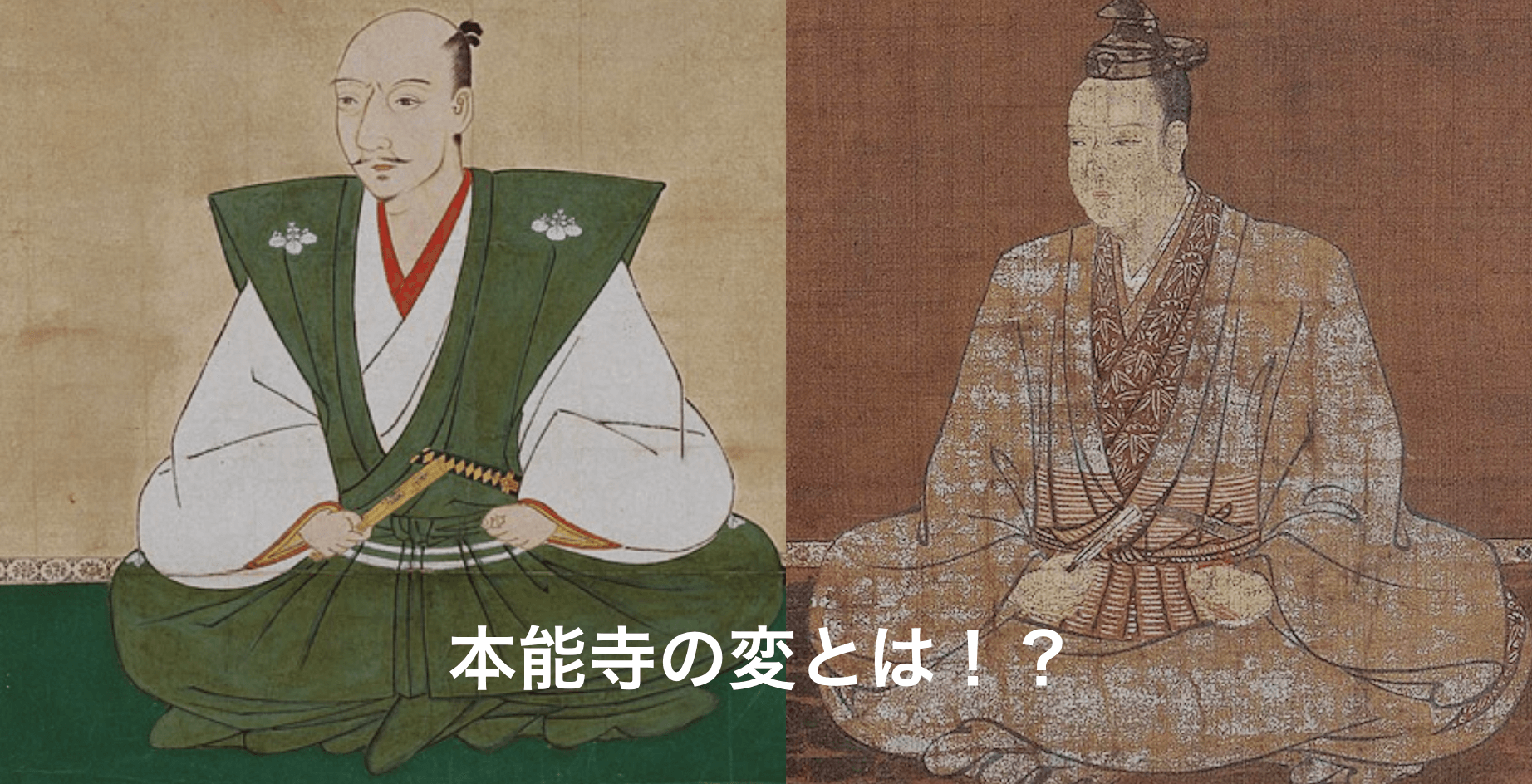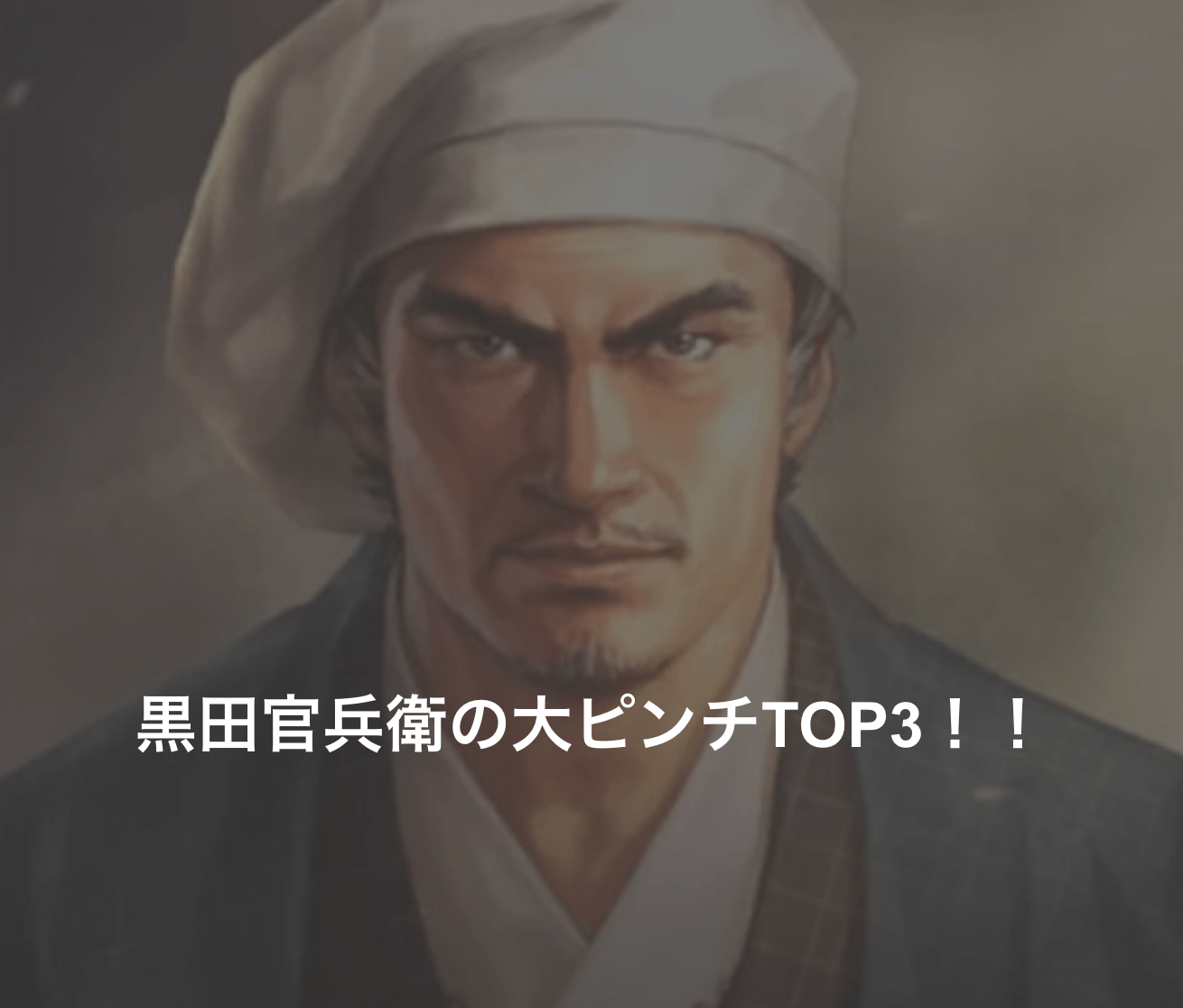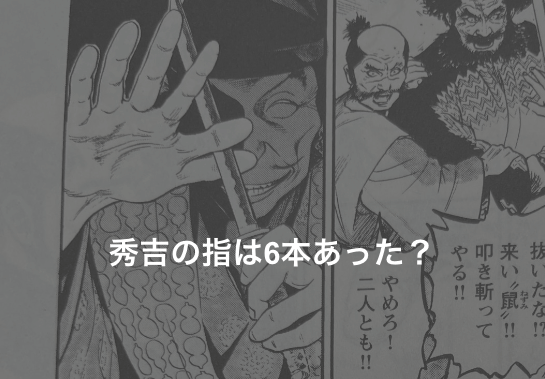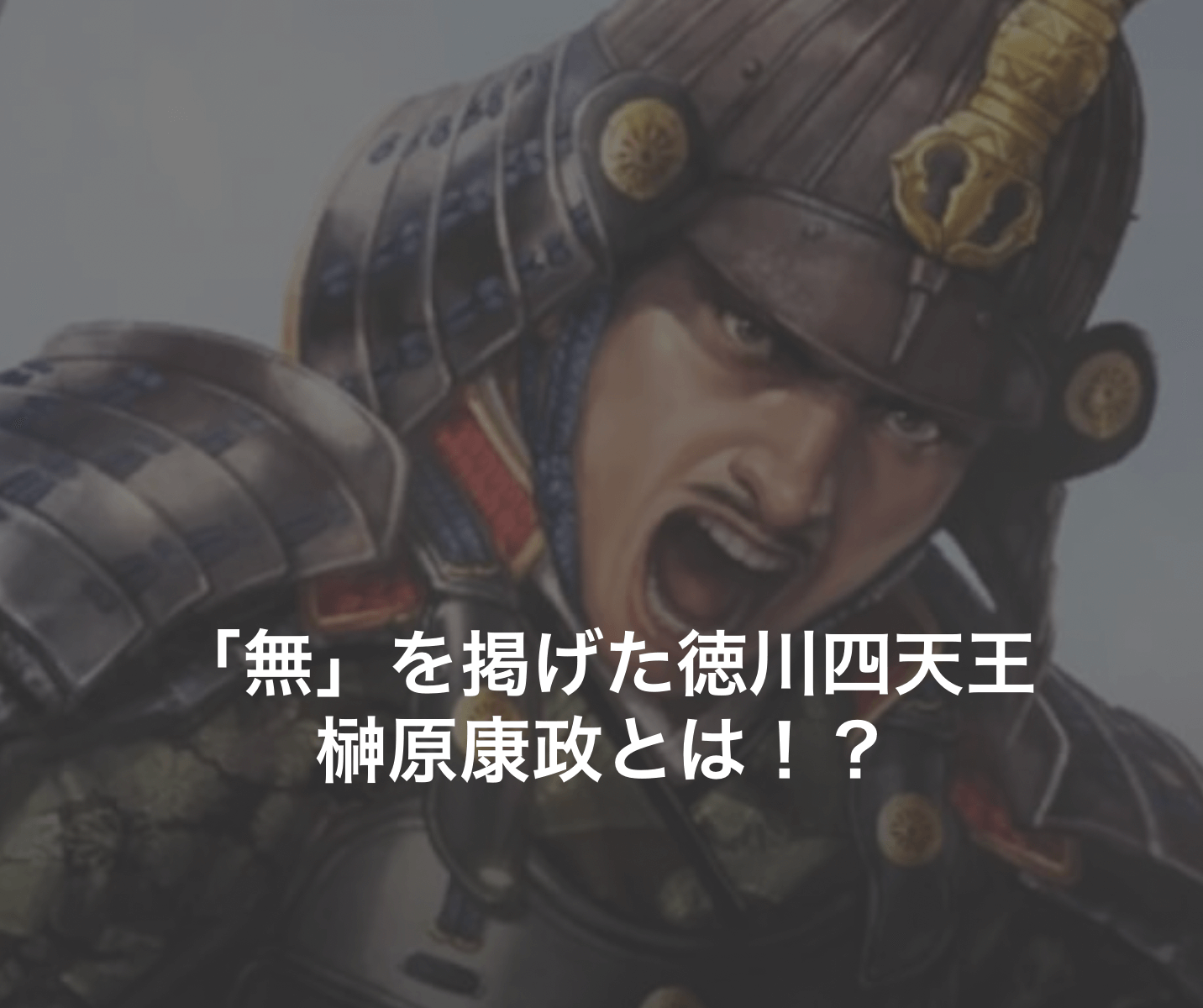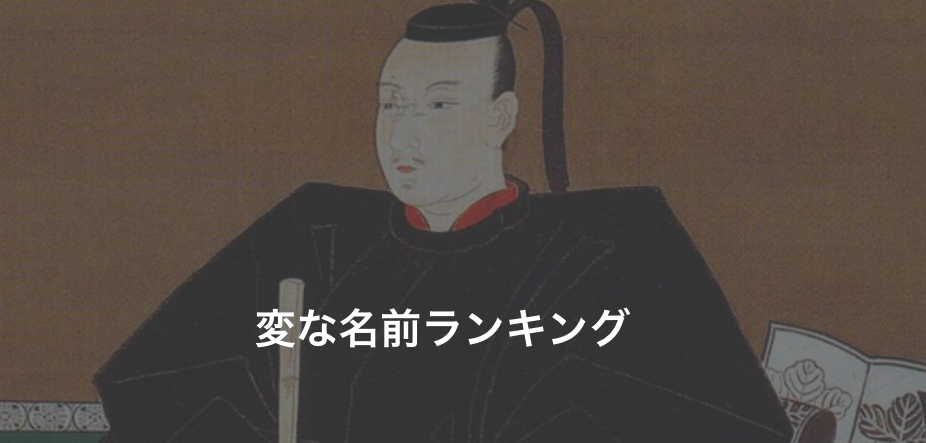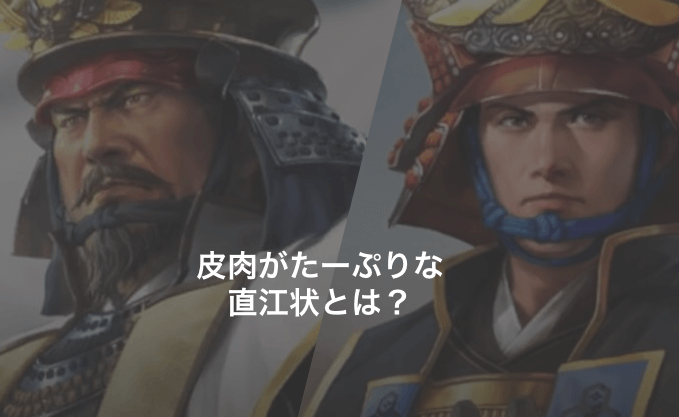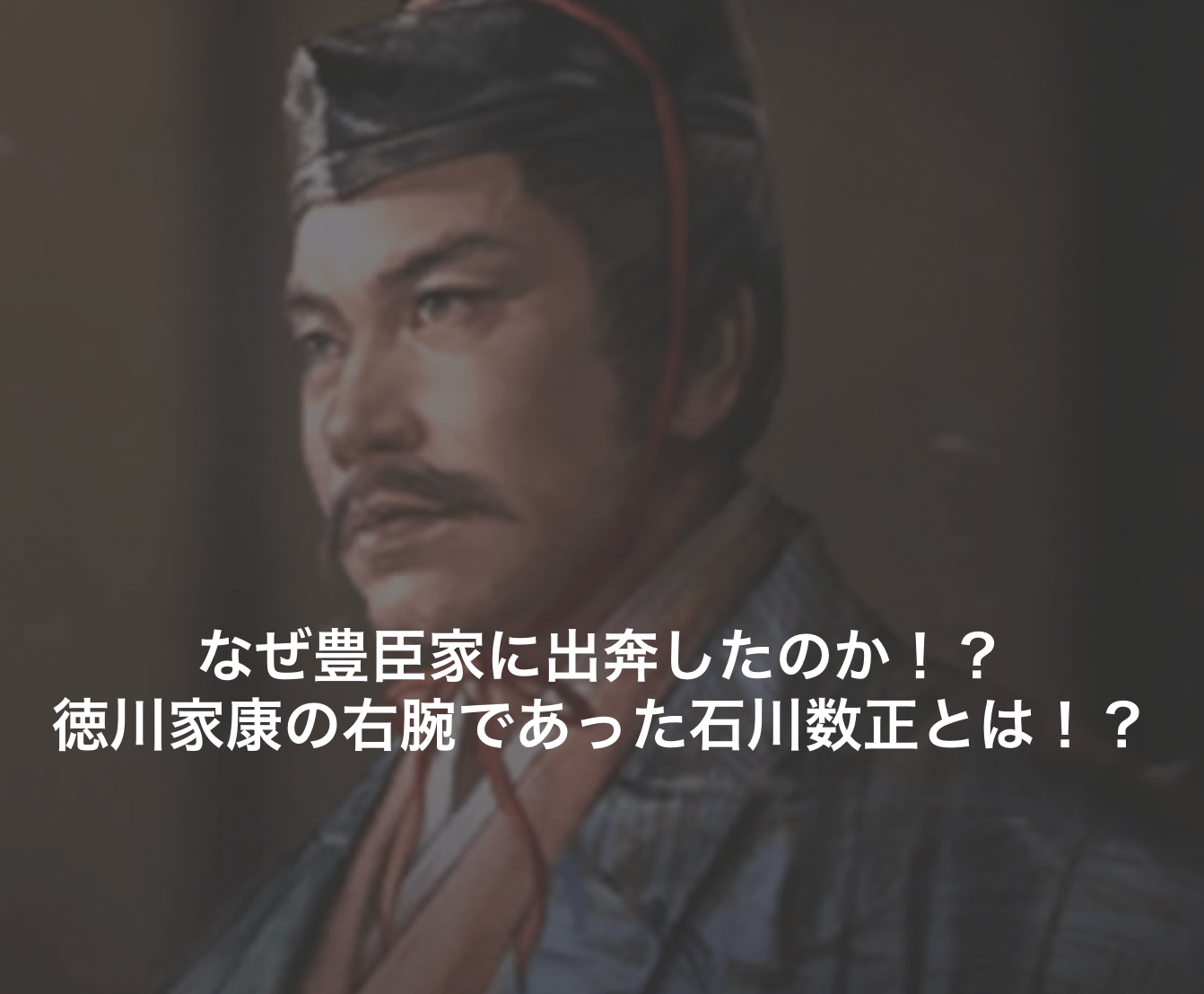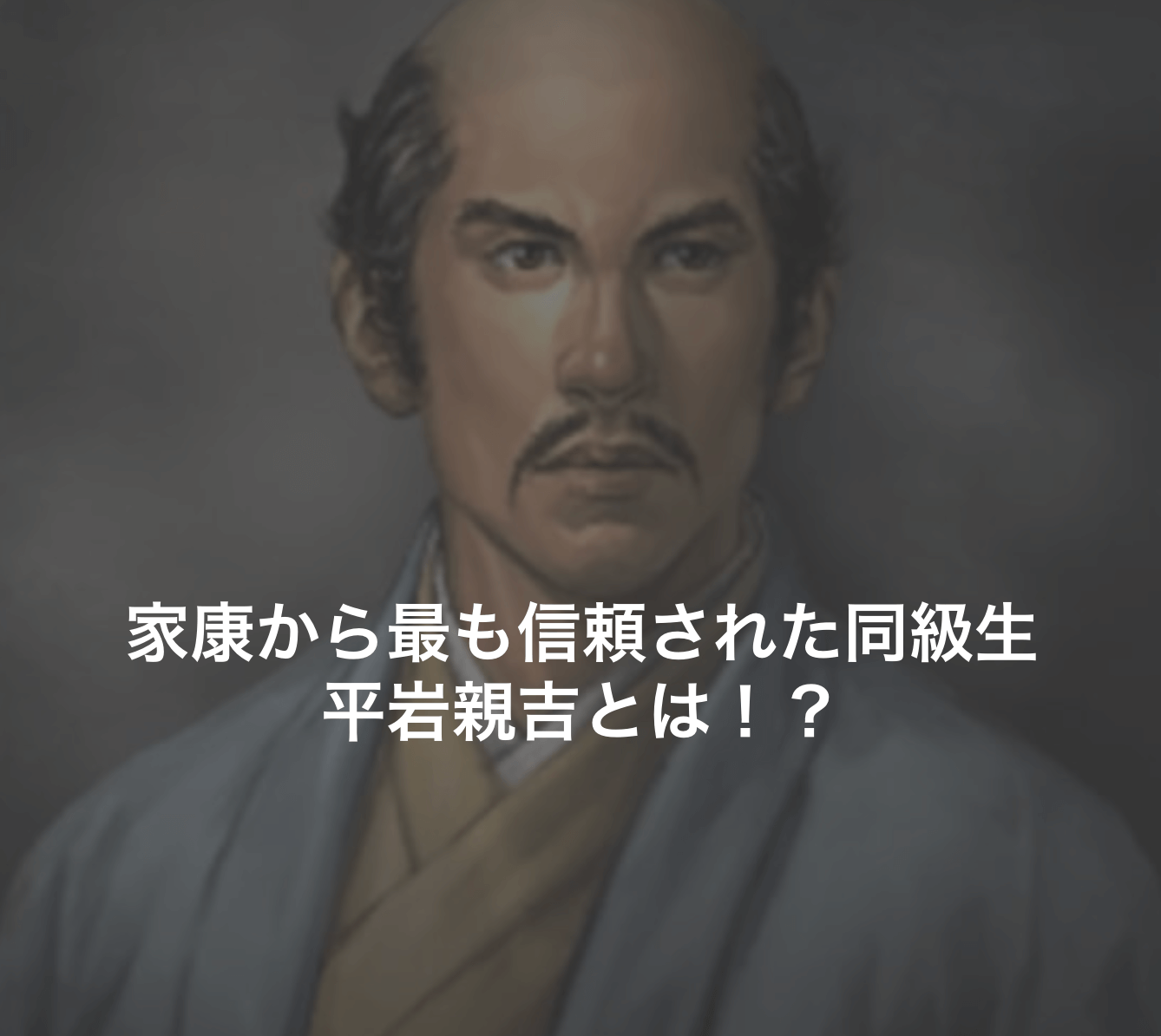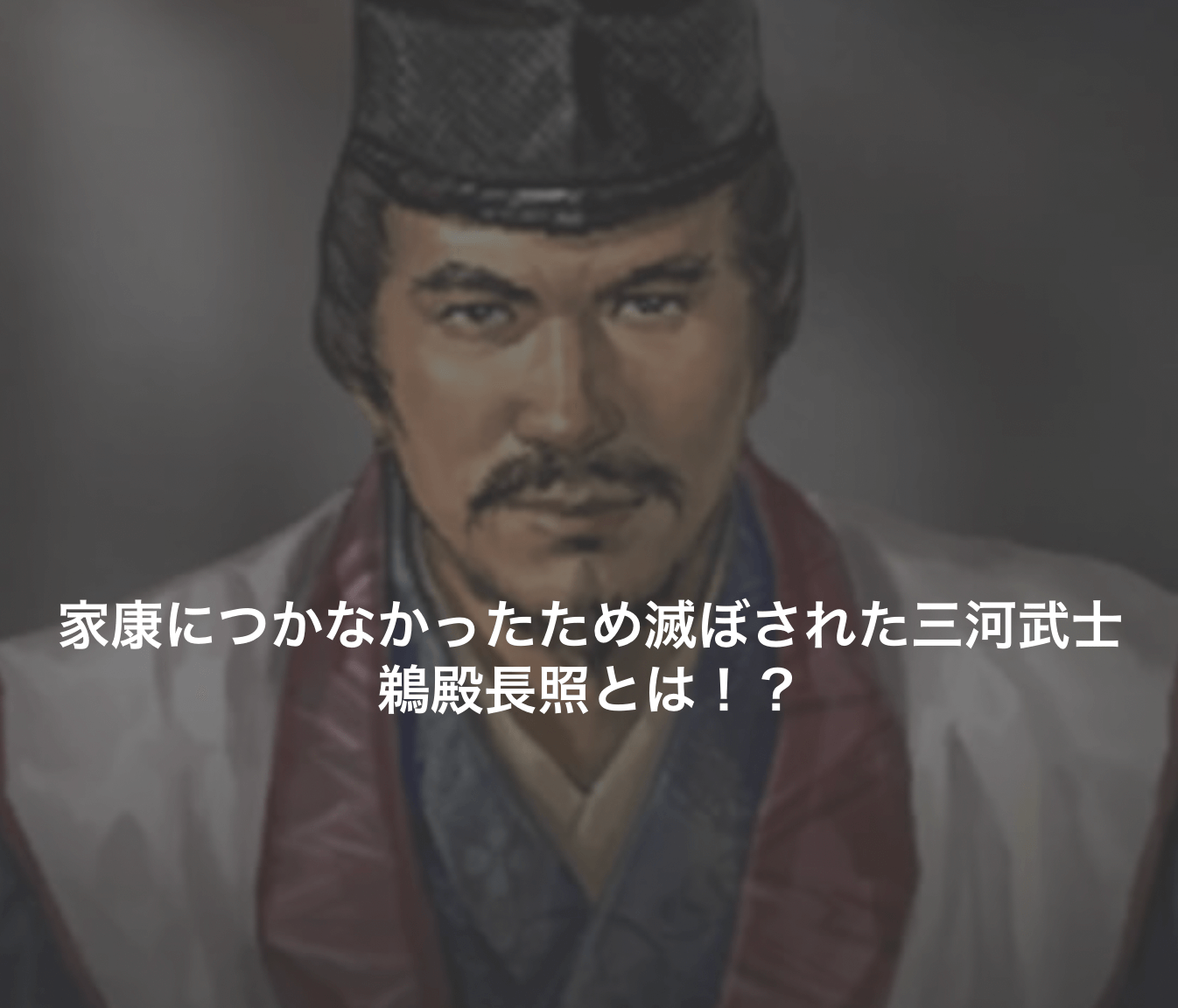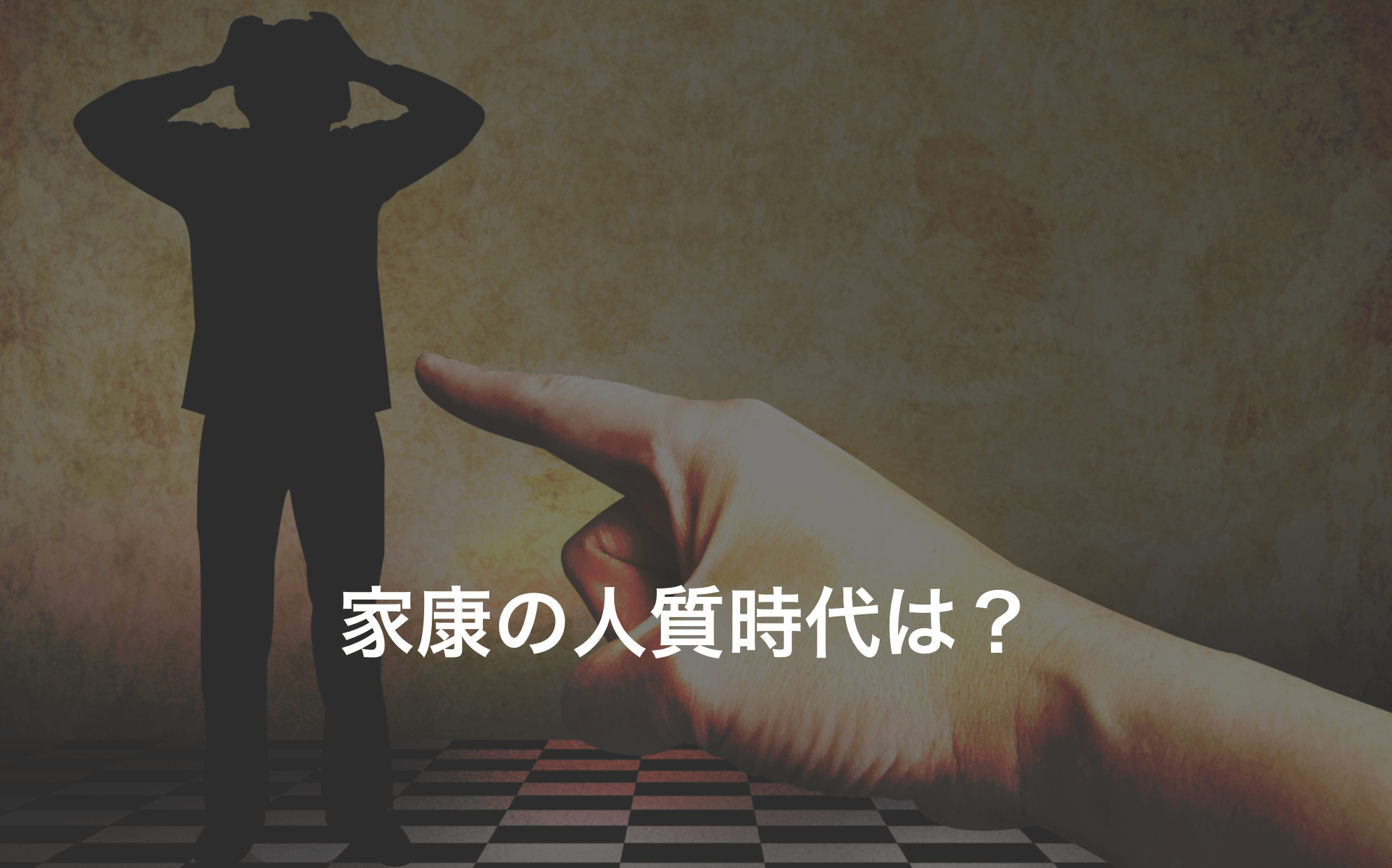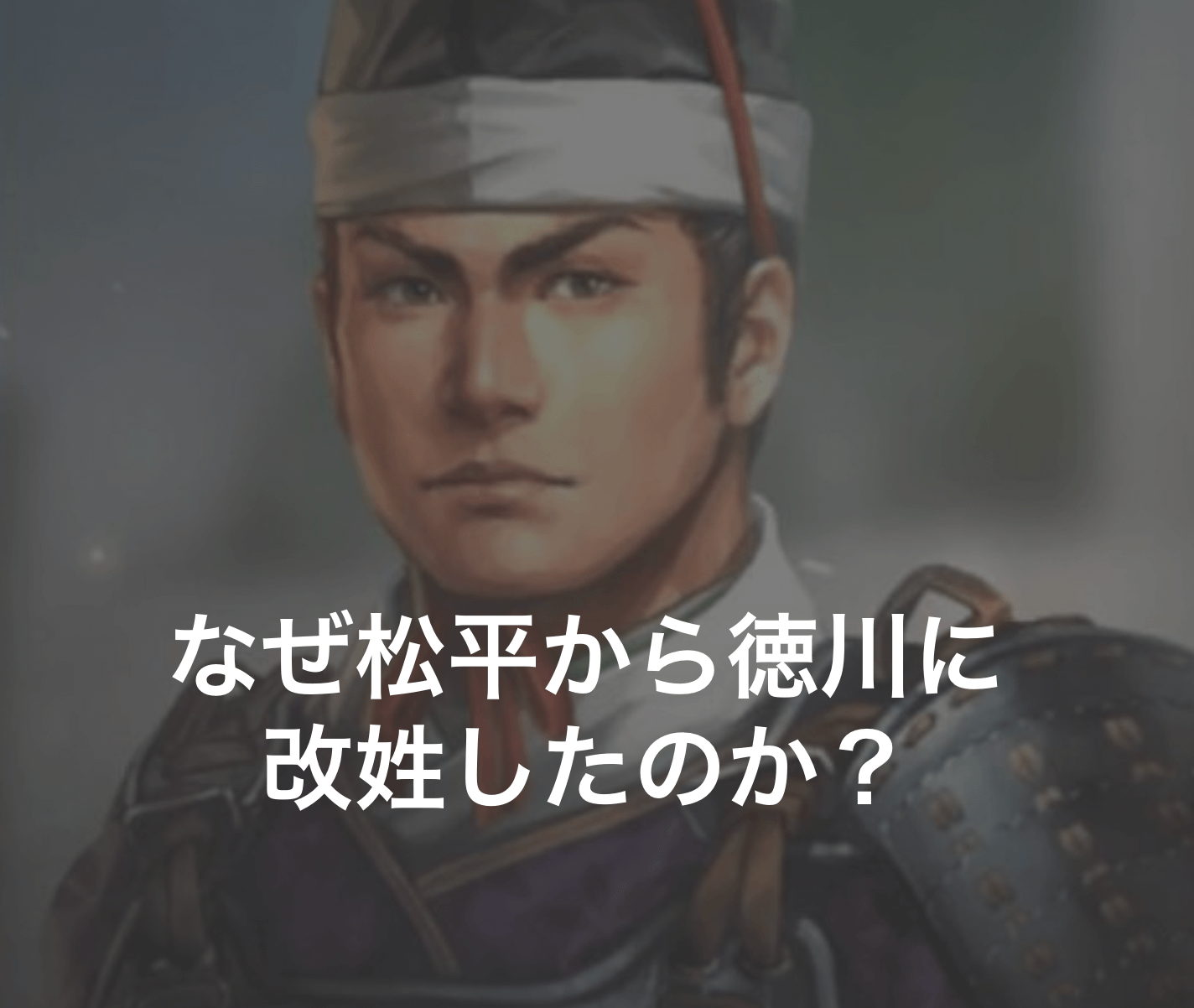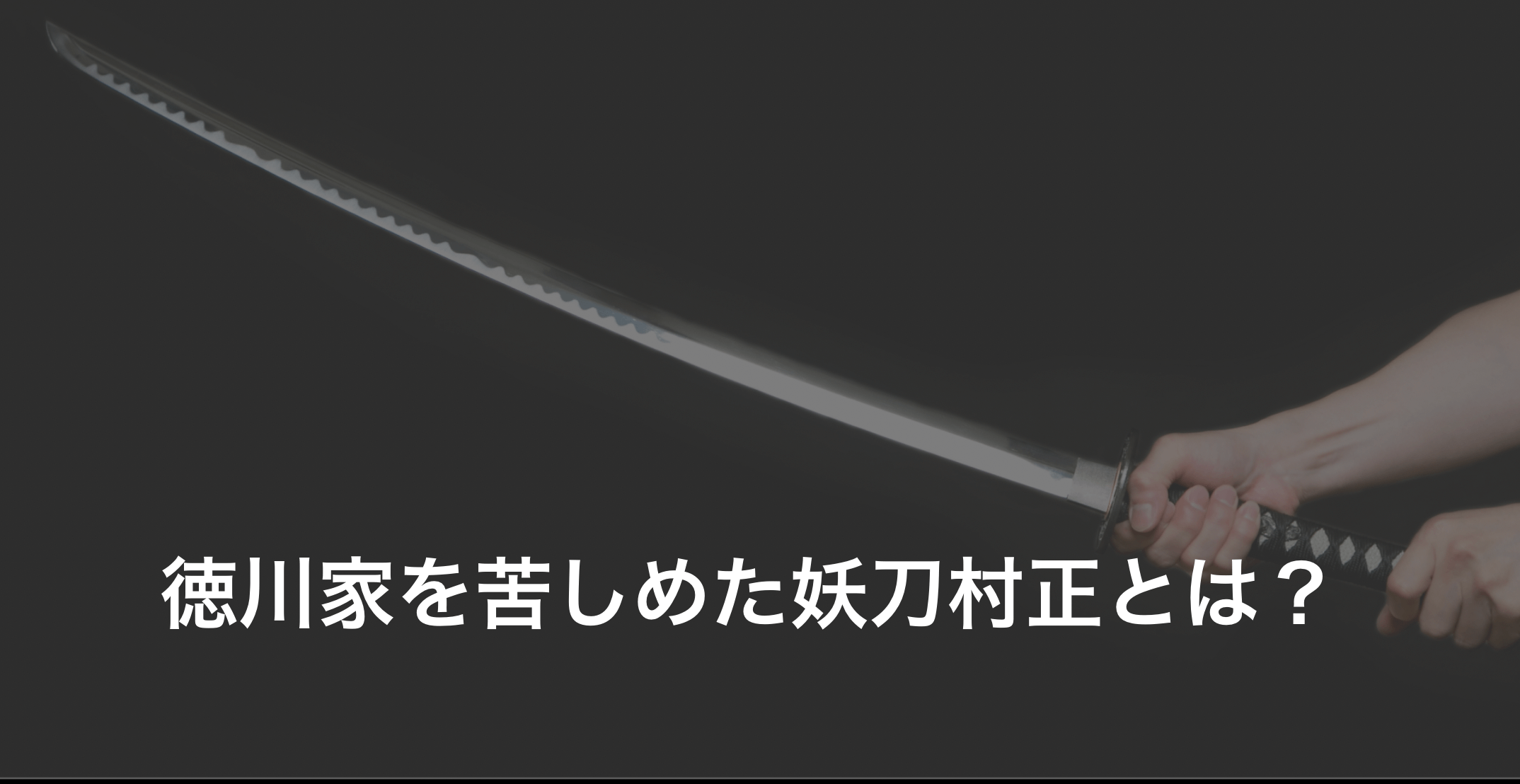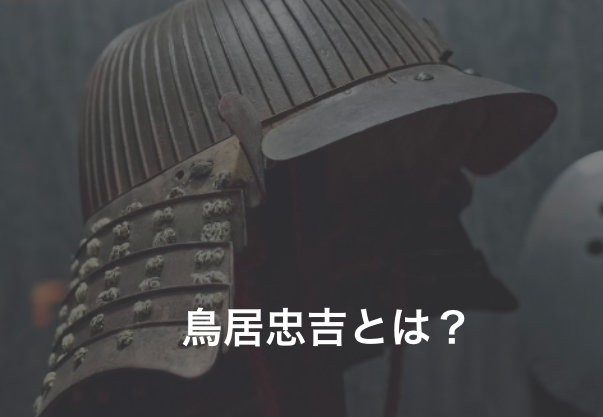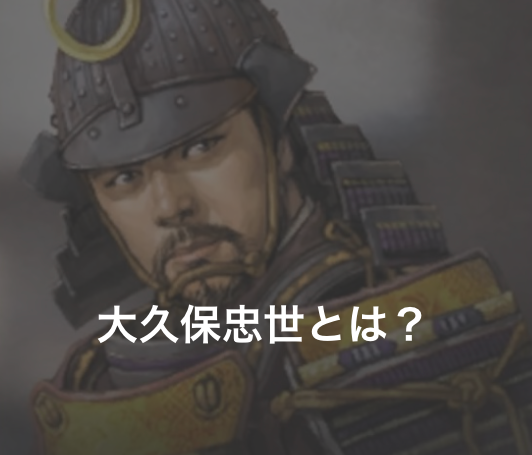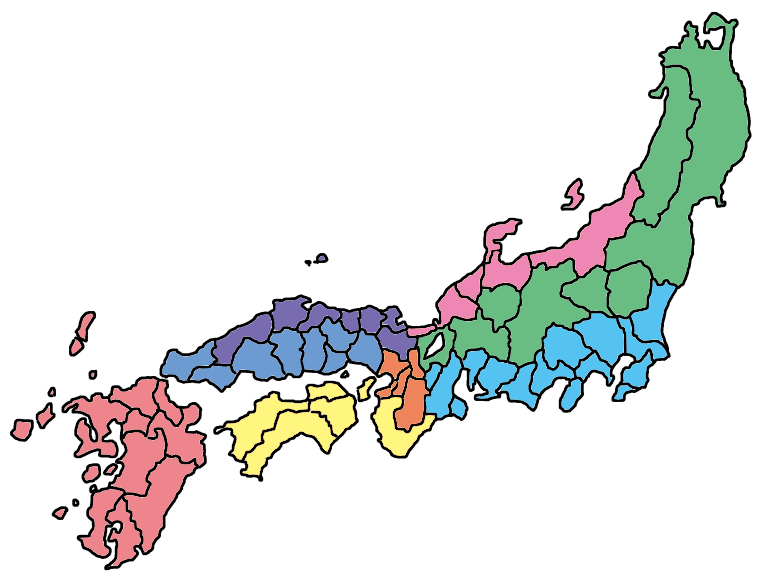views : 10572
最も側室が多かった戦国大名は誰か?【戦国時代の暮らし】
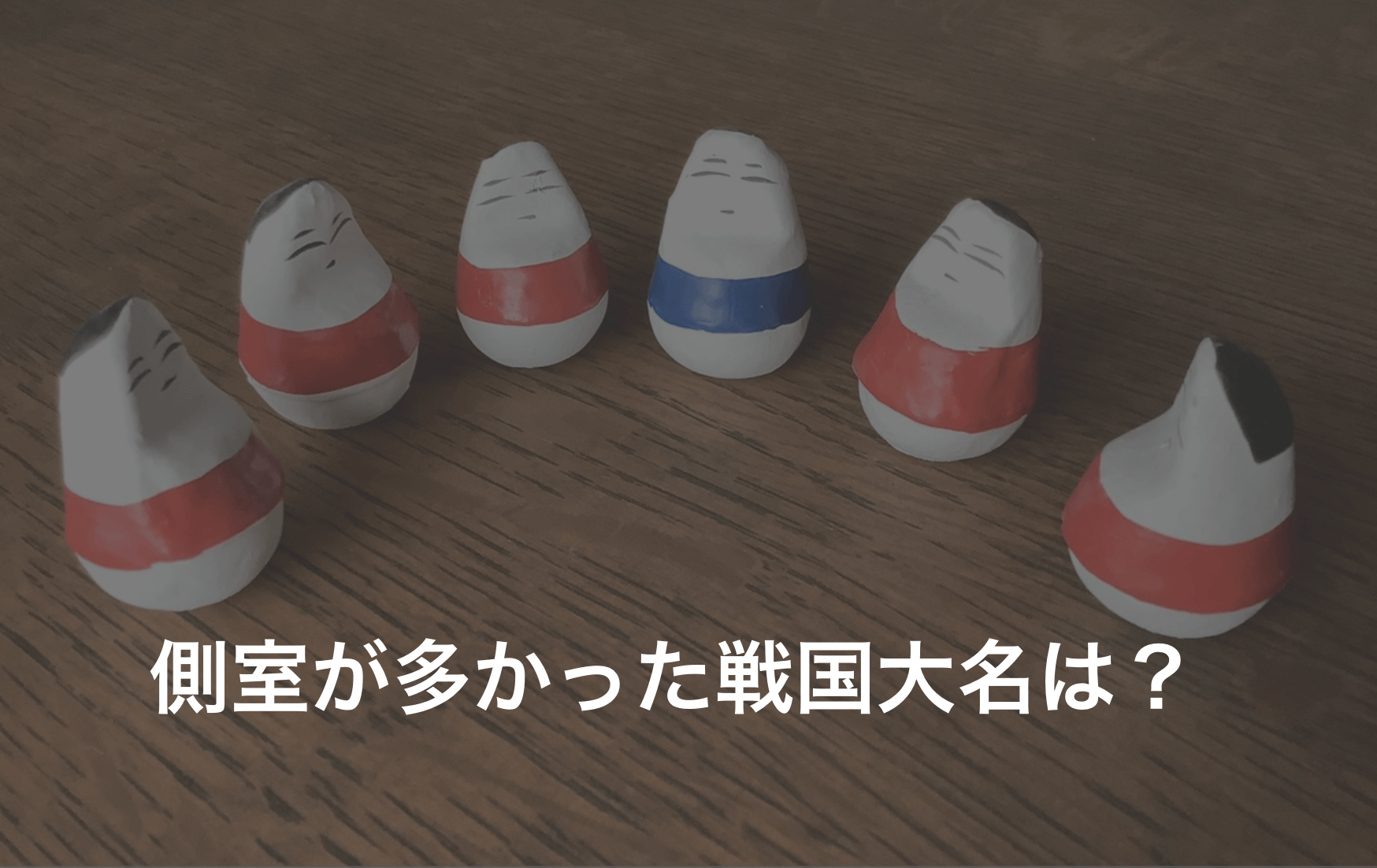
こんにちは、歴史大好きtakaです。
戦国の世では、大名は側室を持つのが世の常識だった。
戦国時代は嫡男が戦死することもあれば、疫病などで子が早死にすることもあった。
側室を持つのは、できるだけ多くの子孫を残し、家系の断絶を避けるために必要な手段であった。
それとともに、側室を持つことは、閏閥を作るという目的もある。
味方を増やすため、戦国大名の娘や妹が、別の側室になることがよくあったのだ。
というわけで、今回は戦国時代の側室について記載していきます。
それでは行ってみよう。
目次[非表示]
側室を持っていた戦国大名
織田信長(11人)
織田信長には正室のほかに、11人の側室がいたといわれています。
正室は帰蝶(濃姫)で、美濃の戦国大名・斎藤道三の娘である。しかし、信長と帰蝶の間に子供はできなかったようだ。
信長の側室で特筆すべきは生駒家宗の娘で、2人の間には嫡男・信忠、次男・信雄、娘の徳姫が誕生しました。
徳川家康(15人)
最初の正室は今川義元の姪の築山殿(つきやまどの)です。仲睦まじいといえる感じではなかったようですが、徳川信康や亀姫などを産みます。

この子誰の子?家康の次男ながら冷遇された結城秀康【マイナー武将列伝】
次に正室になったのは、秀吉の異父妹である朝日姫です。小牧・長久手合戦後、羽柴家と徳川家の和睦のため結婚に至りました。
家康は子供を産める女性を好んでおり、11人の息子と5人の娘に恵まれました。
伊達政宗(8人)
正室は、政略結婚である愛姫(めごひめ)。
政宗が最初に迎えた側室は、飯坂の局です。大層な美女だったようです。
豊臣秀吉(13人)
秀吉の正室は北政所(きたのまんどころ)で、当時としては珍しく恋愛結婚でした。
側室には浅井三姉妹の淀殿や淀殿のいとこ京極竜子など、秀吉の身分の低さというコンプレックスから、高貴なお方が側室に多かったようです。
女好きの秀吉ですから、妻としてではないが抱えていた女性はもっと多くおり、地方の城にもいたようです。
豊臣秀次(43人)
最も多くの側室を抱えたとみられるのは、秀吉の養子にあたる豊臣秀次です。
秀吉に関白職を与えられた秀次には側室が39人いたとも43人いたとも伝えられています。
しかし、秀吉の怒りを買い秀次の罪が決まると、幼い若君4名と姫君、側室・侍女・乳母ら39名の全員が斬首されたようです。
それでは、逆に側室を持たなかった戦国大名と生涯独身であった戦国大名も見てみましょう。
側室を持たなかった戦国大名
一夫多妻制が一般的な戦国時代に一人の女性を愛し抜いた戦国武将を紹介します。
多数派ではないものの探せばそこそこの数がいたようです。
ちなみに、キリスト教に入信している武将は基本的に側室を持ちませんでした。
山内一豊
愛妻家といったら土佐の大名である山内一豊。正室の千代ひとすじの男でした。
現在の高知県民は長宗我部よりも山内一豊を慕っていますね。
石田三成
石田三成も側室を持たず、正室・皎月院(宇多頼忠の娘)との間に8人もの子をもうけています。
黒田官兵衛
官兵衛の正室・櫛橋光
黒田官兵衛の正室。黒田長政の生母。院号は照福院。十五歳で官兵衛に嫁ぐと、その才と徳で夫を支えた。浄土宗を篤く信仰していたと伝わる。
黒田官兵衛はキリシタン大名で洗礼名はドン・シメオン。なので、生涯一人の女を愛しました。
黒田官兵衛は兵庫県姫路市の小寺家の家臣時代に、隣の市である加古川市の櫛橋家の光と婚姻し、二人の子を授かりました。
長男は初代福岡藩主となった黒田長政です。
明智光秀
明智光秀の正室の妻木熙子(つまきひろこ)は相当「美しい女性」だったようです。
明智家と妻木家は親戚同士で、熙子と明智光秀は幼い頃から顔なじみであったようです。
明智熙子は結婚前、「天然痘」(てんねんとう)を患っており、一命を取りとめたものの、左頬に痘痕が残っていました。
明智家から熙子に縁談が来たときに、熙子はその痘痕を恥じて、熙子の妹である「芳子」を嫁がせて欲しいと両親に懇願しますが光秀は「人の容貌はすぐに変わるけれど、心の美しさは変わらない」と、芳子ではなく熙子を妻に選びます。
そして細川忠興の正室となった玉(ガラシャ)を含め3男4女の子宝に恵まれました。
幼い頃からの恋愛感情があったのではないかと思います。
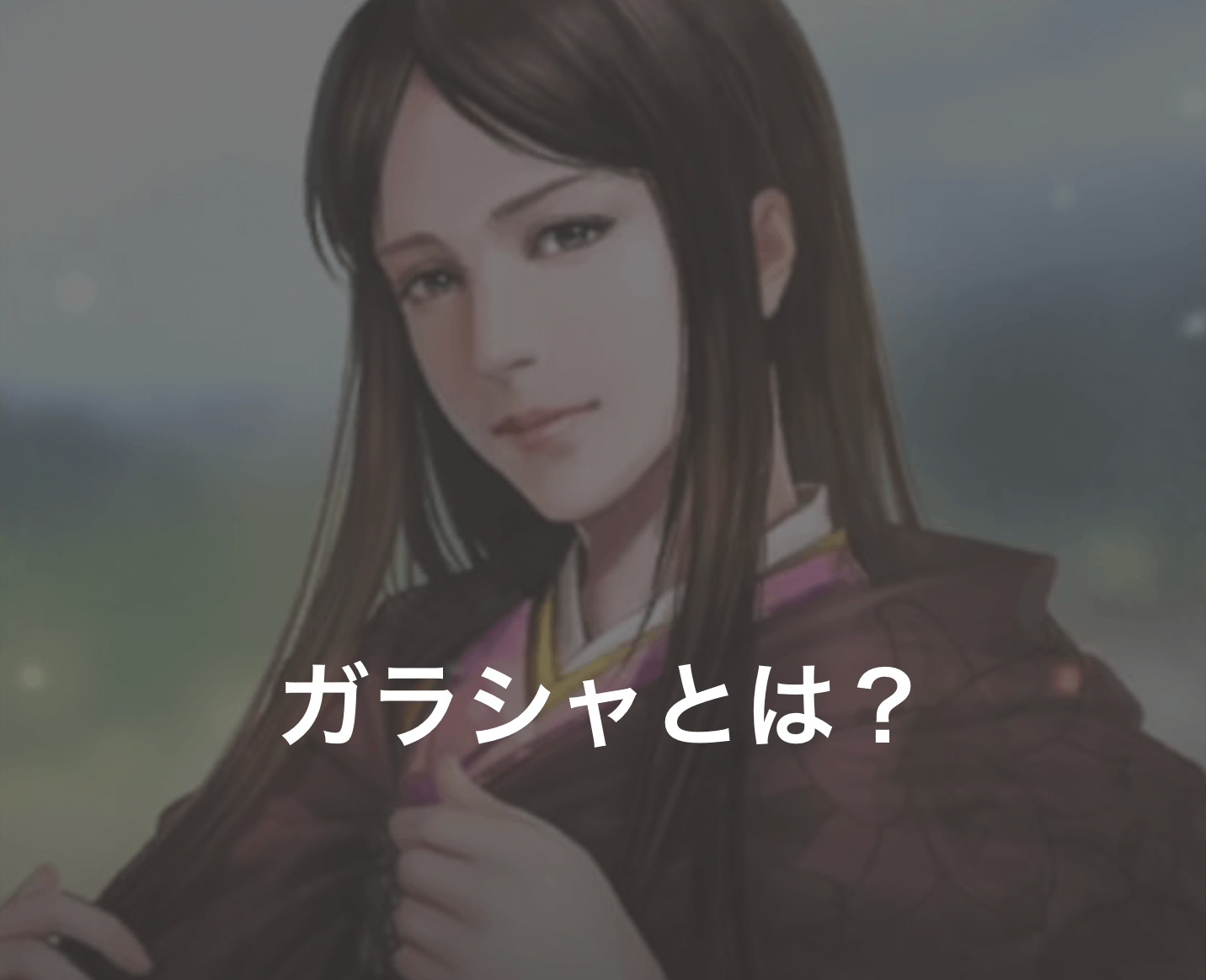
夫への愛と憎悪による悲劇の死、細川ガラシャ【戦国時代の女性】
宇喜多秀家
前田利家の子で、豊臣秀吉の養女・豪姫と婚姻します。
豪姫はキリシタンだったので側室は、認めませんでした。
秀吉の「三国一の婿君」のお眼鏡に適った形だが、仲は大変よく、関ヶ原の敗戦逃走時には資金を工面する等、手助けをしています。
武田勝頼
織田家の養女を正室にします。
大変愛したが、嫡子信勝を生んだ後亡くなったため、悲しんだ勝頼は11年間孤閨を守ります。
2度目の正室として18歳差、北条氏政の妹14歳を娶りました。
健気に尽くし、兄・北条氏政の裏切りの際も苦悩し、最後の天目山でも、生き延びることを勧める勝頼とともに果てました。
再婚はしましたが、どちらも正室なので紹介しました。
独身だった戦国大名
モテないわけではない、結婚しないだけなのだ。
次は生涯独身であった戦国大名を紹介します。
上杉謙信
上杉謙信は「生涯不犯」つまり性交渉を一生しなかったと言われている。
事実として謙信には実子がなく、女性を性対象と見たような形跡がほとんど見えない。
女性に興味はなかったが、「男色」には強い関心があったという説や、軍神、毘沙門天に捧げ、能力を得るため妻帯禁制を堅く守っていたとする説があります。
上杉家公式の藩史にも若い頃の謙信が「御身清浄ニシテ、自然ト塵慮ヲ遠ケ」と意識的に色欲を遠ざける生活をしていたことが伝えられています。
後継者の上杉景勝は姉の子で養子です。
大谷吉継
秀吉から「100万の兵を率いさせてみたい」と称賛された吉継ですが、ハンセン病を患っていました。
当時伝染する病気と考えられていたため、独身だったそうです。
弟・妹などは全て養子です。
戦場では輿に乗り、指揮を執る文武両道の人でした。
まとめ
いかがでした?
秀吉に側室が多いのは想像通り。しかし秀吉に子ができなかったので(誰が父親かわからない秀頼がいたが)、甥の秀次には側室を持たせ豊臣一族を多くし安定化を図ったのでしょうね。
余分に家族を養うので側室を持てる武士はそれなりの身分が必要でした。一夫多妻が認められていた時代でも、身分の低い小者は皆一夫一婦制が当たり前だったようです。
それにしても、側室を何人も持つとはうらやましけしからん。
それでは、今後も戦国時代の暮らしの記事をアップしていきますのでよろしくお願いいたします。
参考
ここが一番おもしろい!戦国時代の舞台裏
「女狂いを控えよ」女好きの豊臣秀吉にさえ助言されたのは? 側室多すぎ武将4選
明智熙子 – 刀剣ワールド
伊達政宗の側室たち
正室・側室