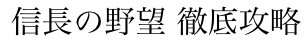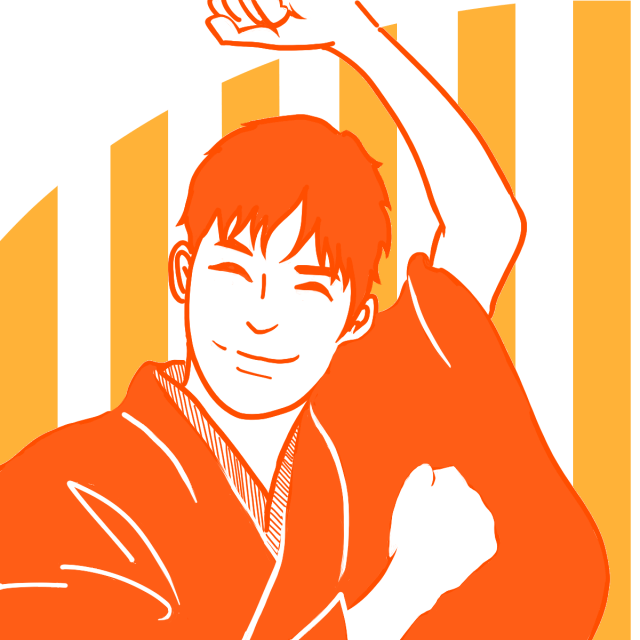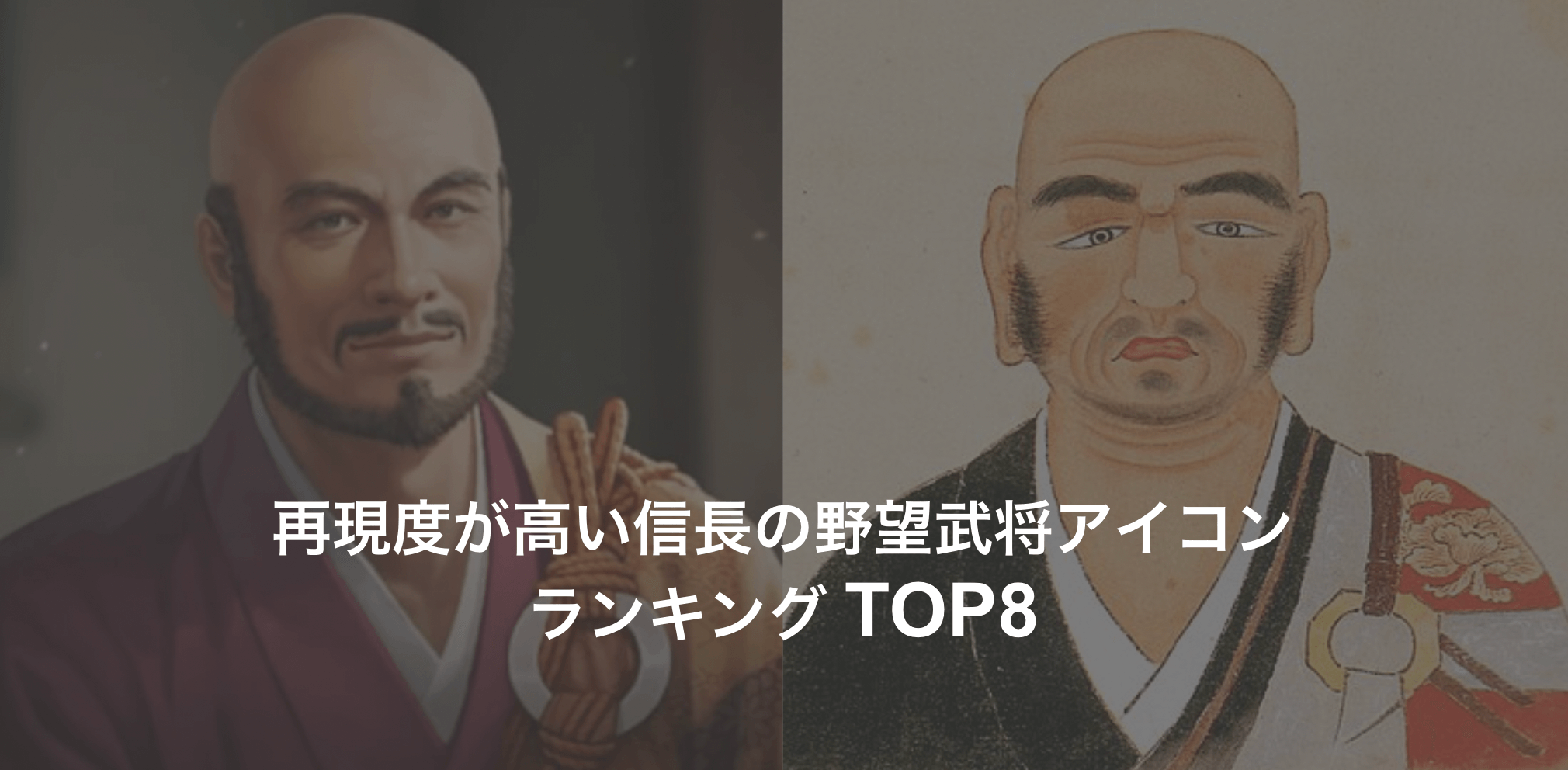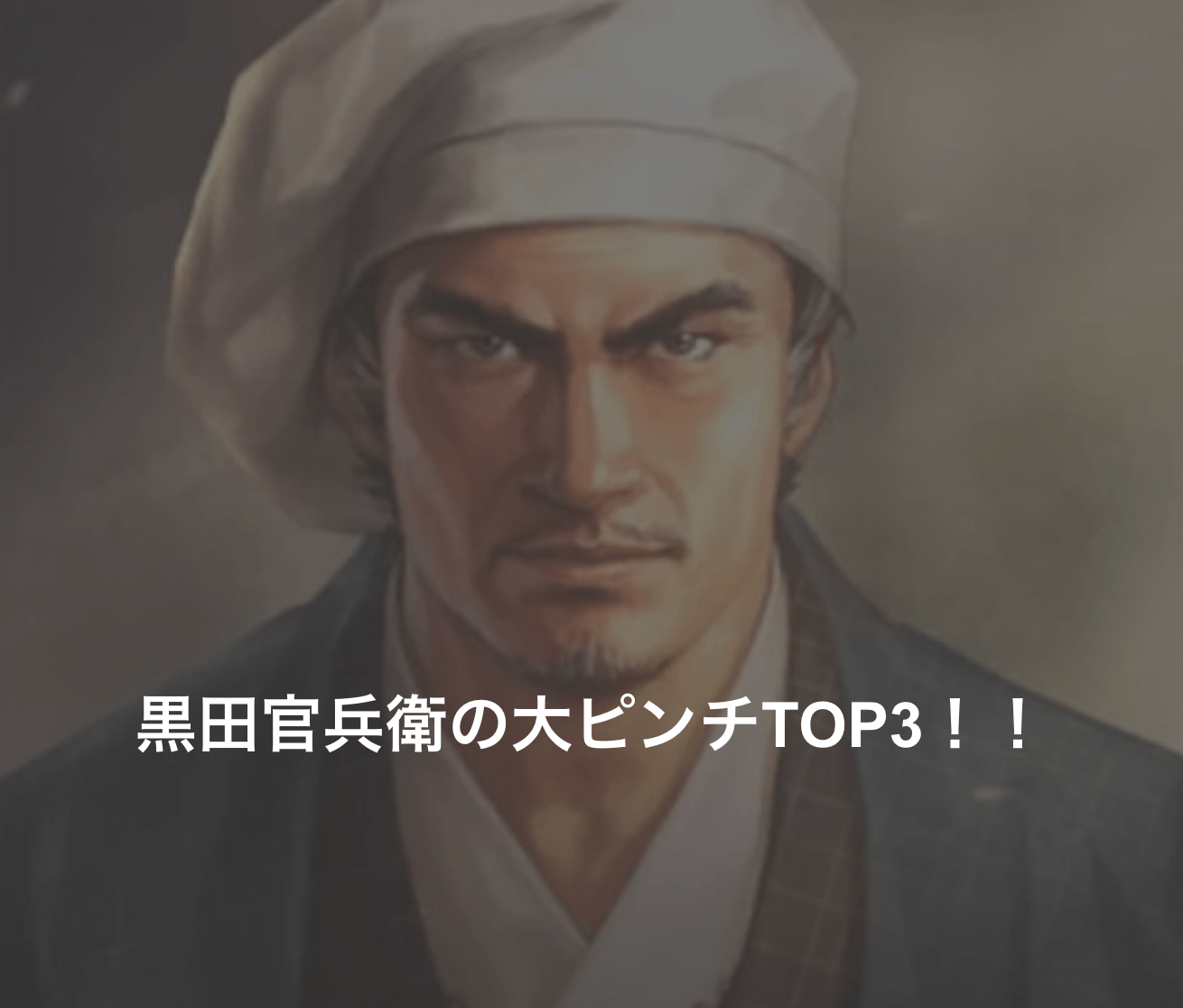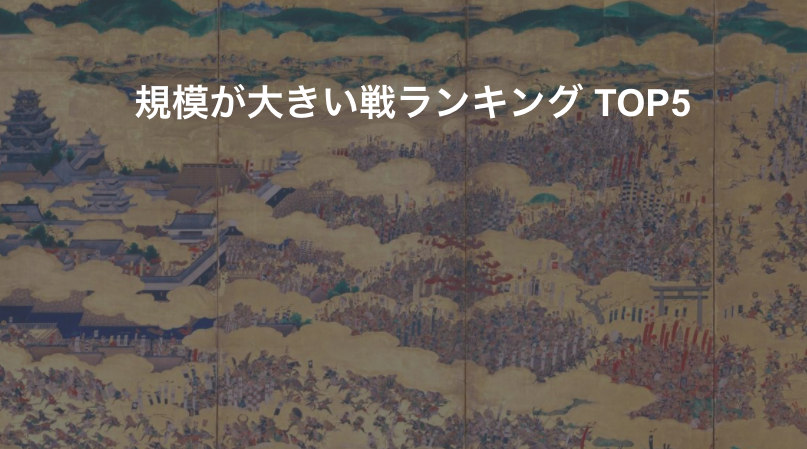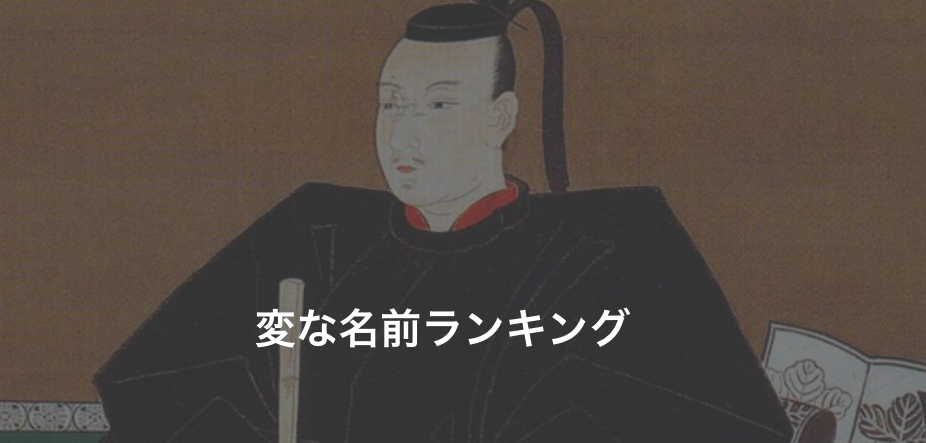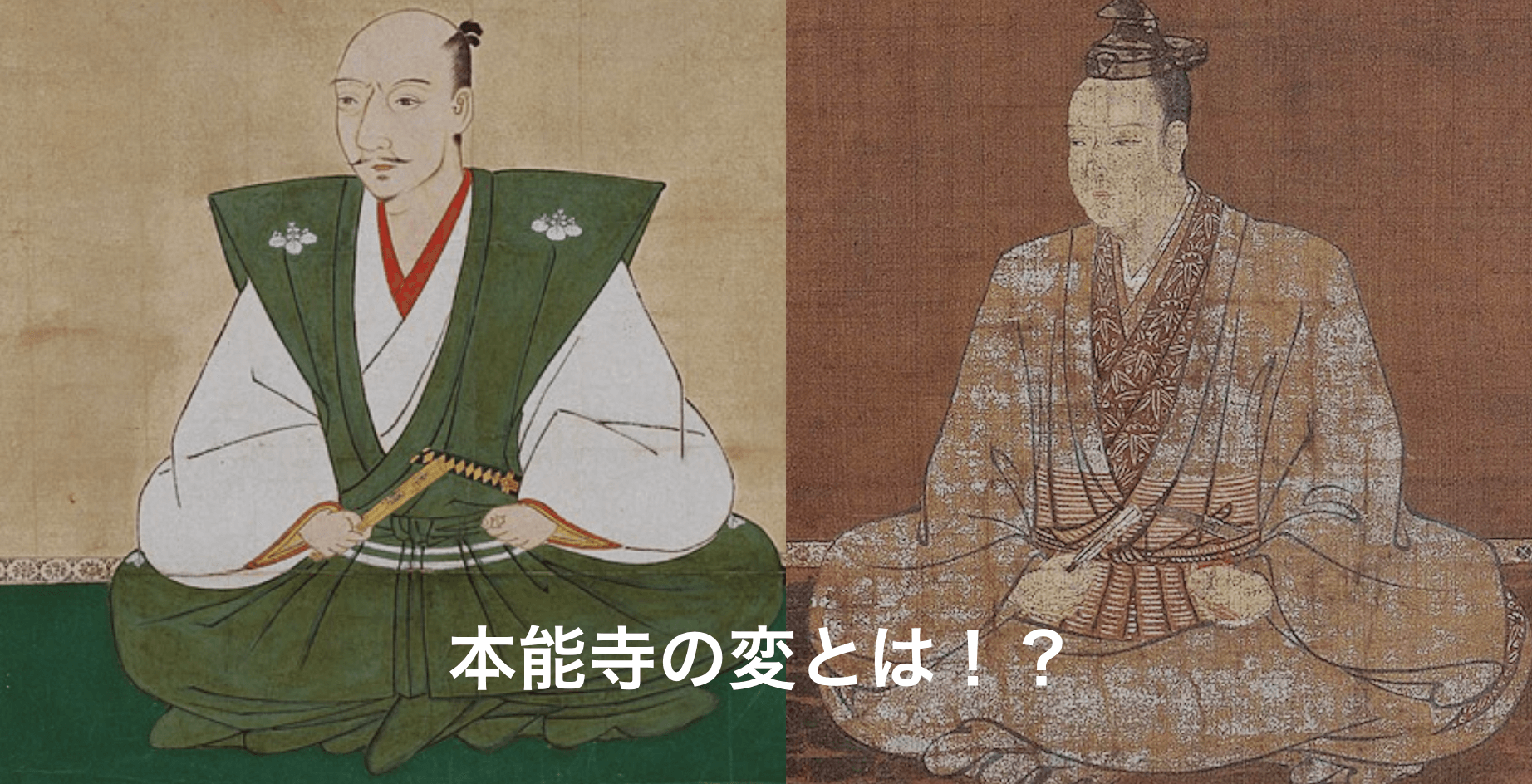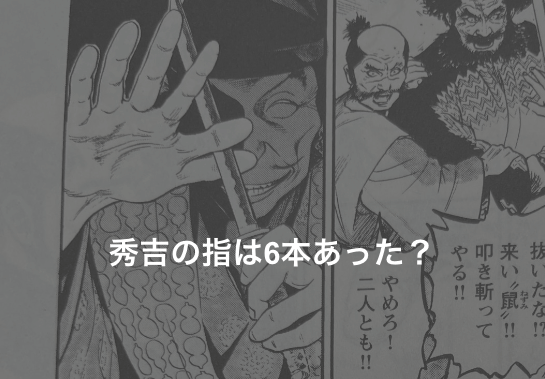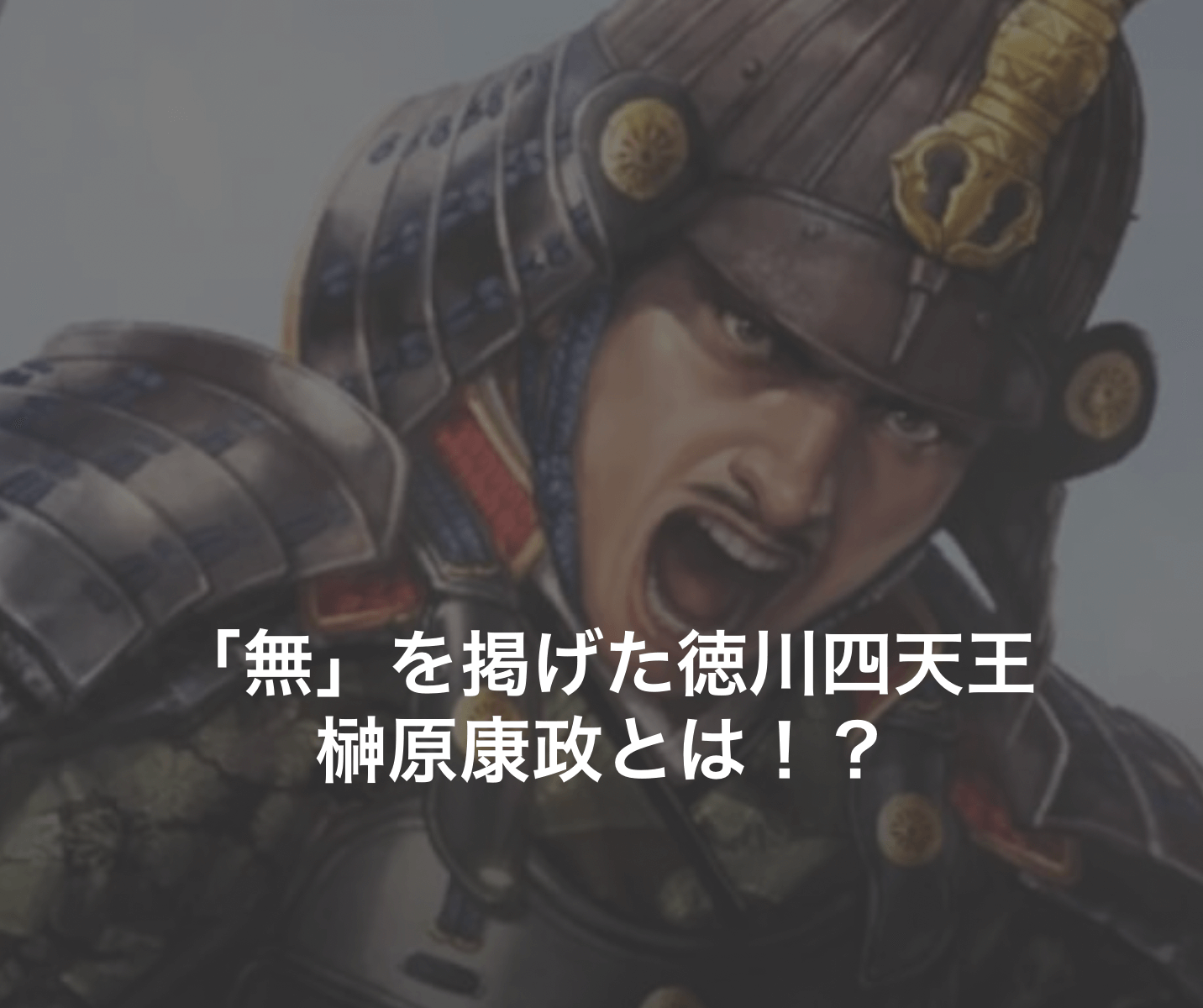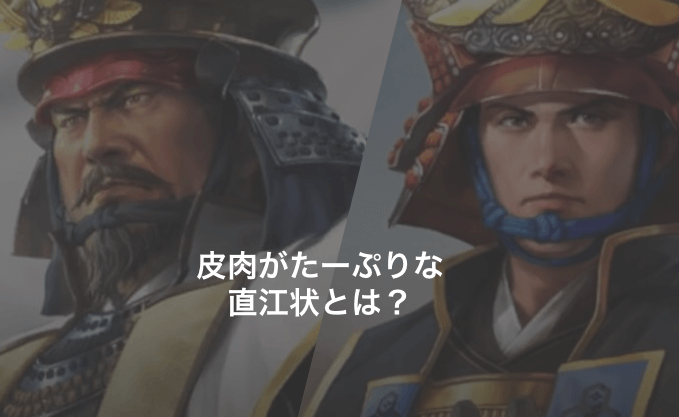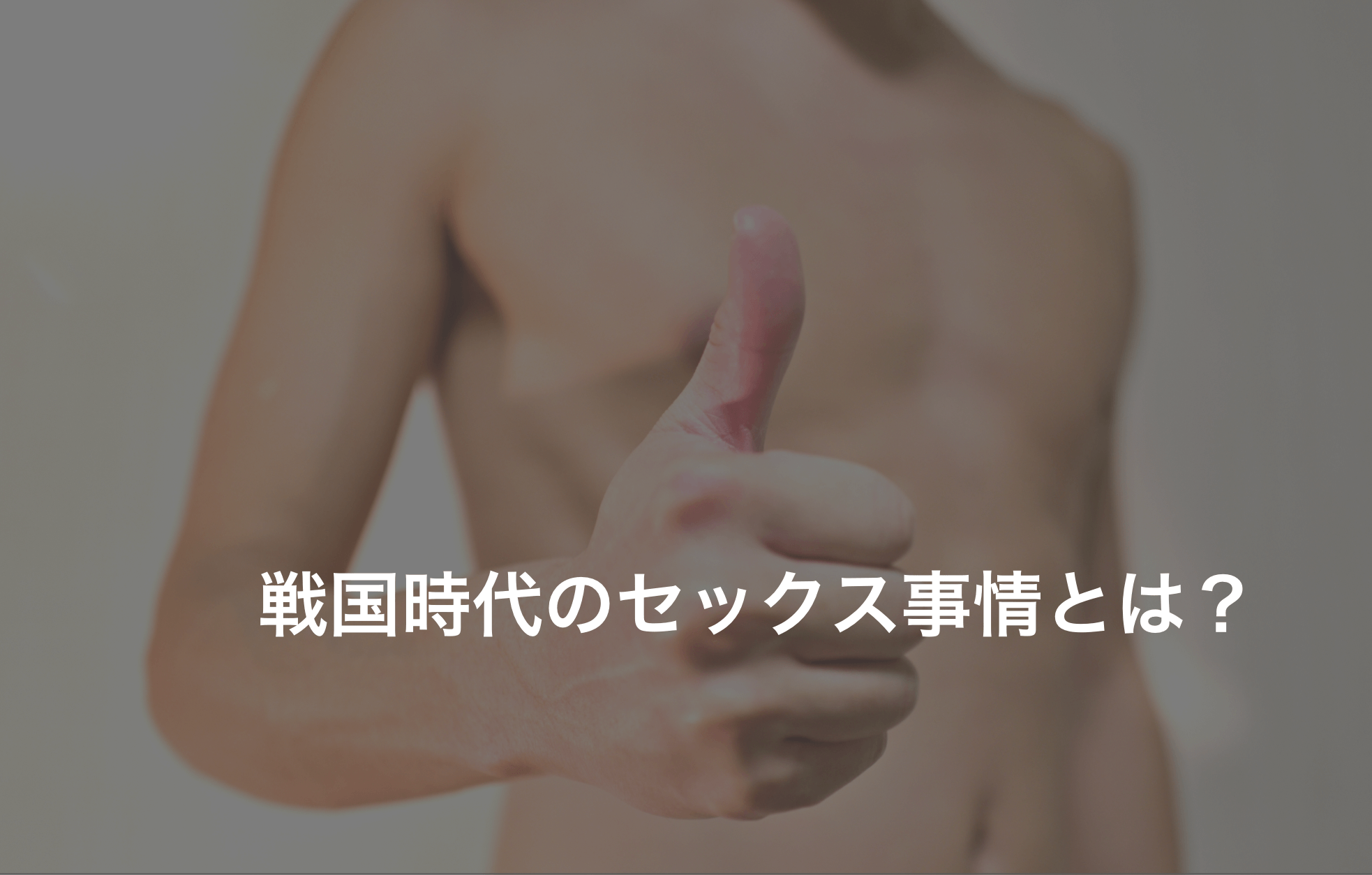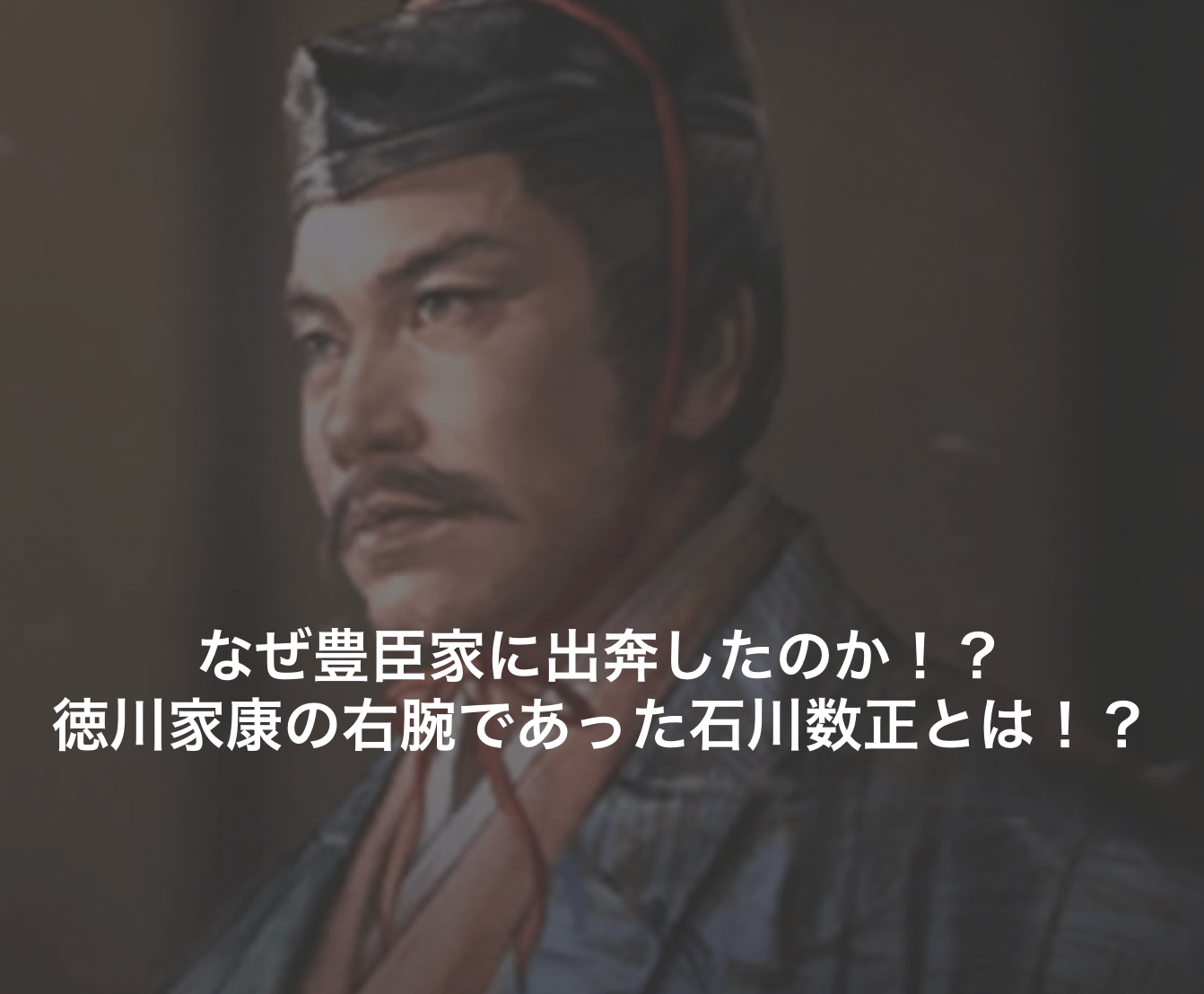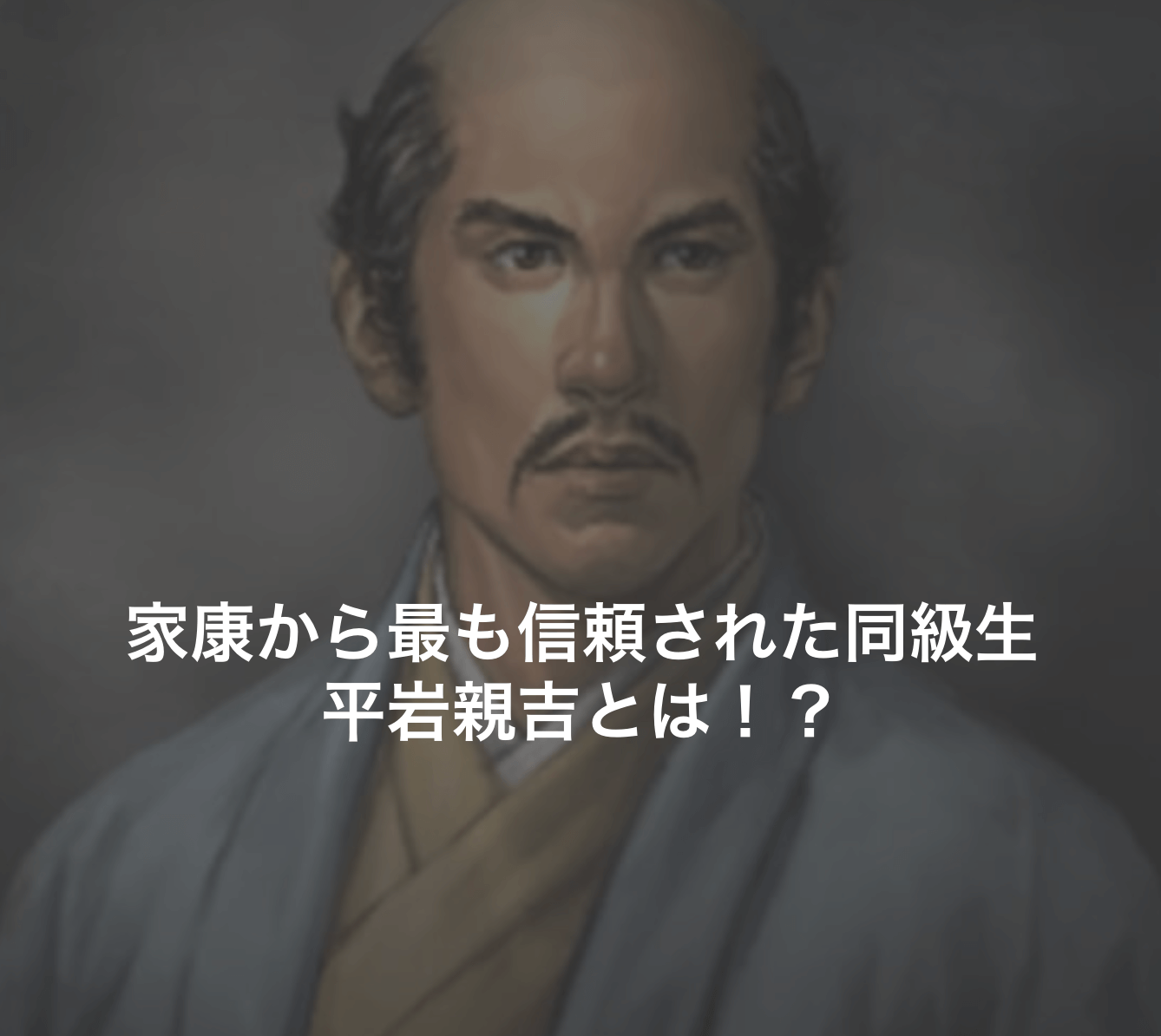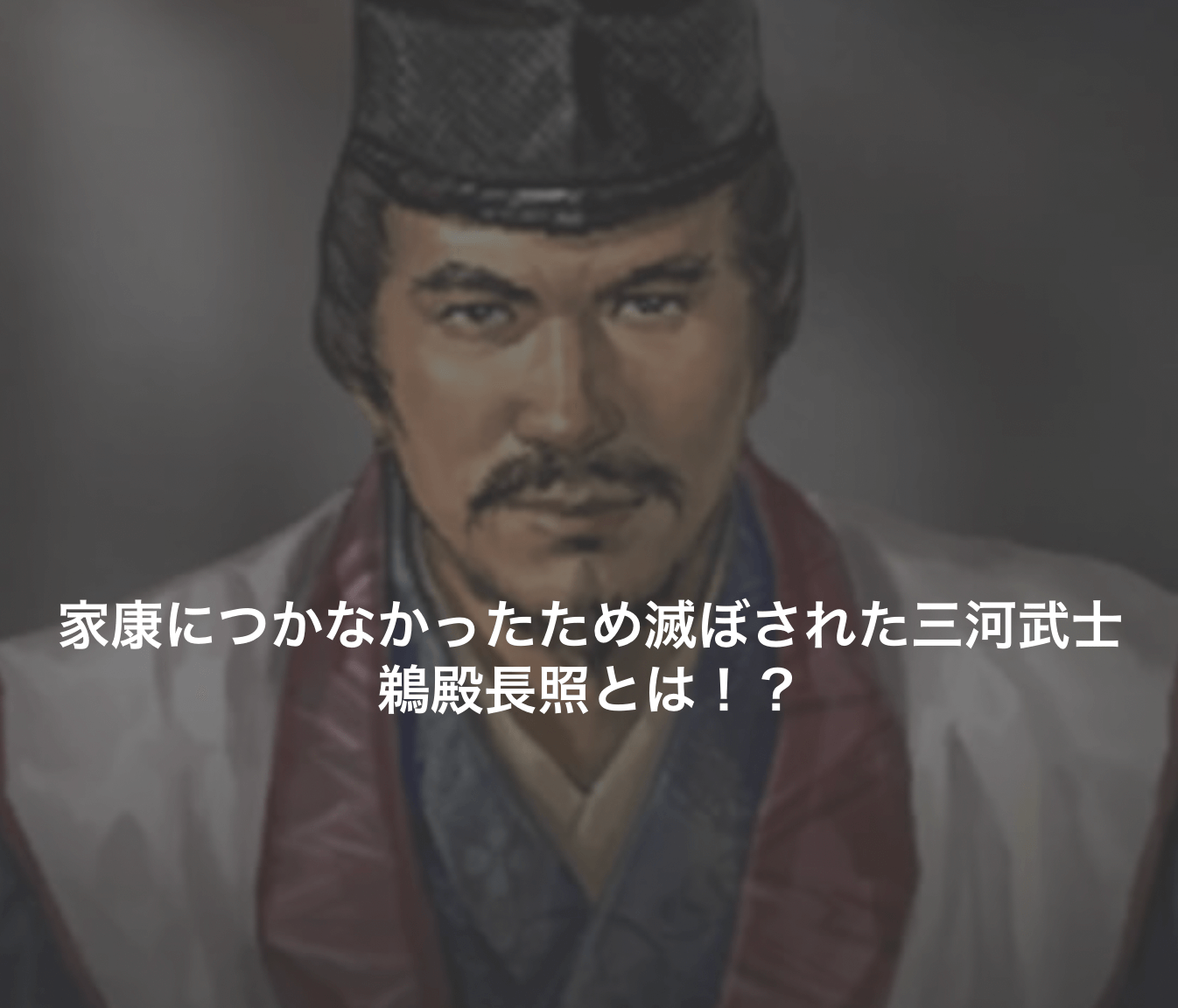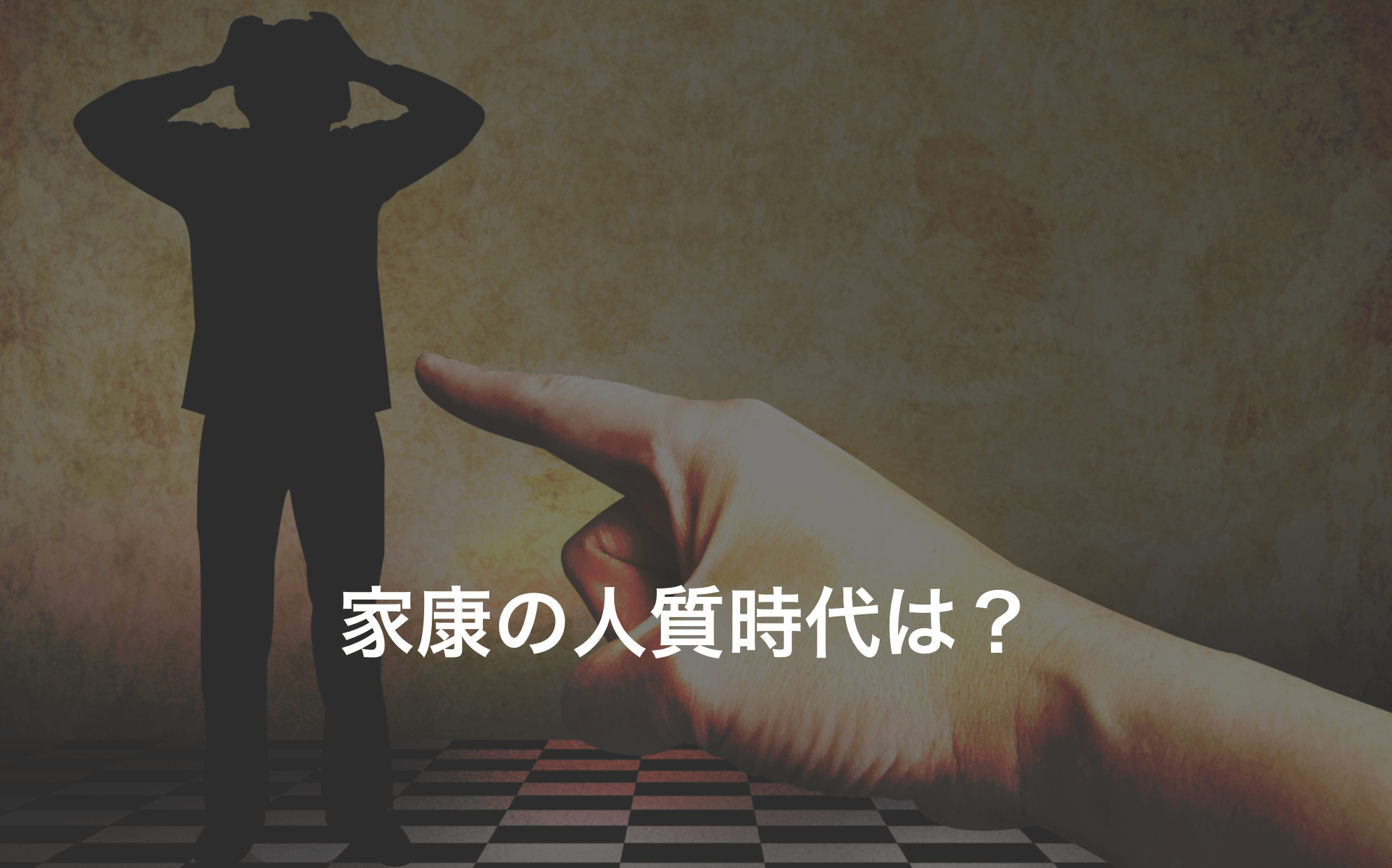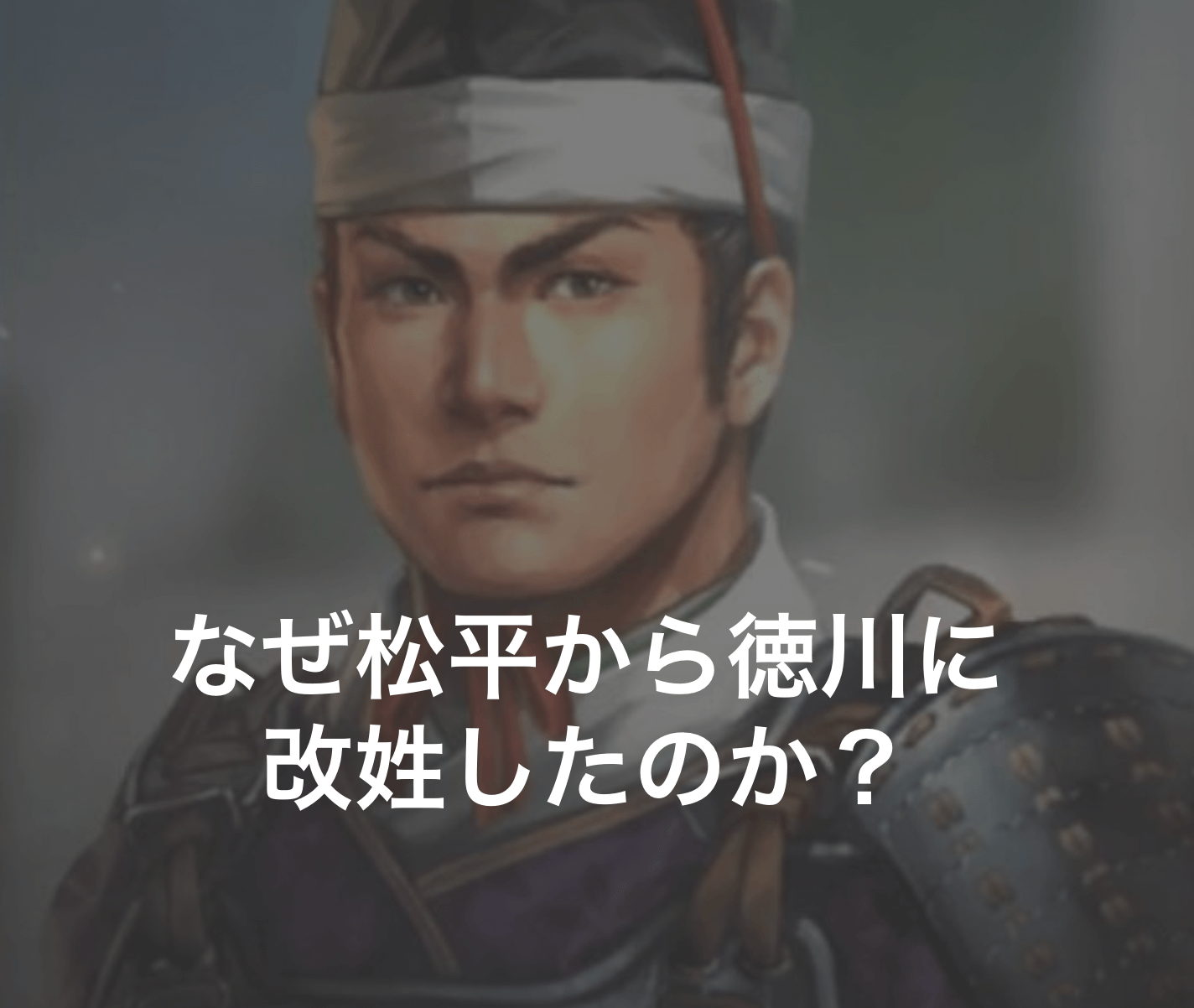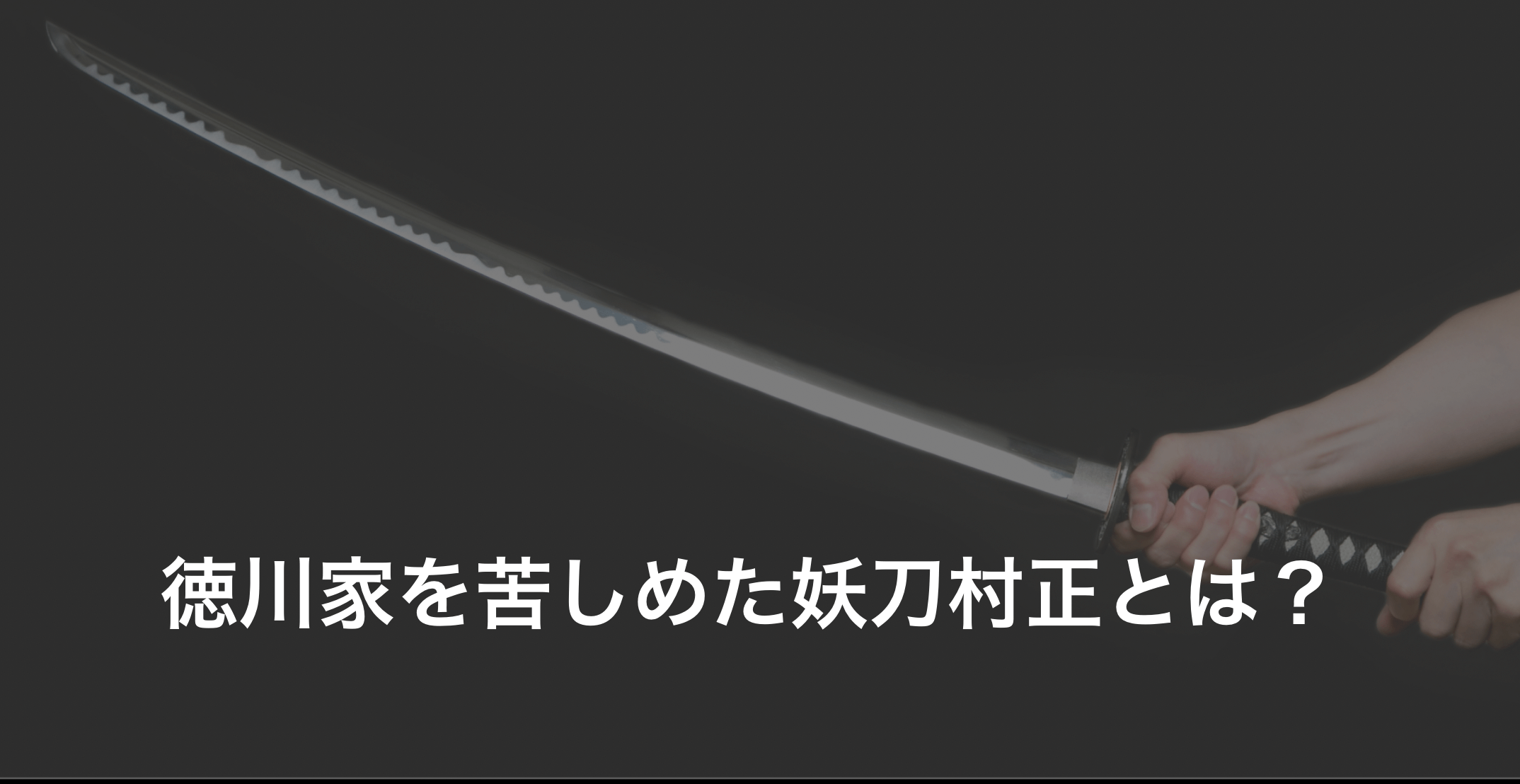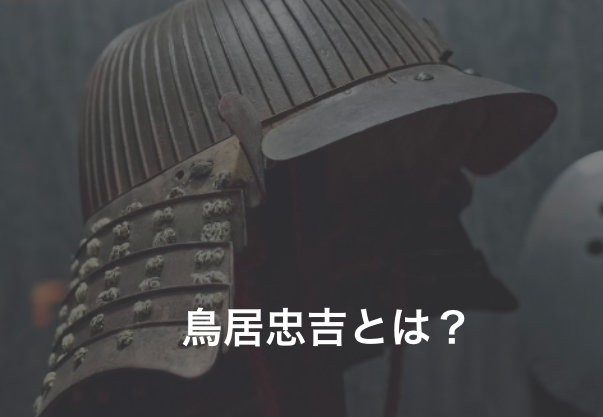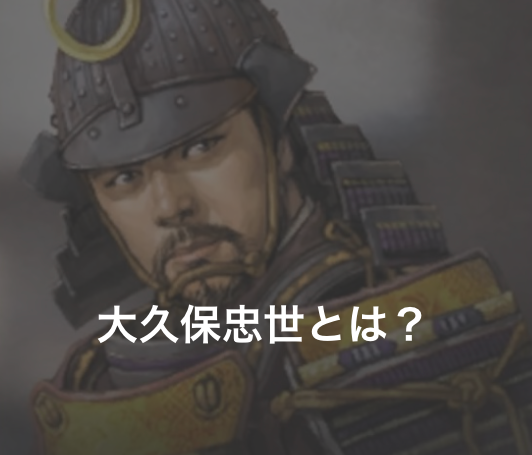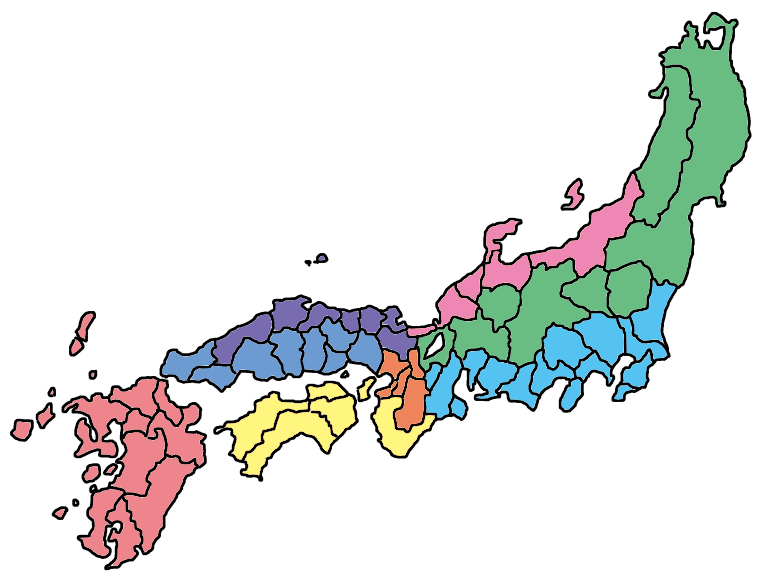views : 26052
戦国武将のかっこいい異名・あだ名ランキングTOP10

こんにちは、歴史大好き管理人のtakaです。
武勇の誉れが高い、または国政に辣腕を振るったため世の人々から異名・あだ名をつけられる戦国武将がいました。
当時実際呼ばれていたかは不明で、ほとんどが後世になって付けられたものですが、それにしても武将の個性を言い得ています。
今回はたくさんある異名・あだ名の中で特にかっこいい異名・あだ名を厳選しランキングにしました。
それではみていきましょう!!!
目次[非表示]
第10位「沈勇の士」

第10位は「沈勇の士(ちんゆうのし)」こと加藤嘉明(かとうよしあきら)です。
豊臣家臣。賤ヶ岳七本槍の1人。「沈勇の士」と評された。豊臣水軍の主力として各地の合戦で活躍。関ヶ原合戦では東軍に属し、伊予松山20万石を領した。
加藤嘉明は、秀吉子飼いの武将で、賤ヶ岳の戦いで武功を挙げ賤ヶ岳七本槍の1人です。
彼は「沈勇の士」と呼ばれています。
沈勇とは、落ち着いていて勇気のあることです。
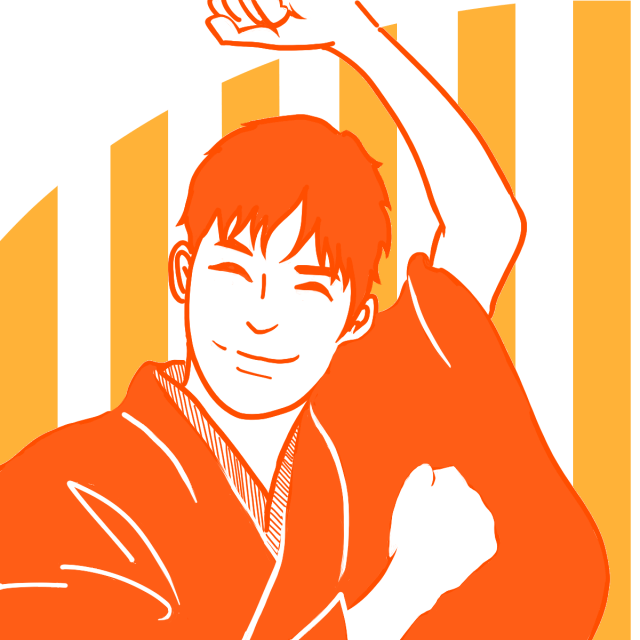
taka
加藤嘉明は日常や戦場で冷静沈着だったんですね。
彼の家臣に対する寛大なエピソードを一つ。
加藤嘉明は南蛮渡来の焼物を多く持っており、その中に虫喰南蛮という小皿10枚の秘蔵の逸品がありました。
ある日、客を饗応する準備の最中に、嘉明の近習が誤って1枚を割ってしまった。
それを聞いた嘉明は、近習を叱るどころか、残り9枚の小皿をことごとく打ち砕いた。
嘉明は「9枚残りあるうちは、1枚誰が粗相したかといつまでも士の名を残す。家人は我が四肢であり、如何に逸品であろうとも家来には代えられぬ。およそ着物・草木・鳥類を愛でる者はそのためにかえって家人を失う。主たる者の心得るべきことである」と述べています。
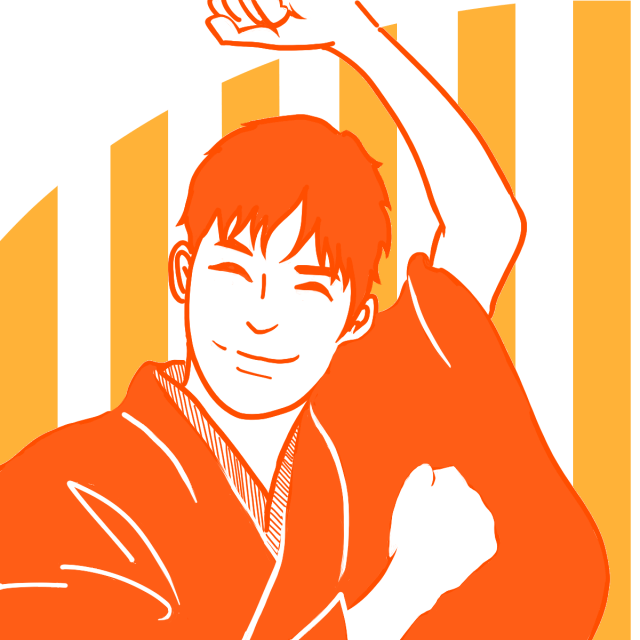
taka
寛大な心で家臣を許したんですね。これは慕われますね。
第9位「丹波の赤鬼」

第9位は「丹波の赤鬼(たんばのあかおに)」こと赤井直正(あかいなおまさ)です。
赤井直正はその武勇から近隣の豪族らから「丹波の赤鬼」と恐れられました。
名前に「赤」の字があり、赤い兜を鎧をまとっていたため、赤鬼なのでしょう。
丹波(兵庫県北部)にいる直正の名声は東国にも及び、甲斐(山梨県)の武田氏が記した軍学書『甲陽軍鑑』では4大将(北条氏康・武田信玄・上杉謙信・織田信長)に次ぐ「名高き大将衆」13人の筆頭に「丹波ノ赤井悪右衛門」として挙げられています。
ちなみに「名高き大将衆」13人は以下です。
- 丹波・赤井悪右衛門(赤井直正)
- 四国土佐・長宗我部(元親)
- 同伊予・来島(村上通康)
- 安芸毛利家・吉川(元春)
- 越前・朝倉叔父金吾(朝倉宗滴)
- 安芸・小早川(隆景)
- 江州北ノ郡・浅井備前(長政)
- 三好家・松永弾正(久秀)
- 徳川家康
- 安房里見家・柾木大膳(正木時茂)
- 上杉家・大田三楽(太田資正)
- 会津・(蘆名)盛氏
- 上総・万喜少弼(土岐為頼)
第8位「黒衣の宰相」
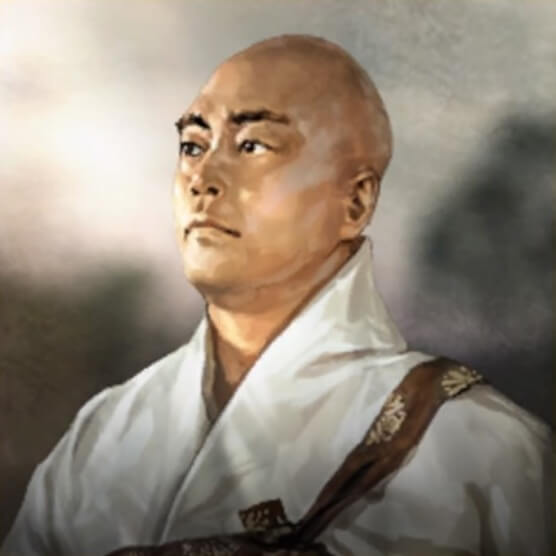
第8位は「黒衣の宰相(こくいのさいしょう)」こと以心崇伝(いしんすうでん)です。
金地院崇伝(こんちいん すうでん)とも呼ばれる。
徳川家臣。武家諸法度などの法令制定を担当する。方広寺鐘銘事件を引き起こして大坂の陣の口実を作るなど調略面でも活躍し「黒衣の宰相」の異名をとった。
徳川家康のもとで江戸幕府の法律の立案・外交・宗教統制を一手に引き受け、江戸時代の礎を作ったとされます。
僧職にありながら政治に参与し、大きな勢力を持っていました。
慶長19年(1614年)、大坂の陣の発端になった方広寺の鐘銘事件にも関与し、「国家安康」「君臣豊楽」で家康を呪い豊臣家の繁栄を願う謀略が隠されていると難癖を付けたのは崇伝とされています。
ちなみに安国寺恵瓊・南光坊天海や太原雪斎などの敏腕坊さんも「黒衣の宰相」と呼ばれたようです。
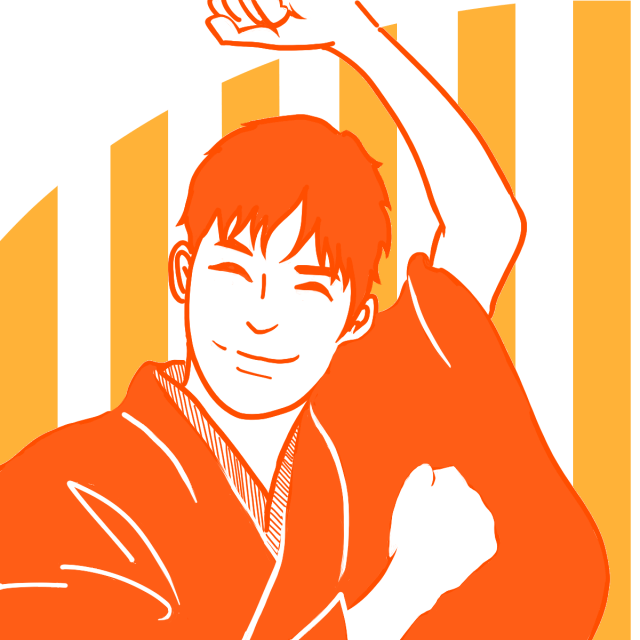
taka
「黒衣」っていうのが中二心をくすぐりますね。
第7位「越後の龍」

第7位は「越後の龍(えちごのりゅう)」こと上杉謙信(うえすぎけんしん)です。
越後とは、現在の佐渡島を除く新潟県全域にあたります。
この地方一帯を治めて戦の天才と呼ばれる程、戦に精通していた為に畏怖の念を込めて「軍神」とも呼ばれます。
自ら「毘沙門天(びしゃもんてん)の化身」と称し、彼の家臣に対しても自分を毘沙門天だと思うように常々言い聞かせていました。
毘沙門天は戦の神で、「毘沙門天の化身」ということで自分を鼓舞し、民衆を統率していたと思われます。
第6位「八咫烏」

第6位は「八咫烏(やたがらす)」こと鈴木重秀(すずきしげひで)です。
八咫烏とは、日本神話に登場するカラスであり導きの神。三本足が特徴。
鈴木重秀の雑賀衆は、旗印に「八咫烏」を掲げていました。
雑賀衆とは、雑賀孫一の率いる、銃の名手を集めた戦国最強と言われる部隊。
現在の和歌山県紀ノ川下流域を本拠地とします。
どの大名にも対等に接し、どの国にも属することがありません。
頭領は背中に八咫烏が染めてある赤い羽織をまといます。
第5位「甲斐の虎」

第5位は「甲斐の虎(かいのとら)」こと武田信玄(たけだしんげん)です。
甲斐は現在の山梨県で、この甲斐に勢力を広げているのが武田氏です。
「風林火山」の戦い方のもと当時最強と呼ばれた武田の騎馬隊。それを指揮していたのが武田家当主・武田信玄でした。
ルイス・フロイスの『日本史』によると、武田信玄は「織田信長がもっとも煩わされ、常に恐れていた敵の1人」だったと書かれています。
第4位「麒麟児」

第4位は「麒麟児(きりんじ)」こと明智光秀(あけちみつひで)です。
織田家臣。優れた才知と教養により重用されるが、突如謀叛を起こし信長を本能寺に討つ。しかし事後調略に失敗し、山崎合戦で敗れ逃亡中に殺された。
麒麟は、中国古代の想像上の聖獣で、竜、鳳凰、亀とともに四霊獣の一つとされています。
王が仁のある政治(善い政治)を行う際に、麒麟は必ず頭上に現れると言われています。
戦国の乱世を終わらせ太平の世を導くのは誰だったのでしょうか。
明智光秀が主人公である2020年大河ドラマの名前は「麒麟がくる」でしたね。
また麒麟児とは、才能が優れていて、将来が期待される少年のことをいう。
織田家のNo.1家老の明智光秀は正に「麒麟児」と呼ぶのにふさわしいでしょう。
第3位「独眼竜」

第3位は「独眼竜(どくがんりゅう)」こと伊達政宗(だてまさむね)です。
伊達家17代当主。輝宗の嫡男。瞬く間に周辺諸国を切り従えて24歳で奥州に覇を唱え「独眼竜」と畏怖された。権謀術数で豊臣・徳川両政権を生き抜いた。
「独眼竜」とは、隻眼(片目)の英傑に対して与えられることがある異称です。
伊達政宗は、幼少の頃病気(天然痘といわれる)で片目の視力を失い、隻眼になりました。
また伊達家には騎馬鉄砲隊の「竜騎兵」がいましたね。
第2位「雷神」

第2位は「雷神(らいじん)」こと立花道雪(たちばなどうせつ)です。
「鬼道雪」とも言う。
大友家臣。立花城西城督。落雷で歩行不能となるが、輿に乗って常に大友軍の先陣を切り「鬼道雪」の異名をとった。生涯を軍陣で過ごした、家中随一の猛将。
立花道雪は、若い頃に落雷を受けた影響で、下半身不随でした。
通常であれば馬に乗れないため出陣できませんが、道雪は家臣に輿を担がせて戦場に立ち、鉄砲と刀を手に指揮を執りました。
これが強いこと強いこと。
豊後(福岡県)にいた彼は、毛利氏の九州進出を幾度も防いでいます。
落雷を受けた際、愛刀「千鳥」を振りかざして雷を一刀両断して一命を取り留めたとされ、その後は雷神の化身として愛刀を「雷切丸(らいきりまる)」に改名して戦場に持ち歩いたといわれています。
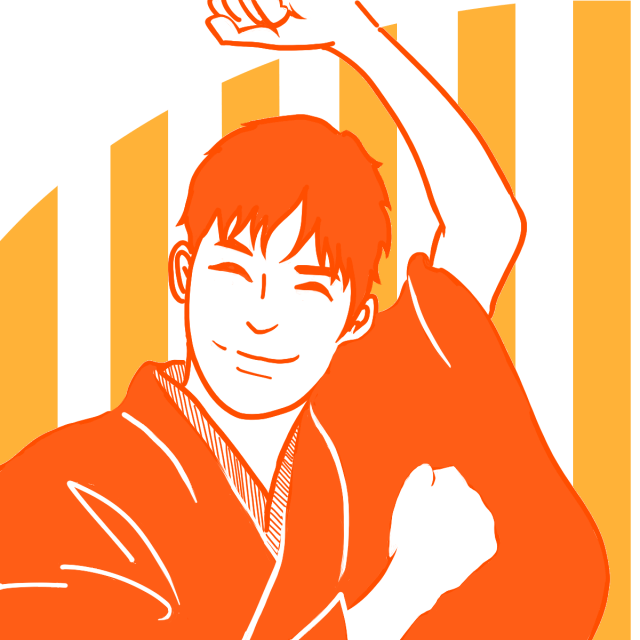
taka
「雷切丸」カッコ良すぎる。アニメに出てきそうだ。
第1位「第六天魔王」

第1位は「第六天魔王(だいろくてんまおう)」こと織田信長(おだのぶなが)です。
「第六天」とは、仏教の世界観において、人々が欲望に囚われて生きている、あさましい世界のことを指しています。
そして、そこに住む魔王「第六天魔王」が人々から仏教を信仰する心を奪い取り、人々を欲望に縛り付けている、とされています。
信長が「第六天魔王」を名乗ったのは、信玄が延暦寺を復興しようというのなら、自分は魔王となってそれを妨げてくれよう、と宣言するためでした。
まとめ
いかがでしたか?
漫画や映画に出てきそうなかっこいい異名・あだ名でしたね。
他にもたくさん異名・あだ名がついている武将がいます。
まとめるのでちょっと待ってください。
これからもランキング記事をアップしていくのでよろしくお願いします。