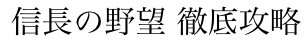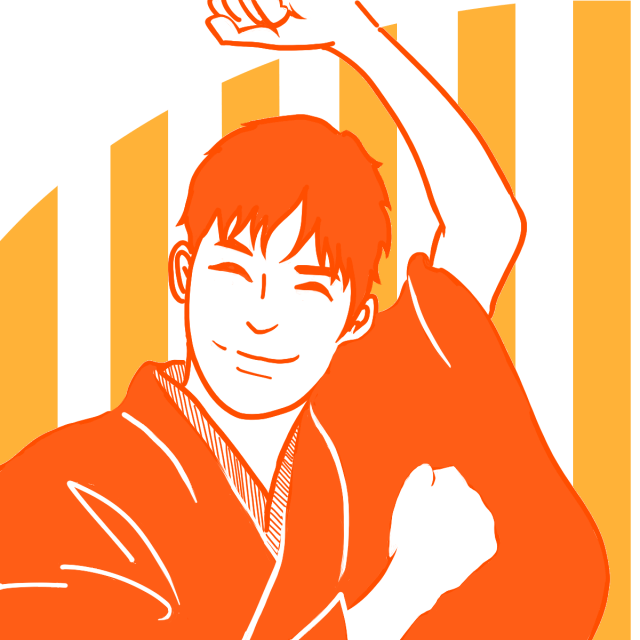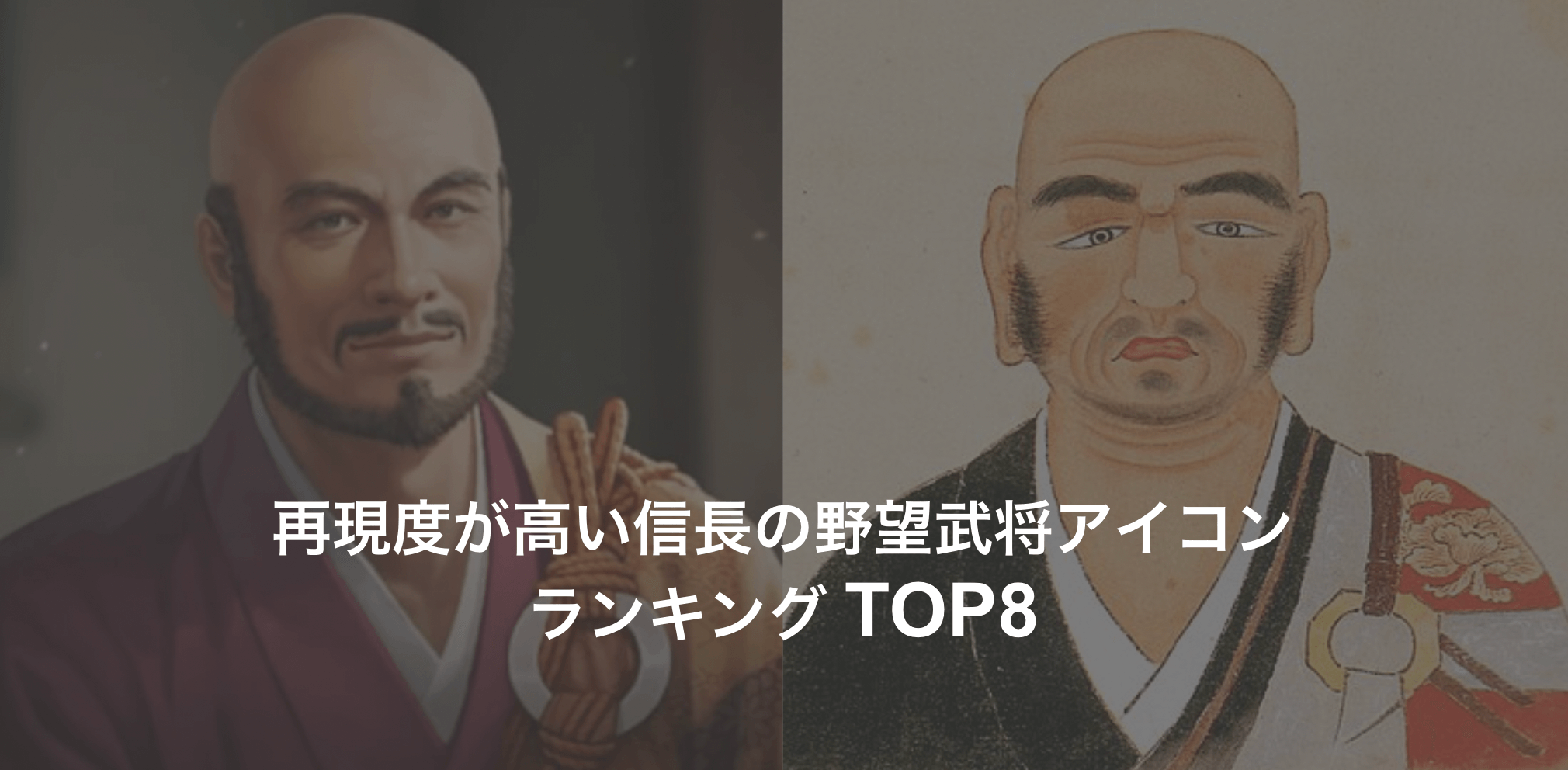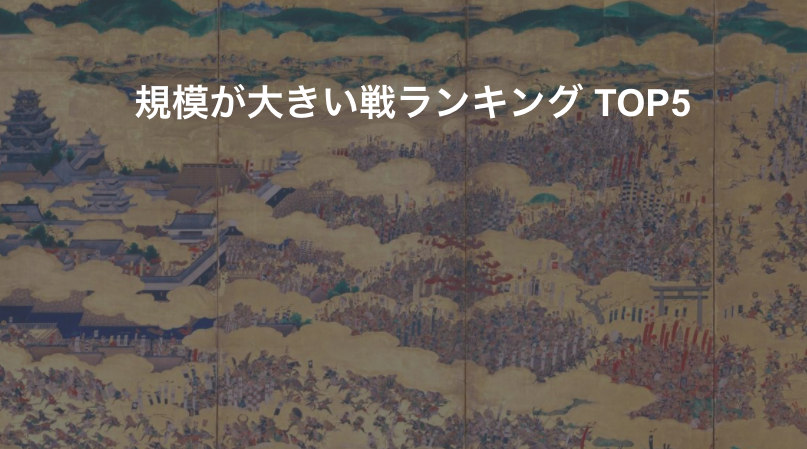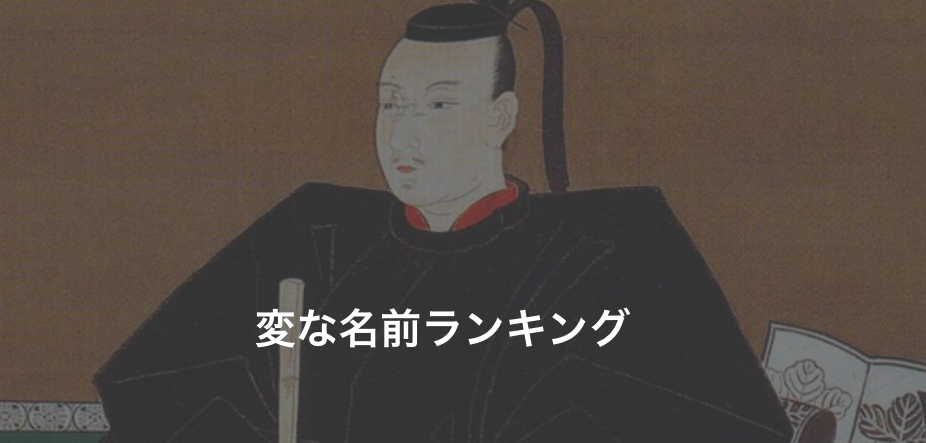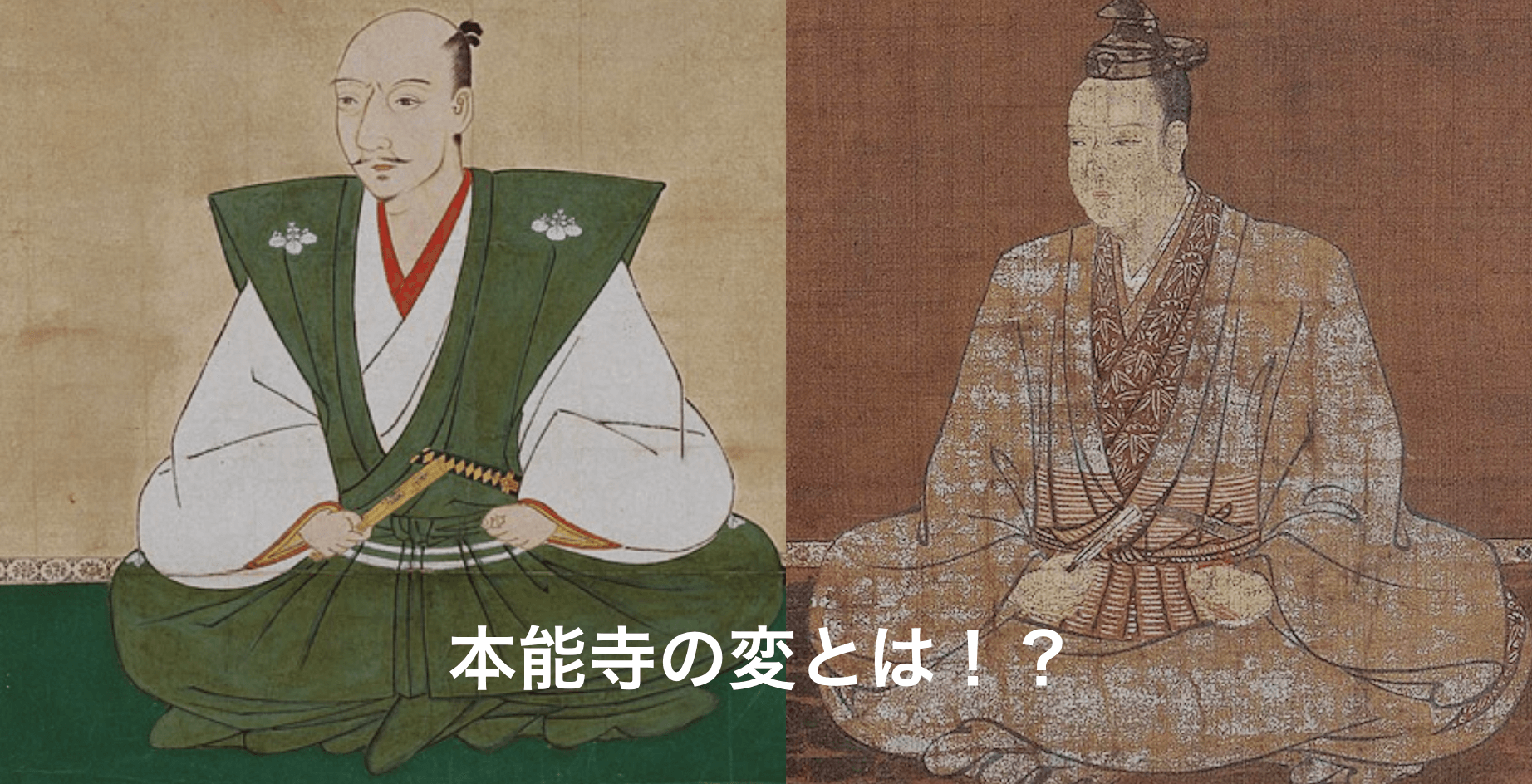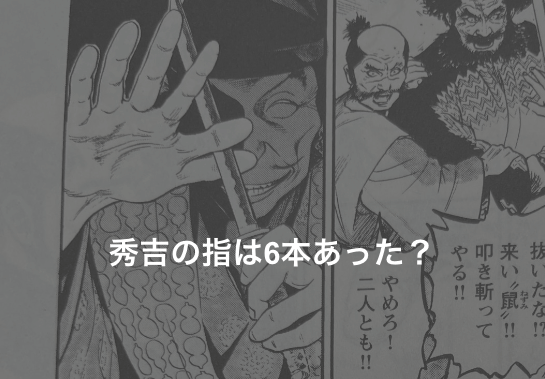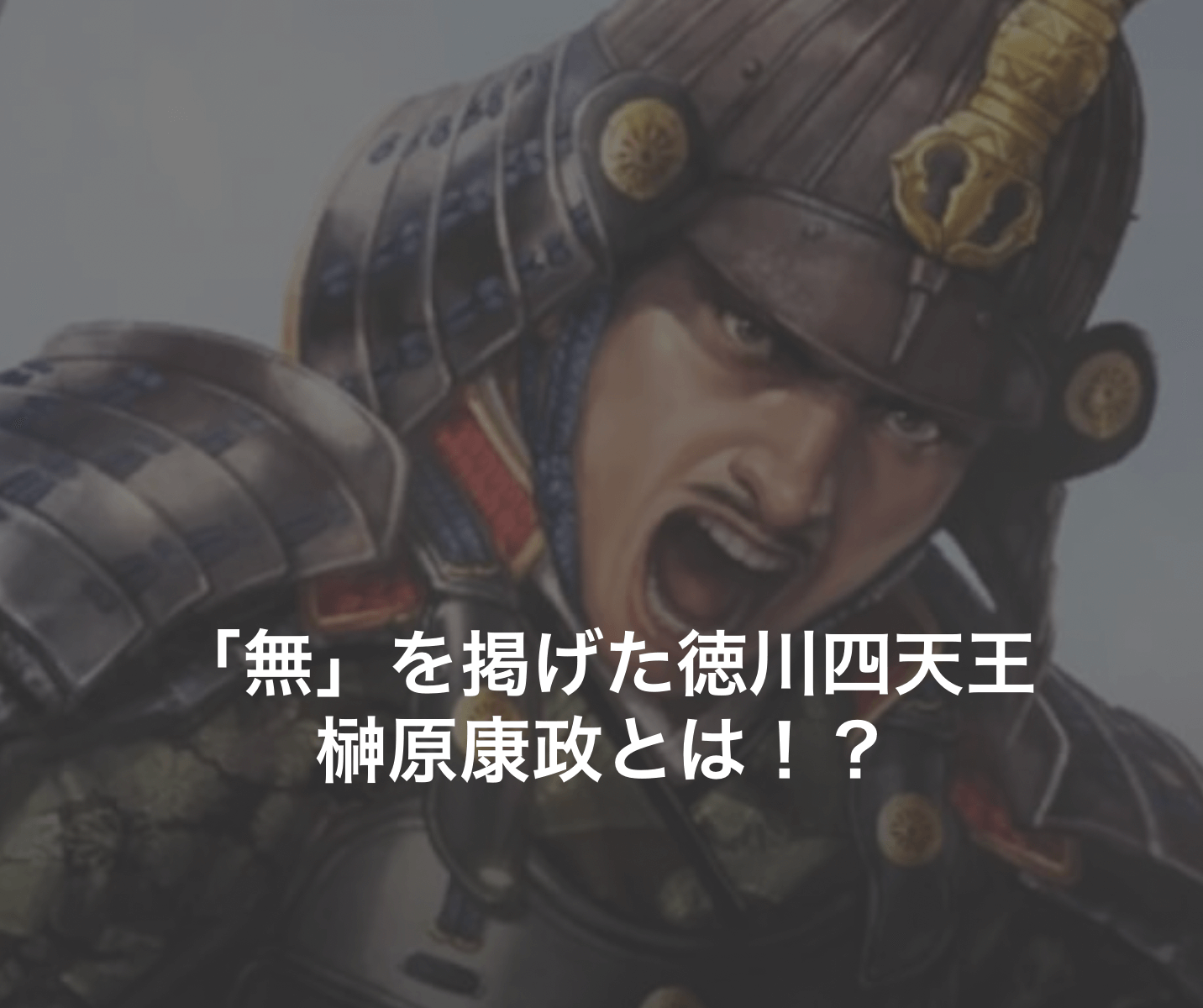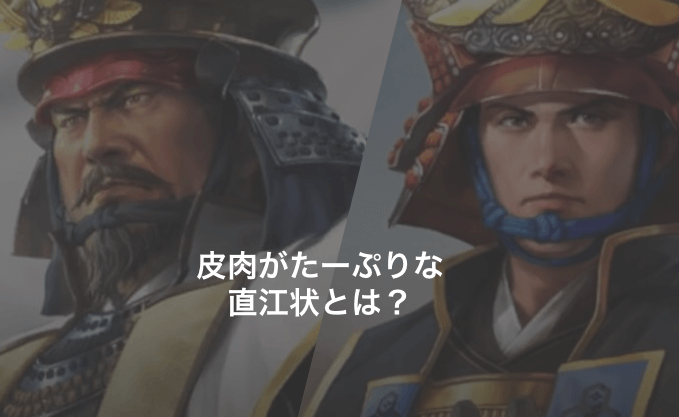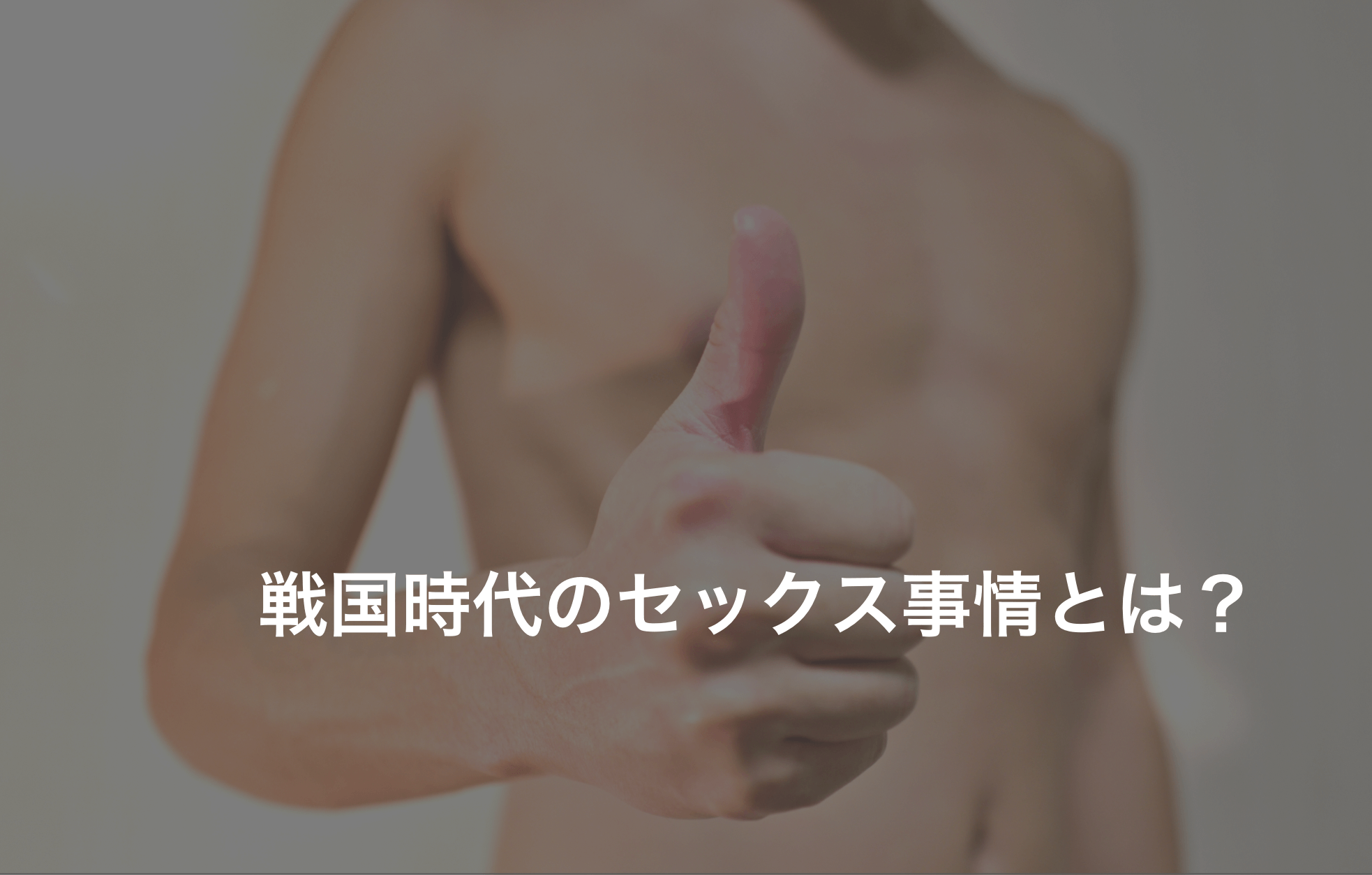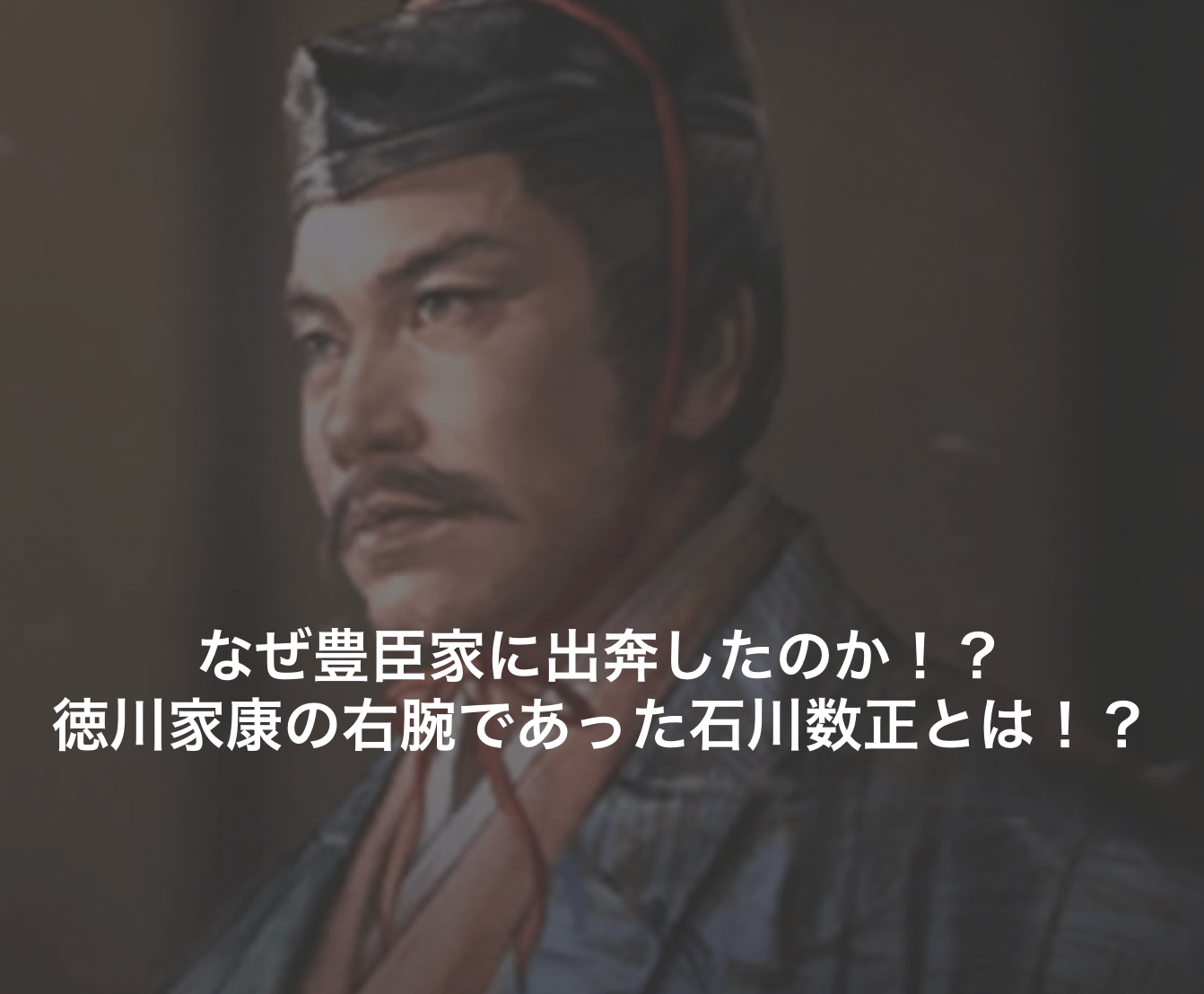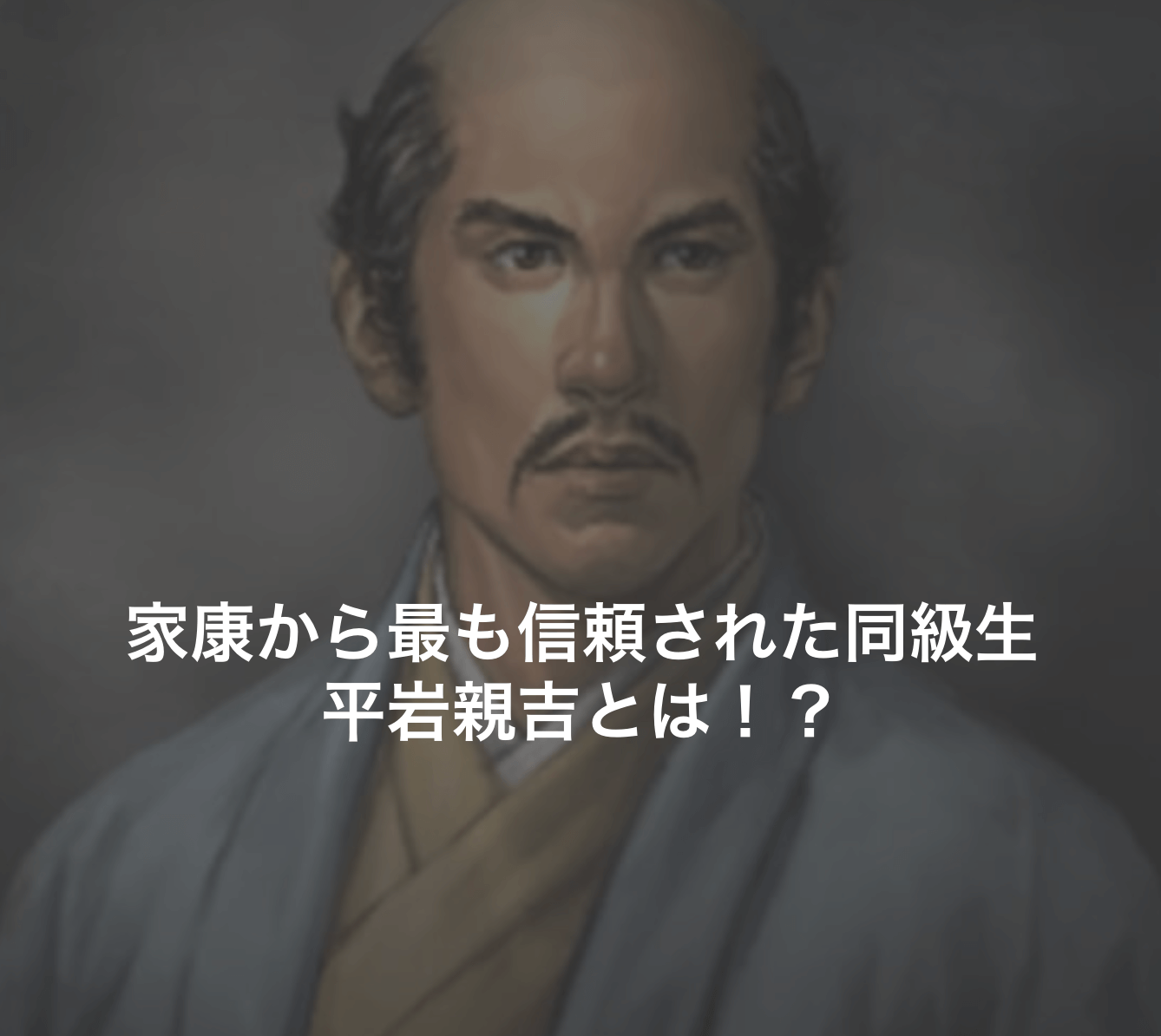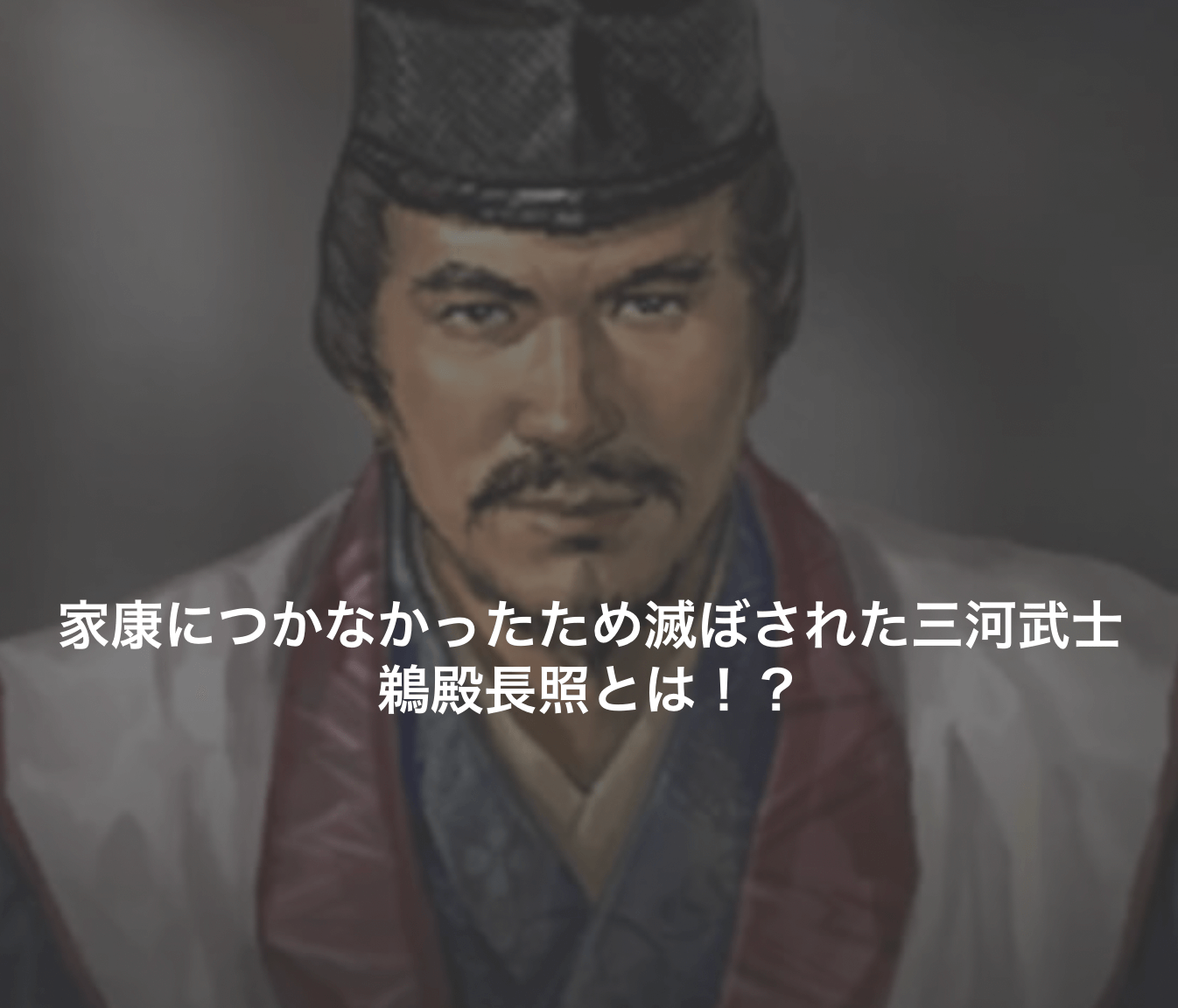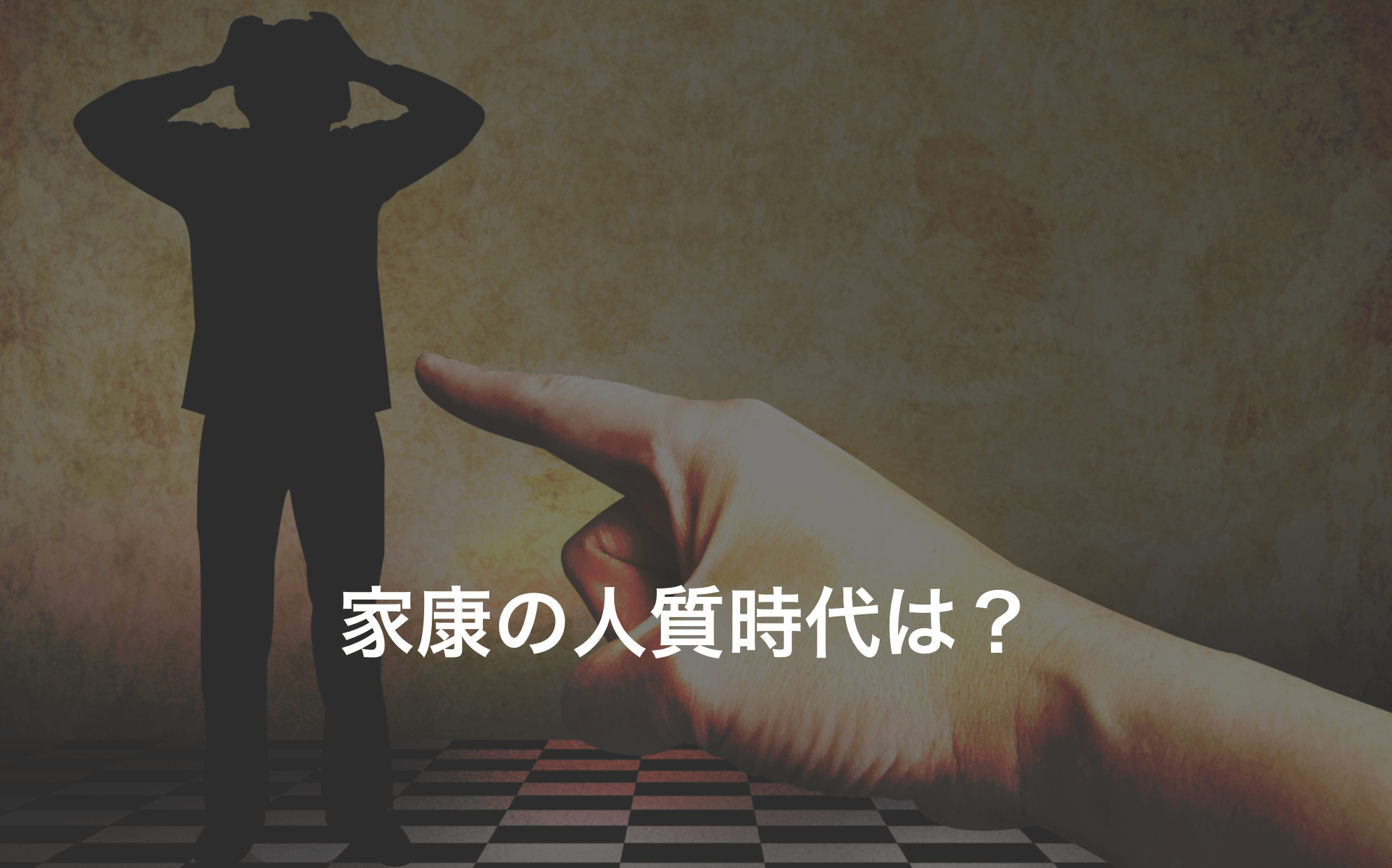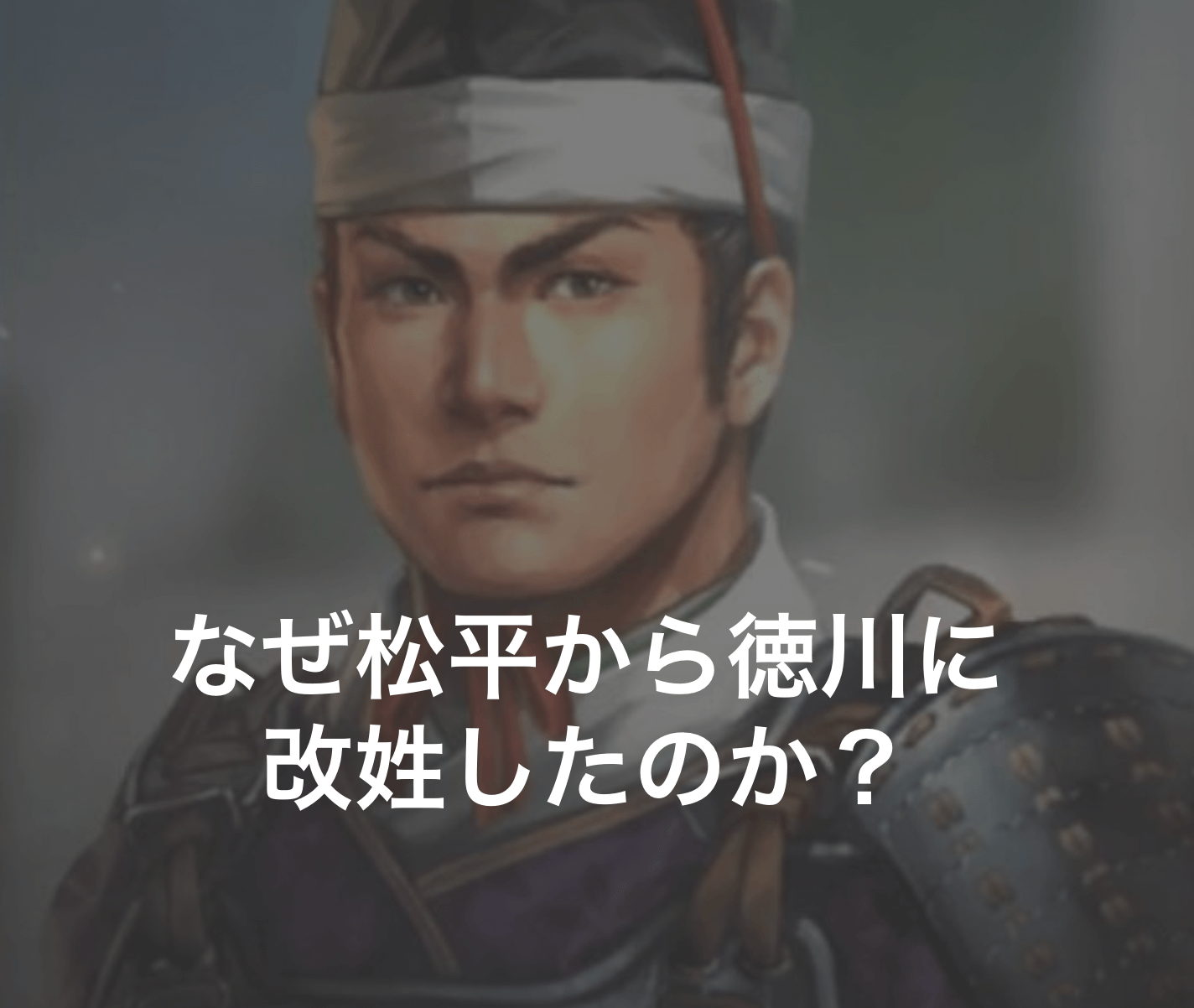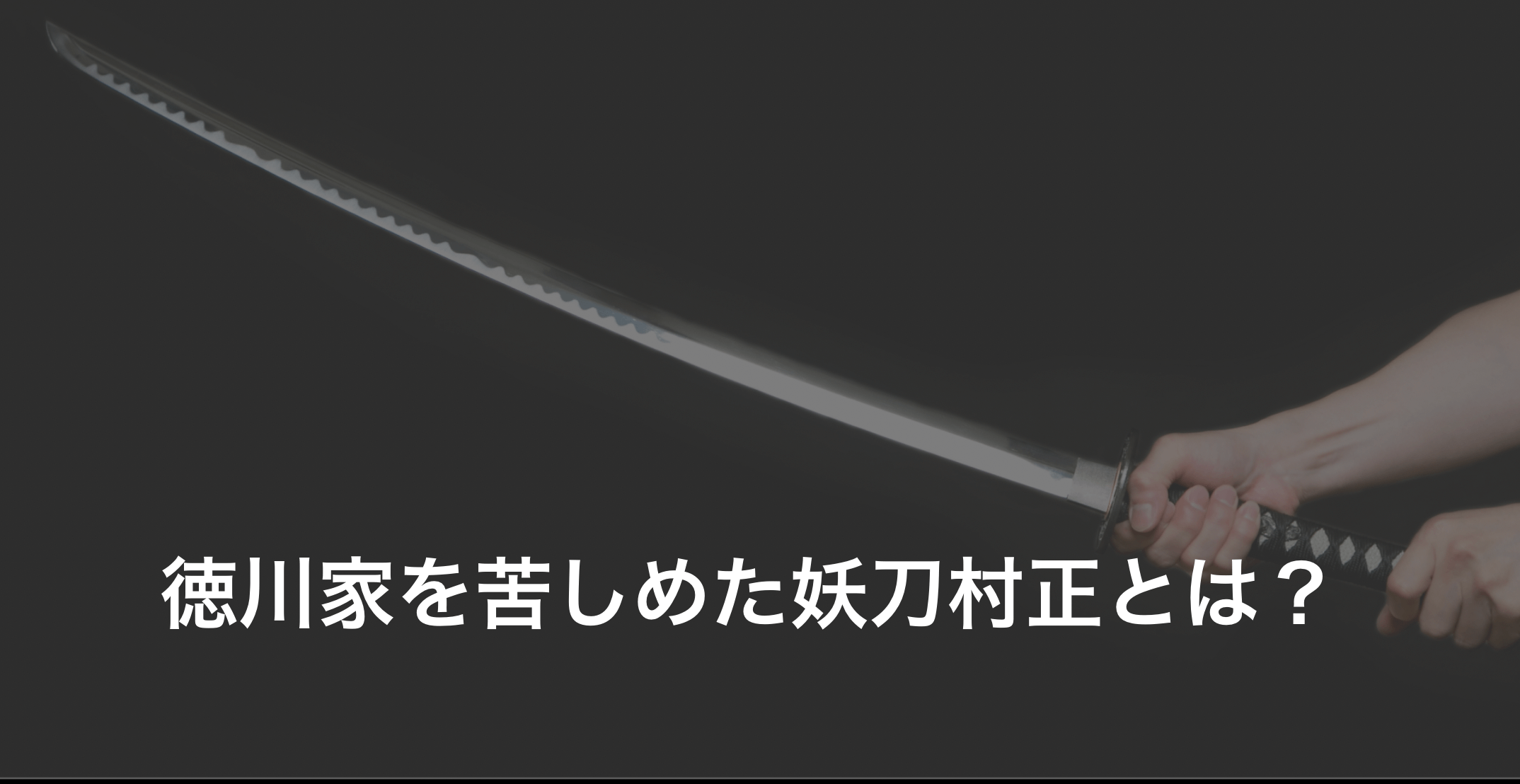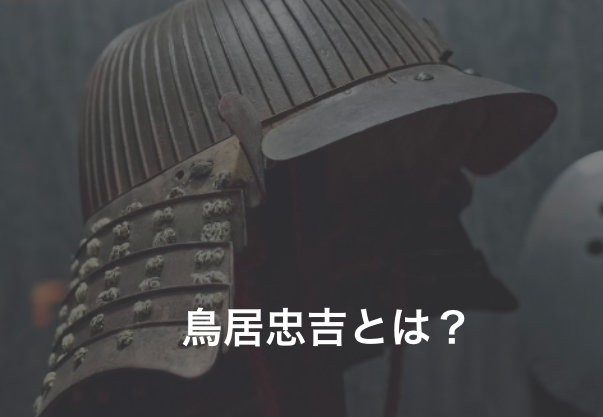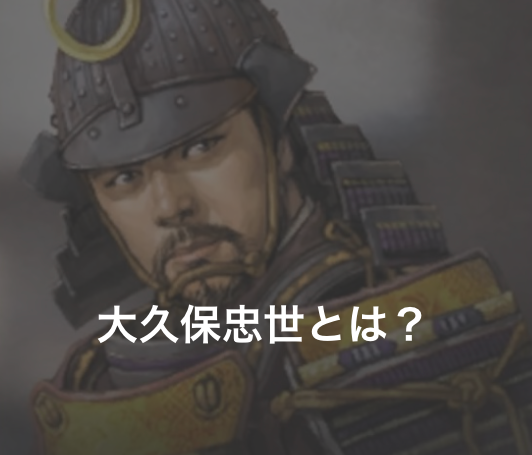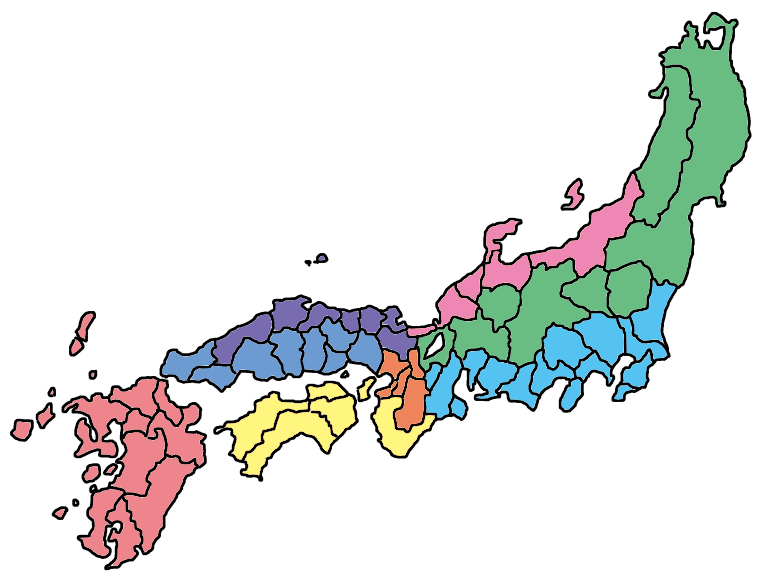views : 6911
障害が残るほどの苦悩、遺書を残し死を覚悟した懺悔など黒田官兵衛の大ピンチTOP3!!
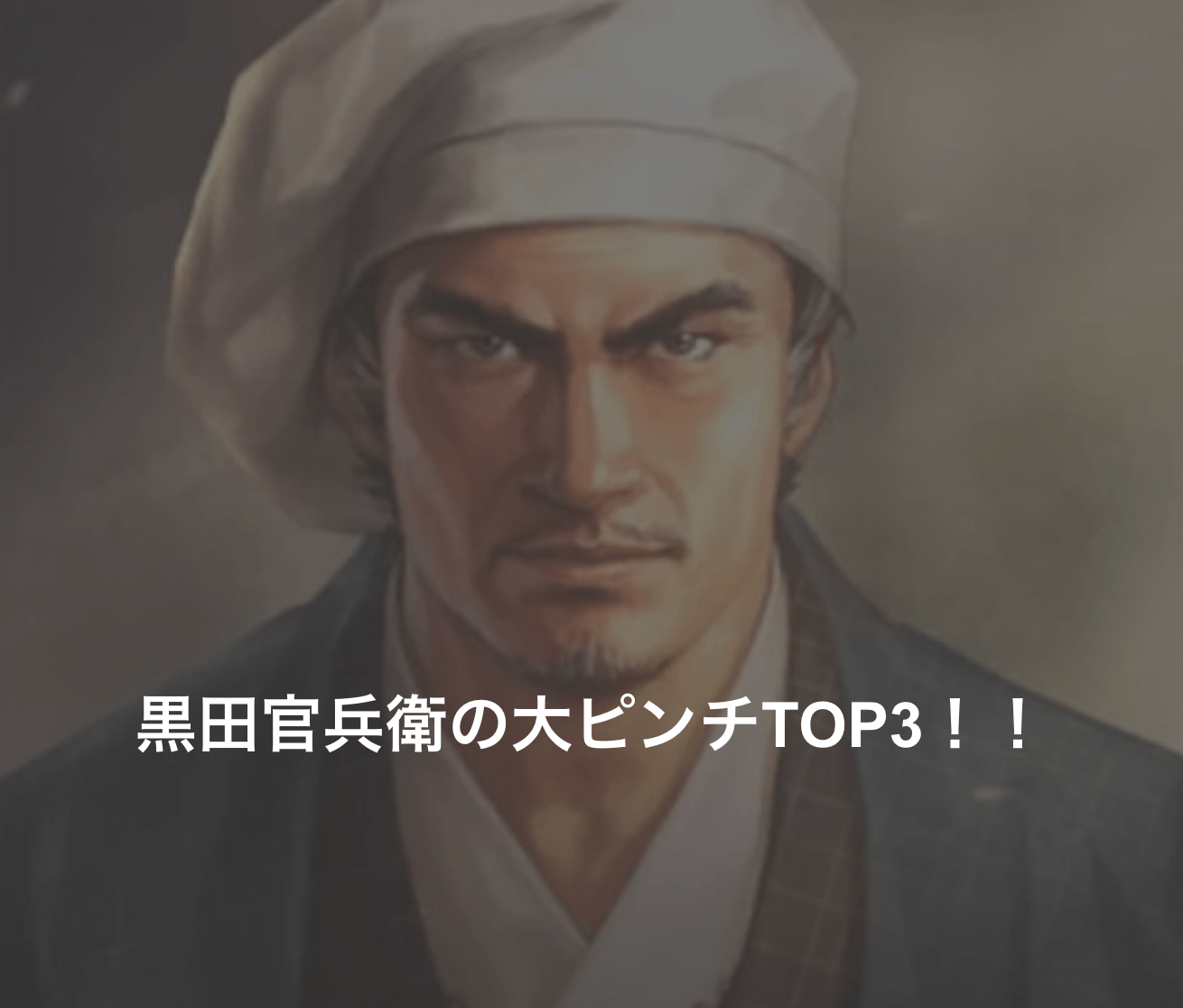
こんにちは、歴史大好き管理人のtakaです。
今回は稀代の軍師・黒田官兵衛が陥った3大ピンチをランキング形式で紹介します!
天才軍師と呼ばれた彼であっても失敗や命の危険があるピンチを経験しています。
平和な現代に暮らしている私たちの失敗なんてこれを見ると大したことがないということがわかると思います。
何個思い当たりますか?
それでは見ていきましょう!
目次[非表示]
第3位 : 秀吉の尻拭いで城井重房を謀殺
秀吉の九州平定の際、黒田官兵衛は秀吉の命により武力による衝突を最小限にするため事前に「味方になってくれたら本領を安堵する」と九州の諸大名・豪族に伝え調略工作をしていました。
この誘い文句に乗った大名の一人が城井鎮房です。
城井鎮房は豊前国の戦国大名で、天然の要害を誇る城井谷城の城主でした。
しかし九州平定後本領安堵のはずが、城井鎮房は紀伊国に転封を命じられ、城井鎮房の所領であった豊前国は黒田官兵衛の所領となりました。
気まずいムードになります。
さらに城井家の家宝である藤原定家の『小倉色紙』の引渡しも秀吉に命じられました。
 taka
takaこの処理に怒った城井鎮房は天正15年(1587年)10月に挙兵し、豊臣軍に明け渡していた元居城の城井谷城を急襲し奪取します。
寡兵だが地の利のある城井鎮房はゲリラ作戦をとり、攻撃してきた黒田長政が率いる豊臣軍を撃退します(岩丸山の戦い)。
このとき長政は死を覚悟し自刃しそうなほど追い詰められました。
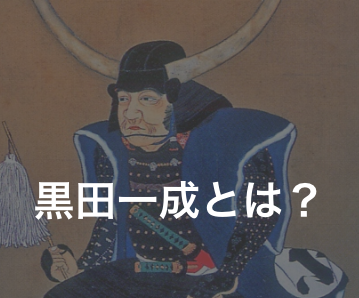
黒田一成(くろだかずしげ)は何をした人?摂津有岡城で官兵衛を助けた人(の息子)!【黒田二十四騎】
黒田一成はこの敗走の際には、長政の影武者になることを志願しました。
しかし、官兵衛は兵站を断つ持久戦をとり、他の国人勢力を攻め下していきついに城井鎮房は降伏しました。
黒田長政は城井家はこのままでは怨恨を残し今後の懐柔が困難と判断し、官兵衛が授けた謀略により、酒宴のせきに誘き寄せ鎮房を家臣団もろとも謀殺します。
鎮房の父・長房も黒田勢に殺害され、官兵衛と同行し肥後国人一揆鎮圧中であった嫡男の城井朝房は官兵衛の手によって暗殺されました。
また降伏の際に引き受けた鎮房の娘・鶴姫と侍女13人も山国川の畔、広津の千本松河原で磔にされ殺害されました。
秀吉の指示でもあったので苦渋の決断だったことでしょう。
第2位 : 囲碁に夢中で謹慎処分
文禄の役の際、黒田官兵衛は養成のため朝鮮から豊前に一時戻りますが、文禄2年(1593年)2月秀吉は官兵衛を再度朝鮮に送ります。
各奉行、各武将が各々の思惑で動き朝鮮での無益な戦いに意欲が削がれた官兵衛は同行していた浅野長政と囲碁を始めます。
そこに石田三成、増田長盛、大谷吉継の三奉行がやってくるも、構わず囲碁を打ち続けていました。
大河ドラマ「軍師官兵衛」では、急用ではないのでまた出直すと三成らがいった為、話をしなかったと官兵衛は言っていました。
しかし、石田三成は無視されたことを怒り、名護屋の秀吉に使いを出して「官兵衛は囲碁をしてばっかりで仕事をいっこもしてませんでした!」とちくります。
さすがにこれまでの功績があるのでこれだけでは特にお咎めはありませんでした。
しかし文禄2年(1593年)6月、宇喜多秀家が率いて黒田長政・加藤清正などが所属している4万2000の軍勢で晋州城を攻め落とし一息着いた頃に、官兵衛は石田三成ら三奉行が豊臣秀吉に囲碁の一件を讒訴していたことを知り、秀吉の許しを得ずに帰国し面会を求めます。
秀吉は朝鮮制圧が長引き、しかも明からの勅使が来ないことに大いに怒っていたので、官兵衛が無断帰国したことに激怒し、登城を指し止めと切腹を言い渡します。
同年6月、黒田官兵衛は出家して剃髪し、「如水円清」と名乗り、蟄居謹慎して正式に切腹の命令が下るのを待ちます。
如水円清とは、「身は褒貶毀誉(ほうへんきよ)の間にありといえども、心は水の如く清し」「水は方円の器に随ふ」という古語から取ったものである。
「人からどう言われようとも、心は水の様に澄んでいる」という意味。身の潔白を訴えます。
また「水は、容器(ここでは秀吉のこと)の形によって、四角にも丸くもなる。人間は、交友関係や環境次第で、善にも悪にも感化されることのたとえ。」の意味もあり、秀吉が善であってほしいということも含んでいたのではないでしょうか。
死罪を覚悟して黒田長政らに遺書を残しています。
これを受け取った長政や、大河ドラマ「軍師官兵衛」では小早川隆景や福島正則や、茶々までもが官兵衛の助命嘆願書を秀吉に送ったことで、秀吉に許され切腹は免れました。
このとき、黒田長政は父・黒田如水を切腹の危機に追いやった石田三成ら三奉行を激しく恨み、関ヶ原ではもちろん石田三成のいない東軍につき、石田三成のみを射殺する特殊部隊を編成しています。
第1位 : 有岡城で幽閉。人質として出していた一人息子が殺される!?
天正6年(1578年)当時の播磨は東に比叡山を焼き討ちするなど無茶苦茶やっている織田家と西に律儀と言われている毛利の大国に挟まれており、どちらにつくか迷っていました。
ほとんどの大名は毛利側に着く方に傾いていたのですが、官兵衛は毛利の現当主の輝元の愚鈍さと信長の天下布武にかける行動力や家臣団の働きなどから織田方に賭け播磨の諸大名を織田方になびかせることに成功します。
信長は播磨平定のため、秀吉を播磨に向かわせますが、官兵衛の事前の説得もあり簡単に播磨を平定できました。
しかし、毛利の外交僧である安国寺恵瓊の工作や本願寺が停戦を破棄し信長に反旗を翻したこと、播磨の最有力大名である別所家が毛利家に寝返ったことなどから、播磨全体が毛利方に一気に変わりました。
さらに織田家臣である摂津有岡城主の荒木村重も謀反を起こします。
信長は村重を重用し一国の城主にまで出世させたので彼が謀反したことにさすがに驚いたようです。
官兵衛の居城である姫路城に駐屯していた秀吉軍は四面楚歌になり孤立してしまいます。
当時官兵衛の主君で合った御着の小寺政職も村重に呼応しようとします。
「村重が思い止まるならば、謀反を思い止まる」と政職は官兵衛に伝えたため、官兵衛は村重を翻意させるために家臣の反対を押し切り単身で有岡城に乗り込んだが、逆に捕まり土牢に幽閉されてしまいます。
官兵衛の家臣団はここが正念場というように一層結束を強めます。
一致団結して「御本丸(官兵衛の妻である光)」に忠節を尽くすという起請文が作成したのである。
しかし、信長は官兵衛が単身で反信長に組したと見え、人質としていた官兵衛の一人息子である松寿丸(後の黒田長政)を処刑するよう秀吉に命令します。
もちろん牢屋の中の官兵衛は、このままでは信長が人質を殺すことは予測できるので本当に絶望の淵です。
有岡城の土牢の真横には池があり常にジメジメしており、しかも立ち上がれないほど狭い牢屋でした。
廃人同様の扱いの中で彼が生きる希望だったのが牢屋の窓の外から見える、日ごとに大きくたくましく育ってゆく藤蔓でした。
この藤が後の黒田家の家紋になります。
黒田家の家紋である藤巴
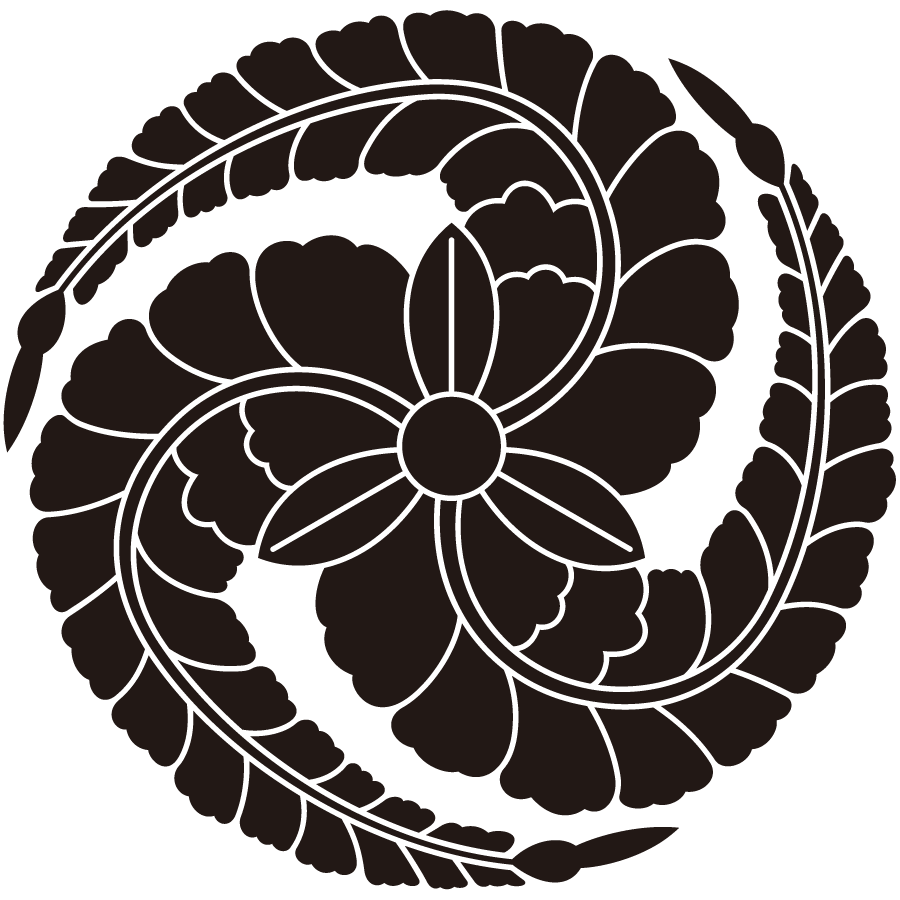
衛生が悪い状態で有岡城が信長によって落とされるまでの1年半の期間を幽閉され、救出されたとき官兵衛の足は不自由になっていたという。
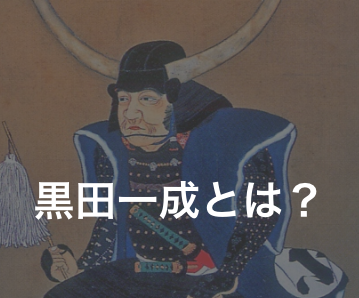
黒田一成(くろだかずしげ)は何をした人?摂津有岡城で官兵衛を助けた人(の息子)!【黒田二十四騎】
子の松寿丸はというと、秀吉の参謀である竹中半兵衛が替え玉を用意し、松寿丸は処刑を免れていました。
これは主君の命令に背く行為なので見つかれば半兵衛が処刑されてしまいます。しかし、半兵衛は病気になっており官兵衛が救出された際にはもう病死していたので、この経緯を知った信長は半兵衛を許し、官兵衛をより一層信頼しました。
まとめ
いかがでしたか?
人を殺さないといけない場面、切腹を言い渡される場面、1年半足が不自由になる程劣悪な環境で囚われる。
このような人生体験を垣間見ると、現代人のストレスの原因なんてちっぽけのように思えますね。
このような苦悩をくぐり抜けた分だけ人として成長していけるのだと思います!
それでは、今後もランキングの記事をアップしていきますのでよろしくお願いいたします。
参照
城井鎮房
黒田官兵衛と碁と将棋