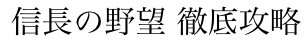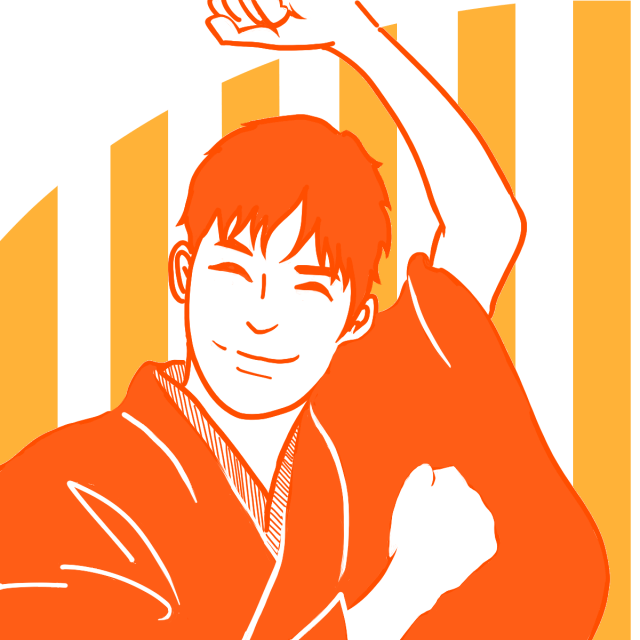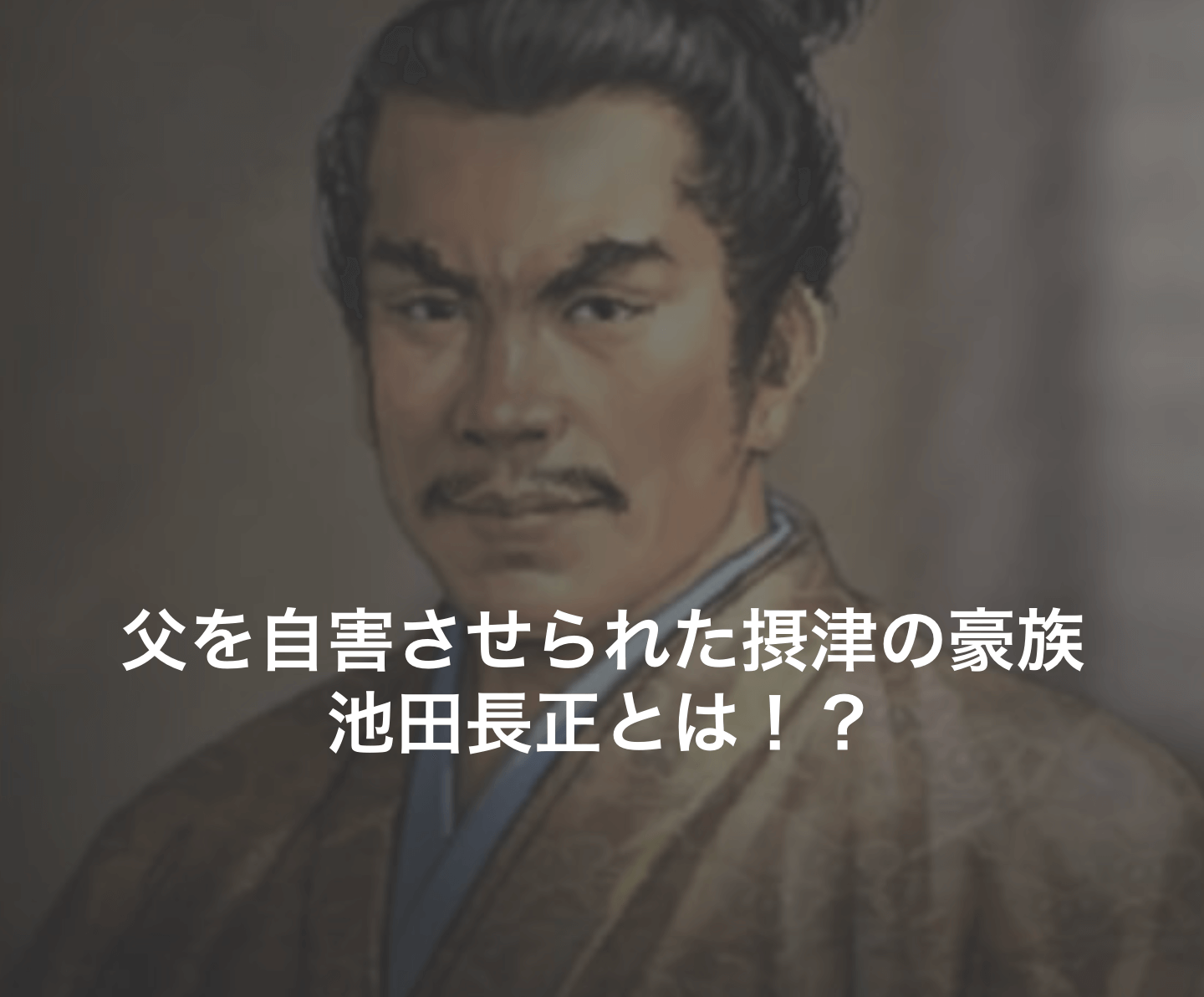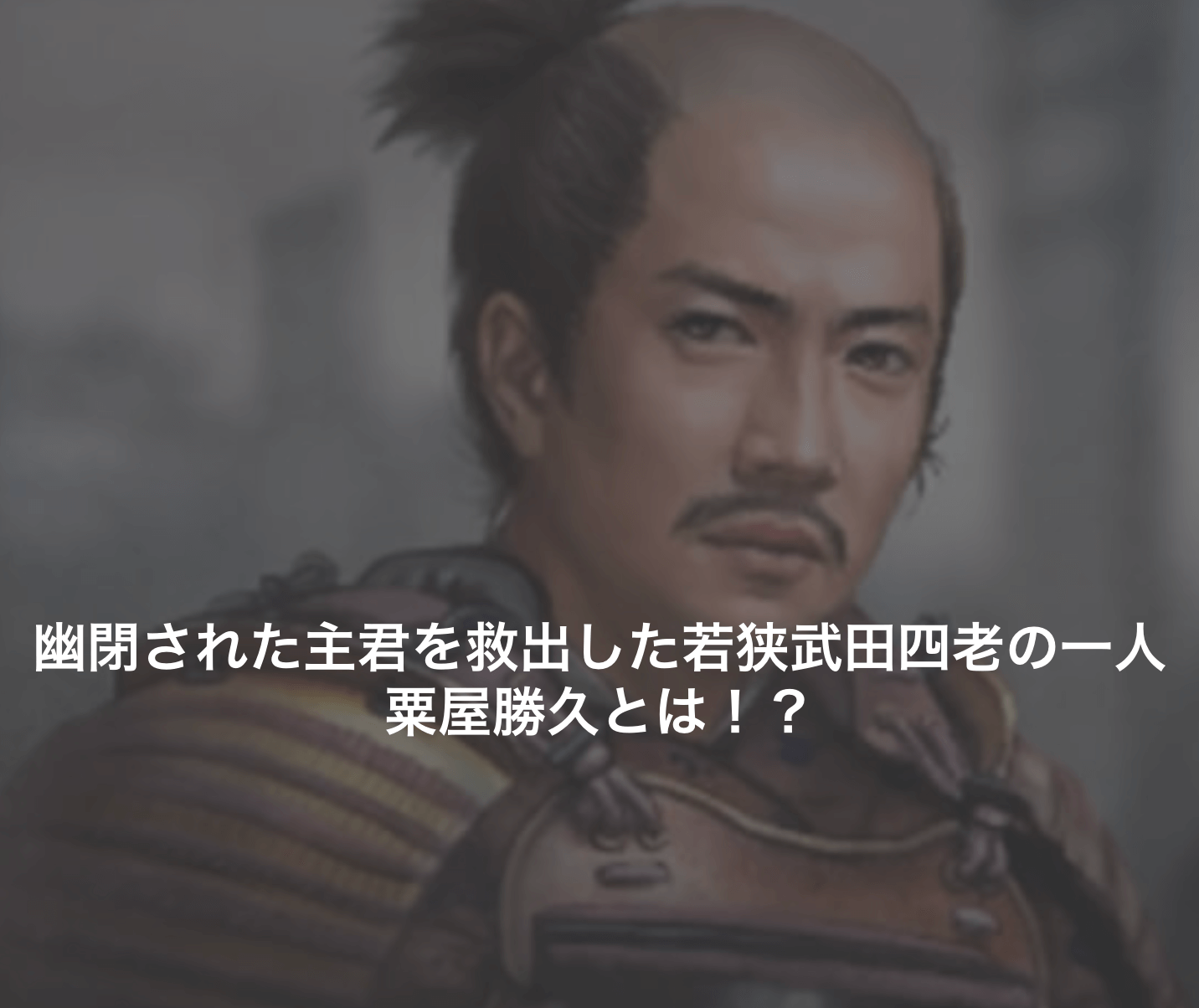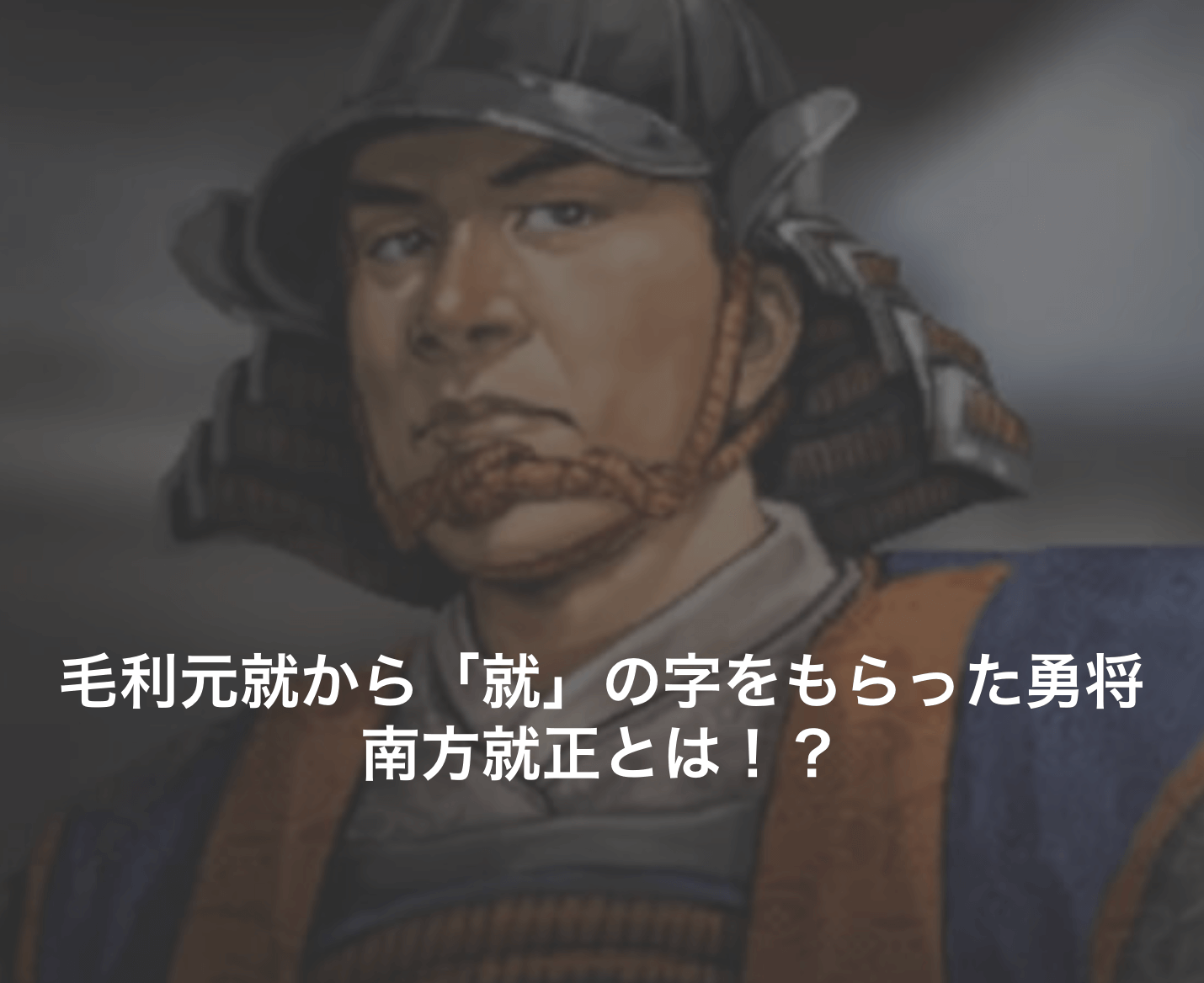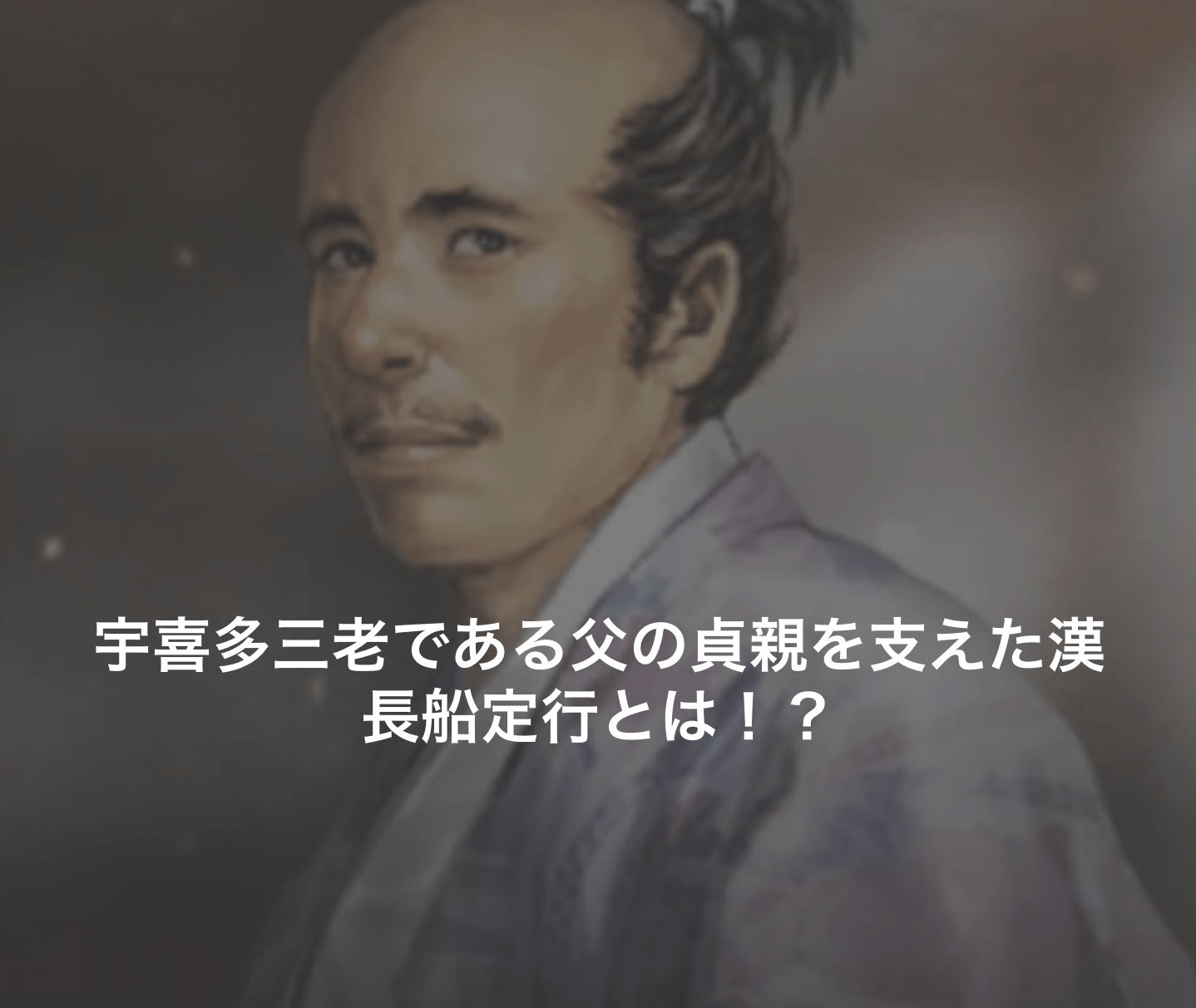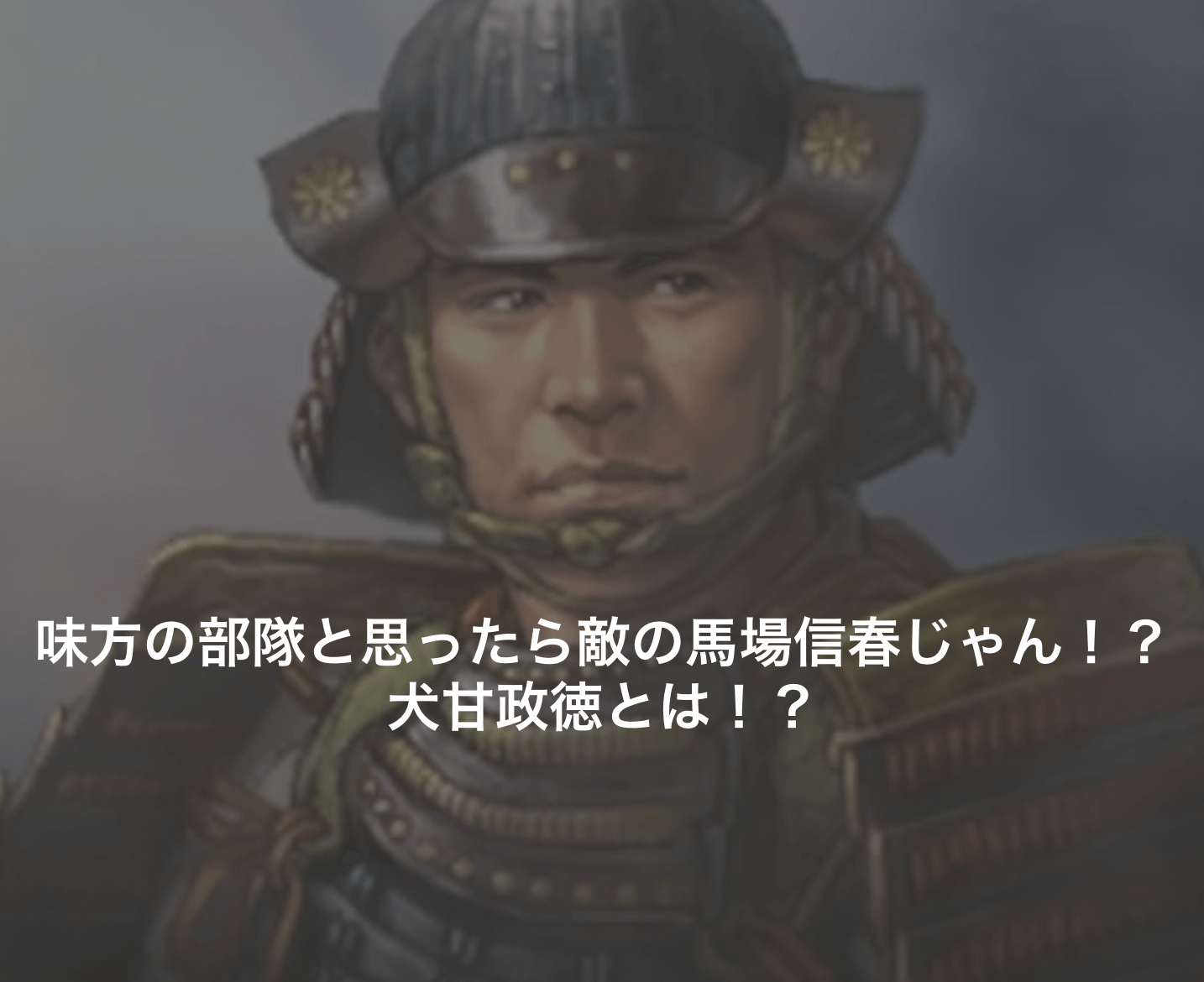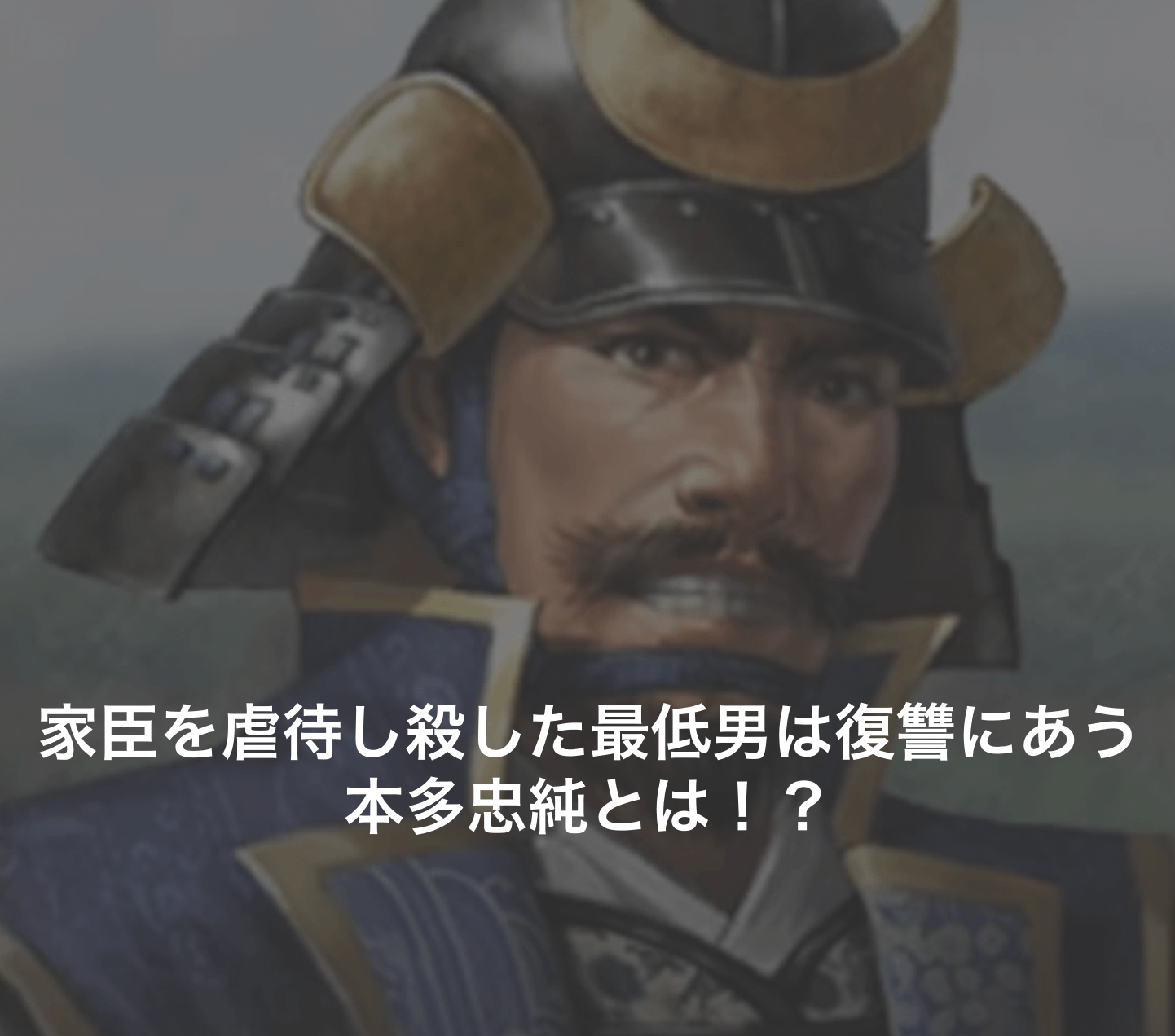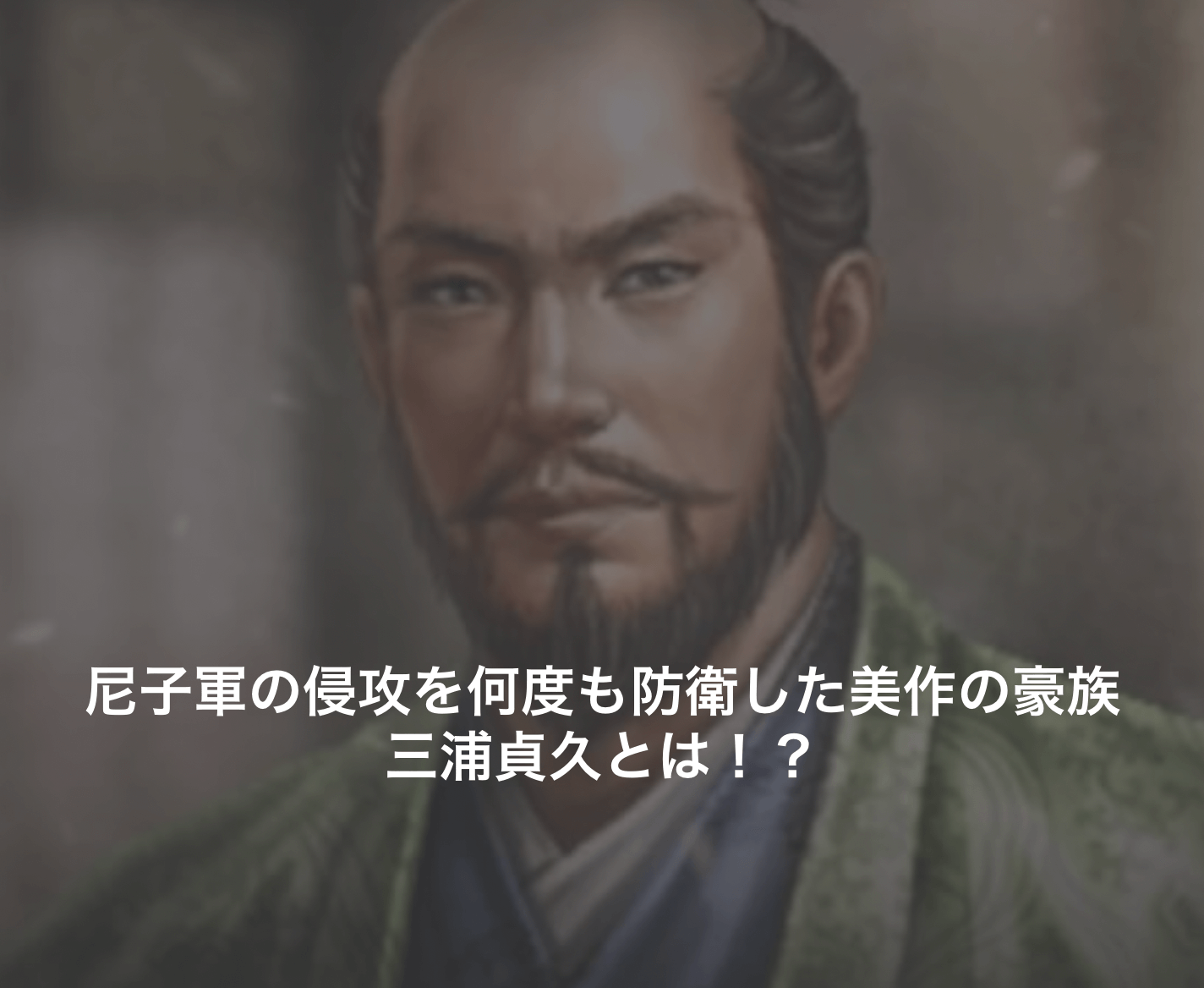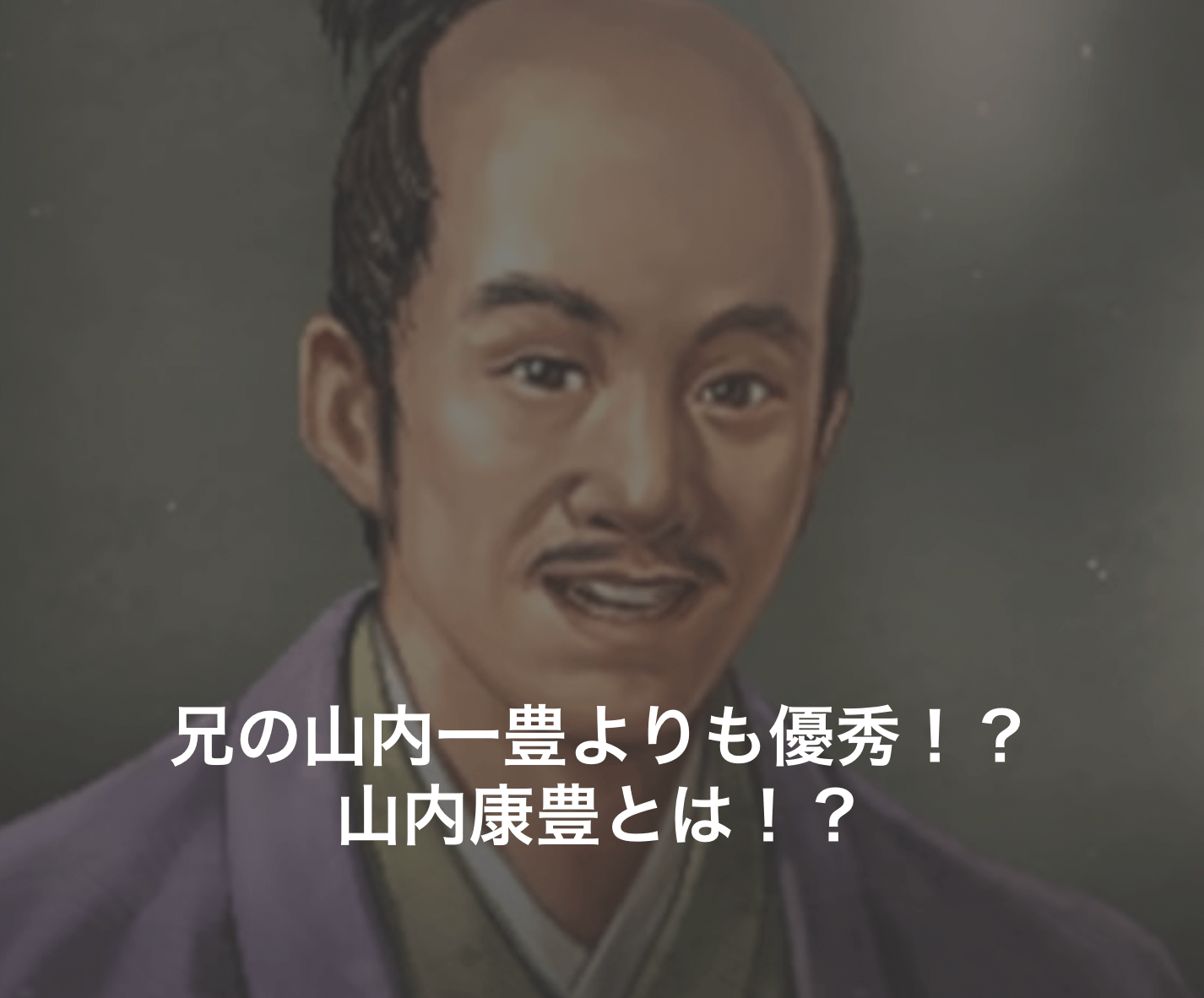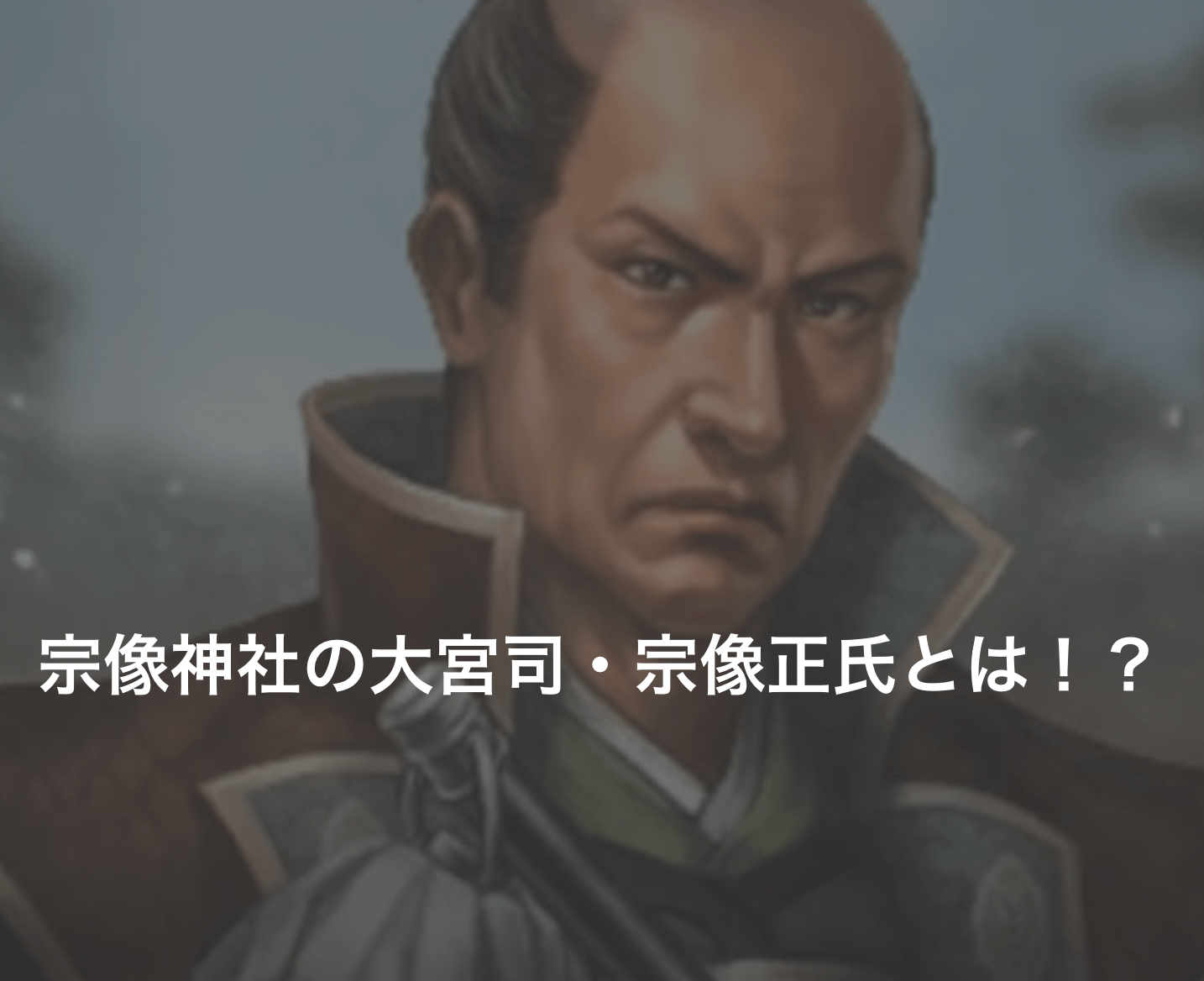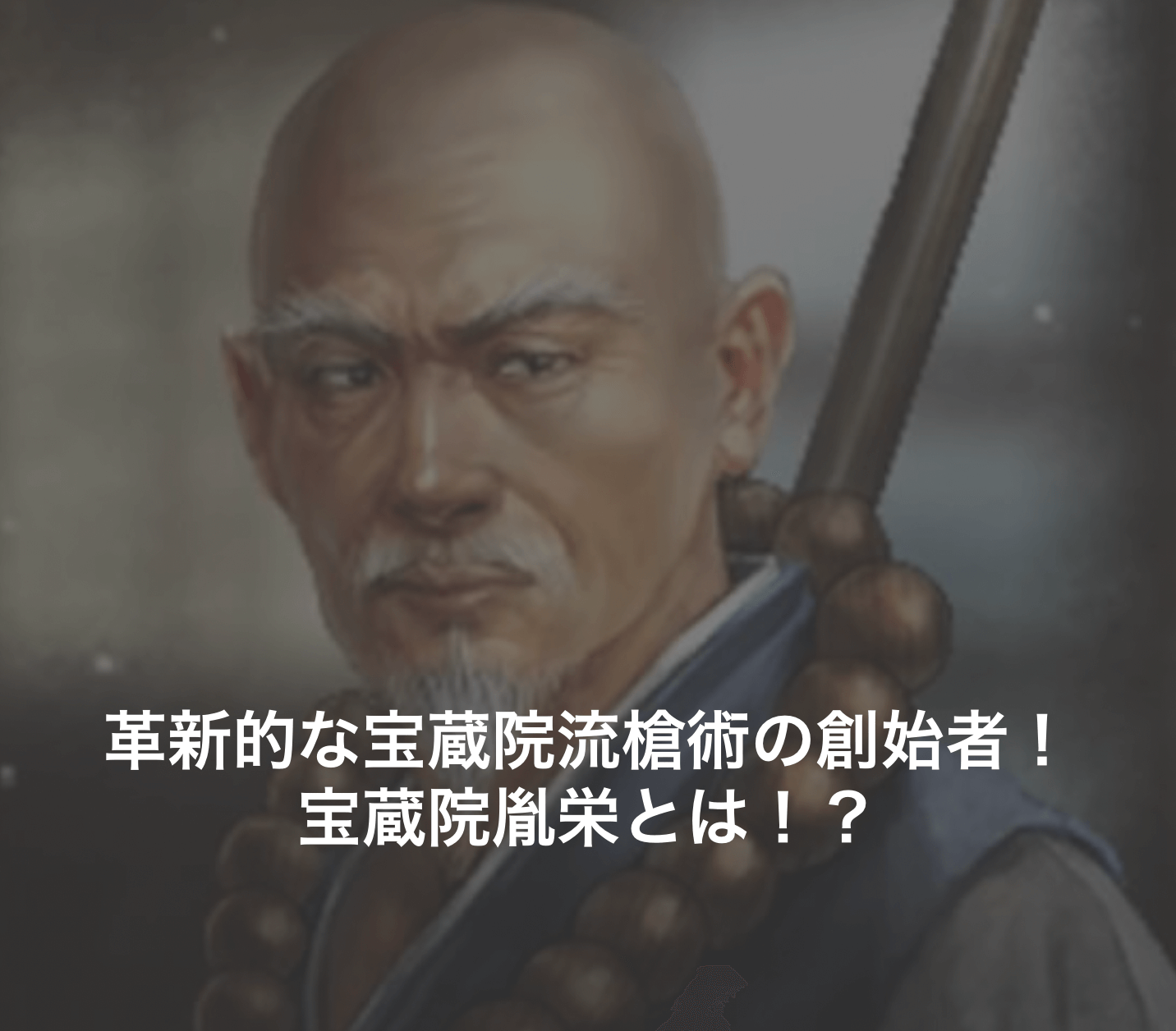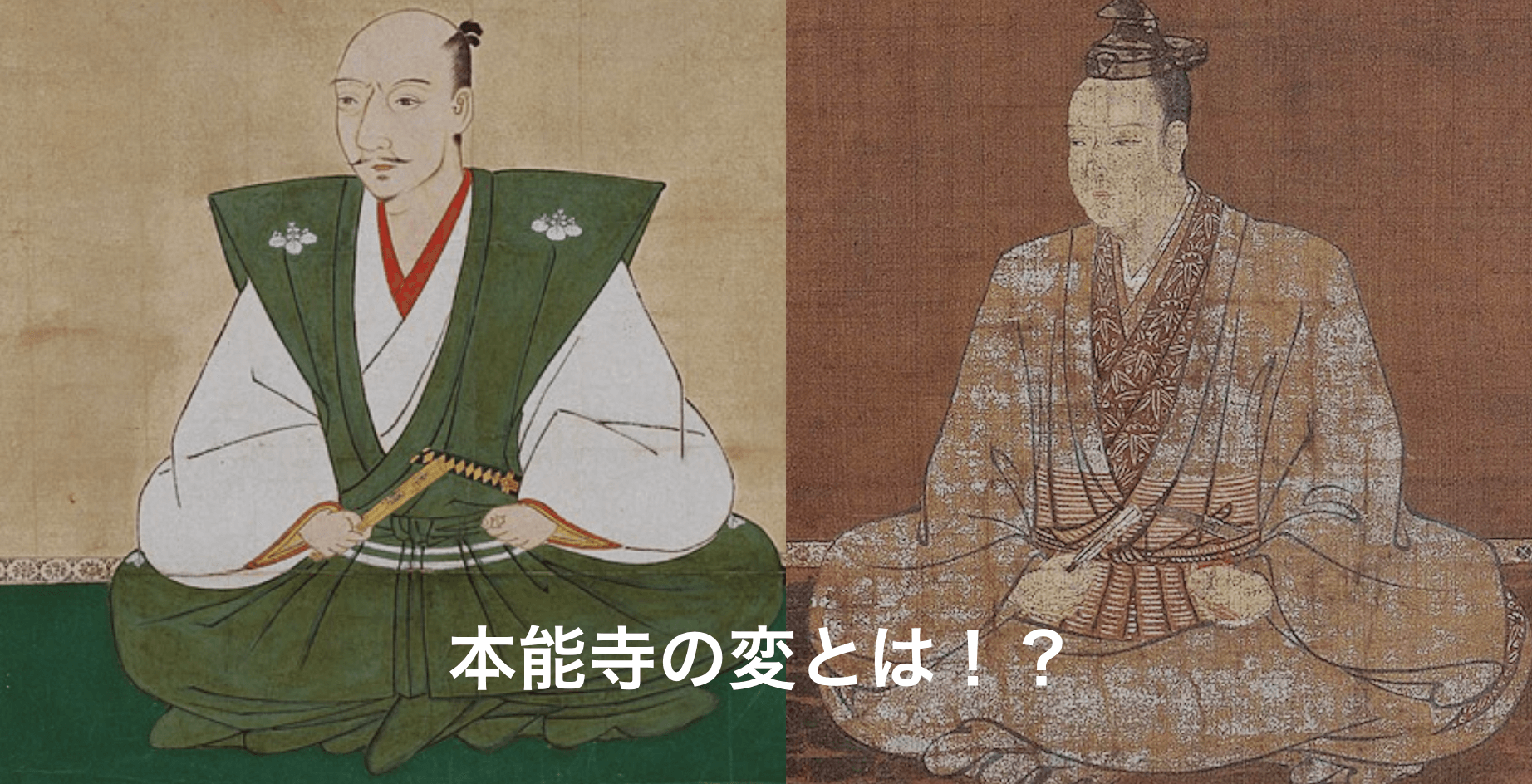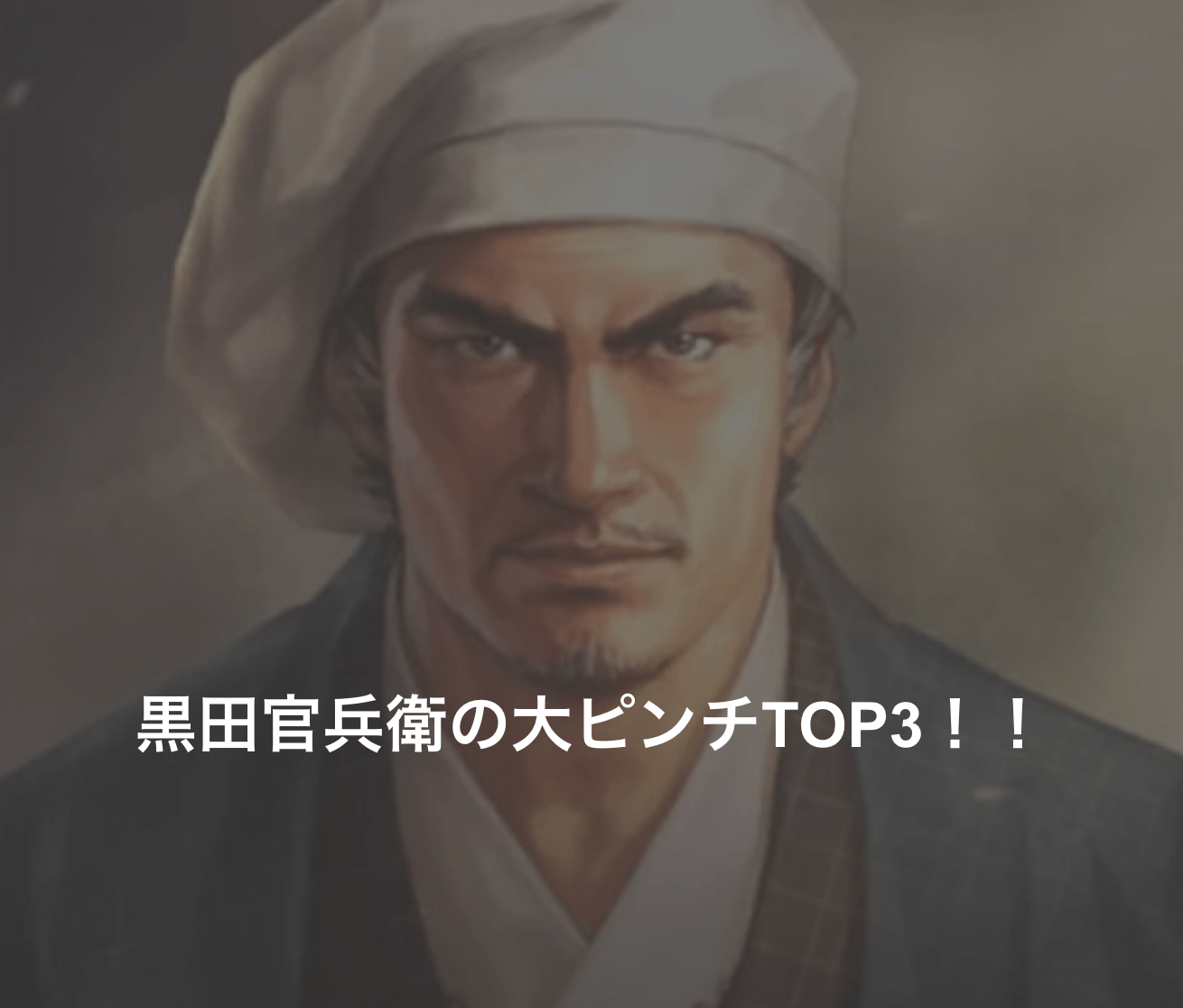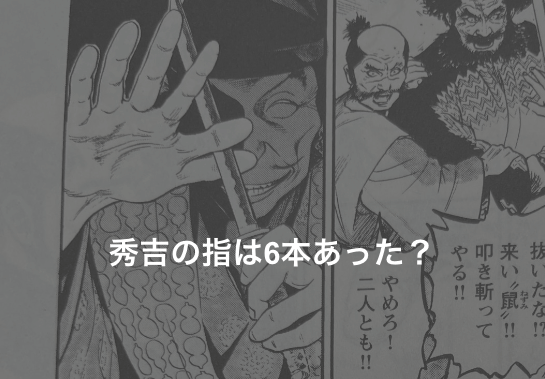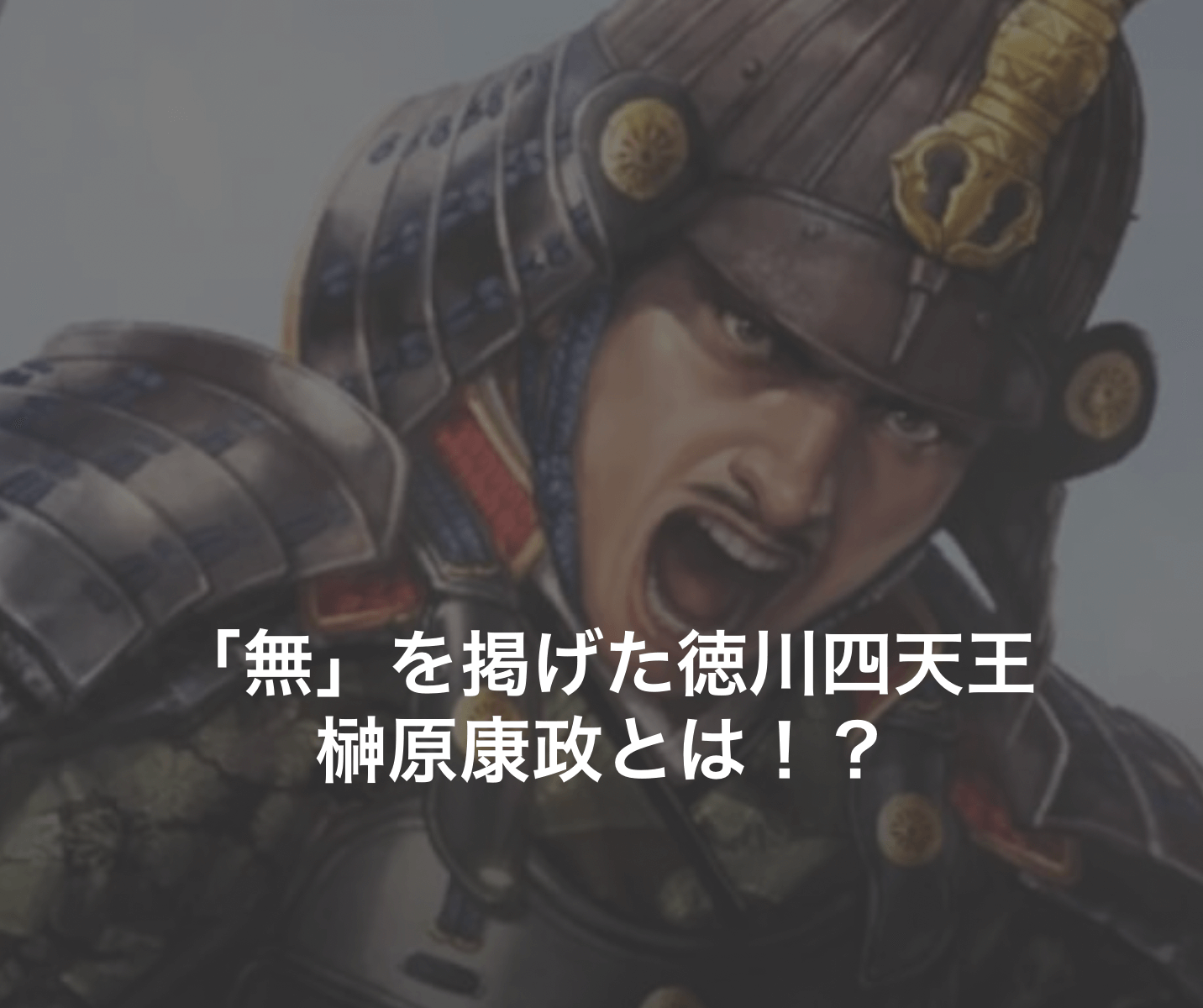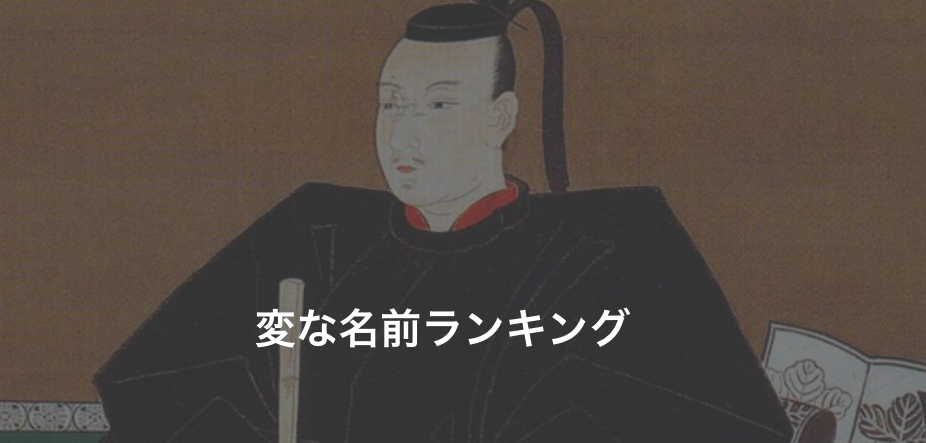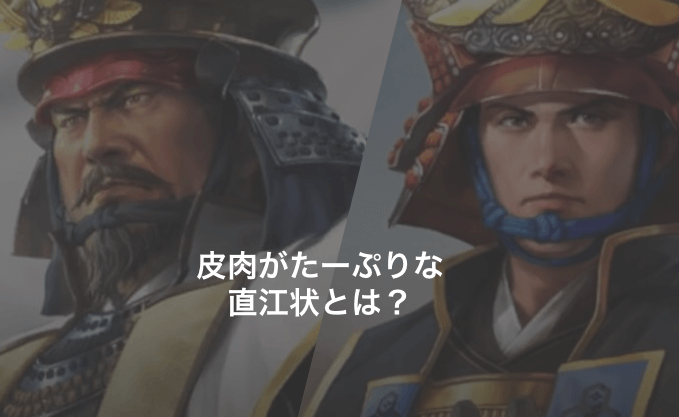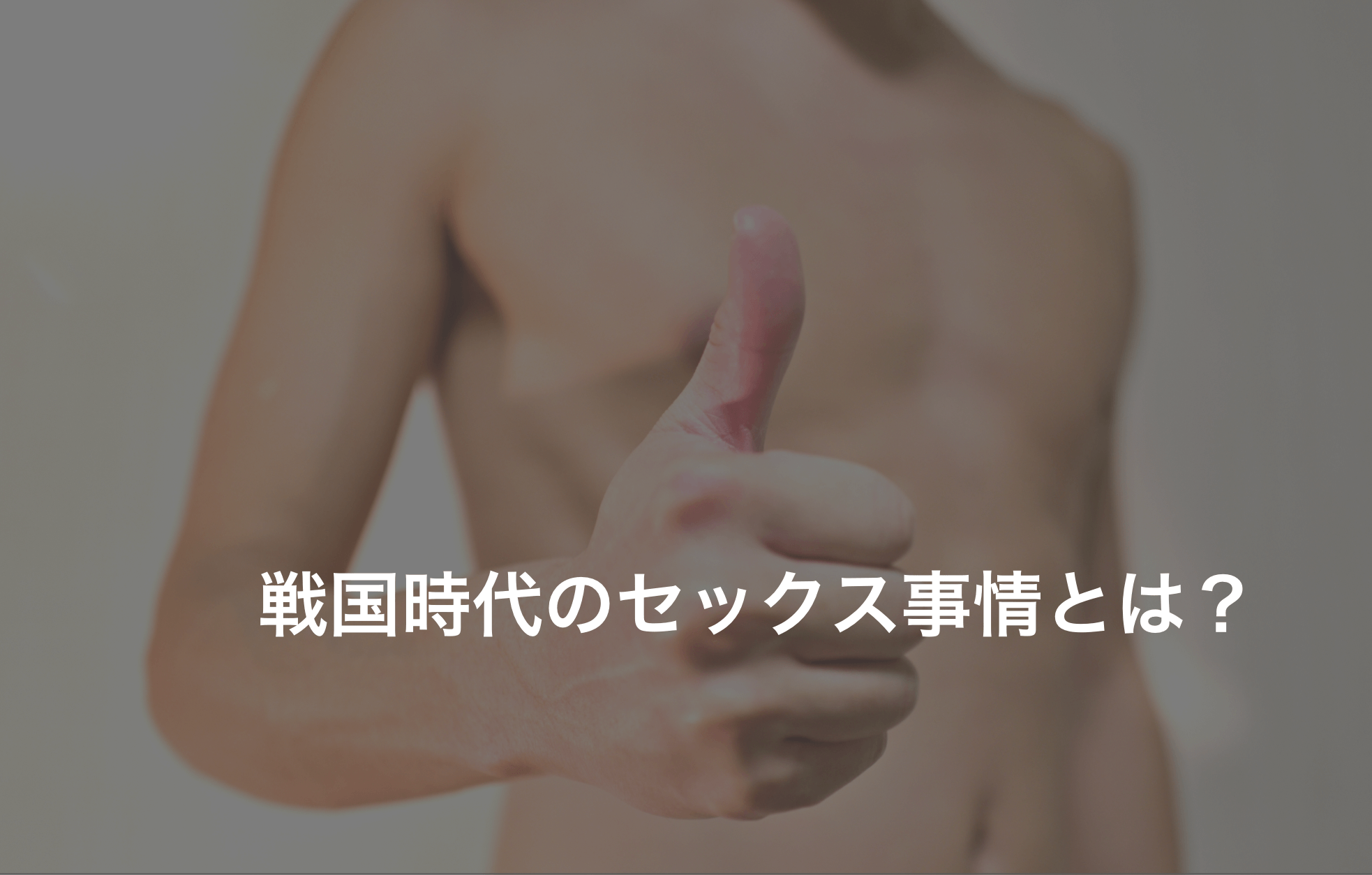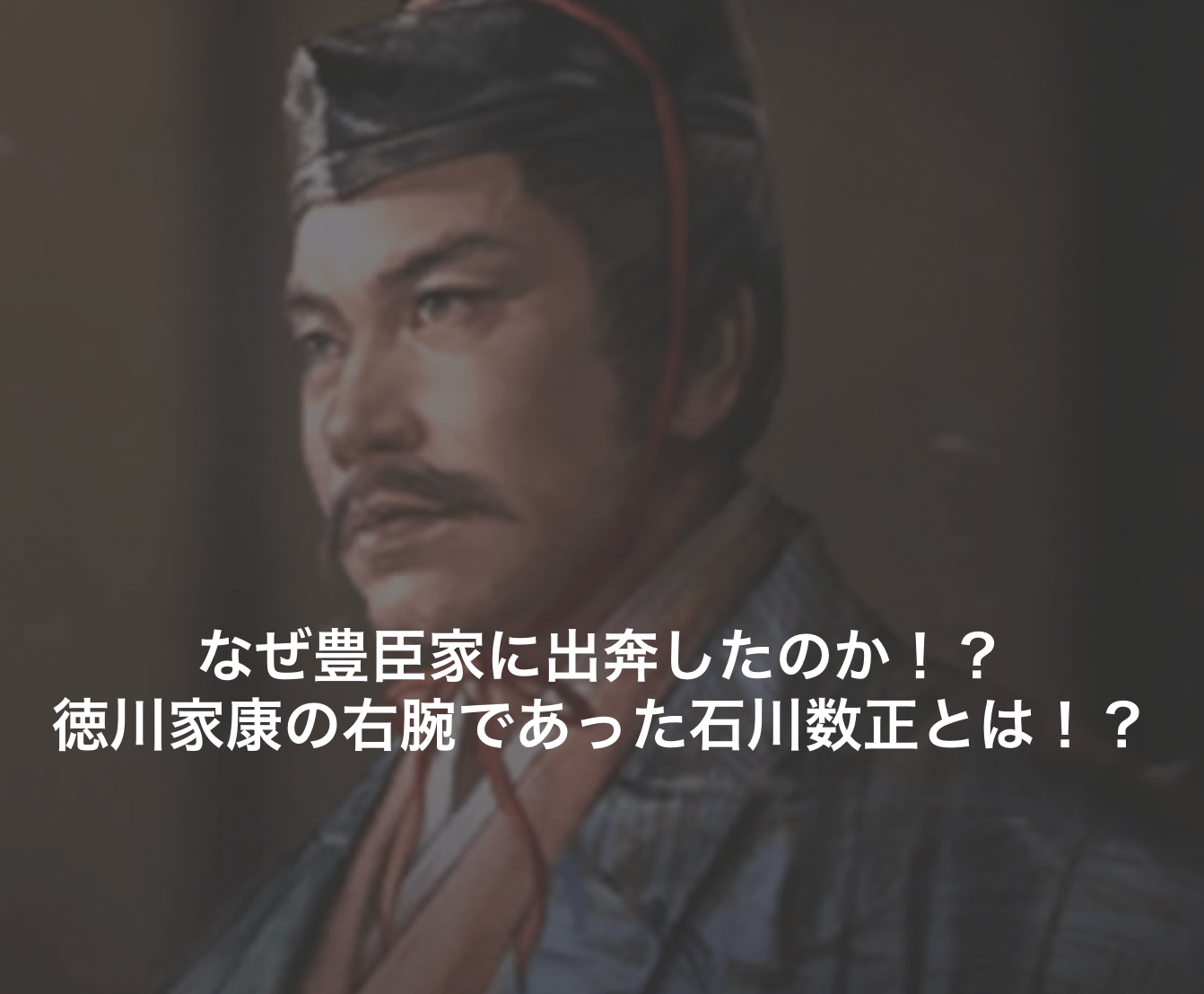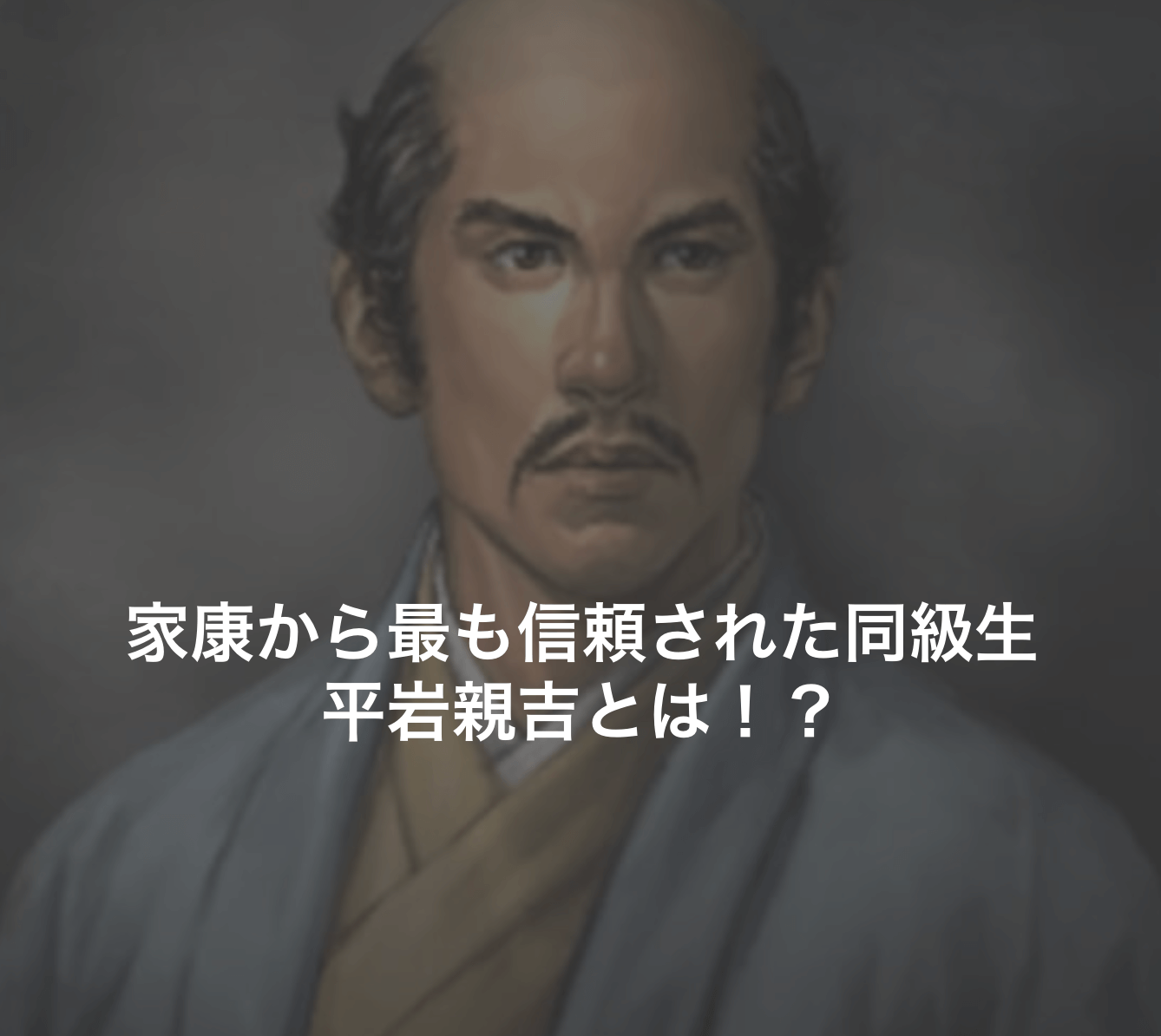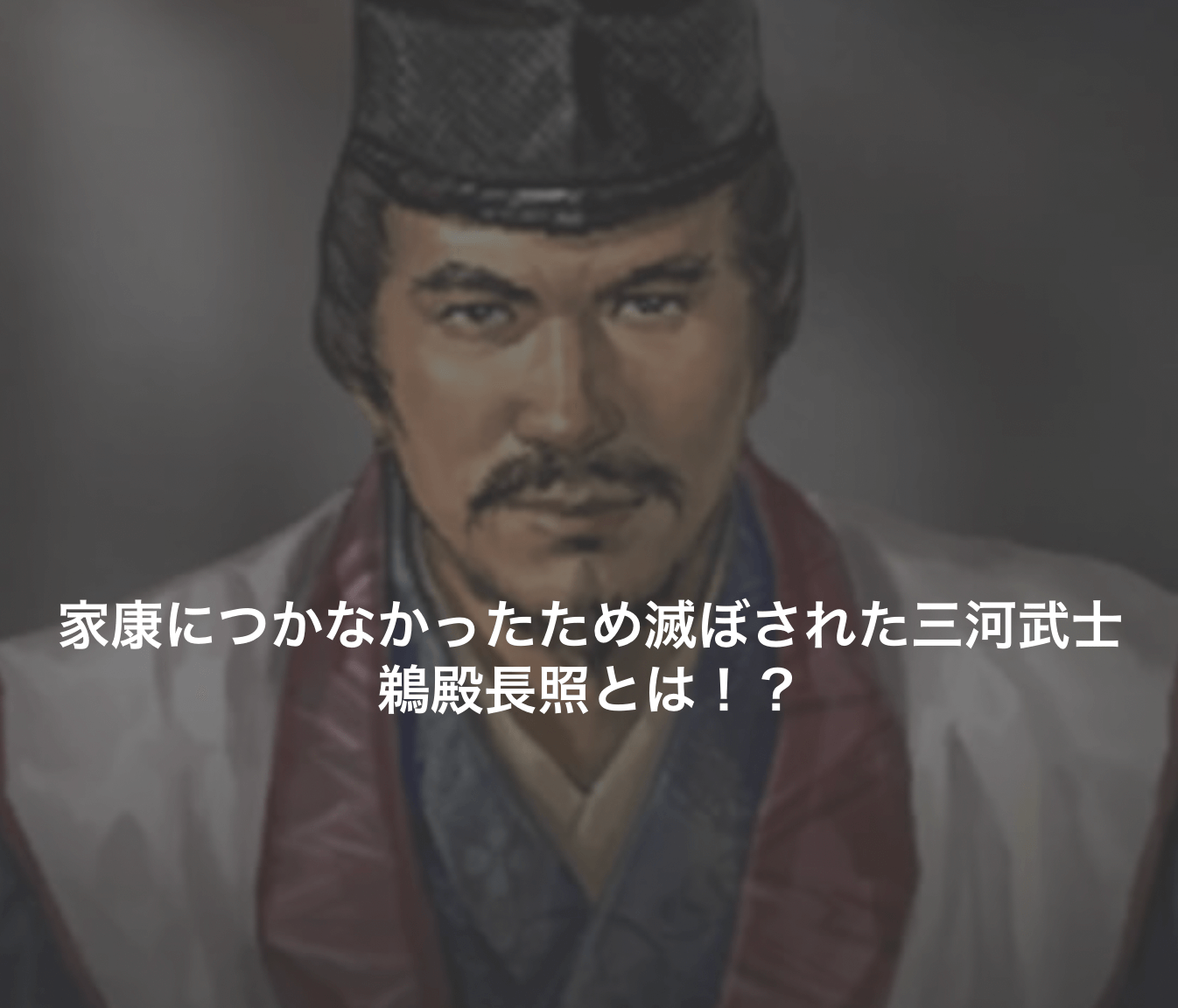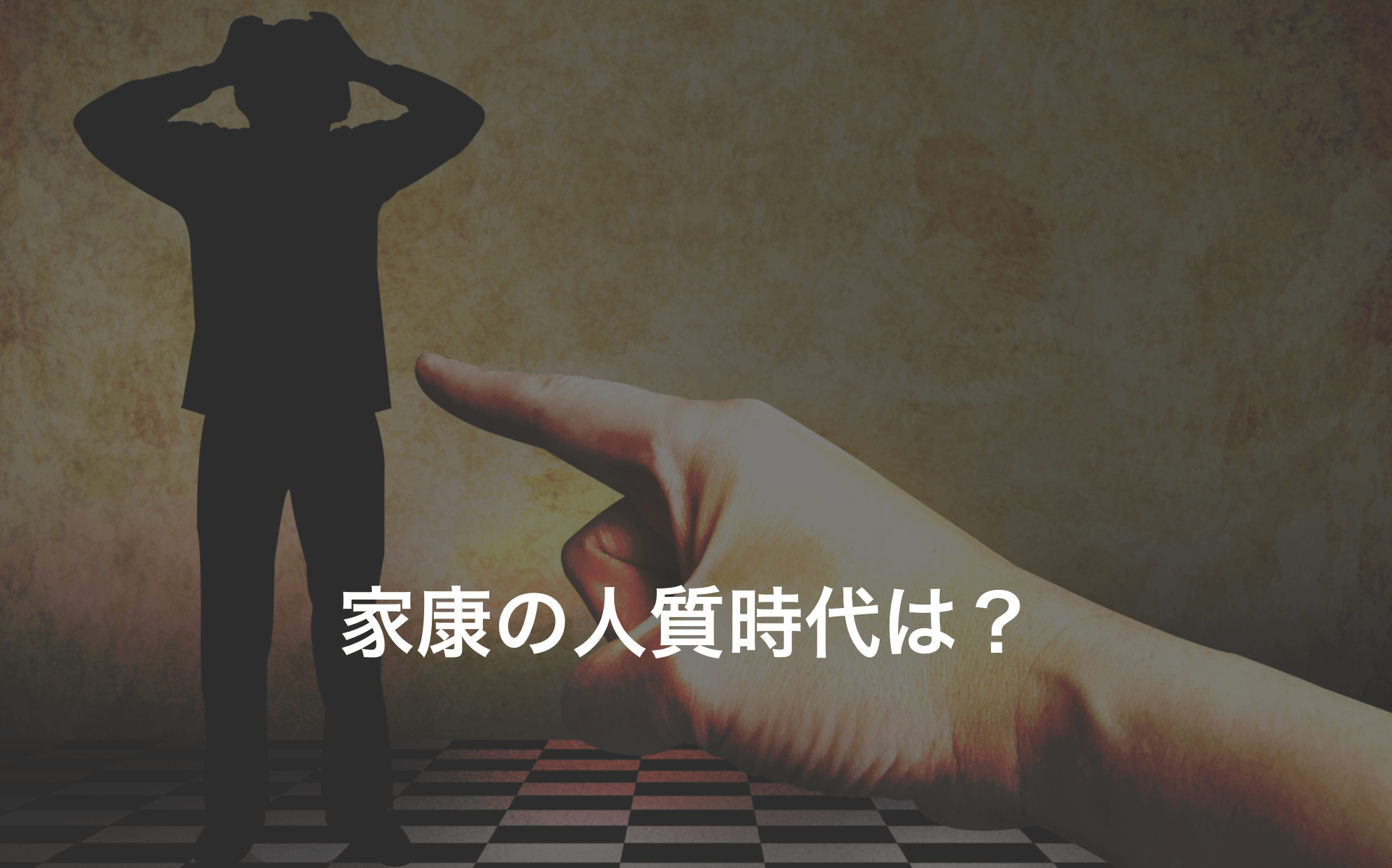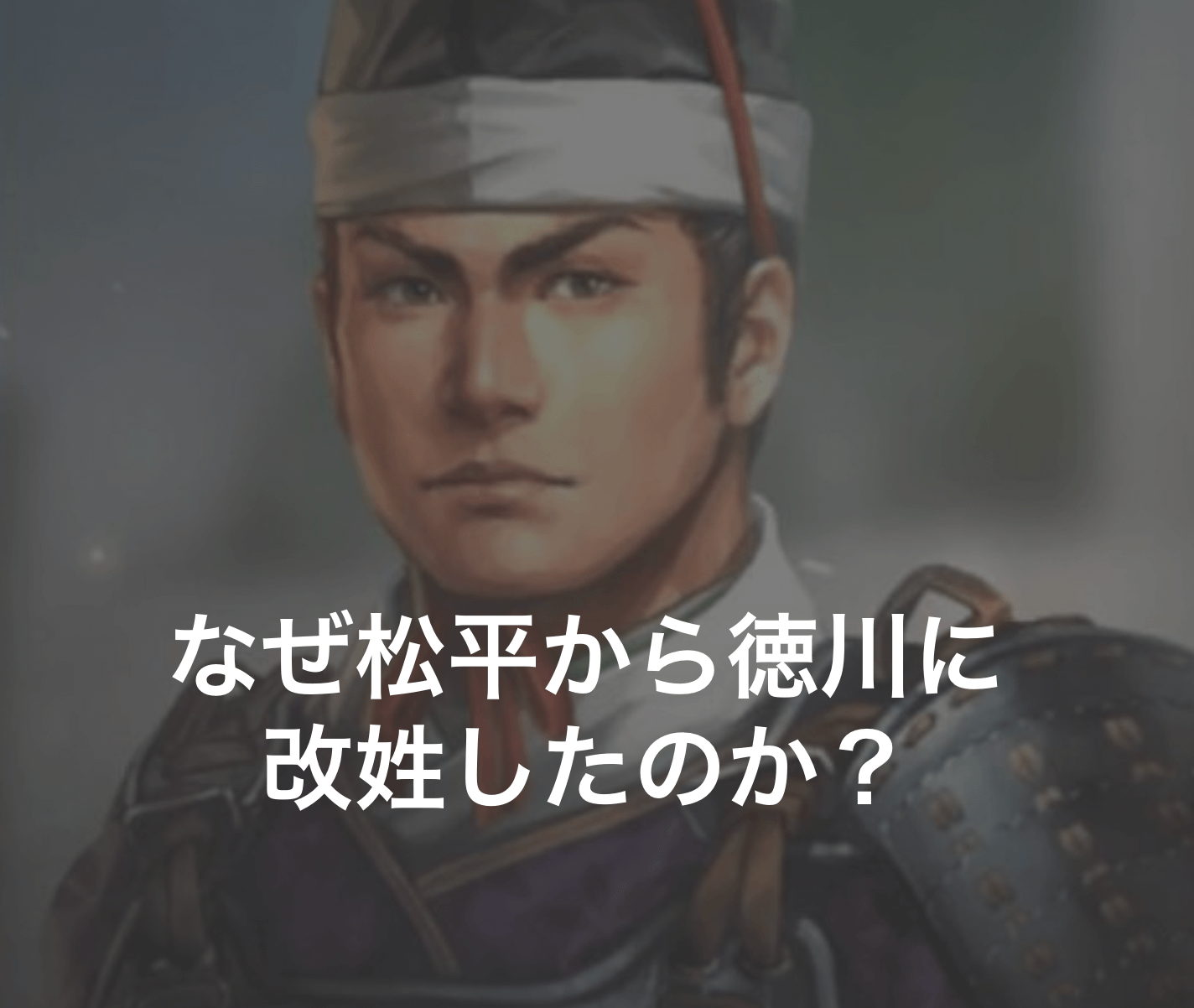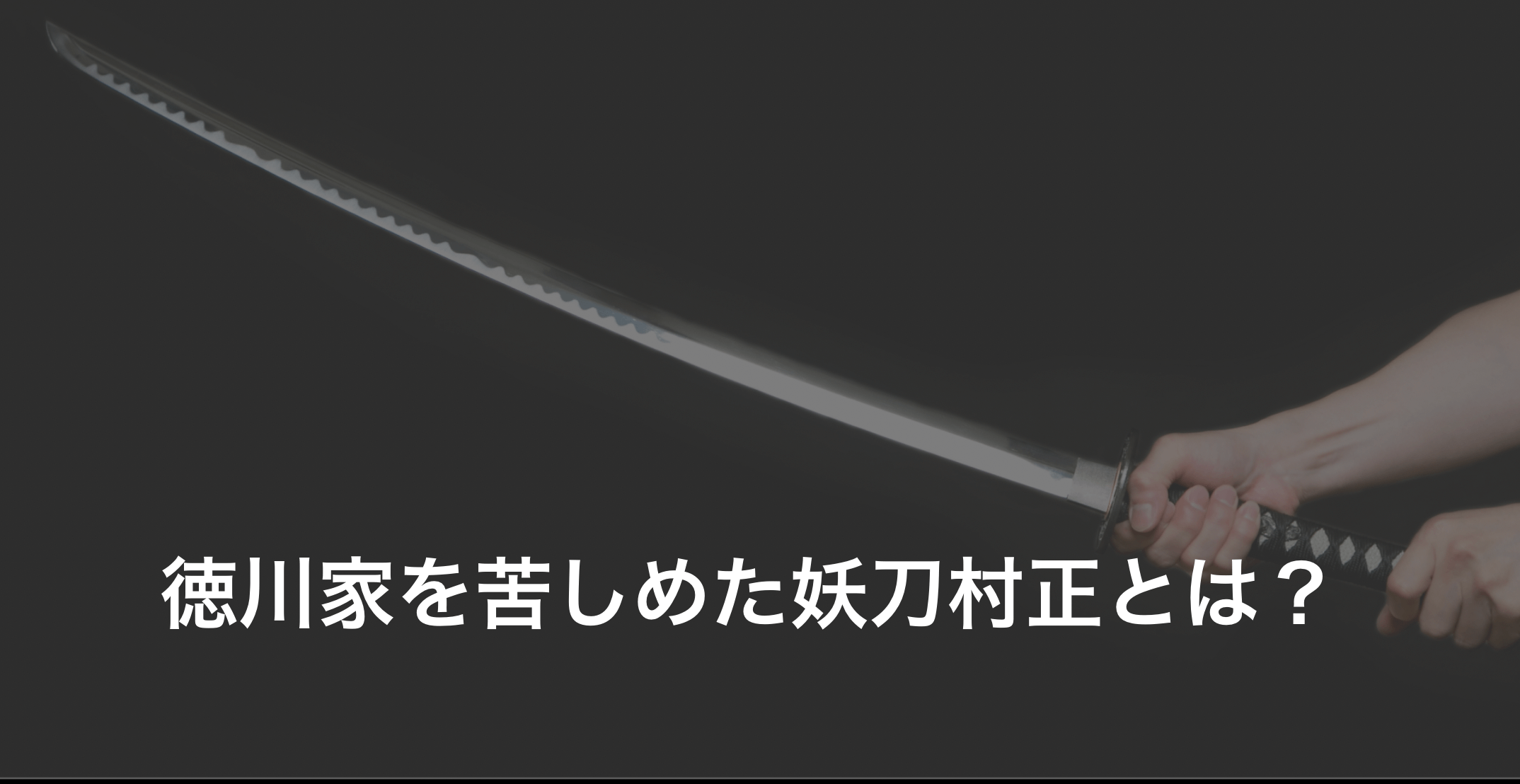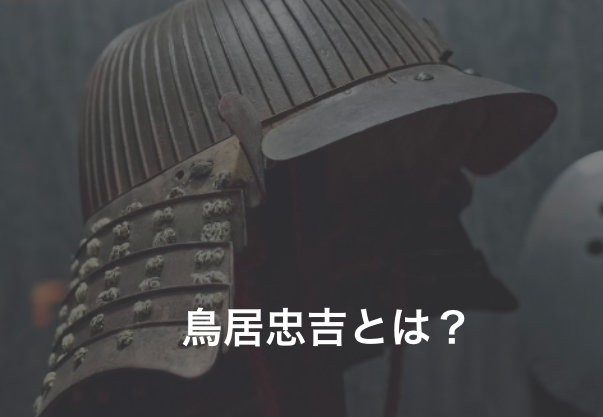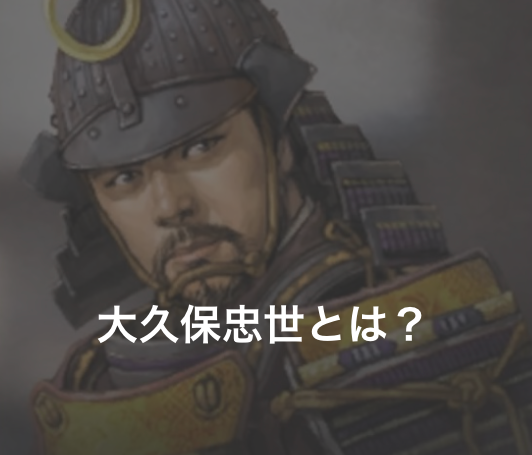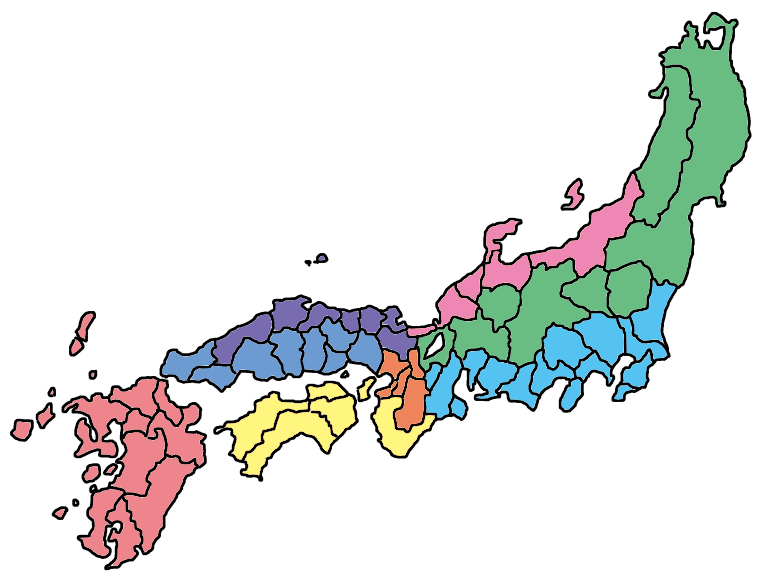views : 4433
那古野勝泰(なごやかつやす)は何をした人?簗田弥次右衛門との禁断の●●な仲(意味深)【マイナー武将列伝】
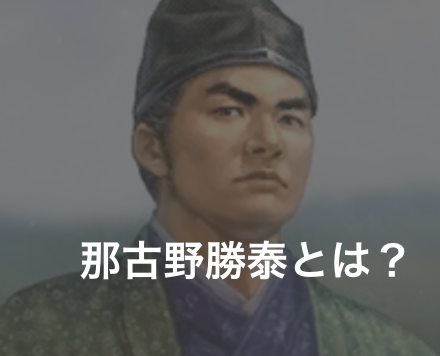
こんにちは、歴史大好きtakaです。
今回紹介するのは尾張斯波家臣・那古野勝泰(なごやかつやす)です。
一体何をした人なんでしょうね。
それでは見ていきましょう!
目次[非表示]
「なごや」の表記
那古野勝泰の苗字の「那古野(なごや)」は現代の名古屋と関係があるのか疑問に思いますよね。
貞治三年(1364年)の大須真福寺の蔵書に尾張国那古野荘と記されたものがあり、応安・応永年間(14世紀中~15世紀前)で見つかった文書は概ね「那古野」のようです。
熱田神宮にある宝刀には大永二年(1522年)と彫られたものがありそれには「名古屋」とあるという。
なので古くは「那古野」で後年、「那古屋」・「名古屋」とも表記されるようになりこれらは全て共通と考えてもよいものでしょう。
名古屋城の南西には那古野の地名が残っており、外堀沿いには那古野神社があります。
名古屋城も実は那古野城の跡に建ち、名古屋城二の丸庭園にはその碑がたっているようです。
信長の野望での那古野勝泰の説明
ゲーム信長の野望では那古野勝泰についてこのように説明されています。
簗田(やなだ)弥次右衛門という人物が出てきましたね。
簗田弥次右衛門(簗田政綱)の説明も見てみましょう。
簗田政綱
織田家臣。桶狭間合戦では斥候として奇襲成功の立役者となり、戦後尾張沓掛3千貫を与えられた。のちに大聖寺城主となるが、一揆の再起により改易された。
1532年生まれ
那古屋弥五郎と簗田弥次右衛門の仲はいわゆる男色です。
説明から推測すると那古野勝泰が16、17歳の頃に、7歳・8歳の簗田政綱と只ならぬ仲になっています。
ちょっと早すぎやしませんか?
wikipediaでは簗田政綱の誕生年が「不明」となっているので、実際は違ったのでしょうか。
『信長公記』での那古野勝泰
太田牛一が記した『信長公記』には「簗田弥次右衛門御忠節の事」という節があります。
原文と訳を一部見てみましょう。
原文
「簗田弥次右衛門御忠節の事」
一、さる程に、武衛様の臣下に簗田弥次右衛門とて、一僕の人あり。面白き巧みにて知行過分に取り、大名になられ候子細は、清洲に那古野弥五郎とて十六、七、若年の、人数三百計り持ちたる人あり。色々歎き候て、若衆かたの知音を仕り、「清洲を引きわり、上総介殿の御身方候て、御知行御取り候へ」と、時々宥め申し、家老の者どもにも申しきかせ、欲に耽り、「尤」と、各同じ事に候。
然る間、弥次右衛門、上総介殿へ参り、御忠節仕るべきの趣、内々申し上ぐるに付いて、御満足斜ならず。
或る時、上総介殿御人数清洲へ引き入れ、町を焼き払ひ、生城に仕り候。信長も御馬を寄せられ候へども、城中堅固に候間、御人数打ち納れられ、武衛様も城中に御座候間、透を御覧じ、乗つ取らるべき御巧みの由、申すに付いて、清洲の城外輸より城中を大事と用心、迷惑せられ候。
【現代語訳】
一、このような時、武衛様(尾張国守護・斯波義統)の家臣に簗田弥次右衛門という、一僕の人(下僕、身分の低い人)がいた。彼は、面白い策略を使って、身分不相応の領地を有する大名になった。その詳細は、清洲城に那古野弥五郎といって、16、7歳でまだ若いが手勢約300人を持っている武士がいた。いろいろと甘い言葉をかけて、男色の関係を持つようになった。その上で、「清洲城内を分裂させ、織田信長の味方になって、領地をもらいなさい」と時々そそのかし、斯波家の家老衆にも言うと、欲に目がくらんで、「もっとも」と賛同した。
そうして、梁田弥次右衛門は、織田信長のところへ行き、「(織田信長に)忠節を尽くして仕えます」と、密かに申し上げると、織田信長は大変満足した。
ある時(天文21年8月16日の深田・松葉両城奪還後)、織田信長は軍勢を清洲へ引き入れ、町を焼き払い、清州城を生城(はだかじろ。城の周囲に何もない城)にしてしまった。織田信長も出馬して清州まで来たが、清州城は堅固な城で、城兵は出陣せずに籠城したので、織田信長は、攻めあぐねた。織田信長は、「城内には武衛様がおられ、攻め込んで武衛様を危険に晒すことは出来ないので、隙を見て乗っ取ろう」と梁田弥次右衛門の策略(内部分裂策)について話したので、それが伝わって、清州城では、「清洲城外より城も中の監視が大事」と用心したので、織田信長は難渋した。
那古野弥五郎(那古野勝泰)と簗田弥次右衛門(簗田政綱)が出てきましたね。
簗田弥次右衛門は下僕の身ながら大名になった。というのも、手勢約300人を持っている那古野弥五郎と男色の関係を持ち、清洲城内で斯波家の家老衆に信長の味方になるようにつくように説得したということが書かれていますね。
信長の野望の説明をもう一度読むと、この「簗田弥次右衛門御忠節の事」の節をまとめているということが分かりますね。
本文内では簗田弥次右衛門が織田信長に忠誠を誓ったとありますが、那古野弥五郎(那古野勝泰)も同様に信長に従ったと思われます。
『信長公記』の「小豆坂の戦い」の節にも、清洲衆で織田信秀に従軍し小豆坂で戦死した那古屋弥五郎という人物が登場しますが、年代から那古野弥五郎(那古野勝泰)の父親ではないかと推測されます。
『尾張円福寺文書』での那古野勝泰
『尾張円福寺文書』に那古野弥五郎勝泰と書かれた礼状があるようです。
他に那古屋又七教久や那古屋因幡守敦順も同世代の人物として名がみられているが那古屋弥五郎と同一人物かは分かっていないようです。
斯波義統との関係
斯波長秀(しばながひで)は何をした人?返り咲いた10万石大名!【マイナー武将列伝】で紹介した斯波長秀の父・斯波義統と那古野弥五郎勝泰は関係があるようです。
那古野氏は古くは陸奥国国人のようで、根拠地が陸奥国である斯波氏について尾張に一緒にきたのかもしれません。
この時期、斯波義統は清州城で坂井大膳や織田信友らによって傀儡化されていました。
また、信秀が死去した後に信長が家督を相続しましたが、信行の家督相続を推していた信友はこれが気に入らず、信長暗殺を計画していました。
自身が傀儡化されていることに嫌気がさしていた斯波義統は、この暗殺計画を知ると信長に「密告する代わりに自分を助けてほしい」と要請しました。
この時に信長に通じたのが簗田弥次右衛門と那古野勝泰でしょう。
これが引き金となって義統が信長側についたと考えた織田信友らは、斯波義統の嫡男の斯波義銀が川狩りに出かけている隙をついて信友らは斯波義統を自害へと追いやります。
ちなみにこの時に救出されたもう一人の斯波義統の息子が斯波長秀ですね。
斯波義銀は信長に保護され、信長は主家である「斯波義統の仇討ち」という名目で清州へ乗り込み、織田信友を謀叛人として処理することに成功します。
その後、信長によって傀儡化されていた斯波義銀は今川義元と組んで信長追放をはかりますが、実行前に信長にバレてしまい義銀は尾張を追放されて大名としての斯波武衛家は滅びました。
斯波家が衰退していく中、那古野勝泰・簗田弥次右衛門は信長に仕官したものと考えられます。
那古野勝泰の部下・丹羽兵蔵の機転
永禄二年(1559年)織田信長は時の将軍足利義輝に拝謁する為に上京しました。
このとき美濃の斎藤氏から信長を暗殺すべく刺客が放たれたようであるが、那古屋弥五郎配下の丹羽兵蔵の機転により信長はその難を逃れています。
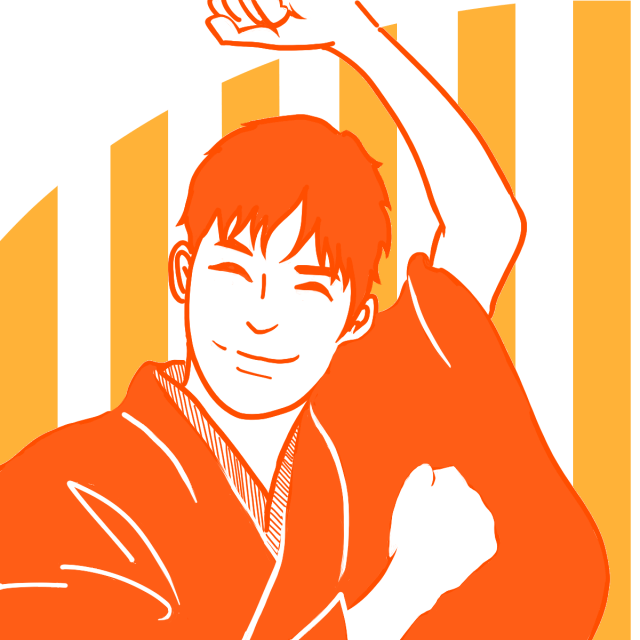
taka
ここで信長が暗殺されていたら歴史変わっていたじゃん。やるじゃん!
まとめ
いかがでしたか?
「信長公記」に男色と書かれるくらい那古屋弥五郎と簗田弥次右衛門は公然の仲だったんでしょうね。
信長の初期の話は、あまり知らなかったので知識が深まりました。
那古野勝泰の情報は全く知りませんでしたが、まとめて記事にしていくと別のマイナー武将列伝の記事で書いた内容が出てきて、点と点が繋がって線になりました。
面白いです。
Google Search Consoleで「那古野勝泰」で調べた人がいたので記事にしてみましたが、誰がこの人調べているんでしょうか?
この記事が役に立てば幸いです。
それでは、今後もマイナー武将列伝をアップしていくのでよろしくお願いします!