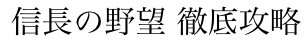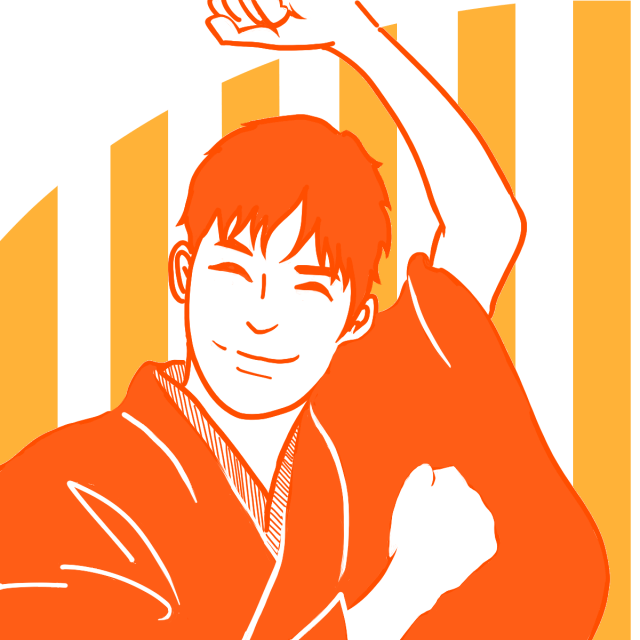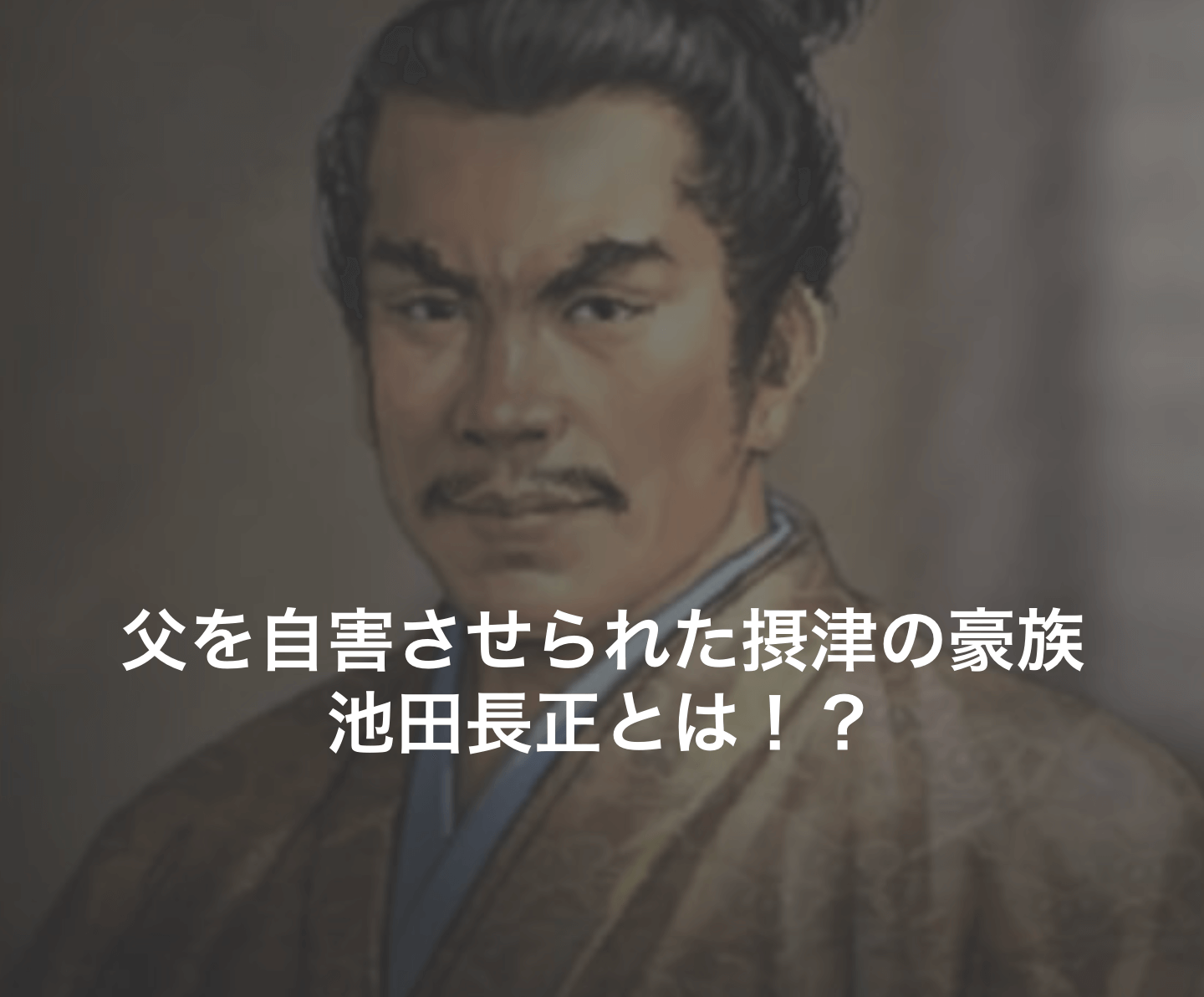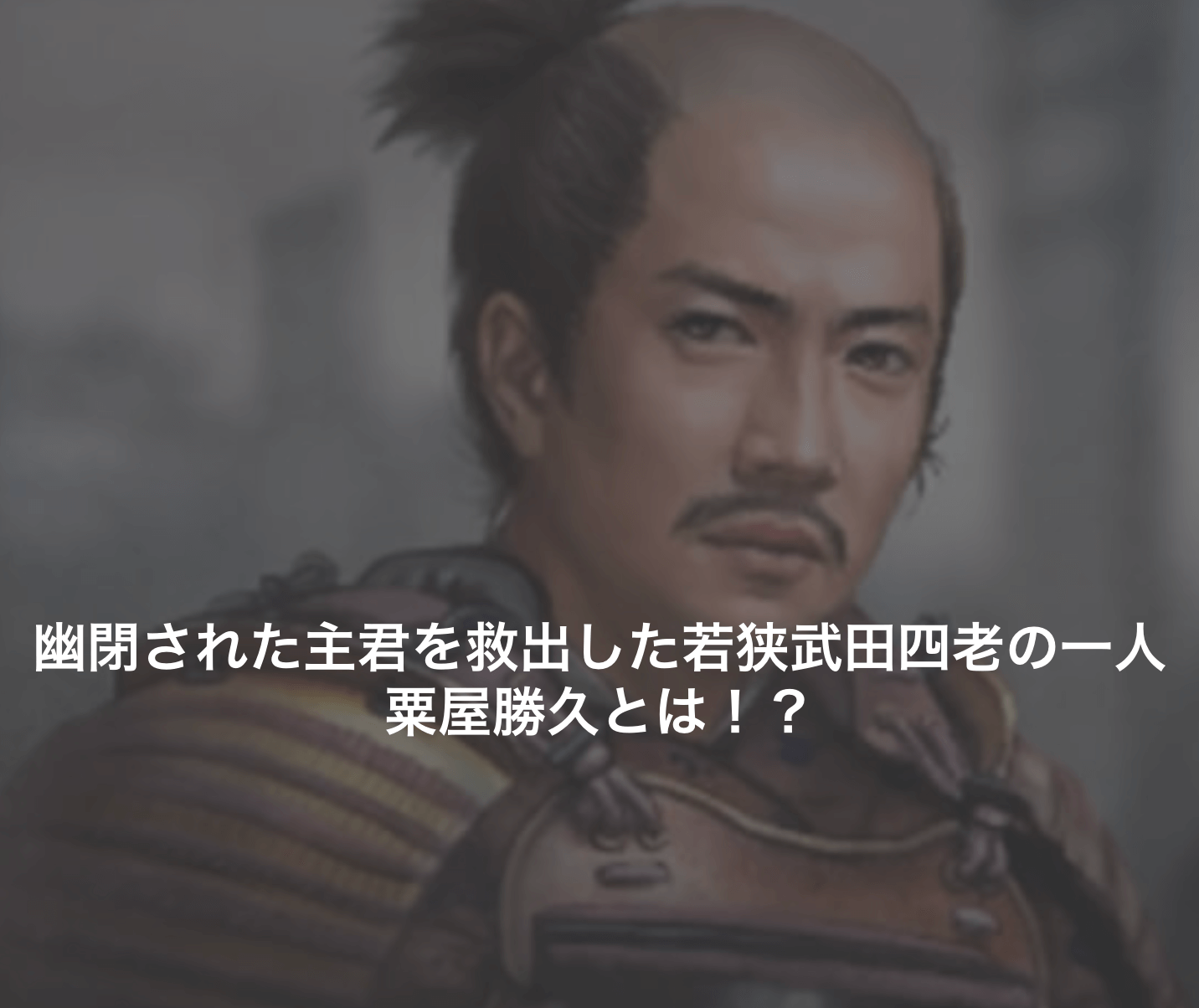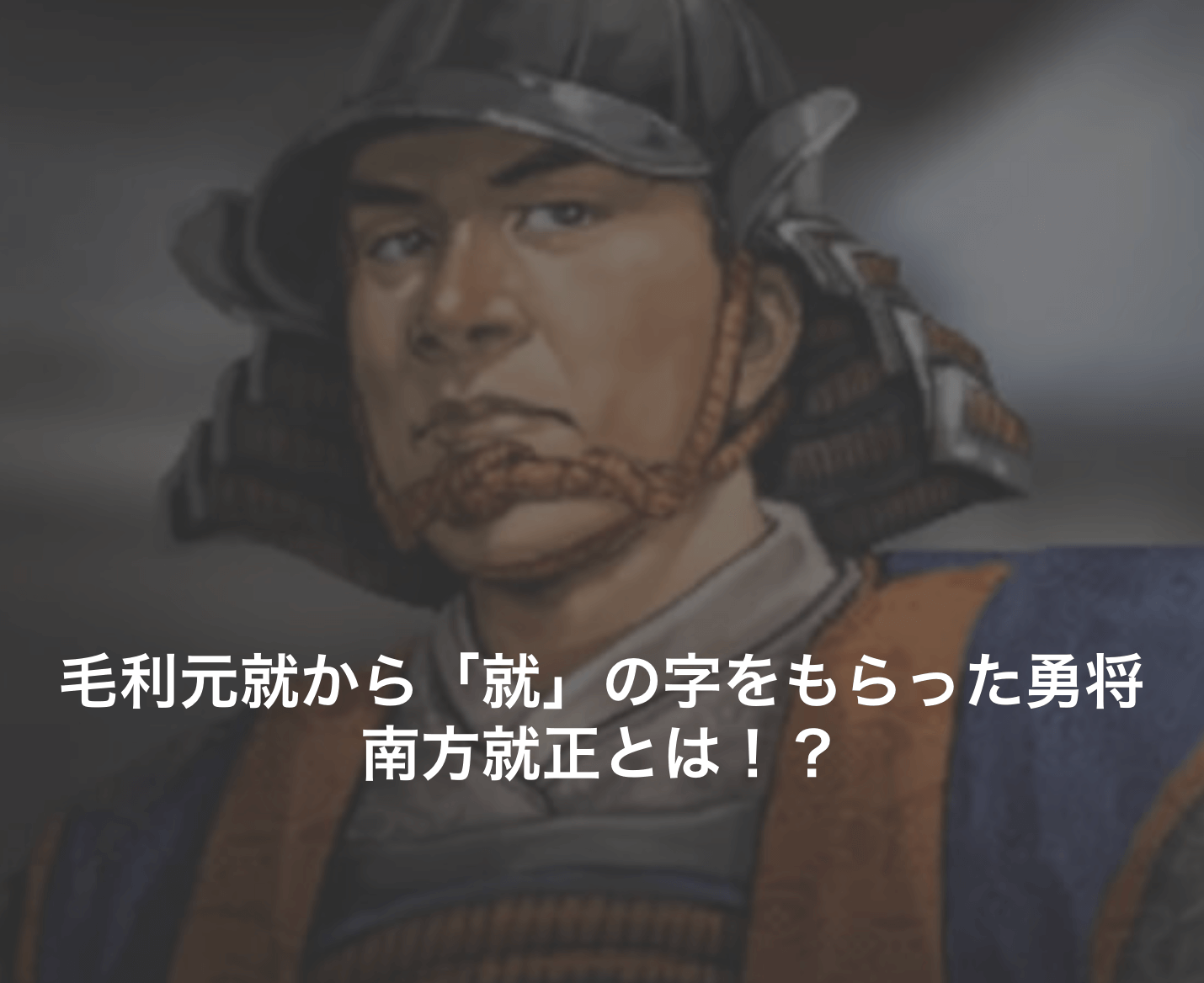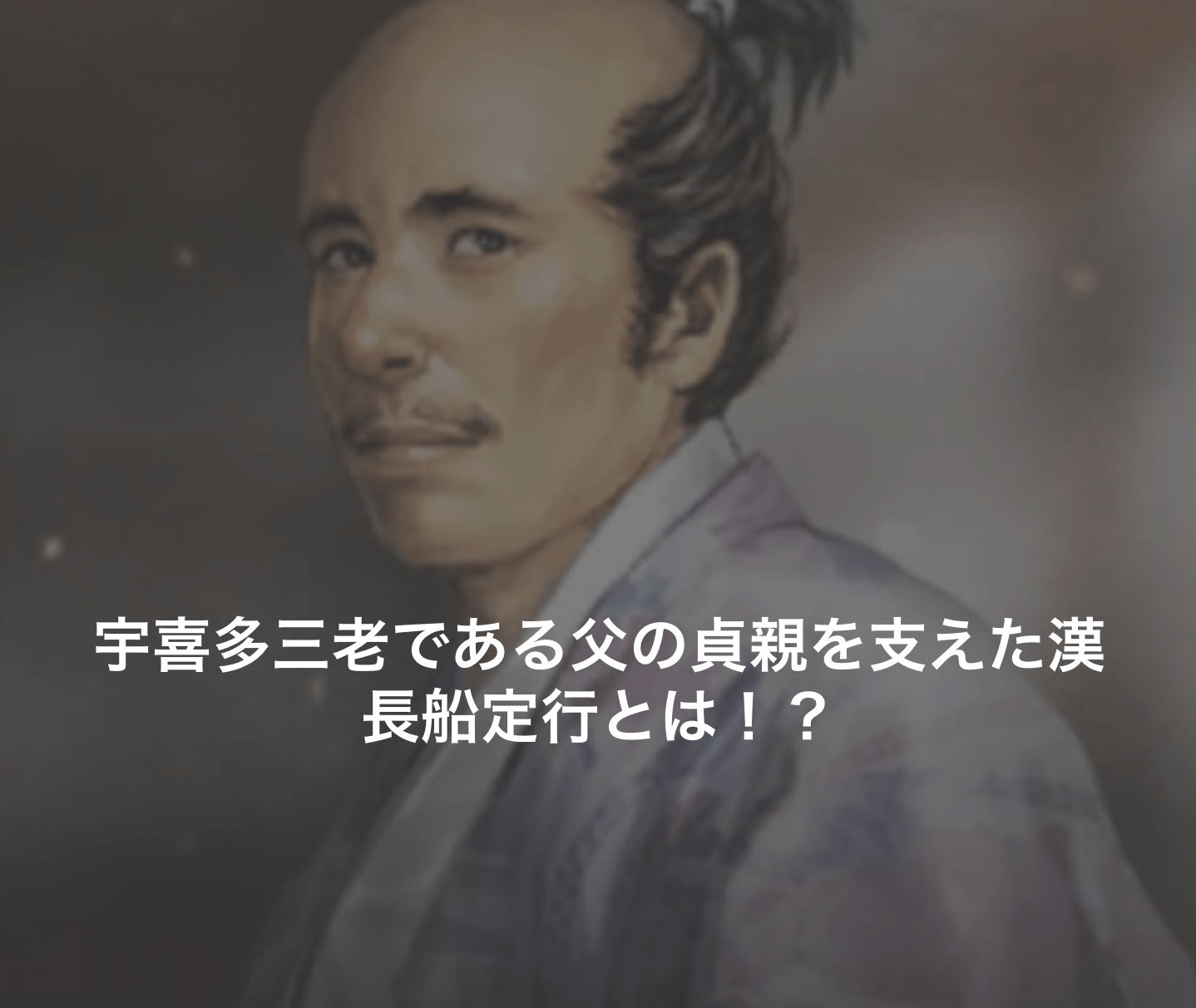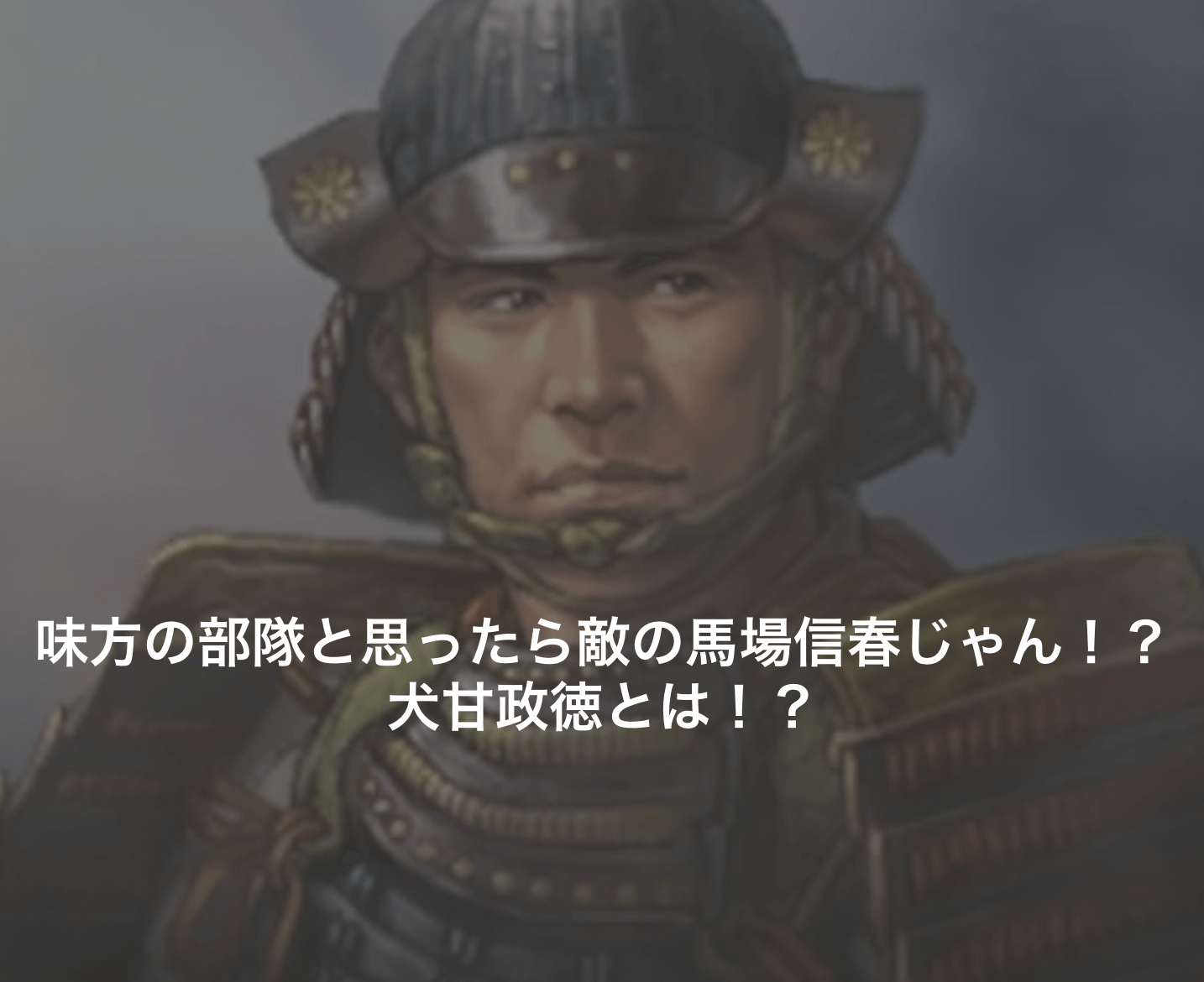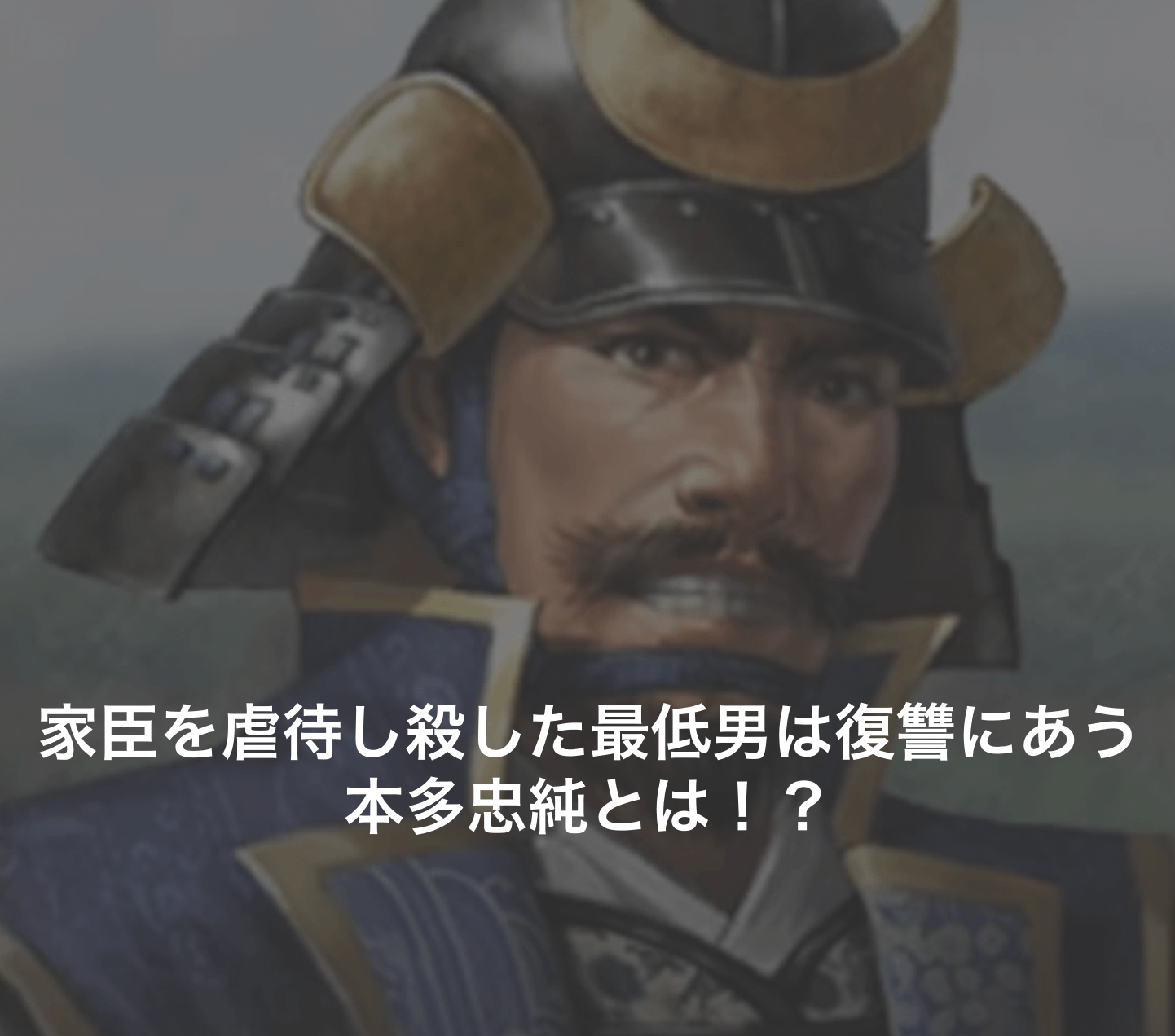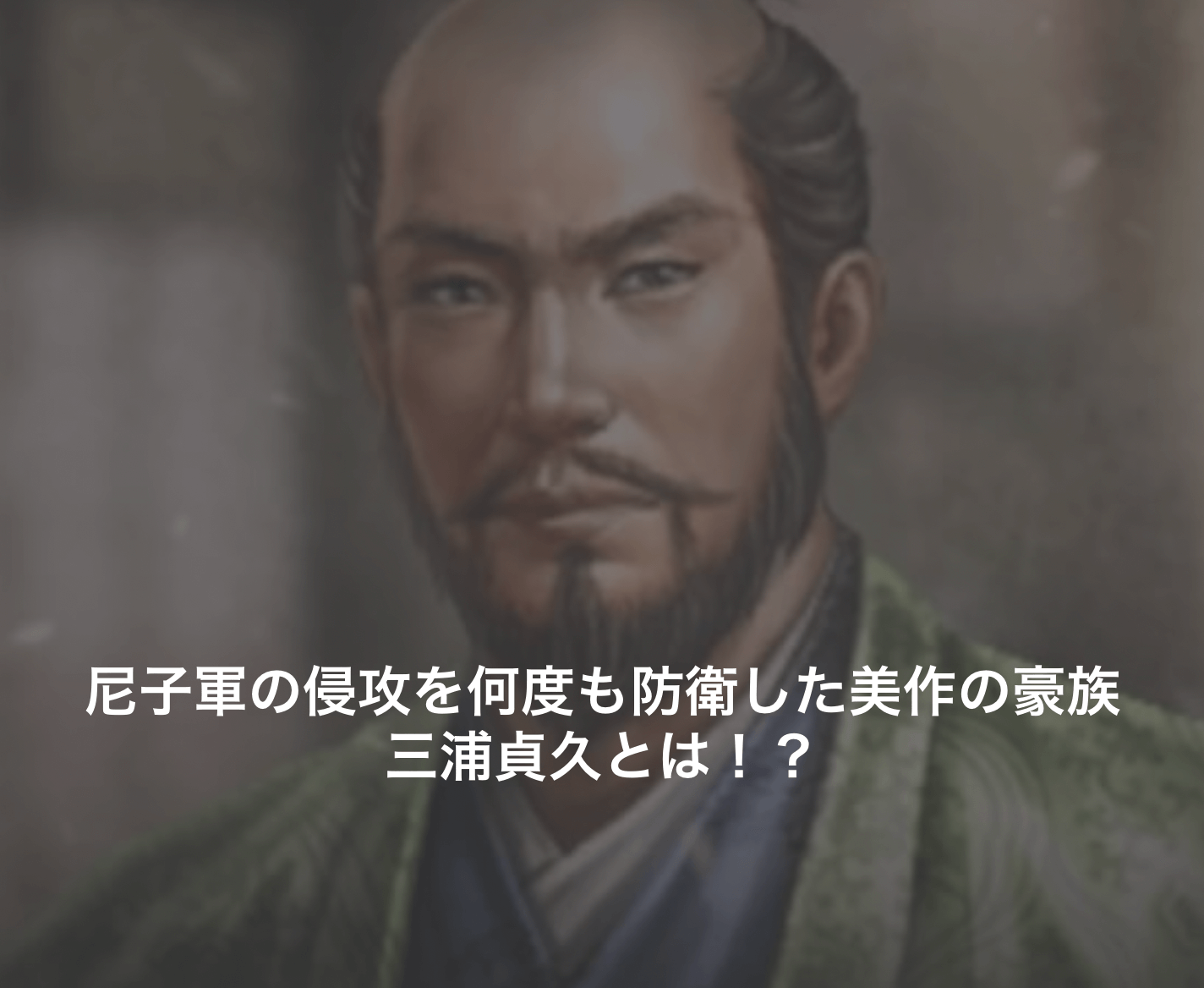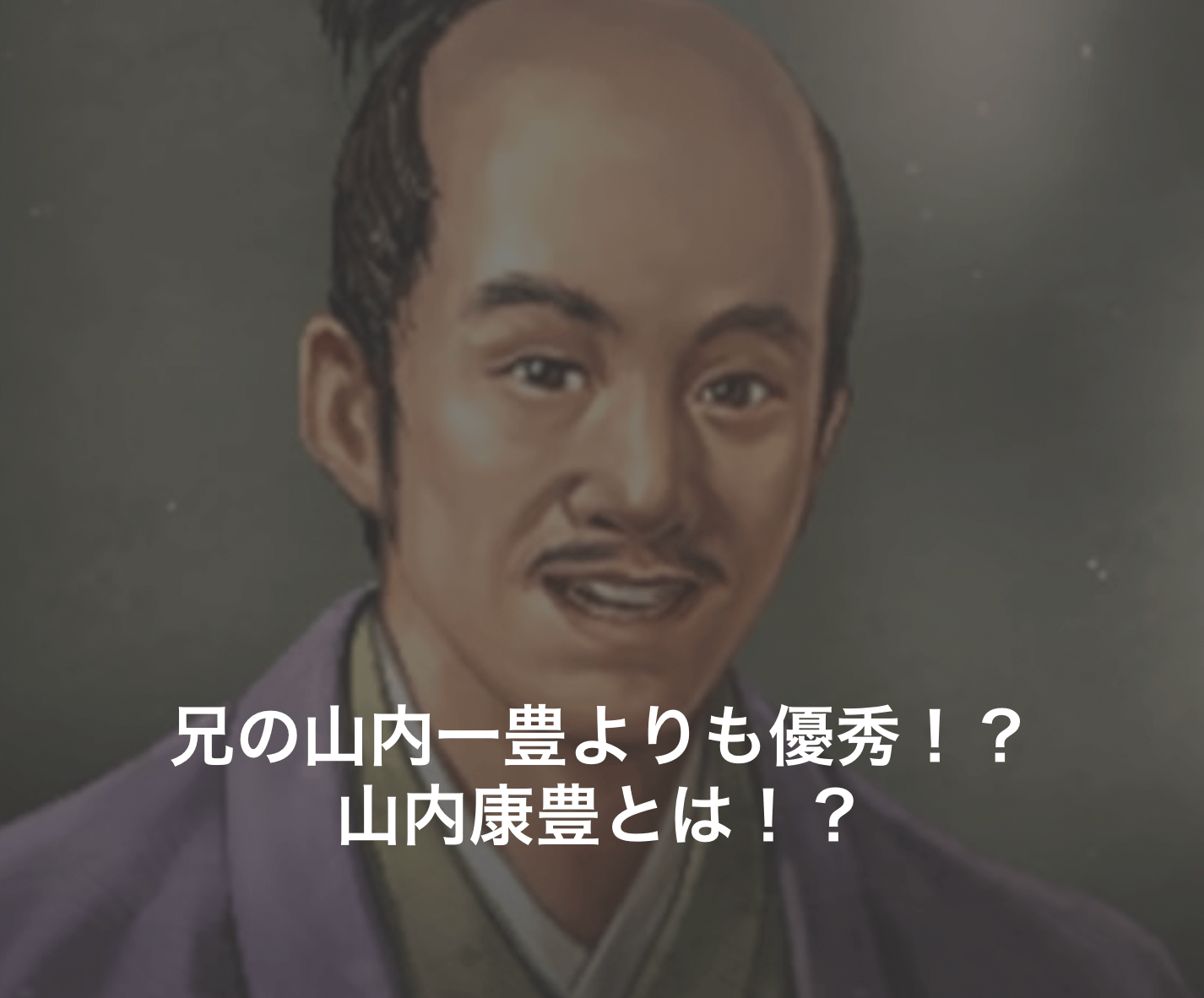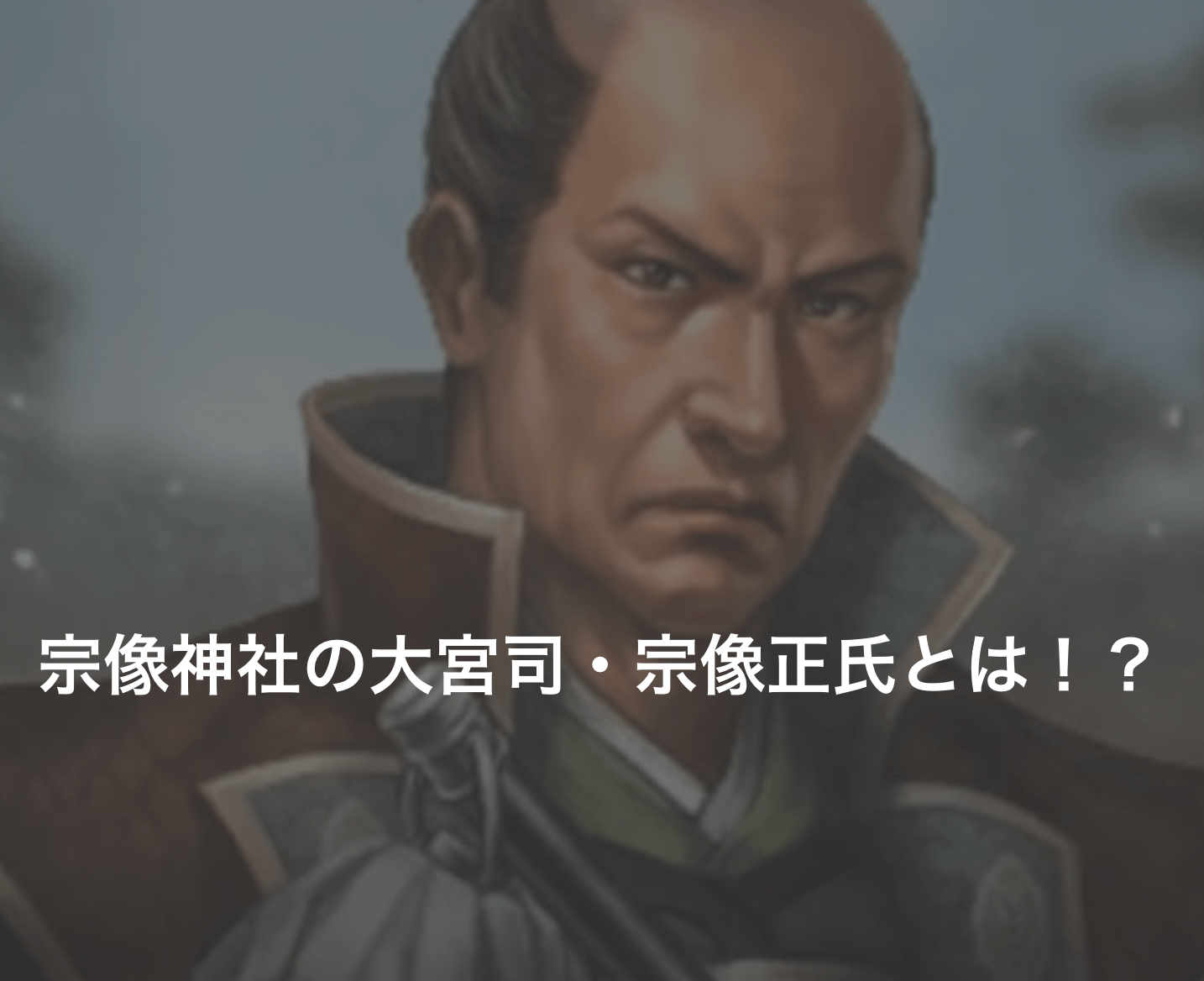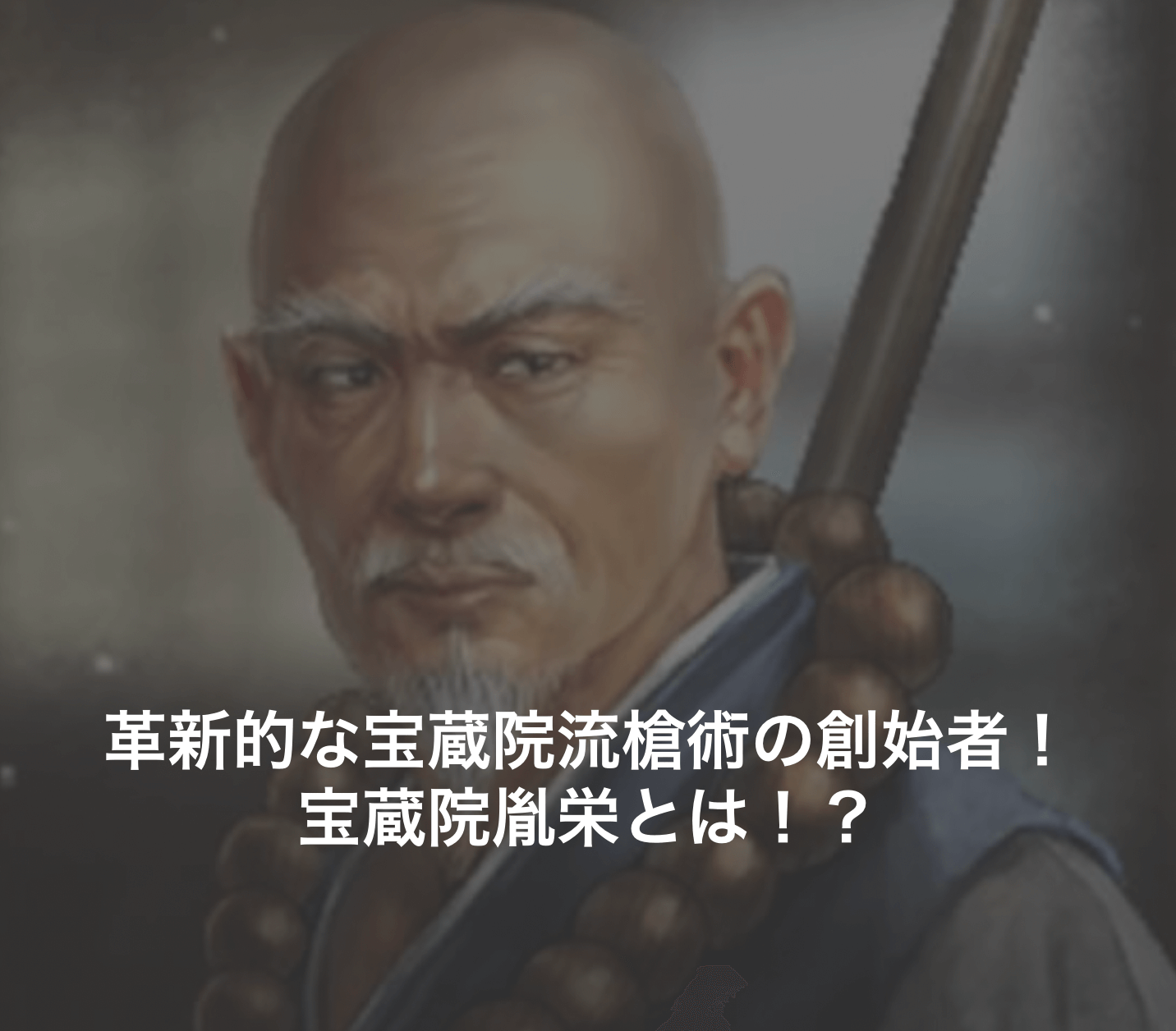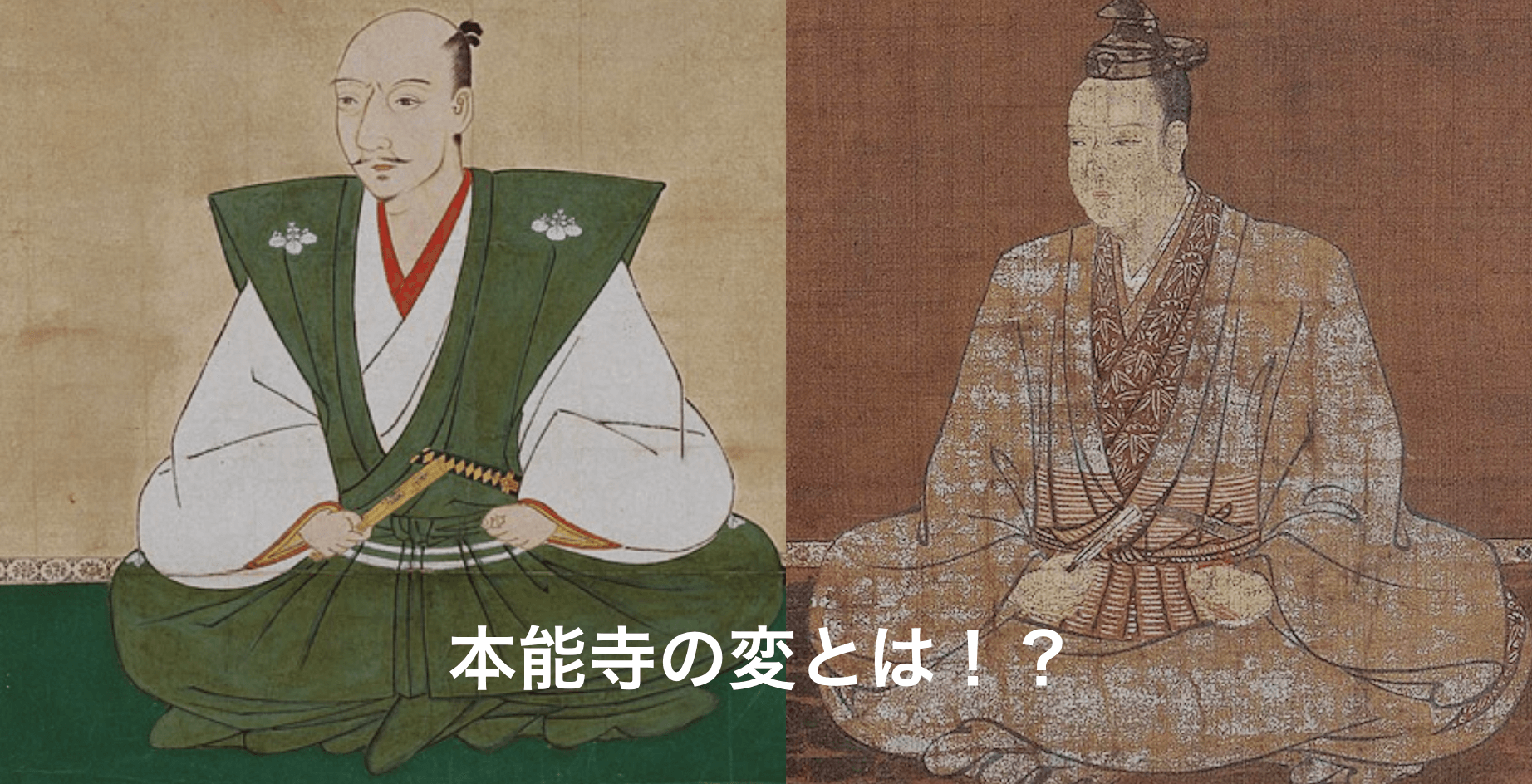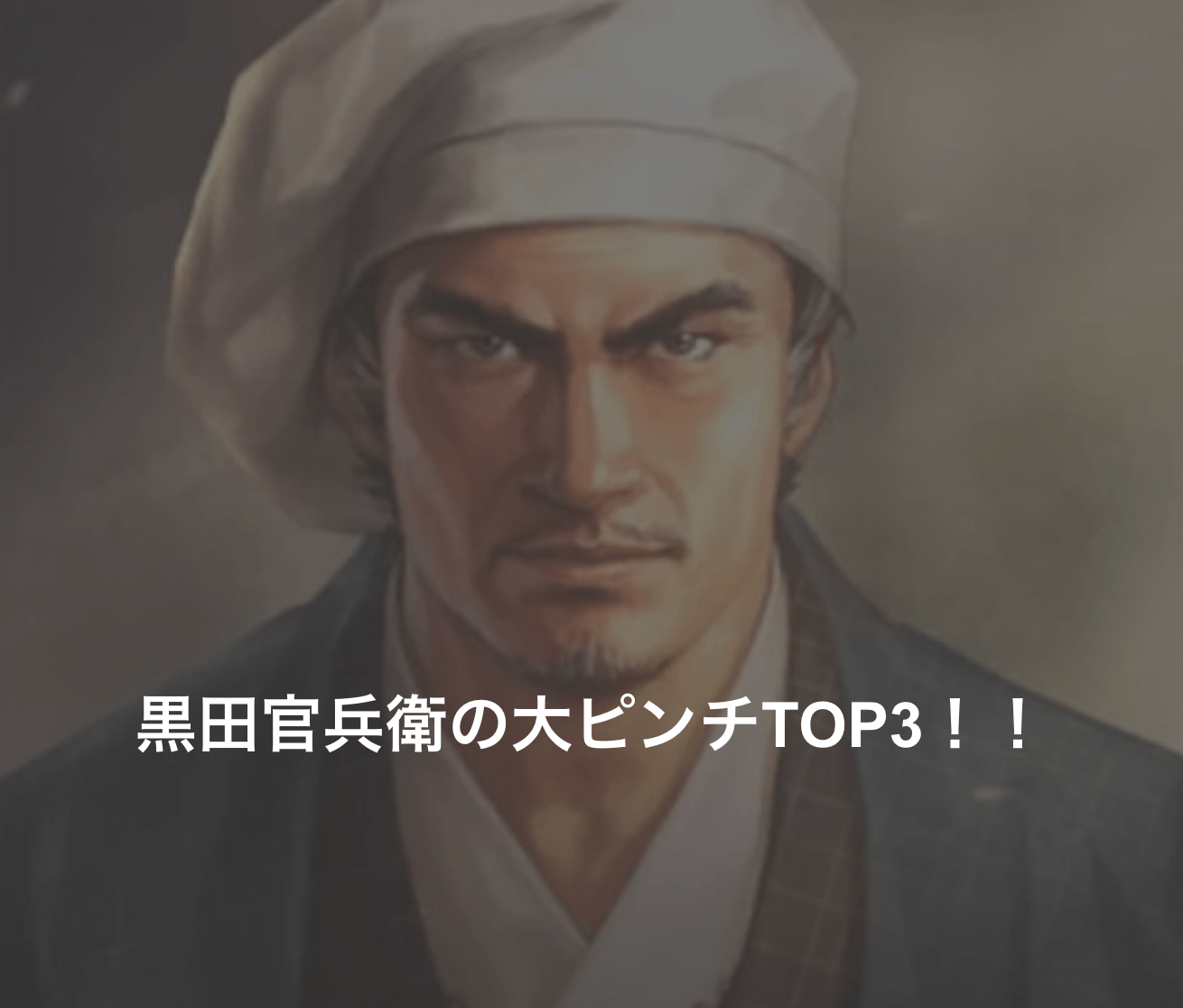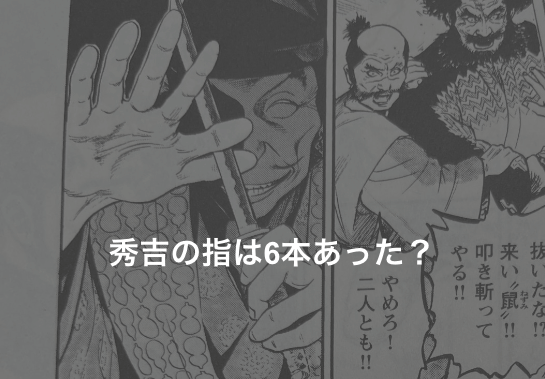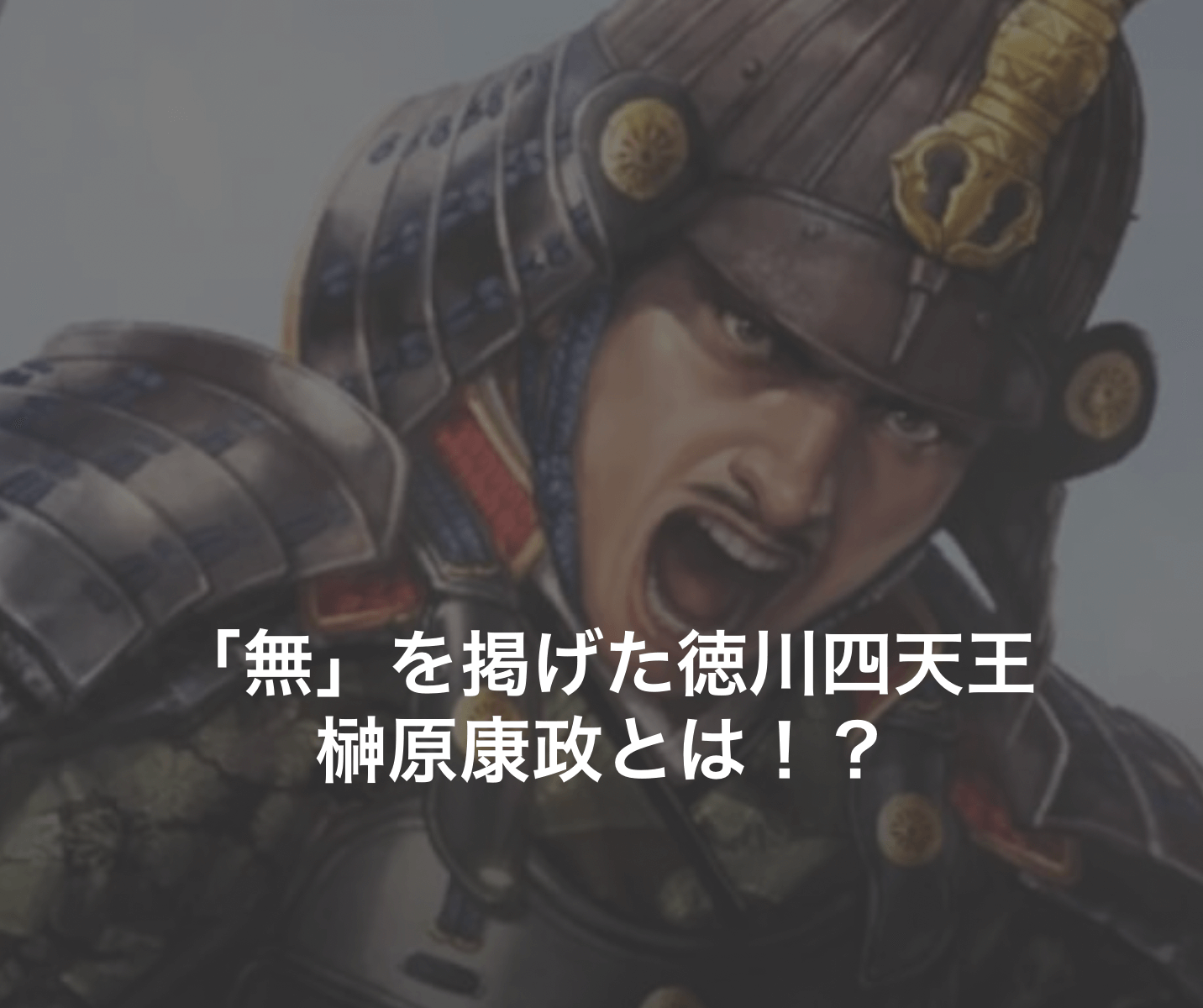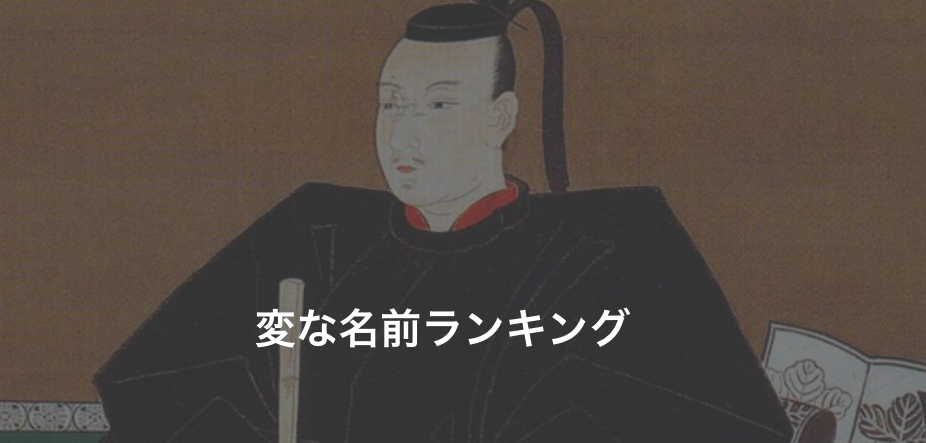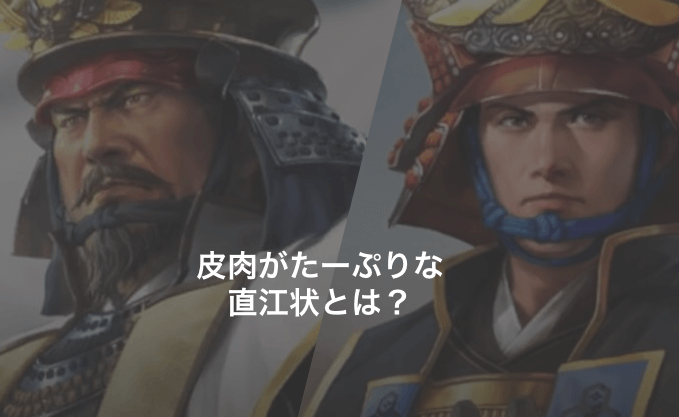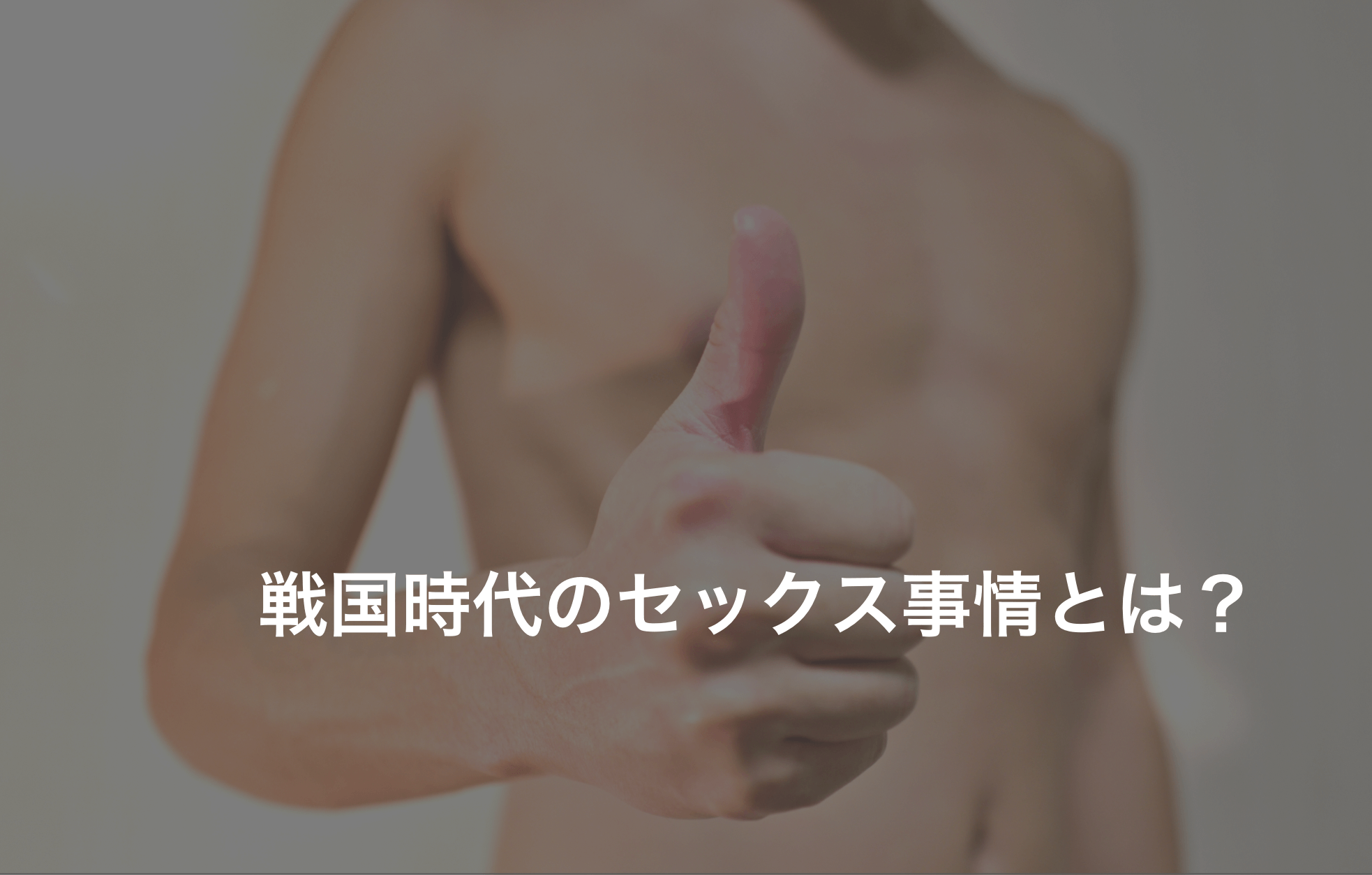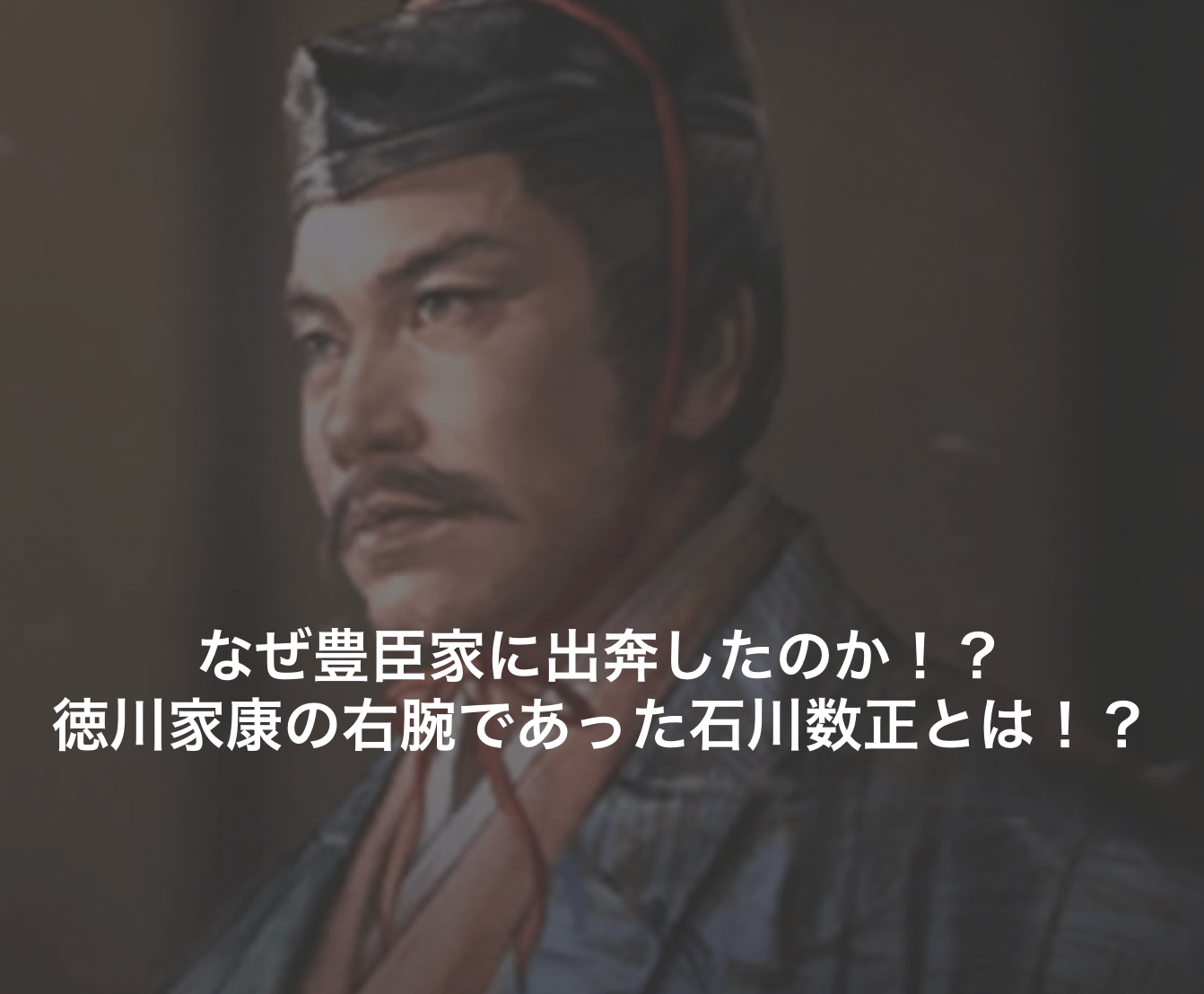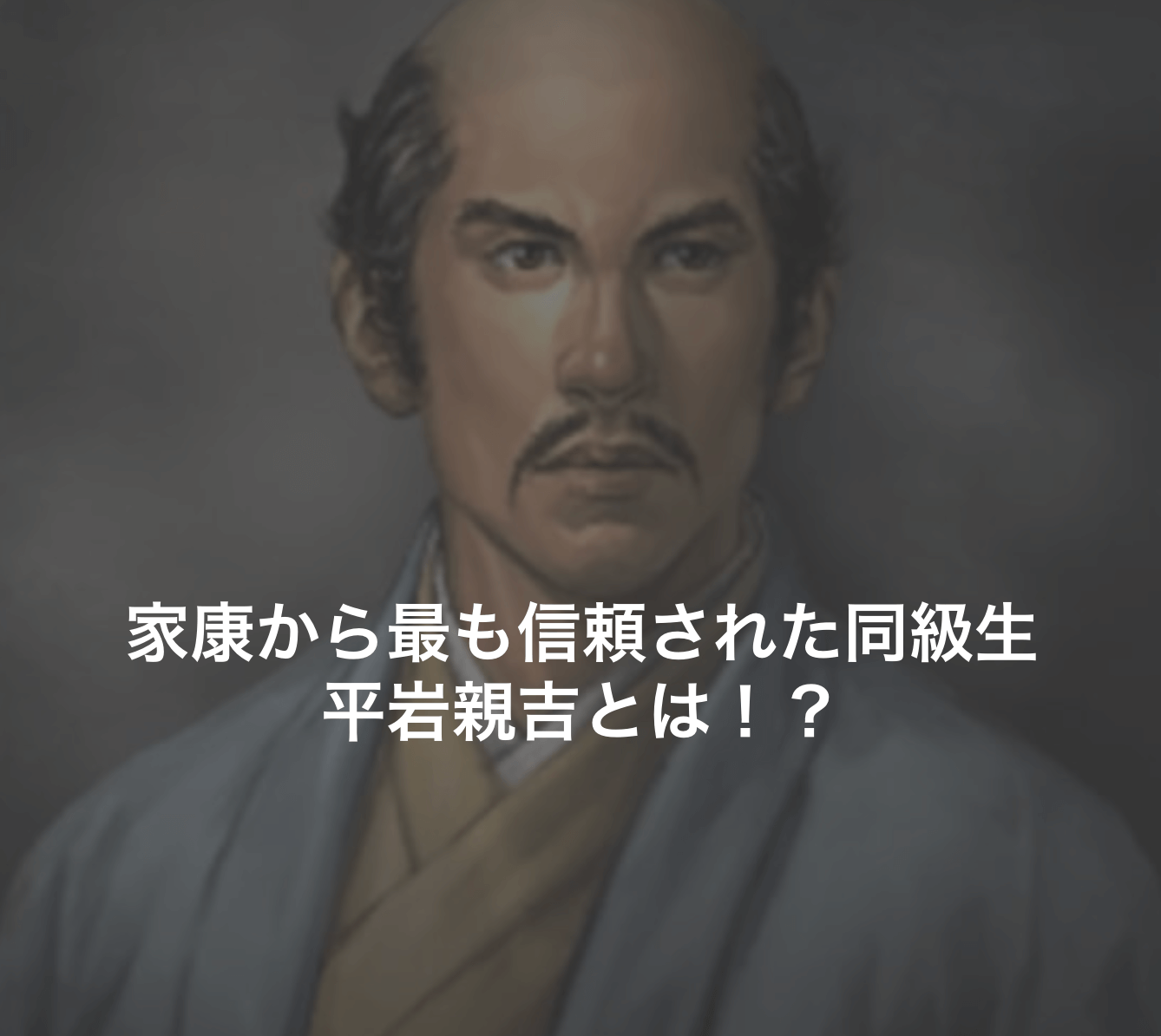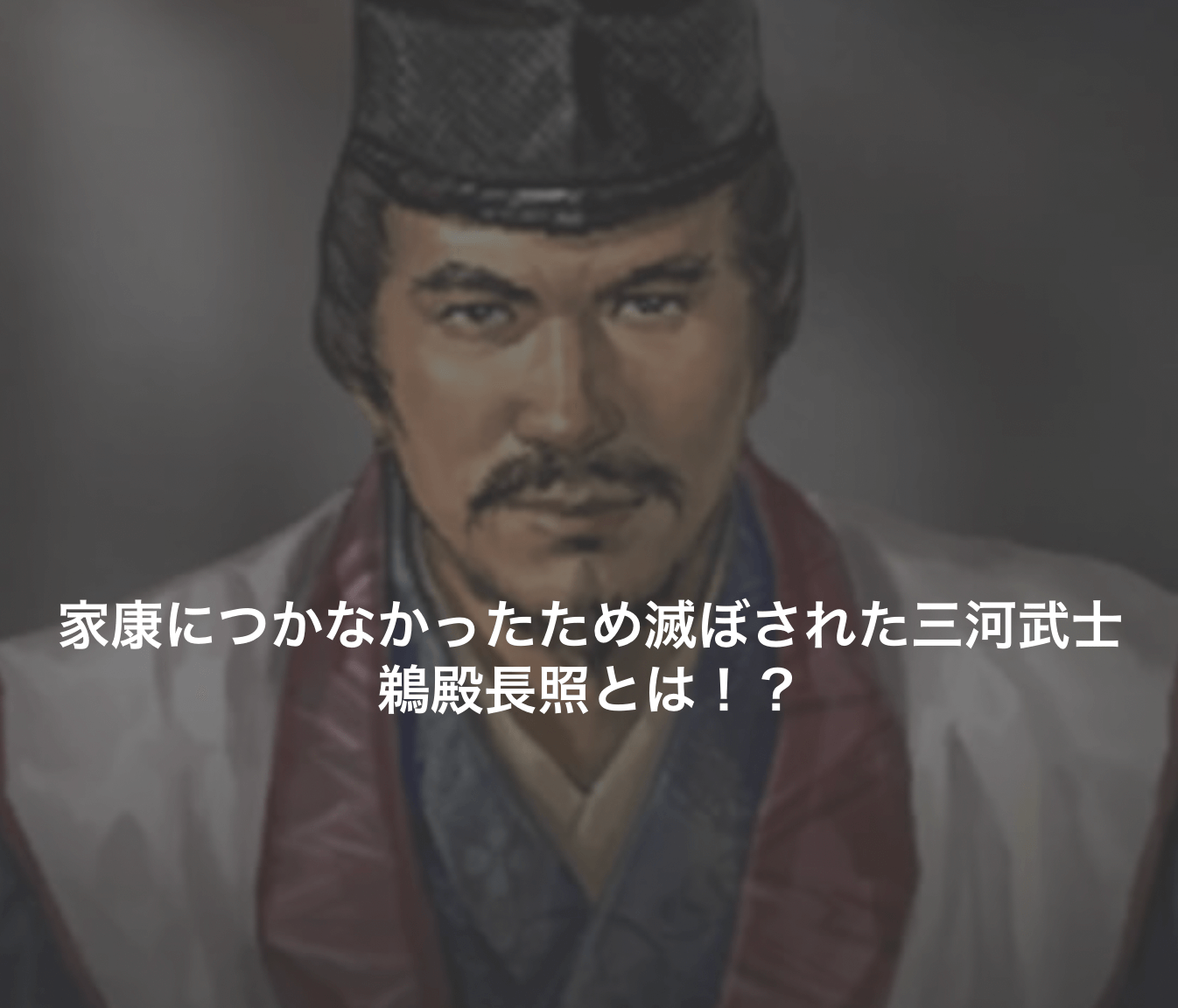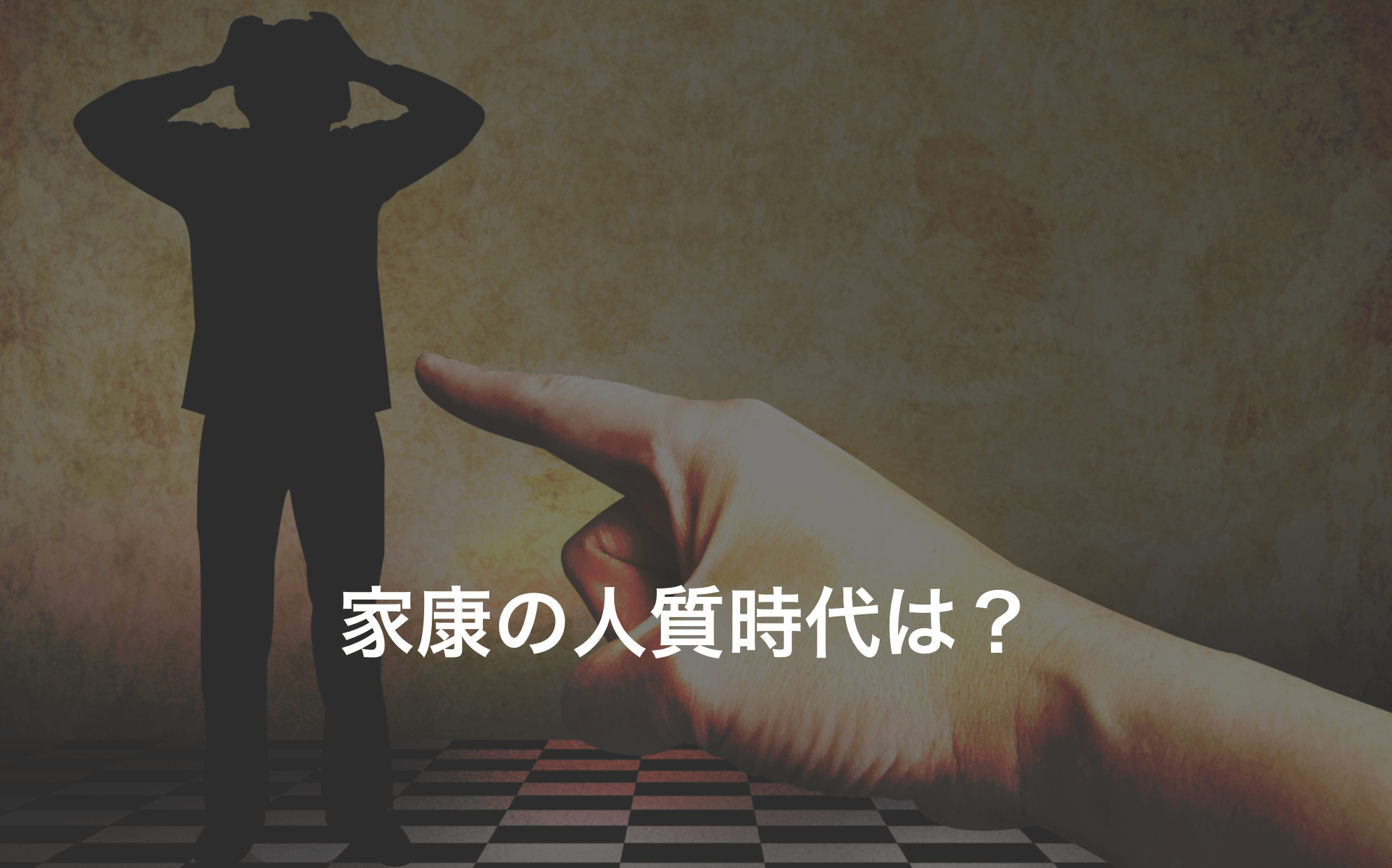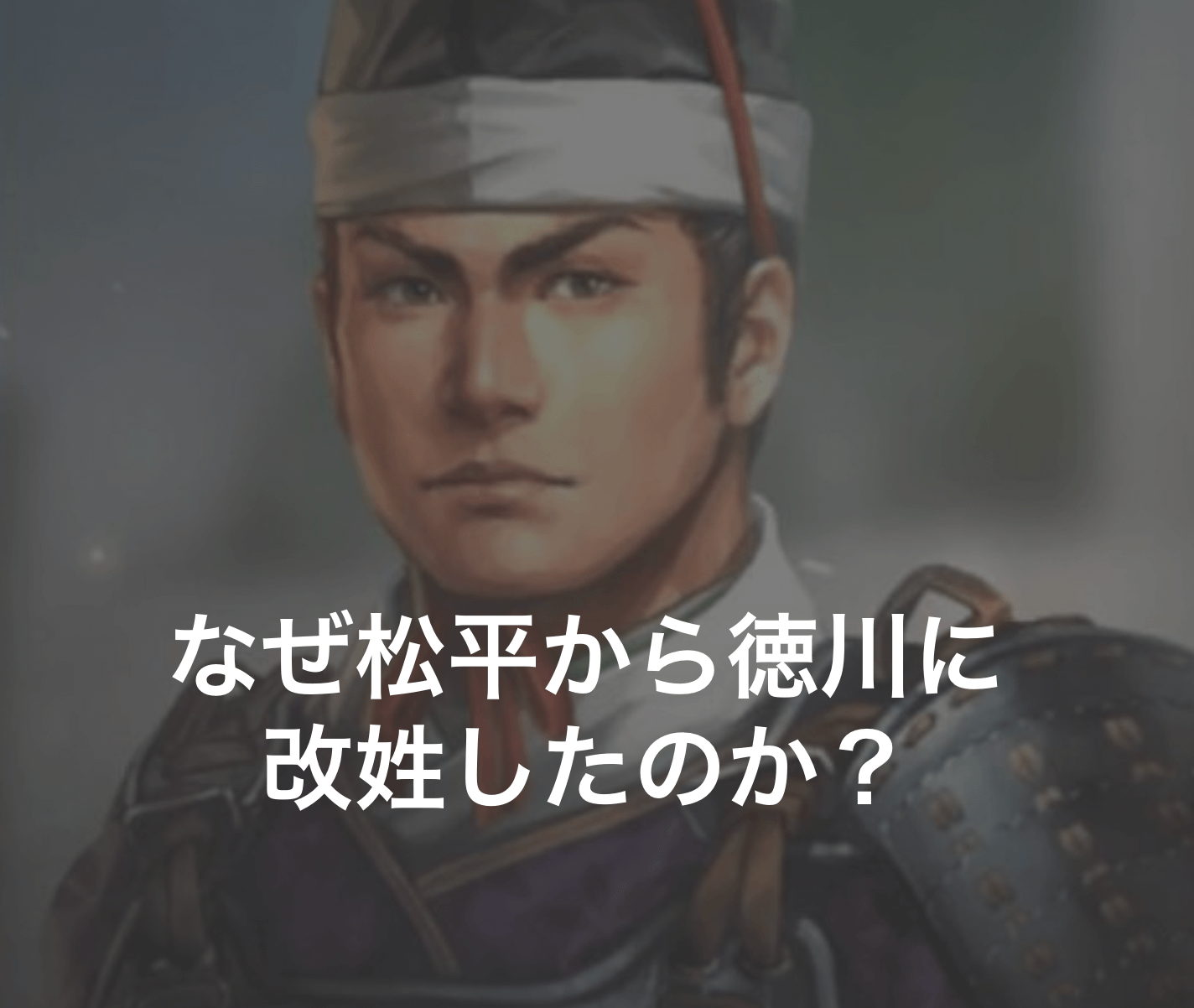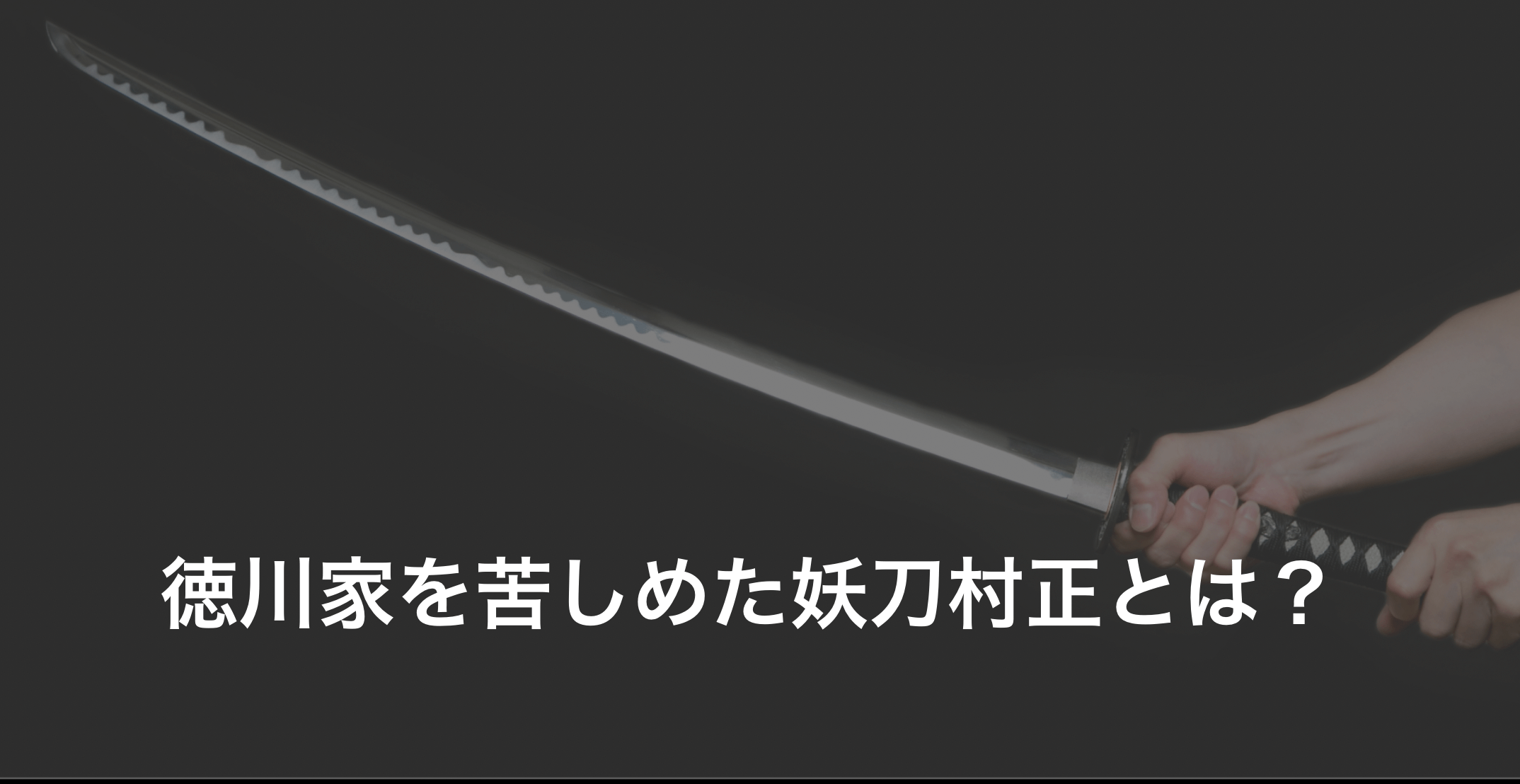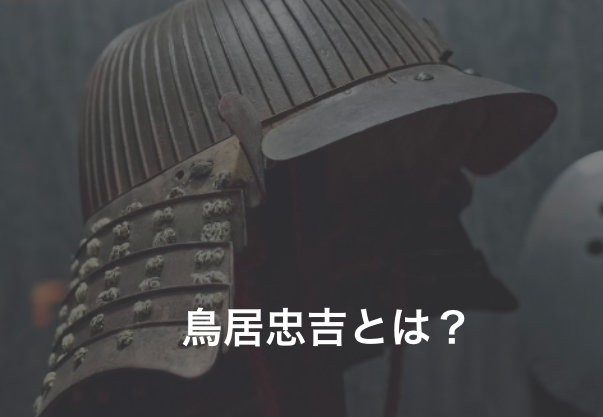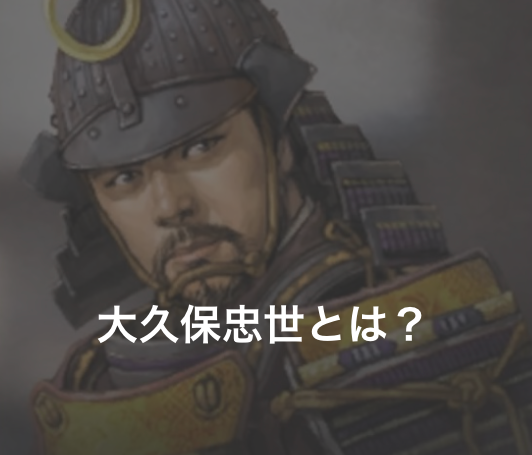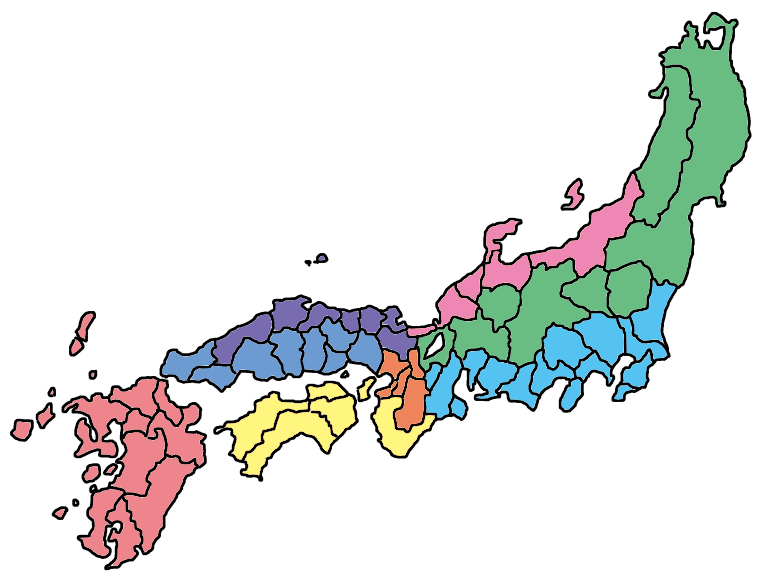views : 1437
上杉に近づき主君と対立したため戦死した大宝寺氏の重臣である土佐林禅棟(とさばやしぜんとう)とは?【マイナー武将列伝】
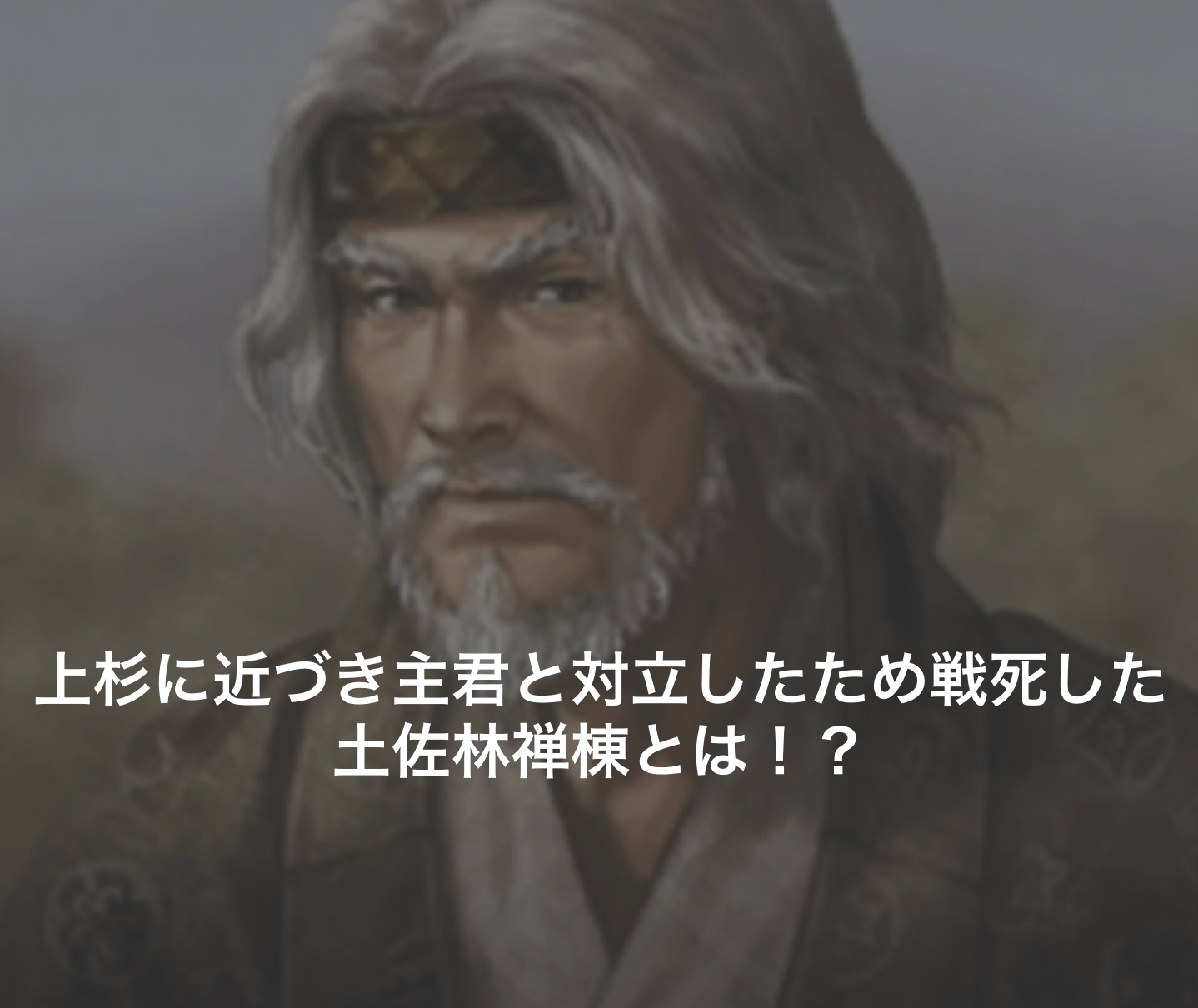
こんにちは、歴史大好きtakaです。
今回紹介するのは、大宝寺氏の家臣である土佐林禅棟(とさばやしぜんとう)です。
一体何をしたのでしょうね?
さっそく行ってみよう。
目次[非表示]
土佐林禅棟の生まれ
土佐林氏は会津や平泉と共に東北仏教文化の中心であった羽黒山の別当職を務めていた家柄で、大宝寺氏と同等の勢力を誇っていたが、文明9年(1477年)に大宝寺氏との抗争によって滅ぼされます。
しかし天文年間(1532年から1555年)に土佐林禅棟が大宝寺氏に仕え、その筆頭格の重臣となっていたました。
出羽国藤島城主。
生年は不明ですが、ゲーム信長の野望では1504年と設定されています。
大宝寺氏の家臣として活躍する
天文10年(1541年)に主君の大宝寺晴時が没すると剃髪し、杖林斎禅棟と号した。
晴時の死後は大宝寺義増の擁立に尽力するも、義増に統率力が無く領内では内紛が絶えなかった。
元々結びつきのあった越後の本庄繁長や、惣領が殺され一時期庄内に逃亡してきた小野寺景道を匿った縁で小野寺氏との交流が生まれ、繁長や小野寺氏らの援助を得ることで大宝寺氏は命脈を保ったと言われている。
土佐林禅棟は大宝寺氏の筆頭家臣として、幕府中枢との外交を担い活躍していきます。
永禄5年(1562年)頃には、幕府政所執事・伊勢貞孝に書状を送り、子が死去した際に13代将軍・足利義輝の弔問を受けたことに御礼を述べている。
この伊勢氏が松永久秀に討たれて没落すると、伊勢氏の代官であった蜷川親世が出羽への下向を打診し禅棟は承認している。
永禄8年(1565年)に義輝が松永久秀らに弑殺されると(永禄の変)、蜷川親世は所領を捨て出羽へ逐電したが、村山郡寒河江荘高松氏に寄寓しそこで死去した。
親上杉派となったため当主に攻められる
永禄11年(1568年)、甲斐国の武田信玄の誘いによって本庄繁長が上杉輝虎(後の上杉謙信)に対して反乱を起こしたとき、大宝寺義増はかつてから交流があった本庄氏に与します。
しかし、上杉氏に軍を差し向けられ大宝寺氏は降伏・臣従し、和睦の条件として大宝寺義氏が春日山城に人質として送られた。
この上杉氏との和睦締結に、土佐林禅棟は尽力していました。
 taka
takaこの頃に土佐林禅棟は親上杉派に傾いていったのでしょう。
永禄12年(1569年)、大宝寺義増の隠居により藤島城主・土佐林禅棟の後見を受け、大宝寺義氏が尾浦に帰参し家督を相続する。
元亀元年(1570年)、土佐林氏と関係の深い越後国人・大川長秀が尾浦城に攻め込むと、大宝寺義氏と土佐林禅棟は対立。
義氏は本庄繁長を通じて上杉謙信に調停を依頼し事態を収拾させた。
その際、土佐林禅棟は流言を信じて疑心暗鬼となり横山城(三川町)に遁走してしまった。
するとその翌年の元亀2年(1571年)に、今度は禅棟配下の国人である竹井時友が大宝寺氏に対し反乱を起こし谷地館に篭城する。
大宝寺義氏はこれを機とし挙兵し、土佐林氏・反大宝寺勢力を徹底的に討伐した。
このときに土佐林禅棟は戦死。
大宝寺義氏はというと、その後弱った家中を軍政の面で縛り上げ、出羽のうち田川郡・櫛引郡・遊佐郡の3郡を手中に収めるなど大宝寺氏往来の勢力を復権させた。
信長の野望での土佐林禅棟
ゲーム信長の野望での土佐林禅棟のパラメーターを見てみましょう。
統率 36 (1936 位)
武勇 46 (1561 位)
知略 58 (1032 位)
内政 50 (1322 位)
外政 52 (1216 位)
合計 242 (1603 位)
2200人中の順位です。
若干文官よりのステータスで、全体的に低めです。
流言を信じたのに知略58もあるのかって感じです。
まとめ
いかがでしたか?
大宝寺氏の重臣として主に中央政権との外交を担った土佐林禅棟。
大宝寺氏3代に渡り仕えますが、上杉氏の魅力に取り憑かれ、反乱を起こすも大宝寺義氏に鎮圧され戦死してしまいました。
大宝寺義氏は「悪屋形」と呼ばれるほど領民からよく思われていなかったので、土佐林禅棟が反乱に成功しなくても滅んでいます。
それでは、今後もマイナー武将列伝の記事をアップしていきますのでよろしくお願いいたします。