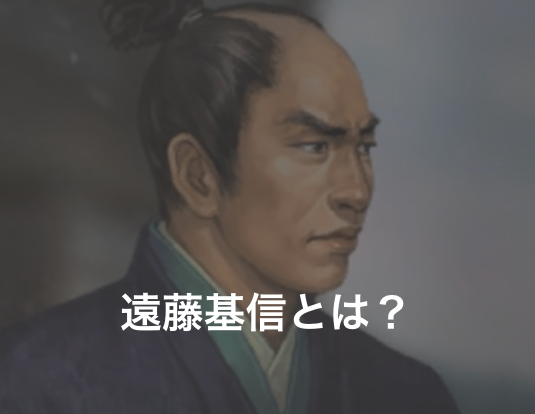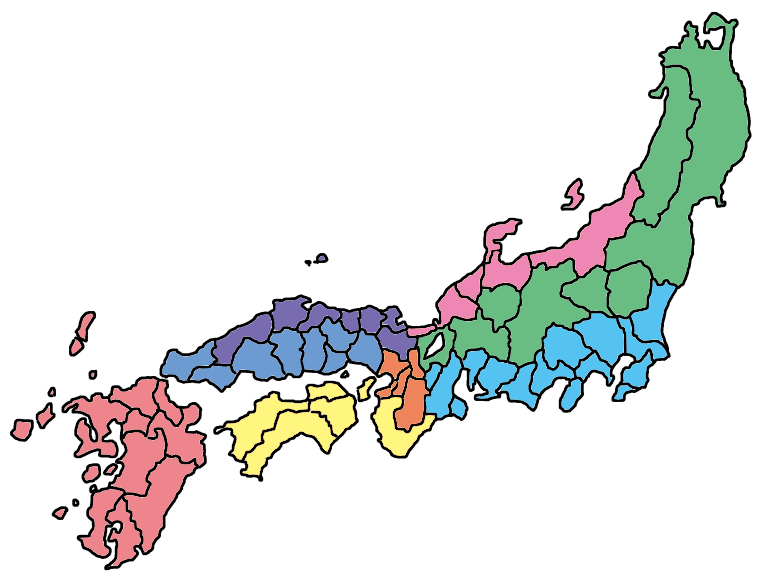武将名鑑【信長の野望 新生】

小早川隆景(こばやかわたかかげ)

小早川隆景(こばやかわたかかげ)
| 小早川隆景 の能力値 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
統率

出陣部隊の防御力、城の防御力に影響する。 |
91 (23 位) | ||||
武勇

出陣部隊の攻撃力、強攻時に敵城に与えるダメージ、 |
75 (224 位) | ||||
知略

出陣部隊の包囲時のダメージ量、城の包囲時の防御力、 |
96 (9 位) | ||||
政務

城の収入に影響する。 |
86 (52 位) | ||||
| 合計 | 348 (17 位)2201人中 | ||||

| 小早川隆景 の基礎データ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 性別 | 男 | ||||
| 幼名 | 毛利徳寿丸 | ||||
| 仮名・通称 | 又四郎 筑前宰相 三原中納言 | ||||
| 法号・戒名 | 隆景寺殿前黄門泰雲紹閑大居士 黄梅院泰雲紹閑 | ||||
| 父 | 毛利元就 | ||||
| 養父 | 小早川興景 | ||||
| 母 | 妙玖 | ||||
| 配偶者・正室 | 問田大方(小早川正平の娘) | ||||

| その他のデータ | 列伝 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 誕生年 | 1533年 | 毛利元就の三男。安芸の豪族・小早川家を継ぎ、山陽地方の攻略にあたる。本能寺の変後は毛利家の存続をはかって豊臣秀吉に接近し、五大老の1人となった。 | |||||||||
| 死亡年 | 1597年 | ||||||||||
主義

革新、中道、保守の3種類ある。忠誠の増減に関係する。 |
保守 | ||||||||||
特性

武将の個性。政略、軍事など、様々な場面で効果を得られる。 |
|||||||||||
| 能弁 | 外交取次次の信用上昇増加 | ||||||||||
| 策謀 | 特殊な調略具申が可能 | ||||||||||
| 地の利 | 合戦で積極的に要所を襲撃 | ||||||||||
戦法

合戦で使える特殊な技。 |
|||||||||||
| 智の一矢 | 自部隊の防御上昇 自部隊の体力回復 | ||||||||||
| シナリオ | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年月 | シナリオ | 年齢 | |||||||||||||
| 1546年1月 | 信長元服 | 元服前 | |||||||||||||
| 1553年4月 | 尾張統一 | 21 | |||||||||||||
| 1560年4月 | 桶狭間の戦い | 28 | |||||||||||||
| 1570年4月 | 信長包囲網 | 38 | |||||||||||||
| 1582年5月 | 夢幻の如く | 50 | |||||||||||||
小早川隆景が登場する合戦
-
厳島の戦い [毛利元就の周防・長門平定]
1555年10月1日
広島県廿日市市宮島町一帯

展望から望む宮島風景
-
須々万沼城の戦い [毛利元就の周防・長門平定]
1557年2月28日 ~ 3月3日
山口県周南市須々万本郷
-
温湯城の戦い [毛利元就の石見・出雲平定]
1558年5月20日 ~ 8月25日
島根県邑智郡川本町
石見銀山争奪のため出雲への侵攻を図る毛利元就は、永禄元年(1558年)5月、子の吉川元春に尼子晴久に従う小笠原長雄が守る石見温湯城を攻撃させた。
まず小笠原長雄は尼子軍と共に別当城(邑南町)に陣を構えて迎え撃つが温湯城に退却。
5月20日、自ら大軍を率いて石見に入った毛利元就・毛利隆元・小早川隆景らの軍勢は、吉川元春の軍勢らと合流し1万2000の軍勢となり、温湯城を包囲した。
この時元就は、温湯城のすぐ東側に陣城である会下山城を作っている。
7月、毛利勢の石見侵攻に対し、出雲富田城の尼子晴久は自ら2万5千の援軍を率いて温泉津に着陣するが、豪雨の影響による増水で江の川を渡河できず温湯城を救援することができなかった。
その際に元就は小笠原氏の所領を江の川の北側へ移し、温湯城のある川本をはじめとした小笠原氏の本領の半分は吉川氏に与えられた。
-
山吹城の戦い [毛利元就の石見・出雲平定]
1559年7月
島根県大田市大森町
永禄元年の山吹城の戦いに敗れ、石見大森銀山を尼子晴久に奪われた毛利元就は、翌2年に銀山を奪還するべく山吹城攻略に向かう。
奥湯城の小笠原長雄を先陣とし、子の吉川元春・小早川隆景ら1万4000人に及ぶ軍勢で出陣した元就は、山吹城の向かいに位置する仙ノ山に本陣を置いた。
数日間の攻撃を試みたが、尼子方の山吹城主の本城常光の抵抗が激しかった。
落城が容易ではないことと、毛利氏の門司城を大友義鎮が攻め始めたこともあり退却を決意する。
撤退中に降露坂で尼子勢に追撃され毛利軍は敗走。
元就も命からがらに逃げるという混乱状態に陥ったと言われる。 -
門司城の戦い [毛利元就と大友宗麟]
1559年9月26日
福岡県北九州市門司区門司
-
門司城の戦い [毛利元就と大友宗麟]
1561年10月10日 ~ 11月5日
福岡県北九州市門司区門司
-
松山城の戦い [毛利元就と大友宗麟]
1562年9月 ~ 1563年1月27日
福岡県京都郡苅田町松山
永禄5年(1562年)9月、大友宗麟は毛利元就による筑前への連絡を断つ目的で尼子義久から出陣の要請を受けた。
宗麟は豊前に戸次鑑連(立花道雪)や吉弘鑑理らを派遣し、元就の家臣の勇将・天野隆重、内藤就藤、毛利元種・元員や杉氏の一族である杉重良が守る苅田松山城を包囲させた。
これに対し元就は、翌永禄6年(1563年)正月に、子の毛利隆元と小早川隆景らの大軍を周防府中(防府)に送り込んで松山城攻略の指揮をさせる。
正月27日の決戦で毛利方が勝利をおさめると、永禄7年(1564年)に第13代将軍足利義輝の仲介を受け入れて、大友氏と毛利氏は和睦し松山城は大友氏に引き渡された。
その後大友方の長野祐盛が松山城に入った。 -
大三岳城の戦い [毛利元就と大友宗麟]
1568年9月4日
福岡県小倉南区辻三
毛利元就は子の吉川元春・小早川隆景らに4万余の大軍を率いて豊前に上陸させると、大友宗麟に従う長野弘勝が守る豊前大三岳城を攻撃した。
9月4日、大三岳城は衆寡敵せず落城し、弘勝は討死し100余名の戦死者を出した。
翌5日までに、長野氏一門が置かれている諸城が落とされ、長野氏は壊滅した。
-
立花城の戦い [毛利元就と大友宗麟]
1569年5月18日
福岡県糟屋郡神宮町立花口
-
月山富田城の戦い [尼子勝久の再興戦]
1569年7月 ~ 1570年2月14日
島根県安来市広瀬町富田

山名鹿之助像
永禄12年(1569年)7月、出雲に侵入した尼子勝久の6000の軍は、かつて尼子氏の本城であった月山富田城を攻囲した。
尼子方に投降する城兵もあらわれるなか、わずか300の兵で富田城を守る城将の天野隆重・野村士悦らは、毛利元就に後詰を要請する。
これに対し元就は毛利軍の主力が九州から撤退してくるのを待つと、永禄13年(1570年)正月6日に総大将に毛利輝元をおき吉川元春・小早川隆景・児玉就久ら2万6000の軍勢で出雲に向かわせた。
天野隆重は寡兵で籠城している際に、月山富田城を明け渡して降伏すると見せかけ、やってきた尼子再興軍に奇襲をかけ秋上宗信らを撃退したり、浄安寺に伏兵とした入った山中鹿之助らに対して鉄砲や矢を猛射し勝利していいる。
毛利勢の援軍が到着し、2月14日に布部山の戦いで尼子勢を破ると、富田城の包囲は解かれた。
-
国吉城の戦い [備中兵乱]
1574年12月25日 ~ 1575年1月1日
岡山県高梁市川上町七地
浦上宗景と毛利輝元の和睦により、宇喜多直家も毛利氏に従い、直家と対立していた三村元親は織田信長に接触し、輝元に対して反乱を起こす。
天正2年(1574年)12月25日、小早川隆景は輝元の命を受けて元親の一族である三村政親のいる備中国吉城を2万の軍勢で攻撃する。
政親は5日間城を守った後、夜間に脱出し、翌年正月元日に国吉城は陥落した。
城内にいた兵士たちは見せしめとして全員斬首された。
兵乱後、毛利氏家臣の口羽春吉が入城した。
-
杠城の戦い [備中兵乱]
1575年1月8日
岡山県新見市上市
-
荒平山城の戦い [備中兵乱]
1575年1月17日 ~ 30日
岡山県総社市秦
-
鬼身城の戦い [備中兵乱]
1575年1月23日 ~ 29日
岡山県総社市山田
荒平山城を包囲しながら、毛利輝元方の小早川隆景は、天正3年(1575年)正月23日、毛利氏に通じた三村一族の成羽城主の三村親成らを先導にして、三村元親の実弟で上田氏の養子となっていた上田実親が居る鬼身城を攻撃する。
鬼身城は、備中南部を扼す要衝であった。
毛利氏の大軍に包囲された上田実親は、城兵の命と引き替えに同月29日に20歳という若さで自刃した。
-
松山城の戦い [備中兵乱]
1575年4月4日 ~ 5月22日
岡山県高梁市内山下
-
常山城の戦い [備中兵乱]
1575年5月24日
岡山県岡山市南区灘崎町迫川
毛利・宇喜多勢の攻撃により、三村方の諸城は次々と落城し、残るは常山城と松山城だけとなった。
連合軍は両城を分断して攻め、松山城が陥落し、三村元親が自害したため三村氏は滅亡した。
常山城は孤立無援となり、家臣たちは四国に落ち延びることを進言したが、元親の妹婿にあたる上野高徳は「元親に毛利氏からの離反を勧めたのは自分であり、元親やその一族が滅びたというのにおめおめと生き永らえることができようか」とこれを受け入れず抗戦を決意し、城内にはわずか100人ほどの兵が残った。
天正3年(1575年)5月24日、小早川隆景率いる毛利勢は宇喜多直家とともに常山城を攻撃する。
この小早川勢には三村親成・親宣父子も4,300ほどの軍勢を率いて従軍している。
激しい攻防戦の末、城方は敵を翻弄し抗戦したが最終的に城は陥落し、隆徳は一族と共に自害した。
常山城は滅亡し、毛利氏による備中国制圧が達成された。
翌年、常山城は毛利氏から宇喜多氏に渡り、戸川秀安が城主となった。
-
上月城の戦い [尼子勝久の再興戦]
1578年4月18日 ~ 7月5日
兵庫県佐用郡佐用町上月
-
忍山城の戦い [織田信長の中国平定]
1579年12月24日 ~ 25日
岡山県岡山市北区上高田
宇喜多直家によって美作祝山城が包囲されるなか、毛利輝元は小早川隆景らとともに大軍を率いて後詰に向かう。
天正7年(1579年)11月16日、宇喜多直家の属城となっていた備中忍山城の近くに布陣した輝元は、伯耆から吉川元春が到着するのを待って、12月24日から忍山城に総攻撃をかける。
毛利勢の吉川経言は宇喜多勢を追い返しその勢いで山下を焼き打ち城を取り囲み、夜半に城中に火を放ち外から攻め寄せた。
城兵は防戦に努めたものの衆寡敵せず、翌25日には落城した。
-
地蔵嶽城の戦い [長宗我部元親の伊予平定]
1580年1月
愛媛県大洲市大洲
天正7年(1579年)、地蔵嶽城主・宇都宮豊綱の家臣で菅田城主の大野直之は、長宗我部元親と結んで主君の豊綱を地蔵嶽城から追放し、城を乗っ取った。
これに危機感を覚えた伊予湯築城の河野通直は、毛利輝元に援軍を要請し、輝元から派遣された小早川隆景率いる援軍とともに地蔵嶽城を攻撃した。
毛利・河野勢の猛攻に耐えきれず、直之は降伏し、こののち宇都宮豊綱が再び城主に返り咲く。
-
辛川の戦い [織田信長の中国平定]
1580年3月13日
岡山県岡山市北区西辛川
宇喜多直家に属城の美作祝山城を包囲された毛利輝元は、自ら祝山城の救援に向かったが、宇喜多勢に阻まれて祝山城まで到達することができないでいた。
そのため輝元は、小早川隆景率いる15000の軍勢に直家の本領である備前に侵攻させたのである。
このとき病床にあった直家に代わり、弟で富山城主の宇喜多忠家が総大将ととなり、宇喜多家の宿老で辛川城の戸川秀安・達安らとともに備前・備中国境に近い備前辛川で小早川勢を迎え撃つ。
辛川城に近い一宮から富山城近くの矢坂まで、七段の陣を立てて防戦を張り、辛川村の北にある山陰には当時13歳で初陣であった戸川達安率いる一隊を忍ばせた。
天正8年(1580年)3月13日、備中高松城から加茂城を経て辛川城近くへと進んだ毛利勢は、真正面に陣取る宇喜多勢めがけて襲いかかります。
激しいぶつかり合いとなるも、宇喜多勢はこの間を見て退却を開始。
小早川軍は深追いし辛川村を通り過ぎたあたりで、山陰に潜んでいた戸川達安隊が飛び出し、毛利軍を挟み撃ちにした。
総崩れとなった小早川軍は、備前から兵を退領き領国へと退却していった。
この毛利軍の大敗は「辛川崩れ」と呼ばれる。
-
丸山城の戦い [羽柴秀吉の四国平定]
1585年7月2日 ~ 14日
愛媛県西条市氷見
四国平定を目指す羽柴秀吉は、中国の毛利輝元に伊予の侵攻を命じた。
毛利輝元は吉川元長・小早川隆景に中国8か国から集めた3万余の大軍をつけて伊予に送った。伊予宇摩・新居郡を勢力下におく石川氏と石川氏の実権を握っていた金子氏を討つため、伊予に上陸した毛利勢は、まず石川氏の居城である高峠城の支城丸山城を包囲する。
丸山城主の黒川広隆は戦わずして降伏開城すると、丸山城には輝元の家臣の香川広景が入った。
-
金子城の戦い [羽柴秀吉の四国平定]
1585年7月14日
愛媛県新居浜市金子
-
高尾城の戦い [羽柴秀吉の四国平定]
1585年7月15日 ~ 17日
愛媛県西条市氷見
-
野々市原の戦い [羽柴秀吉の四国平定]
1585年7月17日
愛媛県西条市野々市
高尾城の戦いに敗れた金子元宅は、7日17日、高尾城を自焼すると野々市原に600余の兵を率いて討って出た。
寡兵の金子勢に勝機はなく、玉砕を覚悟の出陣だったのだろう。
3万余の小早川勢に決戦を挑んだ長宗我部軍の援軍200を含めた総勢800余の金子勢は奮戦するも、ことごとく討ち取られた。
最期13人になるまで戦ったという。こののち首実検をした小早川隆景は元宅らの最期を讃え、野々市に首塚を築いて丁重に供養したという。
この首塚は、現在も千人塚として野々市に残る。
この戦で伊予における最大拠点を失った長宗我部氏は、その後伊予各地で敗戦し、毛利軍に屈することとなる。
-
仏殿城の戦い [羽柴秀吉の四国平定]
1585年7月20日
愛媛県四国中央市川之江町
金子城・高尾城を落とした吉川元長・小早川隆景ら羽柴勢は、伊予仏殿(川之江)城の攻略に向かった。
この仏殿城は讃岐と近接し、阿波・土佐両国にも通じる要衝で、天正10年(1582年)に長宗我部元親が攻略していた。
羽柴勢はここを足がかりにして、阿波・ 讃岐に侵攻した羽柴秀長との連携を強めようとしたのである。
仏殿城兵は戦わずに開城したことにより、伊予は平定された。関ヶ原の戦いの後、仏殿城には加藤嘉明が入っている。
-
小倉城の戦い [豊臣秀吉の九州平定]
1586年10月4日
福岡県北九州市小倉北区城内

小倉城
豊前門司城に集結した毛利輝元ら毛利勢と軍奉行(軍事の総指揮者)の黒田官兵衛らは、吉川元春・小早川隆景を中心に香春岳城主・高橋(秋月)元種の属城である豊前小倉城を攻撃する。
元種は、永禄10年(1567年)の岩屋城・宝満城の戦いで大友宗麟に高橋氏の惣領職を奪われた高橋鑑種の養嗣子で、このときは島津氏に従っていた。
毛利勢は、元種の実父である秋月種実に妨害されながらも10月4日に小倉城を落とす。
城兵の命と引き換えに小倉城城代の小幡玄蕃は自刃し、一命を助けられた城兵は香春岳城に退去した。
-
宇留津城の戦い [豊臣秀吉の九州平定]
1586年11月7日
福岡県築上郡築上町宇留津
-
香春岳城の戦い [豊臣秀吉の九州平定]
1586年11月20日 ~ 12月11日
福岡県田川郡香春町
-
松尾城の戦い [豊臣秀吉の九州平定]
1587年3月29日
宮崎県延岡市松山町
島津勢を豊後から逐った豊臣勢の東九州方面軍は、総大将・羽柴秀長を中心として黒田孝高・蜂須賀家政・毛利輝元・吉川元長・小早川隆景ら9万余の兵で、豊後から日向に侵入していく。
こうした動きに、それまで島津氏に従っていた日向の諸城も秀長に降ったが、日向松尾城(縣城)の土持久綱はに島津義久から「久」の字を賜っていたりと島津家への忠誠は高く依然として抵抗を続けていた。
このため松尾城は包囲され、3月29日に久綱は降伏開城し、島津家久を頼って日向佐土原城に落ちていく。
-
碧蹄館の戦い [文禄の役]
1593年1月26日
京畿道高陽市
小早川隆景が登場する記事一覧
おすすめ記事一覧
-
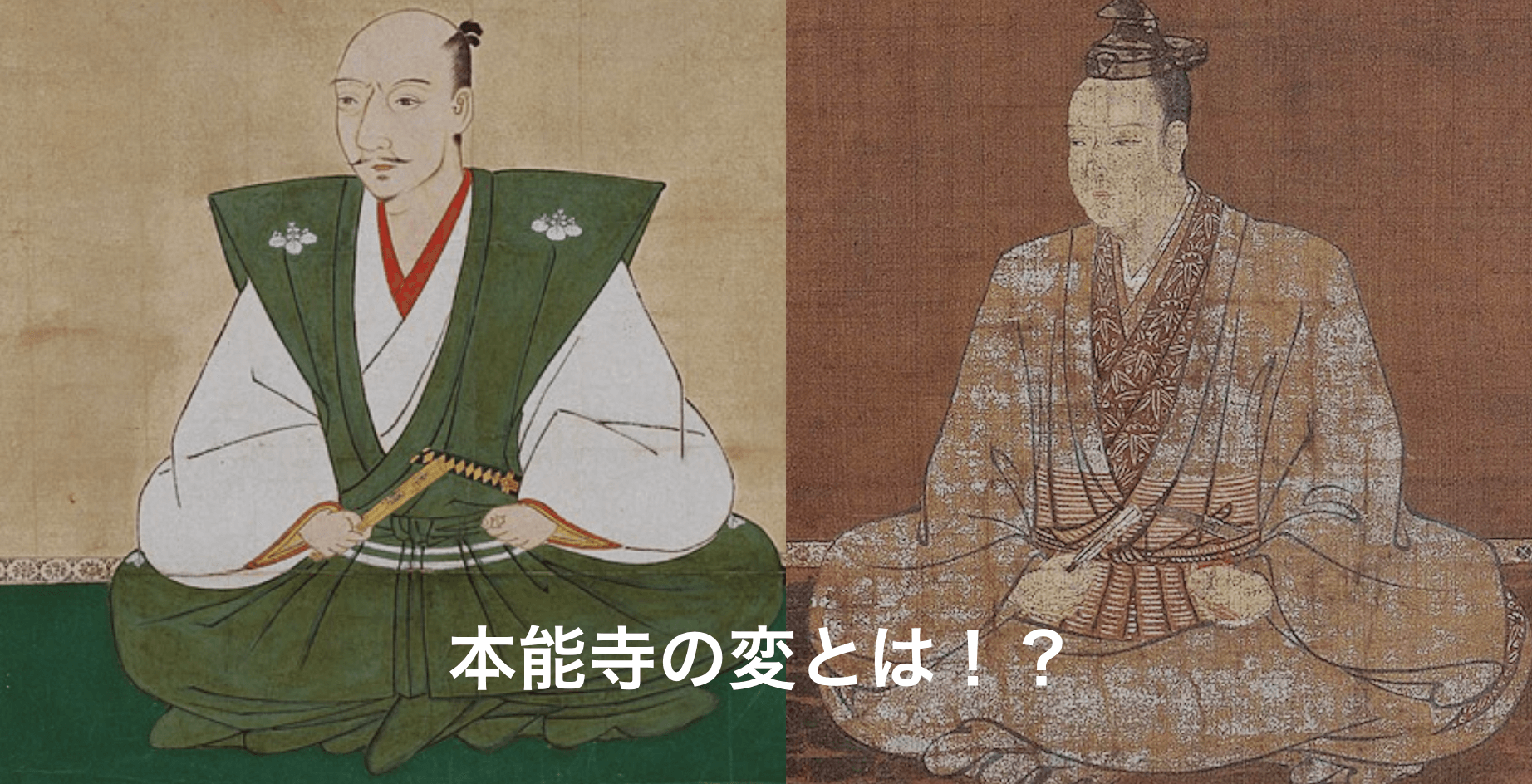
歴史イベント
【新解釈】本能寺の変の真実!光秀が謀反を決意した真の動機とは?
-

ランキング
戦国武将のかっこいい異名・あだ名ランキングTOP10
-
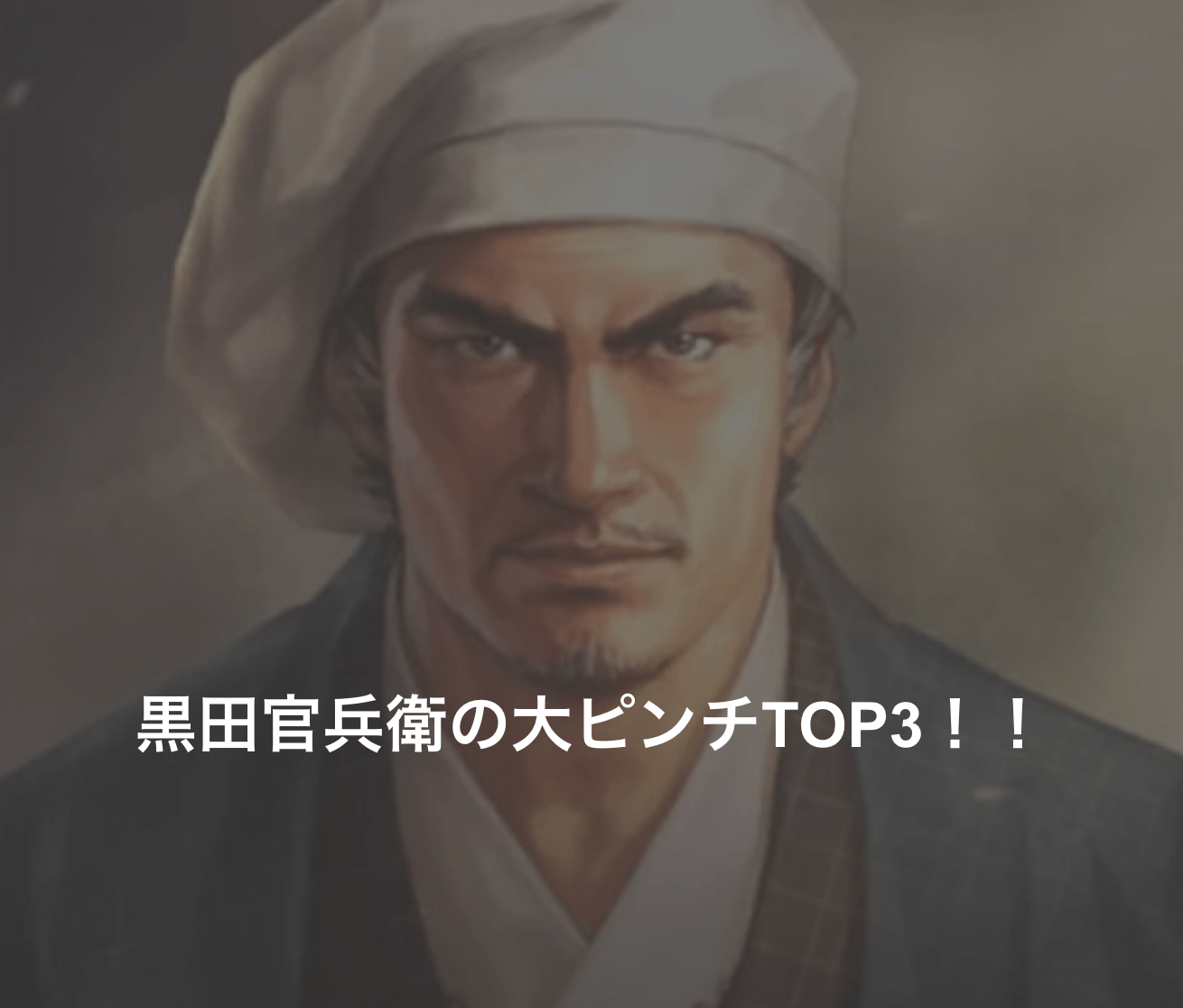
ランキング
障害が残るほどの苦悩、遺書を残し死を覚悟した懺悔など黒田官兵衛の大ピンチTOP3!!
-

ランキング
織田信長を裏切り窮地に陥れた戦国武将ランキングTOP5
-
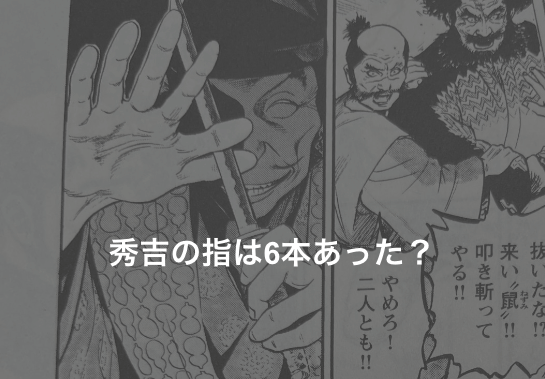
戦国時代の逸話
豊臣秀吉の指は6本あった?その真相に迫る【戦国時代の逸話】
-
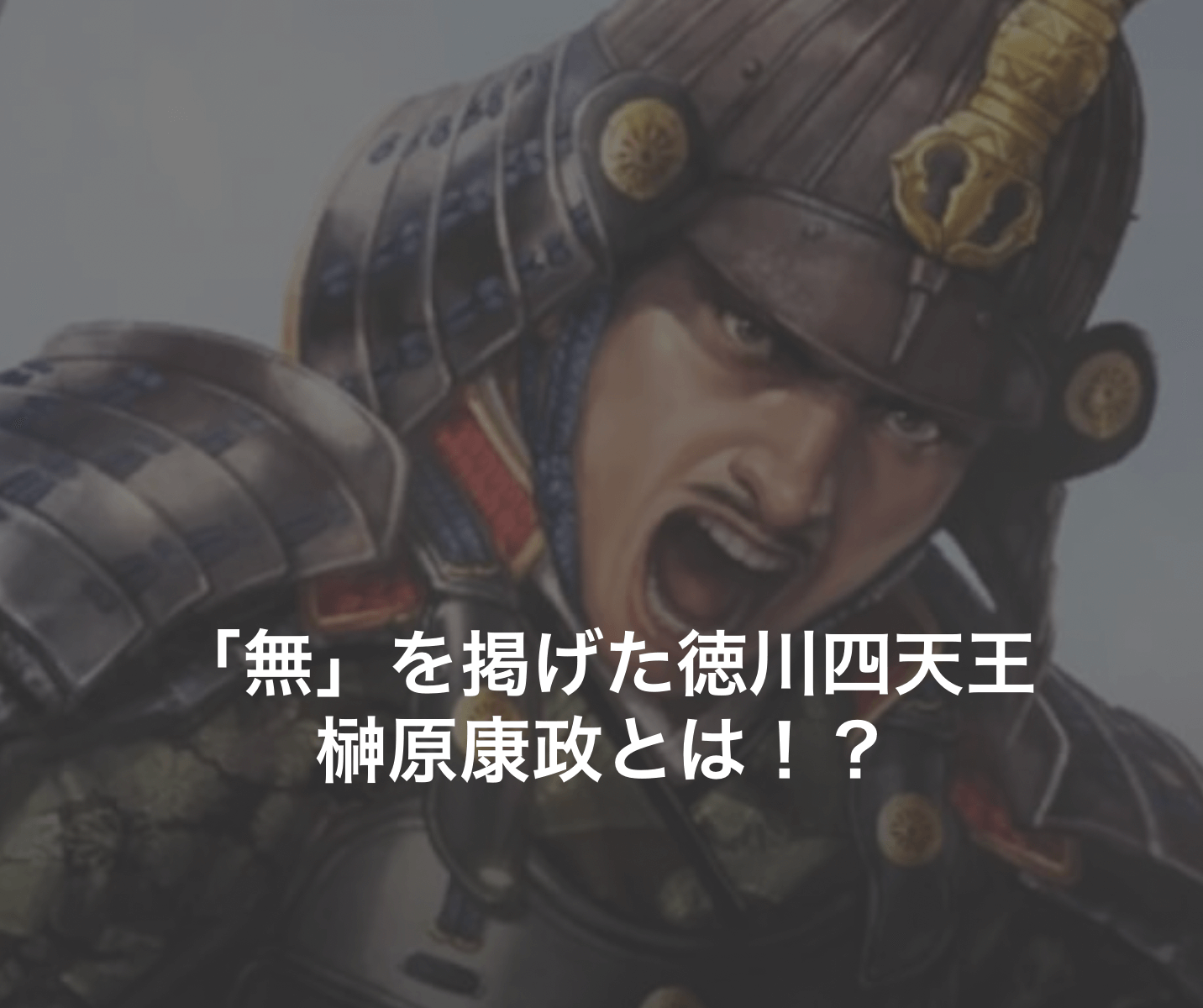
どうする家康
「無」を掲げた徳川四天王・榊原康政(さかきばらやすまさ)とは?【マイナー武将列伝】
-
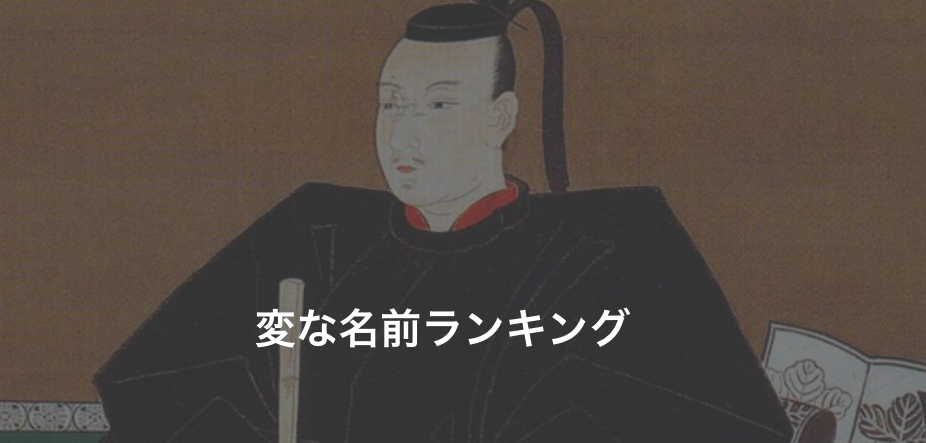
ランキング
戦国武将の変な名前ランキング!!
-
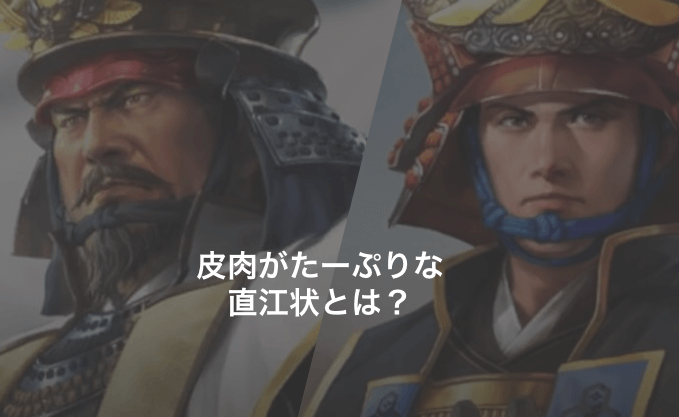
戦国時代の逸話
直江兼続が家康に送った「直江状」とは?痛烈な皮肉がたーぷり【戦国時代の逸話】
-
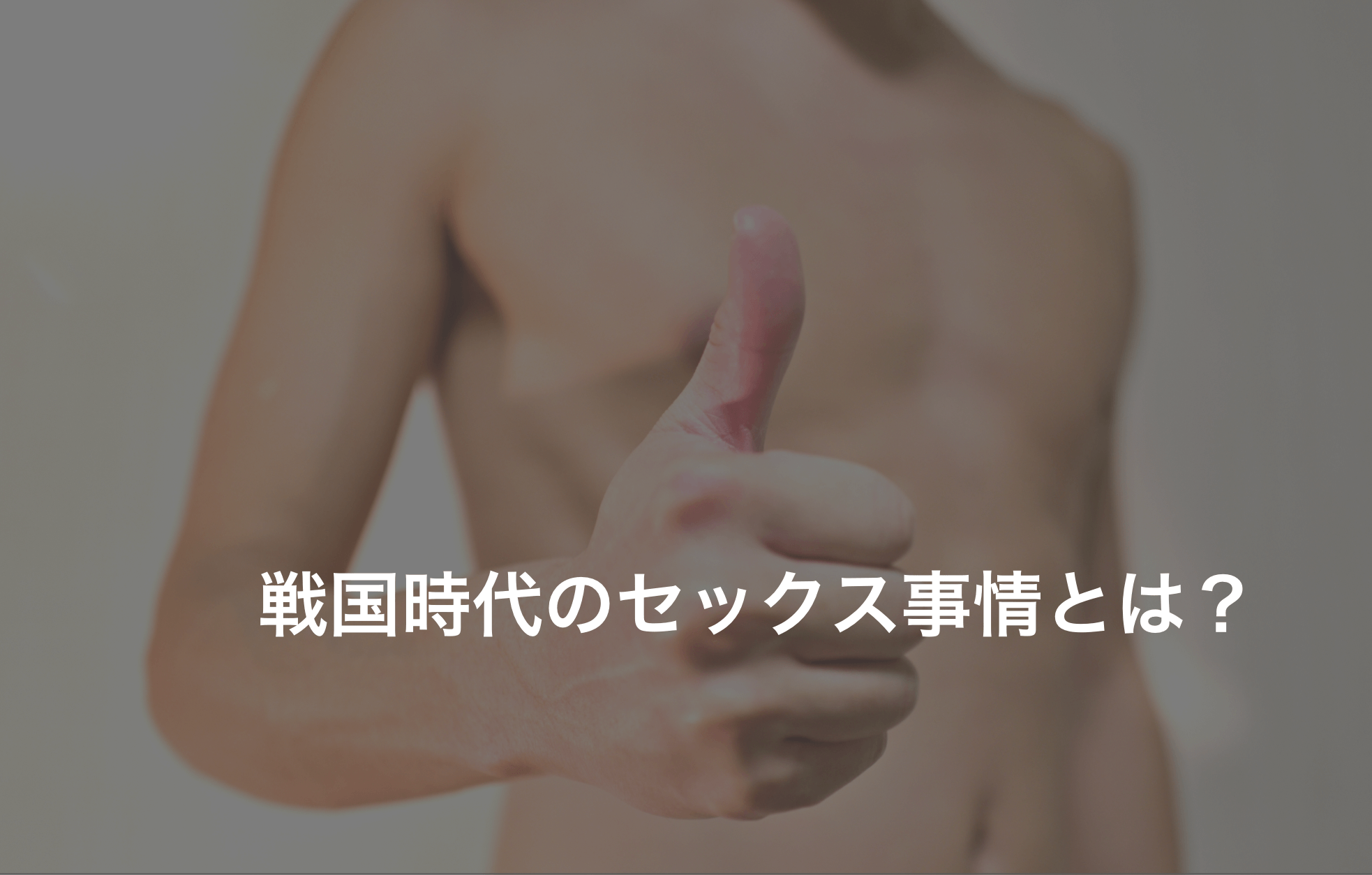
戦国時代の暮らし
戦国武将たちのセックス事情はどんなだった?【戦国時代の暮らし】
-
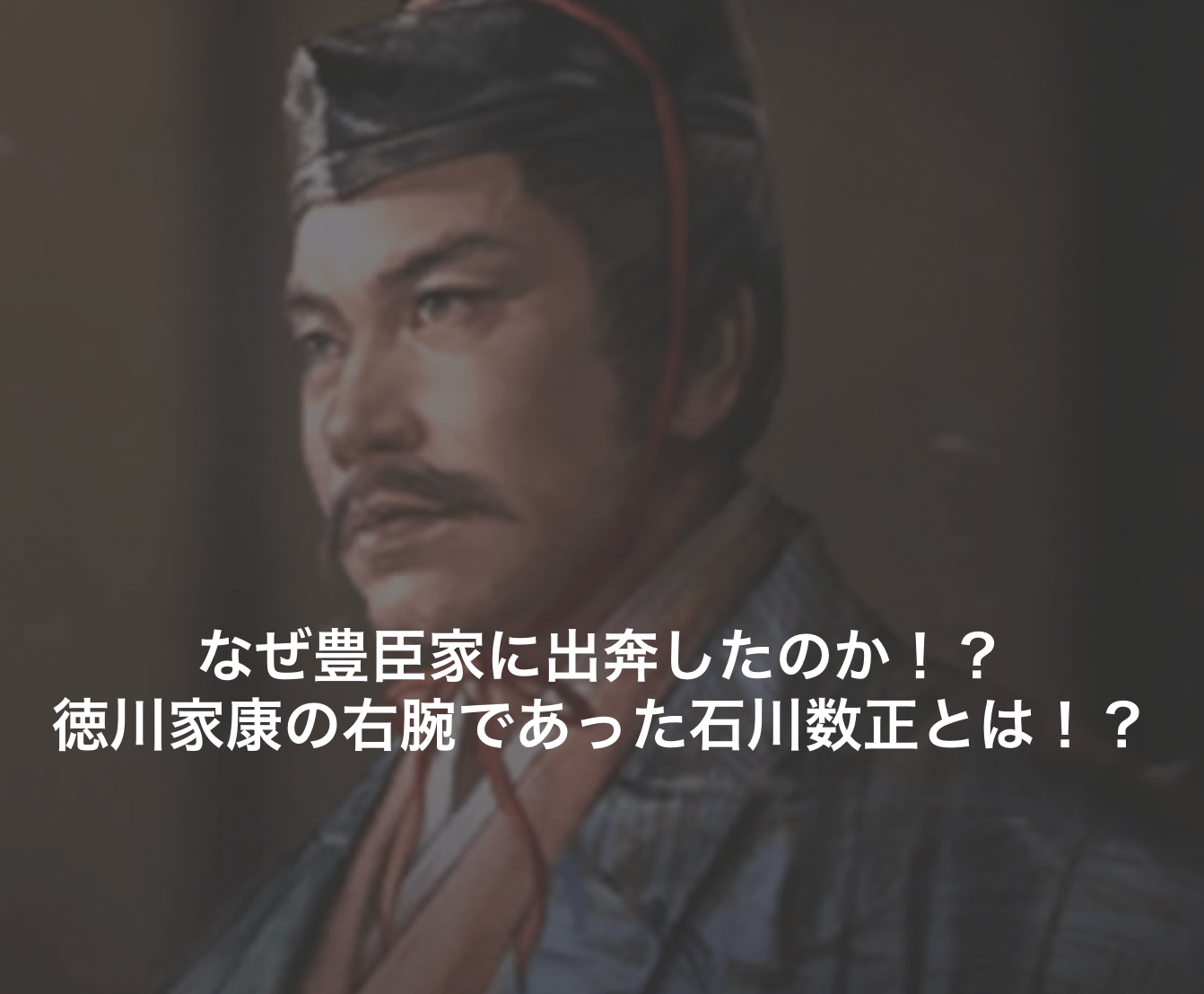
どうする家康
なぜ豊臣家に出奔したのか!?徳川家康の右腕であった石川数正(いしかわかずまさ)とは?【メジャー武将列伝】
-
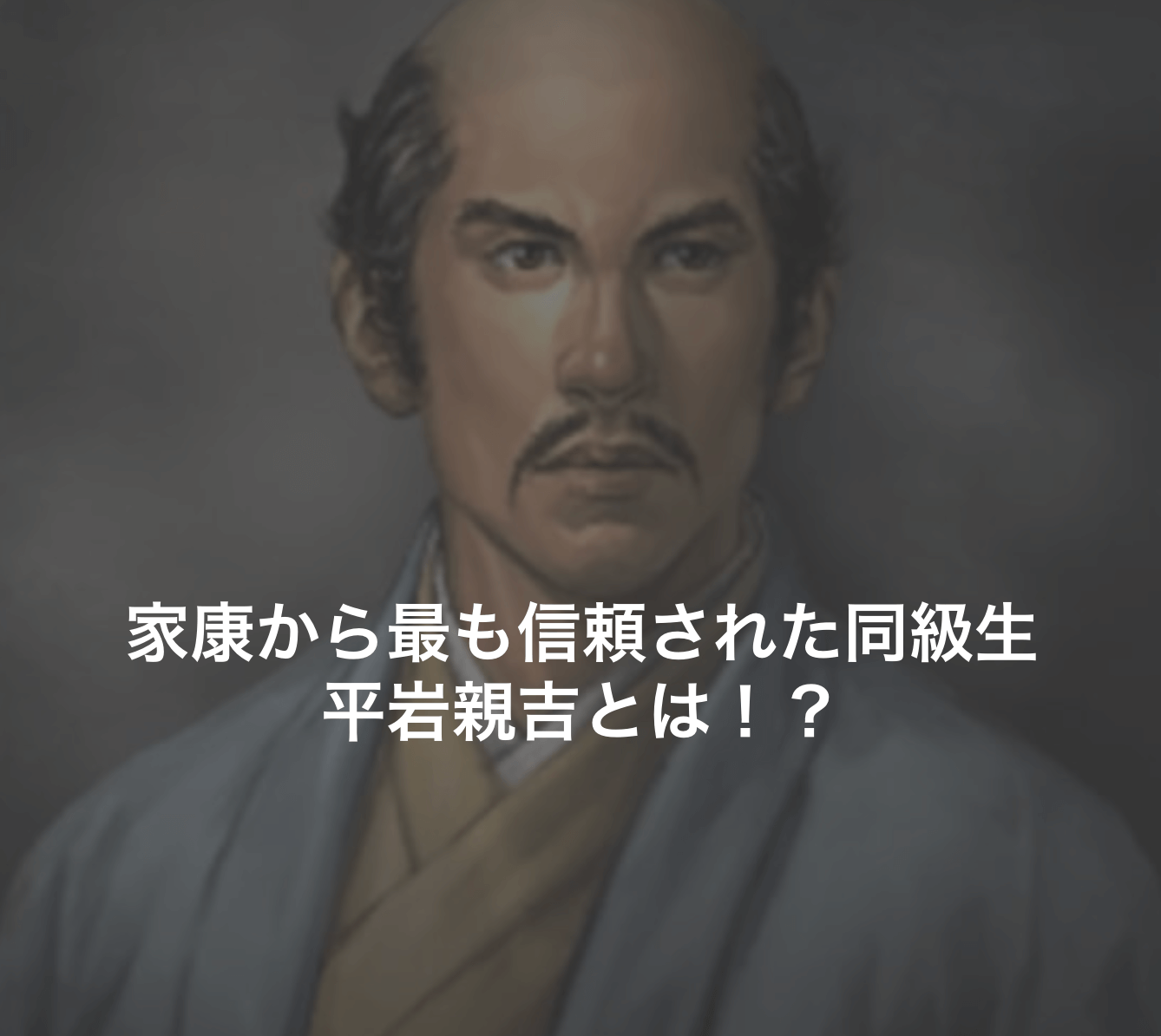
どうする家康
家康から最も信頼された同級生・平岩親吉(ひらいわちかよし)とは?【マイナー武将列伝】
-
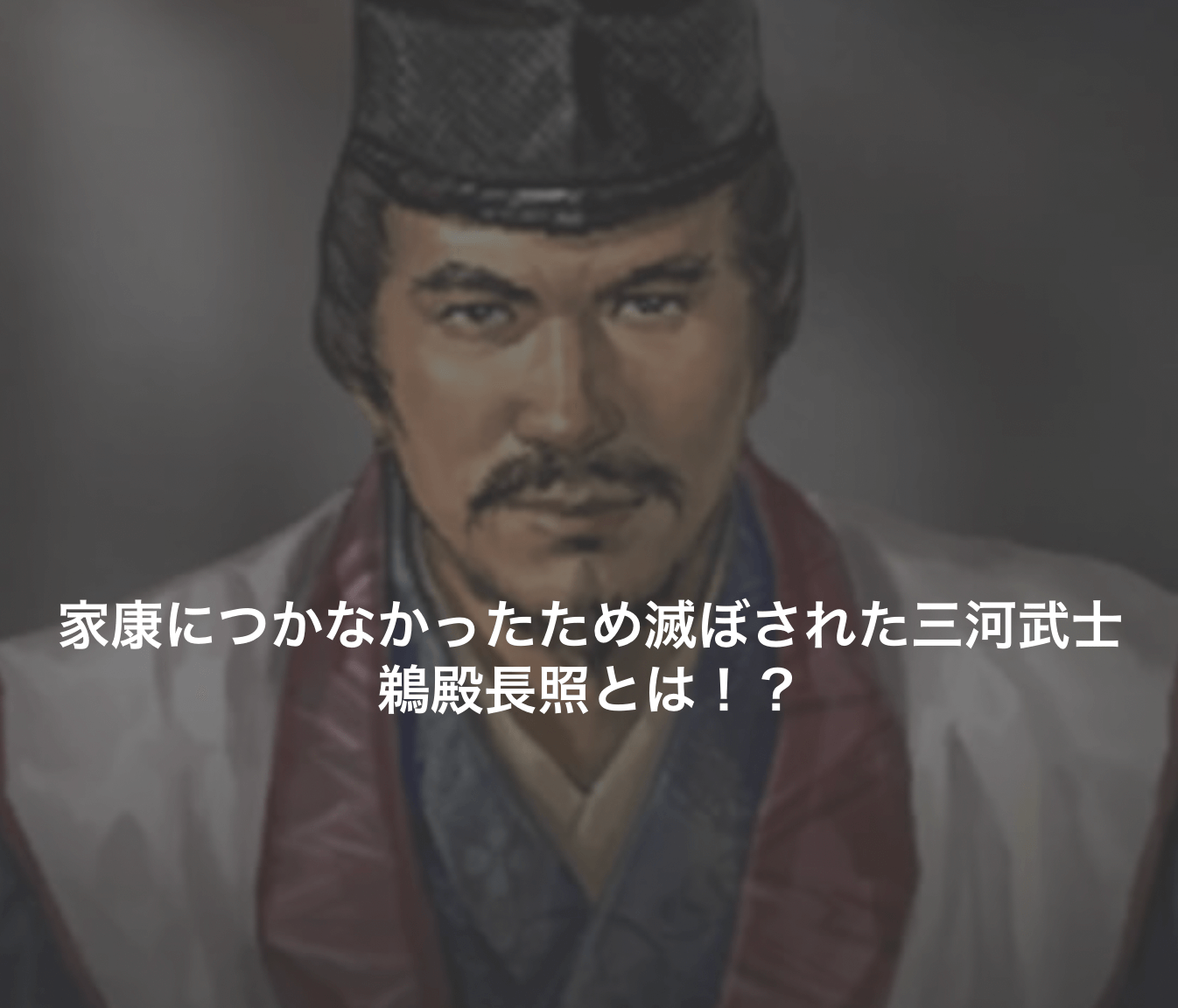
どうする家康
家康につかなかったため滅ぼされた三河武士、鵜殿長照(うどのながてる)とは?【マイナー武将列伝】
-
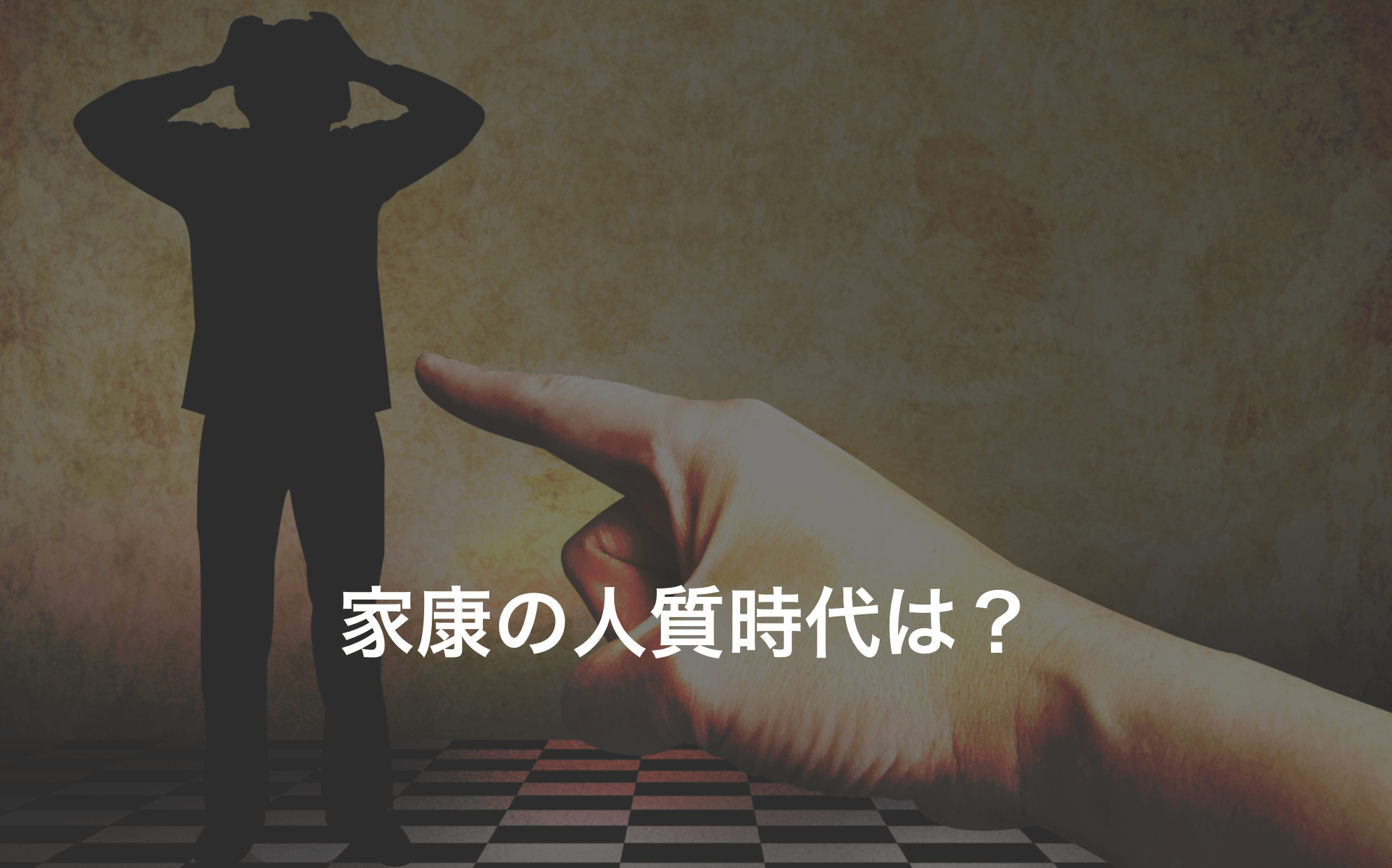
メジャー武将列伝
家康はどんな人質時代を送っていたのか?【メジャー武将列伝】
-
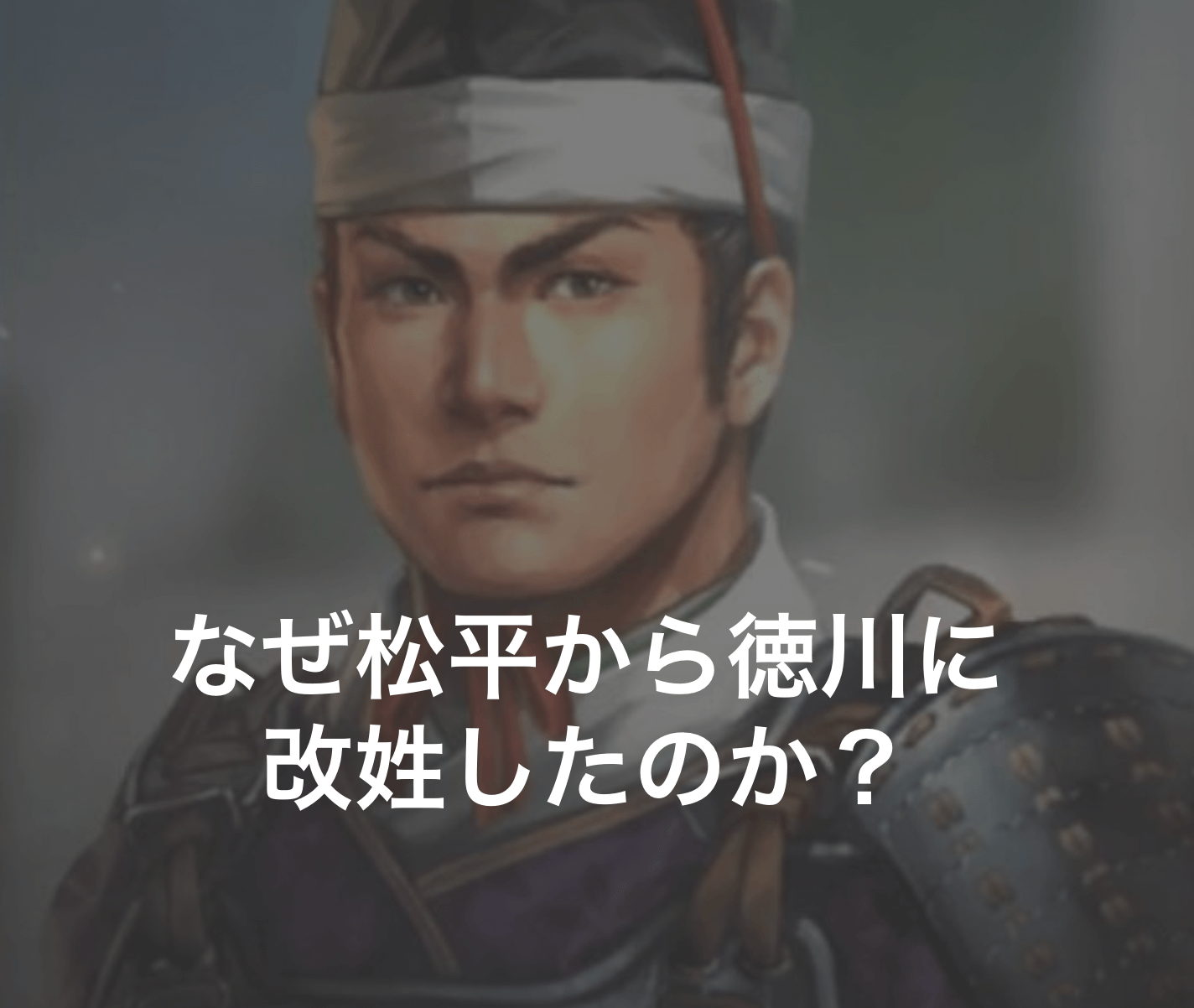
メジャー武将列伝
家康はなぜ松平から徳川に改姓したのか?【メジャー武将列伝】
-
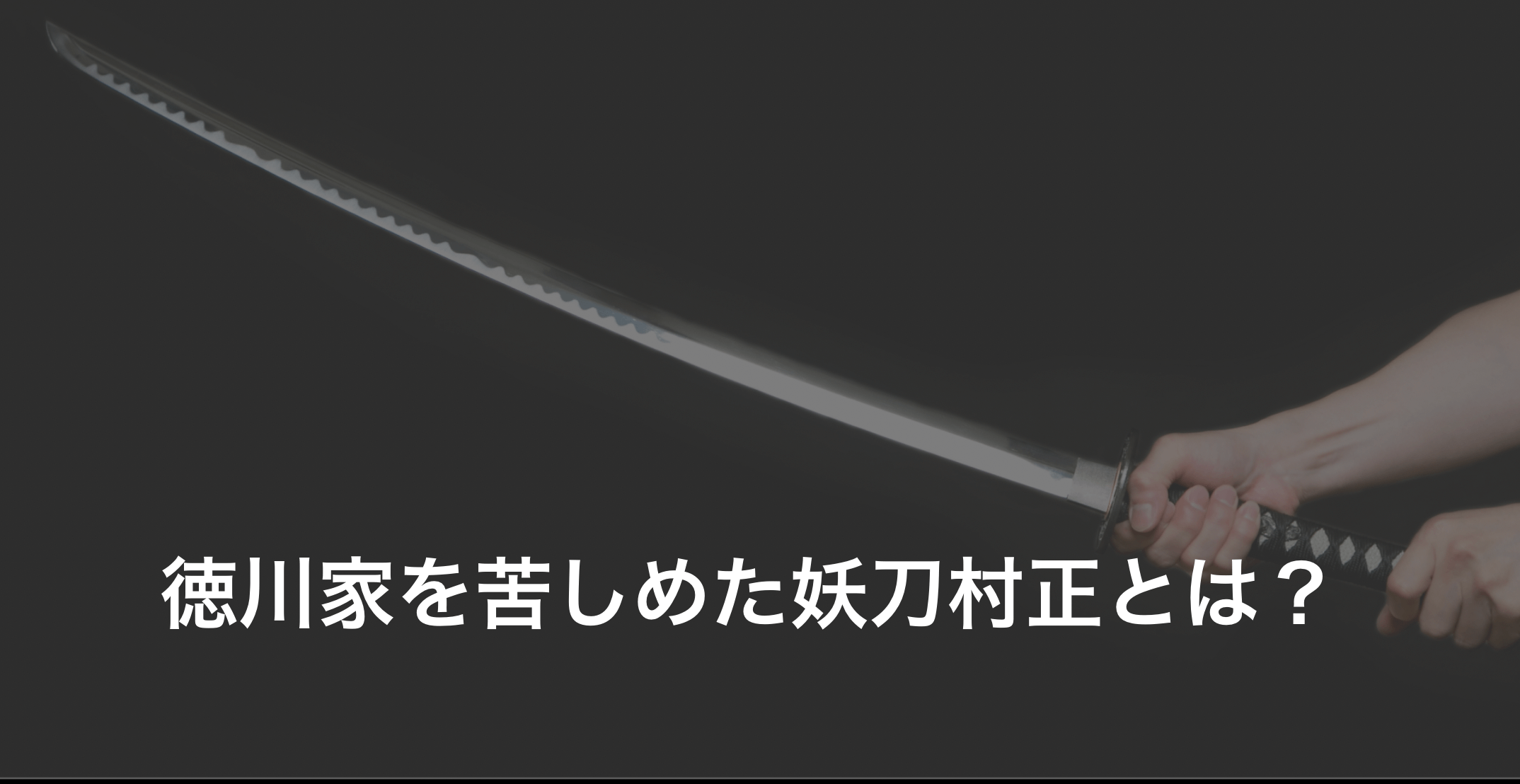
戦国時代の女性
徳川家を苦しめた妖刀「村正」【戦国時代の逸話】
-
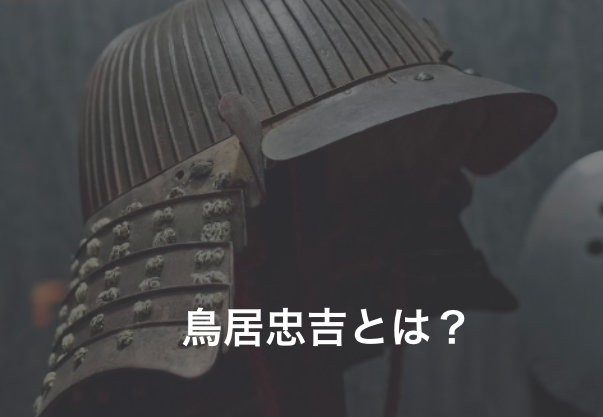
マイナー武将列伝
鳥居忠吉(とりいただよし)は何をした人?息子と共に三河武士の鑑と称された男【マイナー武将列伝】
-
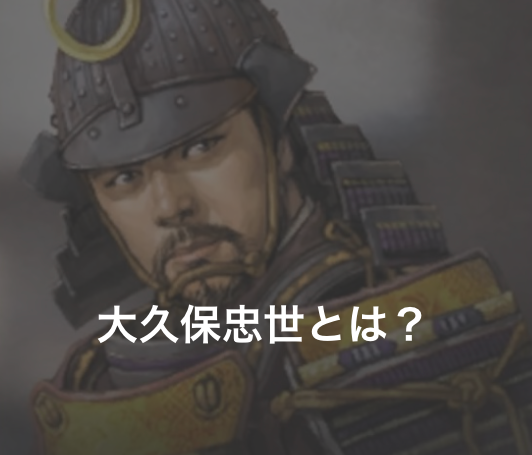
蟹江七本槍
大久保忠世(おおくぼただよ)は何をした人?徳川家臣No.5の実力は?【マイナー武将列伝】
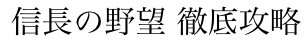



 陶晴賢
陶晴賢

 毛利元就
毛利元就
 毛利隆元
毛利隆元

 吉川元春
吉川元春
 尼子晴久
尼子晴久
 小笠原長雄
小笠原長雄
 本城常光
本城常光
 仁保隆慰
仁保隆慰
 吉弘鎮信
吉弘鎮信
 立花道雪
立花道雪
 吉弘鑑理
吉弘鑑理
 天野隆重
天野隆重
 杉重良
杉重良
 尼子勝久
尼子勝久
 山中鹿之介
山中鹿之介
 毛利輝元
毛利輝元
 三村元範
三村元範
 宍戸隆家
宍戸隆家
 三村元祐
三村元祐
 三村元親
三村元親
 宇喜多直家
宇喜多直家
 三村親成
三村親成
 戸川秀安
戸川秀安
 上野隆徳
上野隆徳
 宇喜多忠家
宇喜多忠家
 豊臣秀吉
豊臣秀吉
 河野通直
河野通直
 大野直之
大野直之
 戸川達安
戸川達安
 吉川元長
吉川元長
 金子元宅
金子元宅
 黒田官兵衛
黒田官兵衛
 秋月元種
秋月元種
 加来統直
加来統直
 豊臣秀長
豊臣秀長
 蜂須賀家政
蜂須賀家政
 宇喜多秀家
宇喜多秀家