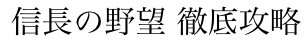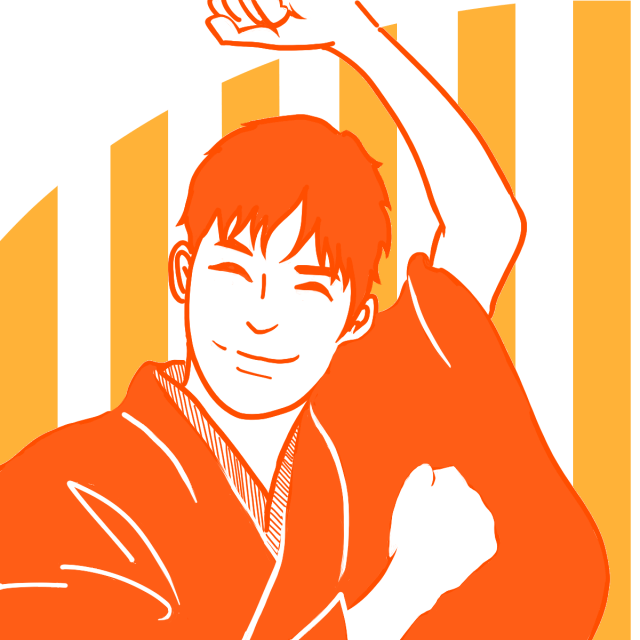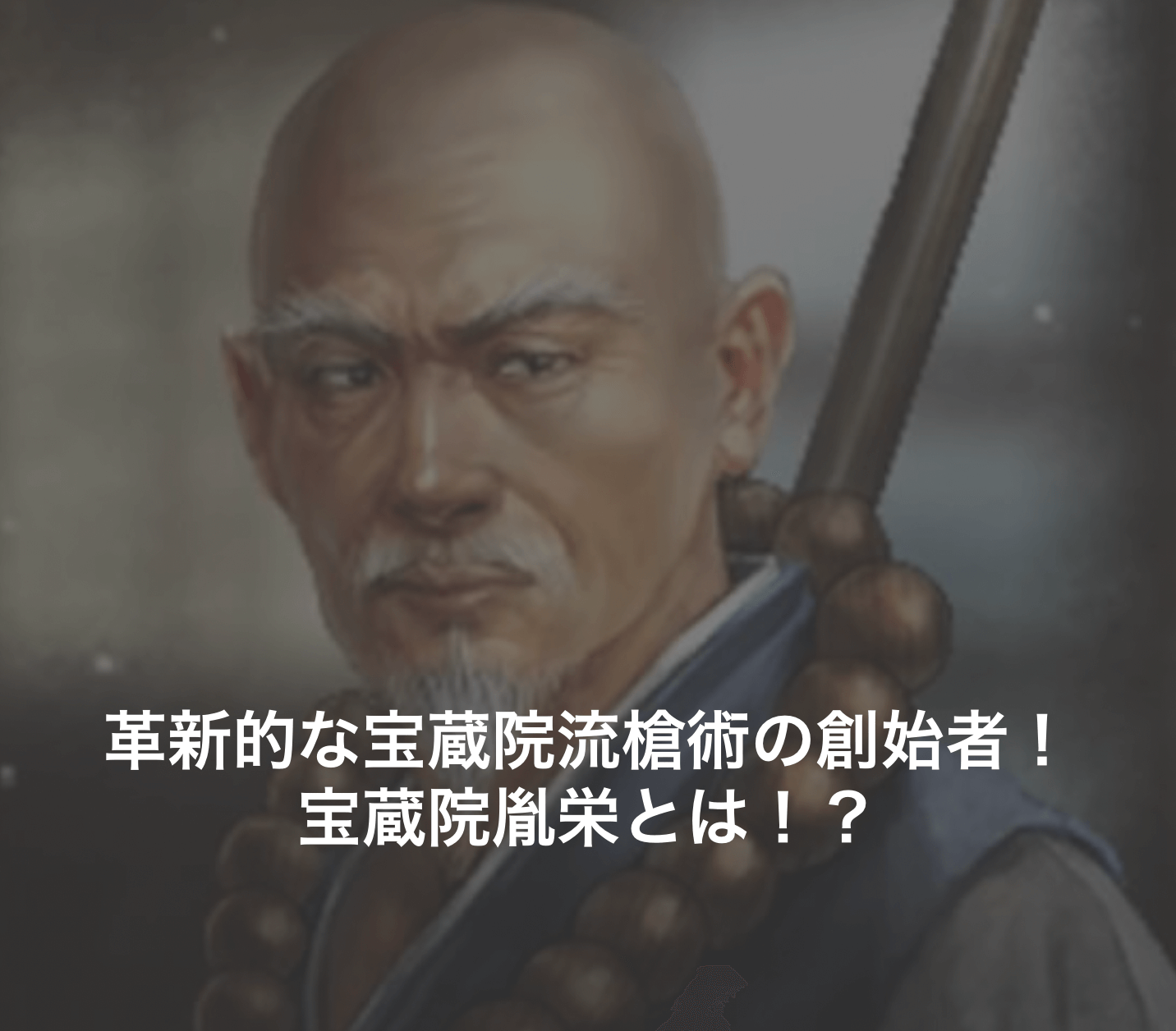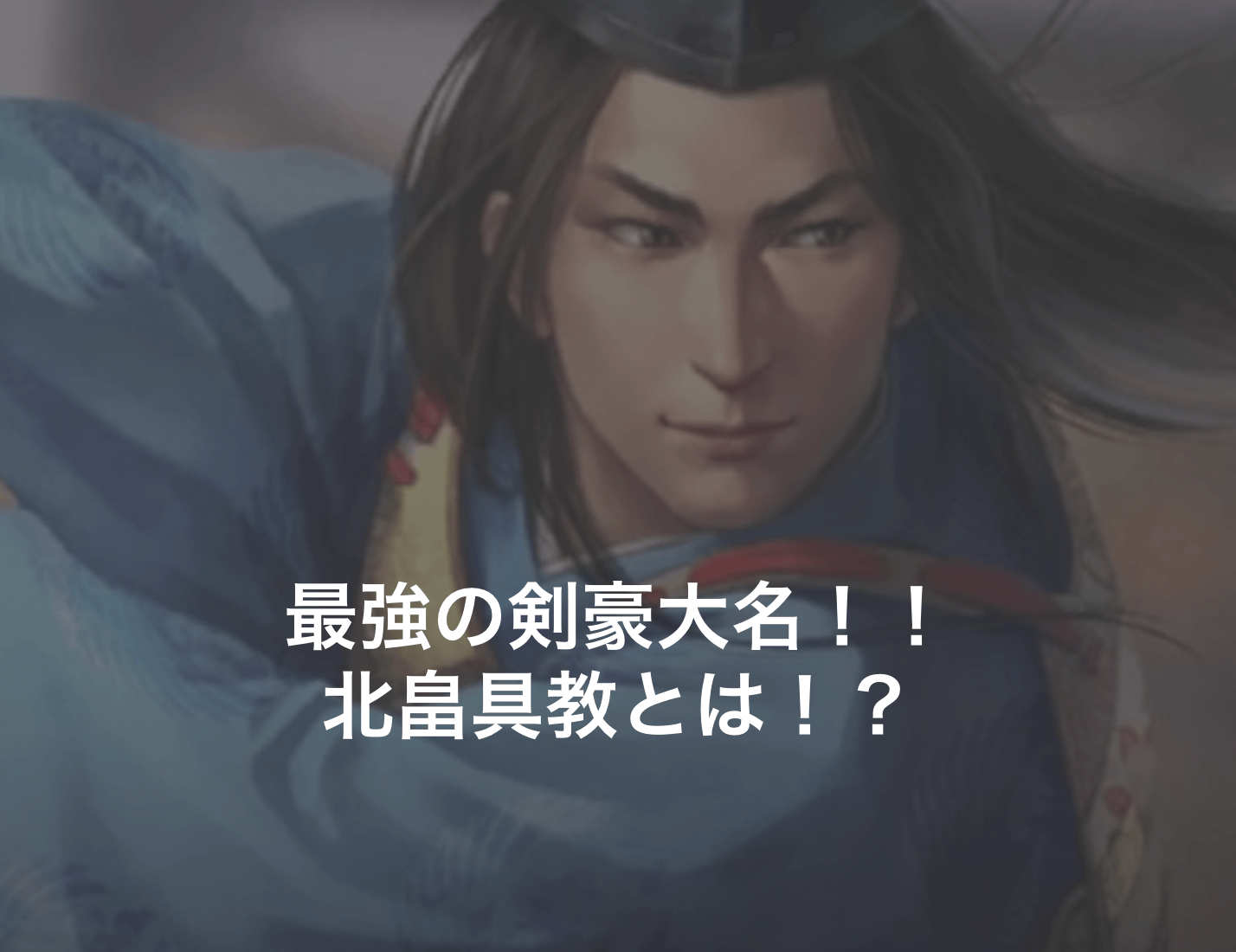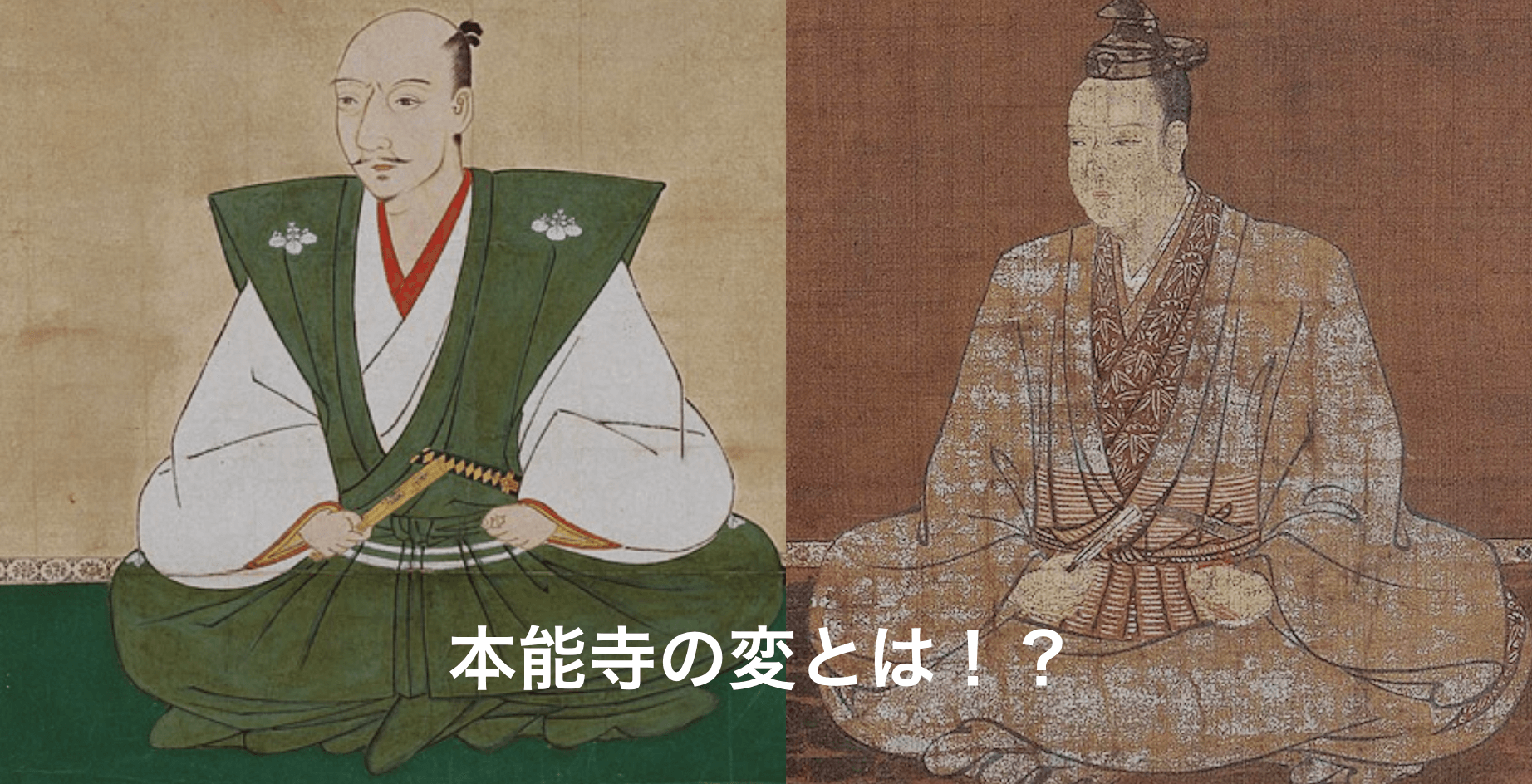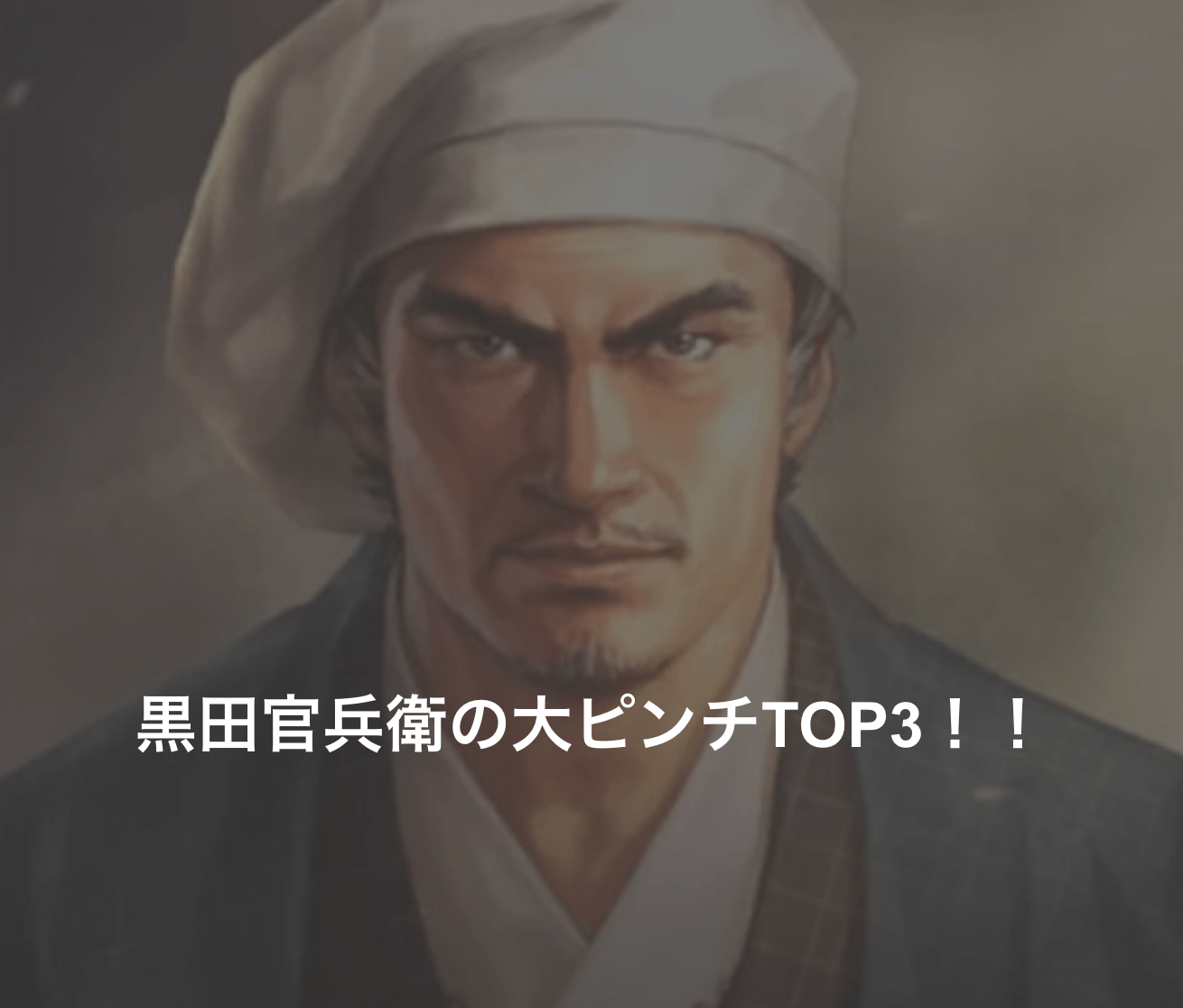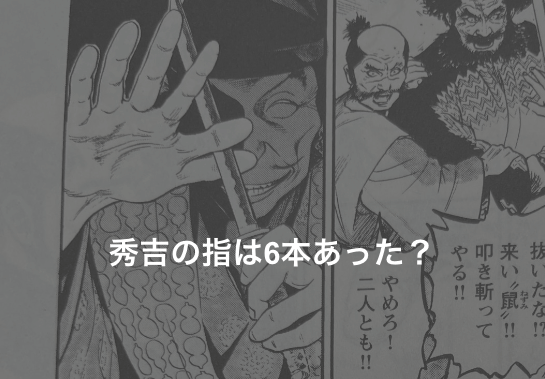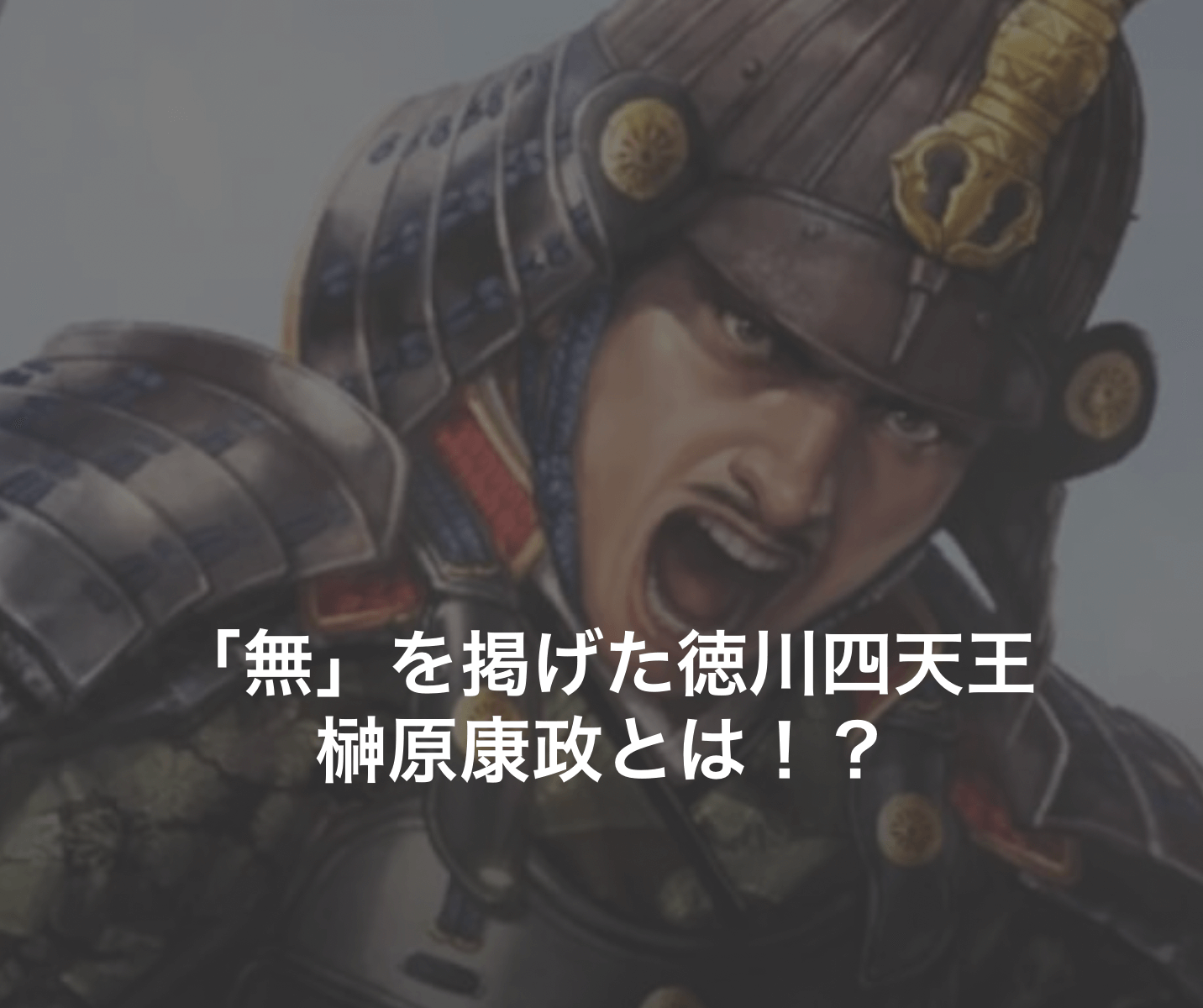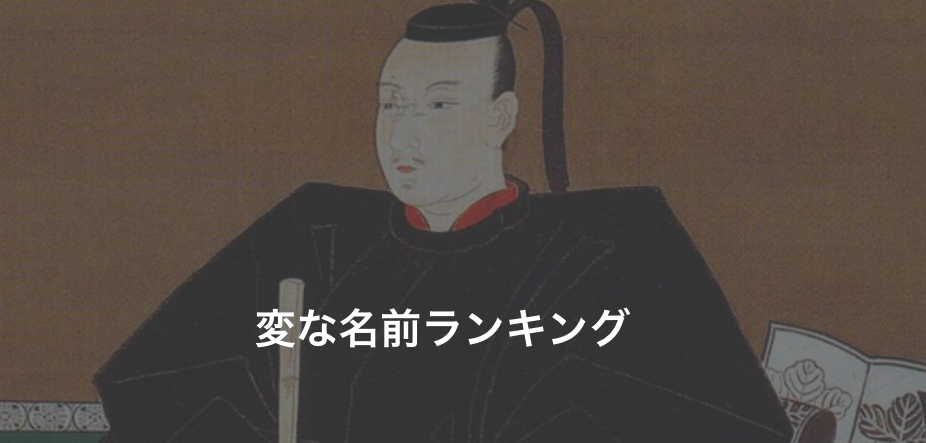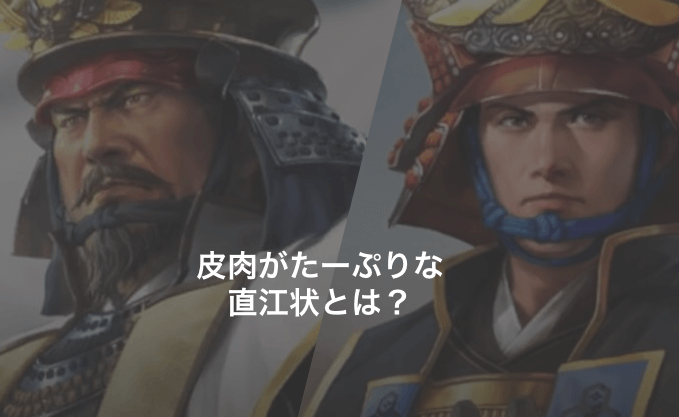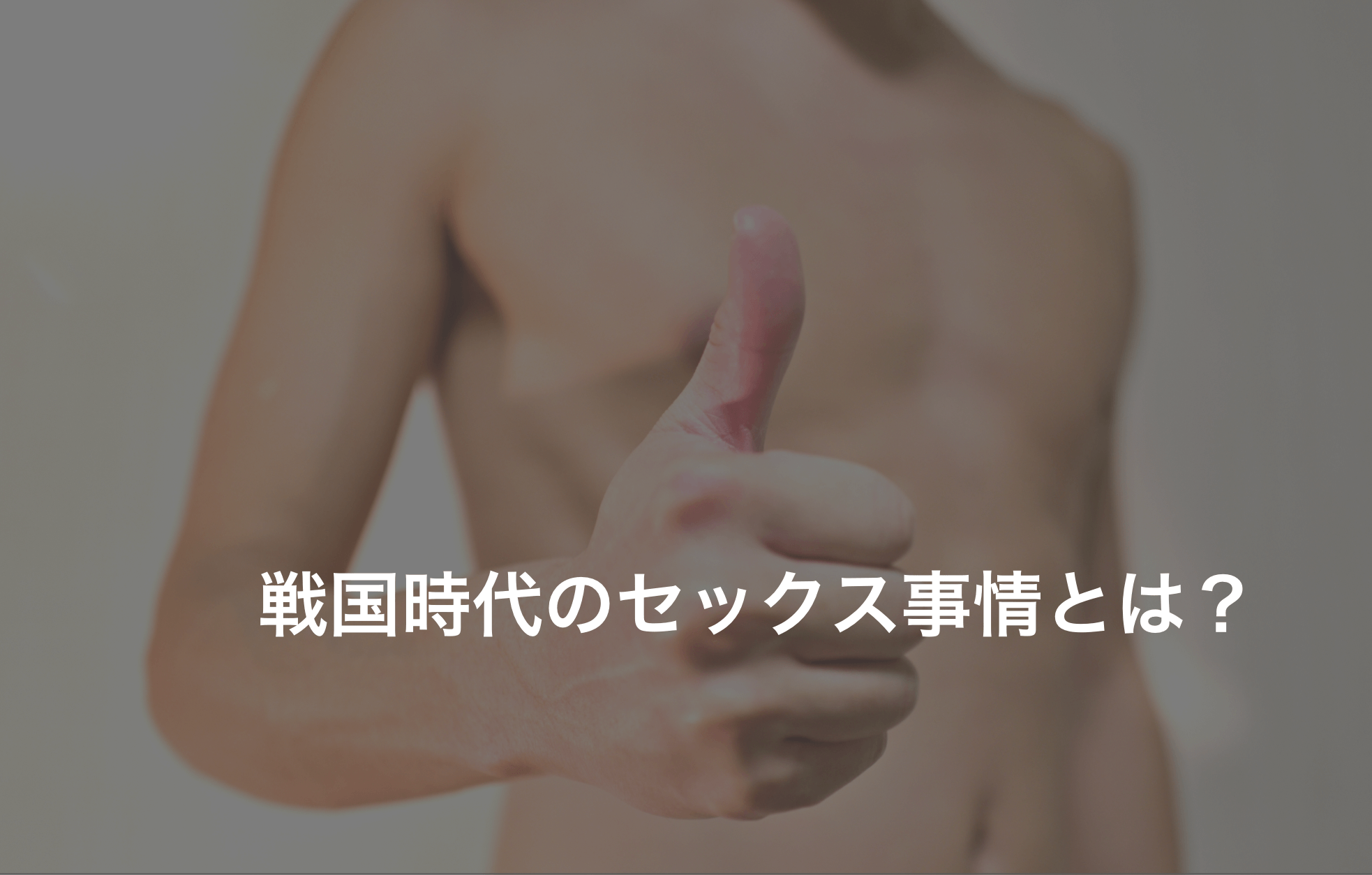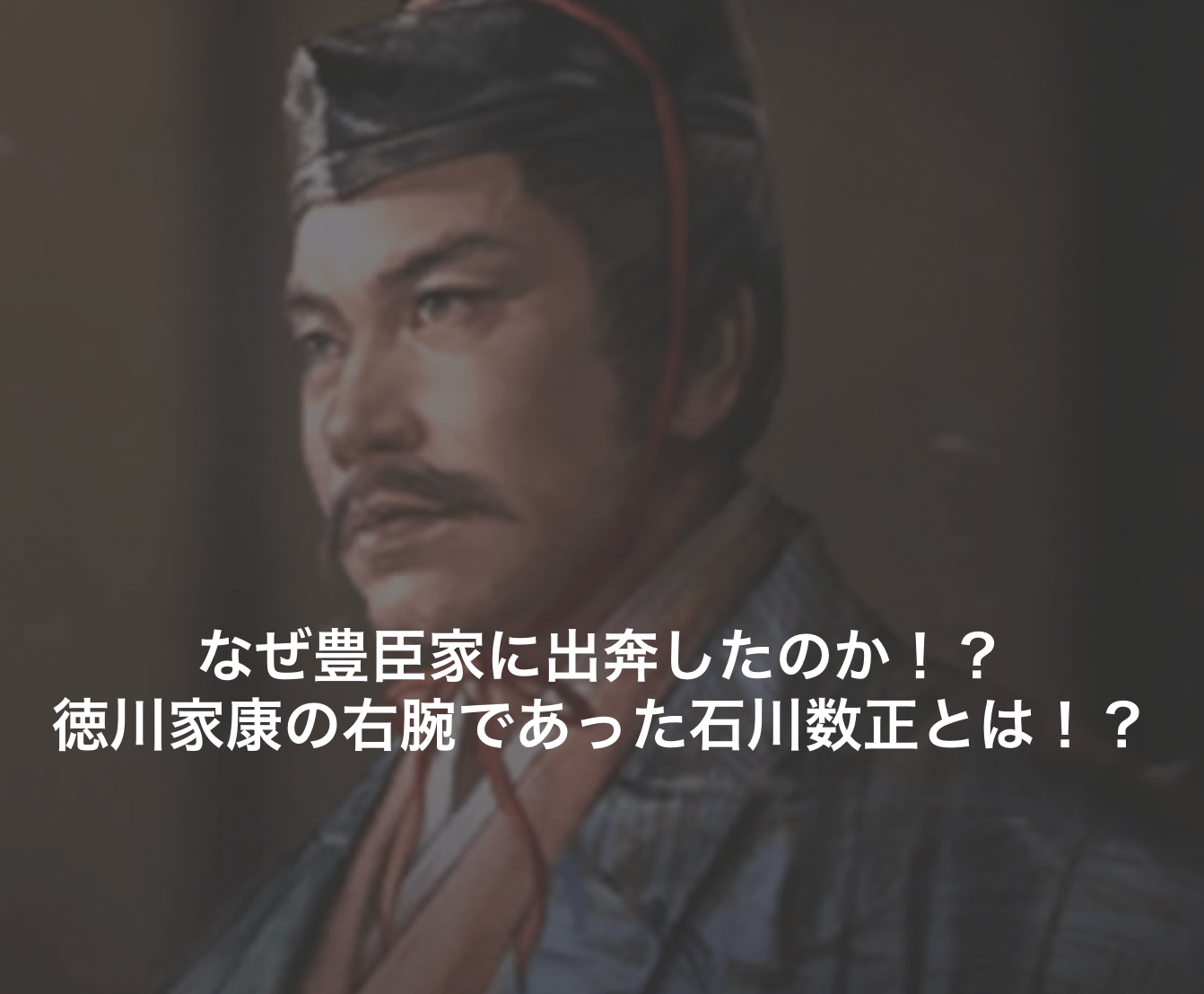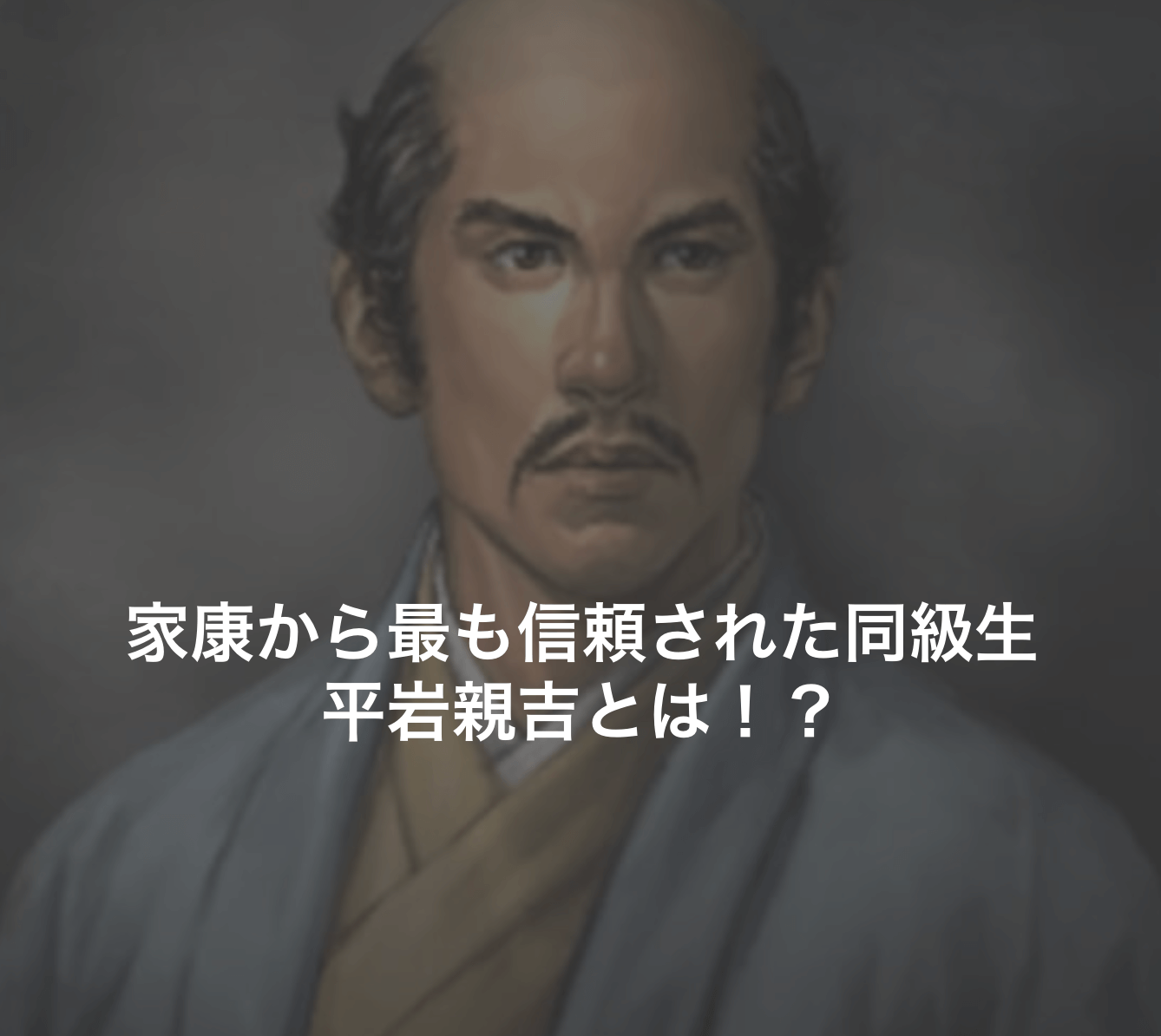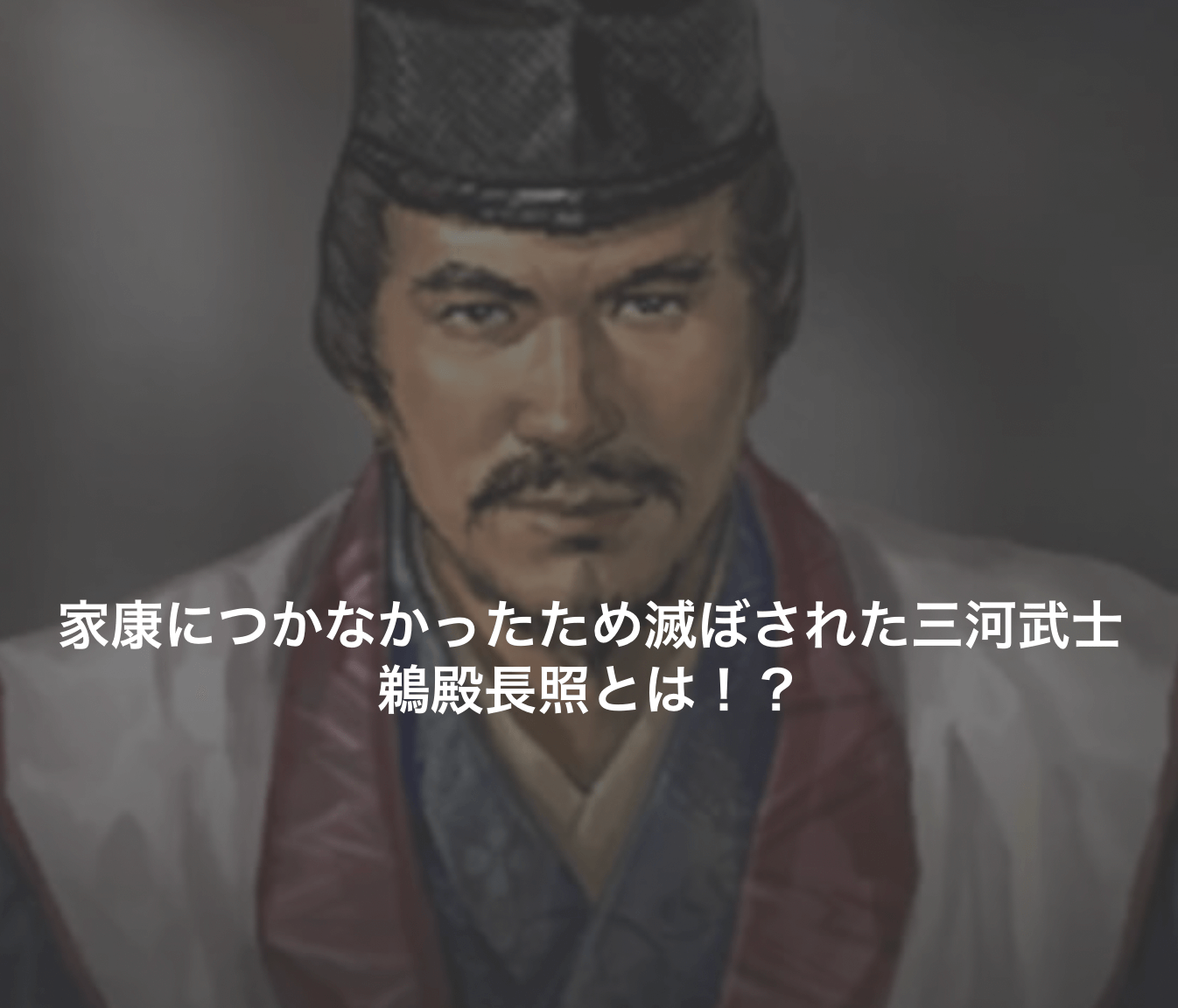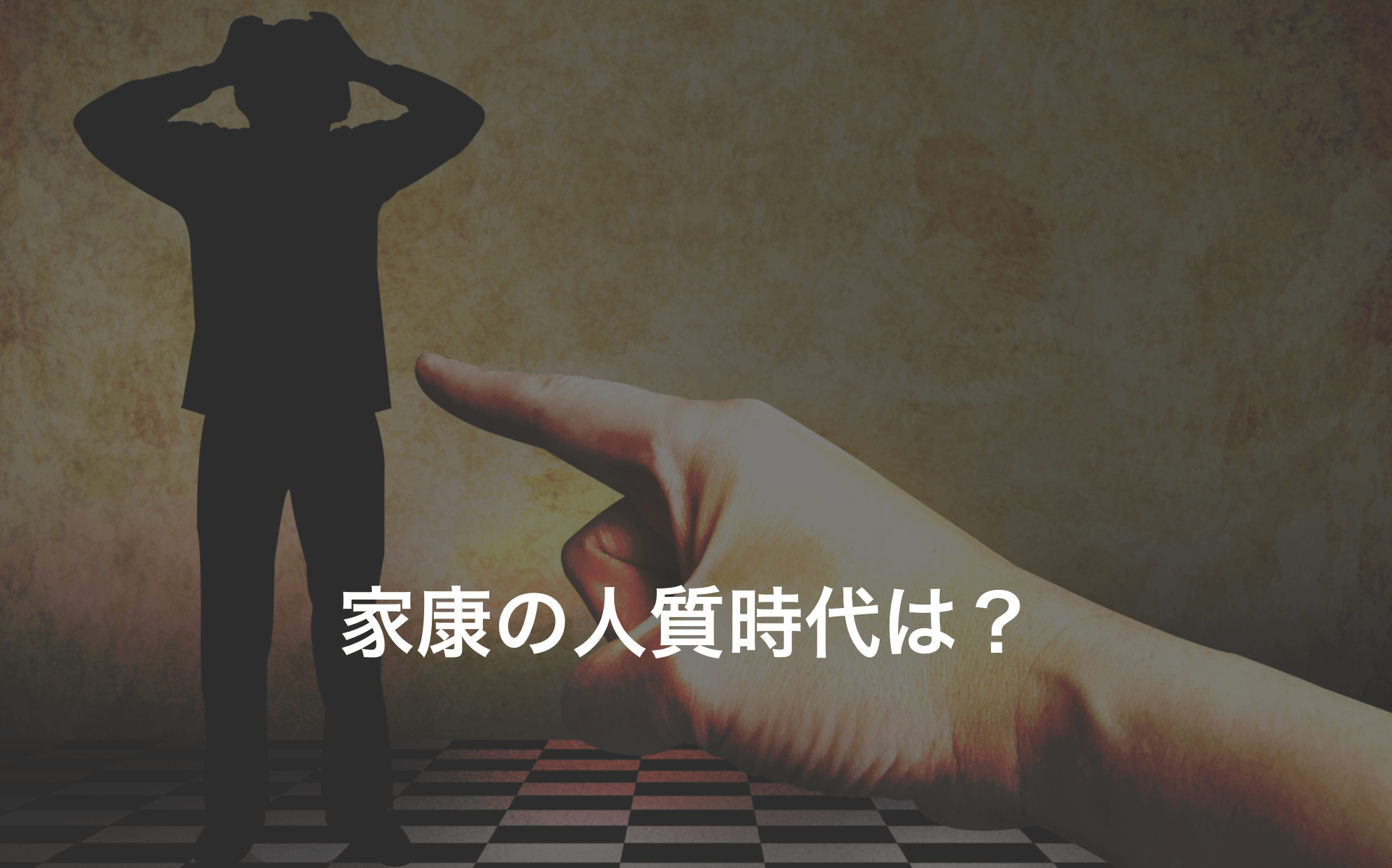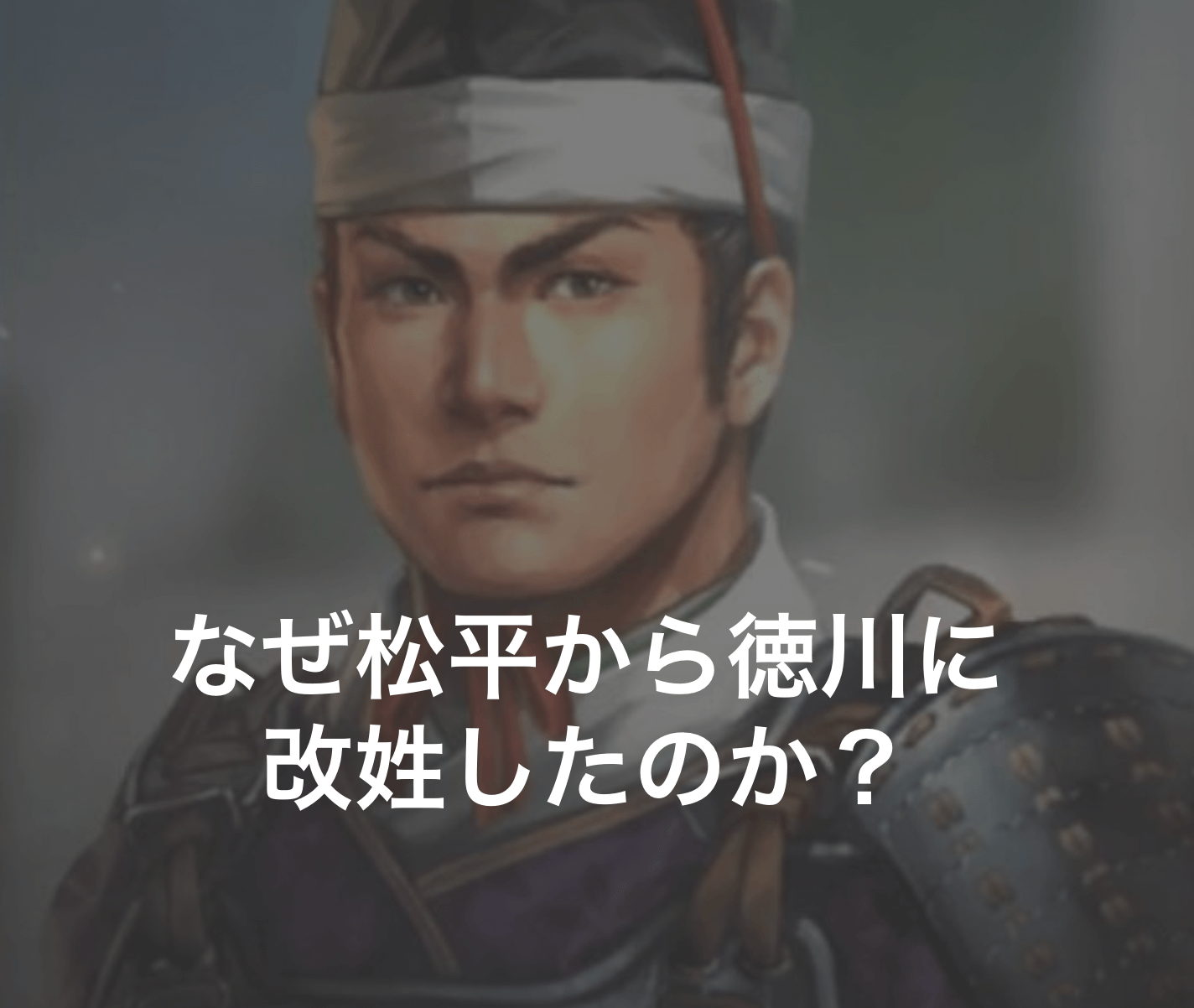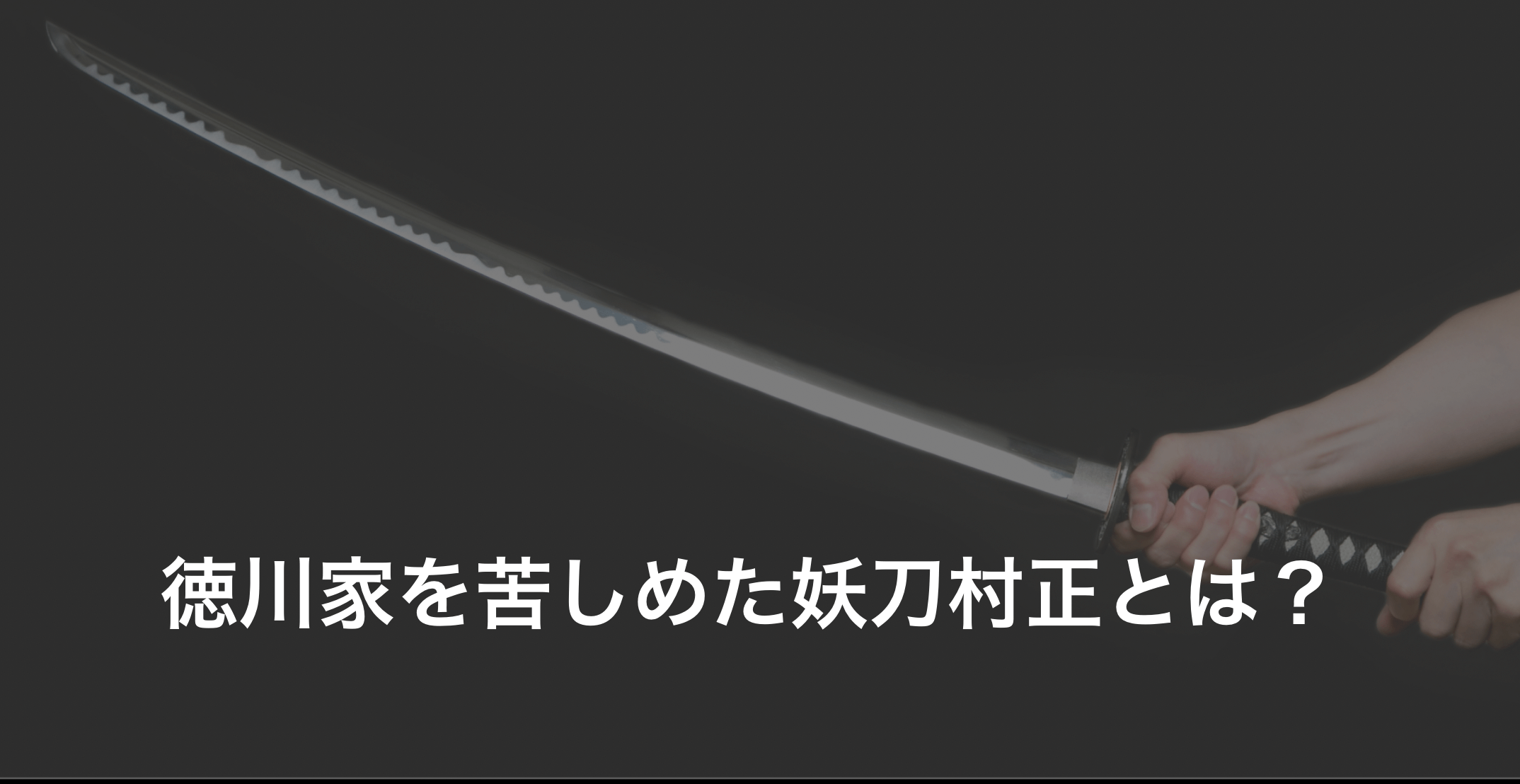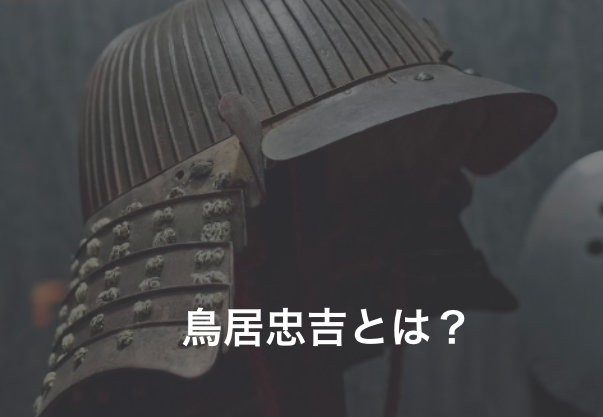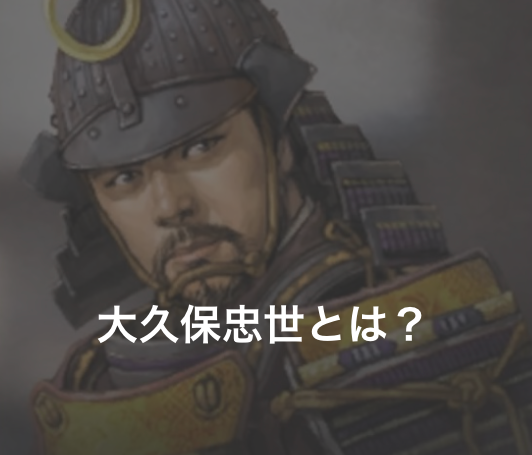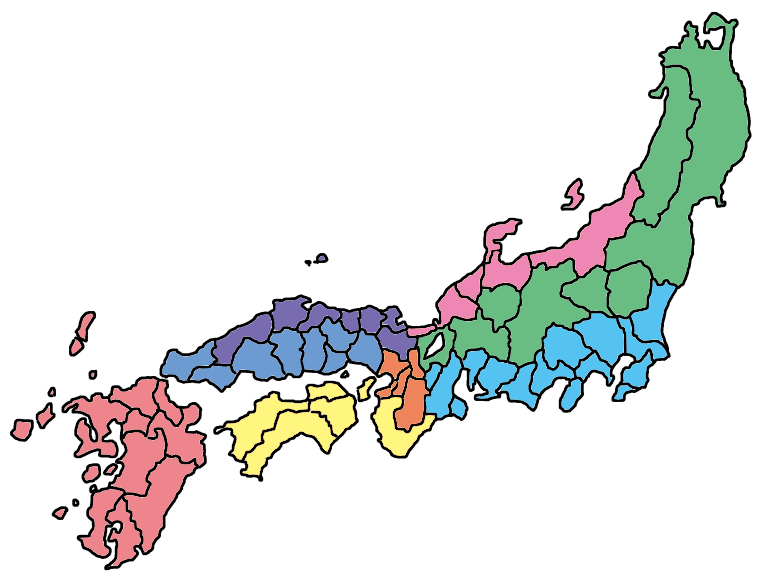views : 4425
愛洲移香斎(あいすいこうさい)は何をした人?剣術三大源流の一つ「陰流」の祖【マイナー武将列伝】
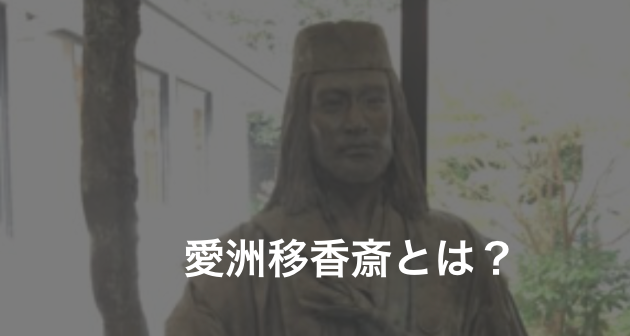
こんにちは、歴史大好きtakaです。
今回紹介するのは剣豪・ 愛洲 移香斎(あいす いこうさい)です。
一体何をした人なんでしょうね。
それでは見ていきましょう!
目次[非表示]
愛洲移香斎の生まれ
享徳1年(1452年)、三重県度会(わたらい)郡南伊勢町五ヶ所浦に愛洲移香斎久忠は生まれました。
この南伊勢町五ヶ所浦を拠点とする豪族「愛洲氏」の一族です。
愛洲氏は熊野水軍の出身で、南北朝時代のころ伊勢に移り、度会郡五所ヶ浦を中心に勢力を張ったといわれています。
城・館址が残っています。
幼少より刀槍の術を好み、剣術の才能があったため、武者修行をもって生業とし、長じると武者修行ため諸国を巡る旅に出ました。
六角定頼らに弓術を教えたという説もあります。
子孫である秋田県の平澤家に伝わる文書・『平澤家伝記』(久忠の9世孫・平澤通有の著)によると、本名は愛洲太郎左衛門久忠、また左衛門尉、日向守、惟孝とも称しています。
愛洲陰流の祖 霊験により開眼する
九州や関東で武芸を磨き、1487年(長享1 愛洲移香斎が36歳の時)日向国の鵜戸権現の岩屋(現・宮崎県日南市鵜戸村)に籠もり厳しい修行を行っていました。
参籠すること37日、神託を得,霊験を得て、刀法の極意を感得し「陰流」を開きました。
クモの動きからヒントを得て影流を開眼したとも伝えられています。
それにあやかり日向守を以降名乗るようになりました。
ひたすら諸国を巡って修行していたが愛洲移香斎が67歳の時、長男の宗通が誕生。
明にまで行った?
一説には愛洲移香斎は若いときに各地へ渡航し、明にまで行ったとされていますが、『武芸流派大事典』では、海外での貿易・略奪にかかわるものではないかとしています。また、愛洲移香斎の出身とみられる伊勢愛洲氏がこれに従事したと考えられるため久忠も関係があったとされています。
明の武術書《武備志》に陰流目録の一部、猿によって刀法を示した図が載っているようです。
剣術三大源流
愛洲移香斎久忠が起こした「陰流(愛洲陰流)」は剣術の源流の一つです。
剣術が最も盛んだった江戸時代には、600もの流派があったと言われていますが、その源流をたどっていくと3つの流派に集約され、「陰流(愛洲陰流)」は「念流」「神道流」と合わせて「剣術三大源流」とも呼ばれています。
陰流は上泉伊勢守秀綱に伝わり「新陰流」として確立され発展し、それが柳生石舟斎に継がれ「柳生新陰流」となり、多くの有力な流派を生んで隆盛しました。
愛洲移香斎久忠が生まれた南伊勢町の「愛洲の里・愛洲の館」では、剣術「陰流・影流」の祖、剣道の始祖とされる「愛洲移香斎」の偉業を讃える「剣祖祭」「愛洲氏顕彰祭」が執り行われ、19団体130人以上の剣士が木刀や真剣などを使い日頃の鍛錬の成果を奉納演武しているようです。
愛洲移香斎久忠の長男の小七郎宗通(惟脩(いしゅう)、元香斎(げんこうさい))は1560年頃関東に下り、上泉伊勢守秀綱や佐竹常陸介義重(ひたちのすけよししげ)らに陰流の奥義を伝えたと言われています。
晩年
晩年は日向守と称し日向に住み、天文7年(1538年)、87歳で死去しました。
家は子の小七郎宗通(元香斎)が継いだ。
まとめ
いかがでしたか?
剣術三大源流「愛洲陰流」の祖である愛洲移香斎。
岩窟で陰流を開いた話は胡散臭いですが、さまざまな流派に引き継がれたことから素晴らしい考え方だったのでしょう!
それでは、今後も剣豪列伝をアップしていくのでよろしくお願いします!